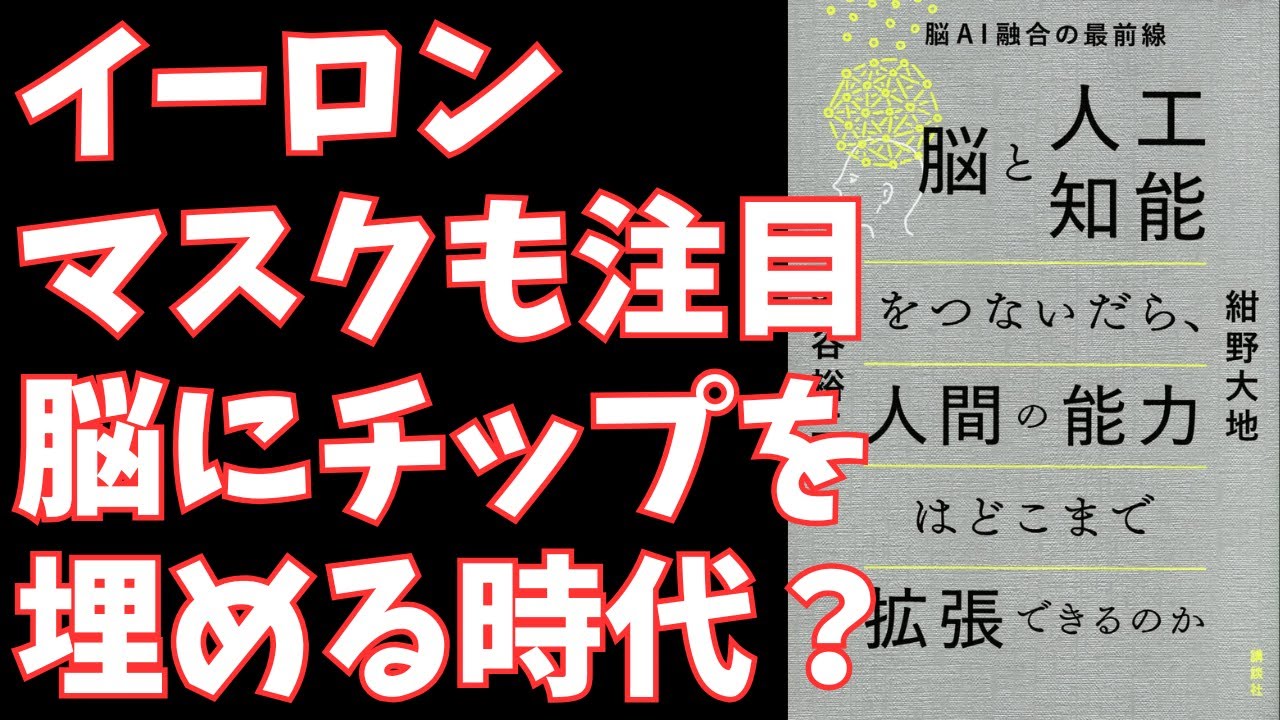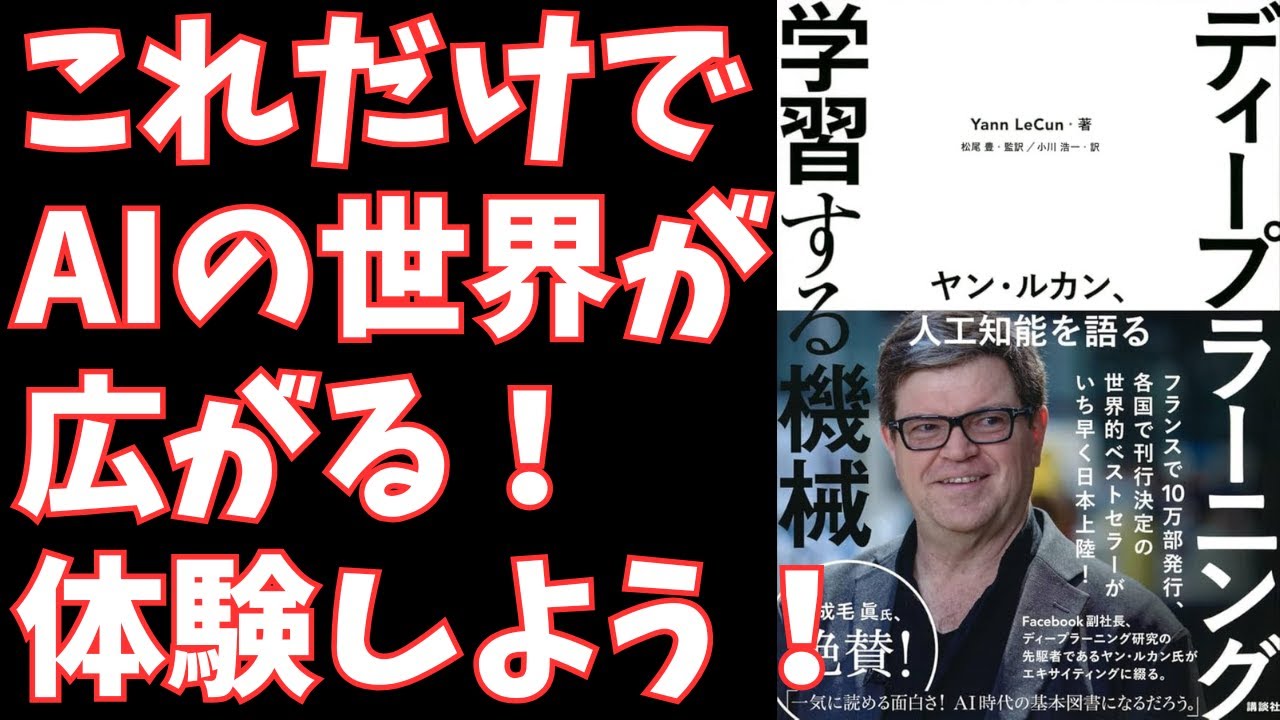『シリコンバレーのエンジニアはWeb3の未来に何を見るのか』- 詐欺か、革命か?元マイクロソフト伝説のプログラマーが解き明かすWeb3の本質
本書『シリコンバレーのエンジニアはWeb3の未来に何を見るのか』は、元マイクロソフトの伝説的プログラマーである中島聡氏が、賛否両論渦巻く「Web3」の正体を、自身のプログラミング経験と深い洞察に基づき解き明かす一冊です。
現在のWeb3業界に蔓延する投機的なブームやポンジスキームまがいのビジネスモデルに警鐘を鳴らしつつも、その根幹技術であるブロックチェーンが持つ「永続性」と「透明性」にこそ、社会を根底から変える革命的な可能性があると著者は語ります。
本書では、Web3を理解するための基本技術(ブロックチェーン、スマートコントラクト、NFT、DAO)から、Game-FiやNFTビジネスのリアルな実態、そして著者が提唱する未来の経済圏「DAE(非中央集権型自律システム)」構想までが、具体的な事例とともに分かりやすく解説されています。
評論家としてではなく、自ら手を動かしコードを書く「実践者」の視点から語られるWeb3の本質は、この新たなテクノロジーの波にどう向き合うべきか、悩めるビジネスパーソンにとって確かな指針となるでしょう。
本書の要点
- Web3業界の現状と課題: 現在のWeb3業界は、金銭欲に煽られた投機的な側面が強く、後から参加した人が損をするポンジスキームまがいの「なんちゃってWeb3」サービスが横行している。
- ブロックチェーン技術の本質的な価値: Web3の根幹技術であるブロックチェーンの真の価値は、特定の企業や管理者がいなくても永続的に動き続け、誰もが情報にアクセスできる「永続性」と「透明性」にある。
- 実践の重要性: 新しい技術の本質を理解するためには、評論家になるのではなく、自ら手を動かしプログラミングを行う「クリエイター」になることが不可欠である。著者のWindows95開発などの経験がその重要性を物語っている。
- DAOからDAEへ: 著者は、DAO(自律分散型組織)の課題を乗り越える新たな概念として、非営利法人が中心となり、開発者がトークンで直接インセンティブを得る「DAE(非中央集権型自律システム)」を提唱している。
- Web3の究極のアプリケーション: ブロックチェーンの透明性と永続性が最も活かされるのは、不動産登記や税金など、お金の流れをオープンにすべき「国家」のような公的な分野であり、社会課題の解決にこそ可能性がある。
はじめに:Web3は「未来」か、それとも「詐欺」か?
「Web3はインターネットの未来だ」「いや、ただの詐欺だ」
今、テクノロジーの世界で最も熱く、そして意見が真っ二つに分かれている言葉、それが「Web3」です。
ある人々は、国家や巨大企業の支配から脱した、公平で非中央集権的な新しい経済圏が生まれると熱狂します。日本政府も2022年にはWeb3推進の方針を打ち出しました。
一方で、多くのコンピュータ科学者やエンジニアは、現在のWeb3を「誇大広告」や「ネズミ講まがいのいかがわしいサービス」と断じ、警鐘を鳴らしています。
この混乱の中、私たちビジネスパーソンはWeb3をどう捉え、どう向き合えばよいのでしょうか?
この問いに、シリコンバレーの最前線から明快な答えを示してくれるのが、本書『シリコンバレーのエンジニアはWeb3の未来に何を見るのか』です。
著者は、マイクロソフト本社で Windows95やInternet Explorerの開発に中心人物として携わった伝説のプログラマー、中島聡氏。パソコンの黎明期からGAFAMの時代まで、常に技術革新の最前線で「手を動かしてきた」彼が、自らWeb3のプログラミングに没頭して見えてきた景色を、余すところなく語ります。
本記事では、本書の内容を紐解きながら、Web3の理想と現実、そしてその先に広がる真の可能性について深く掘り下げていきます。
第1章 Web3とは何か? – 理想と現実のギャップ
Web1.0、Web2.0、そしてWeb3へ
Web3を理解するために、まずはインターネットの歴史を簡単に振り返りましょう。
- Web1.0(1990年代〜): 情報の発信者が企業などで、ユーザーは基本的に情報を受け取るだけの一方通行のウェブでした。ウェブサイトの閲覧が中心です。
- Web2.0(2004年頃〜): ブログやSNSの登場により、ユーザー自身が情報やコンテンツを発信する「双方向」のウェブが実現しました。しかし、その結果として、ユーザーが生み出したコンテンツが集まるプラットフォーム、すなわちGAFAM(Google, Apple, Facebook(Meta), Amazon, Microsoft)が絶大な力を持つ中央集権的な世界が生まれました。
Web2.0の世界では、サービスの運営企業が、ユーザーのコンテンツを削除したり、アカウントを利用停止にしたりと、意のままにコントロールできます。そして、ユーザーが生み出す価値(コンテンツやデータ)の恩恵を受けるのは、ユーザー自身ではなく、広告主を真の顧客とするプラットフォーム企業でした。
この状況を変えるビジョンとして登場したのが「Web3」です。イーサリアムの共同創設者であるギャヴィン・ウッドが提唱したこの概念の核心は、「非中央集権化(Decentralization)」にあります。
特定の企業や国家に支配されることなく、ユーザー自身がデータを所有し、誰にも奪われることのない世界。サービスの成功に貢献したユーザーが、公平に利益の分配を受けられる世界。それがWeb3の描く理想郷です。
Web3を支える4つのキーワード
この理想を支えるのが、以下の4つのキーワードです。
- ブロックチェーン: 取引記録などを「ブロック」という単位でまとめ、それを「チェーン」のようにつないで管理する技術です。「分散台帳」とも呼ばれ、データが改ざんされにくく、透明性が高いのが特徴です。特定の管理者がいなくても、多くの参加者(マイナー)が報酬(暗号資産)を得るために競い合うことで、システム全体が半永久的に維持されます。
- スマートコントラクト: ブロックチェーン上で、あらかじめ決められたルールを自動的に実行するプログラムです。例えば「NFTが売れたら、売上の10%をアーティストに自動送金する」といった契約を、第三者を介さずに(Trustlessに)実行できます。これにより、不動産取引のような複雑な契約や、JASRACのような「中抜き組織」を不要にし、コストを下げ、透明性を高めることが可能になります。
- NFT(非代替性トークン): ブロックチェーン技術を使って発行される、「これは唯一無二のデジタルデータである」という鑑定書のようなものです。コピーが容易だったデジタルアートに「所有権」や「希少性」という概念をもたらし、アーティストに新たな収益の道を開きました。
- DAO(自律分散型組織): ブロックチェーンとスマートコントラクトを用いて、リーダーや中央管理者がいなくても運営される組織のことです。予算の使い方などの重要な意思決定が、ガバナンストークンを持つメンバーの投票と、スマートコントラクトによる自動執行によって行われます。著者は、最もDAOらしいDAOとして「Nouns DAO」への参加経験を語っています。Nouns DAOでは、1日に1つ生成されるキャラクターNFTのオークション売上が組織の基金となり、その使い道をメンバーの投票で決めています。
「なんちゃってWeb3」にご用心
しかし、著者は現在のWeb3サービスの多くが、実は本当の意味でのWeb3ではない「なんちゃってWeb3」だと指摘します。
例えば、多くの「Play2Earn(遊んで稼ぐ)」ゲームでは、NFTや報酬はブロックチェーン上にありますが、ゲーム自体は運営会社のサーバー上で動いています。これは、会社が倒産すればサービスは停止し、ユーザーが購入したNFTも無価値になることを意味します。これは、特定の企業に依存するWeb2.0と何ら変わらない中央集権的な仕組みです。
著者がWeb3技術に感じる最大の魅力は、一度ブロックチェーン上に正しく作られたアプリケーションは、開発者がいなくなっても永続的に動き続ける「永続性」にあります。この永続性が保証されてこそ、真のWeb3と言えるのです。
第2章 Web3業界のリアル – 投機と搾取の温床か?
理想とは裏腹に、現在のWeb3業界は投機マネーが渦巻き、消費者を惑わすビジネスが横行しています。その実態を、本書は容赦なく暴き出します。
Game-Fiの罠:「遊んで稼ぐ」はポンジスキームか?
Web3ビジネスで今最も盛り上がっている分野の一つが「Game-Fi(ゲームファイ)」、特に「X2Earn(〜して稼ぐ)」と呼ばれるモデルです。
- Axie Infinity(Play2Earn): モンスターを戦わせて、ゲーム内通貨を稼ぐ。
- STEPN(Move2Earn): NFTのスニーカーを買い、歩いたり走ったりすることでゲーム内通貨を稼ぐ。
これらのゲームでは、ユーザーが稼いだゲーム内通貨(アプリコイン)を暗号資産取引所で法定通貨に換金できるため、「稼げる」ことが大きな魅力となっています。
しかし、そのビジネスモデルには大きな問題が潜んでいます。著者は、この仕組みが本質的に「ポンジスキーム」や「ネズミ講」と同じだと断言します。
そのカラクリはこうです。
ユーザーへの報酬は、運営者が元手ゼロで発行できる独自の「アプリコイン」で支払われます。運営者の収益源は、ゲームを始めるためにユーザーが購入するNFTの売上です。つまり、後から参加した新規ユーザーが支払ったお金が、先行して参加していたユーザーへの報酬の原資となっているのです。
このモデルは、新規ユーザーが永遠に増え続ける限りにおいてしか成立しません。ひとたび成長が止まれば、アプリコインの価格は暴落し、後から参入した多くのユーザーは大きな損失を被ることになります。これは、消費者を守る規制が追いついていないことを利用した、パチンコやガチャをしのぐ「新たな搾取ビジネス」だと著者は厳しく批判しています。
NFTブームの裏側:コミュニティと先行者利益
2021年頃から始まったNFTブームも、その実態は投機的な側面が色濃いものでした。
猿のイラストで有名な「Bored Ape Yacht Club (BAYC)」などの高額NFTコレクションの成功の裏には、巧みなマーケティングとコミュニティ形成があります。
発行元は、Discordなどのツールを使ってリリース前からコミュニティを形成し、「ホワイトリスト(誰よりも早く、安くNFTを手に入れる権利)」を一部の初期参加者に与えることで希少性を煽ります。これが「即日完売」や二次流通市場での価格高騰を生み出し、さらなる人気を呼ぶのです。
インフルエンサーたちは、この「先行者利益」を活用して安く手に入れたNFTを「今後の値上がりが期待できる」と紹介し、市場を盛り上げます。これは、自分が儲けるための「ポジショントーク」に他なりません。
著者は、Yuga Labs(BAYCの発行元)のビジネスの本質は、Web3が目指す非中央集権的なものではなく、ディズニーのような昔ながらの「IP(知的財産)ビジネス」に過ぎないと分析しています。
ビッグテックはWeb3をどう見ているか?
GAFAMのような巨大企業もWeb3を静観しているわけではありません。しかし、その取り組みは、Web3の本質である非中央集権化とは異なる方向を向いています。
Facebookから社名変更したメタは、メタバースに巨額の投資をしていますが、これはユーザーを自社のVRグラスとアカウントに囲い込む「閉じた世界」を目指すものであり、Web3のオープンな思想とは相容れません。
GoogleやMicrosoftも、ブロックチェーン関連のインフラサービスやスタートアップ投資を行ってはいますが、まだ本腰を入れているとは言えず、危機感を抱いている様子もない、と著者は見ています。
第3章 Web3の未来 – 伝説のプログラマーが見る景色
現在のWeb3業界への幻滅を語る一方で、著者は技術そのものが持つ可能性に強い確信を抱いています。その確信は、彼自身が「手を動かし、コードを書き続けた」ことから生まれています。
手を動かす者だけが見える世界
著者は、イノベーションは計画からは生まれず、現場のエンジニアが試行錯誤する中から生まれると自身の経験を元に語ります。
マイクロソフト時代、次世代OSとして社内で本命視されていたのは、多くの人員と予算を投じられた「Cairo」プロジェクトでした。しかし、そこでは議論ばかりが続き、コードは一向に書かれませんでした。
一方で、中継ぎと見なされていた小さなチーム「Chicago」に自ら移った著者は、プログラマーの自由な発想を重視する環境で、現在のWindowsの原型となる「右クリックメニュー」や「エクスプローラ」といった画期的な機能を次々と実装します。結果的に、世界を席巻したのは、机上の空論ではなく、手を動かして作られたWindows95でした。
この「実践主義」こそが、著者の信条であり、新しい技術と向き合う上での極意なのです。
DAOからDAEへ:真の非中央集権エコシステム
著者は、自らフルオンチェーン(全てのデータがブロックチェーン上にある)のNFTプロジェクトを立ち上げ、プログラミングを行う中で、Web3が目指すべき新たなビジョンにたどり着きます。
それが「DAE(Decentralized Autonomous Ecosystem:非中央集権型自律システム)」という構想です。
これは、メンバーの多数決という人間的な要素が強く、リーダーシップの不在という課題を抱えるDAOから、「Organization(組織)」を排除するアイデアです。
その代わりに、スマートコントラクトによって自律的に連動する複数のサービスが、一つの経済圏(エコシステム)を形成します。
著者がその最初の例として開発しているのが「Draw2Earn」というWeb3版お絵描きアプリです。
このアプリでは、あるアーティストが描いた絵(オリジナル作品)を、別のクリエイターが利用して二次創作を行うと、その収益の一部がスマートコントラクトによって自動的にオリジナル作者にも分配されます。
この仕組みでは、ロイヤリティを分配するための組織は不要です。クリエイターは、価値を提供しない「中抜き業者」に搾取されることなく、正当な報酬を受け取ることができます。そしてこのエコシステムは、ブロックチェーンが存続する限り、永続的に動き続けます。
著者は、こうした非営利的な目的(社会への価値提供)を中心に、開発者がトークンによって直接インセンティブを得るDAEこそが、GAFAMのような新たな中央集権的勝者を生むことなく、Web3の理想を実現する道だと考えています。
結論:ビジネスパーソンはWeb3とどう向き合うべきか
投機的なバブルが弾け、「クリプトの冬」が訪れた今、私たちはWeb3とどう向き合えばよいのでしょうか。本書は、その羅針盤となるいくつかの重要な視点を与えてくれます。
第一に、「世の中にうまい儲け話などない」という原理原則を忘れないことです。「遊んでいるだけで楽に稼げる」といった甘い言葉の裏には、必ずリスクが潜んでいます。先行者利益を謳う話は、その原資がどこから来ているのかを冷静に考えるべきです。
第二に、「消費者」になるのではなく、「クリエイター」になることです。新しい技術が登場した時、ただそれを利用する側でいるだけでは、本質的な価値は見えてきません。たとえ小さくても、自ら手を動かして何かを作ってみる。プログラマーでなくとも、その精神はビジネスのあらゆる場面で活きるはずです。
そして最後に、「クリプトの冬」はむしろ好機だと捉えることです。熱狂が冷め、投機的なプレイヤーが市場から去った今こそ、技術の本質に向き合い、真に価値のあるサービスを構築しようとする人々にとっては、絶好の機会です。
Web3が社会に真の価値を提供するまでには、まだ3年、5年、あるいはそれ以上の時間が必要かもしれません。しかし、その根幹にある「永続性」と「透明性」という技術の火種は消えていません。
本書は、Web3という混沌の先に広がる未来を、確かな技術的知見と揺るぎない信念で照らし出す、すべてのビジネスパーソン必読の一冊と言えるでしょう。