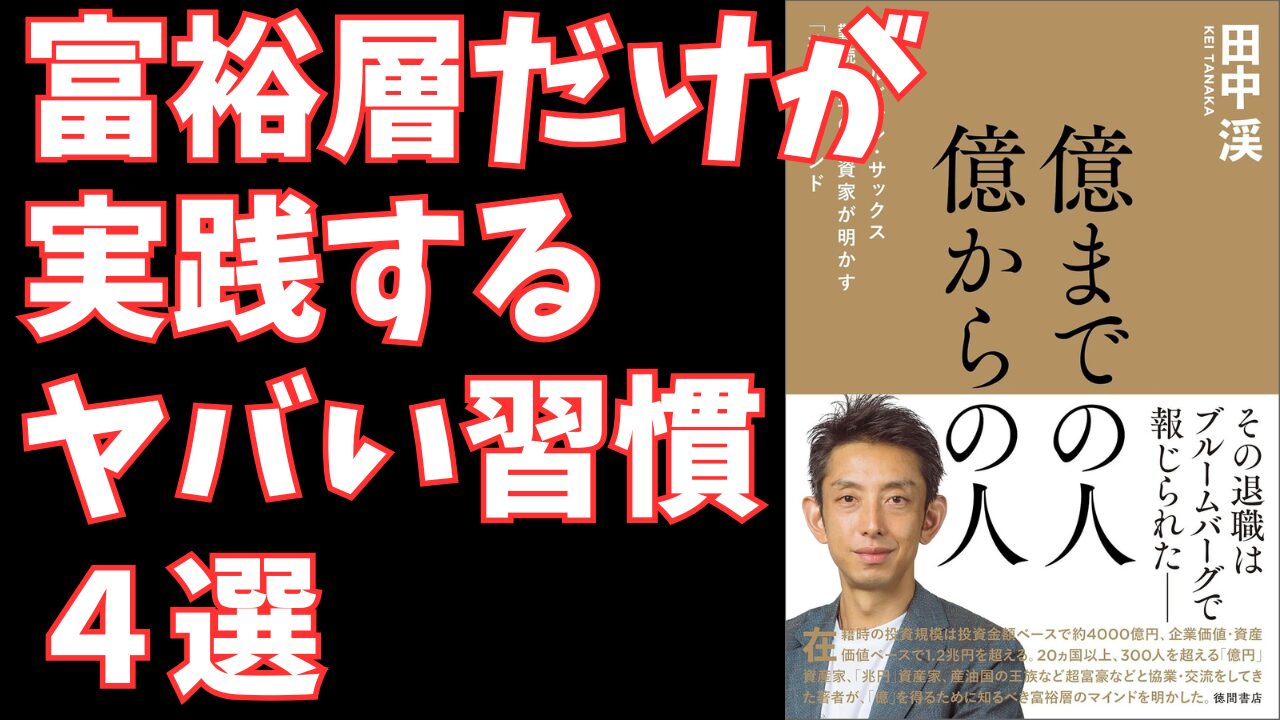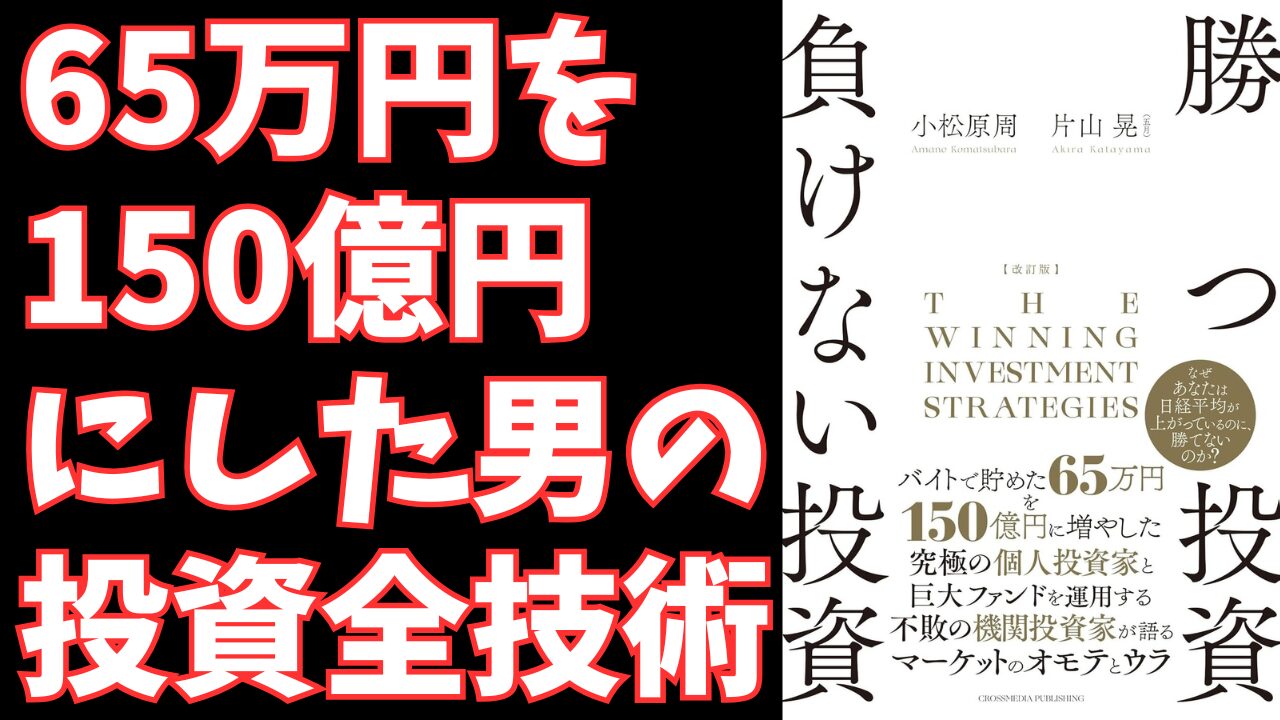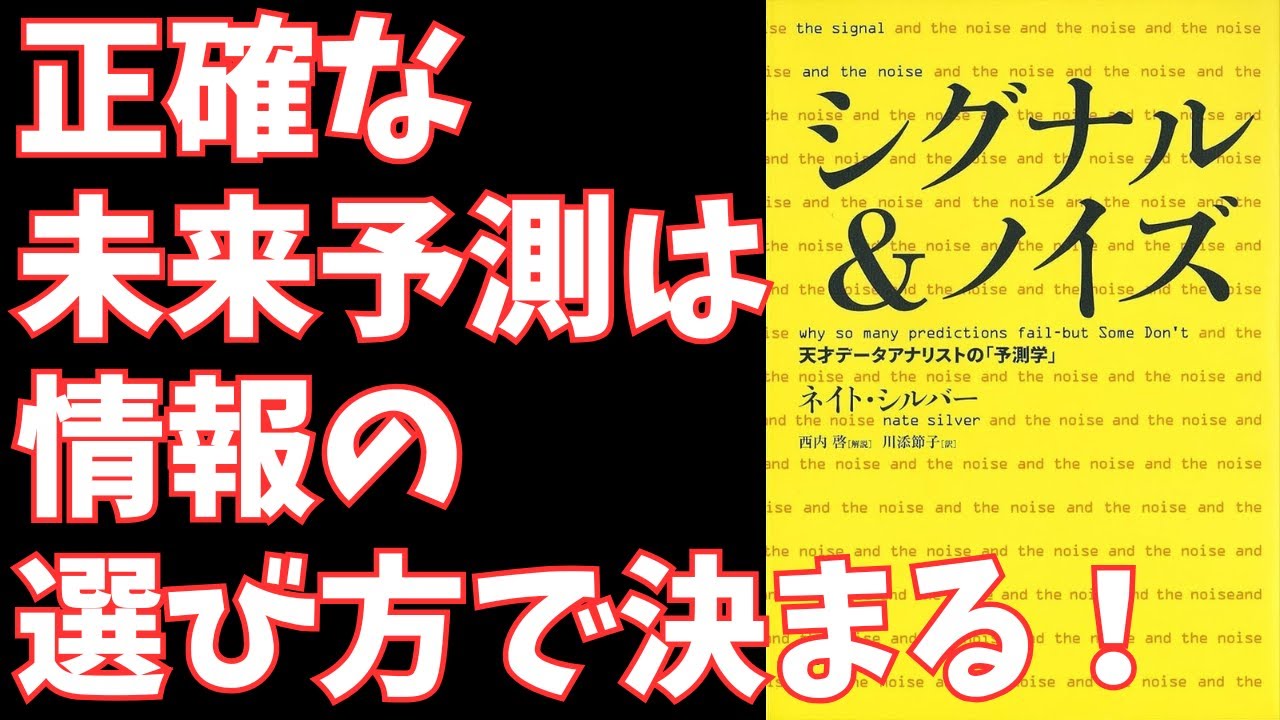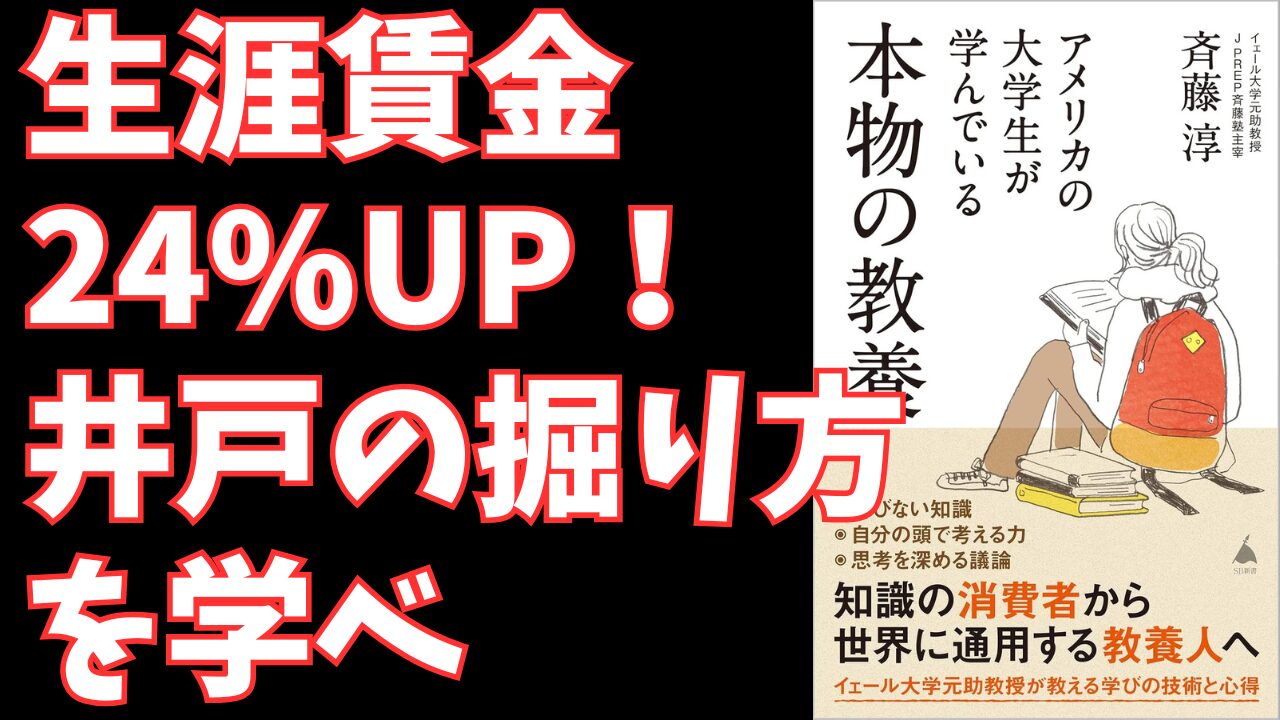『人生にお金はいくら必要か』老後2000万円問題の「本当の」解決策|人生設計の基本公式を全解説
本書『人生にお金はいくら必要か』は、世間を騒がせた「老後2000万円問題」の本質を解き明かし、一人ひとりが自分自身の状況に合わせて将来必要なお金を計算できる「人生設計の基本公式」を提示する一冊です。
本書が提唱するのは、他人の平均値に惑わされることなく、自分の収入やライフプランに基づいて「必要な貯蓄率」を算出し、計画的に資産を形成していくことの重要性です。さらに、その資産を「長期・分散・低コスト」の原則に則って正しく運用する方法や、iDeCo・NISAといった税制優遇制度の具体的な活用法まで、網羅的に解説されています。
この記事では、本書の核心である「人生設計の基本公式」の使い方を具体的なケーススタディを交えながら詳しく解説するとともに、忙しいビジネスパーソンが陥りがちな運用の罠を避け、シンプルかつ合理的な資産形成を実現するためのエッセンスを凝縮してお伝えします。
本書の要点
- 「老後2000万円」は他人の平均値。自分の数字で計算することが本質的な解決策である。
- 「人生設計の基本公式」を使えば、現役時代にどのくらいの貯蓄をすべきか(必要貯蓄率)を自分自身で算出できる。
- 資産運用は「長期・分散・低コスト」が鉄則。具体的な商品は「インデックスファンド」と「個人向け国債」で十分。
- iDeCoやNISAといった税制優遇制度を最大限に活用することが、効率的な資産形成のカギとなる。
- 資産寿命は不確実な運用益をあてにするのではなく、老後の資産を計画的に取り崩すことで延ばしていくべきである。
はじめに:「老後2000万円問題」に終止符を打つ一冊
2019年、金融審議会の報告書をきっかけに日本中を駆け巡った「老後2000万円問題」。この報道を受け、「自分の将来は大丈夫だろうか」と漠然とした不安を抱いたビジネスパーソンは少なくないでしょう。
メディアでは連日、年金制度への不信感や資産運用の必要性が叫ばれましたが、その多くは「で、具体的に自分はどうすればいいのか?」という最も知りたい問いへの明確な答えを示してはくれませんでした。
今回ご紹介する『人生にお金はいくら必要か』(山崎元・岩城みずほ著)は、まさにその問いに「明確な答え」と「具体的な方法」を提示してくれる一冊です。
著者たちは、この問題の本質は「他人の平均値にもとづく老後資金の目処」に振り回されることにあると指摘します。そして、本当に必要なのは「魚を与えることではなく、魚の釣り方を教えること」、つまり、自分自身の状況に合わせて必要額を計算する方法を知ることだと喝破します。
この記事では、本書の核心である「人生設計の基本公式」を中心に、あなたの老後不安を解消し、今日から実践できる具体的な資産形成のステップを、本書の事例を交えながら詳しく解説していきます。
「老後2000万円問題」の正体とは?
多くの人が誤解していますが、本書によれば、金融審議会の報告書そのものは決して悪い内容ではなかったとされています。では、なぜあれほどの大騒ぎになったのでしょうか。
ポイント①:「2000万円」は単なる一例に過ぎない
報告書で示された「2000万円」という数字は、あくまで総務省の家計調査をもとにした「高齢夫婦無職世帯の平均的な姿」から導き出された一例に過ぎませんでした。
高齢夫婦無職世帯の平均的な姿で見ると、毎月の赤字額は約5万円となっている
これをもとに「収入と支出の差である不足額約5万円が毎月発生する場合には、20年で約1300万円、30年で約2000万円の取崩しが必要になる」
と試算されたもので、すべての国民に2000万円の貯蓄を強いるような内容ではなかったのです。収入や支出の状況、働き方のプラン、退職金の有無、家族構成などは人それぞれ。2000万円で足りる人もいれば、まったく足りない人もいるのは当然です。
本書が最も問題視しているのは、報告書が「自分の数字で将来の計算をする方法を説明しなかったこと」にあります。
ポイント②:公的年金は破綻しない
この騒動をきっかけに「年金制度は破綻するのではないか」という不安が再燃しましたが、本書はこれを明確に否定しています。
日本の公的年金は、現役世代が払った保険料で高齢者世代の年金を賄う「賦課方式」が基本です。将来、支給額が実質的に目減りすることはあっても、日本という国が続く限り、制度そのものが破綻することは考えにくいのです。
GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の資料によれば、年金給付の財源の約9割はその年の保険料収入と国庫負担で賄われています。極論すれば、積立金の運用が大失敗しても、9割程度の給付は可能だということです。
年金制度を過度に不安視するのではなく、将来受け取れる年金額を把握し、それをベースに人生設計を考えることこそが建設的なのです。
あなたの不安を解消する「人生設計の基本公式」
では、自分にとって必要な貯蓄額は、どうやって計算すればいいのでしょうか。その答えが、本書が提示する「人生設計の基本公式」です。
この公式は、現役時代の生活レベルに対して、老後の生活レベルをどの程度に設定したいかを考え、それを実現するために「現役時代の手取り年収のうち、何パーセントを貯蓄に回すべきか(=必要貯蓄率)」を算出するものです。
一見複雑に見えるかもしれませんが、必要な項目は6つだけ。電卓があれば誰でも計算できます。
- 今後の手取り年収(Y): 現役時代を通じて得られるであろう、税金や社会保険料が引かれた後の年収の平均値。
- 老後生活費率(x): 現役時代の生活費に対し、老後の生活費を何割にしたいかの倍率(例:7割なら0.7)。
- 年金額(P): 将来受け取れる公的年金などの手取り額。夫婦の場合は合算。
- 現在資産額(A): 現在の預貯金や投資資産の合計。今後の大きな支出(教育費、住宅頭金など)は差し引く。
- 現役年数(a): これから働く年数。
- 老後年数(b): リタイアしてから亡くなるまでの想定年数。
これらの数字を公式に当てはめることで、あなただけの「必要貯蓄率」が明らかになります。この貯蓄率を守って計画的に貯蓄を続ければ、お金に関する将来の心配はほとんどなくなる、と本書は断言しています。
計算をせずに、現実を見ないことこそが、必要以上の不安を引き起こし、例えば、勧められるまま、よく分からないままに、買うべきでない金融商品を買ってしまうなど、お金の問題に関する大きな失敗の原因になります。
まずは自分の数字で計算し、漠然とした不安を具体的な目標に変えることが第一歩です。
ケーススタディで実践!あなたの必要貯蓄率は?
「人生設計の基本公式」の有効性は、具体的な事例でシミュレーションすることで、より深く理解できます。本書に掲載されているケースを参考に、様々なライフステージでの計算例を見ていきましょう。
ケース1:新入社員・山田くん(23歳・独身)の場合
- 今後の手取り年収:480万円(40歳先輩を参考に控えめに設定)
- 老後生活費率:0.7倍
- 年金額:197万円(65歳からと仮定)
- 現在資産額:0円
- 現役年数:42年(65歳まで)
- 老後年数:35年(100歳まで生きると想定)
この条件で計算すると、山田くんの必要貯蓄率は約15.2%となります。
つまり、生涯にわたって手取り年収の約15%を貯蓄し続ければ、100歳までの生活設計の辻褄が合う計算です。
若いときは、年収が低いので、貯金するのは大変だとか、貯金するよりも自己投資にお金を使うべきだといった意見もありますが、貯蓄の重要性には早い時期に気付くことが肝要です。
「運よく余ったら貯蓄する」のではなく、給料が入ったらまず必要額を天引きで貯蓄し、残ったお金で生活するという習慣を若いうちから身につけることが、人生の主導権を握る上で極めて重要です。
ケース2:山田くんが結婚したら?(33歳・妻28歳)
山田くんが33歳で結婚。現在資産は450万円に増えました。妻が専業主婦になるケースで再計算してみましょう。
大きく変わるのは「年金額」と「老後年数」です。
妻の年金(手取り80万円と仮定)が加わり、夫婦の年金額は277万円に。また、妻の方が長生きする可能性を考慮し、老後年数は5年延ばして40年とします。
すると、必要貯蓄率は約6.6%に下がります。
ただし、これは子どもがいない場合の楽観的な数字です。
もし、子どもが一人生まれ、大学までの教育費として1000万円を想定する場合、「現在資産額」から1000万円を差し引いて計算します(450万円 – 1000万円 = -550万円)。
その結果、必要貯蓄率は約10.1%に上昇します。
この貯蓄率の達成が難しいのであれば、「妻がパートに出て収入を増やす」「老後生活費率を見直す」といった対策を検討することになります。このように、ライフイベントが発生するたびに公式を使ってシミュレーションし、家計の軌道修正を行うことが、この公式の真骨頂なのです。
【超重要】シンプルで正しいお金の増やし方
必要な貯蓄率が分かり、計画的に貯蓄ができるようになったら、次のステップは「貯まったお金を適切に運用し、増やす」ことです。本書が提唱する運用法は、驚くほどシンプルです。
運用の3大原則「長期・分散・低コスト」
本書は、資産運用のコツは「長期・分散・低コスト」の3つに集約されると述べています。
- 長期投資: 短期的な価格変動に一喜一憂せず、じっくりと腰を据えて資産の成長を待つ。
- 分散投資: 一つの資産に集中投資するのではなく、国内外の様々な資産に分けて投資することでリスクを抑える。
- 低コスト: 金融機関に支払う手数料を極限まで抑える。手数料は確実なマイナスリターンであり、運用成績に大きな影響を与える。
この3原則を呪文のように唱えながら自分の運用を見直せば、大きな失敗は避けられるでしょう。
選ぶべき商品は、たったの3つでいい
世の中には無数の金融商品がありますが、本書は「個人が必要な商品は3つだけで大丈夫」と言い切ります。
- 外国株式のインデックスファンド: 日本を除く先進国や全世界の株価指数に連動する投資信託。低コストで世界経済の成長の恩恵を受けられる。
- 国内株式のインデックスファンド: TOPIX(東証株価指数)に連動する投資信託。日経平均よりも分散が効いており安定的。
- 個人向け国債変動金利型10年満期: 元本割れのリスクが極めて低く、金利上昇にもある程度対応できる安全資産。
運用商品は、「外国株式のインデックスファンド」、「国内株式のインデックスファンド」、「個人向け国債変動金利型10年満期」の3つを知っていればそれでよく、金融マンやファイナンシャルプランナーが紹介してくれるようなその他の運用商品やサービスはいっさい知らなくて構いませんし、運用を間違えないためには、むしろ知らない方がいいくらいのものなのです。
これら以外の、例えば手数料の高いアクティブファンドや、仕組みが複雑な保険商品、毎月分配型の投資信託などは、すべて不要だと断言しています。
最強の布陣!iDeCoとNISAを使い倒す
運用を行う上で、iDeCo(個人型確定拠出年金)とNISA(少額投資非課税制度)の活用は必須です。これらは国が用意してくれた、運用益が非課税になるなどの税制優遇を受けられる「有利なお金の置き場所」です。
- iDeCo: 掛け金が全額所得控除の対象となり、所得税・住民税が安くなる強力なメリットがある。ただし、原則60歳まで引き出せない。
- つみたてNISA: 年間40万円までの投資で得た利益が最長20年間非課税になる。いつでも引き出し可能で、金融庁が厳選した低コストな商品が中心。
本書が推奨する手順は、
- まずiDeCoの拠出限度額を最大限に利用する。
- 次につみたてNISAの非課税枠を使い切る。
- それでも余裕があれば、課税口座(特定口座)で運用する。
というものです。この有利な制度を使わない手はありません。
今すぐ捨てるべき、お金に関する「4つの思い込み」
最後に、本書で紹介されている「10大注意事項」の中から、特にビジネスパーソンが陥りがちな罠を4つご紹介します。これらを意識するだけで、あなたのお金を守る力は格段に向上するはずです。
- 「専門家の言うことだから」という思い込み
金融機関の担当者は、あなたの資産を増やすプロではなく、自社の利益のために手数料を稼ぐプロです。彼らの勧める商品を鵜呑みにしてはいけません。「無料相談」には近づかず、「欲しいのはこの商品だけ」という強い意志を持って接することが重要です。 - 「インカム収入(分配金・配当)が大事」という思い込み
「毎月分配金がもらえる」「配当利回りが高い」といった言葉に惹かれてはいけません。運用の評価は、値上がり益(キャピタルゲイン)とインカムゲインを合計したトータルリターンで判断するのが鉄則です。インカム収入へのこだわりは、手数料の高い不適切な商品を選ぶ温床になります。 - 「買い値にこだわる」という思い込み
「買った値段より下がっているから売れない」というのは、最も不合理な判断の一つです。過去の買い値は、今後の運用判断とは何の関係もありません。「変えられない過去」ではなく、「これから変えられる将来」に目を向けましょう。 - 「手数料は気にするほどではない」という思い込み
手数料は、あなたのリターンを確実に蝕むコストです。本書では「0.5%ルール」、つまり「運用金額に対して年間に支払うトータルの手数料が明確に0.5%以下の運用商品・サービス以外に、一切関わらない」という行動ルールを提唱しています。 これを守るだけで、不適切な商品の大半を排除できます。
まとめ:漠然とした不安を、具体的な行動計画へ
『人生にお金はいくら必要か』は、私たちを長年縛り付けてきた「老後資金」という漠然とした不安に対し、極めてシンプルかつ強力な羅針盤を与えてくれる一冊です。
本書の最大の功績は、お金の問題を「他人事」から「自分事」へと転換させてくれる点にあります。
「人生設計の基本公式」というツールを手に入れることで、あなたはもう、メディアが報じる平均値や、金融機関のセールストークに惑わされることはありません。自分の人生の舵を自分で握り、ライフプランの変化に柔軟に対応しながら、着実に未来への資産を築いていくことができるようになるはずです。
忙しい日々の中で、将来のお金のことを考えるのは後回しになりがちです。しかし、本書が示す方法は、一度理解してしまえば、決して難しいものではありません。
この記事をきっかけに本書を手に取り、ぜひあなた自身の「人生設計の基本公式」を計算してみてください。その一つのアクションが、漠然とした不安を具体的な行動計画へと変え、より豊かで安心な未来への第一歩となることを確信しています。