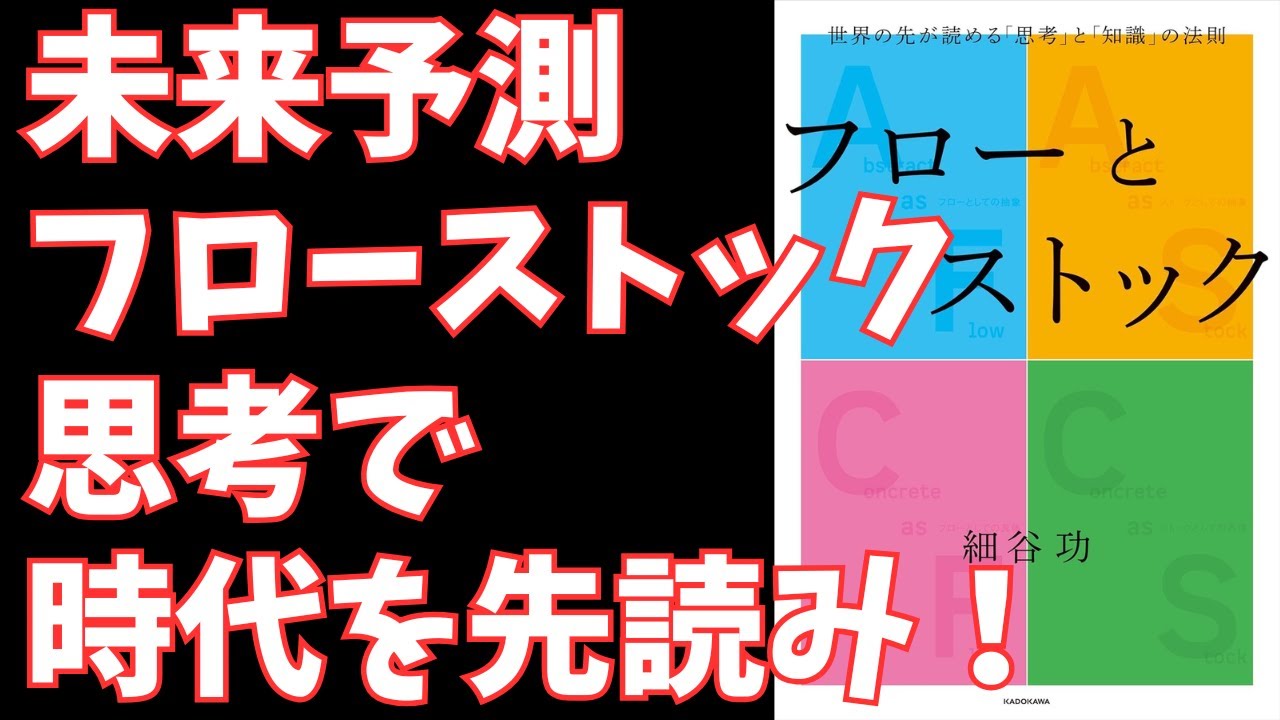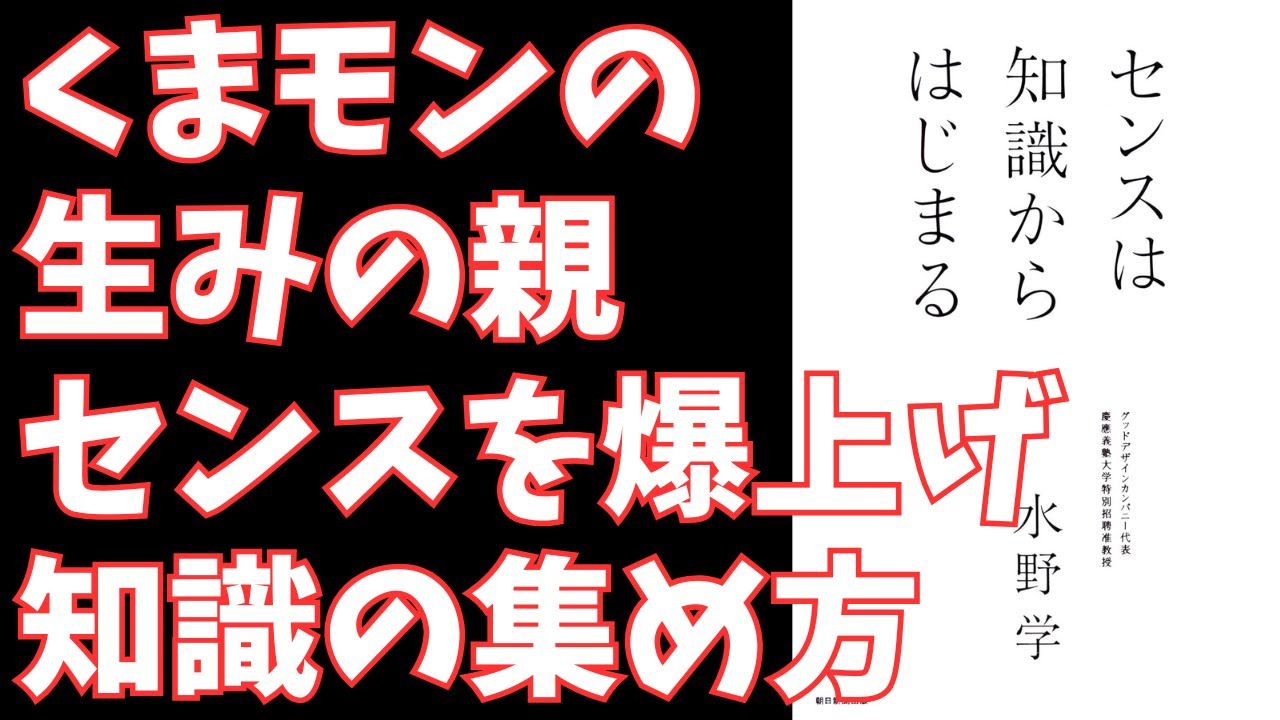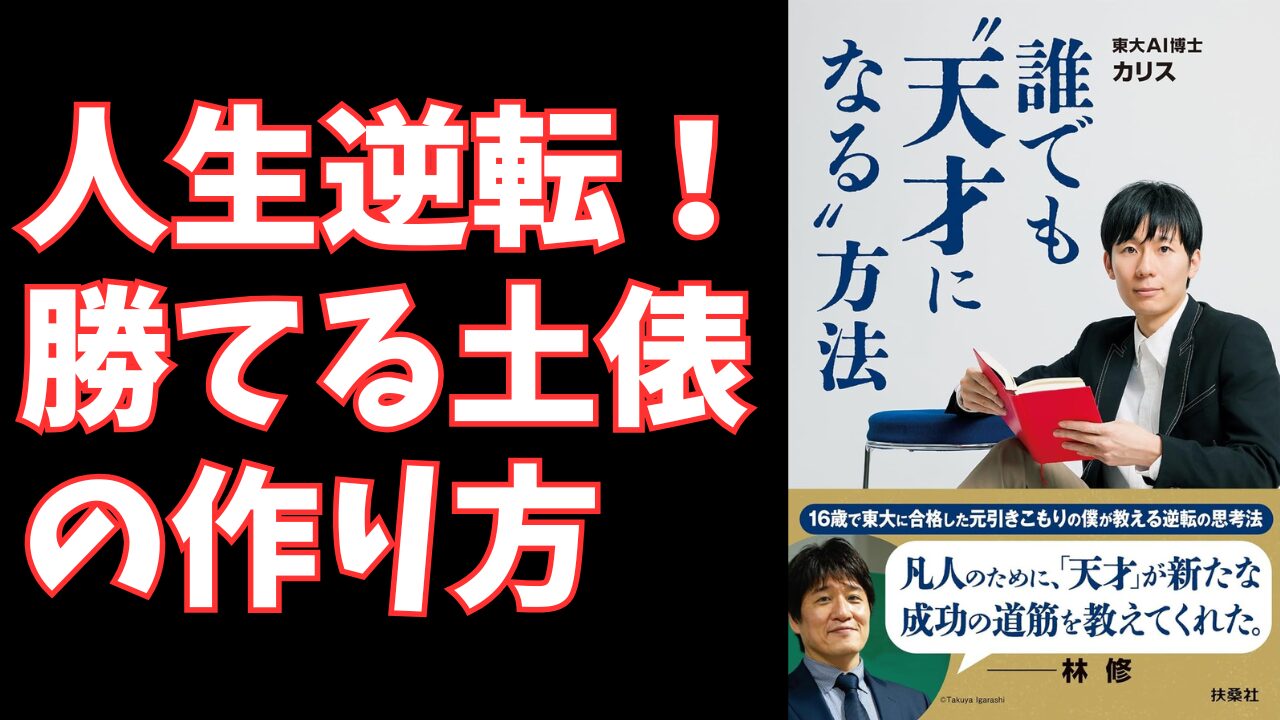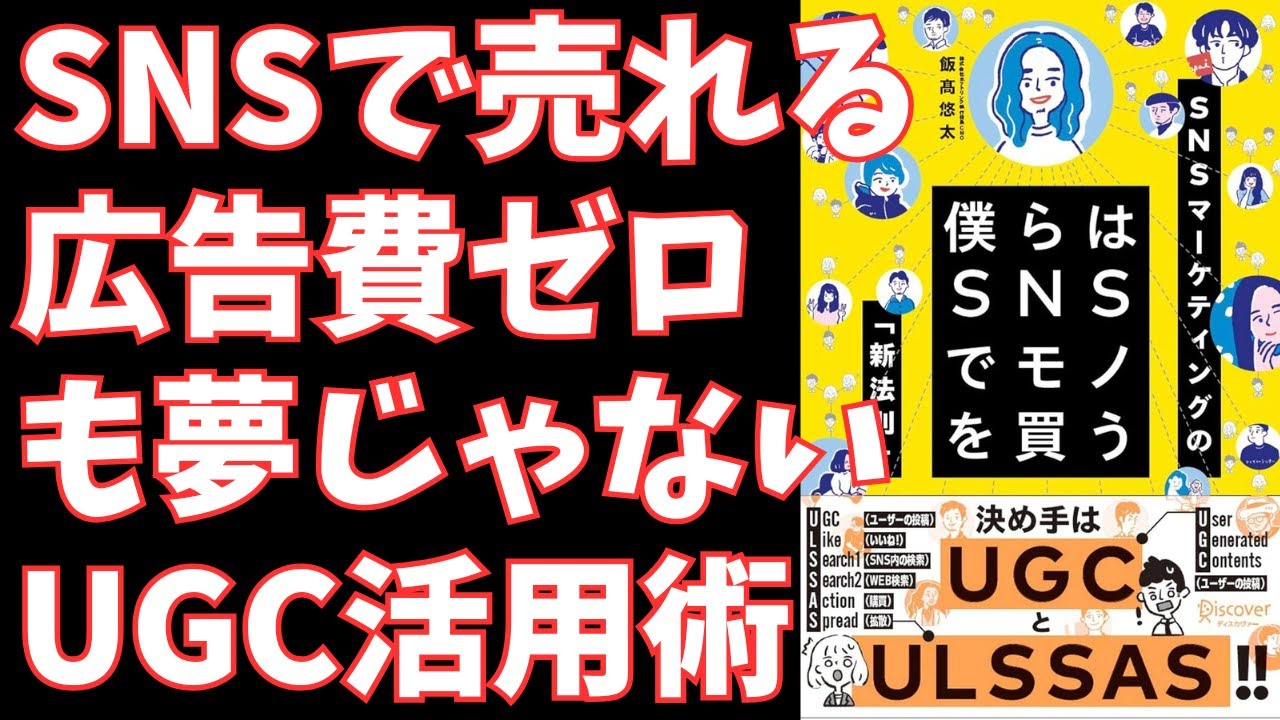『愛すべき凡庸な日常』|仕事と人生に疲れたあなたへ贈る、ささやかな日常を愛おしむヒント
本書『愛すべき凡庸な日常』は、会社員でありながら作家として活動する守田樹氏による、エッセイと小説からなる作品集です。うつ病の経験、ミニマリストとしての生活、会社員としての日常、そして「隠居」への憧れなど、著者自身の等身大の経験が、ユーモアと誠実な筆致で綴られています。
この記事では、多忙な日々を送るビジネスパーソンに向けて、本書の中から特に心に響くエピソードを厳選して紹介します。ストレスとの上手な付き合い方、日常に潜む面白さを見つける視点、そしてこれからの働き方や生き方を考えるヒントが満載です。明日からの毎日を、少しだけ愛おしく、そして軽やかに過ごすためのヒントがきっと見つかるはずです。
本書の要点
- 何気ない日常にこそ面白さは潜んでいる:見慣れた風景や些細な出来事も、視点を変えればユニークな発見やユーモアの源泉になります。
- 弱さや失敗は、ユーモアで乗り越えられる:自身の弱さや過去の失敗を深刻に捉えすぎず、笑いに変えることで、前向きな力に変えることができます。
- 自分だけの「ストレス解消法」を持つ:他人の評価を気にせず、自分が心から「楽しい」「心地よい」と感じる方法で、心と体を労わることが大切です。
- 「好きなこと」から始める小さな挑戦が人生を豊かにする:仕事の役に立つかで判断せず、純粋な好奇心から始めた趣味や学びが、思いがけない喜びや新しい道を開くきっかけになります。
- オルタナティブな生き方を想像してみる:現在の働き方や生活が全てではありません。「隠居」のような異なる生き方を具体的に想像することで、今の自分を客観視し、心に余裕が生まれます。
はじめに:なぜ、あなたの日常は「凡庸」で終わるのか
「毎日同じことの繰り返しだ…」
「仕事に追われて、自分の時間なんてない」
「このままでいいんだろうか…」
多忙な日々を送る中で、ふとそんな思いに駆られることはありませんか。守田樹氏の『愛すべき凡庸な日常』は、そんなあなたの心にそっと寄り添い、凝り固まった日常に新たな風を吹き込んでくれる一冊です。
著者は、私たちと同じように会社員として働きながら、うつ病を経験し、ミニマリストとして生活を模索する、ごく普通の(しかしユニークな)人物。本書で描かれるのは、ドラマティックな成功体験ではありません。喫茶店でのささやかな出会い、うつ病の主治医とのやり取り、壮大な(?)隠居計画、そしてクスッと笑える失敗談の数々。
しかし、その 「凡庸」とも思える日常を、著者は鋭い観察眼とユーモアで切り取り、かけがえのない「愛すべき」時間として描き出します 。
この記事では、本書のエッセンスを抽出し、忙しいビジネスパーソンが明日から実践できる「日常を面白がるヒント」を、具体的なエピソードと共にお届けします。あなたの「凡庸な日常」が、少しだけ輝き出すきっかけになれば幸いです。
見出し1:「なんか、じわる」― 日常にユーモアを見出す視点
仕事のプレゼン資料、びっしりと埋まったスケジュール、鳴り止まない通知。効率と成果が求められるビジネスの世界では、「遊び心」や「ユーモア」は後回しにされがちです。しかし、著者は日常に潜む「なんか、じわる」瞬間を見つける天才です。
名古屋の「横浜銀行」から始まる思索
本書に収録されている「名古屋の横浜銀行」というエッセイは、著者のユニークな視点が光る一編です。
名古屋のホテルに滞在中、バルコニーから「横浜銀行」の看板を見つけた著者。通常なら「ああ、支店があるんだな」で終わる光景です。しかし、著者はここで一つの問いを立てます。
「なぜ名古屋に横浜銀行があるのだろうか」
そして、無意味とも思える思索を続けた結果、ある仮説にたどり着きます。
「新幹線のぞみ号の視点に立つと、名古屋の隣は横浜である」
のぞみ号は名古屋を出ると、次は新横浜に停車します。つまり、のぞみ号にとっては、名古屋と横浜は「お隣さん」。だから横浜銀行があっても不思議ではない、という結論です。
このエピソードは、私たちに 固定観念を外して物事を見る面白さ を教えてくれます。ビジネスにおいても、常識を疑い、異なる視点から物事を捉え直すことで、革新的なアイデアが生まれることは少なくありません。日々の業務の中で「当たり前」とされていることに対し、「なぜだろう?」と問いを立ててみる。それだけで、退屈だった仕事が少しだけ面白いゲームに変わるかもしれません。
喫茶店のマダムが残した言葉
もう一つ、「喫茶店のマダム」のエピソードも印象的です。
お気に入りの喫茶店で読書をしていると、品の良いマダムに「なんの本を読んでいるの?」と話しかけられます。
「急にごめんなさいね。なんの本を読んでいるのかさっきからずっと気になっていて、思わず声をかけちゃったの。ほら若い子って最近本を読む人が少ないから、すごく気になってしまったの。」
そして、こう付け加えるのです。
「これからもたくさん本を読んでいってね。」
この言葉を、著者はまるで未来の自分からのメッセージのように受け止めます。このささやかな出会いをきっかけに、「本という小さな世界を愛し続け、少しでも拡張できるような存在になりたい」という決意を新たにするのです。
日々の業務で関わる人々との何気ない会話。そこにも、あなたの仕事観や人生観を揺さぶるような、大切な言葉が隠されているかもしれません。ただ通り過ぎるのではなく、少しだけ耳を傾け、その言葉の意味を味わってみる。そんな心の余裕が、日々の仕事に深みを与えてくれるのではないでしょうか。
見出し2:激務に疲れた心に効く処方箋 ― ストレスとの向き合い方
終わらない仕事、複雑な人間関係、将来へのプレッシャー。ビジネスパーソンにとって、ストレスは切っても切れない存在です。本書では、著者のうつ病経験を通して、ストレスと上手に付き合うための具体的なヒントが示されています。
「ヤブ医者」だと思った主治医の的確なアドバイス
うつ病からの回復期、著者は「世間から遅れをとっている」という焦りから、転職や資格取得に手を出そうとします。しかし、主治医であるT先生はそれを止め、「いまはとにかく休む。やっている仕事のことだけを考えれば良い」と告げます。
著者は心の中で「なんだ、あのヤブ医者は」と反発しますが、実は先生の言う通り、内緒で挑戦した資格の勉強は全く続かず、挫折を繰り返していました。
そんなある日、先生はこう問いかけます。
「守田君の今好きなことは何かな?」
著者が「コーヒーを淹れたり、飲み比べたりすることです」と答えると、先生は意外な提案をします。
「じゃあ、コーヒーの資格取ってみる?」「仕事のことは考えなくていいんだよ。趣味でやるだけなら出来そうじゃない?好きなコーヒーのこと勉強してみたら?」
仕事に役立つか、世間的に評価されるか、といった基準ではなく、 ただ「好き」という気持ちに従って行動してみる 。このアドバイスが、著者を良い方向へ導きます。コーヒーインストラクター検定の勉強は、集中力の低下に苦しみながらも「とにかく楽しかった」と振り返ります。そして、合格率8割の試験に合格した時、久しぶりに心からの嬉しい気持ちを味わうのです。
もしあなたが今、焦りや無力感に苛まれているなら、一度「〜ねばならない」という思考を手放してみませんか。仕事の成果とは全く関係のない、あなたが純粋に「好き」だと思えることに没頭する時間を作ってみてください。それは、遠回りのようで、実は心を回復させる一番の近道なのかもしれません。
自分だけの究極の「ストレス発散丼」
著者には、とっておきのストレス解消法があります。それが「ストレス発散丼」。
仕事帰りに少し良いステーキ肉を買い、ニンニクを効かせた我流のソースで仕上げ、炊きたてのご飯一合と共に一気にかき込む。
肉を食らう、米を食らう、この瞬間僕は、生きていると感じる。
一心不乱に肉と米を掻き込む。うまい、と声が漏れる。
このエピソードから学べるのは、 自分だけの「儀式」を持つことの重要性 です。それは、誰かに見せるためのものでも、お洒落なものである必要もありません。ただひたすら自分の欲求に正直になり、心と体を満たすための行為。そんな自分だけの贅沢が、明日への活力を生み出します。
あなたの「ストレス発散丼」は何ですか?高級なディナーでなくても、お気に入りのラーメンを食べる、好きな音楽を大音量で聴く、ただひたすら眠る、など何でも構いません。自分を甘やかすための「儀式」を、ぜひあなたの生活にも取り入れてみてください。
見出し3:「今の働き方、このままでいいの?」と悩むあなたへ
がむしゃらに働き続けてきたけれど、ふと立ち止まった時、「このままでいいのだろうか」という問いが頭をよぎる。そんな経験はありませんか。本書は、既存の価値観に縛られない、オルタナティブな生き方を想像させてくれます。
家賃3万円、週2労働の「隠居マニュアル」
著者は、来たるべき「隠居生活」に向けた計画(案)を、真剣に、そしてユーモラスに練り上げています。その名も「隠居マニュアル」。
候補は、東京だ。人生で一度くらいは上京しておきたい。
家賃は3万円。東京に家賃3万円の物件などあるのかと調べたらちゃんとあった。
大原扁理氏の著書を参考に、年収90万円(月7万5千円)での東京暮らしをシミュレーションします。家賃3万円を引いた4万5千円で生活し、年金や奨学金は支払い猶予を申請。週に2〜3回、時給1200円のバイトをすれば、残りの時間は全て創作や読書、散歩といった好きなことに費やせる、という計画です。
あれ、月に66時間って、今の仕事、普通に1週間で到達している気が…。いや、きっと何かの間違いである。
この自虐的なツッコミに、思わず笑ってしまいます。このマニュアルは、あくまで「机上の空論」かもしれません。しかし、 今とは全く違う働き方、生き方を具体的に想像してみること自体に価値があります 。
今の収入や社会的地位がなくなったら、自分には何が残るのか。本当にやりたいことは何なのか。「隠居マニュアル」は、そんな本質的な問いを私たちに投げかけます。今の生活に行き詰まりを感じたら、あなたも自分だけの「隠居マニュアル」を作ってみてはいかがでしょうか。それだけで、少し肩の力が抜けるはずです。
「100万ドルの夜景」の正体は「100万ドルの残業代」
神戸の夜景を見ていた著者は、ある事実に気づきます。きらびやかな夜景を作り出している高層ビルの光は、そこで働く人々の残業の光ではないか、と。
100万ドルの残業代
そうか、この夜景の正体は、残業だったのか。
この気づきを得てから、美しいと思っていた夜景が、必死に働く人々の姿と重なり、素直に楽しめなくなってしまいます。
私たちは、誰かの労働の上に成り立った便利な社会に生きています。そして自分自身も、社会を回すため、夜景の一部となるために、身を粉にして働いているのかもしれません。
このエピソードは、仕事の意味を深く考えさせます。何のために働くのか。誰のために働くのか。あなたの仕事は、誰かの生活を支え、社会の光の一部になっている。そう思うと、日々の業務にも少しだけ誇りが持てるかもしれません。同時に、働きすぎて自分自身が燃え尽きてしまわないよう、健全なバランスを保つことの重要性も示唆しています。
見出し4:弱さや失敗も、愛すべき自分の一部
成功体験ばかりがもてはやされる世の中で、自分の弱さや失敗に引け目を感じてしまうことはないでしょうか。著者は、自身の弱さや情けない部分を隠すことなく、ユーモアを交えて描き出します。
ゲームと現実が混同する夜
深夜、コンビニへ向かう途中で財布を忘れたことに気づいた著者。その時、ふとこう考えてしまいます。
まあ、途中でモンスターを倒して稼ぎながら行けば良いか…ん。
直前までロールプレイングゲームに没頭していたせいで、現実とゲームの世界が混同してしまったのです。この出来事に著者は「とうとう現実と虚構の区別が曖昧になってしまったのか。僕はもうダメかもしれないと思った」と恐怖を覚えますが、その情けない姿をありのままに綴ることで、読者の笑いを誘います。
遅すぎた父への尊敬
本書の白眉とも言えるのが「父のこと」というエッセイです。
幼少期は憧れの存在だった父。しかし、思春期になると疎遠になり、父の関心を引きたくて心ない言葉をぶつけてしまいます。
「うるせえ、何も知らないくせに父親面するんじゃねーよ」
大人になり、自分が社会に出て働くことの厳しさを知って初めて、父の偉大さに気づきます。男兄弟三人を養い、会社の愚痴一つ言わず、黙々と働き続けた父。浪人や突然ピアノを始めるといった自分のわがままを、いつも黙って応援してくれた父。
僕は、大人になってみて、ようやく父の偉大さに気付いたのである。それと同時に、僕にはそれはできない、という申し訳ない気持ちにもなった。
後悔と申し訳なさを抱えながらも、著者は「遅すぎるということはない」と、これから自分なりの形で親孝行をしていきたいという決意を語ります。そして、最後にこう締めくくります。
今は自信を持って答えることができる。
僕は心から父を尊敬している。
完璧な人間などいません。誰にでも弱さがあり、過去の過ちがあります。大切なのは、 その弱さや失敗から目をそらさず、きちんと向き合うこと 。そして、それを乗り越えようとすること。著者の誠実な姿勢は、不器用ながらも前を向いて生きる勇気を与えてくれます。
まとめ:あなたの「凡庸な日常」を「愛すべき日常」に変えるために
守田樹氏の『愛すべき凡庸な日常』は、私たちに特別な成功法則を教えてくれる本ではありません。しかし、本書には、日々の生活を豊かにし、困難な時代を生き抜くための、ささやかで、しかし確かなヒントが散りばめられています。
- 視点を変えれば、退屈な日常はユーモアと発見に満ちた冒険になる。
- ストレスに押しつぶされそうな時は、「好き」という純粋な気持ちを道しるべにする。
- 今の働き方に疑問を感じたら、大胆な「妄想」で心を解放してあげる。
- 自分の弱さや失敗も、笑い飛ばし、愛すべき個性として受け入れる。
本書を読み終えた時、あなたはきっと、自分の「凡庸な日常」が、少しだけ愛おしく感じられるはずです。
もしあなたが、日々の仕事や生活に疲れを感じているのなら、ぜひこの本を手に取ってみてください。きっと、著者の守田樹という、どこか憎めない「隣人」が、あなたの心にそっと寄り添い、「まあ、ぼちぼち行こうや」と肩を叩いてくれることでしょう。