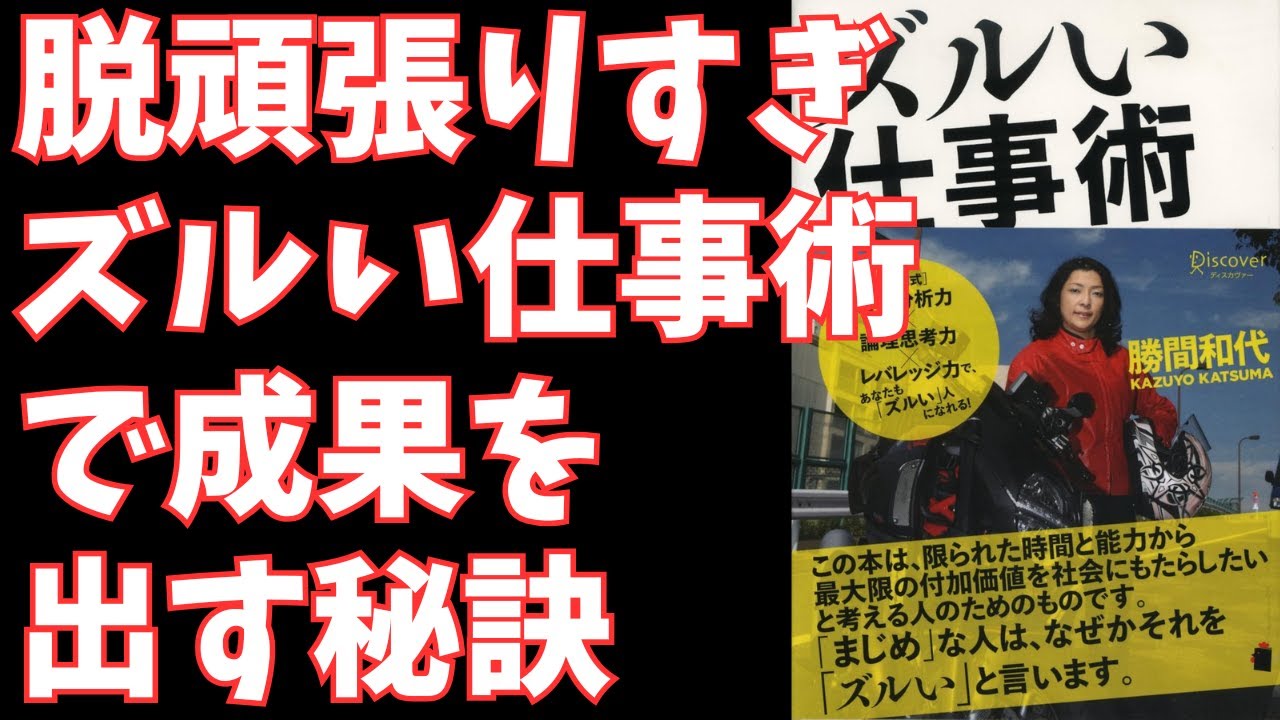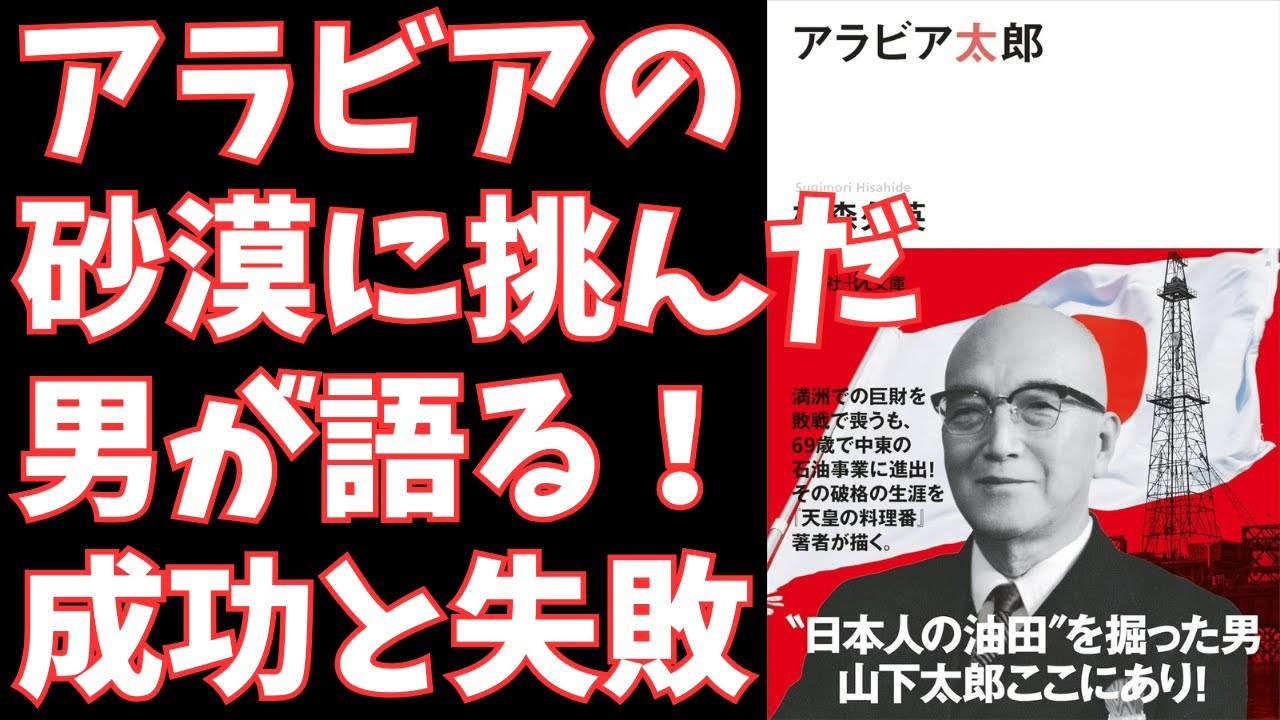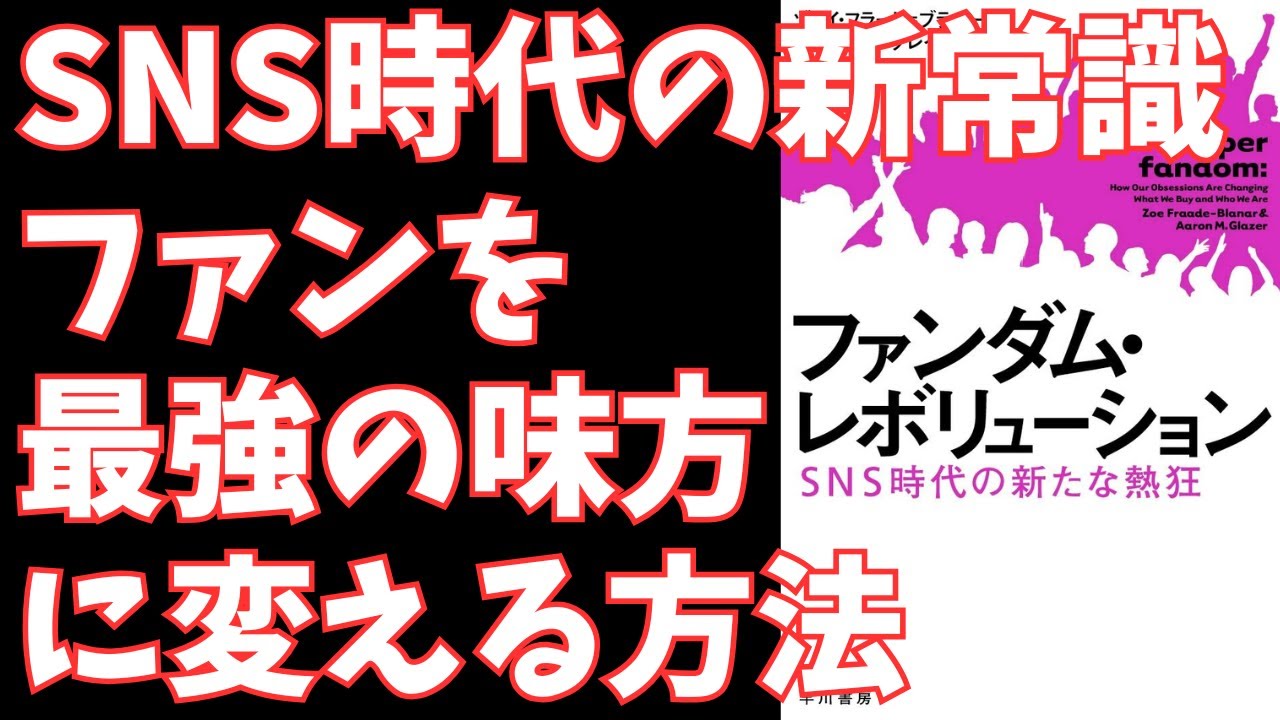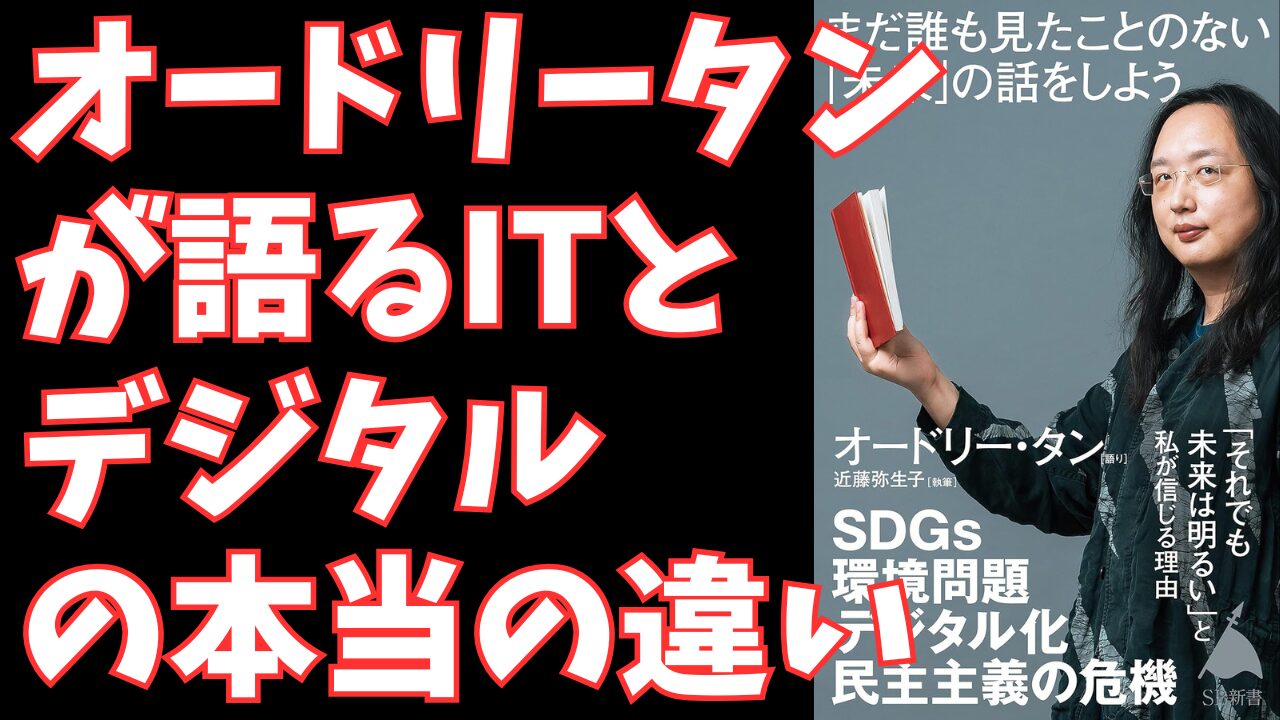パン屋『365日』に学ぶ常識を覆す思考法|ビジネスのヒント満載の『考えるパン』
本書は、人気ベーカリー「365日」のオーナーシェフである杉窪章匡氏が、自身のパン作りにおける哲学と具体的な製法を語った一冊です。しかし、これは単なるパンの専門書ではありません。そこには、業界の常識を疑い、物事の本質を徹底的に思考し、独自の理論を再構築(リノベーション)していくプロセス が詳細に描かれており、あらゆるビジネスパーソンにとって学びの多い「思考法の教科書」とも言える内容になっています。
この記事では、本書で語られる「365日」のパン作りの裏側にある哲学を、忙しいビジネスパーソンの視点から読み解き、日々の仕事に活かせるヒントとしてお伝えします。
本書の要点
- 常識のリノベーション: 伝統的な製パン法を鵜呑みにせず、メリットとデメリットを天秤にかけ、自らが求める「おいしさ」のために理論を再構築する。
- 素材こそが主役: 国産小麦粉の味と香りを最大限に活かすため、発酵やグルテン形成を最小限に抑えるという、素材から逆算した製法を貫く。
- デザインによる問題解決: パンの形やサイズは単なる見た目ではなく、食べ手の体験をコントロールし、作り手の意図を伝えるための「問題解決の手段」と捉える。
- 「思い」から始まる思考: すべてのパン作りは「この素材をどう活かすか」「どんな風に食べてもらいたいか」という作り手の強い「思い」から出発し、それを実現するための理論と技術を構築する。
- パン屋の枠を超える経営: 職人としてのこだわりと、スタッフが幸せに働ける「健全経営」を両立させ、パン屋を「総合食料品店」として再定義することで、顧客のライフスタイルに深く関わっていく。
はじめに:なぜ、私たちは「365日」のパンに心を奪われるのか?
東京・代々木公園に本店を構えるベーカリー「365日」。その小さな店には、ひっきりなしにお客さんが訪れます。手のひらサイズの可愛らしいパン、独創的なフォルムのクロワッサン、そして何より、一口食べれば小麦の豊かな香りと味わいが口いっぱいに広がる、唯一無二のおいしさ。多くの人々が、その魅力の虜になっています。
しかし、その圧倒的なおいしさの裏側には、著者である杉窪章匡氏の、常識を徹底的に疑い、自分の頭で考え抜くという、凄まじいまでの探求心と哲学 が隠されています。
本書『「365日」の考えるパン』は、その思考の軌跡を解き明かす一冊です。杉窪氏は語ります。「僕のパンのつくり方は、形も大きさも食感とかも全部、わかりやすくいうとリノベーション(新しく構築する)です」と。
この記事では、杉窪氏の「リノベーション思考」を軸に、彼のパン作りがいかにしてビジネスの世界で戦う私たちに多くの示唆を与えてくれるのかを、本書の具体的なエピソードを交えながら探っていきます。
当たり前を疑う力。「リノベーション思考」の原点
ビジネスの世界では、既存のやり方や業界の慣習を「そういうものだから」と受け入れてしまいがちです。しかし、杉窪氏のパン作りは、その「当たり前」に疑問符を突きつけることから始まります。
彼がパン作りを学んでいた当時、日本のバゲットの多くが、本場フランスのものと比べてクラム(内側の白い部分)がボロボロと崩れることに気づきます。フランスのバゲットは指で丸めるとゴムのようになるのに、なぜ日本のものは違うのか? この素朴な疑問が、彼の理論構築のスタート地点でした。
物ごとにはすべてメリットと、デメリットが両方あります。
僕が思うに、本に書かれているような、昔から教えられてきた日本のパンづくりは、しっかりこねて、発酵をしっかりとって、グルテンをとにかく強くして、大きく膨らませることが一番、という視点。
…でも、これらをすることによって、デメリットも少なからずあると思いました。
杉窪氏は、従来の日本の製パン法が「見た目の失敗がなく、大きく膨らむ」ことを優先してきた結果、パンのヒキ(噛んだときの歯ごたえ)が強くなりすぎたり、発酵によって小麦粉本来の味が薄まったりするという デメリット に着目します。
例えば、発酵途中で行う「パンチ」という工程。これはガスを抜いて酵母の活動を活性化させ、グルテンを強化することでパンが大きく膨らむ(窯のびする)というメリットがあります。しかし、その一方で 発酵が進むことで小麦粉の糖分が消費され、甘みが減り、味が薄まる というデメリットも生じます。
杉窪氏の目指すパンは「小麦粉の味を大切にする」こと。だから彼は、メリットとデメリットを天秤にかけ、「365日」では パンチをしない という選択をします。
これは、私たちの仕事にも通じる重要な視点です。これまで当たり前とされてきた会議、毎日作成している報告書、長年続いている業務フロー。それらは本当に「目的」に対して最適な手段なのでしょうか? 「ボリューム(成果物の見た目や量)」を出すために、「味(本質的な価値)」を犠牲にしていないでしょうか?
杉窪氏の姿勢は、 目的を明確にし、その目的達成のために既存の手段がもたらすメリットとデメリットを冷静に分析し、時には大胆に「やめる」決断をすることの重要性 を教えてくれます。
すべては「素材」のために。本質から逆算する思考法
「365日」のパン作りのコンセプト、その根幹にあるのは「国産小麦粉のおいしさを伝えたい」という強い思いです。そのために、製法のすべてが「素材の味をいかに減らさずに、焼きあがりまでもっていくか」という一点から逆算して組み立てられています。
発酵は「火通りをよくするため」の手段
多くのパン職人が「発酵によってパンはおいしくなる」と考える中、杉窪氏はその常識すら疑います。
パン生地が発酵によっておいしくなるという発想は、僕にはないのです。
ではなぜパンは発酵をとるのかといえば、火通りをよくするためです。
彼は、パスタや餃子の皮など世界の小麦粉料理が薄いか細い形状であることに着目し、パンだけがなぜ「かたまり」で火が通るのかを考察します。その答えが、発酵によって生まれる「ガスの気泡」でした。気泡が火の通り道を作ることで、分厚い生地でも中まで火が通る。つまり、 発酵の主目的は「味の熟成」ではなく、「火通りを良くする」という物理的な現象 だと再定義したのです。
この考えに基づけば、素材の味を最大限に残すためには、目的(火が通ること)を達成できる 最小限の発酵 に留めるのが最も合理的、という結論に至ります。パン生地の味のピークはこね終えた直後であり、発酵が進むほど糖が消費され味が薄くなっていくからです。
自分の五感を信じる。数値データより「味見」
杉窪氏の素材へのこだわりは、小麦粉の選び方にも表れています。通常、パン職人は小麦粉の特性を「たんぱく値」や「灰分値」といった数値データで判断します。しかし、彼はその数値を一切見ません。彼が頼りにするのは、自らの「味見」です。
だから、僕はたんぱく値も灰分値もまったく見ません。味見をして、僕なりの判断基準を決めたんです。
食べ物って口の中に入れるのが、だれにでも一番わかりやすい。数値よりも何よりも正確です。
彼は小麦粉を「白・黄・グレー・茶」の4色に分類し、実際に粉のまま口に入れて味や香り、口溶けを確認します。口の中で唾液と混ざり合うことで、グルテンの強さ(なかなか消えないか、サッと溶けるか)まで判断するのです。
この姿勢は、ビジネスにおけるデータ分析の在り方を考えさせます。もちろんデータは重要ですが、それに依存しすぎるあまり、現場の感覚や顧客の生の声といった「生きた情報」を見失ってはいないでしょうか。最終的な価値を判断するのは、いつだって人間(顧客)の五感です。 データと向き合いつつも、最後は自分たちの感覚を信じて判断する。 そのバランス感覚が、真に価値のあるプロダクトやサービスを生み出すのではないでしょうか。
デザインとは「問題解決」である
「365日」のパンは、その独特で可愛らしい形も魅力の一つです。しかし、それらは単に見た目を面白くするためのものではありません。杉窪氏にとって、デザインとは 「どう食べさせて満足させるか」を設計し、「問題を解決するためのもの」 なのです。
食べ方を限定し、最高の体験を届ける「クロッカンショコラ」
例えば、細長い楕円形の「クロッカンショコラ」。なぜこの形なのか。
これなら食べるとき、99%の人が細長い先端からかじって食べるはずです(横から食べる人がいたら、ちょっと変わってますね)。みんなが同じ食べ方をするシェイプです。
ということは、パン生地、ガナッシュ、カリカリアクセントのパールクラッカンがどんな比率で口に入るのが一番おいしく感じてもらえるか、あらかじめ計算づくで構成することができるのです。
丸いパンであれば、どこから食べるか、一口の大きさはどれくらいか、それはすべて食べる人に委ねられます。しかし、この細長い形状は、食べる人の行動を自然に誘導します。これにより、作り手が「このバランスが最高においしい」と意図した通りの体験を、ほぼすべての人に届けることが可能になるのです。これは、 顧客体験(UX)を緻密に設計する アプローチそのものです。
ベンチタイムなし、型で焼く。弱点を補う合理的なデザイン
「365日」の製法は、グルテンを弱く作るため、生地が柔らかく、形が安定しにくいという難点があります。そのままでは綺麗に膨らみません。そこで、ブリオッシュやあんぱん、カレーぱんなどは 「型」に入れて焼きます。
これは、見た目を個性的にするためではなく、「型の力を借りないと綺麗に焼きあがらない」という 必然性から生まれた問題解決策 なのです。同時に、この方法は「上手に丸く成形する技術がなくても、新人スタッフが失敗なく綺麗に焼ける」というメリットも生み出しました。
さらに、生地のグルテンが元々弱いため、分割後に生地を休ませる「ベンチタイム」という工程も不要になります。これも工程を一つ省略できるという大きなメリットです。
このように、一つの課題(グルテンが弱い)を解決するためのデザイン(型を使う)が、別の問題(新人教育、作業効率)まで解決しています。自社の 「弱み」を正確に把握し、それを補うための工夫が、結果として新たな「強み」を生み出す。 この発想は、多くの企業にとって参考になるはずです。
パン屋は「総合食料品店」たれ。事業領域の再定義
杉窪氏の視線は、パン作りだけに留まりません。彼は「365日」を単なるパン屋ではなく、 「総合食料品店」 として位置づけています。
実は「365日」がめざしているのは、パン屋ではなく総合食料品店です。
多面的な使い勝手のいいお店。パンを買うついでに納豆を買ってもらってもいいし、それとは逆で醤油を買うついでにパンを買ってもらうこともできる。
店内にはパンだけでなく、契約農家から届く野菜、米、納豆、醤油や味噌といった調味料、さらには器やカトラリーまで並びます。これは、顧客の「パンを買う」という単一の行動だけでなく、 「毎日の食事」という、より大きなライフスタイル全体に寄り添おうとする意志の表れ です。
姉妹店のカフェ「15℃」では、モーニングでパンだけでなく、ごはんとお味噌汁の「さかな定食」まで提供しています。パン屋だからパンだけ、というのは作り手側の都合でしかない。顧客が朝食に求めるものは多様であり、その選択肢を広げることが顧客満足につながる、という考え方です。
私たちは自社のビジネスを「〇〇業」という既存の枠組みで捉えてはいないでしょうか。顧客が本当に求めている価値は何かを突き詰めれば、事業領域はもっと広がる可能性があります。 自社のコアコンピタンスを活かしながら、顧客のどのような「不」を解決できるのか。 「365日」の取り組みは、事業を再定義する重要性を示唆しています。
人を育てる哲学。「タイマーなしのミキシング」が教えること
本書の後半では、杉窪氏の経営者として、また教育者としての一面も語られます。彼の哲学は、人材育成においても一貫しています。
彼はスタッフを育てる上で、仕事の3ステップである 「状況把握」「判断」「実行」 を徹底させます。その象徴的な取り組みが、「タイマーを使わないミキシング」です。
多くのパン屋では「1速で〇分、2速で〇分」というマニュアルに沿ってミキサーを動かします。しかし、「365日」ではタイマーを使いません。スタッフは自分の目、耳、触感で生地の状態を「状況把握」し、次にどうすべきかを「判断」し、「実行」することが求められます。
朝から晩まで働いても、目的意識を持っていなかったら、10年やっても20年やっても、人は成長しないです。
例えば、ミキシングの後半に行う「足し水」。ここでは固形の「氷」を使います。氷であれば一度に入れることができ、溶けるまでの時間を他の作業に充てられます。そして、ミキサーが回るボウルから聞こえる「カラカラ」という音がしなくなったら、氷が溶けた合図。最後に目で見て、触って最終確認をする。これは、 五感を使って状況を判断する訓練 であると同時に、 作業を効率化するための仕組み でもあります。
「見て盗め」という古い慣習についても、杉窪氏は「手取り足取り教えるよりも、見て盗んだ人の方が、上の立場になった時に周囲を見る力が養われている」と、その本質的な価値を再評価します。
これは、部下や後輩の育成に悩む多くのビジネスパーソンにとって、耳の痛い話かもしれません。しかし、短期的な効率を求めて答えだけを与えるのではなく、 いかにして相手に「考えさせ」、主体的な成長を促すか。 その仕組みをどうデザインするか。杉窪氏の哲学は、真のリーダーシップとは何かを問いかけてきます。
まとめ:あなたの仕事の「当たり前」は、本当に正しいか?
『「365日」の考えるパン』は、一人の職人がいかにして常識と向き合い、自らの「思い」を形にしてきたかの記録です。その根底に流れるのは、常に「なぜ?」と問い続け、物事の本質を探求する真摯な姿勢です。
・そのプロセスは、本当に目的にかなっているか?
・数値やデータだけでなく、自分の五感で本質を捉えているか?
・顧客の体験を向上させるための「デザイン」ができているか?
・自社の事業領域を、自ら狭めていないか?
・仕組みによって、人の成長を促せているか?
本書を読み終えたとき、あなたはきっと、自分の仕事における様々な「当たり前」を、もう一度見つめ直したくなるはずです。パンという身近な食べ物を通して、これほどまでに深く普遍的な「思考法」を学べる本は、そう多くはありません。
日々の業務に追われ、思考が停止しそうになっているビジネスパーソンにこそ、手に取っていただきたい一冊です。