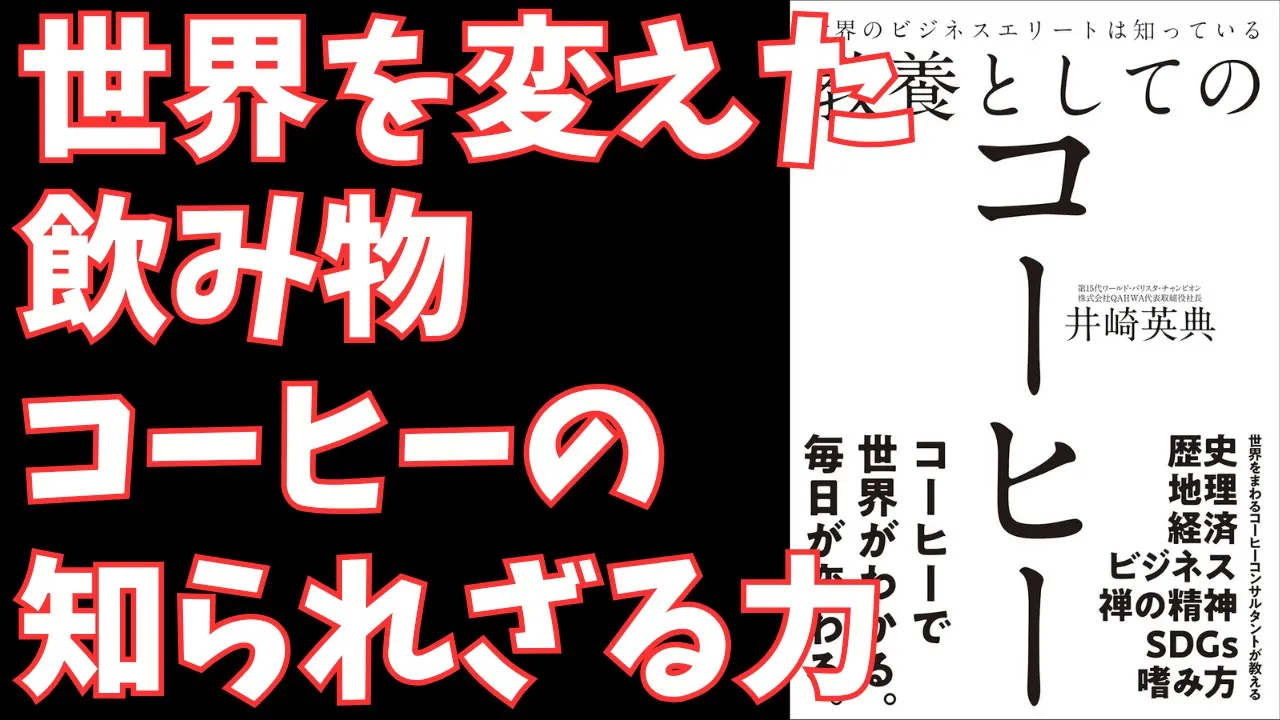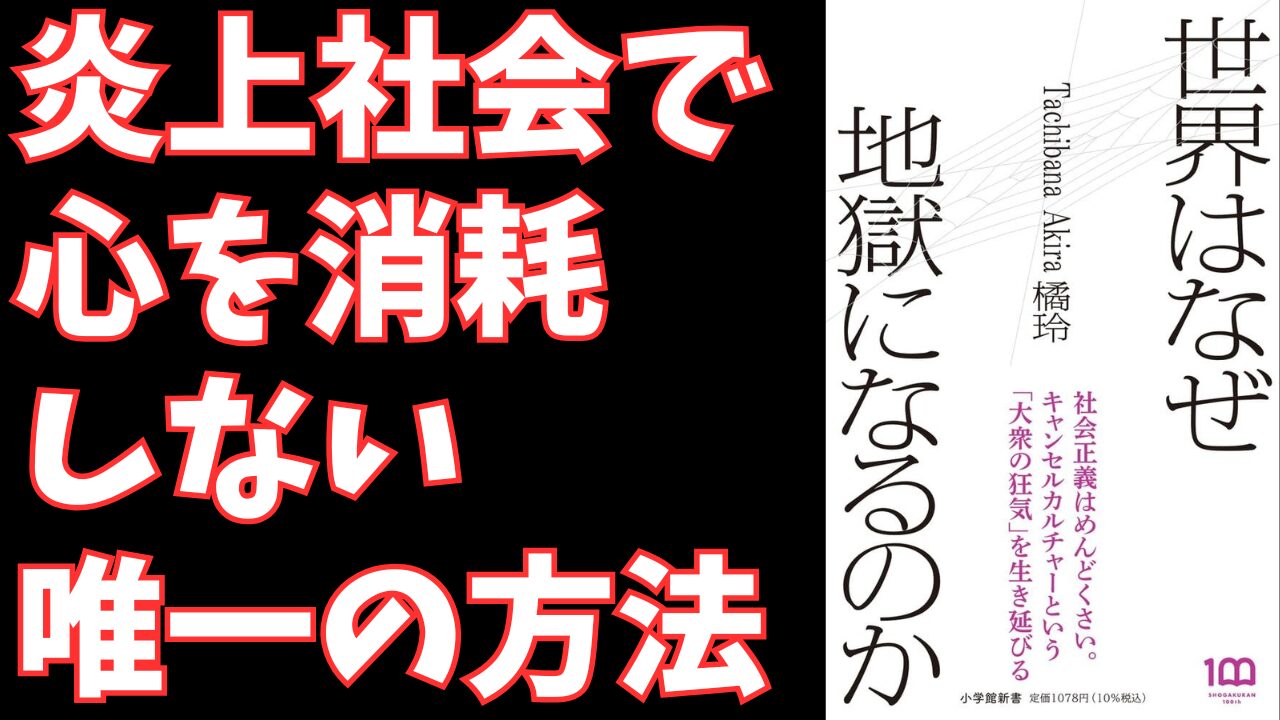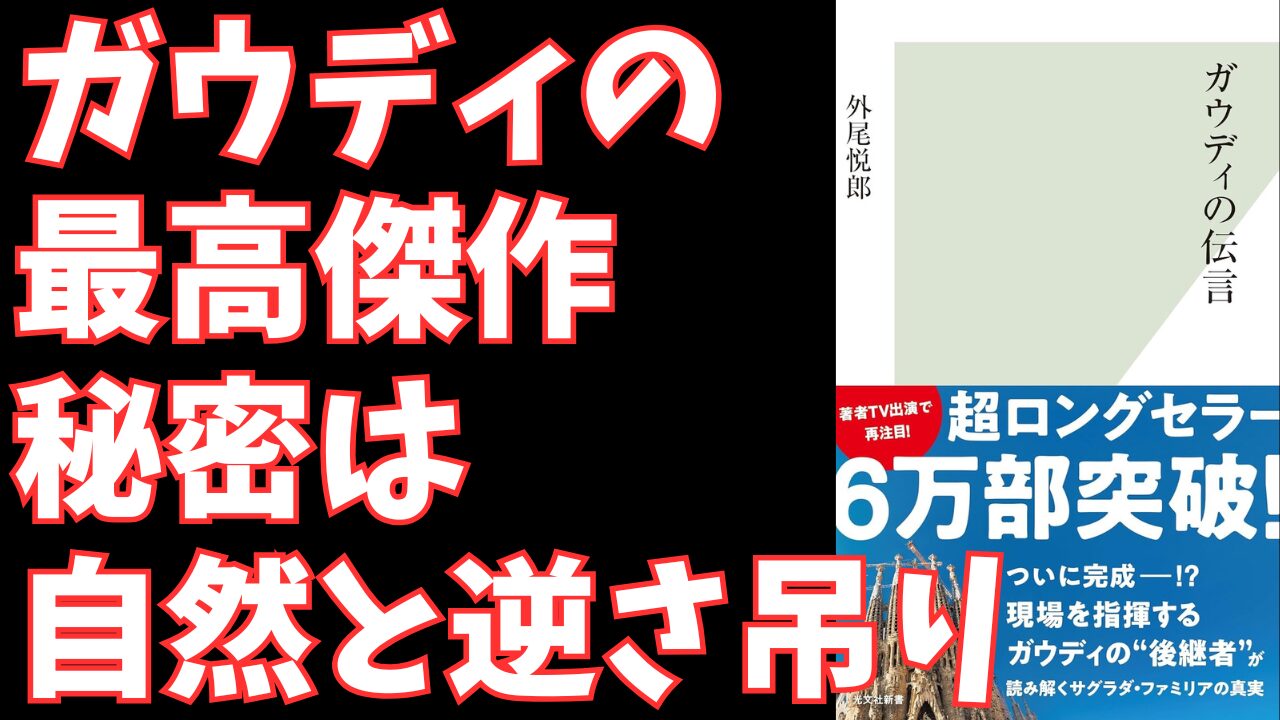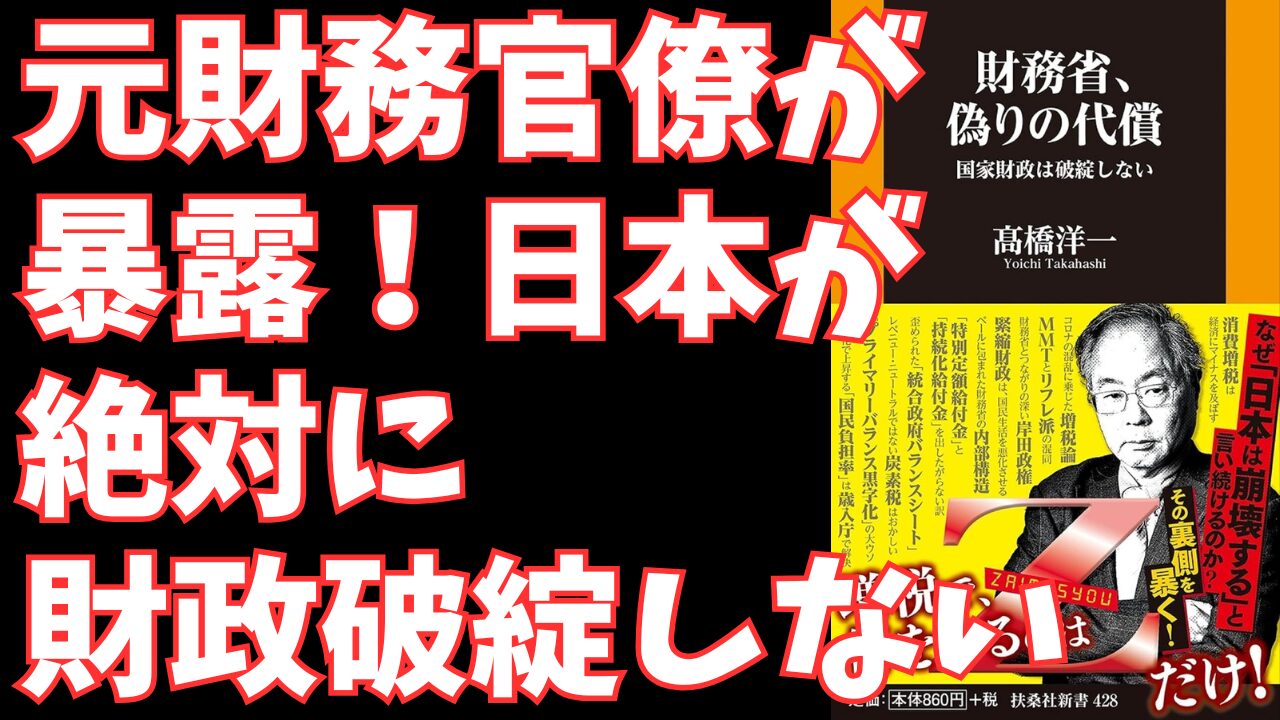髙橋洋一『外交戦』|地政学と貿易で読み解く国際ニュースの本質
本書『外交戦 ~日本を取り巻く「地理」と「貿易」と「安全保障」の真実~』は、元大蔵官僚で経済学者の髙橋洋一氏が、複雑に見える国際関係を 「貿易」と「安全保障」という2つの原理原則 に基づいて、きわめてシンプルに解き明かす一冊です。
感情論や先入観を排し、地政学や経済学の理論といった「確かなもの」だけで事実を見つめれば、日韓関係の悪化や米中貿易戦争といった最新ニュースの本質が驚くほどクリアに理解できます。本書は、多忙なビジネスパーソンが世界情勢の「本当のところ」を見抜き、自分の頭で考えるための思考法を身につけるための、最適なガイドブックと言えるでしょう。
本書の要点
- 外交の基本は「貿易」と「安全保障」 であり、この2つは密接に結びついた表裏一体の関係にある。
- 国際関係を読み解くには、国家の地理的条件が行動を左右する 「地政学」 と、民主主義国同士は戦争をしないという 「民主的平和論」 が極めて重要な視点となる。
- 貿易においては、一部に打撃を受ける産業が出ても国全体では利益が最大化するため、 「自由貿易」が最適解 である。貿易赤字は国の損得とは無関係であり、問題視する必要はない。
- 安全保障は国家の自己責任であり、国連はアテにならない。価値観を共有する国々と同盟を結び、 集団的自衛権によって脅威を牽制する ことが、戦争を回避する最も有効な手段である。
- 日韓の輸出規制問題は安全保障上の措置であり、米中対立は単なる貿易摩擦ではなく覇権争いである。これらの問題も 原理原則に立ち返れば、その本質を冷静に分析できる。
なぜ、国際ニュースは複雑に見えるのか?
「アメリカと中国の貿易戦争は、結局どちらが勝つのか?」
「なぜ、日韓関係はここまでこじれてしまったのか?」
「トランプ大統領の行動は、日本にとってプラスなのか、マイナスなのか?」
日々、ニュースで報じられる国際情勢。なんとなく追いかけてはいるものの、背景が複雑で、誰が何を目的として動いているのか、本質を理解するのは難しいと感じているビジネスパーソンは多いのではないでしょうか。
巷の解説に耳を傾けても、個人的な感情論や「〇〇はけしからん」といった精神論に終始し、かえって混乱してしまうことも少なくありません。
著者の髙橋洋一氏は、こうした状況を「原理原則を理解していないうえに、個人的な感情や先入観によって、事実を見つめる目が曇っているからだ」と指摘します。
物事には、時代や場所が変わっても揺らぐことのない「原理原則」が存在します。国際関係も例外ではありません。その原理原則さえ押さえれば、一見複雑に見えるニュースも、驚くほどシンプルにその構造を理解できるようになるのです。
この記事では、髙橋洋一氏の著書『外交戦』の内容を基に、忙しいビジネスパーソンが国際情勢の本質を見抜くための思考のフレームワークを解説していきます。
外交をシンプルに捉える「たった2つ」の基本要素
髙橋氏は、国際関係を考える上での大原則として、まず 「外交とは、国家間の『貿易』と『安全保障』について話し合うことである」 と定義します。この2つは、外交における車の両輪であり、切り離して考えることはできません。
経済的な結びつきが強い国とは軍事的な結びつきも強くなり、逆に対立していつ戦争になるかわからない相手とは誰も貿易をしたがらない。これは自明の理です。
その最も顕著な例が EU(欧州連合) と NATO(北大西洋条約機構) です。
EUは強力な「経済同盟」であり、加盟国間の貿易は原則として無関税です。一方、NATOはアメリカとヨーロッパ諸国による「軍事同盟」であり、その加盟国はEU加盟国とほぼ一致します。
歴史的には、まずNATOという軍事同盟が作られ、その上でEUという経済的な結びつきが築かれました。これは、強固な安全保障の土台があってこそ、活発な貿易が可能になる ことを象徴しています。貿易で結ばれた国は「一蓮托生」の関係。だからこそ、経済同盟と軍事同盟は一体になるのが当然なのです。
外交交渉は「合コン」と同じ
では、各国の政府はどのように貿易や安全保障のルール作りを行っているのでしょうか。
髙橋氏は、これを「合コン」にたとえて分かりやすく説明します。
交渉とは、内容が国益にかなうかを見きわめるために参加するものだ。
「いい人、いるかな」と思って参加するのが合コンなら、さしずめ「いい条件、引き出せるかな」と思って参加するのが外交交渉の席、ということになるだろう。
[cite_start]仮にいい条件が引き出せなかったら、「ご縁がなかったということで」と後腐れなく退席すればいい。 [cite: 1]
TPP(環太平洋パートナーシップ)協定の交渉に一度参加したら抜けられない、といった議論がかつてありましたが、これは国際常識ではあり得ません。自国に不利だと判断すれば、どの国でも席を立つ権利があります。
まずは参加してみて、メリットとデメリットを吟味する。この ドライで合理的な視点 が、外交の基本なのです。
【貿易編】経済学が示す「自由貿易が最強」である理由
外交の片方の車輪である「貿易」。これについては、経済学の長い歴史の中で「自由貿易が最適解である」という結論が実証されています。
自由貿易協定に対しては、「海外から安い製品が流入し、国内の農家などが打撃を受ける」といった批判がつきものです。しかし、髙橋氏は「こうしたいい分は、海外から安い製品が入ってくることで消費者が得る利益を丸々見過ごしている」と一蹴します。
経済学の「消費者余剰」と「生産者余剰」という考え方を使えば、このロジックは明快に説明できます。
- 消費者余剰: 消費者が「この値段までなら払ってもいい」と思う価格と、実際の価格との差額。つまり「お得感」の総量。
- 生産者余剰: 生産者が「この値段より安くても売りたい」と思う価格と、実際の価格との差額。つまり「利益」の総量。
貿易が自由化され、海外から安い製品が入ってくると、国内の販売価格は下がります。
これにより、たしかに国内生産者の利益(生産者余剰)は減少します。しかし、それ以上に 消費者が得する分(消費者余剰)が大幅に増加する のです。
重要なのは、国内生産者が被る損失分は、国内消費者が得る利益で十分に穴埋めできる という点です。政府は、自由貿易で得た国全体の富を、打撃を受けた産業に再分配する政策(職業訓練の支援など)を行えば、文字通り「誰も損をしない状況」を作り出すことが可能なのです。
損をする一面だけを切り取って悲観するのは、経済をマクロな視点で見れていない証拠。髙橋氏は、この世界で起こっていることは「自分の身のまわりの『半径1メートル』の視野では見きわめられない」と強調します。
「貿易赤字」を問題視するのはバカバカしい
「日本の貿易収支が赤字に転落!」といったニュースを見聞きすると、国の財政が危ういかのような印象を受けませんか?
しかし、これも全くの誤解です。髙橋氏は、この誤解を解くために、こんな問いを投げかけます。
[cite_start]「あなたがよく行くデパートに対する、あなたの〝貿易収支〟はどれくらいですか?デパートでは買うばかりなのだから、もちろん大赤字でしょう。でもあなたは破産していませんね。国の貿易赤字もこれと同じことですよ」 [cite: 1]
国の貿易収支とは、単に「モノの輸出総額」と「モノの輸入総額」を比べたものに過ぎません。輸入企業が海外から100万ドルの商品を仕入れ、国内で大ヒットさせて大儲けしたとしても、国の貿易収支上は100万ドルの「輸入」として記録されます。
つまり、貿易赤字は国の損得や経済成長とは全く関係ありません。
本当に国家の経済の健全性を測りたいのであれば、見るべきは「貿易収支」ではなく 「経常収支」 です。経常収支は、貿易収支に加え、海外への投資から得られる利益(第一次所得収支)などを含んだ、国の総合的な収支です。
日本は貿易収支が赤字でも、経常収支は長年黒字を続けており、海外に持つ資産(対外純資産)は世界一です。物事の一面だけを見て、心配しても意味のないことを心配するのはやめるべきなのです。
【安全保障編】地政学と民主的平和論で世界のリアルを読む
外交のもう一方の車輪、「安全保障」。これを考える上で欠かせない視点が2つあります。「地政学」と「民主的平和論」です。
① 地政学:地理的な条件が国家の運命を決める
「地政学」とは、地理的な条件がその国の政治や軍事、経済にどのような影響を与えるかを考える学問です。
国家の歴史とは、「より広い、よりよい土地」をめぐる領土の奪い合いの歴史 でした。特に近代以降は、航海技術の発達により 「海を制する国」が覇権を握ってきました。
19世紀のイギリス(パクス・ブリタニカ)が、圧倒的な海軍力で世界中に植民地を広げたこと。そして現代のアメリカが、太平洋と大西洋という2つの大海を制し、世界中の国々と同盟を結ぶことで覇権国家となったこと。これらは全て地政学で説明できます。
今も、国同士は土地をめぐって腹の探り合いを続け、「相手が引いたら自分が押す」という駆け引きが絶えず繰り広げられています。この地政学的な視点を持つことで、なぜ中国が南シナ海にあれほど執着するのか、その意図が明確に見えてきます。
② 民主的平和論:民主主義国同士は戦争をしない
もう一つの重要な理論が 「民主的平和論」 です。これは、「民主主義という政治システムを持つ国同士は、戦争をしない」という国際政治学の理論で、今や「もっとも法則らしい法則」とされています。
なぜなら、民主主義国家には、戦争を抑制する仕組みが幾重にも組み込まれているからです。
- 価値観の共有: 同じ価値観を持つため、体制転覆をかけた戦いをする必要がない。
- 国内のブレーキ: 複数政党制や議会、言論の自由が、一人のリーダーの暴走に歯止めをかける。
- 国民の意思: 戦争で危険にさらされるのは国民自身。選挙などを通じて、国民が好戦的な政府を支持しない。
つまり、民主主義国同士は基本的に「話せばわかる」間柄なのです。
この理論から導き出される結論はシンプルです。自国の安全を確保するためには、価値観を同じくする民主主義国家と集団でまとまり(集団的自衛権)、そうでない国々からの脅威に備えることが最も有効 だということです。
最新の国際情勢を「原理原則」で斬る!
ここまで見てきた「貿易」と「安全保障」の原理原則を当てはめれば、最新の国際ニュースもその本質が見えてきます。
ケース1:日韓関係の真相
2019年、日本が韓国を「ホワイト国」から除外したことをきっかけに、日韓関係は戦後最悪と言われるほどに悪化しました。
韓国側はこれを「徴用工問題への報復だ」と主張し、日本国内でも同様の見方が広がりました。
しかし、髙橋氏はこれを 「安全保障」の問題 だと断言します。
ホワイト国とは、兵器転用可能な物資の輸出管理が厳格な国を指す「優遇対象国」です。日本から韓国へ輸出されたフッ化水素(サリンの原料にもなる)が、韓国を経由してイランや北朝鮮といった国に不正に流れているのではないか、という疑惑が浮上しました。
この疑惑が事実であれば、日本の安全保障だけでなく、世界の安全保障を脅かす重大な事態です。だからこそ日本は、韓国を優遇対象から外し、輸出管理を厳格化したのです。これは報復やヘイトといった感情的なものではなく、世界の安全保障に対する日本の責任を果たすための、極めて合理的な措置 なのです。
韓国が本来すべきだったのは、疑惑を晴らすデータを示すか、事実であれば再発防止策を講じることでした。しかし、韓国政府が問題のすり替えやGSOMIA(軍事情報包括保護協定)破棄といったカードを切ったことで、事態はさらにこじれてしまいました。髙橋氏は、こうした韓国の行動の背景には、大国の顔色をうかがう「事大主義」という地政学的な宿命や、「自力で独立を勝ち取った経験がない」という歴史的なアイデンティティの危うさがあると分析しています。
ケース2:米中対立の本質
激化する米中貿易戦争。これも単なる二国間の貿易摩擦と捉えてはいけません。髙橋氏は、現代をアメリカ・中国・ロシアによる 「三つ巴の冷戦」 の時代だと位置づけます。
アメリカが中国に仕掛けている貿易戦争は、その覇権争いの一環です。表向きは関税の応酬ですが、その裏には ファーウェイ問題に代表される「サイバー覇権」や、軍事的な覇権をめぐる熾烈な争い があります。
では、この戦い、どちらに軍配が上がるのか。髙橋氏は、圧倒的にアメリカが有利 だと見ています。その最大の理由は、中国経済が抱える構造的な弱点、すなわち 「国際金融のトリレンマ」 です。
詳細は本書に譲りますが、ごく簡単に言うと、国家は
- 為替レートの安定(固定相場制)
- 独立した金融政策
- 自由な資本の移動
この3つを同時に実現することはできません。
多くの先進国は「1. 為替レートの安定」を諦めて変動相場制をとり、「2」と「3」を実現することで自由貿易を推進しています。
しかし、一党独裁体制の中国は、体制を維持するために自国に有利な為替レート(元安)を維持する必要があり、「1. 固定相場制」を手放せません。 その結果、「3. 自由な資本の移動」を制限せざるを得ず、これが自由貿易を進める上での大きな足かせとなっているのです。
アメリカはこの弱点を巧みに突き、中国をじわじわと追い詰めています。中国は、この構造的な問題を解決しない限り、国際社会で孤立を深めていく可能性が高いのです。
まとめ:「自分の頭で考える」ための思考のヒント
本書を通じて髙橋氏が一貫して伝えたいメッセージは、「自分の頭で考える習慣を持つ」 ことの重要性です。感情や思い込みに流されず、原理原則に立ち返って物事の本質を見抜く。そのための思考法のヒントを最後にいくつかご紹介します。
- 一方通行の思考から脱却する
ある政策について考えるとき、「やった場合」のデメリットばかりに目を向けるのではなく、「では、やらなかった場合はどうなるか」 を比較検討することが重要です。双方向からシミュレーションすることで、より深く、筋の通った結論を導き出せます。 - 「英語で説明できるか?」と自問する
国際常識は、世界共通言語である英語で説明できるものです。「個別的自衛権」のように、日本国内でしか通用しない概念は、国際社会の交渉のテーブルには乗りません。自分の考えが、世界の人を納得させられるロジックか を常に意識することが、偏った思考から抜け出すための有効なフィルターになります。
複雑な現代社会を生き抜くビジネスパーソンにとって、世界情勢を正しく理解し、未来を予測する力は不可欠なスキルです。本書『外交戦』は、そのための強力な武器となる「思考のOS」をインストールしてくれる一冊と言えるでしょう。