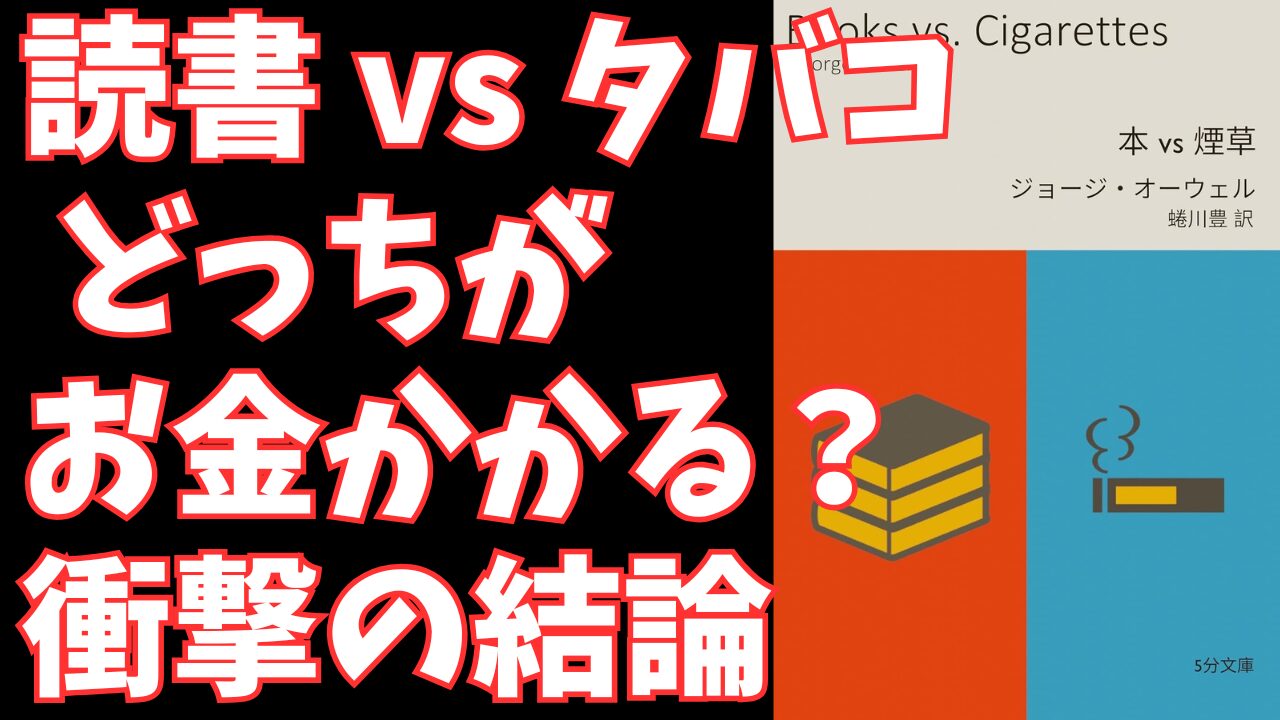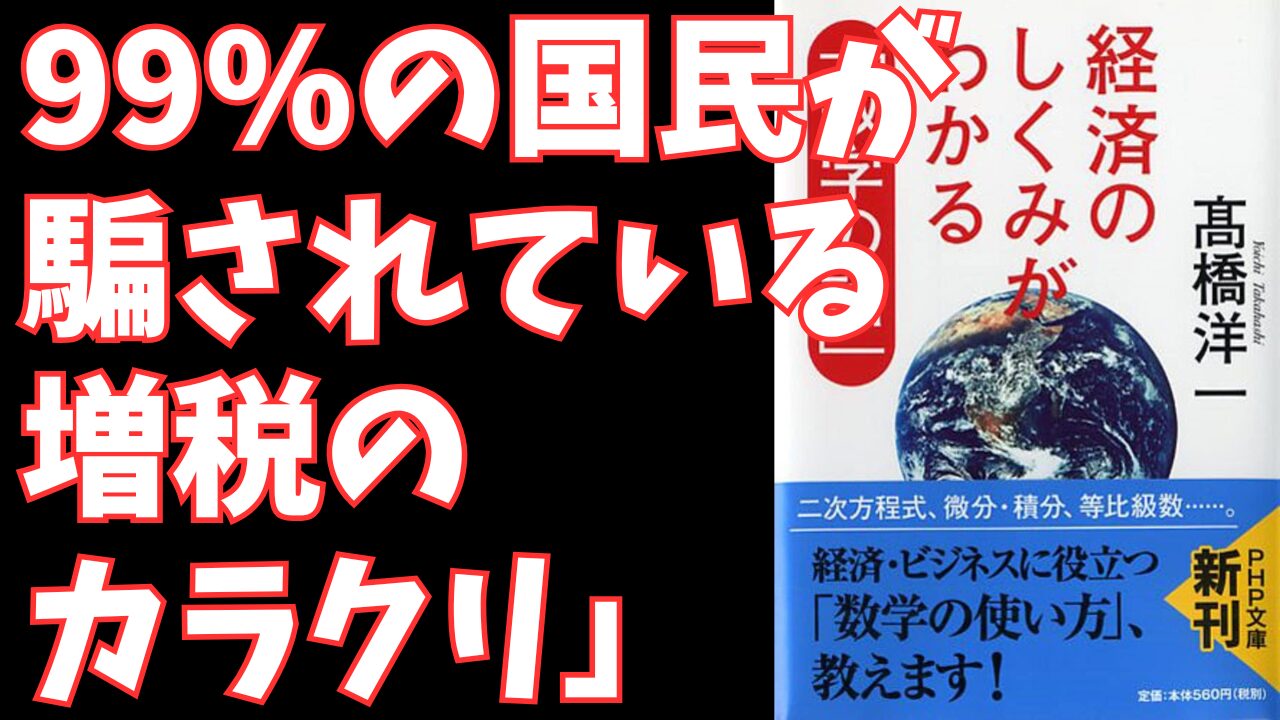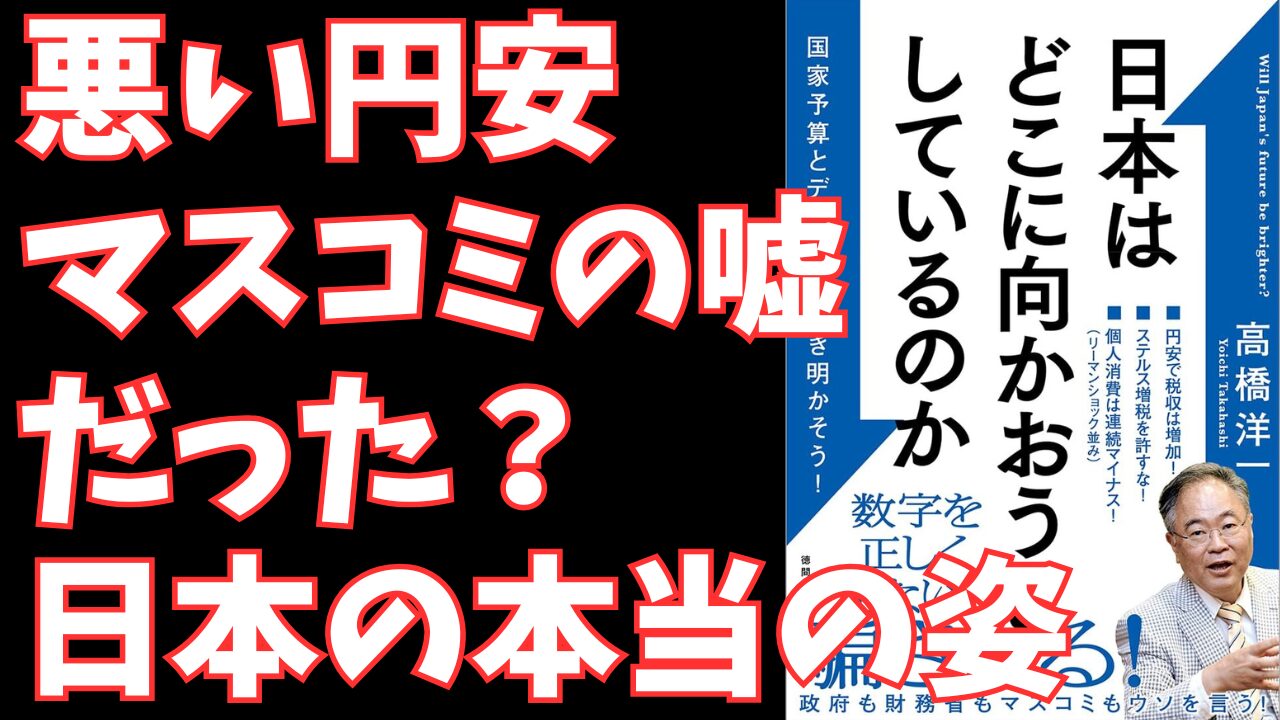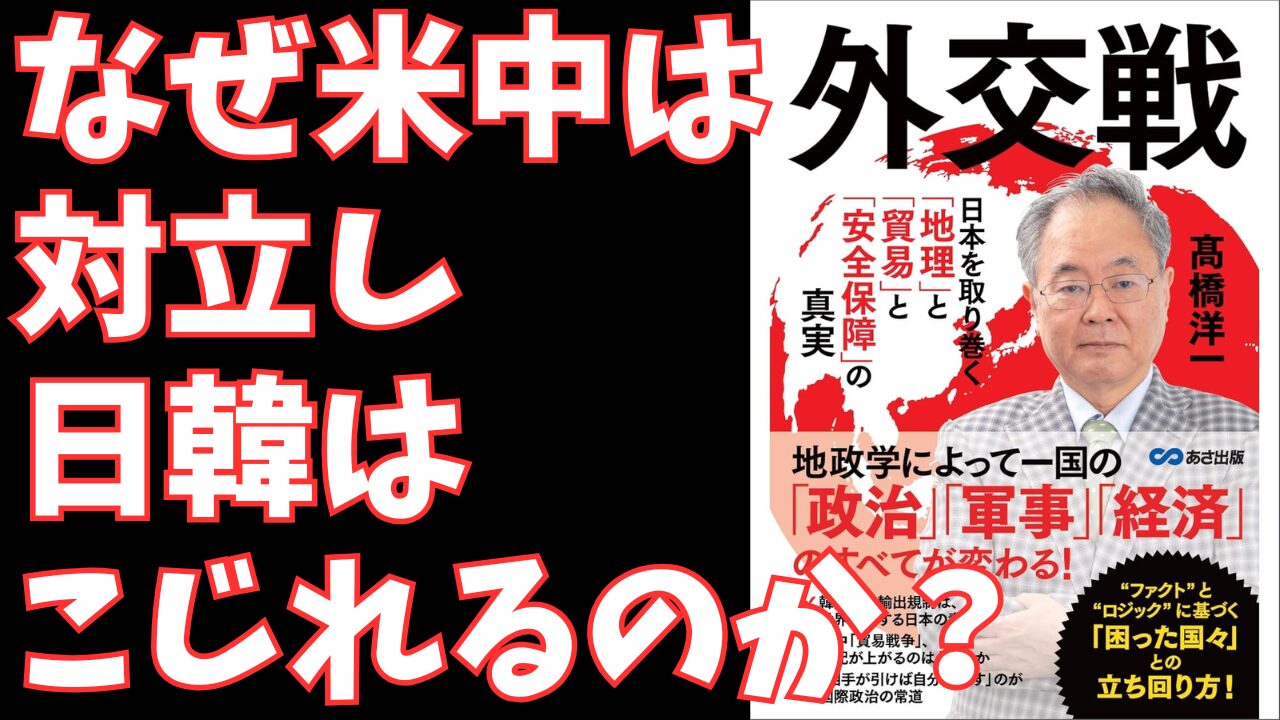J.K.ローリングはなぜ炎上した?橘玲『世界はなぜ地獄になるのか』が解き明かすキャンセルカルチャーの深層
本書『世界はなぜ地獄になるのか』は、現代社会が直面する「生きづらさ」の根源を、「リベラル化」という不可逆的な変化から解き明かす一冊です。著者の橘玲氏は、「誰もが自分らしく生きられる社会」を目指すリベラルな価値観が、皮肉にも格差の拡大、社会の複雑化、そして「キャンセルカルチャー」のような新たな対立を生み出していると指摘します。本書では、小山田圭吾氏の炎上事件やJ.K.ローリング氏をめぐる論争など、具体的な事例を詳細に分析しながら、ポリティカル・コレクトネス(ポリコレ)や社会正義をめぐる対立が、実は人間の本性に根差した「ステータスゲーム」の一環であることを明らかにします。この記事では、本書のエッセンスを抽出し、なぜ善意のはずの「正義」が暴走し、世界が「地獄」の様相を呈するのか、そして私たちがこの時代をどう生き抜くべきかのヒントを探ります。
本書の要点
- リベラル化のパラドックス: 「誰もが自分らしく生きられる社会」を目指すリベラル化は、遺伝の影響を増幅させ、結果的に経済格差や男女の性差を拡大させるという逆説的な事態を引き起こしている。
- キャンセルカルチャーの本質: 社会正義を求める運動は、ときに他者の過去の発言や行動を掘り起こし、社会的に抹殺しようとする「キャンセルカルチャー」へと変貌する。これはリベラル化の必然的な帰結である。
- 評判格差社会のステータスゲーム: 現代社会の対立の根底には、誰もが参加を強いられる「ステータスゲーム」が存在する。SNSによって評判が可視化されたことで、人々は道徳的な優位性を示す「美徳ゲーム」に走り、他者を攻撃することで自らのステイタスを高めようとする。
- ポリコレという新たな火種: ポリティカル・コレクトネス(ポリコレ)は、多様な人々が共存するグローバル空間に必要なルールだが、その過剰な適用は「言葉狩り」や新たな分断を生み出す原因にもなっている。
- 「地獄」からの脱出は不可能: 私たちが生きる現代は、ユートピアとディストピアが一体化した「ユーディストピア」である。この複雑な世界から抜け出す特効薬はなく、世界の仕組みを正しく理解し、地雷を踏まないようにうまく適応していくことが唯一の生存戦略となる。
はじめに:なぜ私たちの社会はこんなにも息苦しいのか
「最近、世の中がギスギスしている」「SNSを見るとうんざりする」「何気ない一言で炎上するのが怖い」。多くのビジネスパーソンが、このような息苦しさを感じているのではないでしょうか。かつては許されていたことが許されなくなり、良かれと思って発した言葉が誰かを傷つけ、激しい非難にさらされる。そんな光景が日常茶飯事となっています。
なぜ、私たちの社会はこれほどまでに不寛容で、対立に満ちた「地獄」のような場所になってしまったのでしょうか。
その根源的な問いに、作家・橘玲氏が鋭く切り込んだのが本書『世界はなぜ地獄になるのか』です。橘氏は、この混乱の原因が、私たちが疑いなく「良いこと」だと信じてきた「リベラル化」、すなわち「誰もが自分らしく生きたい」と願う価値観の普及そのものにあると喝破します。
例えば、ジャニーズ事務所の創設者であるジャニー喜多川氏による性加害問題。長年業界の「公然の秘密」とされてきたこの問題が、BBCの報道という「外圧」をきっかけに日本社会を揺るがす大スキャンダルへと発展しました。これは、かつて「芸能界は特殊な世界だから」という理屈で黙認されてきたことが、社会全体のリベラル化によって通用しなくなった象徴的な出来事です。
社会がリベラル化し、人権意識が高まるのは素晴らしいことです。しかし、橘氏は「光が強ければ強いほど、影もまた濃くなる」と述べ、リベラル化がもたらす新たな問題を直視すべきだと警鐘を鳴らします。
リベラル化が引き起こす4つの問題
橘氏は、リベラル化が必然的に引き起こす問題を4つに整理しています。これこそが、現代社会の「生きづらさ」の根本原因です。
- リベラル化によって格差が拡大する
意外に思われるかもしれませんが、社会が自由で公平になるほど、環境要因の影響が減り、生まれ持った遺伝的な才能や能力の差が顕著になります。誰もが「自分らしく」能力を発揮できる結果、成功する者とそうでない者の経済格差はむしろ拡大するのです。 - リベラル化によって社会がより複雑になる
かつて個人は「家」や「ムラ」といった共同体に属していましたが、リベラルな社会では人々はそのしがらみから解放されます。しかし、それは同時に、一人ひとりが異なる利害を持つ無数の個人を調整しなければならないことを意味し、政治や社会の仕組みが機能不全に陥りやすくなります。 - リベラル化によってわたしたちは孤独になる
自由には責任が伴います。共同体の庇護を失った個人は、すべての選択を自己責任で引き受けなければなりません。また、人間関係も流動的・刹那的になり、長期的なつながりを築くことが難しくなり、孤独を感じる人が増えていきます。 - リベラル化によって、「自分らしさ(アイデンティティ)」が衝突する
「自分らしく生きる」ためには、「自分らしさ」を見つける必要があります。このアイデンティティをめぐり、マジョリティ(多数派)とマイノリティ(少数派)の間だけでなく、マイノリティ集団同士でも軋轢や衝突が頻発するようになります。
これらの問題こそが、私たちが日々感じる「地獄」の正体です。そして、リベラルな価値観が生み出したこの問題を、リベラルな政策で解決しようとすること自体が、さらなる混乱を招いていると橘氏は指摘するのです。
キャンセルカルチャーの到来 – 小山田圭吾氏の炎上事件は何だったのか
リベラル化の帰結として現れた最も象徴的な現象が「キャンセルカルチャー」です。本書は、日本にその到来を告げた「小山田圭吾炎上事件」を詳細に分析することから始まります。
2021年、東京五輪の開会式作曲担当だったミュージシャンの小山田圭吾氏が、過去の雑誌インタビューでのいじめ発言を理由に辞任に追い込まれました。SNSでは「全裸でグルグル巻にしてウンコ食わせて」といった衝撃的な部分だけが切り取られ、拡散されました。
しかし、本書が一次資料である『ROCKIN’ON JAPAN』と『Quick Japan』の原文を丹念に読み解くと、まったく異なる様相が見えてきます。
- 特殊な学校環境: 小山田氏が通っていた和光学園は、発達障害のある生徒を積極的に受け入れる、当時としては非常にリベラルな学校でした。インタビューで語られた「いじめ」の多くは、健常な生徒と障害のある生徒が混在する非日常的な空間で起きた出来事だったのです。
- 編集された「事実」: ネットで拡散された情報の元になった匿名ブログでは、小山田氏が「いじめを自慢する加害者」に見えるよう、原文の一部が意図的に削除・編集されていました。例えば、陰惨ないじめ行為について「かなりキツかったんだけど、それは」と困惑を示す一文が削られていたのです。
- 屈折した友情: 『Quick Japan』の記事全体を読むと、それは単なるいじめの武勇伝ではなく、小山田氏と「沢田くん」という障害のある同級生との、友情とは呼べないまでも、ある種の「屈折した交流」の物語として描かれています。小山田氏が沢田くんからの年賀状を大人になるまで大切に持っていたという事実は、単純な加害者・被害者という構図では捉えきれない関係性を示唆します。
- 雑誌側の「人格プロデュース」: 一方で、『ロッキング・オンJAPAN』の記事は、小山田氏を「オシャレ系」から脱却させ、「やさぐれた才能あるアーティスト」としてプロデュースしようという編集長の意図があった可能性が指摘されています。その結果、障害という重要な文脈が消され、単なる残虐ないじめの話として読まれることになったのです。
もちろん、ダウン症の人々に対する差別的な発言など、擁護できない部分があったことは事実です。しかし、この事件は、文脈を無視した情報がいかに人を社会的に抹殺(キャンセル)する凶器となり得るか、そして「正義」の名の下に行われる糾弾がいかに危ういものであるかを浮き彫りにしました。
ポリコレという名の新ルール – なぜ言葉遣いがこれほど問題になるのか
キャンセルカルチャーと密接に関わるのが「ポリティカル・コレクトネス(ポリコレ)」です。橘氏は、ポリコレを「グローバル空間のルール」だと定義します。
かつての人類は、家族や親族といった150人程度の「俺たちのルール」が通用する共同体で生きてきました。しかし、グローバル化が進んだ現代では、異なる文化や価値観を持つ人々が日常的に出会います。そこで殺し合いを避けるために必要となるのが、誰もが最低限守るべき新しい規範、それがポリコレなのです。
本書では、このポリコレがいかに私たちの言葉遣いに影響を与えているかが、具体的な例で示されます。
例えば、ビジネスの現場。日本では役職にかかわらず「さん」付けが主流になり、アメリカではCEOですらファーストネームで呼び捨てにされます。一見正反対ですが、「全員の言語的な距離を同じにする」というポリコレの原則では共通しています。
しかし、日本語の敬語システムは、もともと身分制社会で相手との上下関係を示すために発達したものであり、フラットな人間関係を前提とするポリコレとは相性が悪いのです。その結果、「連絡させていただきます」のような過剰で文法的にも誤用とされる敬語が蔓延したり、逆に何気ない言葉が「敬語警察」の標的になったりする混乱が生じています。
「障害者」という表記をめぐる議論も同様です。「害」という字を避けて「障がい者」とすべきだという意見がある一方で、当事者団体からは「社会によって能力の発揮を“障害”されているのだから、この表記で正しい」という主張も出ています。言葉の言い換えだけでは、問題の本質は解決しないのです。
このように、差別をなくそうという善意から生まれたポリコレのコードが、新たな対立や「言葉狩り」を生み、「表現の自由」と衝突する事態が頻発しています。
終わらない承認欲求 – 「ステータスゲーム」の残酷な現実
なぜ人々は、これほどまでに他者を攻撃し、キャンセルしようとするのでしょうか。橘氏は、その根源に人間の本能である「ステイタスゲーム」があると指摘します。
疫学者マイケル・マーモットの「ホワイトホール研究」では、イギリスの公務員の死亡率が、その地位(ステータス)が下がるにつれてきれいな勾配を描いて高くなることが示されました。ステイタスが低いことは、文字通り「死」に直結するのです。私たちの脳は、他者との比較で自分の地位を測る「ソシオメーター」を持っており、ステイタスが下がると身体的な痛みと同じ苦痛を感じるようにできています。
このステイタスを高めるための戦略は、主に3つあります。
- 成功ゲーム: 富や名声を見せびらかす。
- 支配ゲーム: 権威や権力によって他者を従わせる。
- 美徳ゲーム: 自分の方が道徳的に優れていると誇示する。
現代のSNS社会で爆発的に増えたのが、この「美徳ゲーム」です。成功や支配には実績が必要ですが、美徳ゲームは誰でも簡単に参加できます。不道徳な者を探し出し、「正義」を振りかざして攻撃すれば、コストをかけずに自分の道徳的地位を相対的に引き上げ、快感を得ることができるのです。
不祥事を起こした芸能人への過剰なバッシングや、政治家の失言に対する執拗な攻撃は、まさにこの美徳ゲームの典型例です。SNSはこのゲームの参加を促し、評判を可視化することで、人々を「その場にとどまるためには、全力で走りつづけなくてはならない」という「赤の女王」状態へと追い込んでいます。
「正義」はなぜ暴走するのか – J.K.ローリングと《理論》
美徳ゲームを加速させているのが、大学などのアカデミズムから生まれた「批判理論(《理論》)」です。ジェンダー・スタディーズや批判的人種理論(CRT)といった思想は、キャンセルカルチャーの理論的な支柱となっています。
これらの《理論》は、フランスのポストモダン思想を源流としながらも、それを独自に解釈し、「差別されているマイノリティはつねに正しく、差別するマジョリティはつねに間違っている」という極端な善悪二元論へと行き着きました。
この《理論》の奇妙さを示すのが、本書でも紹介されている「デタラメ論文実験」です。3人の研究者が、フェミニズムやジェンダー研究の学術誌に、意図的にバカげた内容の論文を投稿したところ、その多くが査読を通過し、高く評価されてしまったのです。例えば、「ドッグパークでの犬の交尾からレイプ文化を考察する」といった論文が、著名な学術誌の記念論文として掲載されそうになったというのですから、驚きを通り越して呆れてしまいます。
この《理論》が現実社会で猛威を振るったのが、『ハリー・ポッター』の作者J.K.ローリング氏が「TERF(トランス排除的なラディカルフェミニスト)」のレッテルを貼られ、キャンセルされた事件です。
ローリング氏は、「生物学的な性は現実(sex is real)」とツイートしたことをきっかけに、トランスジェンダー活動家から激しい攻撃を受けました。彼女はトランスジェンダーの権利を擁護しつつも、性自認だけで女性用トイレや更衣室のような空間への立ち入りを認めれば、生物学的な女性の安全が脅かされる可能性がある、という懸念を表明しました。
これは、生物学的な女性の権利を擁護する一部のフェミニストと、性自認を尊重すべきだとするトランスジェンダー活動家との間で起きている、いわば「左派(レフト)同士の衝突」です。しかし、《理論》の世界では、より多くのマイノリティ性を持つ者(この場合はトランスジェンダー)がより大きな正義を持つとされ、ローリング氏の nuanced な意見は「差別」として断罪されてしまいました。
結論:私たちはこの「地獄」をどう生き延びるか
では、この複雑で対立に満ちた「地獄」を、私たちはどう生き抜けばいいのでしょうか。
橘氏は、残念ながらこの地獄から抜け出す特効薬はないと結論づけます。私たちが生きる現代は、ユートピア(自分らしく生きられる社会)の実現がディストピア(絶え間ない対立)を生み出す、いわば「ユーディストピア」だからです。
天国と地獄が一体である以上、私たちにできるのは、この世界の仕組みを正しく理解し、うまく適応していくことだけです。そのための具体的な生存戦略として、橘氏は「地雷原に近づくな」というシンプルなアドバイスを提示します。
- 炎上しやすいテーマ(地雷)には手を出さない
- 個人を名指しで批判しない
- 批判されても反論せず、無視かブロックする
これは消極的な態度に思えるかもしれません。しかし、SNSで正義を振りかざす「極端な人」は、こちらの理屈など聞きません。彼らは自らを「被害者」であり「正義」だと信じ込んでいるため、どのような対話も不毛な泥仕合に終わるだけです。
人生の貴重な時間とエネルギーを不毛な争いで消耗するのではなく、世界の仕組みを冷静に理解し、地雷を避けながら自分の人生を生きる。それが、この「大衆の狂気」の時代を生き延びるための、最も合理的で賢明な処世術なのかもしれません。
本書は、現代社会の息苦しさに悩むすべてのビジネスパーソンにとって、現状を理解し、未来を生き抜くための羅針盤となる一冊です。