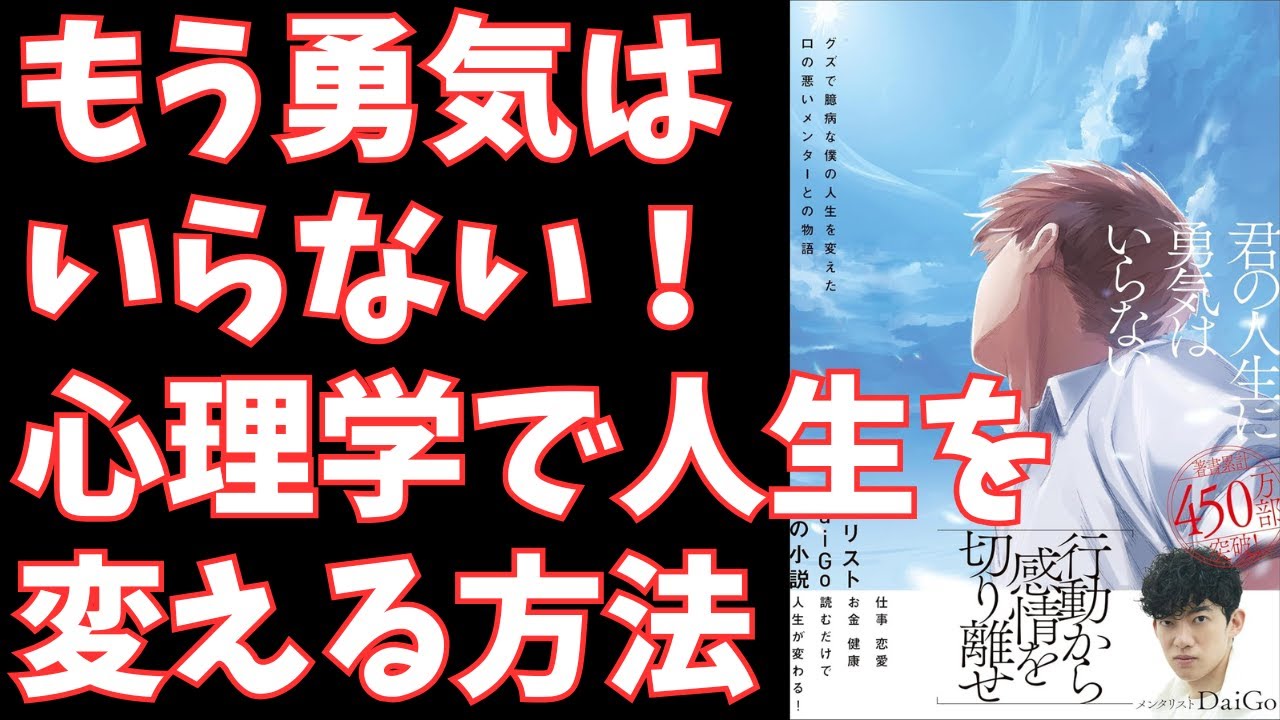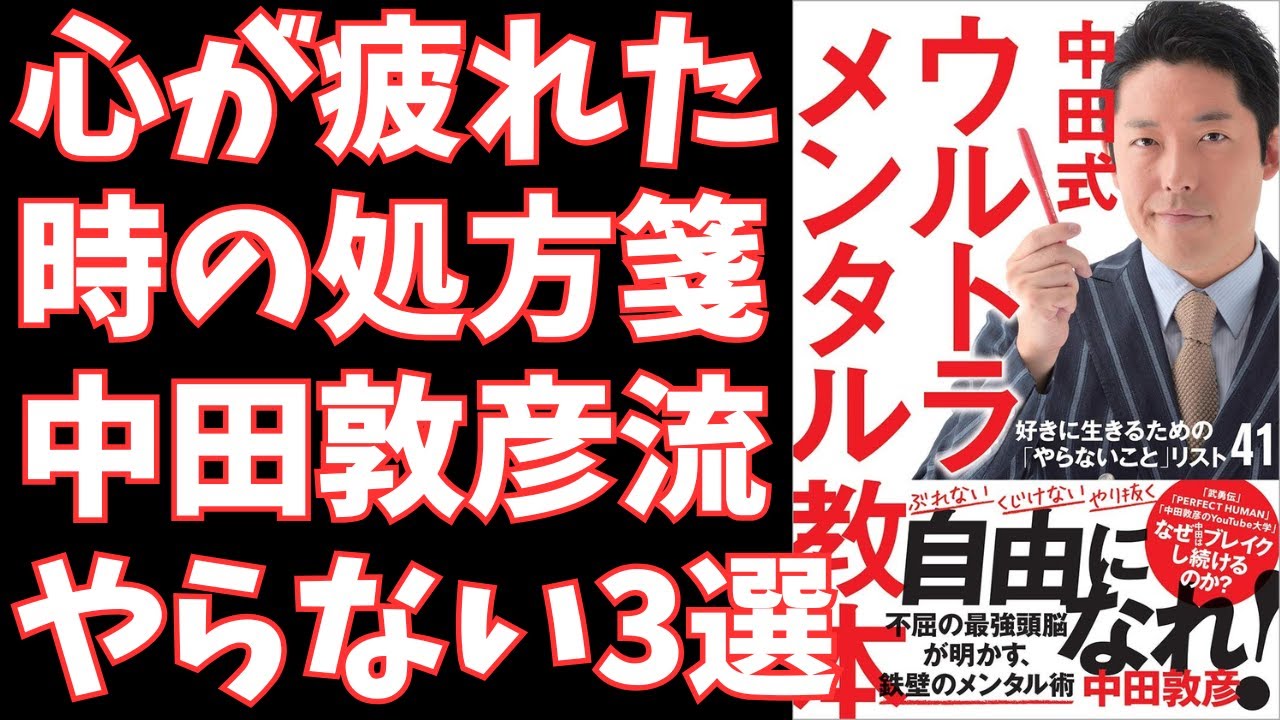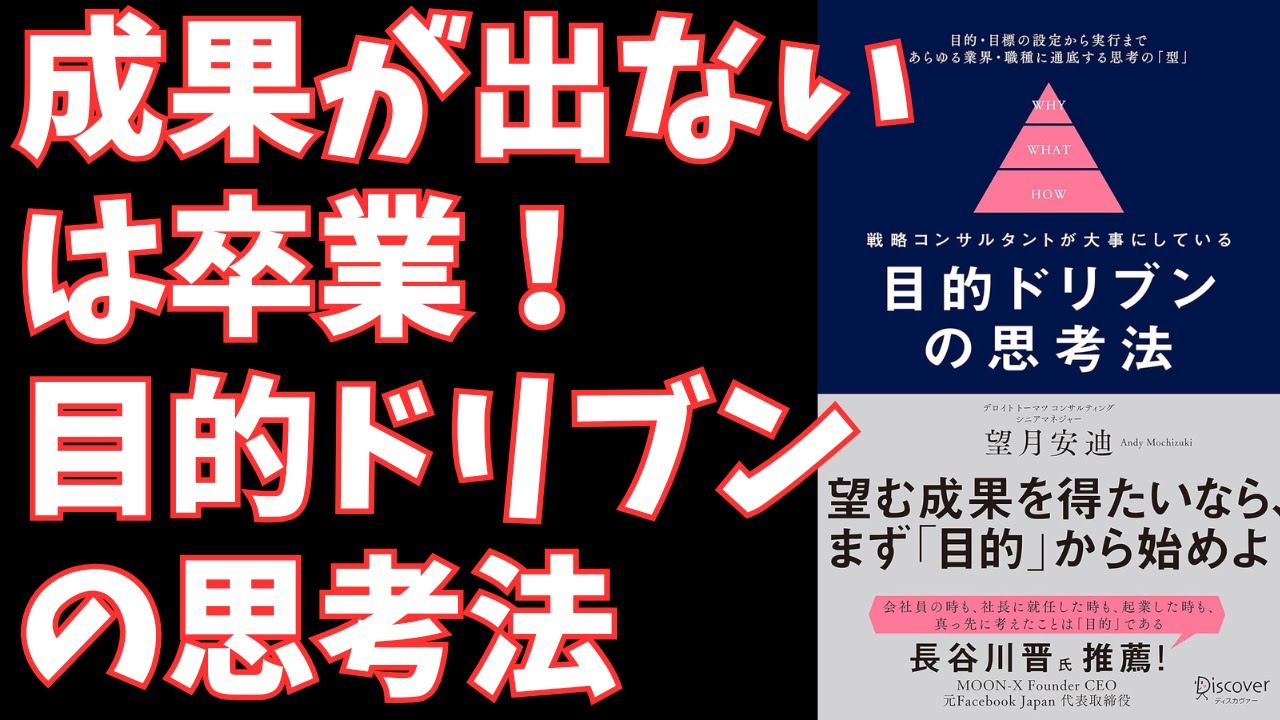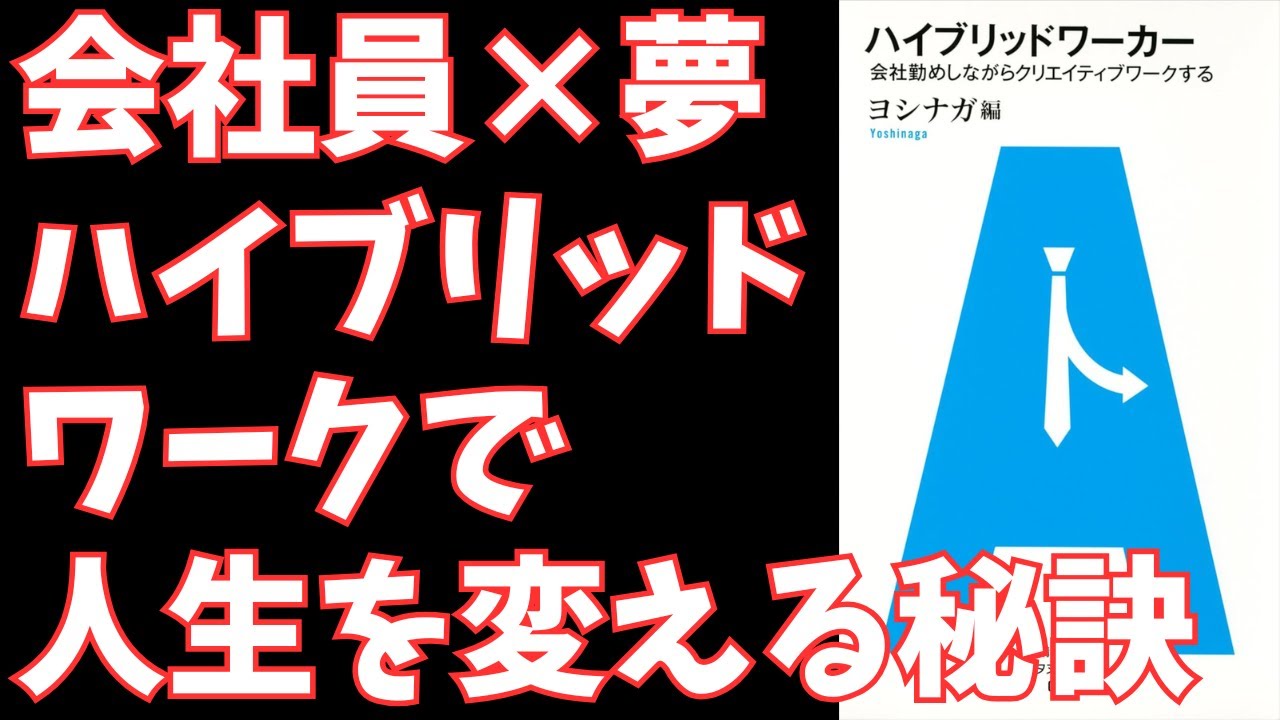『「好き」を言語化する技術』|「やばい!」で終わらせない、仕事にも活きる伝わる言葉の作り方
本書『「好き」を言語化する技術』は、アイドルやアニメなどの「推し」の魅力を自分の言葉で語るための具体的な技術を解説した一冊です。しかし、その内容は趣味の領域に留まりません。「感動を細分化し、自分の感情の源泉を探り、相手に伝わるよう工夫する」というプロセスは、まさにビジネスシーンで求められる企画説明やプレゼンテーション、日々の報告・連絡・相談における「伝える力」そのものです。
この記事では、書評家である著者が長年培ってきた言語化の技術を、多忙なビジネスパーソンが明日から実践できるスキルとして再整理し、本書の核心的なノウハウを具体的な事例と共に解説します。語彙力に自信がない方でも、本書の「ちょっとしたコツ」を掴むことで、あなたの「伝えたいこと」はもっと深く、もっと正確に相手に届くようになるでしょう。
本書の要点
- 言語化の鍵は語彙力ではなく「細分化」: 感動を「どこが」「どのように」良かったのか具体的に分解することが、オリジナルの言葉を生み出す第一歩です。
- 他人の言葉に流されず「自分の言葉」を作る: SNSなどの情報に触れる前に、まず自分のありのままの感想をメモする習慣が、思考の独自性を守ります。
- ありきたりな表現(クリシェ)を避ける: 「泣ける」「考えさせられる」といった安易な言葉を使わず、「なぜそう感じたのか?」を深掘りすることで、思考停止を防ぎます。
- 読解力より「妄想力」で感想を広げる: 正しさにとらわれず、「なぜ?」「どこが?」と自由に思考を広げることが、ユニークな切り口の感想に繋がります。
- 伝わる文章は「工夫」の賜物: 文章のゴール(読者と伝えたいこと)を明確にし、書き出しや構成を工夫することで、初めて相手に意図が伝わります。
なぜ、あなたの「伝えたいこと」は「やばい!」で終わってしまうのか?
「昨日のプレゼン、どうだった?」
「〇〇社の新しいサービス、どう思う?」
ビジネスシーンで意見を求められたとき、頭の中には様々な感情や考えが渦巻いているのに、いざ言葉にしようとすると「すごく良かったです」や「面白いと思いました」といった、ありきたりで中身のない言葉しか出てこない。そんな経験はないでしょうか。
それはまるで、大好きなアイドルのライブを観た後に「とにかく最高だった!やばかった!」としか言えない、あの感覚に似ています。
本書『「好き」を言語化する技術』は、まさにその「『やばい!』しか出てこない」という悩みに、正面から向き合った一冊です。著者は書評家として日々「本」という推しの魅力を言語化し続けてきた三宅香帆さん。彼女は、「自分の感想を言葉にするうえで大切なことは、語彙力ではない」と断言します。
では、何が必要なのか? それが、本書で一貫して語られる「自分の言葉をつくる、ちょっとしたコツ」です。
多くのビジネスパーソンは、「うまく話せないのは、語彙や知識が足りないからだ」と考えがちです。しかし、本書を読めば、その考えが一種の思い込みであったことに気づかされるでしょう。本当に大切なのは、自分の内側にある感情や思考を、いかに丁寧に観察し、分解し、再構築するか、という技術なのです。
この記事では、本書で紹介される数々のテクニックの中から、特にビジネスパーソンが応用しやすいポイントを抽出し、あなたの「伝える力」を一段階引き上げるための具体的な方法論を解説していきます。
ステップ1:言語化の「準備」- 他人の言葉の濁流から「自分の言葉」を守る
現代は、SNSを開けば他人の意見や感想が洪水のように流れ込んでくる時代です。素晴らしい映画を観た後、自分の感動を整理する前にTwitterで検索し、他人の巧みな感想を読んで「そうそう、これ!」と満足してしまった経験はありませんか?
著者はこの行為に警鐘を鳴らします。なぜなら、他人の言葉は、知らず知らずのうちに自分のオリジナルの感想を上書きしてしまうからです。強い言葉や巧みな表現は、それがまるで最初から自分の意見だったかのような錯覚さえ引き起こします。
これをビジネスシーンに置き換えてみましょう。会議で新しい企画について意見を求められた際、影響力のある上司が「この企画は画期的だ」と発言した途端、自分が抱いていた小さな違和感を口に出せなくなり、いつの間にか「自分も画期的だと思っていた」かのように振る舞ってしまう。これは、自分の思考が他人の言葉に支配されている状態です。
では、どうすれば自分の言葉を守れるのか。著者が提唱する最も重要で、かつシンプルな方法が「まっさきに自分の感想をメモする」ことです。
自分の「好き」を言語化する前に、他人の言語化を見ることは、やめておきましょう。
具体的に言うと、「SNSやインターネットで自分の推しについての感想を見るのは、自分の感想を書き終わってから!!」。
対象に触れた直後の、まだ言語化されていない「もやもや」とした感情。これこそが、あなただけのオリジナルの感想の源泉です。その熱量が高いうちに、誰にも見せない自分だけのメモ帳や非公開のブログに、単語の羅列でも箇条書きでもいいので書き留めておく。
- 一曲目に〇〇の曲がきたこと
- 〇〇のダンスがうまくなっていたこと
- 〇〇の衣装がかわいかったこと
本書で挙げられているライブの感想の例のように、まずは心を動かされた「事実」を具体的にリストアップすることから始めます。この段階では、うまい言葉を探す必要は一切ありません。この「他人の言葉による汚染」から自分を隔離する時間を持つことが、独自の視点を育むための第一歩となるのです。
ステップ2:言語化の「実践」- 語彙力ではなく「細分化」と「妄想力」が武器になる
自分だけの感想のタネを確保したら、次はいよいよそれを言葉にしていく段階です。ここで多くの人が「語彙力がないから…」と挫折しますが、著者はここでも「必要なのは語彙力ではない」と繰り返します。鍵となるのは「細分化」と「妄想力」です。
言語化とは、つまり「細分化」のこと
「あのプレゼン、最高だった」という感想は、何も伝えていません。「最高」という大きな塊を、具体的な要素に分解していく作業こそが「細分化」です。
感想のオリジナリティは細かさに宿るからです。
たとえば、ライブの感想に「最高!」という言葉しかでてこないという悩みは、ライブの「どこが」最高だったのかを言えたら解消されます。
- なぜ「最高」だと思ったのか?
- 導入で提示されたデータが意外性に富んでいて、引き込まれたから。
- 〇〇さんの語り口が熱っぽく、本気度が伝わってきたから。
- 最後の質疑応答で、こちらの意図を正確に汲み取った回答をしてくれたから。
このように、「最高」という感情を構成している要素を一つひとつ分解し、それぞれに言葉を与えていく。この作業を行うだけで、あなたの感想は途端に具体的で、説得力のあるものに変わります。
これはネガティブな感想を言語化する際にも有効です。「あの企画は微妙だった」で終わらせず、「不快」だったのか「退屈」だったのかをまず分類し、その原因を探ります。
- 不快: 提示されたデータに、こちらの事業を軽視するような意図を感じた。
- 退屈: 結論が業界の常識の範囲内であり、目新しさがなかった。
このように感情を細分化することで、単なる悪口ではない、建設的なフィードバックとしての言葉が生まれるのです。
感想は「読解力」ではなく「妄想力」で生み出す
細分化するネタそのものが思いつかない、という人もいるでしょう。著者は、感想を書くのに「読解力」や「観察力」は必要なく、むしろ「妄想力」が大切だと説きます。
「妄想力」とはなにか?
それは、自分の考えを膨らませる能力のことです。
例えば、推しの俳優の演技が「よかった」と感じたとき、「なぜよかったんだろう?」という問いから思考を広げていきます。
「あの自然な演技、どうしてできたんだろう? もしかしたら、彼自身の過去の経験が反映されているのか? いや、監督が徹底的にリアリティを追求するタイプだから、その指導の賜物か? 以前の作品と比べると、明らかに演技の幅が広がっているな…」
このように、正解かどうかは脇に置き、自分の頭の中で自由に思考をこねくり回す。この「妄想」のプロセスが、他の誰も気づかなかったユニークな視点や深い洞察に繋がっていきます。
ビジネスにおいても、ある成功事例を分析する際に、公開されているデータだけをなぞるのではなく、「この成功の裏には、担当者のどんな個人的な執念があったのだろう?」「このプロジェクトがもし失敗していたとしたら、どんな要因が考えられただろう?」と妄想を広げることで、表層的な理解に留まらない、本質的な学びを得ることができるのです。
ステップ3:言語化の「伝達」- あなたの言葉を相手に「届ける」ための文章術
自分だけの言葉をつくりだせたら、最後のステップはそれを相手に伝わる形に「編集」することです。本書の第5章「推しの素晴らしさを文章に書く」は、ブログや企画書、報告書など、あらゆるビジネス文書作成に応用できる珠玉のノウハウが詰まっています。
書き始める前にやるべき、たった2つのこと
いきなり書き始めるのは悪手です。その前に、文章の「ゴール」を明確に設定しなければなりません。
- 読者を決める: この文章は誰に読んでほしいのか?(例:このジャンルを全く知らない人、自分と同じくらい詳しい同僚、意思決定をする役員)
- 伝えたいポイントを一点に絞る: この文章を読み終えたとき、読者に「これだけは伝わっていてほしい」という核心は何か?
この2つを決めるだけで、文章の方向性が定まり、途中で迷子になることが格段に減ります。特に「伝えたいことは一点に絞る」のは重要です。あれもこれもと欲張ると、結局何も伝わらない凡庸な文章になってしまいます。
文章の顔、「書きだし」で心を掴む
読者は多忙です。最初の数行で「読む価値がある」と思わせなければ、すぐに離脱してしまいます。本書では、読者の興味を引く4つの書き出しパターンが紹介されています。
- よかった要素を描写する: 最も伝えたい核心部分(例:映画のワンシーン、製品の画期的な機能)を冒頭で具体的に描写する。
- 自分語りをする: 読者が共感できるような自分自身の体験談から始めることで、テーマを自分ごととして捉えてもらう。(例:「『働き始めたら、本が読めなくなったよ』。かつて友人が漏らしたこの言葉の意味を、私はこの映画で知ることになった」)
- 「文脈」で始める: より大きな歴史やジャンルの中にテーマを位置づけることで、新規性や共通点を示す。(例:「これまでのアイドル史になかった、彼女たちの新しさとは何か」)
- 奥の手、「問い」ではじめる: 「なぜ〇〇は私たちの心を掴むのか?」のように、読者に問いかけることで、その答えを探す旅へと誘う。
これらのパターンは、プレゼンの冒頭やレポートの導入部分にもそのまま応用できるでしょう。
文章は「修正」で磨かれる
著者は、作家・森見登美彦さんの「プロとアマチュアの違いは、修正の数だ」という言葉を引用し、修正の重要性を説いています。 一度で完璧な文章を書こうとせず、「修正は当たり前」という前提で、まずは最後までラフに書き終えることが大切です。
そして、修正する際は「別人になったつもり」で客観的に読み返し、以下の3つの視点で見直すことを推奨しています。
- 文章の順番を変える: 一番パンチのあるフレーズを冒頭に持ってくるだけで、文章全体の印象が劇的に変わる。
- いらない文章を削る: 「せっかく書いたのに」という気持ちを捨て、伝えたい核心と関係ない情報を大胆に削ることで、文章はシャープになる。
- 見出しをつける: 長い文章は、内容の塊ごとに見出しをつけるだけで、格段に読みやすくなる。
この「書く→修正する」というサイクルを回すことで、あなたの文章の質は着実に向上していきます。
まとめ:あなたの「好き」が、最強の「伝わる力」に変わる
本書で紹介されているのは、単なる文章テクニックではありません。それは、自分の内面と深く向き合い、思考を整理し、他者への想像力を働かせながら言葉を紡いでいく、という一連の思考プロセスそのものです。
「推しを語る」という、最も熱量のある個人的な行為をトレーニングの場とすることで、私たちは楽しみながら、ビジネスシーンで不可欠な「言語化能力」と「伝達力」を磨くことができます。
「やばい!」の一言で片付けてしまっていた豊かな感情の機微を、自分だけの言葉で表現できたとき。その言葉が、同僚やクライアントの心を動かし、仕事の成果へと繋がったとき。あなたは、自分の「好き」という感情が、これほどまでにパワフルな武器になることに驚くはずです。
まずは、今日あなたが「心が動いたこと」を、誰にも見せずにこっそりとメモするところから始めてみてはいかがでしょうか。その小さな一歩が、あなたの言葉を、そしてあなたの仕事を、より豊かに変えていくはずです。