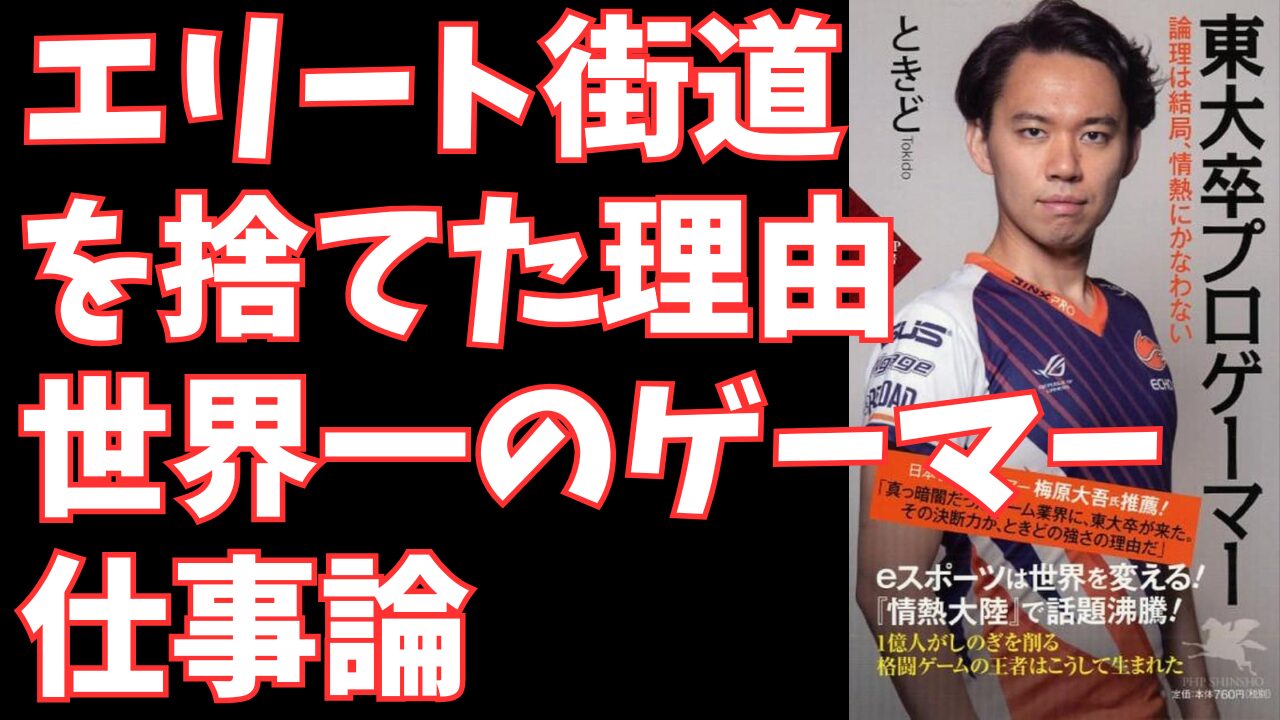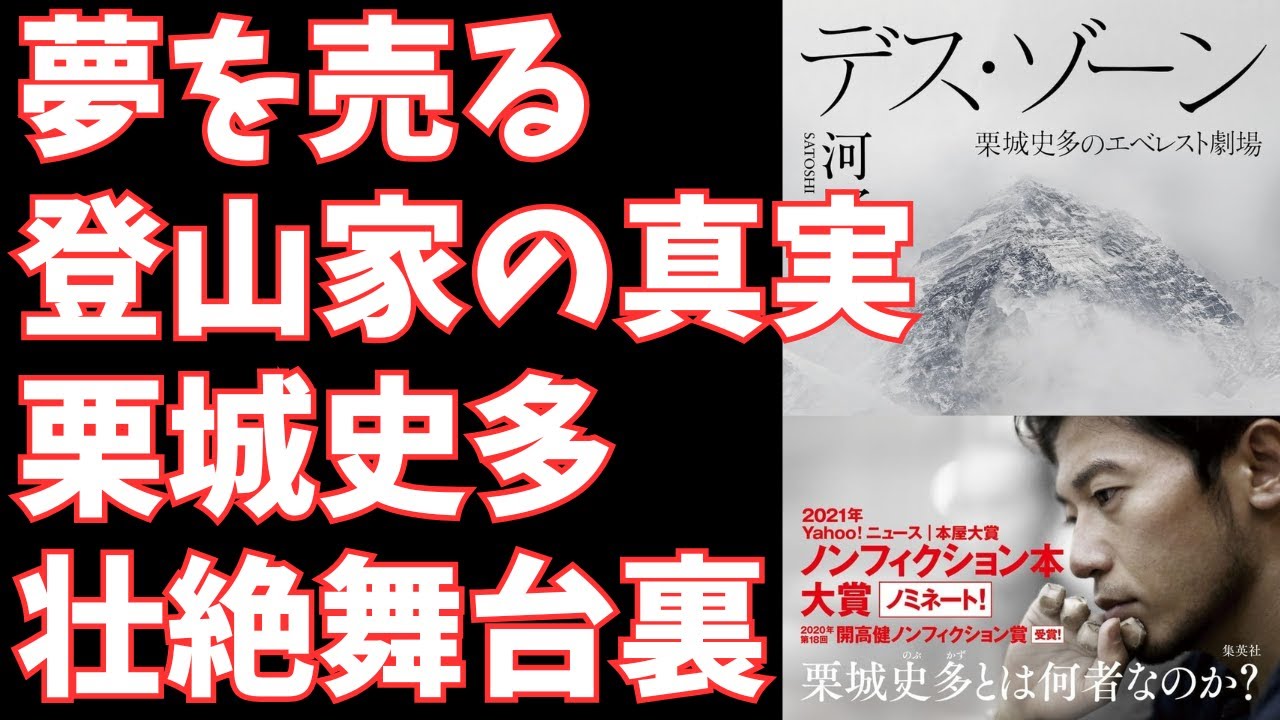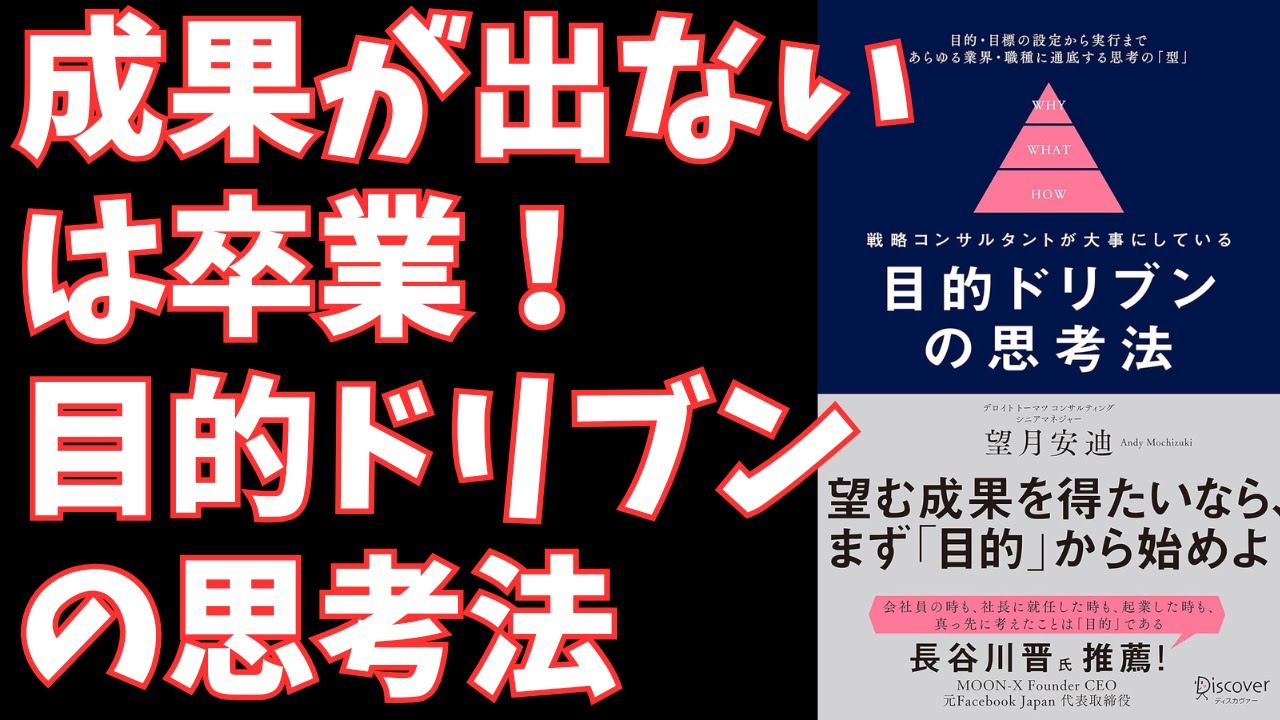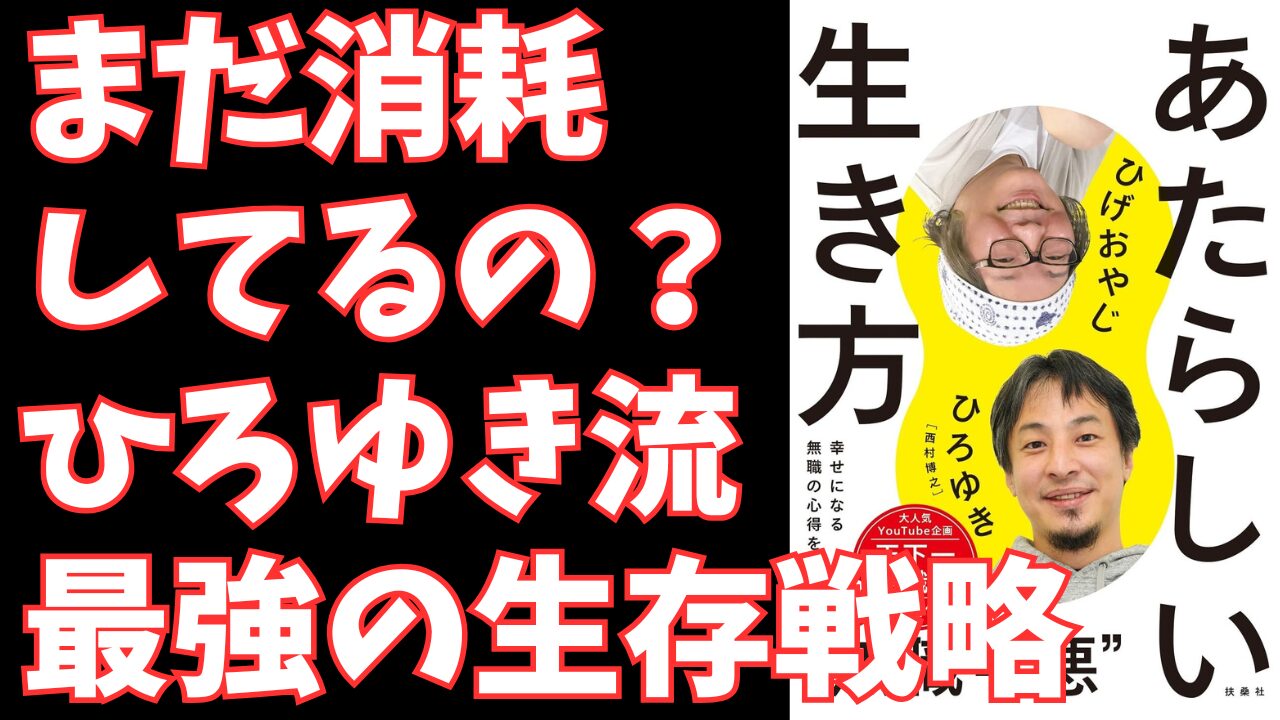けんすう著『物語思考』|「やりたいこと」が見つからない悩みを解決する新しいキャリア設計術
本書『物語思考』は、「やりたいこと」が見つからずに行動できないと悩むビジネスパーソンに向けて、具体的な「やり方」を提示する一冊です。従来の精神論的な自己啓発書とは一線を画し、人生を一つの「物語」と捉え、自分をその「主人公(キャラクター)」として設定することで、客観的に人生を進めていくという画期的な手法を提案しています。
「何をしたいか(Do)」ではなく「どうありたいか(Be)」から理想の姿を描き、その理想を実現するための「キャラ」を設計し、行動に移していく。このプロセスを通じて、不安や恐れを乗り越え、日々のプロセスそのものを楽しめるようになり、結果として充実した人生を送ることができるようになると著者は説きます。この記事では、その具体的なステップと核心的な考え方を、書籍内の事例を交えながら詳しく解説していきます。
本書の要点
- 「何をしたいか(Do)」ではなく「どうありたいか(Be)」から始める
多くの人がつまずく「やりたいこと探し」ではなく、自分が将来「どうありたいか」という状態をイメージすることからキャリア設計をスタートさせます。 - 人生を一つの物語と捉え、理想の自分を「キャラクター」として設定する
自分自身を客観視し、行動しやすくするために、理想の状態から逆算した「キャラ」を設定します。これにより、他人事のように自分の人生をプロデュースでき、不安や恐れを乗り越えやすくなります。 - 行動はキャラ設定から生まれ、キャラは行動によって強化される
「自分はこういうキャラだ」と認識することで、そのキャラらしい行動が自然と促されます。そして、その行動を繰り返すことで、キャラ設定がより強固なものになっていきます。 - 理想のキャラが活きる「環境」に身を置く
人間は環境に大きく影響されるため、設定したキャラが自然体でいられるような環境(人間関係)に身を置くことが、自分を変える上で最も効果的で効率的な方法です。 - 失敗は物語を面白くする要素と捉え、挑戦を続ける
物語に失敗や困難がつきものであるように、人生における失敗もまた、物語に深みを与える重要な要素と捉えます。リスクを適切に管理することで、失敗を恐れず挑戦を続けられるようになります。
はじめに:「やりたいこと」という呪いから解放されるために
「あなたのやりたいことは何ですか?」
この問いに、胸を張って即答できるビジネスパーソンはどれくらいいるでしょうか。「やりたいことが見つからない」「情熱を注げるものがない」——。多くの人が、そんな漠然とした悩みを抱えながら、日々の業務に追われています。
世の中には「好きなことを見つけろ!」「リスクを恐れず行動せよ!」と謳うビジネス書が溢れています。しかし、それらを読んで一時的にモチベーションが上がっても、数日後には元の生活に戻ってしまう、という経験をしたことがある人も少なくないでしょう。なぜなら、それらの本の多くは「何をすべきか」は示してくれても、「どうすれば行動できるのか」という具体的な方法論に欠けているからです。
今回ご紹介する、けんすう(古川健介)氏の著書『物語思考 「やりたいこと」が見つからなくて悩む人のキャリア設計術』は、まさにその「どうすればいいかわからない」という悩みに、極めて具体的かつ実践的な解決策を提示してくれる一冊です。
本書が提唱するのは、「自分を主人公にした物語を作るように人生を設計する」という、その名も「物語思考」。これは、やる気を出すための精神論ではなく、行動できない原因となる不安を解消し、誰でも実践可能な「ハウツー」にまで落とし込まれた画期的なメソッドです。
この記事では、『物語思考』のエッセンスを抽出し、忙しいビジネスパーソンの皆さんが明日から実践できる形で、その思考法と具体的なステップを詳しく解説していきます。
「物語思考」とは? なぜ「やりたいこと」探しはうまくいかないのか
本書の根幹をなす「物語思考」とは、一言でいえば「自分の理想どおりに人生を過ごすために、いっそ一つの物語を作るように考えよう」というアプローチです。自分を物語の主人公、つまり「キャラクター」として設定し、そのキャラを動かしていく感覚で人生を進めていきます。
「Do(何をしたいか)」ではなく「Be(どうありたいか)」
多くの人がキャリアに悩むとき、「何をしたいか(Do)」から考え始めます。しかし、著者によれば、これこそが挫折の始まりです。なぜなら、経験のないことに対して「やりたい」という感情を具体的に抱くのは非常に難しいからです。
そこで『物語思考』では、まず「どうありたいか(Be)」から考えることを推奨しています。
「かっこいい大人になりたい」「家族と幸せに暮らしたい」「お金に縛られずに自由に生きたい」といった「なりたい状態」であれば、多くの人がイメージしやすいはずです。
この「未来のなりたい状態」こそが、現在の行動に最も大きな影響を与えると著者は指摘します。
人間、過去にやってきたことを惰性で今日してしまうことが多いから、なんとなく過去の自分のほうが今の自分に影響を与えそうな感じがしますが、現在の行動には未来になりたい自分像のほうが影響を与えるんですね。
例えば、「10年間野球をやってきた」という過去があっても、「プロのテニスプレイヤーになりたい」という未来の目標ができれば、その日からテニスの練習を始めるはずです。このように、まず「どうありたいか」という未来像を明確にすることが、行動を変えるための第一歩となるのです。
なぜ「物語」として考えるのか
自分を客観視し、まるでゲームのキャラクターを操作するように人生を進めることで、多くのメリットが生まれます。
- 他人事化できる: 自分のことだと思うと「失敗したらどうしよう」「恥ずかしい」といった不安が先に立ちますが、「この物語の主人公なら、ここでどう動かすのが面白いか?」と考えることで、冷静かつ大胆な判断がしやすくなります。
- 失敗がリスクでなくなる: 何も起きない平坦な人生は、物語としては退屈です。挑戦や失敗は、物語を面白くするための「イベント」や「伏線」と捉えることができます。失敗を恐れるどころか、むしろ物語を盛り上げる要素として歓迎できるようになるのです。
従来の自己分析やキャリアプランニングがうまくいかなかったのは、「今の自分」を起点に未来を描こうとしていたからです。しかし、未来が予測不可能な現代において、そのアプローチは機能しづらくなっています。『物語思考』は、未来の理想像から逆算して「今」の行動を変えていく、全く新しいキャリア設計術なのです。
ステップ1:行動を縛る「頭の枷」を外す
「物語思考」を実践する上で、最初のステップは「頭の枷(かせ)を外す」ことです。
「何の制限もなかったら、どうなりたいですか?」と聞かれたとき、多くの人が「年収600万円くらいかな」「今の会社で部長になれれば」といった、非常に現実的な範囲で答えてしまいます。これは、自分自身で「さすがにこれは無理だろう」という限界ラインを無意識に引いてしまっているからです。これが「頭の枷」です。
この枷がある限り、せっかく作る物語もスケールの小さな、ワクワクしないものになってしまいます。そこで本書では、まずこの枷を取り除くための具体的なワークを提案しています。
ワーク:「10年後になりたい状態」を100個書き出す
やり方はシンプルです。カフェなどで時間を確保し、何の制限も設けずに「10年後になりたい状態」をとにかく100個書き出すのです。
「エルメスのバッグを持つ」といった物欲でも、「毎日8時間睡眠をとる」といった健康面のことでも、粒度は問いません。誰かに見せるものではないので、自分の心が本当にワクワクするようなことを自由に書き出してみましょう。
多くの人は30〜50個で手が止まってしまいますが、そこから無理やりにでも100個ひねり出すことが重要です。意外にも、後半で無理やり書いたことのほうが、自分の本質的な願望だったりすることもあります。
もし「なりたい状態」が思い浮かばなければ、「こうはなりたくない」というネガティブな状態から考え、その逆を書き出してみるのも有効な方法です。
解像度を上げて、コンフォートゾーンを動かす
リストを書き出したら、次はその解像度を上げていきます。
例えば「ベンツが欲しい」なら、実際にディーラーに行って試乗してみる。「高級ホテルに泊まりたい」なら、まずはそのホテルのカフェに行ってみる。そうやって五感で体験することで、漠然とした憧れが具体的な目標へと変わっていきます。
こうした行動は、自分の「コンフォートゾーン(心地よいと感じる基準)」を引き上げる効果もあります。
著者は大学受験の際に、「自分は早稲田大学生だ」と思い込むために、合格体験記を自分で書いたり、大学の構内を我が物顔で歩いたりしたそうです。そうすることで、脳が「早稲田大学生であることが当たり前」と錯覚し、「その状態を失うのが怖い」という気持ちから、自然と勉強に身が入るようになったといいます。
このように、まず自分の限界を取っ払い、理想の状態をありありと思い浮かべられるようになることが、壮大な物語を始めるための最初の、そして最も重要な一歩なのです。
ステップ2&3:最強の武器「キャラ」を作り、行動する
「なりたい状態」が明確になったら、次はいよいよ物語の核となる「主人公=キャラクター」の設定です。ここが『物語思考』の最も重要な山場となります。
なぜ「キャラ」が先なのか?
多くの人は、まず行動して結果を出し、その結果をもって「自分はこういう人間だ」と認識しようとします。しかし、この順番では多くの場合うまくいきません。ダイエットを例にとると、「食事制限と運動を頑張る(プロセス)→5kg痩せる(結果)→自分は痩せている人間だ(アイデンティティ)」という流れです。しかし、結果はすぐに出ないため、多くの人が途中で挫折してしまいます。
『物語思考』では、この順番を逆にします。
自分はこういうキャラクターだと認識する(アイデンティティ)
↓
そのキャラがやりそうなプロセスを実行する
↓
結果が出る
先に「自分はアスリートのようなキャラだ。お菓子は食べないし、定期的に運動する」というキャラ(アイデンティティ)を決めてしまうのです。そうすれば、そのキャラらしい行動(健康的な食事や運動)をとることが「当たり前」になり、結果が出なくてもプロセスを継続しやすくなります。
「俺はいいけどYAZAWAはなんて言うかな」
このキャラ設定の好例として、著者はアーティストの矢沢永吉さんの逸話を紹介しています。スタッフがミスをした際に、矢沢さんは「俺はいいけどYAZAWAはなんて言うかな」と言ったそうです。
これは、「個人としての矢沢永吉」と「スーパースターという商品としてのYAZAWA」を明確に分けている証拠です。矢沢永吉さん自身が「YAZAWA」というキャラクターをプロデュースし、演じきっているのです。
私たちも同様に、「なりたい状態」を実現するために最も効率的なキャラは何か?という視点で、自分をプロデュースしていくのです。
キャラ設定と行動の具体的な方法
では、どうやってキャラを作るのか。
- キャラの原型を作る: ステップ1で書き出した「なりたい状態」を体現している実在の人物(有名人、歴史上の人物、身近な人など)をリストアップします。これがキャラの原型となります。
- キャラの性質を抜き出す: リストアップした人物がどのような性質(性格、行動様式)を持っているかを書き出し、自分の「なりたい状態」を達成するのに役立ちそうな要素を抜き出していきます。
キャラの輪郭が見えてきたら、次は「そのキャラなら、こういう時どう行動するか?」をシミュレーションし、リスト化します。
- 朝起きたら何をするか? → すぐに起きて活動を開始する
- 上司に怒られたらどうするか? → 「ご指摘ありがとうございます!」と言い、即座に改善報告をする
- 未経験の仕事を依頼されたらどうするか? → 関連書籍を5冊読んで土地勘をつける
このリストをもとに、まずは一つでもいいので実際に行動してみましょう。「褒められたら『ありがとうございます!』と素直に言う」といった小さなことで構いません。
行動がキャラを作り、キャラが行動を促す。 この両輪を回していくことで、理想の自分へと近づいていくのです。「本当の自分とは違う」と感じるかもしれませんが、人の内面は曖昧なもの。行動を続けるうちに、周りからもそう認識され、やがて自分自身もそのキャラを「本当の自分」だと信じられるようになっていきます。
ステップ4:自分を変える一番の近道は「環境」を変えること
理想のキャラを設定し、行動を始めても、それを持続させるのは簡単ではありません。そこで重要になるのが、「環境の力」です。
著者は「個人が成功するかどうかは、その人の高い能力や才能のおかげではなく、時代などの環境によって、役割が付与されただけなのではないか」とまで言い切ります。それほどまでに、環境が人に与える影響は絶大なのです。
「勇気がない」のではなく「環境が違う」だけ
「起業したいけど勇気がない」という悩みはよく聞かれます。しかし、著者はそれを個人の資質の問題ではないと指摘します。
例えば、アメリカのスタンフォード大学では、学生にアンケートを取ると「卒業したら全員が起業する」と答えたという話があります。彼らが皆、特別な起業家精神を持っているわけではありません。「周りのみんなが起業するのが当たり前」という環境にいるから、起業という選択肢を取るのに特別なエネルギーが要らないだけなのです。
これはキャリアにおいても同じです。
理想の自分や「こうしたい」というものがあるときに「自分が努力をする」とか「まわりがなんと言おうと自分の信念を貫く」とかはダメなパターンです。一部の超人をのぞいて、普通の人は、そんなことできません。非合理的です。効率が悪すぎるんです。
最も効率的で効果的な方法は、設定したキャラが活きる環境、つまり「理想とする人々がいるコミュニティ」に飛び込んでしまうことなのです。ラーメンを食べ歩くサークルにいればラーメンに詳しくなりますし、ストイックに運動するサークルにいれば自然と体は絞れていきます。
理想の環境に入り込む「サードドア」
とはいえ、理想のコミュニティに真正面から入っていくのは難しい場合もあります。そこで著者が紹介するのが「サードドア」という考え方です。
これは、行列のできるナイトクラブの入口に、一般客が並ぶ「ファーストドア」、VIP専用の「セカンドドア」の他に、誰も知らない裏口=「サードドア」がある、という比喩です。つまり、お金もコネもない人間が成功するためには、他の人とは違う抜け道を探す必要がある、ということです。
例えば、著者の知人は、起業家コミュニティに入るために「起業家専門のインタビューメディア」を立ち上げました。メディアという立場を利用することで、多くの起業家と対等な関係を築き、人脈と知識を得て、最終的に自身の起業を成功させました。
また、「つながりたい人のお客さんになる」のも有効なサードドアです。特に、相手が「今一番頑張っていること」のお客さんになるのが効果的です。新作を出したばかりの作家の感想を誰よりも早くSNSに投稿したり、立ち上げたばかりのサービスの一番のユーザーになったりすることで、相手に強く認知され、応援してくれる貴重なファンとして関係を築くことができるのです。
SNSで応援団を作る
リアルな環境を変えるだけでなく、SNSを活用して応援してくれる人を増やすことも現代においては非常に重要です。
著者は、SNSでの発信を以下の3つに分け、フォロワーが少ないうちは「Information(有益な情報)」の発信に徹することを推奨しています。
- Information(情報): ニュースなど、誰が言っているかに関わらず価値のある情報。
- Opinion(意見): ある事象に対する自分の意見や感想。
- Diary(日記): 「ラーメン食べた」などの日常の共有。
知らない人の意見や日記に興味を持つ人はほとんどいません。まずは特定の分野で「この人は有益な情報をくれる」というポジションを確立し、フォロワーが増えてから少しずつ意見や日常を混ぜていく。そうすることで、徐々にあなた自身のファン、つまり物語の応援団が増えていくのです。
ステップ5:失敗を恐れず「物語を転がす」技術
キャラが定まり、環境も整ったら、最後はいよいよ「物語を転がす」、つまり具体的な挑戦を始めるフェーズです。しかし、ここでも「新しいことを始めるのが怖い」という最後の壁が立ちはだかります。
このステップでは、その恐怖や不安を乗り越え、物語を前進させるための具体的なコツが紹介されています。
不安を乗り越える5つのコツ
- 不安なことはすべて紙に書き出す(ジャーナリング): 頭の中でぐるぐると回り続ける不安や悩みを、紙に書き出すことで客観視できます。「この物語の主人公は、こんなことで悩んでいるのか。だとしたら、次はこう動かすべきだな」と、他人事のように冷静な判断が下せるようになります。
- アイデアを温めない: 「完璧なアイデアが浮かんでから行動しよう」と考えるのは、行動できない人の典型的なパターンです。アイデア自体に価値はほとんどなく、実行力が全てです。美大の実験で「質より量を求めたグループ」の方が良い作品を生み出したように、まずは下手でもいいから完成させる、大量に行動することが成功への近道です。
- 「判断」と「決断」を区別する:
- 判断: 情報を集め、論理的に答えを導き出すこと(例:このキノコに毒はあるか?)。
- 決断: データだけでは答えが出ないことに対し、意思を固めること(例:転職すべきか?)。
多くの人は、決断すべきことを判断しようとして、情報を集めすぎて動けなくなります。時間を区切って情報を集めたら、あとは「決断」する。この区別が、物語を停滞させないために重要です。
- リスク管理表を作る: 挑戦におけるリスクは、「とるか、とらないか」の二元論で考えると恐怖で動けなくなります。リスクは「管理する」ものと捉えましょう。「起業して収入がなくなったら」というリスクに対し、「半年分の生活費を貯める」「失敗したらすぐに戻れるように、今の会社と良好な関係を保っておく」といった回避策や対策を事前にリストアップしておくことで、安心して挑戦に踏み出せます。
「失敗」は物語を面白くする最高のコンテンツ
物語思考で最も重要なマインドセットは、「失敗はプラスである」と捉えることです。
失敗のない主人公の物語が面白くないように、人生もまた、失敗や挫折があるからこそ深みを増します。スティーブ・ジョブズが一度Appleを追放されたエピソードは、彼の人生という物語をよりドラマチックにしています。
現代のSNS社会では、失敗談すらも人々を惹きつける「コンテンツ」になります。 著者が運営する有料メディアでも、成功談より失敗談のほうが圧倒的に人気があるそうです。
失敗を恐れて何もしないことが、物語としては最大のリスクです。物語を転がし、時に失敗し、それを乗り越えていく。そのプロセス自体を楽しむことこそが、『物語思考』の真髄なのです。
まとめ:あなたの「成長物語」を始めよう
『物語思考』は、単なるキャリア設計術にとどまらない、人生そのものを豊かにするためのOS(オペレーティングシステム)です。
未来を予測することが困難なこの時代に、「今の自分」を起点にしたキャリアプランはもはや機能しません。「やりたいこと」という曖昧なものを探し続けるよりも、「未来のなりたい自分」から逆算して「キャラ」を作り、そのキャラとして行動し、物語を転がしていく。 このアプローチこそが、私たちを不確実性の時代における不安から解放し、充実した「今」を与えてくれます。
本書は、ゴールに到達することだけが成功ではないと教えてくれます。むしろ、困難に立ち向かい、仲間と出会い、失敗しながらも成長していく「プロセス」そのものにこそ、幸せや充実感があるのだと。
もしあなたが「やりたいことが見つからない」「どう行動していいかわからない」と立ち止まっているのであれば、ぜひ本書を手に取り、自分だけの「物語」を書き始めてみてください。それは、あなたという主人公が、なりたい自分になっていく、最高の「成長物語」になるはずです。