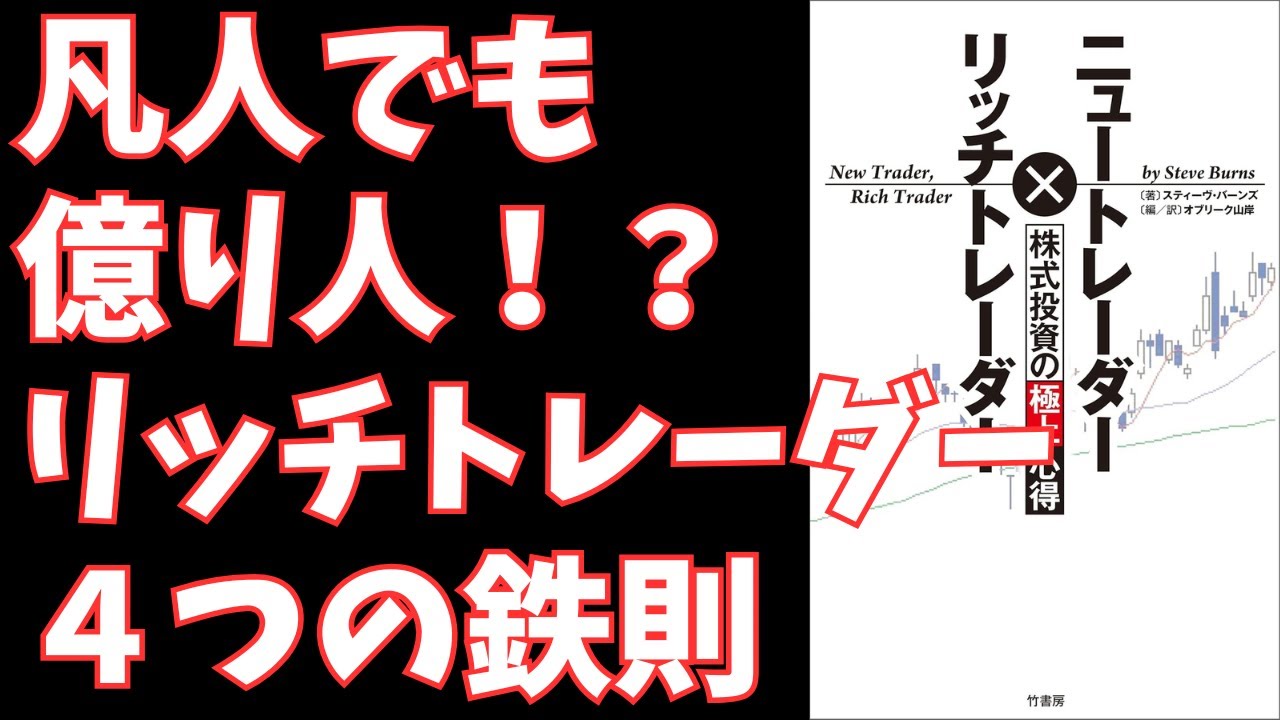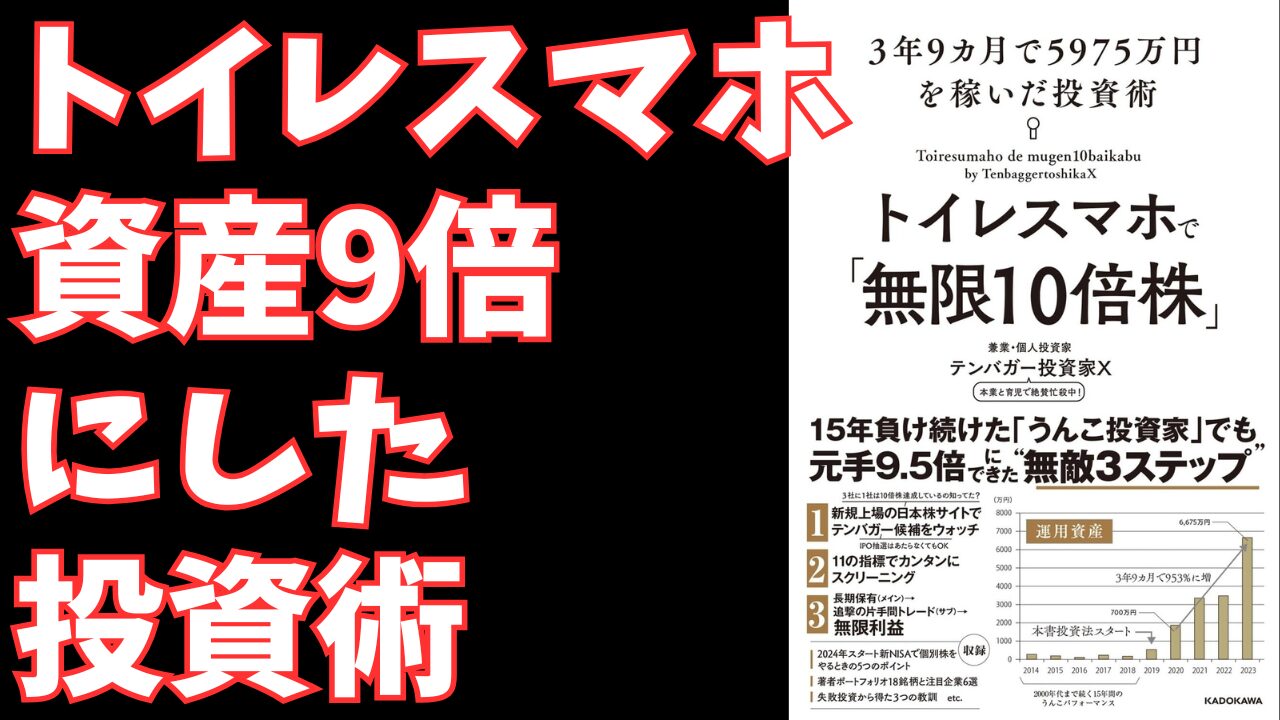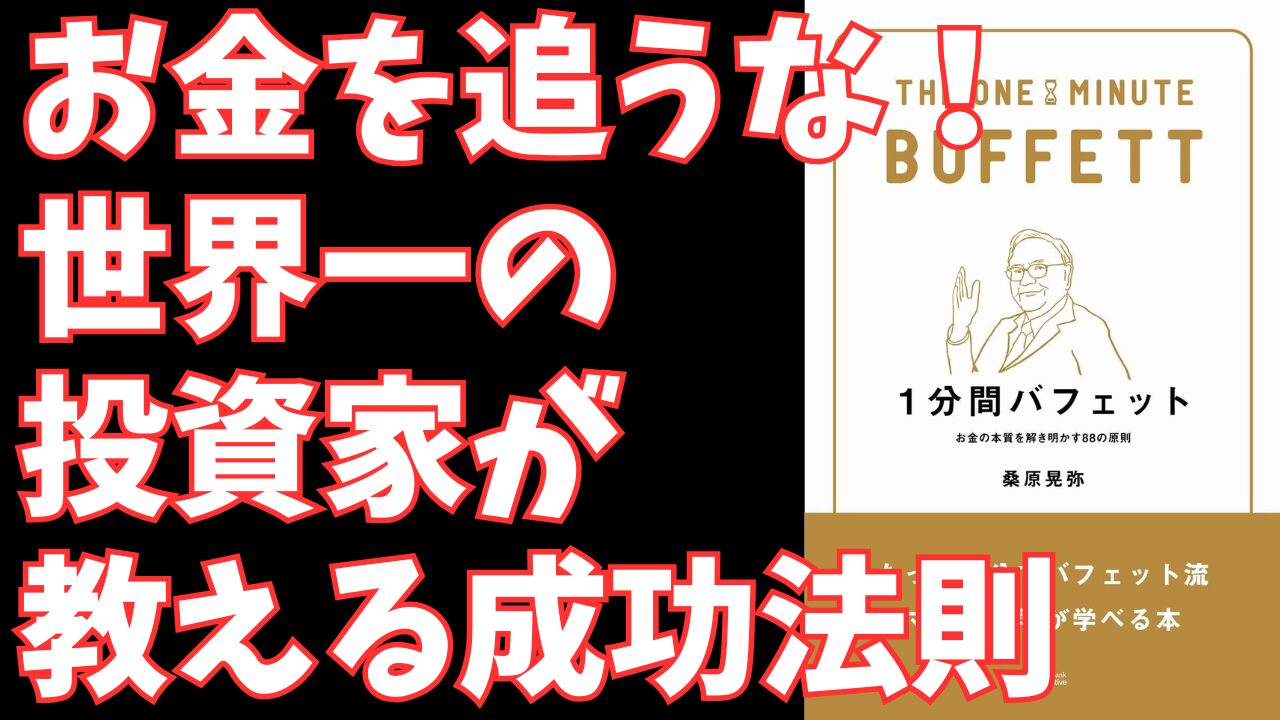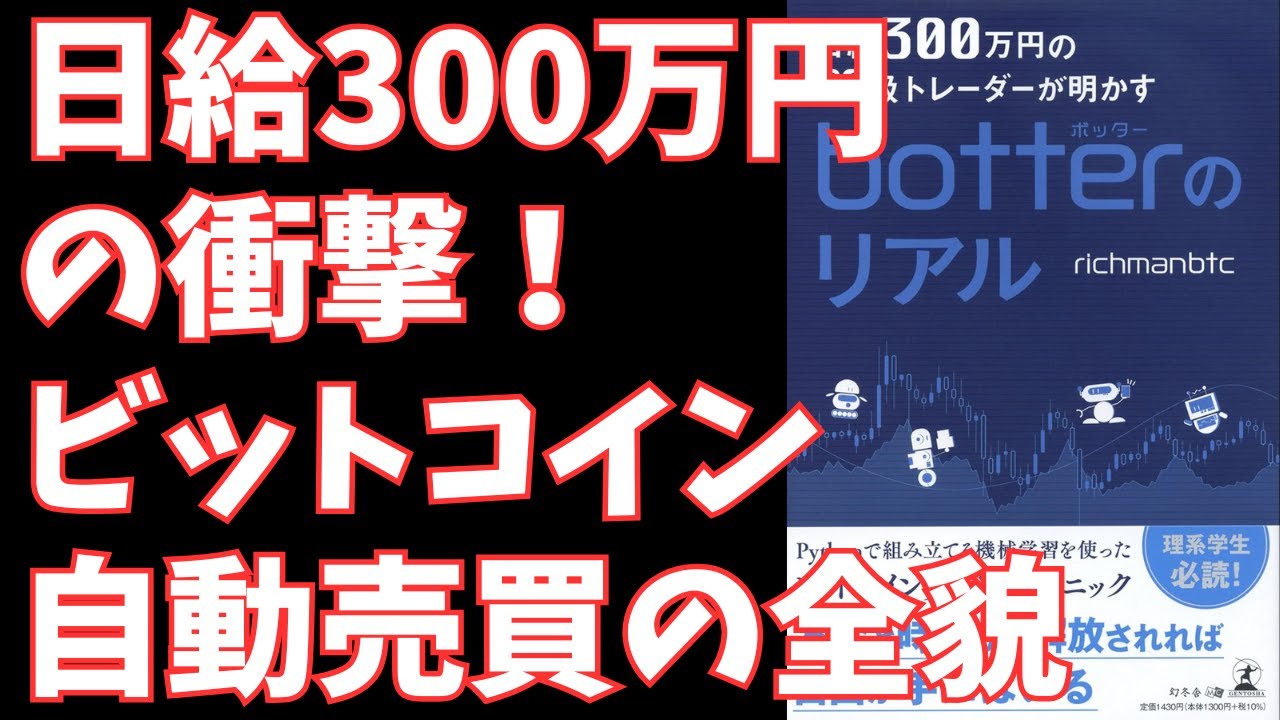『60歳からの知っておくべき経済学』髙橋洋一|財政破綻・増税・年金問題の嘘をデータで暴く
本書『60歳からの知っておくべき経済学』は、元大蔵・財務官僚であり数量政策学者の髙橋洋一氏が、データと経済学の常識に基づき、日本にはびこる経済の「俗論」を痛快に論破する一冊です。
多くの国民が信じ込まされている「日本の借金は1000兆円超で財政破綻寸前」「増え続ける社会保障費のために消費増税は不可欠」「少子高齢化で年金制度は崩壊する」といった言説が、いかに事実と異なるかを具体的なデータを用いて明らかにします。
この記事では、忙しいビジネスパーソンの方々が、メディアや政府の発表に惑わされず、日本経済の真の姿を理解し、ご自身の資産形成やビジネス判断に役立てられるよう、本書の核心部分を分かりやすく解説していきます。なぜ円安は日本にとって好ましいのか、なぜ財務省は国民を騙してまで増税したいのか。その全ての答えがここにあります。
本書の要点
- 日本の財政は危機的ではない
政府と日銀を一体と見なす「統合政府バランスシート」で分析すれば、日本は借金まみれどころか、むしろ資産超過の状態にあり、財政破綻の可能性は極めて低い。 - 消費増税は景気を悪化させる愚策
過去のデータが示す通り、消費増税は金融危機や大災害に匹敵するほどの経済的ダメージを与えてきた。景気回復には、増税ではなく大胆な「金融緩和」と「財政政策」が不可欠である。 - 年金制度は破綻しない
公的年金は、現役世代が高齢世代を支える「賦課方式」という保険制度であり、積立金が枯渇して破綻することはない。少子高齢化が進んでも、経済成長を達成すれば制度は維持可能である。 - 経済の真実はデータ分析でわかる
経済の議論で重要なのは「川を上り(歴史を遡り)、海を渡る(国際比較をする)」という視点。思い込みを捨て、散布図や相関係数といった客観的なデータでファクトを見抜く能力が求められる。 - 多くの経済政策は「財務省の利益」のために歪められている
財政破綻論を煽って増税し、予算配分権を強化することは、財務官僚の天下り先確保に繋がっている。国民の利益よりも省益を優先する「ザイム真理教」ともいえる体質が、日本経済の成長を妨げている。
はじめに:あなたの経済常識、本当に正しいですか?
「日本の借金は1200兆円を超え、国民一人当たり1000万円の借金を背負っている。このままでは財政は破綻してしまう」
「少子高齢化が進む日本では、社会保障費を賄うために消費増税は避けられない」
テレビや新聞で毎日のように繰り返されるこれらの言説を、あなたは信じて疑わなかったかもしれません。しかし、本書の著者である髙橋洋一氏は、これらが「すべて誤解だ」と断言します。
髙橋氏は、かつて大蔵省(現・財務省)に在籍し、小泉内閣・第一次安倍内閣ではブレーンとして活躍した、まさに政策決定の中枢にいた人物です。そんな彼が、データという動かぬ証拠を突きつけながら、日本の経済・財政に関する「七つの俗論」を一つひとつ丁寧に解き明かしていきます。
- 財政破綻論: 日本は借金で破綻するという主張
- 最低賃金引き上げ論: 最低賃金を上げれば景気が良くなるという主張
- 格差・貧困論: 構造改革で格差が広がったという主張
- 年金破綻論: 年金制度はいずれ崩壊するという主張
- 少子高齢化危機論: 少子高齢化が続くという主張
- 人口減少危機論: 人口が減ると日本経済はダメになるという主張
- 消費増税必要論: 社会保障のために消費増税が必要だという主張
なぜ、このような俗論が「常識」としてまかり通ってしまうのでしょうか。髙橋氏は、その背景には意図的に情報を操作し、国民を洗脳しようとする財務省の存在があると指摘します。
この記事を読めば、これまで常識だと思っていた経済ニュースの見方が180度変わるはずです。そして、何が真実で、何が嘘なのかを見抜くための「思考の武器」を手に入れることができるでしょう。
第1部:日本の財政は破綻しない!財務省が隠す「不都合な真実」
嘘だった「日本の借金1000兆円」のカラクリ
「国の借金が過去最高」というニュースを聞くたびに、日本の未来を憂いている方も多いのではないでしょうか。しかし、髙橋氏は「日本の財政は危機的ではない」と断言します。その根拠となるのが「統合政府バランスシート(BS)」という考え方です。
通常、財政破綻論者が持ち出すのは「政府」単体のBSの負債部分だけです。しかし、政府と日本銀行(日銀)は、会計上「親会社」と「子会社」の関係にあります。政府は日銀の株式の55%を保有し、役員任命権も持っているからです。
企業会計では、親会社と子会社の財務状況を連結して判断するのが常識です。それと同じように、国の財政も政府と日銀を一体の「統合政府」として、その連結BSで見るべきなのです。
では、統合政府のBSはどうなっているのでしょうか?
本書で示されている2021年度のデータでは、政府と日銀を連結すると、資産が約1613兆円、負債が約1546兆円となり、なんと約67兆円もの「資産超過」になるのです。これに加えて、目には見えない資産である「徴税権(将来税金を集める権利)」が約500兆円あるとされています。
財務省は、政府単体のBS(約700兆円の債務超過)だけを国民に見せて「借金が大変だ!」と危機を煽っていますが、子会社である日銀の資産を意図的に隠しているのです。これは、民間企業であれば粉飾決算と非難されてもおかしくない行為です。
国債が暴落しないことが「財政健全」の証拠
もし本当に日本が財政破綻の危機にあるのなら、日本国債は暴落し、金利は急騰するはずです。なぜなら、金利とは「信用リスク」を表す指標だからです。返済能力が危うい相手にお金を貸すとき、高い金利を要求するのは当然ですよね。
しかし、日本の10年物国債の金利は、世界的に見ても極めて低い水準(本書執筆時点で約0.6%)で推移しています。これは、世界中の投資家が「日本政府は絶対にデフォルト(債務不履行)しない」と確信し、絶大な信頼を置いている証拠に他なりません。
財務省がいくら「財政危機だ!」と叫んでも、市場は「日本の財政は超健全だ」と冷静に判断しているのです。
では、なぜ財務省は嘘をついてまで財政危機を煽るのでしょうか?その目的は、増税を正当化し、省庁の予算配分権(歳出権)を強化することにあります。予算を握ることで他の省庁に恩を売り、退官後の財務官僚の「天下り先」を確保するという、まさに省益のための壮大なプロパガンダなのです。
第2部:なぜ日本経済は成長しないのか?元凶は「緊縮財政」と「増税」
消費増税は経済にとって「大災害」レベルの愚策
「社会保障の財源確保のために、消費増税はやむを得ない」。そう考えている人も多いかもしれませんが、髙橋氏は「消費増税は経済を破壊する愚策だ」と強く批判します。
その証拠に、過去の日本のGDP成長率を見てみましょう。本書によれば、GDPが大きく落ち込んだワースト5のうち、2つが消費増税のタイミングと重なっています。
- ワースト3位:2014年4〜6月期(消費税8%へ引き上げ)→ 年率換算7.4%減
- ワースト4位:2019年10〜12月期(消費税10%へ引き上げ)→ 年率換算6.3%減
ちなみに、他のワースト記録はリーマンショック(①、②)と東日本大震災(⑤)です。つまり、消費増税は、世界的な金融危機や未曾有の大災害に匹敵するほどのダメージを日本経済に与えてきたのです。
災害は避けられませんが、増税は政治判断で避けることができます。経済成長を促し税収を自然に増やすのが正しい政策であるにもかかわらず、わざわざ経済を悪化させる増税を繰り返してきた。これが、日本の「失われた30年」の大きな原因の一つなのです。
経済成長の鍵は「金融緩和」と「財政政策」
では、どうすれば経済は成長するのでしょうか?髙橋氏は、「金融政策」と「財政政策」の両輪が必要だと説きます。
- 金融政策:日銀が世の中に出回るお金の量を調整すること。景気が悪い時は「金融緩和」でお金の量を増やし、金利を下げる。
- 財政政策:政府が税金や公共投資を調整すること。景気が悪い時は「財政出動」で公共投資を増やしたり、減税したりする。
特に重要なのは、まず「金融緩和」を先行させることです。金融緩和を行うと、金利が下がり、円安になります。円安になれば輸出企業の業績が向上し、株価も上昇します。そうして景気回復の土台ができたところで、効果的な財政出動を行えば、経済は大きく成長するのです。
実際に、アベノミクスではこの手法(大胆な金融緩和)によって、長年のデフレから脱却するきっかけを掴みました。しかし、財務省を中心とする「緊縮増税派」は、財政規律を理由に金融緩和に抵抗し、常に増税の機会をうかがっています。彼らの主張がいかに日本経済の足かせになってきたか、本書はデータで明らかにしています。
第3部:年金は破綻しない!社会保障の正しい考え方
「少子高齢化で年金制度は崩壊する」という大嘘
「私たちが年金をもらう頃には、制度は破綻しているのではないか…」
そんな不安を抱く現役世代は少なくありません。しかし、これもまた大きな誤解です。
日本の公的年金制度は、自分が支払った保険料を積み立てて将来受け取る「積立方式」ではありません。現役世代が支払った保険料を、その時々の高齢者への給付に充てる「賦課方式」という仕組みで運営されています。いわば、世代間の「仕送り」のようなものです。
この方式である限り、日本という国と国民が存在し続ける限り、年金制度が破綻することはありません。
「でも、少子高齢化で支える人が減ったら、財源が足りなくなるのでは?」という疑問が湧くでしょう。しかし、重要なのは支える「人数」だけではありません。「人数 × 一人当たりの所得」で考える必要があります。
たとえ現役世代の人口が減ったとしても、経済が成長して一人ひとりの所得が増えれば、年金制度は十分に維持できるのです。例えば、昔は7人で1人の高齢者を支えていたかもしれませんが、一人当たりの給料が当時の2倍になれば、3.5人で支えることが可能になります。
つまり、年金問題を解決する真の処方箋は、経済成長を達成することなのです。財務省は「社会保障費の増大」を理由に増税を主張しますが、本来は経済成長を阻害する増税こそが、将来の年金制度を危うくする行為だと言えるでしょう。
年金財政はバランスが取れている
本書では、厚生労働省が公表している「公的年金バランスシート」も紹介されています。これによると、将来にわたる年金の資産(将来の保険料収入+積立金など)と負債(将来の給付額)は、ほぼ2400兆円でバランスが取れています。
年金破綻論者が言うような「積立金が枯渇したら終わり」という話は、そもそも賦課方式である日本の年金制度には当てはまらない、全く的外れな批判なのです。
第4部:個人で資産を守り、形成するための経済学
本書はマクロ経済だけでなく、私たち個人の資産形成に役立つ知識も豊富に提供してくれます。
投資のプロが明かす「最強の金融商品」とは?
退職金を元手に投資を考えている方もいるでしょう。しかし、髙橋氏はFXや暗号資産といった短期的な投機には手を出すべきではないと警告します。3ヶ月以内の為替や株価の動きは、専門家でも予測不可能な「ランダムウォーク(酔歩)」だからです。
では、個人投資家にとって最も安全かつ有利な金融商品は何でしょうか?
髙橋氏が「最強の金融商品」として推奨するのが「国債」、特に「個人向け国債 変動金利型10年満期」です。
その理由は以下の通りです。
- 元本保証:国が破綻しない限り、元本割れのリスクがない。
- 金利上昇に対応:変動金利型なので、今後金利が上昇する局面でも、受け取る利息が増える。
- 換金のしやすさ:発行から1年経てば、いつでも国が額面価格で買い取ってくれる。
金融機関があまり積極的に勧めてこないのは、手数料が安く儲からないからですが、それだけ個人にとって有利な商品だということの裏返しでもあります。
民間保険や持ち家のリスクを正しく理解する
日本人は保険好きと言われますが、髙橋氏は多くの民間保険、特に貯蓄性のある「変額保険」などには懐疑的です。手数料が高く、保障と投資信託が組み合わさった複雑な商品は、金融機関が儲かるだけで、契約者にとっては不利な場合が多いと指摘します。
また、「持ち家か賃貸か」という永遠のテーマについても、「資産がないなら賃貸のほうがいい」と断言します。数千万円もの住宅ローンは、金利変動や不動産価格下落のリスク、災害リスクなどを抱え込むことになるからです。住むためだけであれば、リスクの少ない賃貸の方が合理的だという視点は、マイホーム購入を検討している人にとって一考の価値があるでしょう。
第5部:経済の真実を見抜く「思考の武器」を手に入れる
本書の最大の魅力は、単に経済の知識を教えるだけでなく、経済の真実を自力で見抜くための「考え方」を示してくれる点にあります。
騙されないための最強ツール「相関係数」
髙橋氏が最も重要視するのが、思い込みを捨て、データに基づいて定量的に考える姿勢です。そして、そのための最強のツールが「相関係数」と「散布図」です。
相関係数とは、2つの要素(例えば「お金の伸び率」と「GDP成長率」)がどれくらい強い関係にあるかを-1から+1の数値で示す指標です。
本書では、この手法を使って様々な俗論を論破していきます。
例えば、世界各国の「お金の伸び率」を横軸に、「名目GDP成長率」を縦軸にとって散布図を作成すると、両者には非常に強い正の相関(相関係数0.94など)があることが分かります。これは、「世の中に出回るお金の量を増やせば経済は成長する」という経済学の常識を視覚的に証明するものです。
この分析手法は、Excelなどを使えば誰でも簡単に行うことができます。一つの国のデータだけを見て議論するのではなく、国際比較のデータで散布図を描いてみる。この習慣を身につけるだけで、メディアの偏向報道やエコノミストの的外れな予測に騙されることはなくなるでしょう。
まとめ:経済リテラシーを身につけ、未来を生き抜く
『60歳からの知っておくべき経済学』は、タイトルに「60歳から」とありますが、むしろ現役で働くすべてのビジネスパーソンにこそ読んでほしい一冊です。
本書を読むことで、私たちは以下の重要な視点を得ることができます。
- 国の政策の裏側を読み解く力:増税や社会保障制度改革のニュースの裏に、どのような意図(特に財務省の思惑)が隠されているのかを見抜けるようになります。
- メディアリテラシーの向上:テレビや新聞が垂れ流す情報を鵜呑みにせず、データに基づいてファクトチェックする習慣が身につきます。
- 合理的な資産形成:感情やイメージに流されず、リスクとリターンを正しく評価し、自分に合った資産運用を選択できるようになります。
- ビジネスにおける洞察力:会計知識(BS/PL)の重要性を理解し、自社や取引先の経営状況を的確に把握する力が養われます。
変化の激しい時代を生き抜くために、専門家やメディアの言葉をただ信じるのではなく、自らの頭で考え、判断する力が不可欠です。本書は、そのための最強の「武器」となる経済リテラシーを与えてくれます。ぜひ一度手に取って、目からウロコの体験をしてみてください。