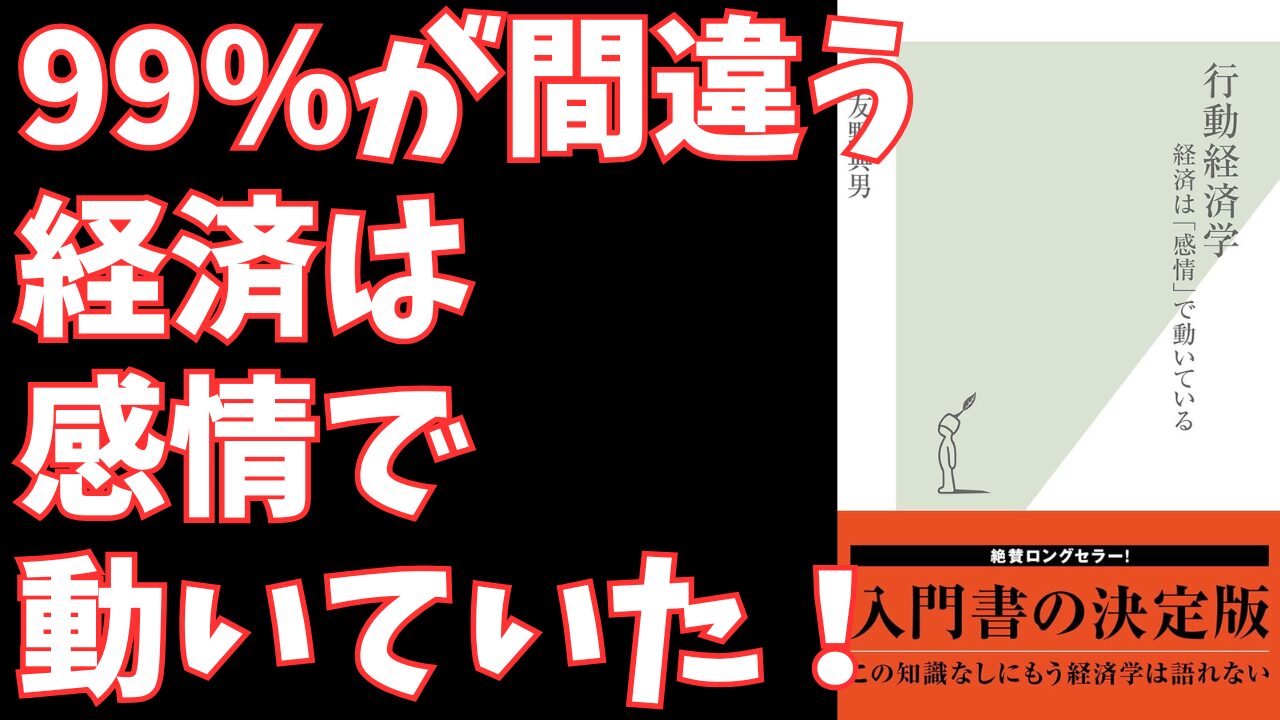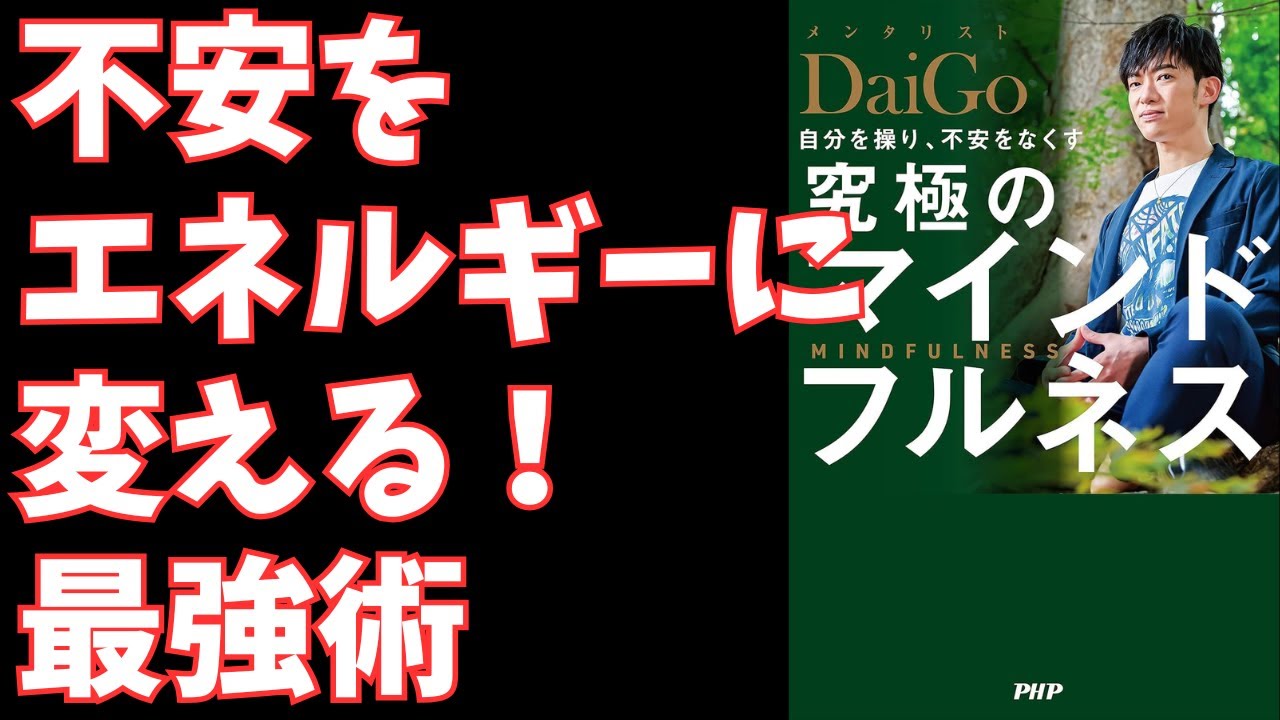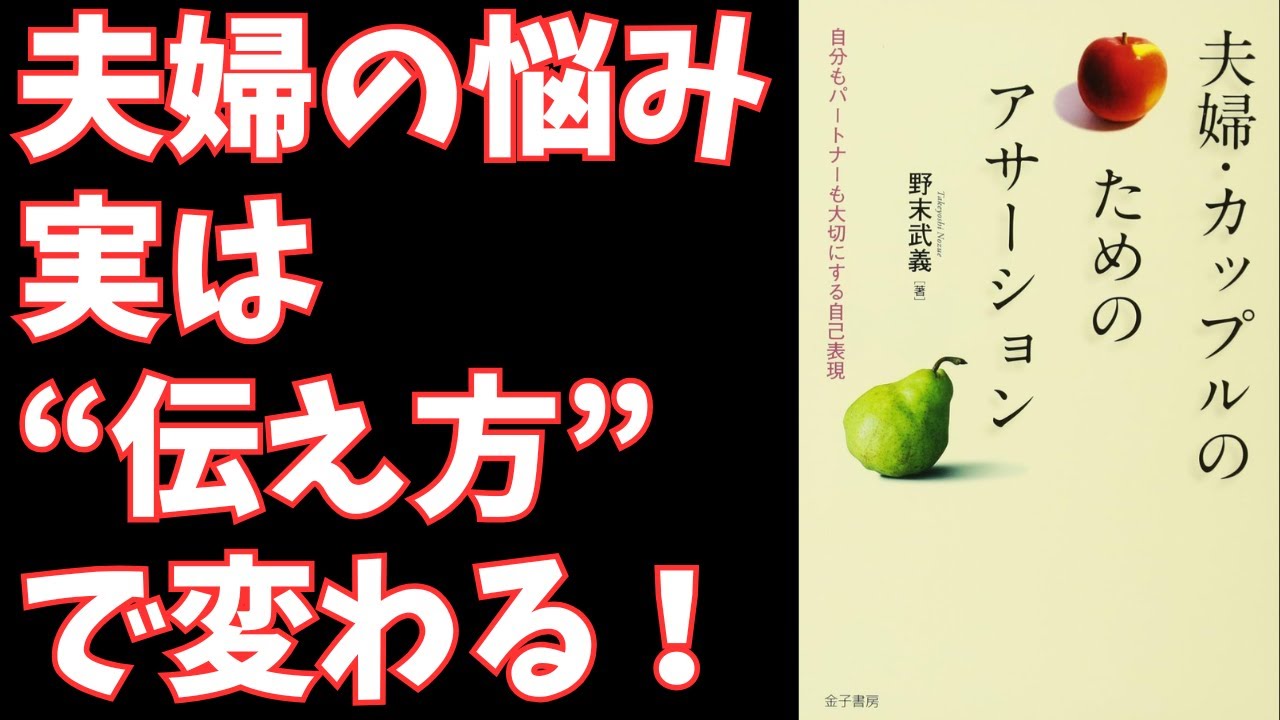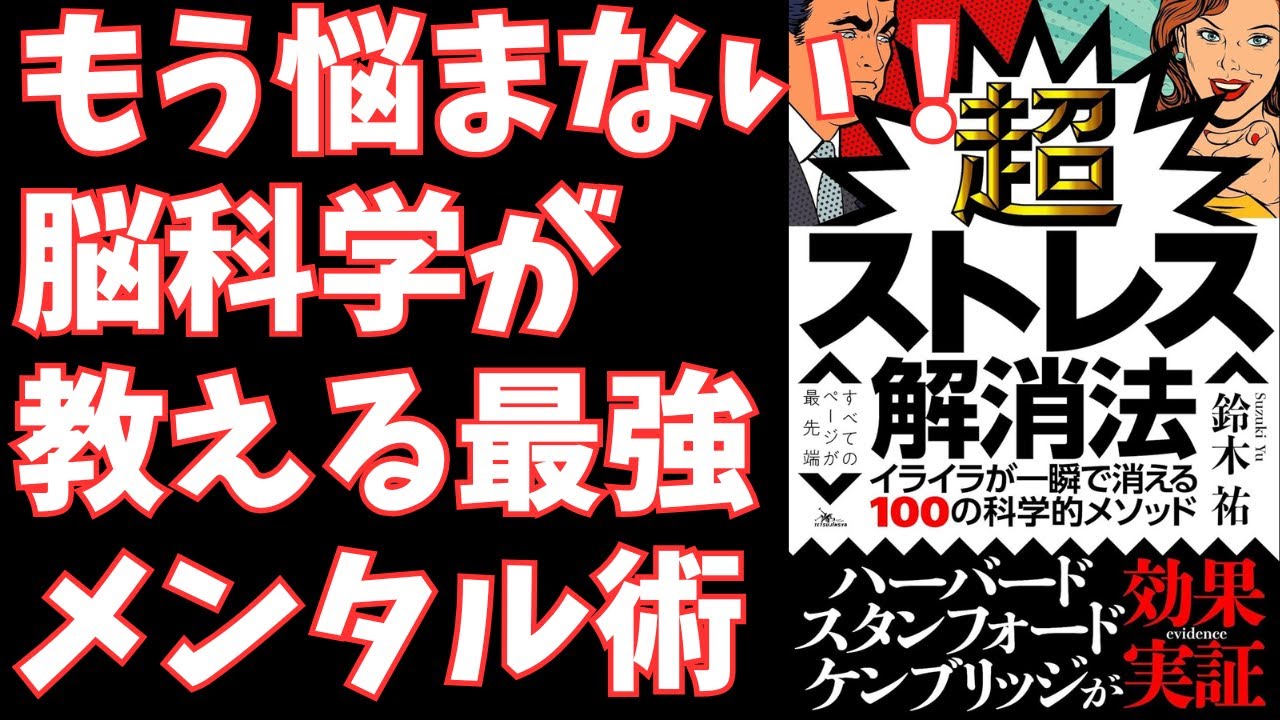『悩みどころと逃げどころ』ちきりん×ウメハラに学ぶ、キャリアを再定義する思考法
本書『悩みどころと逃げどころ』は、社会派ブロガーの「ちきりん」氏と、日本人初のプロゲーマーである「梅原大吾(ウメハラ)」氏という、全く異なるバックグラウンドを持つ二人が、「学歴」「競争」「人生」といった普遍的なテーマについて交わした100時間にも及ぶ対談をまとめた一冊です。
「学校エリート」として社会の王道を歩んできたちきりん氏と、学校では眠り続け、ゲームの世界で実力のみでのし上がってきたウメハラ氏。二人の対話は、私たちが無意識に囚われている「学校的価値観」の正体を浮き彫りにし、変化の激しい現代社会を生き抜くための新しい思考のOSを提供してくれます。
この記事では、本書の中から特に忙しいビジネスパーソンに響くであろうエッセンスを抽出し、具体的な事例を交えながら、明日からの仕事やキャリア観に活かせる学びをお伝えします。
本書の要点
- 「いい大学→いい会社→いい人生」という学校的価値観は崩壊している。 変化の激しい時代において、従順であることや決められた正解をこなす能力は、もはや成功を保証しない。
- 短期的な「結果」よりも、長期的に勝ち続けるための「プロセス」が重要。 安易な方法で目先の勝利を掴むのではなく、試行錯誤を続ける誠実な戦い方こそが、真の評価と成長につながる。
- とことん「あがく」経験が、自分だけの「いい人生」への納得感を生む。 回り道や一見無駄に見える経験こそが、自分の器を知り、進むべき道を確信させてくれる。
- 「逃げる」ことは敗北ではなく、自分が勝てる場所を探すための積極的な戦略である。 固執を手放し、自分の強みが活きるフィールドを見極める勇気が、新たな可能性を切り拓く。
- 人生のプロフェッショナルとは「人生の楽しみ方」を自らの生き様で示せる人である。 勝ち負けだけでなく、どうすればより豊かに、面白く生きられるかを追求し、提示することが価値となる。
はじめに:あなたのOSは「学校」のままアップデートされていますか?
「いい大学に入り、いい会社に就職すれば、いい人生が送れる」
かつて、多くの人が信じて疑わなかったこの成功モデル。あなたも心のどこかで、この価値観を引きずってはいないでしょうか。
本書『悩みどころと逃げどころ』は、この「学校的価値観」という、私たちの思考に深く根付いたOSに、根源的な問いを投げかけます。
著者は、社会派ブロガーとして絶大な影響力を持つちきりん氏と、日本人初のプロ格闘ゲーマーとして世界に名を馳せる梅原大吾(ウメハラ)氏。
かたや、いい大学から大企業へと進んだ「学校エリート」。かたや、学校の授業は「寝るところ」と割り切り、ゲームセンターで実力だけを頼りに生きてきたアウトロー。
このあまりにも対照的な二人の対話が、なぜこれほどまでに私たちの心を揺さぶるのでしょうか。それは、二人がそれぞれの経験を通して、「学校では教わらなかった、社会を生き抜くための真実」を掴み取っているからです。
本記事では、この刺激的な一冊から、多忙な日々を送るビジネスパーソンが自らのキャリアと人生を見つめ直すための、重要な視点を紐解いていきます。
学歴は必要か?二人の全く異なる答え
本書の議論の出発点となるのが「学校へ行く意味」です。このテーマに対し、二人の意見は真っ向から対立します。
ウメハラが語る「学歴差別の厳しい現実」
学校嫌いで、授業中はほとんど寝て過ごしたというウメハラ氏。そんな彼が、「もし若者にアドバイスするなら『できるだけ行っておいたほうがいい』」と語るのは、非常に示唆に富んでいます。
その理由は、彼自身が経験した学歴差別の厳しい現実にありました。
プロゲーマーとして身を立てる前、アルバイトをしていた時期のウメハラ氏は、学歴がないというだけで、屈辱的な扱いを受けたと言います。
たとえばレジからお金がなくなった時、学歴のない奴が真っ先に疑われるんですよ。わかります?
本社まで呼ばれましたからね。「レジ触った?」「監視カメラつけてるから、調べりゃわかるんだよ」とまで言われて。
これは衝撃的なエピソードです。仕事の能力以前に、「学歴」というフィルターを通して人格まで判断されてしまう。面と向かって罵倒されるのではなく、醸し出す空気で見下される。その経験から、ウメハラ氏は「実力主義の時代ですなんてキレイごとは言えない」と断言します。
大企業への就職という入り口だけでなく、日常の些細な場面にまで存在する学歴という壁。これは、エリートコースを歩んできた人間には想像しにくい、リアルな社会の側面です。
ちきりんが警鐘を鳴らす「学校エリート」の落とし穴
一方、国立大学から証券会社、外資系企業へと進んだちきりん氏は、異なる視点から学校教育の危うさを指摘します。
彼女が見てきたのは、「ちゃんと勉強したのにこんな悲惨なことになるとは知らなかった」という人々でした。
従順ないい子が、「学校でまじめに頑張ってれば一生安泰だぞ」って言われてそのとおりやってきたのに、40歳になっていきなりハシゴをはずされ、食べていけなくなりましたって、ヒドくないですか?
「先生の言うことを聞く」「テストで良い点を取る」といった学校での成功体験は、「自分のア-タマで考える力」を養う機会を奪います。その結果、倒産やリストラといった予期せぬ事態に直面した時、どう行動すればいいかわからなくなってしまうのです。
ちきりん氏は、「大学さえ出ておけばなんとかなる」という考え方こそが有害だと指摘します。その考えに毒されると、本来であれば別の道で才能を発揮できたかもしれない人までが、借金をしてまで大学に進学し、結果的に自分のやりたいことを見失ってしまう、というのです。
学歴がないことで選択肢を奪われる人生と、学歴を得たがために自分の意思で選択できなくなる人生。どちらも「いい人生」とは言えないでしょう。本書は、この二項対立を通して、私たちが「学ぶ」ことの本当の意味を問い直してきます。
結果かプロセスか?ビジネスパーソンが陥りがちな罠
「ビジネスは結果がすべてだ」。これは多くのビジネスパーソンにとって共通認識かもしれません。しかし、本書における二人の対話は、その言葉の裏にある深い意味を明らかにします。
「結果が全て」は本当か?ウメハラがゲームセンターで学んだこと
勝負の世界に生きるウメハラ氏が「本当に大事なのは結果に至るプロセスなんですよ」と語る場面は、本書のハイライトの一つです。
これは決して、負け惜しみの綺麗事ではありません。彼がその哲学を学んだのは、ゲームセンターという実力主義のコミュニティでした。
かつてのウメハラ氏は、勝つためだけに、誰でも簡単に扱える「強いキャラクター」ばかりを使っていました。連戦連勝を重ねるものの、ゲームセンターの常連たちからの評価は決して高くありませんでした。
ある日、常連客から「それはもうわかったから、ちょっと使うキャラクターを変えてみたら?」と、操作は難しいが奥深いキャラクターを勧められます。
そのキャラクターを使い始めた当初は、負け続けました。しかし、不思議なことに、負けているにもかかわらず、周りのプレイヤーから話しかけられるようになり、コミュニティに受け入れられていったのです。
この経験から、彼は「たとえ勝負事であっても、ただ勝てばいいわけじゃない」ということを学びます。
- 簡単なキャラでの勝利: 短期的には効率が良いが、思考が停止し、成長が止まる。対策もされやすく、長期的には勝てなくなっていく。
- 難しいキャラでの挑戦: 試行錯誤と思考力が求められる。短期的な勝率は下がるが、それが思考力を鍛え、長期的に勝ち続ける力、そして何より他者からの尊敬に繋がる。
これはビジネスの世界にも通じます。目先の利益や効率だけを追い求め、流行りの手法や安易な方法に飛びつくのか。それとも、時間はかかっても、自社の強みを活かした独自の価値提供を追求し、顧客や社会から信頼される存在を目指すのか。ウメハラ氏のエピソードは、後者の重要性を雄弁に物語っています。
「頑張ってますアピール」はなぜ評価されないのか
一方で、ちきりん氏は「結果を出せない人に限ってプロセスに逃げがち」という現実も指摘します。
彼女が若手社員だった頃、徹夜で仕上げた資料を、あえて疲れた顔で上司に提出したことがありました。その頑張りを評価してもらいたかったのです。しかし、上司の反応は冷ややかでした。
「その顔なに? もしかして徹夜して頑張ったことをアピールしたいの? 悪いけどここは学校じゃないから、そんなことには何の意味もないよ。資料の出来だけが問題なんだから、おまえが徹夜したかどうかなんて何の関係もないよ」
この一言で、彼女は自分が「頑張ってさえいれば褒めてもらえる」という学校的価値観に染まっていたことに気づきます。
ウメハラ氏の言う「プロセス」と、ちきりん氏が否定する「プロセス」。この違いはどこにあるのでしょうか。
それは、他者評価のためだけのプロセスか、自己の成長と本質的な価値創造に繋がるプロセスか、という点にあります。ウメハラ氏が重視するのは、思考を深め、新たな戦い方を生み出すための試行錯誤という、まさに成長に直結するプロセスです。一方、徹夜アピールは、成果物の価値とは無関係な自己満足に過ぎません。
ビジネスの世界で求められるのは、結果に結びつく、質の高いプロセスなのです。
「いい人生」の定義とは?自分だけの答えを見つける方法
本書の核心は、「いい人生とは何か、それはどうすれば手に入るのか」という問いにあります。ここでも二人のアプローチは対照的でありながら、本質的な部分で繋がっていきます。
「あがく」ことの本当の意味―回り道こそが納得感を生む
ウメハラ氏は、「とことんまで頑張って、あがいてあがいてあがき尽くす」ことの重要性を説きます。
彼は17歳で世界一になった後も、「ゲームだけで食べていけるのか」という不安や、「もっと広い世界があるのではないか」という葛藤から、一度ゲームの世界を離れ、介護や麻雀の世界に身を置きました。
その「あがき」の期間を通して、彼は「他の分野での自分の器はこんなものか」と知り、「やはり自分には格闘ゲームしかない」という揺-るぎない納得感を得たと言います。
そういう、本気出して真剣にあがいた経験を経ないと、このレベルの納得感は得られない。
もし最初からプロゲーマーへの道が用意されていたら、その道を選ばなかったかもしれない、と彼は言います。それは、あらかじめ上限を決められることなく、自分の可能性をとことん試したかったからです。
ビジネスパーソンにとっても、これは重要な視点です。キャリアプラン通りに進むことだけが正解ではありません。時には畑違いの部署への異動や、一見キャリアと無関係な副業への挑戦など、意図的な「あがき」や「回り道」が、最終的に「これこそが自分の道だ」という強い確信に繋がるのです。
「つらかったら逃げてもいい」ちきりん流・戦略的キャリア構築
ウメハラ氏のストイックな「あがき」に対し、ちきりん氏は「つらかったら逃げる」という、一見正反対の戦略を提示します。
しかし、彼女の言う「逃げる」は、単なる敗走や諦めではありません。
勝てないとわかったら、そんなところに居続けず、勝てる世界を探しに行きましょう
これは、自分の強みが活かせない土俵で無駄な戦いを続けるのではなく、自分が最も輝ける場所、勝てる市場を見つけ出すための、極めて戦略的な移動を意味します。
彼女自身、ブログという世界の中で、誰も競争相手がいない「自分にしか実現できない世界」に逃げ込んだからこそ、今の地位を築けたと分析します。
ウメハラ氏が「一つの道を深く掘る」ことで納得感を得たのに対し、ちきりん氏は「複数の道を渡り歩く」ことで自分だけの場所を見つけました。アプローチは違えど、両者に共通するのは、与えられた場所でただ待つのではなく、自らの意思で居場所を能動的に探し、作り出している点です。
「石の上にも三年」という言葉に縛られ、今の仕事や環境に違和感を抱えながらも動けずにいる人にとって、ちきりん氏の「戦略的な逃げ」という発想は、心を軽くし、次の一歩を踏み出す勇気を与えてくれるでしょう。
学校的価値観から脱却し、自分らしく生きるために
本書を通して、二人は「学校的価値観」の呪縛から自由になることの重要性を繰り返し訴えます。
あなたを縛る「思考停止の呪文」に気づいていますか?
「家族のため」「親のため」「もういい年だから」
こうした言葉を、自分の決断の言い訳に使ってしまっていないでしょうか。ちきりん氏は、これらの言葉を「思考停止を正当化できる呪文」と呼びます。
この呪文を唱えることで、私たちは「自分は本当は何をしたいのか」という最も重要な問いと向き合うことから逃げてしまいます。
もちろん、家族や責任が大切なのは言うまでもありません。しかし、それを理由に思考を停止させ、他人の価値観や「既製品のいい人生」に自分を当てはめてしまうと、本当の意味での納得感は得られません。
大切なのは、あらゆる制約条件を踏まえた上で、誠実に自分自身と向き合い、考え尽くし、自己決定すること。 そのプロセスこそが、「いい人生」の土台となるのです。
プロの仕事とは「楽しみ方を提示する」こと
対談の終盤、ウメハラ氏はプロゲーマーの役割について、非常に本質的な定義を語ります。
僕は、プロゲーマーの仕事っていうのは、そのゲームの楽しい遊び方を発掘して、ファンの人にプレーを通してそれを伝えることだと思ってるんです。「こうやって遊ぶとこのゲームは今までよりおもしろくなるよ」って。
単に勝つことや、開発者の設計ミスを見つけて利用するようなプレイではなく、そのゲームが持つ本来の面白さや可能性を提示し、ファンをワクワクさせることこそがプロの仕事だ、と。
この言葉に、ちきりん氏は「人生も同じだ」と応じます。
大人の、そして教育者の本来の役割は、「こうやったら人生の勝負に勝てますよ」という攻略法を教えることではありません。「こうやって過ごすと、人生はサイコーにおもしろいんだぜ」と、自らの生き方をもって示すことなのです。
あなたの仕事は、顧客や社会に対して、どんな「楽しみ方」や「新しい豊かさ」を提示できているでしょうか。この問いは、日々の業務の意味を再発見するきっかけになるはずです。
まとめ:あなたの「悩みどころ」と「逃げどころ」はどこですか?
『悩みどころと逃げどころ』は、単なる成功法則を提示する本ではありません。正反対の二人の生き様を通して、読者一人ひとりが自分自身の「悩みどころ」と向き合い、「逃げどころ」、すなわち自分が輝ける場所を見つけるためのコンパスとなる一冊です。
私たちは皆、多かれ少なかれ「学校的価値観」に影響されて生きています。しかし、その価値観が絶対のものではないと知ること、そして自分だけの物差しを持つことの重要性に気づかせてくれます。
結果が出ずに悩んでいる時、キャリアの岐路に立たされた時、あるいは今の人生に漠然とした違和感を抱いている時。この本はきっと、あなたに新たな視点と、もう一度「あがいてみよう」と思える勇気を与えてくれるでしょう。