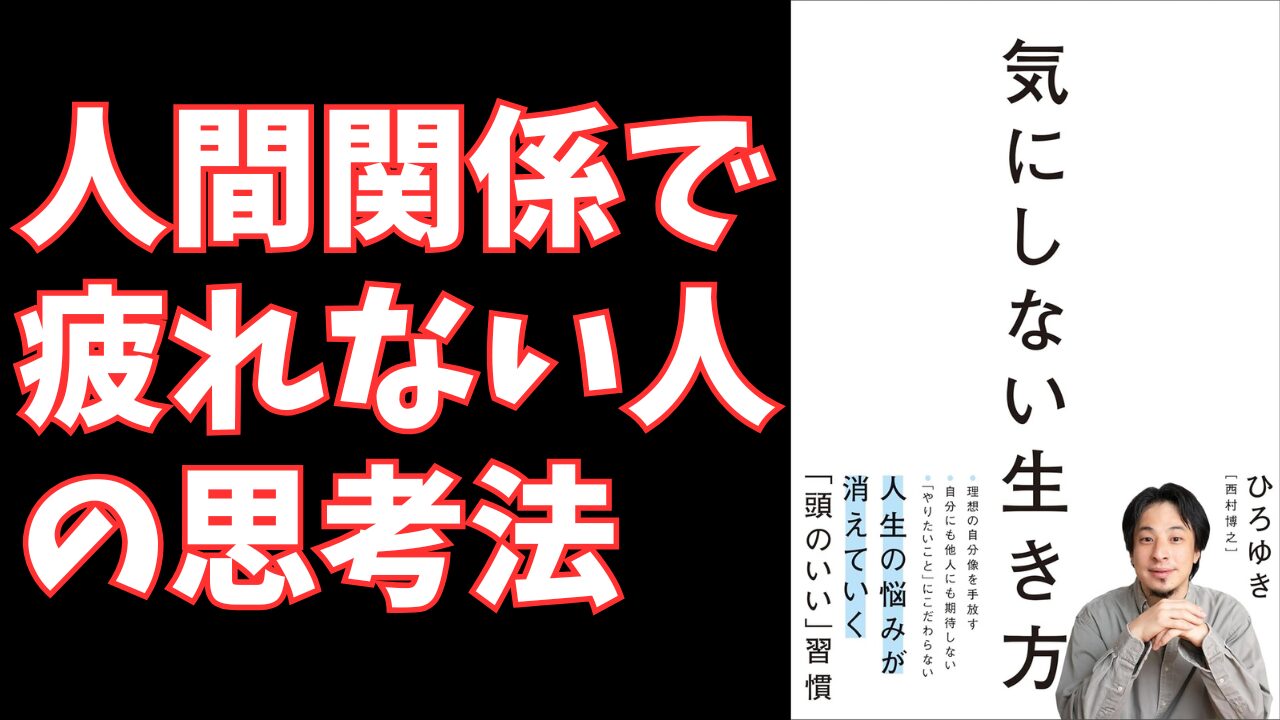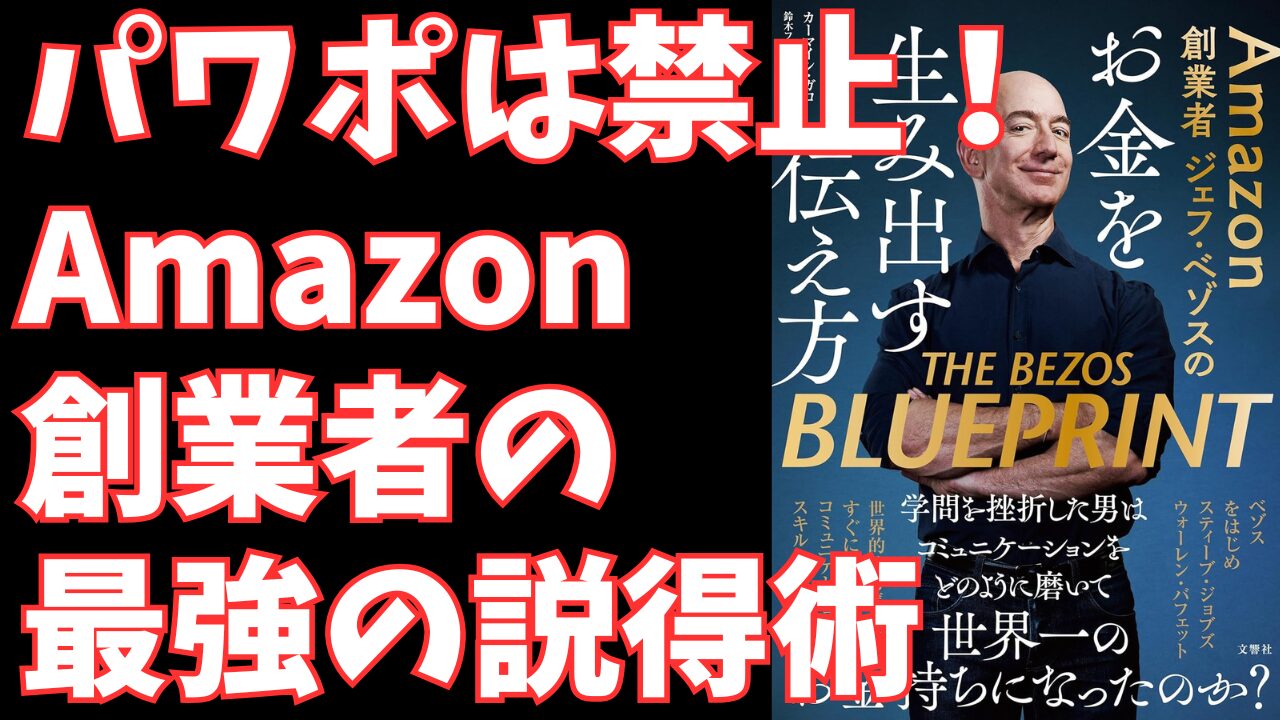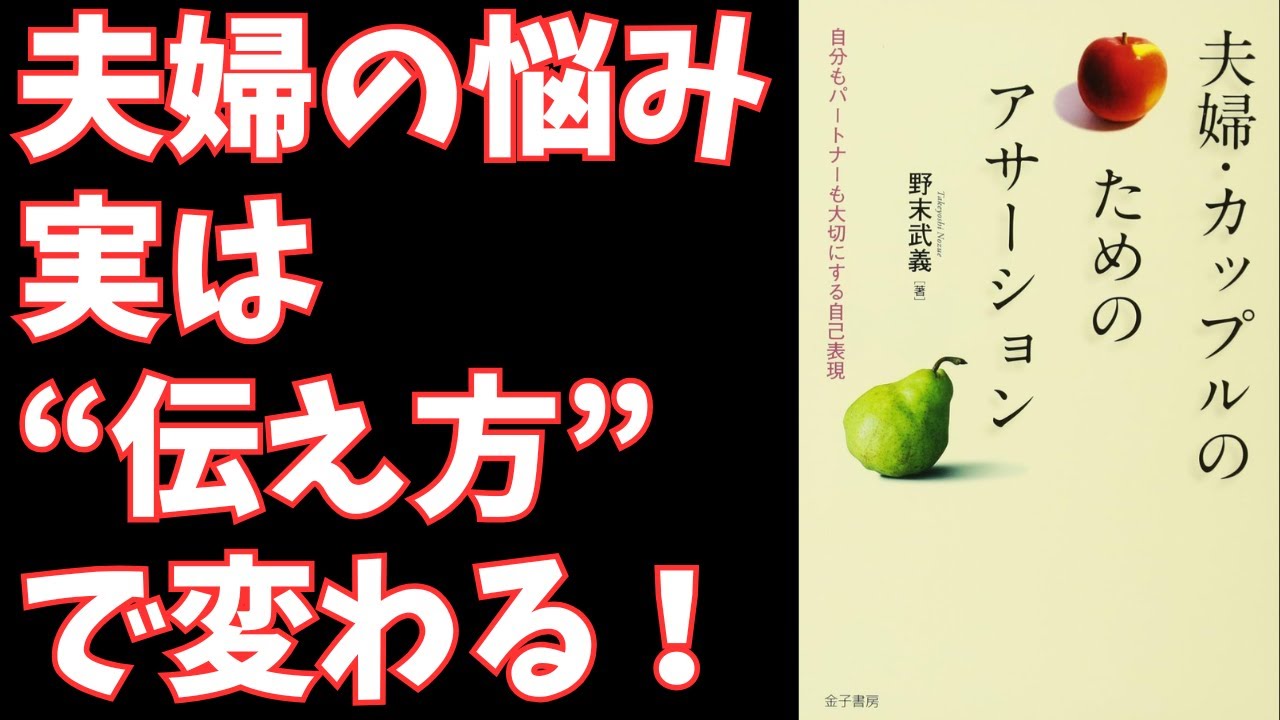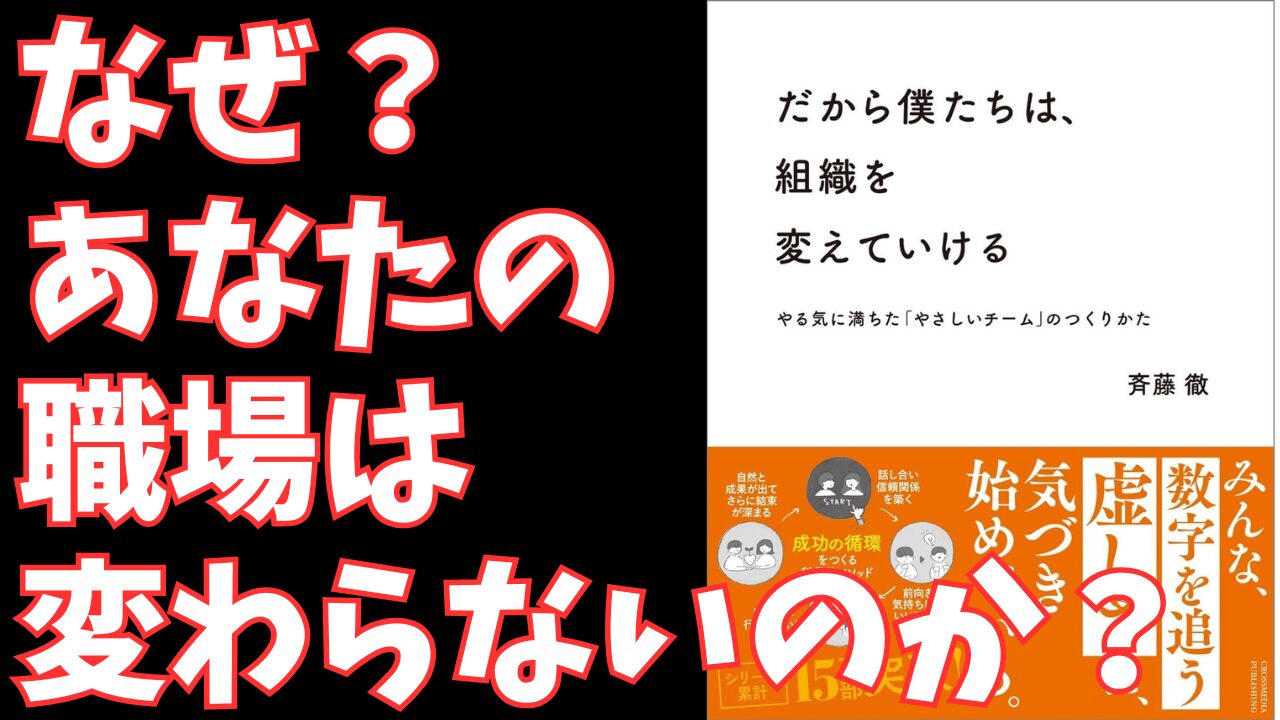天才IT大臣オードリー・タンに学ぶ、複雑な問題をシンプルに解決する思考法|4ステップと15のキーワード
この記事では、台湾のデジタル担当政務委員(IT大臣)として世界的に知られるオードリー・タン氏の著書『天才IT大臣オードリー・タンが初めて明かす 問題解決の4ステップと15キーワード』を基に、彼女の卓越した問題解決の思考法を解説します。
本書で提示されるのは、「問題と向き合う」「問題を受け入れる」「問題に対処する」「問題を手放す」という4つのステップと、それらを構成する15のキーワードです。
コロナ禍での「マスクマップ」開発など、数々の難題を解決してきた彼女の思考の根底には、「すべての人の側に立つ」という徹底した対話の姿勢と、オープンで透明なアプローチがあります。
この記事を読むことで、多忙なビジネスパーソンが直面する複雑な課題に対し、どのように向き合い、シンプルかつ効果的に解決していくかのヒントを得ることができるでしょう。
本書の要点
- 問題解決の4ステップ:すべての問題は「向き合い、受け入れ、対処して、手放す」という4つのプロセスで捉えることで、冷静かつ建設的に取り組むことができる。
- 対話とエンパシーの重視:対立を避け、「すべての人の側に立つ」姿勢で徹底的に「傾聴」する。相手の経験に基づき理解しようとする「エンパシー」が、あらゆる問題解決の出発点となる。
- 多重視点と脱ゼロサム思考:一つの視点に固執せず、多様な意見を自分の中に積極的に取り込む「多重視点」を持つことで、どちらかが得をすればもう一方が損をする「ゼロサム思考」から脱却できる。
- 透明性と集合知の活用:情報は徹底的に「透明」にし、オープンにすることで、多様な知恵を集める「集合知」が生まれる。マスクマップやタピオカミルクティーのように、誰もが参加できる共創の場を作る。
- 「競争からの脱却」と共創:個人間の競争は不要であり、重要なのはチーム全体で価値を創り出すこと。自分の不完全さを認め、他者と補い合うことで、より大きな成果を生み出す。
はじめに:なぜ今、オードリー・タンの思考法が求められるのか?
現代のビジネス環境は、予測不能な変化と複雑な課題に満ちています。そんな中、台湾のデジタル担当政務委員であるオードリー・タン氏が示す問題解決のアプローチは、世界中から大きな注目を集めています。
彼女は、新型コロナウイルスのパンデミックにおいて、官民連携で「マスクマップ」を迅速に開発し、市民の不安を解消したことで一躍有名になりました。また、Uberのような新しいサービスを巡る社会の対立を、「vTaiwan」というオンラインプラットフォームを通じて対話の力で解決に導くなど、その実績は枚挙にいとまがありません。
天才プログラマーとして知られる彼女ですが、その力の源泉は単なるITスキルではありません。彼女の思考の根底には、深い人間理解と、あらゆる立場の人々を尊重する哲学があります。
本書で明かされるのは、彼女が日々実践している「4つのステップ」と「15のキーワード」です。これらは、国家レベルの大きな問題から、私たちの職場や個人の悩みまで、あらゆる課題に応用可能な普遍的なフレームワークと言えるでしょう。
この記事では、本書のエッセンスを抽出し、忙しいビジネスパーソンが明日からの仕事に活かせるよう、具体的な事例を交えながら分かりやすく解説していきます。
STEP1 問題と向き合う:解決の鍵は「傾聴」と「エンパシー」
問題が発生したとき、私たちはつい性急な判断を下したり、自分の意見を押し通そうとしたりしがちです。しかし、オードリー・タン氏は、問題解決の最初のステップとして、まず徹底的に「向き合う」ことの重要性を説きます。
すべての人の側に立って対話する「解決思考」
オードリー氏の問題解決の根幹をなすのが、「すべての人の側に立つ(take all the sides)」という姿勢です。これは、賛成者、反対者はもちろん、まだ声を上げていない人々の立場にも身を置き、ひたすら話を聴くことから始まります。
彼女は、「問題を見つける一番簡単な方法は、その問題に実際に直面した人の話をよく聴くことだ」と語ります。
この姿勢が具体的に現れたのが、Uberの導入を巡る論争でした。タクシー業界とUber、そして専門家や政府関係者といった利害が対立する人々が、オンラインプラットフォーム「vTaiwan」上で議論を交わしました。そこでは、すべての発言が公開され、誰もが後から議論に参加できる「安全な空間」が確保されました。誰かが発言を独占することなく、対話を通じて意思疎通を図ることで、最終的に社会的な合意形成へと繋がったのです。
ビジネスの現場でも、対立する意見を無理に一つにまとめようとするのではなく、まずはそれぞれの立場や意見をすべてテーブルの上に広げ、透明な場で対話することから始めるのが重要です。
「エンパシー」は同情ではなく、経験に基づく理解
「傾聴」を実践する上で欠かせないのが「エンパシー」です。しかし、オードリー氏の言うエンパシーは、単なる同情(シンパシー)とは異なります。
「エンパシー」とは、相手のコンディションがよくないから、自分もそのよくない状態に合わせるのではなく、自分自身の経験に照らして相手を理解しようと試みることです。
例えば、相手が「昨晩はよく眠れなかった」と言ったとき、「大変でしたね」と同情するだけでなく、「自分が睡眠不足だったら、相手にはゆっくり話してほしいだろうな」と自分の経験に基づいて想像し、行動に移すことがエンパシーです。
このエンパシーを養うための簡単なトレーニングとして、彼女は「10分間の傾聴練習」を提案しています。友人や家族とペアになり、「5分間は絶対に相手の話に口を挟まずに聴き、その後5分間で自分が聴いた内容を説明する」というものです。これを実践するだけで、早急な判断をせず、相手の真意を深く理解する対話力が身につくと言います。
会議や1on1ミーティングの場で、まずは相手の話を遮らずに最後まで聴き、その背景にある経験や感情を想像してみる。この小さな習慣が、チームの信頼関係を深め、より良い解決策を生み出す土壌となるのです。
STEP2 問題を受け入れる:「不完全主義」と「集合知」の力
すべての意見を聴き、問題と向き合った次に必要なのは、それらを「受け入れる」ことです。ここでのポイントは、完璧な唯一の正解を求めるのではなく、不完全さを受け入れ、みんなの知恵を組み合わせることです。
天才ではない。「思想の運び手」としての不完全主義
「IQ180の天才」と称されるオードリー氏ですが、彼女自身はその言葉を「身長です」とユーモアでかわし、自分は「不完全な存在」であると公言しています。
私は、「門を開けて車を作るので、自分にはそれができると思ったら皆さんに参加してほしい」のです。そのために、最初に共通の価値観、いわゆる核心部分を確立し、それからみんなの力を結集して共創します。私は不完全な存在ですからすべての人の側に立ちますし、誰かがもっとよい意見を出してくれたらその人を擁護し、サポートします。
この「開門造車(門を開けて車を作る)」という言葉は、独りよがりではなく、広く大勢の意見を取り入れて開発を進めるという彼女の信念を表しています。
実際に、マスクマップの開発初期には、システムの表示と薬局の在庫にズレが生じる問題がありました。その際、彼女はすぐに薬剤師たちの声に耳を傾け、彼らの提案を取り入れてシステムを修正しました。「本当に私が天才だったら、起こりうるすべての状況が瞬時にひらめいたはずだ」と語るように、自らの不完全さを認め、他者からのフィードバックを積極的に受け入れる姿勢こそが、より良いものを生み出す原動力なのです。
タピオカミルクティーに学ぶ「集合知」
「不完全さ」を受け入れるからこそ、他者の力、すなわち「集合知(Collective Intelligence)」を最大限に活かすことができます。集合知とは、多くの人々の知恵を集め、一人では到達できないような優れた解決策や創造物を生み出す力のことです。
オードリー氏は、集合知を「集思(衆知を収集する)」と「広益(有益な意見を幅広く吸収する)」の二つに分け、その重要性を説いています。
彼女が集合知の象徴として挙げるのが、意外にも「タピオカミルクティー」です。
タピオカミルクティーには複数の起源とたくさんの創作理論が絡んでいるため、誰も特許や商標権を主張できないという特徴があるからです。…(中略)…「タピオカ・ミルク・お茶」は、現地の事情に合わせて好きなように入れ替えることができるのです。
ベースのお茶を変えたり、豆乳を使ったりと、誰もが自由にアレンジを加えて新しい価値を生み出せる。このオープンなあり方こそが集合知の本質です。
ビジネスにおいても、一部の専門家だけでプロジェクトを進めるのではなく、多様なバックグラウンドを持つメンバーが参加できるプラットフォームを用意し、誰もが「ジグソーパズルの1ピース」として貢献できる文化を育むことが、革新的なアイデアを生む鍵となります。
STEP3 問題に対処する:行動を促す「透明性」と「イノベーション」
問題を受け入れたら、次はいよいよ「対処する」、つまり行動に移す段階です。オードリー氏のアプローチの核心は、徹底した「透明性」によって市民の参加を促し、社会全体でイノベーションを起こすことにあります。
著作権の放棄と「徹底的な透明性」
オードリー氏は、自身の名前「唐鳳」や肖像権、著作権をすべて放棄し、誰もが自由に使えるようにしています。インタビューの内容もすべてインターネット上で公開されています。これは単なるパフォーマンスではありません。
「『透明』と『公開』をベースにすることによって、より多くの人からの理解を得て、その参加を促してイノベーションの花火と変革をみんなで創り上げていきたいと思ったからです」
彼女の知識や思想は、オープンソースのソフトウェアのように、誰かが自由に利用し、二次創作し、さらに発展させていくための「公共財」なのです。
この「透明性」が劇的な効果を発揮したのが、コロナ禍でのマスク供給でした。政府はマスクの在庫データをすべて公開し、民間エンジニアが自由にアプリを開発できるようにしました。その結果、わずか数日で多様な「マスクマップ」が生まれ、市民は安心してマスクを手に入れることができました。
政府が国民に透明性を求めるのではなく、政府が国民に向けて情報を透明化する。この逆転の発想が、パニックを防ぎ、官民の信頼関係を構築したのです。企業においても、経営情報やプロジェクトの進捗を可能な限りオープンにすることが、従業員の主体的な参加を促し、組織全体の力を引き出すことに繋がります。
ハッシュタグに学ぶ「ソーシャル・イノベーション」
オードリー氏が目指すのは、単なるビジネス上のイノベーションではなく、社会全体の課題を解決する「ソーシャル・イノベーション」です。彼女はこれを「みんなのことにみんなが協力する」と定義しています。
その好例が「#ハッシュタグ」です。もともとは一人の開発者が提唱したアイデアでしたが、特許を申請しなかったため、誰もが自由に使えるようになりました。そして、当初の意図を超えて、社会運動や情報共有など、さまざまな用途で活用されるようになり、社会に大きな影響を与えました。
イノベーションの特徴は、誰でも元の意義に別の意義を乗せられることにあります。新しい意義が加わったあと、誰かが別の意義を創り出し、またそれが使用される。そうやって拡張可能性や拡散性がさらに高まり、ますます強くなるのです。
「ピンクのマスク事件」も同様です。ピンクのマスクを嫌がった男の子の話を受け、大臣たちが一斉にピンクのマスクを着けたことで、それが「かっこいい」という価値観に転換され、マスク着用率の向上という公衆衛生の課題解決に貢献しました。
トップダウンで強制するのではなく、誰もが楽しく参加できる「仕掛け」を作る。これこそが、人々を動かし、社会を変えるソーシャル・イノベーションの本質です。
STEP4 問題を手放す:競争から抜け出し、未来を共創する
問題に対処し、一つの解決に至ったとしても、それで終わりではありません。最後のステップは、その成果や考え方を「手放す」ことです。これは、成果を独占せず、個人間の競争から脱却し、未来の世代へと繋いでいくという、オードリー氏の哲学の集大成です。
「個人の競争力」は誤訳だった
私たちは幼い頃から「競争に勝て」と教えられてきました。しかし、オードリー氏は「個人間の競争」という考え方そのものに疑問を投げかけます。
かつて「competence(何かをするために必要な能力)」が「競争力」と翻訳されたために、個人の競争力を鍛えろ…(中略)…と叫ばれるようになりました。…(中略)…つまり、「個人の競争力」は誤訳だったのです。
彼女によれば、現代社会における競争のほとんどは、企業間や組織間といった「団体戦」であり、個人同士が社内で競い合うような組織は、結局チームワークに優れた組織に負けてしまいます。
新教育課程の策定に関わった際も、彼女は学力順位だけで生徒を評価するのではなく、多様な学習履歴を持つ生徒が互いに補い合うチームを作ることの重要性を訴えました。
ビジネスリーダーは、社内の競争を煽るのではなく、社員一人ひとりの異なる能力(competence)を尊重し、それらを組み合わせることでチーム全体のパフォーマンスを最大化する環境を整えるべきです。評価制度や組織文化を、「競争」から「共創」へと転換することが求められています。
ログアウトするときの世界を、より良くするために
オードリー氏のすべての行動の根底には、ある一つのシンプルな願いがあります。
いつか自分がログアウトするときの世界がログインしたときよりもよくなる。そう思えるなら、非常に嬉しく、幸せなことです。
彼女は、自身の人生をコンピュータへの「ログイン」と「ログアウト」にたとえ、自分がこの世を去るときに、少しでも良い社会を次世代に残したいと考えています。
そのために、彼女は「自分と向き合う」時間を非常に大切にしています。特に、毎日8時間の睡眠は、単なる休息ではなく、日中に得た情報を整理し、思考の一貫性を保つ(自己整合する)ための重要なプロセスだと位置づけています。 スマートフォンのスワイプのような無意識の刺激を避け、意識的に自分と対話する時間を確保することが、安定した思考の基盤を作ると言います。
先天性の心臓病を抱え、幼い頃から死と隣り合わせだった彼女にとって、毎晩眠ることは「死と向かい合う練習」でもありました。その日の心配事をすべて手放し、安心して眠りにつく。この繰り返しが、過去に囚われず、常に未来に向けたイノベーションを生み出すための心の隙間を作っているのです。
まとめ:明日から実践するオードリー・タンの思考法
オードリー・タン氏が示す問題解決の4ステップは、単なるテクニックではありません。それは、他者への深い敬意と、未来への責任感に裏打ちされた生き方そのものです。
最後に、彼女の思考法を私たちの仕事や生活に活かすための、具体的なアクションをいくつか提案します。
- 会議の場で「傾聴者」に徹してみる:次に参加する会議では、まず自分の意見を言う前に、他のメンバーの話を最後まで遮らずに聴くことに集中してみましょう。そして、「なぜこの人はこう考えるのだろう?」と、その背景にある経験や価値観に思いを馳せてみてください。
- 自分の仕事を「オープン」にしてみる:抱えているプロジェクトの進捗や資料を、勇気を出してチームや関係者に公開してみましょう。「私は不完全なので、皆さんの知恵を貸してください」という姿勢でフィードバックを求めることで、思わぬアイデアや協力が得られるかもしれません。
- 「競争」の代わりに「貢献」を意識する:同僚をライバルと見るのではなく、「この人の強みと自分の強みを組み合わせれば、どんな新しい価値を生み出せるだろう?」と考えてみましょう。評価の軸を、個人としての勝ち負けから、チームや社会への貢献度にシフトさせてみることが大切です。
- 意識的に「自分と向き合う」時間を作る:一日の終わりに、スマートフォンを置いて5分間だけ静かに過ごす時間を作ってみましょう。その日あったことを整理し、自分の感情と対話することで、心に平穏が訪れ、明日への活力が湧いてくるはずです。
オードリー・タン氏の思考は、私たち一人ひとりが「思想の運び手」となり、より良い未来を「共創」していくための羅針盤となるでしょう。本書を手に取り、彼女の言葉にさらに深く触れてみることをお勧めします。