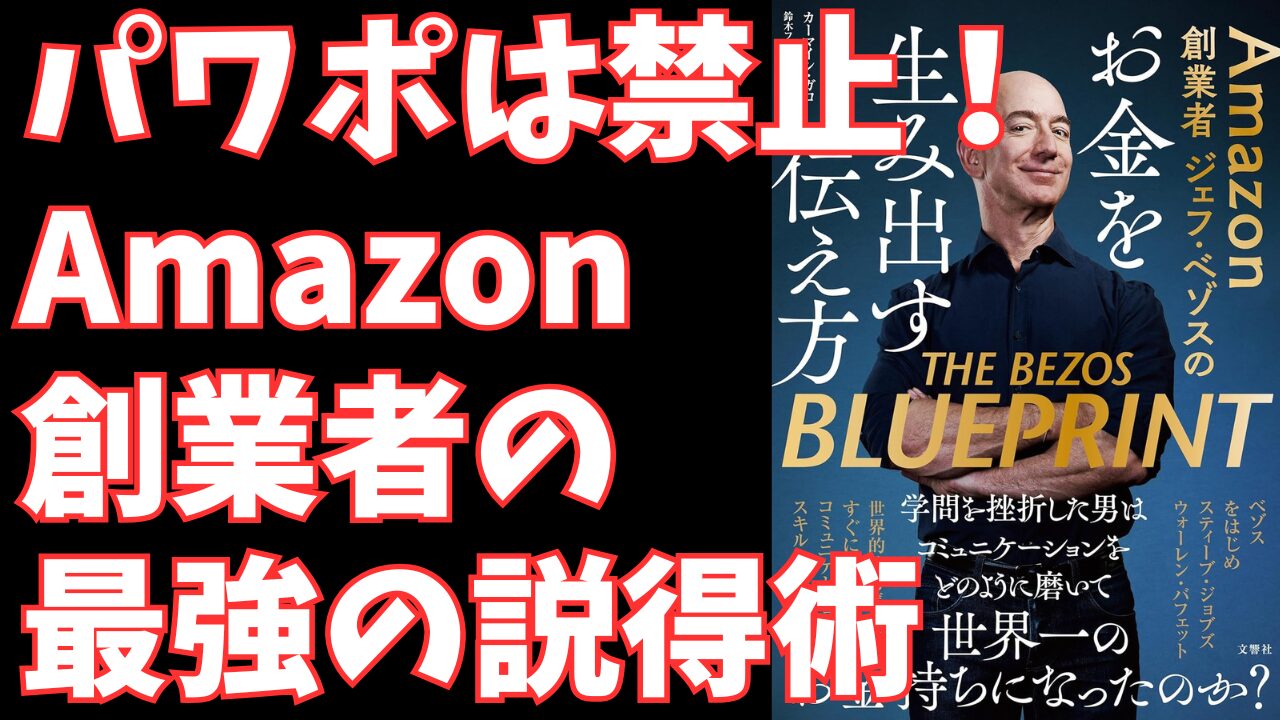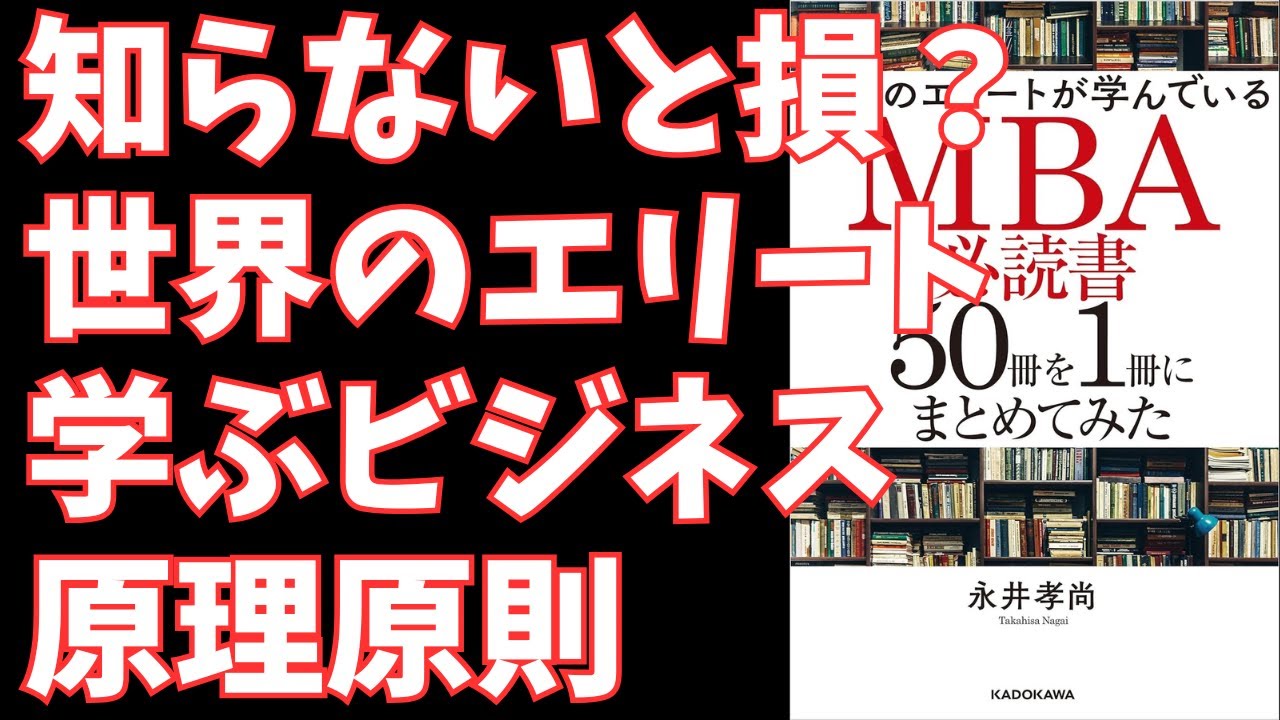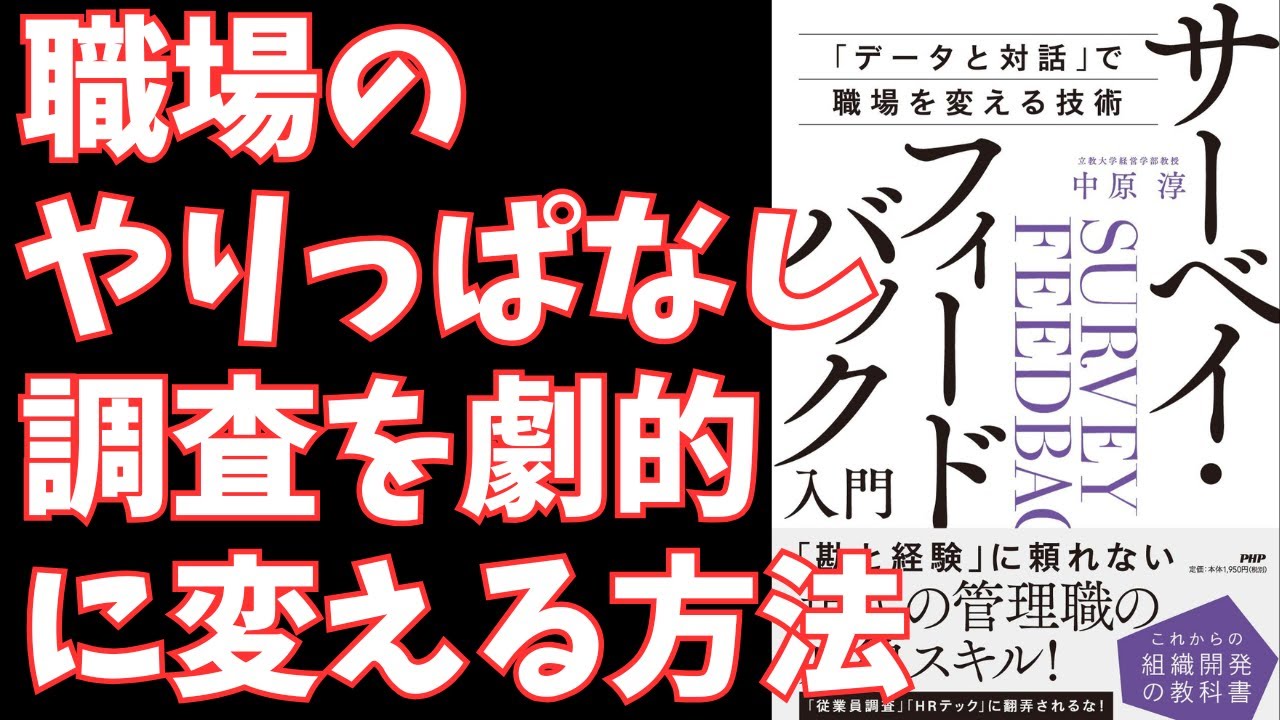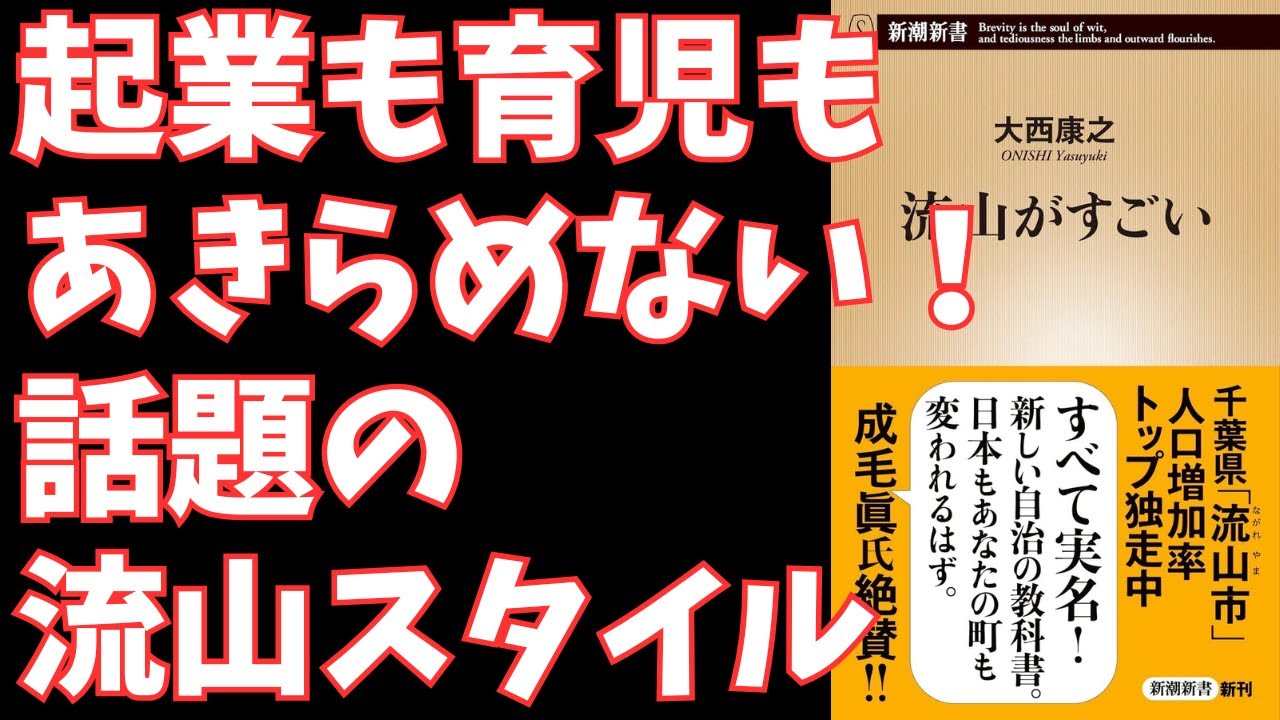『ニュー・エリートの時代』に学ぶポストコロナの生存戦略|加速する3つの二極化を乗り越える働き方とは
この記事では、元マイクロソフトのチーフアーキテクトである中島聡氏の著書『ニュー・エリートの時代 ポストコロナ「3つの二極化」を乗り越える』の内容を基に、コロナ禍を経て激変したビジネス環境で私たちがどう生き抜くべきかを解説します。本書の核心である 「ビジネス」「働き方」「人材」という3つの二極化 の実態を明らかにし、これからの時代に価値を生み出し続ける 「ニュー・エリート」 になるための具体的な思考法やスキルを、書籍内の事例を交えながら探求します。変化の時代を生き抜くための羅針盤となる一冊です。
本書の要点
- ポストコロナの時代は、リモートワークへの適応度によって 「ビジネス」「働き方」「人材」の3つの二極化 が決定的に加速する。
- 生き残るためには、リモートでも効率的に機能する業種を選び、必須ツールを使いこなし、 長時間労働ではなく生産性と結果で勝負する 人材になる必要がある。
- 真のDX(デジタル・トランスフォーメーション)は業界の内部からではなく、ITを駆使する外部の新規参入者によって引き起こされる。
- イノベーションは常に「個人」の情熱から生まれ、その基本は 「手を動かす」「プロトタイプを作る」「当事者意識を持つ」 という3つの行動にある。
- これからの時代は、オンラインツールを駆使し、時間や場所に縛られずに高い成果を出す 「ニュー・エリート」 が活躍し、その働き方が新たなスタンダードになる。
はじめに:ポストコロナで加速する「3つの二極化」とは?
2020年、新型コロナウイルスのパンデミックは、私たちの働き方やライフスタイルに否応なく変化を突きつけました。多くの企業がリモートワークを導入し、オンラインでのコミュニケーションが当たり前になりました。著書『ニュー・エリートの時代』で、中島聡氏はこの変化を一過性のものではなく、社会構造を根底から変える 「進化圧」 であると指摘し、その結果として 「3つの二極化」 が加速していると警鐘を鳴らします。
本書で語られる「3つの二極化」とは、以下の通りです。
- ビジネスの二極化
人が集まることに価値を置いていた飲食業や観光業などが大打撃を受ける一方で、マイクロソフトやGoogleのようなソフトウェア企業は影響が少なく、むしろ成長を遂げました。このように、ビジネスモデルがリモートワーク時代に適応できるか否かで、企業の明暗がはっきりと分かれました。 - 働き方の二極化
SlackやZoom、Google Driveといったオンラインツールを日常的に使いこなせる人と、パソコンすら苦手な人との間で、生産性に致命的な差が生まれました。ツールを使いこなせない管理職が旧来の働き方に固執することで、組織全体の生産性を引き下げるという問題も浮き彫りになっています。 - 人材の二極化
リモートワークでは、一人ひとりの成果が可視化されやすくなります。これまで長時間労働や「会社に尽くす姿勢」で評価されてきた人材がその強みを発揮できなくなり、「本当に会社に必要な人材」と「実はいなくても困らない人材」が明確に分かれてしまうのです。
この3つの二極化は、最終的に 貧富の差 として社会に現れます。では、この厳しい時代を私たちはどう生き抜けば良いのでしょうか。本書は、その答えが 「ニュー・エリート」 という新しい人材像にあると示唆しています。
【ビジネスの二極化】進化圧に乗るか、淘汰されるか
本書の第1章では、「ビジネスの二極化」がなぜ起こるのか、その構造が解き明かされています。中島氏は、多くの日本企業が掲げるDX(デジタル・トランスフォーメーション)について、「本当のDXは『業界の外』から起こる」 と断言します。
既存の企業が自社の業務をIT化するのではなく、Amazonが書店業界を根底から変えたように、過去のしがらみを持たない新規参入企業がIT技術を武器に業界構造そのものを破壊する。これがDXの本質です。
新型コロナウイルスがもたらした「進化圧」は、この動きをさらに加速させました。例えば、米国の小売業界では、ロックダウンによって多くのデパートが経営破綻に追い込まれる一方で、オンライン販売に強みを持つAmazonの株価は急騰しました。これは、消費者のライフスタイルが劇的に変化したことを象徴する出来事です。
この変化は、飲食業界でも同様です。マクドナルドやドミノ・ピザのように、オンライン注文や自社デリバリー網といった IT投資に余力のある大手チェーン は順調に回復しました。一方で、IT投資が難しい中小の個人経営レストランは、Uber Eatsなどの高い手数料に苦しみ、多くが淘汰の危機に瀕しています。
このように、コロナ禍は「IT投資ができる企業」と「できない企業」の差を残酷なまでに可視化しました。中島氏自身も、この状況を座視できず、個人経営の飲食店を支援するために、テイクアウトの予約・決済サービス 「OwnPlate(おもちかえり.com)」 をオープンソースで開発したエピソードを紹介しています。これは、ITの力で多様性を守ろうとする、著者自身の「当事者意識」の表れと言えるでしょう。
この章で示されているのは、変化を「危機」と捉えるか、「チャンス」と捉えるかの重要性です。新しいライフスタイルから生まれる潜在的なニーズを掴み、テクノロジーを活用して新たな価値を提供できる企業や個人だけが、この時代を生き残ることができるのです。
【働き方の二極化】生産性を劇的に変える「ツール」と「スキル」
第2章では、「働き方の二極化」を乗り越えるための具体的なツールとスキルについて語られます。中島氏は、リモートワーク時代の生産性の差は 「ツールの選択と習熟度で決まる」 と強調します。
著者は、ハワイのコンドミニアムを購入した際のエピソードを挙げています。不動産会社の担当者とGoogle Driveのスプレッドシートを共有することで、一度も電話をすることなく、メールとスプレッドシート上でのやりとりのみでスムーズに物件選びが完了したそうです。このように、文系の職種であってもツールを使いこなせれば、10時間かかっていた仕事が3時間で終わる ようになる、と著者は説きます。
リモートワークにおいて最も重要なスキルとして挙げられているのが 「非同期コミュニケーション」 です。多くの人は「リモートワーク=Zoom会議」と誤解していますが、これは大きな間違いです。著者は、「ミーティングは人々の時間を奪い、生産効率を下げるもの」と断言し、安易にZoom会議を申し込むのは失礼でさえあると指摘します。
情報の共有や意見交換のほとんどは、Slack のようなチャットツールを使った非同期コミュニケーションの方がはるかに効率的です。自分の都合の良い時間に情報を確認し、じっくり考えてから発言できるため、より深いレベルでの意思疎通が可能になります。Zoomのような同期コミュニケーションは、少人数で緊急の意思決定が必要な場合に限定して使うべきなのです。
Slackは生産性を上げ、Zoomは生産性を下げる という著者の言葉は、これからの働き方を考える上で非常に重要な示唆を与えてくれます。
また、リモートワークを「監視するツール」を導入する企業の愚かさについても厳しく批判しています。勤務時間を秒単位で管理したり、PC画面をランダムに撮影したりする行為は、社員の「やっているフリ」を助長するだけで、生産性の向上には全く繋がりません。これからの評価は、束縛した「時間」ではなく、Githubでの活動履歴のように、ツール上に残る記録によって可視化された 「成果」 に基づいて行われるべきなのです。
【人材の二極化】これからの時代を牽引する「ニュー・エリート」の条件
本書の核心である第3章では、3つの二極化の先に生まれる 「ニュー・エリート」 の姿が描かれます。彼らは、これまでのエリートとは全く異なる価値観と働き方を持つ人々です。
ニュー・エリートの共通点として、以下のような特徴が挙げられます。
- オンライン・ツールを使いこなし、生産効率が桁違いに高い
- 非同期コミュニケーション能力に長けている
- 時間に束縛されることを嫌い、成果のみで勝負する
- 会社との関係は対等で、「やる価値がある」仕事だけを選ぶ
- オフィスには出勤せず、好きな場所でリモートで働く
彼らは主にソフトウェア・エンジニアなどの専門職ですが、その働き方はあらゆる職種に影響を与えていくでしょう。特に重要なのは、その圧倒的な生産性の高さです。彼らは他の人の数倍から数十倍の成果を出すため、会社側もその「わがままな働き方」を認めざるを得ないのです。
では、どうすればこのような「ニュー・エリート」になれるのでしょうか。その鍵は 「イノベーション」 にあります。そして、イノベーションを起こすのは会社や組織ではなく、いつだって「個人」の情熱だ、と中島氏は力説します。
そのための行動原則として、本書では3つの基本が提示されています。
イノベーションの基本①:手を動かせ
ソフトウェアの世界では、「アイデアは誰でも出せるが、それを実際に動くものにできるのはごく一部の人だけ」と言われます。イノベーションは、評論家やMBA取得者ではなく、自ら手を動かしてものを作れる エンジニア から生まれます。スティーブ・ジョブズが天才的なビジョナリーであったと同時に、「ものづくり」の得意なスティーブ・ウォズニアックと組んだからこそAppleは成功したのです。
イノベーションの基本②:プロトタイプを作れ
新しいアイデアは、仕様書やプレゼン資料だけではその価値が伝わりにくいものです。中島氏自身がWindows 95を開発した際、最初に 動くプロトタイプ を作ったエピソードは象徴的です。英語が不得手だった彼は、会議でうまく発言できませんでしたが、誰よりも早くプロトタイプを作ることで、その価値を雄弁に示しました。実際に触れる「動くもの」は、ただの資料とは比較にならない圧倒的な説得力を持つのです。
イノベーションの基本③:当事者意識を持て
ただがむしゃらに働くのではなく、「会社にとって何が重要か」 を常に見極め、そこにリソースを集中させることが重要です。マイクロソフト時代の上司から「本当に大切なのは、ここぞというときに頑張ることだ」と教わった著者は、頼まれてもいないのにInternet ExplorerとWindowsの統合機能を作り、それが後のWindows 98の主要機能となりました。無駄な会議や意味のない仕事に時間を費やすのではなく、会社にとって本当に価値のあることを見抜き、自ら行動する 「当事者意識」 こそが、イノベーションの源泉となるのです。
大企業病との戦い:日本の組織が抱える課題
第4章では、日本の大企業が抱える根深い問題、いわゆる 「大企業病」 にメスを入れます。中島氏は、トヨタ自動車の自己改革に関する記事を引用し、その内情を分析します。
若手エンジニアが「調整業務や会議が多く、エンジニアとして成長できない」と感じて退職していく現状は、多くの日本企業に共通する課題です。優秀なエンジニアほど、ベンチャー企業やGAFAのような成果主義の企業に活躍の場を求めてしまいます。
また、著者は日本の経営者に、インテルの創業者アンディ・グローブの言葉「Only the Paranoid Survive(偏執狂だけが生き残れる)」を引用し、「本当の危機感」 が欠けていると指摘します。ビル・ゲイツやスティーブ・ジョブズのような、明日会社が潰れるかもしれないというほどの危機感(パラノイア)を持つ経営者でなければ、破壊的なイノベーションが次々と起こる現代で生き残ることはできないのです。
さらに、「現場迎合主義」の問題も深刻です。事業の撤退などの重要な経営判断を、その事業に関わる現場の人間に委ねてしまうと、誰もが自分の仕事を失いたくないため、正しい判断ができなくなります。これは、コーポレートガバナンスの欠如の象徴であり、会社を食い物にする構造そのものなのです。
これらの課題を乗り越えるには、個々の社員が前述の「当事者意識」を持ち、おかしいと思うことには声を上げ、時には会社を辞めてでもビジョンを持った経営者の下で働くという覚悟が必要なのかもしれません。
まとめ:未来を生き抜くために、私たちは何をすべきか
『ニュー・エリートの時代』は、ポストコロナという不確実な時代を生きる私たちビジネスパーソンにとって、多くの実践的なヒントと厳しい問いを投げかけています。
加速する 「3つの二極化」 の波に飲み込まれないためには、もはや旧来の価値観や働き方に安住することは許されません。
自らの市場価値を高めるために、どんなスキルを磨くべきか?
日々の業務において、生産性を最大化するためにどんなツールをどう使うべきか?
そして何より、会社や社会に対して「当事者意識」を持ち、自らの手で価値を生み出す覚悟があるか?
本書が示す「ニュー・エリート」とは、一部の天才的なプログラマーだけを指す言葉ではありません。それは、変化を恐れず、自律的に学び、ツールを駆使して成果を出し、時間と場所に縛られずに自分らしい生き方を実現しようとする、すべてのビジネスパーソンの未来像 なのです。
まずは、日々の仕事の中で「この会議は本当に必要か?」「もっと効率的なツールの使い方は無いか?」と自問することから始めてみてはいかがでしょうか。その小さな一歩が、二極化の波を乗りこなし、未来の「ニュー・エリート」へと繋がる道となるはずです。