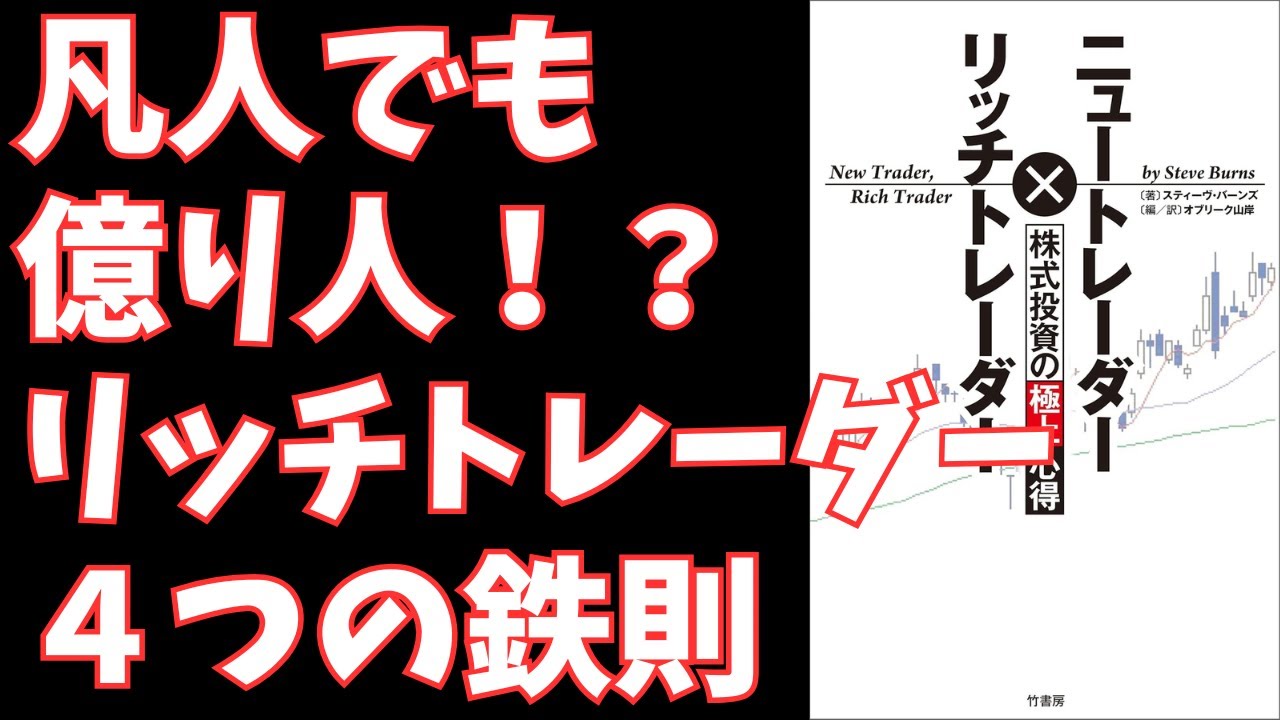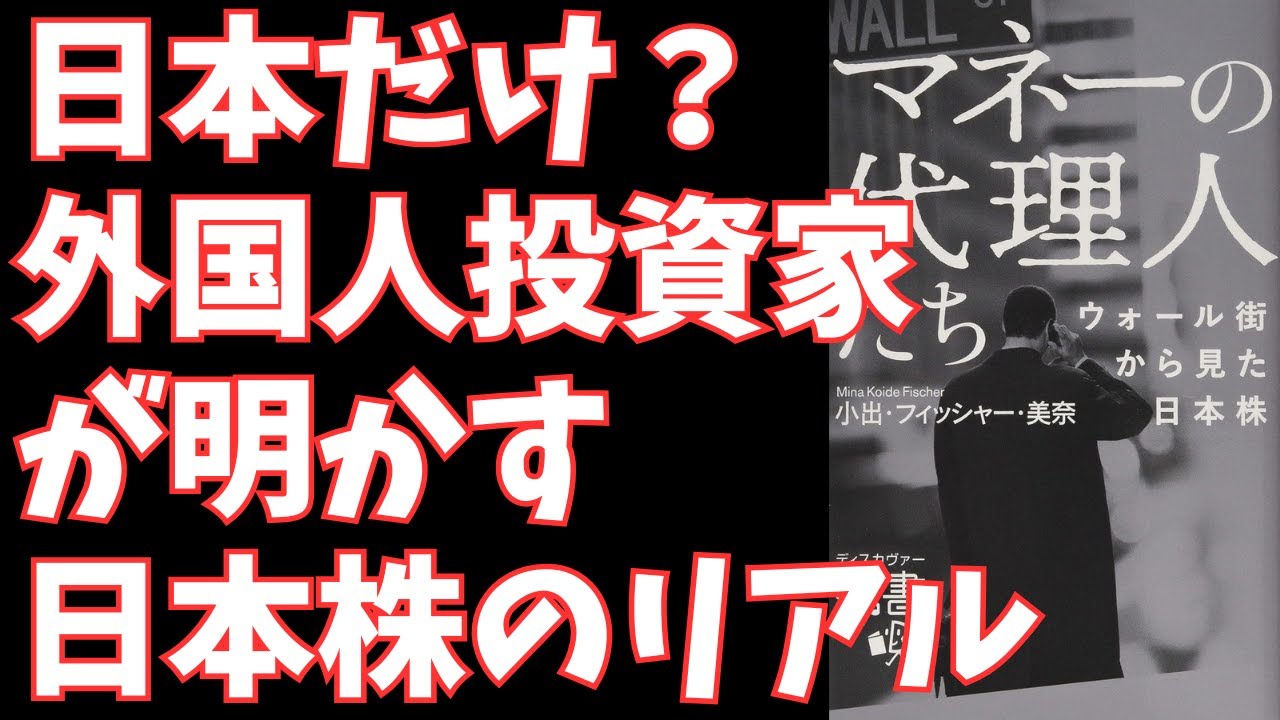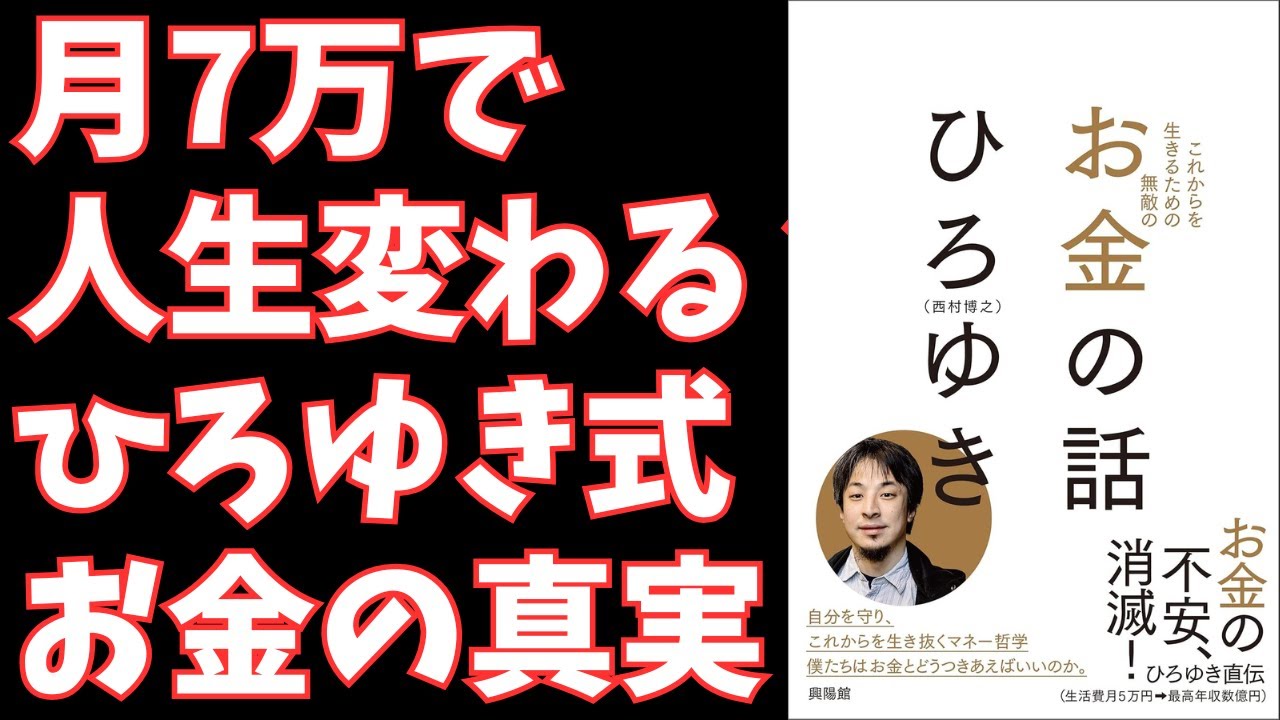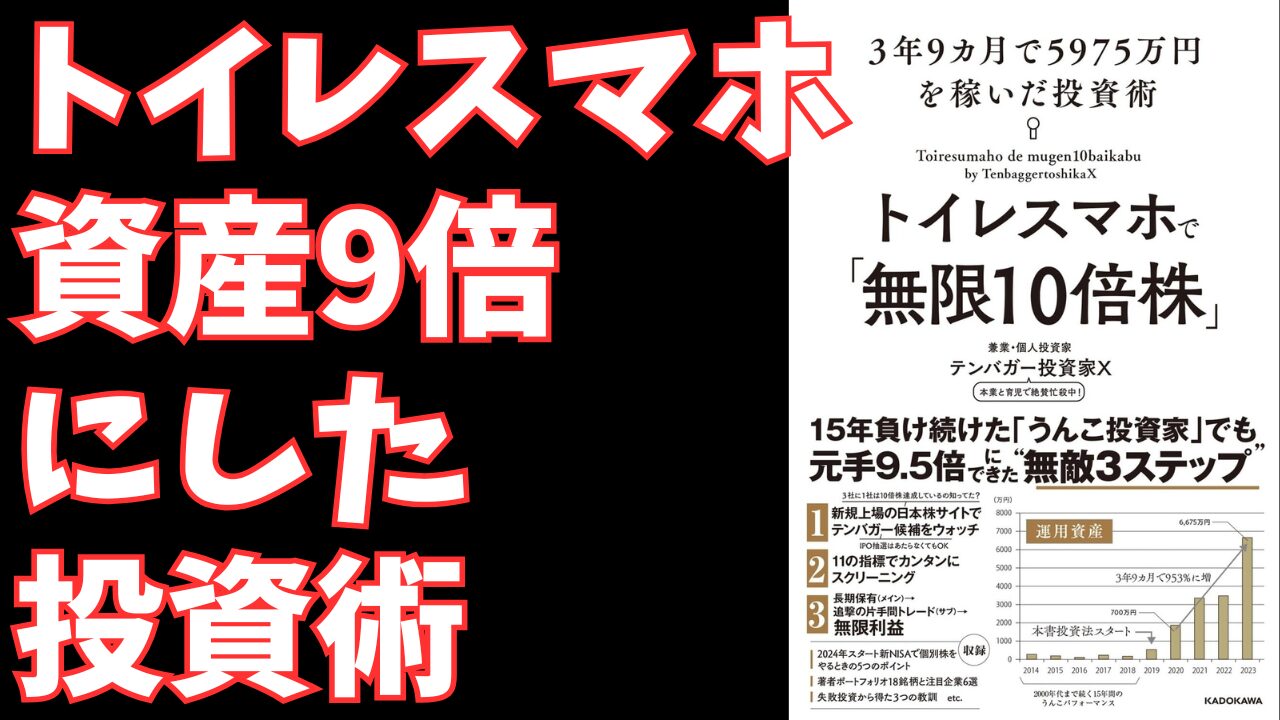『母が子に伝えたい大切なお金と社会の話』レビュー|子供のお金の教育に悩む親が読むべき一冊
「うちにはお金、どのくらいあるの?」「どうしたらお金は増えるの?」
子どもからの純粋な質問に、ドキッとした経験はありませんか?
本書『母が子に伝えたい大切なお金と社会の話』は、そんな親たちの悩みに寄り添い、単なる貯蓄や投資のテクニックではなく、子どもがこれからの社会を幸せに生き抜くための「お金との向き合い方」を教えてくれる一冊です。
著者の櫻井かすみ氏は、貯金ゼロや投資詐欺被害といった壮絶な経験を乗り越え、純資産1億円を築いた人物。その実体験と小学校教諭免許状を持つ教育者としての視点から語られる言葉には、圧倒的な説得力があります。
この記事では、忙しいビジネスパーソンである親御さんに向けて、本書の核心部分を抽出し、明日から家庭で実践できる具体的なアクションプランと共に、その要点を詳しく解説していきます。
本書の要点
- お金の教育は「使い方」から始める: お金を単なる数字としてではなく、社会とのつながりを学ぶツールと捉え、日常の買い物や会話を通じてその価値を教えることが重要です。
- 失敗は最高の学びの機会: おこづかいやお年玉は、親の管理下で「小さな失敗」を経験させる絶好のチャンス。無駄遣いや計画性のなさを経験することが、将来の大きな失敗を防ぎます。
- 「働く」とは「人の役に立つこと」: お金は「ありがとうの対価」であると教えることで、子どもは労働の本当の意味を理解し、社会貢献への意識を育むことができます。
- 投資の本質を伝える: 投資は単にお金を増やす手段ではなく、自分の未来や社会をより良くするための「応援」であるという視点を持ち、子どもと一緒に考えることが大切です。
- 親子でお金のことをオープンに話す: 家庭でお金の話をタブーにせず、家計や将来の計画について語り合うことが、子どもの経済的自立を促し、何より親子の絆を深めます。
なぜ今、家庭で「お金の話」が必要なのか?
私たち親世代の多くは、学校でお金について体系的に学ぶ機会がありませんでした。日本では長らく、家庭でお金の話をすることはどこかタブー視される風潮さえありました。しかし、時代は大きく変わりました。
低金利が続き、銀行にお金を預けているだけでは資産は増えず、むしろインフレによって価値が目減りしていく時代です。国が「貯蓄から投資へ」と舵を切り、2022年からは高校の家庭科で金融教育が必修化されるなど、お金の知識は「一部の人が知るもの」から「誰もが身につけるべき必須スキル」へと変化しています。
本書の著者、櫻井かすみ氏は、まさにその大切さを身をもって経験した人物です。離婚後に経験した2度の貯金ゼロ、3度の投資詐欺被害、そして無職の状態から純資産1億円を築き上げるまでの道のりは、決して平坦なものではありませんでした。
「お金を増やしたいと追い求めるあまり、趣味や娯楽はそっちのけ、とにかく運用額の増減にメンタルが左右されてしまう人生を送っていた時期もあります。」
彼女が自身の壮絶な失敗談を包み隠さず語るのは、お金に振り回される人生の辛さを誰よりも知っているからこそ。そして、「お金は幸せに近づくためのツールであって、それ自体が目的ではない」という核心的なメッセージを、次世代を担う子どもたちに伝えたいという強い想いがあるからです。
子どもからの「おうちにはお金、いくらあるの?」という無邪気な質問に、私たちはどう答えるべきか。本書は、その答えが単なる金額の提示ではないことを教えてくれます。それは、お金を通じて社会の仕組みを伝え、人生を豊かに生きるための知恵を授ける、絶好の機会なのです。
【実践編】明日からできる!子どもの金銭感覚を育む3つのステップ
本書では、日常生活の中で自然にお金の教育を取り入れるための具体的な方法が数多く紹介されています。ここでは特に重要で、すぐに実践できる3つのポイントを解説します。
ステップ1:おこづかいの「正解」は金額ではなく「対話」にある
「おこづかい、何歳から、いくらあげるべき?」これは多くの親が抱える悩みです。本書が示す答えは非常にシンプルです。
「結論、子どもと一緒に金額を決める」
大切なのは、世間の相場に合わせることではなく、その金額を設定する理由や使い道について、親子で話し合う機会を持つことです。この対話を通じて、子どもはお金の価値や計画性を学び始めます。
本書では、おこづかいの渡し方として「定額制」「その都度制」「MIX制」の3つの方法が紹介されています。
- 定額制: 計画性を育むのに最適。限られた予算でやりくりするスキルが身につきます。
- その都度制: 「本当に必要か?」を考えさせる機会になる一方、計画性は育ちにくい側面も。
- MIX制: 定額で日常の支出を管理させつつ、遠足など特別な支出にはその都度渡す、柔軟な方法。
どの方法を選ぶにせよ、重要なのは「子どもの失敗を許容する」という姿勢です。
「私は子どもの頃のお金の失敗は、どんどんしたほうが良いと考えています。親の目の届く範囲内の失敗なので金額も少額ですし、何かあっても親がカバーできるからです。」
おこづかいを初日に全部使ってしまい、残りの一ヶ月を我慢する。その経験こそが、どんな教科書よりも雄弁にお金の計画的な使い方の重要性を教えてくれるのです。
また、お年玉のようなまとまったお金は、子どもにお金の管理を実践させる絶好の機会。全額を親が管理して貯金するのではなく、一部(あるいは全額)を子どもに委ね、「使う分」「貯める分」「増やす(投資する)分」に分けさせる「3つの貯金箱作戦」も非常に有効です。この実践を通じて、子どもは自分にとっての「良い使い方」とは何かを学んでいきます。
ステップ2:「見えないお金」の価値を「見える化」する
キャッシュレス決済が当たり前になった現代、子どもたちは現金に触れる機会が減っています。交通系ICカードやスマホ決済は非常に便利ですが、お金を使っている感覚が薄れ、「魔法のカード」と勘違いしてしまうリスクも孕んでいます。
国民生活センターには、子どもがオンラインゲームに無断で高額課金してしまったという相談が後を絶ちません。2022年度の相談件数は4,024件、平均契約額は約33万円にも上ります。
では、どうすれば「見えないお金」の価値を伝えられるのでしょうか?
本書が提案するのは、物理的な現金と並べて価値を「見える化」するというシンプルな方法です。
「電子マネーにチャージされている5,000円分は目に見えないけれども、見える現金5,000円札1枚を並べて同じ価値であることを伝えます。さらに1,000円札5枚を並べるのも良いでしょう。」
また、駅の券売機でICカードにチャージする作業を子どもと一緒に行うのも効果的です。現金が電子データに変わる瞬間を目の当たりにすることで、「ピッ」と鳴る音の裏には、親が働いて得たお金が存在することを実感できます。
ゲーム課金についても、「ダメ!」と一方的に禁止するのではなく、まずは仕組みを説明し、おこづかいの範囲内で、自分のお金でやらせてみることが重要です。自分のお金が減る痛みを知ることで、子どもは「本当にこのアイテムは必要なのか?」と自問するようになります。
ステップ3:「投資」とは未来への「応援」だと教える
「投資」と聞くと、多くの大人は「リスク」「損をする」といったネガティブなイメージを抱きがちです。しかし、本書は投資の本当の意味を教えてくれます。
投資とは、単にお金を増やすことではなく、「自分や社会をより良くすること」
この本質を子どもに伝えるために、著者は「リンゴの木」の例え話を用います。
「小さな種を土に植えて、水や日光を与えて育てると、大きな木になって実がなるでしょ? 投資は種がお金に代わったもので、そこに手間をかけて、未来にもっとたくさんの実(お金)を得るための準備をすることなんだよ」
この考え方に基づけば、投資の対象は株や投資信託だけではありません。
* 自分の時間を投資する: 勉強やスポーツの練習をすれば、未来の可能性が広がる。
* おこづかいを投資する: お金を貯めて本を買えば、新しい知識が得られる。
NISAなどの制度を利用してお金を増やすことも大切ですが、その前に「どんな会社を応援したいか?」「どんな未来を作りたいか?」を親子で話し合うことが、投資教育の第一歩となります。
その会社の商品やサービスが、誰かを幸せにしているか? 社会の役に立っているか? そのような視点で投資先を選ぶことを教えれば、子どもは経済活動と社会貢献のつながりを自然と理解していくでしょう。
お金の話は「人生の話」~親が伝えるべき最も大切なこと
本書を貫く最も重要なメッセージは、「お金について考えることは、人生について考えること」だという点です。
「なぜ働かないといけないの?」
この根源的な問いに対して、あなたならどう答えますか?
「生活のため」「お金を稼ぐため」という答えだけでは、子どもは働くことの本当の価値を理解できません。本書は、その答えを明確に示しています。
「働くとは、お金を稼ぐためだけでなく、人の役に立つこと」
レストランのシェフは美味しい料理で人を幸せにし、バスの運転手は安全な移動で人を助ける。その「ありがとう」の対価として、私たちはお金を受け取ります。お金は、人と人とをつなぎ、社会を支え合うための潤滑油なのです。
この考え方は、子どもの進路相談にも活かすことができます。「どの大学に行くか」「どの会社に入るか」だけでなく、「自分の『好き』や『得意』を、どうやって人の役に立つ形に変えられるか?」という視点で一緒に考えることで、子どもは自分だけのキャリアパスを見つけていくことができます。
また、人生の三大支出である「住宅費」「教育費」「老後資金」といったシビアな話も、包み隠さず伝えることが大切です。特に教育費については、家庭の経済状況を正直に話し、奨学金という「良い借金」の選択肢も含めて親子で計画を立てることが、子どもの自立心を育み、将来のトラブルを避けることにつながります。
まとめ:お金に振り回されない人生を、我が子へ
本書『母が子に伝えたい大切なお金と社会の話』は、テクニックに偏りがちな金融教育に一石を投じ、その本質が「いかに幸せに生きるか」という人生のテーマと直結していることを教えてくれる羅針盤のような一冊です。
著者の櫻井氏が自身の壮絶な失敗から学んだ教訓は、重く、そして温かいです。
* お金は、使い方次第で人生を豊かにする「道具」であること。
* お金の価値は、社会的な信用と「人と人とのつながり」の中にあること。
* そして何より、お金を増やすこと以上に、自分や家族にとっての「本当の幸せ」とは何かを考え続けること。
これらのメッセージは、子どもだけでなく、私たち親自身の生き方をも問い直すきっかけを与えてくれます。
今日から、食卓で、買い物先で、移動中の車内で、少しだけ「お金の話」をしてみませんか?
「このお菓子は100円だけど、これを我慢したら明日2つ買えるね」
「パパやママの仕事は、こんな風に人の役に立っているんだよ」
そんな小さな会話の積み重ねが、子どもの心に「お金」というツールを正しく使いこなし、自分自身の人生を主体的に切り拓いていくための、確かで力強い土台を築いていくはずです。