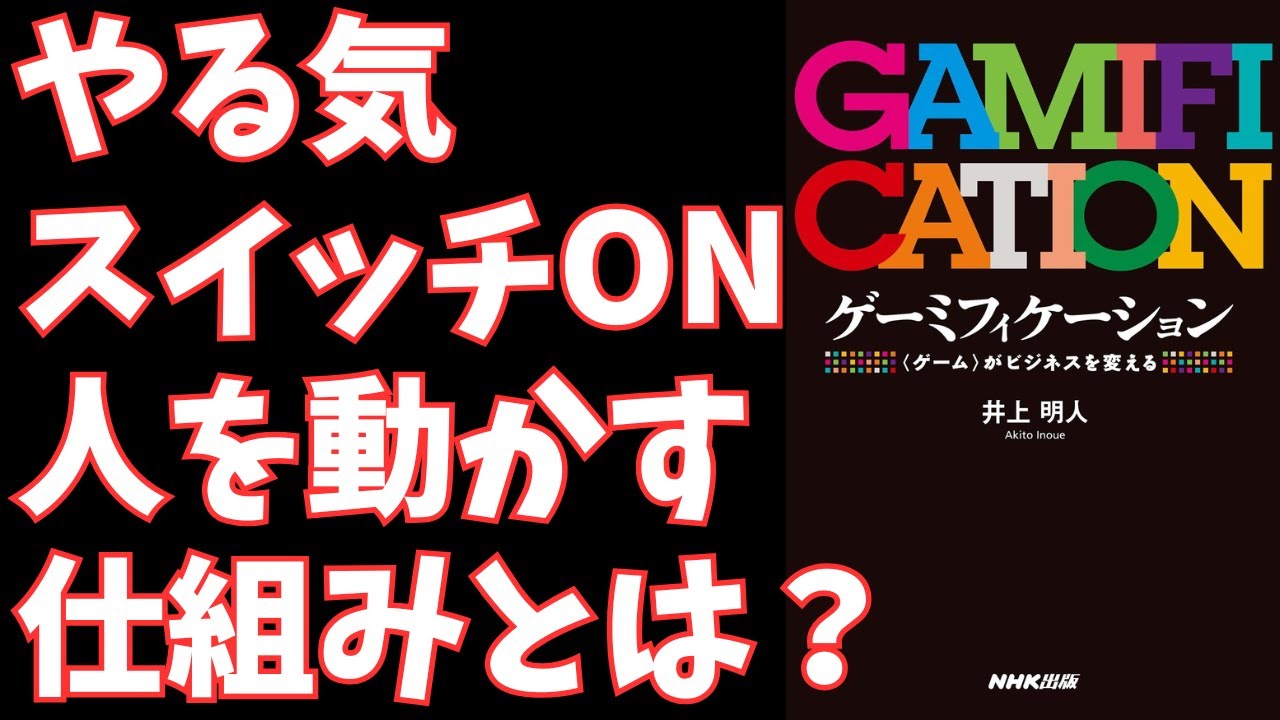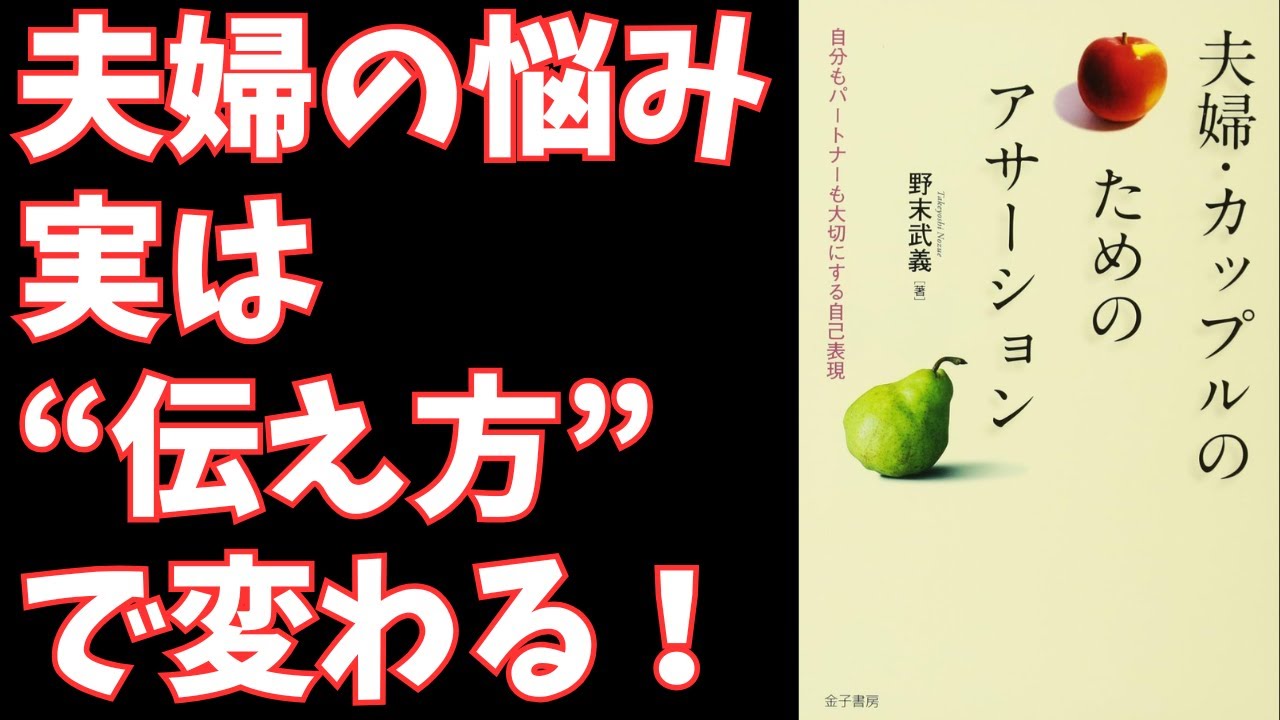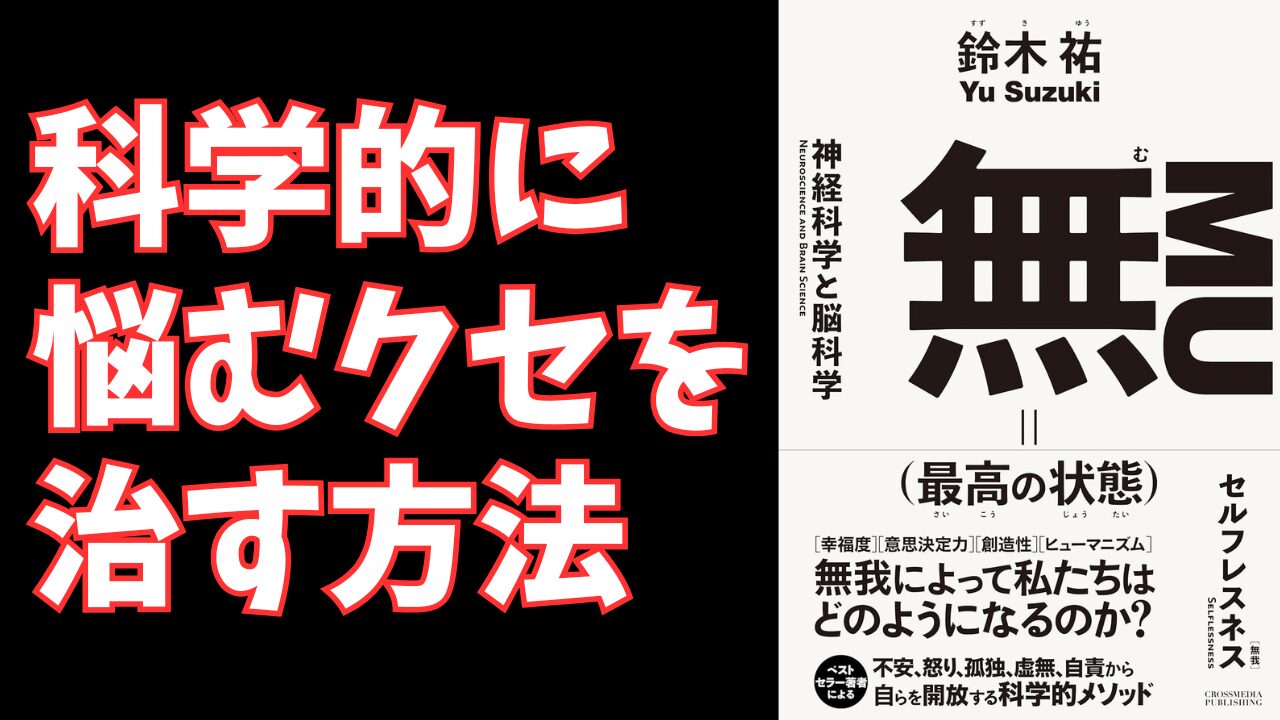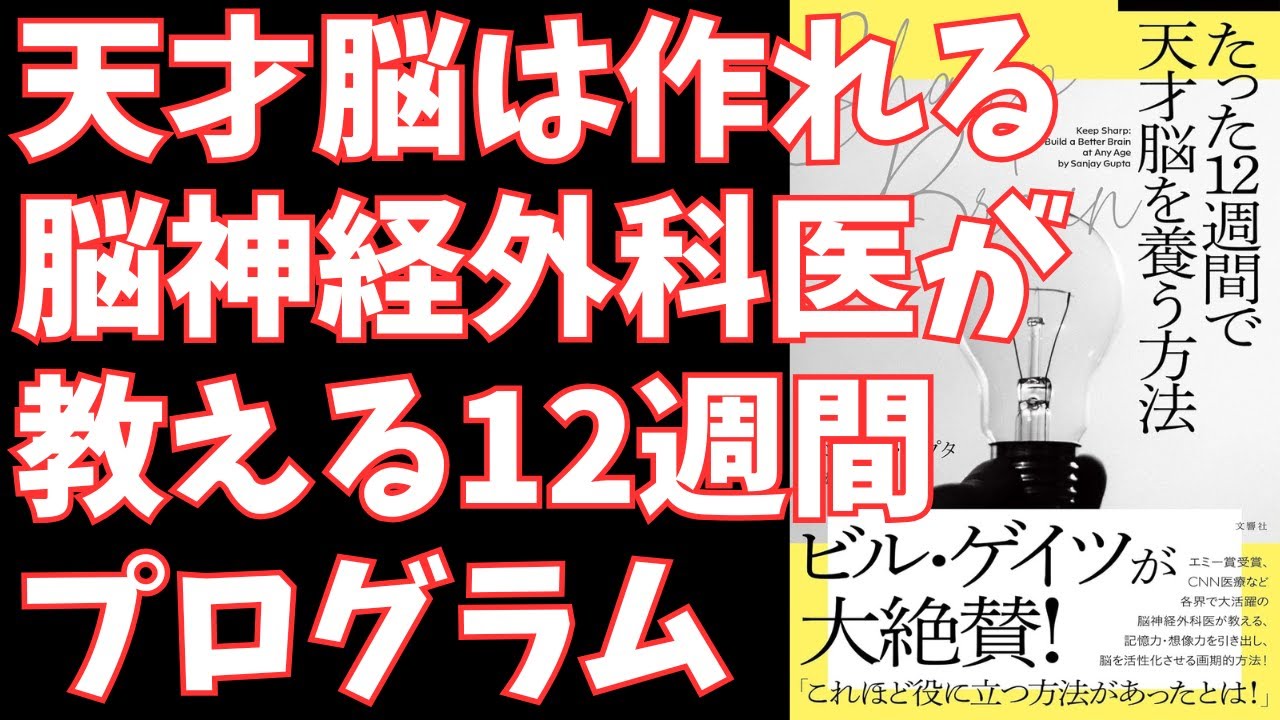行動経済学~経済は「感情」で動いている~|ビジネスの意思決定を変える心理学
本書は、従来の経済学が想定する「合理的な人間」像を覆し、私たちの経済行動がいかに感情や直感に影響されているかを解き明かす『行動経済学』の入門書です。なぜ私たちはダイエットに失敗し、計画的な貯蓄ができず、時には不合理な投資をしてしまうのか。その背後にある心のメカニズムを、豊富な事例とともに解説しています。ビジネスパーソンが陥りがちな判断の罠を理解し、自分や他者の行動をより深く洞察することで、交渉、マーケティング、組織運営など、あらゆる場面でより良い意思決定を下すためのヒントを提供します。
本書の要点
- 経済は「勘定」だけでなく「感情」で動く:人間の経済行動は、合理的な計算だけでなく、直感や感情、心のバイアスに大きく左右される。
- プロスペクト理論と損失回避性:人は絶対的な価値ではなく、ある基準点からの「利得」と「損失」で物事を判断し、同じ額であれば利得の喜びよりも損失の痛みを2倍以上強く感じる。
- ヒューリスティクスとバイアス:人は複雑な判断を迫られたとき、経験則(ヒューリスティクス)に頼るが、それが体系的な判断の誤り(バイアス)を生む原因となる。
- フレーミング効果:同じ内容でも、伝え方や見せ方(フレーム)によって人の意思決定は大きく変わる。これはマーケティングや交渉に応用できる。
- 人は利己的であると同時に協力的:人は自己の利益を追求するだけでなく、「公正さ」や「お返し(互酬性)」を重んじ、時にはコストを払ってでも裏切り者を罰する社会的選好を持つ。
はじめに:なぜ私たちは「不合理な選択」をしてしまうのか?
「ダイエット中なのに、つい甘いものを食べてしまう」
「老後のために貯蓄が必要だとわかっているのに、衝動買いがやめられない」
「株価が下がっている。損切りすべきだと頭ではわかっているのに、いつか戻るはずだと塩漬けにしてしまう」
ビジネスや日常生活において、後から考えれば「なぜあんな判断をしたのだろう?」と首をかしげたくなるような、不合理な選択をしてしまった経験は誰にでもあるのではないでしょうか。
従来の経済学では、人間は常に自分の利益を最大化するために、合理的な計算に基づいて行動する「経済人(ホモ・エコノミカス)」であると想定されてきました。この経済人とは、神のような存在で、感情に流されず、完璧な自己コントロールができ、常に最適な選択をする人物です。
しかし、現実の私たちはどうでしょうか?流行遅れが嫌で服を買い、BSEが怖いから牛肉を避け、最後は直感で投資を決める。私たちの行動は、常に合理的とは言えません。
本書『行動経済学~経済は「感情」で動いている~』は、この「経済人」という前提に疑問を投げかけ、人間の心理や感情が経済行動に与える影響を解き明かす「行動経済学」の世界をわかりやすく解説した一冊です。
この記事では、本書の中から特にビジネスパーソンが知っておくべき重要なコンセプトを厳選し、具体的な事例を交えながら、あなたの意思決定をアップデートするためのヒントをお伝えします。
あなたも「経済人」ではない!標準的経済学の非現実的な人間像
本書の冒頭で、著者は読者にいくつかのクイズを投げかけます。その一つが、有名な「モンティ・ホール問題」です。
【問題】
あなたはクイズ番組に出演しています。目の前にはA、B、Cの3つのドアがあります。1つのドアの後ろには車が、残りの2つのドアの後ろにはヤギがいます。
1. あなたはAのドアを選びました。
2. すると、答えを知っている司会者が、Cのドアを開けてヤギを見せました。
3. 司会者はあなたにこう言います。「Aのままでいいですか? Bのドアに変えてもいいですよ」
さあ、あなたならどうしますか?
多くの人は、「残りはAとBの2つだから、確率はどちらも1/2。変えても変えなくても同じだ」と考え、選択を変えないのではないでしょうか。
しかし、正解は「Bのドアに変える」です。変えることで車が当たる確率は、なんと1/3から2/3に跳ね上がるのです。
この問題は、ノーベル賞受賞者や数学者でさえ間違えることがあるほど、私たちの直感が当てにならないことを示しています。従来の経済学が前提とする「経済人」であれば、このような確率問題や論理問題を間違うことはありません。しかし、現実の私たちは、完璧な計算能力も無限の情報処理能力も持っていません。
私たちは、ハーバート・サイモン(ノーベル経済学賞受賞者)が提唱した「限定合理性」のもとで生きています。つまり、限られた時間、情報、認知能力の中で、完璧ではないけれども、そこそこ満足のいく(満足化)意思決定をしているのです。
行動経済学は、このような「神のような経済人」ではなく、不合理で、感情豊かで、間違いもする「生身の人間」の行動を直視することから始まります。
なぜ私たちは「直感」で判断し、間違うのか?- ヒューリスティクスとバイアス
私たちは日々の意思決定において、すべての選択肢を吟味し、複雑な計算をしているわけではありません。多くの場合、無意識のうちに「ヒューリスティクス」と呼ばれる、いわば思考のショートカットや経験則を用いています。
ヒューリスティクスは、迅速な判断を可能にする便利なツールですが、時として「バイアス(偏り)」と呼ばれる体系的な判断の誤りを引き起こします。本書で紹介されている代表的なものを3つ見ていきましょう。
1. 利用可能性ヒューリスティクス:思い出しやすい情報に影響される
これは、頭に思い浮かびやすい事例や情報に基づいて、その事象の発生確率を判断してしまう傾向のことです。
例えば、「自殺と他殺、アメリカではどちらが多いか?」と聞かれると、多くの人は「他殺」と答えます。なぜなら、ニュースでは殺人事件が頻繁に報道され、記憶に残りやすいからです。しかし、実際には自殺者の方が他殺者よりも多いのです。
【ビジネスでの罠】
* 最近の成功・失敗体験への固執:直近のプロジェクトの成功体験に引きずられ、市場環境が変化しているにもかかわらず同じ手法を繰り返して失敗する。逆に、一度の失敗を恐れるあまり、有望なチャンスを逃してしまう。
* メディア報道による過剰反応:ある業界のネガティブなニュースが大きく報じられたことで、その業界全体のリスクを過大評価し、投資や取引の機会を失う。
2. 代表性ヒューリスティクス:ステレオタイプで判断する
これは、ある事象が特定のカテゴリーの典型的なイメージ(代表例)に似ているというだけで、そのカテゴリーに属する確率が高いと判断してしまう傾向です。
例えば、3週連続で株価予測を的中させたアナリストがいると、「この人は優秀だ」と判断しがちです。しかし、それは単なる偶然かもしれません。少数のサンプルから全体を判断してしまうこの誤りは「少数の法則」と呼ばれます。
また、コイン投げで5回連続「表」が出ると、「次はそろそろ裏のはずだ」と考えてしまう「ギャンブラーの誤謬」もこの一種です。本来、 प्रत्येक回の確率は独立しており、1/2であるはずなのに、私たちは短期的な偏りを修正しようとする心理が働いてしまうのです。
【ビジネスでの罠】
* 短期的な業績での評価:数ヶ月の業績が良いだけで部下を過大評価したり、逆に悪いだけで過小評価したりする。長期的な視点での「平均への回帰」を忘れてしまう。
* 学歴や経歴による偏見:特定の大学出身である、有名企業に勤めていた、といったステレオタイプで相手の能力を判断し、本質を見誤る。
3. アンカリングと調整:最初の情報に引きずられる
これは、最初に提示された情報(アンカー=錨)が基準点となり、その後の判断がその基準点に引きずられてしまう傾向のことです。
ある実験では、不動産の専門家に物件の査定を依頼しました。その際、グループごとに異なる「希望販売価格」(アンカー)を提示したところ、専門家たちの査定額は、提示された希望販売価格に大きく影響されるという結果が出ました。驚くべきことに、実験後、彼らのほとんどは希望販売価格を判断材料にしたとは認識していませんでした。
【ビジネスでの罠】
* 価格交渉:最初に高い価格を提示することで、その後の交渉の基準(アンカー)を高く設定し、有利な結果に導く。逆に、相手から提示された最初の価格に無意識に引きずられてしまう。
* 目標設定・業績予測:前期の売上高がアンカーとなり、それを基準に今期の目標を設定してしまう。市場の成長性などを考慮した、より客観的な目標設定が妨げられる。
「得る喜び」より「失う痛み」が2倍強い!- プロスペト理論
行動経済学の中核をなすのが、ダニエル・カーネマンとエイモス・トヴェルスキーが提唱した「プロスペクト理論」です。これは、人々が不確実な状況下でどのように意思決定を行うかを説明する理論で、その核心には3つの重要な性質があります。
1. 参照点依存性:人は「変化」で判断する
私たちは、物事の価値を絶対的な水準で判断しているわけではありません。ある「参照点(基準点)」からの変化、つまり「利得」か「損失」かで価値を判断します。
例えば、年収500万円の人が300万円に減給されれば絶望しますが、年収100万円だった人が300万円に昇給すれば大喜びするでしょう。同じ「年収300万円」という状態でも、参照点が異なるため、その価値(満足度)は全く違うのです。
2. 感応度逓減性:変化への感度はだんだん鈍くなる
利得も損失も、その額が大きくなるにつれて、追加的な1単位の変化がもたらす価値(満足や不満)は小さくなっていきます。
1万円を儲けたときの喜びと、100万円の儲けが101万円になったときの喜びは、同じ1万円の増加でも大きさが違います。これは、利得や損失の限界的な価値が逓減することを意味します。
この性質から、人々は利得の局面ではリスクを避ける(リスク回避的)傾向があり、損失の局面ではリスクを取る(リスク追求的)傾向があることがわかります。
例えば、
* A: 確実に30万円もらえる
* B: 80%の確率で40万円もらえるが、20%の確率で何ももらえない
という選択では、多くの人が期待値(32万円)の高いBよりも、確実なAを選びます。
しかし、これが損失の局面になると、
* A’: 確実に30万円失う
* B’: 80%の確率で40万円失うが、20%の確率で何も失わない
という選択では、多くの人がA’を避け、一発逆転の可能性があるB’を選ぶ傾向があります。
3. 損失回避性:最も重要な心のバイアス
プロスペクト理論で最も重要なのが「損失回避性」です。これは、人々は同じ額であれば、利得を得る喜びよりも、損失を被る痛みの方をはるかに強く感じるという性質です。その強さは、およそ2倍から2.5倍にもなると言われています。
この損失回避性が、私たちの様々な不合理な行動を説明します。
【損失回避性が引き起こすビジネスの罠】
* 損切りできない心理:投資した株が値下がりしたとき、損失を確定させる(売却する)痛みを避けるために、「いつか回復するはずだ」と根拠なく保有し続けてしまう。
* 保有効果:自分が一度所有したモノに対して、客観的な価値以上に高い評価をしてしまう傾向。長年愛用したマグカップを、市場価格よりもはるかに高い値段でないと手放したくないと感じる心理です。
* 現状維持バイアス:変化には、良くなる可能性(利得)と悪くなる可能性(損失)の両方が伴います。損失回避性が働くため、私たちは未知の損失を恐れて、現状を維持しようとする傾向が強くなります。これは、組織改革や新しいシステムの導入に対する抵抗の大きな原因となります。
伝え方次第で結果が変わる「フレーミング効果」
同じ内容であっても、どのような言葉で、どのような文脈で提示されるか(これを「フレーム」と呼びます)によって、人々の受け取り方や意思決定が大きく変わってしまう現象を「フレーミング効果」と呼びます。
本書で紹介されている有名な「アジアの病気問題」を見てみましょう。
【問題】
ある特殊なアジアの病気が流行し、600人の命が危険にさらされています。対策として2つのプログラムが提案されました。《ポジティブ・フレーム》
* プログラムA:200人が助かる。
* プログラムB:1/3の確率で600人全員が助かり、2/3の確率で誰も助からない。《ネガティブ・フレーム》
* プログラムC:400人が死ぬ。
* プログラムD:1/3の確率で誰も死なず、2/3の確率で600人全員が死ぬ。
ポジティブ・フレーム(助かる)で質問された場合、多くの人は確実なAを選びます。これは利得局面でのリスク回避的な選択です。
一方、ネガティブ・フレーム(死ぬ)で質問された場合、多くの人はDを選びます。これは損失局面でのリスク追求的な選択です。
しかし、よく見るとAとC、BとDは、それぞれ全く同じ結果を意味しています。ただ「助かる」という言葉で表現するか、「死ぬ」という言葉で表現するかの違いだけで、人々の選択は180度変わってしまうのです。
【ビジネスでの応用】
* マーケティング:「脂肪分1%含有」と表示するより、「脂肪分99%カット」と表示する方が、はるかに健康的に聞こえます。
* 交渉・プレゼンテーション:新しいプロジェクトを提案する際、「この案を採用すれば、シェアが5%拡大します」と利得を強調するだけでなく、「現状維持では、ライバルにシェアを5%奪われます」と損失を回避できる点を訴えることで、相手の意思決定を促すことができます。
* 初期設定(デフォルト)の効果:私たちは、特に理由がなければ初期設定のままにしておく傾向があります。臓器提供の意思表示カードにおいて、「提供しない」をデフォルトにしている国では提供率が低く、「提供する」をデフォルトにしている国では提供率が劇的に高くなるという事例は、この効果の強力さを示しています。
なぜ私たちは「お互い様」で行動するのか?- 社会的選好
標準的経済学の「経済人」は、他者を顧みず自己の利益だけを追求します。しかし、現実の私たちはそれほど利己的ではありません。ボランティア活動や献血が存在し、無人の野菜販売所が成り立つのはなぜでしょうか。
それは、私たちが「社会的選好」、つまり自分だけでなく他者の利益や、社会的な公正さも考慮に入れて行動する性質を持っているからです。
最終提案ゲームが示す「公正さ」
この性質を明らかにする有名な実験が「最終提案ゲーム」です。
【ルール】
1. あなた(提案者)は1000円を与えられます。
2. あなたは、その1000円を見知らぬ相手(応答者)とどう分けるかを提案します。
3. 相手があなたの提案を受け入れれば、その通りに分配されます。
4. 相手が提案を拒否すれば、2人とも1円ももらえません。
もし両者が「経済人」なら、あなたは相手に1円だけを提案するはずです。なぜなら、相手にとっては0円より1円もらう方が得なので、拒否しないはずだからです。
しかし、世界中で行われた実験の結果は、この予測を裏切ります。
* 提案者の多くは、40%~50%という非常に公平な提案をします。
* 応答者は、提案額が20%~30%を下回ると、たとえ自分の取り分がゼロになるとしても、その不公平な提案を拒否(処罰)することが多いのです。
これは、私たちが単なる利得の最大化だけでなく、「公正さ」を強く求めていることを示しています。不公平な相手に対しては、たとえ自分がコストを払ってでも罰を与えたいという感情(利他的処罰)が働くのです。
強い互酬性:善意には善意を、悪意には悪意を
この「公正さ」の感覚は、「強い互酬性」という概念で説明されます。これは「お互い様」の精神であり、相手が協力的ならば自分も協力し、相手が非協力的ならば自分も非協力的になる、あるいは罰を与えるという行動原理です。
この強い互酬性が、社会における信頼関係や協力関係を支える基盤となっています。ビジネスにおいても、短期的な利益のために相手を裏切るような行為は、長期的には評判を落とし、誰からも協力されなくなるという結果を招きます。公正な取引を心がけ、相手の善意に善意で応えることが、最終的には自分自身の利益にもつながるのです。
まとめ:ビジネスの武器としての行動経済学
本書『行動経済学~経済は「感情」で動いている~』は、私たちの意思決定が、自分で思っている以上に「不合理」であり、感情や直感、そして他者との関係性の中で揺れ動いていることを明らかにしました。
私たちが持つ心のバイアスは、決して欠陥ではありません。それは、人類が進化の過程で生き残るために身につけてきた、思考のショートカットであり、社会を形成するためのメカニズムでもあります。
重要なのは、自分や他者がそのようなバイアスを持っていることを自覚し、理解することです。
- 重要な意思決定をするときは、アンカリングされていないか、利用可能性の高い情報にだけ頼っていないか、一歩引いて考えてみる。
- 交渉やプレゼンでは、相手が「損失」をどう感じるかを考慮し、効果的なフレームで伝える。
- 組織の改革を進めるときは、現状維持バイアスが働くことを前提に、変化への不安を丁寧に取り除く。
- チームの協力を引き出すためには、短期的なインセンティブだけでなく、公正さや互酬性に根ざした信頼関係を築く。
行動経済学の知見は、あなたを完璧な「経済人」に変える魔法ではありません。しかし、人間という「感情で動く」存在を深く理解するための強力なレンズを与えてくれます。このレンズを通して世界を見ることで、あなたはきっと、ビジネスと人生における、より賢明な航海士となることができるでしょう。