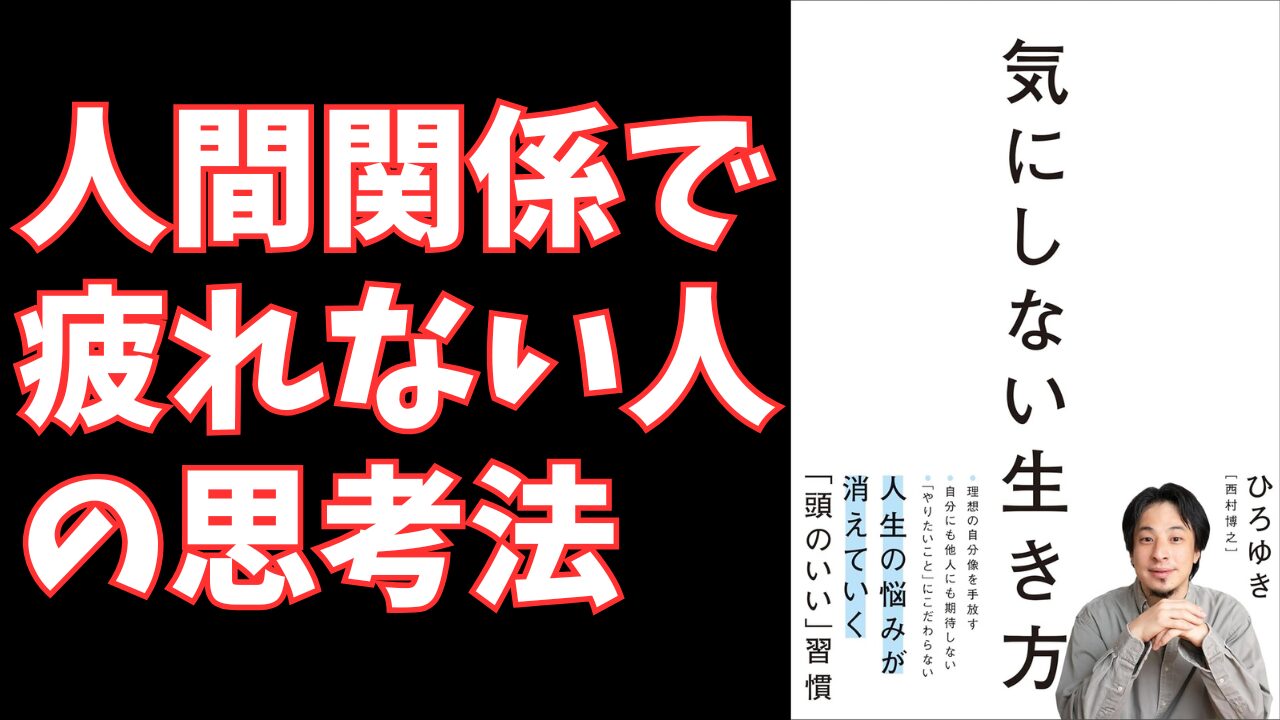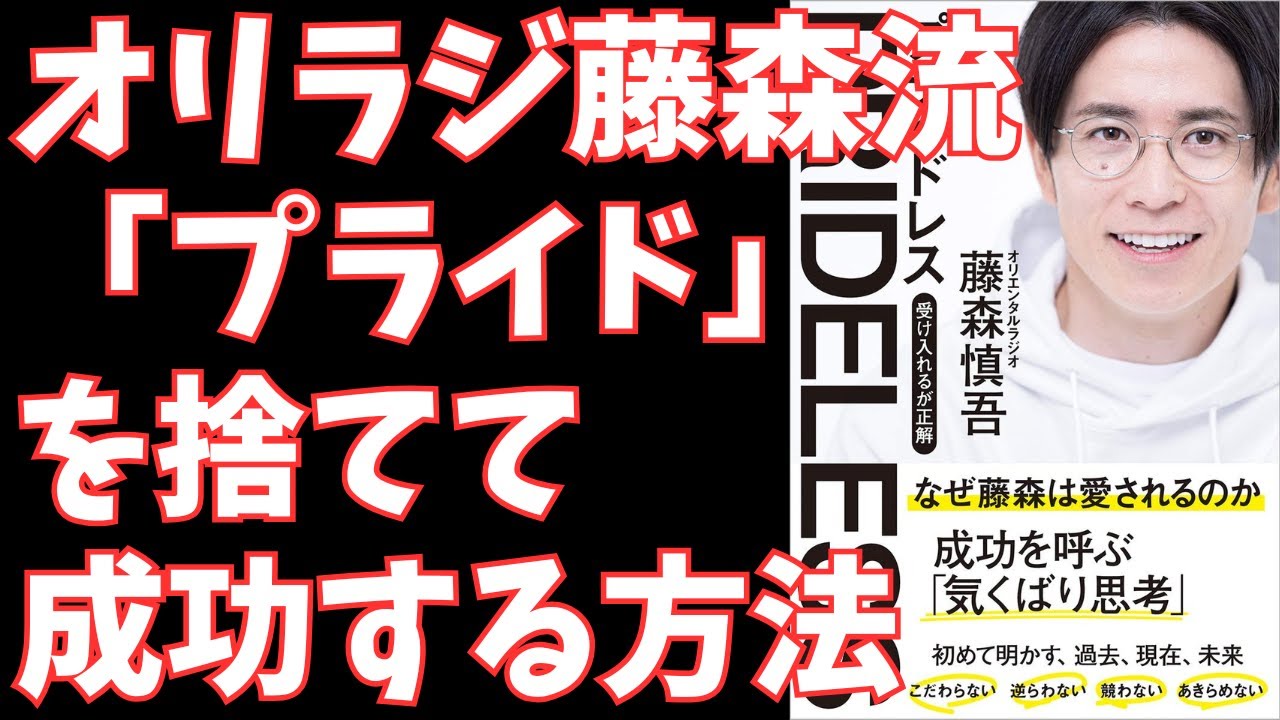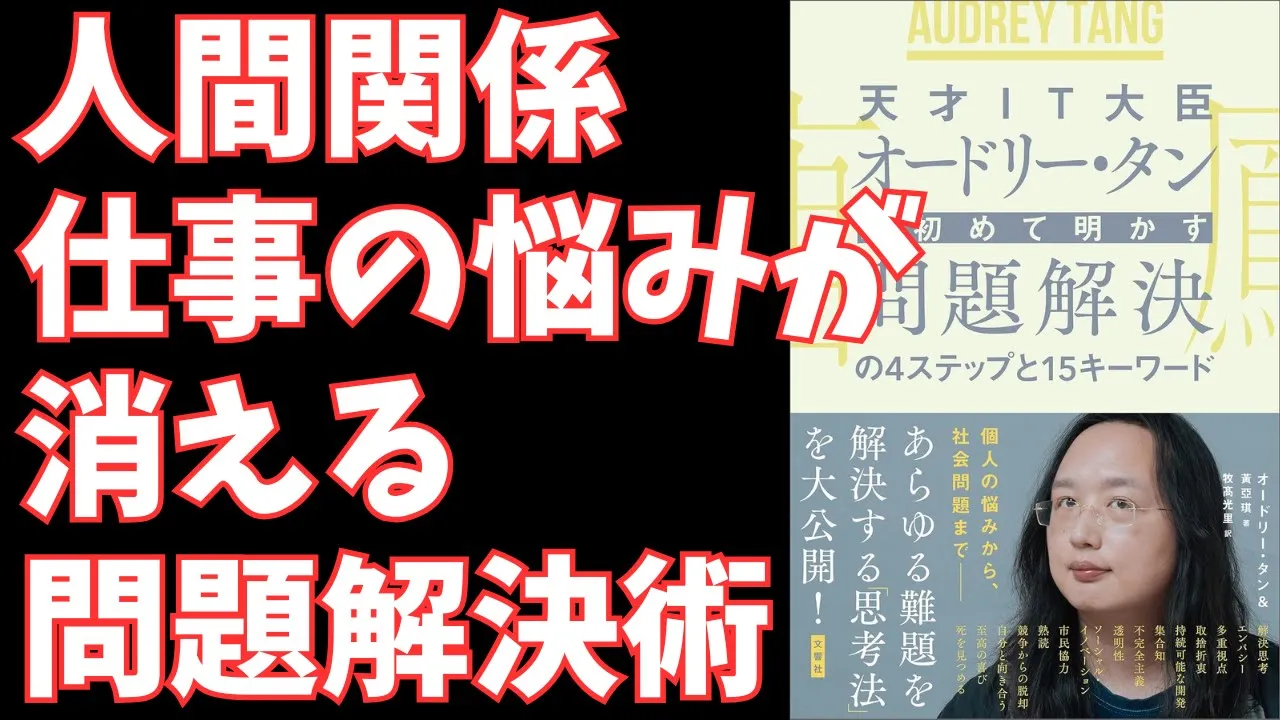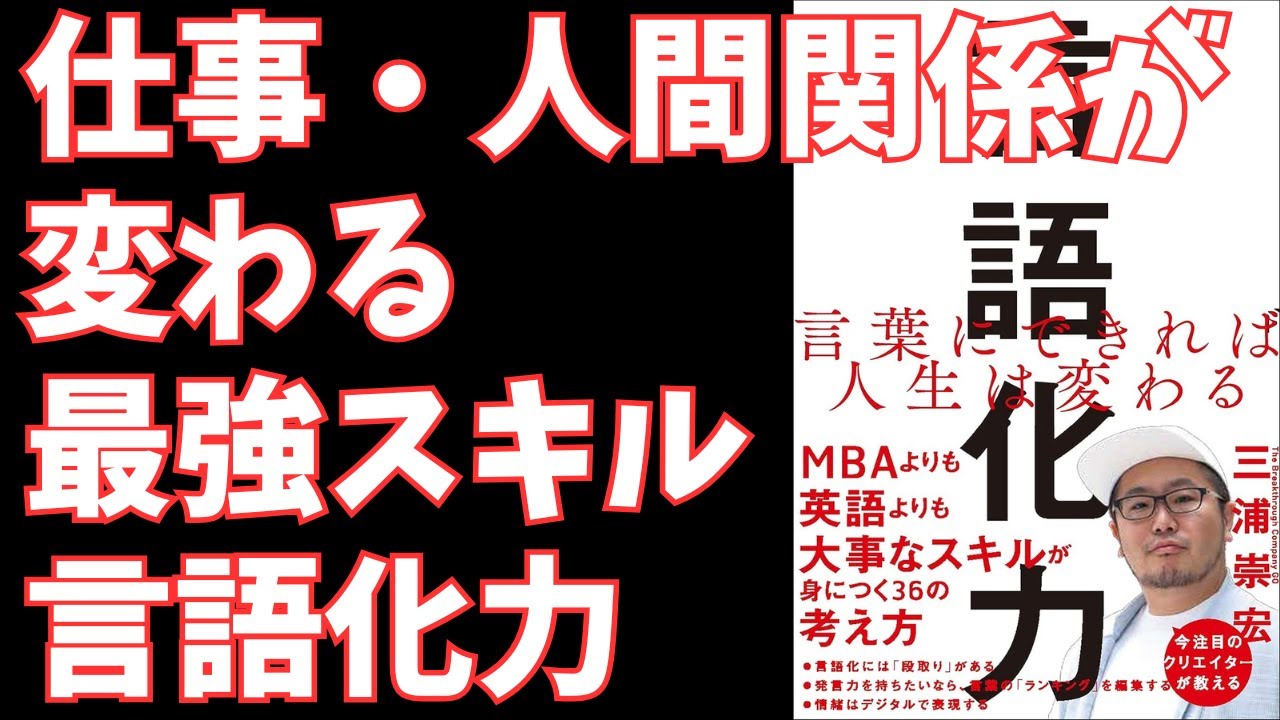なぜ、あなたのチームは「指示待ち」なのか?『だから僕たちは、組織を変えていける』に学ぶ、自走する組織の作り方
この記事では、書籍『だから僕たちは、組織を変えていける』を基に、現代の組織が抱える「息苦しさ」の正体と、それを解消し「やる気に満ちた自走するチーム」を作るための具体的な方法を解説します。社会の変化に組織が追いついていない現状を指摘し、変革の鍵となる「心理的安全性」と「成功循環モデル」について、忙しいビジネスパーソンにも分かりやすく要約します。
本書の要点
- 社会は指数関数的に変化していますが、多くの組織は旧来の「工業社会型」の統制モデルから脱却できていません。
- これからの「知識社会」で価値を生むのは、メンバーが自ら考え動く「自走する組織」です。
- 組織変革は「結果」からではなく「関係の質」から始めるべきです(成功循環モデル)。
- 「関係の質」の核心は、誰もが本音で話せる「心理的に安全な場」を作ることです。
- メンバーの「行動の質」を高めるには、アメとムチ(外発的動機)ではなく、「自律性・有能感・関係性」を満たす内発的動機づけが不可欠です。
なぜ、あなたの組織は「変われない」のか?
「最近の若手は指示待ちで、主体性がない」
「チームに活気がなく、会議でも誰も発言しない」
「ルールで縛らないと、メンバーがサボるのではないか不安だ」
多くのリーダーが、このような悩みを抱えています。しかし、本書『だから僕たちは、組織を変えていける』は、その原因はメンバー個人にあるのではなく、社会の変化と組織のあり方との間に生じた「ズレ」にあると指摘します。
私たちは今、半導体の性能向上に牽引され、社会が指数関数的に変化する時代に生きています。一方で、多くの組織は、いまだに「工業社会」の古いパラダイム(考え方)に基づいたままです。
- 工業社会の組織: トップダウンで統制し、業務を標準化・効率化することで価値を生む(統制する組織)。
- 知識社会の組織: 変化に適応し、斬新なアイデアや創造性で価値を生む(自走する組織)。
社会が「知識社会」に移行したにもかかわらず、組織が「工業社会」のままでは、メンバーの主体性や創造性は発揮されません。むしろ、古い組織モデルがメンバーの「やる気」を奪っているのです。
本書は、このギャップを埋め、やる気に満ちた「やさしいチーム(=自走する組織)」を作るための具体的なメソッドを提示しています。
目指すべきは「統制」から「自走」へ
著者が提唱する、これからの知識社会で目指すべき組織像は、次の3つのモデルです。
- 学習する組織: 顧客の幸せを探求し、常に新しい価値を生み出す。
- 共感する組織: 社会の幸せを探求し、持続可能な繁栄をわかちあう。
- 自走する組織: 社員の幸せを探求し、多様な人が自ら考え協働する。
これらは、トップがすべてを管理し、メンバーが歯車のように動く「統制する組織」とは対極にあります。例えば、指揮者不在でも世界的な演奏をする「オルフェウス管弦楽団」のように、メンバー一人ひとりがリーダーシップを発揮し、緊密に対話しながら価値を共創する組織です。
すべては「関係の質」から始まる
では、どうすれば「自走する組織」になれるのでしょうか?
多くの組織が陥る間違いは、「結果の質」をいきなり求めようとすることです。「売上目標を達成しろ!」と圧力をかけると、人間関係が悪化し(関係の質の低下)、メンバーは思考停止に陥り(思考の質の低下)、指示待ちか防衛的な行動しか取らなくなります(行動の質の低下)。これは「失敗の循環」です。
本書が示す「成功循環モデル」は、その逆からスタートします。
①関係の質 → ②思考の質 → ③行動の質 → ④結果の質
まず「関係の質」を高めることで、思考が前向きになり(思考の質)、自発的な行動が生まれ(行動の質)、自然とパフォーマンスが向上する(結果の質)というサイクルです。
組織変革の第一歩は、ノルマやルール作りではなく、「信頼関係の構築」にあるのです。
STEP1. 関係の質を高める「心理的安全性」の作り方
「関係の質」を高める核心こそ、近年注目されている「心理的安全性」です。
心理的安全性とは、チームの中で「こんなことを言ったら馬鹿にされないか」「無能だと思われないか」といった4つの不安(無知・無能・否定・邪魔)を感じることなく、誰もが本音で発言し、挑戦できる状態を指します。
Googleが巨額の資金を投じた「プロジェクト・アリストテレス」でも、チームの生産性を決める最も重要な因子は、メンバーの能力や経歴ではなく、「心理的安全性」であることが発見されました。
「犯人探し」という大罪
心理的安全性を最も破壊する行為が「犯人探し」です。ある病院の看護チームを対象とした実験では、ミスに対して厳しく罰するチーム(厳しいチーム)は、ミスの報告件数が少ないように見えました。しかし実際は、ミスを隠蔽していただけで、実際のミス発生率は高かったのです。
失敗を罰する組織では、誰もリスクを取らなくなり、組織の学習能力は失われます。
リーダーこそ「強がりの仮面」をはずそう
心理的安全性を確保するために最も影響力があるのは、リーダーの行動です。
多くの場合、リーダーは「弱みを見せてはいけない」「なめられてはいけない」という「強がりの仮面」をつけています。しかし、その完璧主義やコントロール欲求こそが、メンバーを萎縮させ、場の安全性を壊しているのです。
リーダーがすべきことは、自ら「素の自分」を見せる勇気を持つこと。自分の弱さや失敗談を率直に開示することで、メンバーは「この場は強がらなくてもいいんだ」と安心し、本音で話せるようになります。
STEP2. 思考の質を高める「仕事の意味」の共有
関係の質が改善し、場が安全になると、メンバーの「思考の質」を高めるステップに進みます。ここで重要なのは「仕事の意味(WHY)」の共有です。
人は、やらされ仕事(しなくちゃ)では動きませんが、その仕事の意味に腹落ちすれば(しよう・したい)、自ら動き出します。
社会にとっての意味(パーパス)
かつてスカンジナビア航空は、顧客と社員が接する「15秒」を「真実の瞬間」と名付け、「顧客に最高の体験を届けること」を全社の北極星(パーパス)として共有し、奇跡の黒字転換を果たしました。
組織のパーパス(ミッション・ビジョン・バリュー)が明確で、それが単なる「お題目」ではなく、現場の行動にまで浸透していることが重要です。
自分にとっての意味(コーリング)
ある研究では、病院の掃除係でも、自分の仕事を「義務(ジョブ)」と捉える人、「天職(コーリング)」と捉える人がいました。天職と捉える人は、「医師や看護師が治療に専念できるよう、効率よく掃除する」と自ら仕事に意味を見出し、患者を励ますなど、役割を超えた行動を取っていました。
どんな仕事でも、本人がその意味づけを変える(ジョブ・クラフティング)ことで、「天職」に変えることができるのです。
STEP3. 行動の質を高める「内発的動機づけ」
思考の質が高まり、「この仕事には意味がある」と感じられるようになったら、最後は「行動の質」です。
メンバーを自走させるエンジンは、アメとムチ(給料や罰則)といった「外発的動機づけ」ではありません。これらは単純作業には有効ですが、依存性を生み、創造性を奪います。
知識社会で必要なのは「内発的動機づけ」、すなわち本人の内側から湧き上がる「やる気」です。本書は、そのやる気を引き出す「黄金のスリーカード」を提示しています。
自律性(自分で選択したい)
多くの組織は、ルールや管理体制といった「組織の罠」や、上司の「責任感の罠(成果を求められるほど管理的になる)」によって、メンバーの自律性を奪っています。
「規律を最小化」し、信頼して任せる(ただし放任ではない)ことが重要です。有能感(能力を発揮したい・成長したい)
簡単すぎず、難しすぎない「最適な難易度」の課題(フロー体験)を与えることで、人は無我夢中になり、成長を実感できます。関係性(人とつながりたい・貢献したい)
人は孤立していてはやる気が出ません。組織心理学者のアダム・グラントの研究では、最も成功するのは、見返りを求めず他者に貢献する「ギバー(与える人)」でした。助け合い、貢献しあえる関係性が、個人の幸福と組織の成果を両立させます。
変革は「たったひとり」から始められる
「こんな大きな組織、自分ひとりでは変えられない」と思うかもしれません。しかし、ガンジーはたったひとりでインド独立の運動を始め、非暴力・不服従の対話を続けて世界を動かしました。
組織変革も同じです。まずは自分自身が変わる(インサイド・アウト)ことから始まります。
そして、自分が変えられないこと(関心の輪)に文句を言うのではなく、自分が直接影響を及ぼせる範囲(影響の輪)──例えば、自分のチームや、たった数人の部下との関係──にエネルギーを集中させるのです。
あなたの小さな「影響の輪」で「成功循環モデル」を回し始めれば、そのポジティブな変化は必ず周囲に伝播し、やがて組織全体を動かす「ティッピングポイント」が訪れます。
本書は、組織を変えたいと願うすべての「スモールイノベーター」に、その勇気と具体的な武器を与えてくれる一冊です。