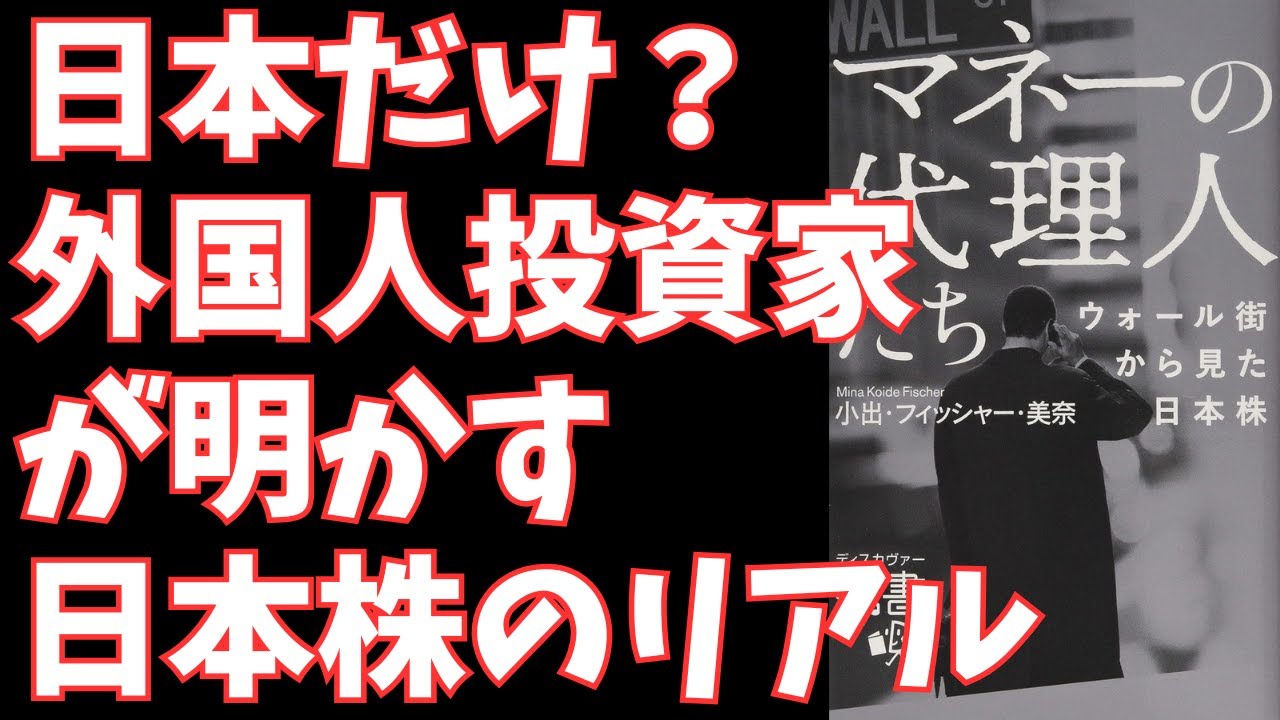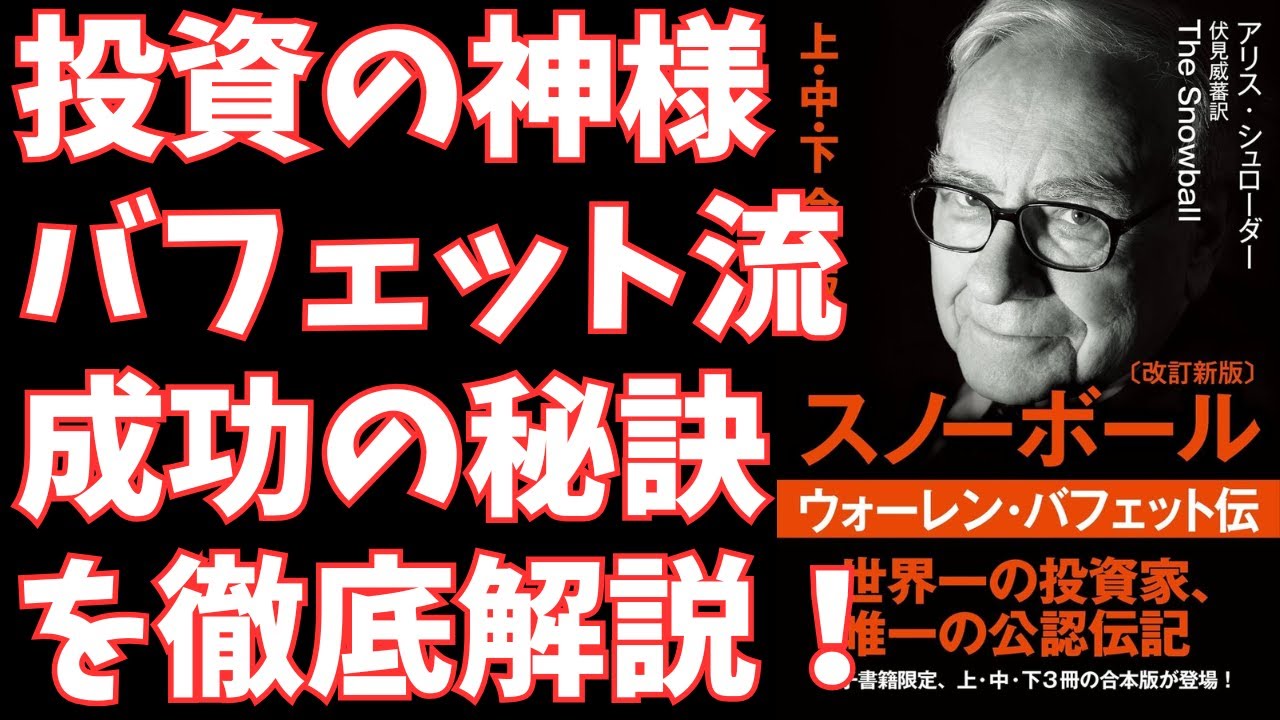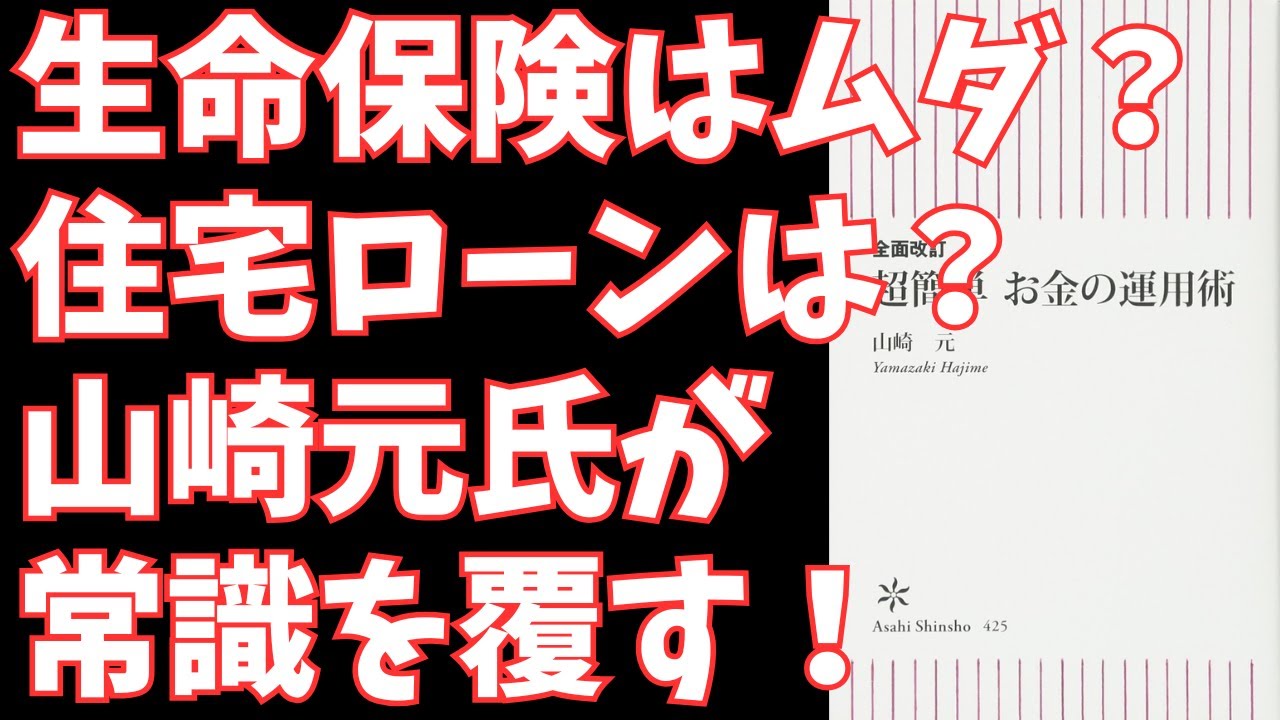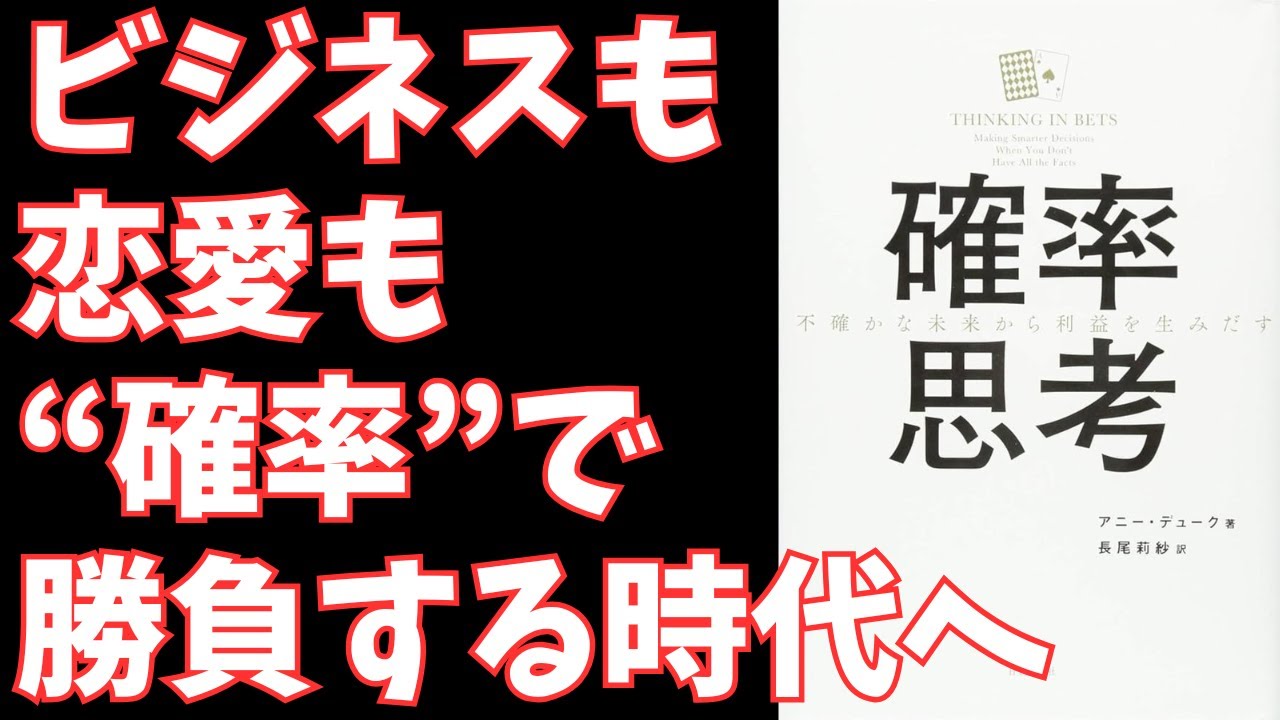専門知識だけでは危険?『アメリカの大学生が学んでいる本物の教養』に学ぶ、生涯賃金を高める「思考の文法」
「教養」と聞くと、あなたは何を思い浮かべるでしょうか。「エリートが嗜む高尚な趣味」「役に立つか分からない雑学」といったイメージかもしれません。しかし、本書『アメリカの大学生が学んでいる本物の教養』は、その認識を根底から覆します。
著者の斉藤淳氏は、教養とは「特定の目的」のために身につけるものではなく、「自分の中心」を構成する人生哲学や価値観を形成し、それを守るための「知的バックボーン」 であると説きます。
この記事では、本書で提示される「本物の教養」とは何か、そしてそれがなぜ専門知識以上に、現代を生きるビジネスパーソンの「生涯賃金」や「思考力」に直結するのかを、具体的な事例と共に解き明かしていきます。
本書の要点
- 教養とは、特定の目的のためでなく、「自分の中心」を構成し、「思考の文法」を習得するプロセスである。
- 専門知識は陳腐化するが、教養教育(リベラル・アーツ)を受けた人の方が生涯賃金が高い傾向にある。
- 「知っていること」自体に価値はなく、「知識を使ってどう考えるか」が重要である。
- 教養人は「井戸の掘り方」を知っており、権威におもねらず、知的謙虚さと批判精神を持つ。
- 本書のゴールは、知識をもとに自分の意見を形成し、他者と合意形成を目指す「よき思考者(Good Thinker)」になること。
なぜ、専門知識だけでは「稼げなく」なるのか?
「教養よりも、まずは仕事に直結する専門スキルだ」
多くのビジネスパーソンがそう考えるのも無理はありません。しかし、本書は衝撃的な研究結果を提示します。
スタンフォード大学の研究によると、早期に職業教育(専門教育)を受けた人よりも、教養教育を受けた人の方が「生涯賃金」が高かった というのです。特にドイツのデータ分析では、教養教育を受けた者の生涯稼得賃金が、職業教育を受けた者に対して24%も上回っていました。
なぜ、このような逆転が起こるのでしょうか。
理由は明快です。専門知識は、遅かれ早かれ「陳腐化」するから です。
あなたが今、最先端の武器として使っているプログラミング言語やマーケティング手法も、5年後、10年後には時代遅れになっているかもしれません。その知識が最新である間は大きな武器になりますが、陳腐化した途端に丸腰同然になってしまいます。
一方、教養(リベラル・アーツ)とは、特定の知識そのものではありません。それは、「思考の文法」 であり、時代がどれだけ移り変わっても有意義に「学びつづけること」「考えること」「判断すること」 を可能にする土台です。
変化の激しい現代社会において、専門知識だけを追い求めることは、実は非常にリスクの高い選択なのです。
あなたの「知っている」は価値がない?
では、「教養=物知り」ということでしょうか? 著者はそれも明確に否定します。現代において、「知っていること」それ自体の価値は暴落している からです。
本書で挙げられる「ハードディスク・ドライブの値段」の例は象徴的です。
著者が大学生の頃、20MB(メガバイト)のハードドライブは20万円もしました。つまり、1MBあたり1万円です。
それが今ではどうでしょう。512GB(ギガバイト)のストレージを持つiPhoneが10万円ちょっとで手に入ります。これは、30年前なら51億2000万円にも相当する容量です。
「知識の貯蔵装置」の値段がこれほどまでに安くなったということは、知識を「溜めておくこと」自体の価値が劇的に下がったことを意味します。私たちは、膨大な知識を安価な外部デバイスに「外注」できるようになったのです。
もはや「物知り」であるだけでは価値がありません。はるかに重要なのは、「その知識を使って何を考えるか」 なのです。
あなたは「水の選び方」と「井戸の掘り方」どちらを学んでいるか?
本書では、知識との向き合い方について、日本の教育とアメリカの教育を対比させた巧みな比喩が登場します。
日本の教育:「おいしいペットボトル入りミネラルウォーターの選び方」を教える
- これは「知識の消費」です。すでに体系化された学説や史実を、教科書を通じて効率よくインプットします。
アメリカの教育:「井戸の掘り方」を教える
- これは「知識の生産体験」です。例えば歴史の授業でも、単に史実を暗記するのではなく、「なぜ起こったのか」「自分はどう考えるか」を大量の文献を読み込んだ上で 議論 します。
「選び方」を知っていても、店からペットボトルが消えたら水を確保できません。しかし、「井戸の掘り方」を知っていれば、自力で水源を探し、水を確保できます。
ビジネスパーソンに必要なのは、後者の「井戸の掘り方」です。
自分で知識生産の試み(=井戸を掘る)を体験し、その大変さを知っている人は、2つの重要な態度を身につけます。
- 感謝と謙虚さ: 他者が生み出した知識(水)が、どれほどの時間や労力の賜物であるかを実感でき、学びに対して真摯になれます。
- 批判精神: 知識の源泉を探ることの大変さを知っているからこそ、どこかの誰かが流布する「安易な正解」に惑わされず、批判的に捉え、自分なりに考える知的体力が身につきます。
日常を「学びの場」に変える、よき思考者の習慣
「井戸を掘る」というと大袈裟に聞こえるかもしれませんが、教養はアカデミックな場や難解な本の中にだけあるのではありません。著者は、学ぶ機会は日常にあふれている と言います。
その好例が、著者自身のコンビニエンスストアでの夜勤アルバイトの経験です。
著者は当時、ただレジを打つだけでなく、おにぎりのパッケージの裏側を見て、どの工場から運ばれてきたかを確認していたといいます。
地元の山形では仙台の工場から、首都圏では埼玉の工場から。この情報から、地域の物流インフラや経済活動の重心がどこにあるのか を窺い知ることができました。
また、大学で経済学を学んでいた著者は、店を訪れる人々の購買行動を「ミクロ経済学的に眺め、『なぜ、人はこれを買うのか』などと仮説を立てつつ」 レジを打っていたそうです。
これは、自身の体験や実践を通じて「世界の手触りを確かめる」行為であり、学んだ「思考のフレームワーク」を使って日常を分析する、立派な教養の実践です。
「事実」に惑わされないための「推論のリテラシー」
情報が錯潔する現代では、何が正しいのかを見極めることが非常に困難です。専門家でさえ、奇想天外な陰謀論にハマってしまうことがあります。
教養人は、事実を100%見抜こうとする傲慢さ(それは不可能です)ではなく、「より確からしいもの」を見つけるための 「推論のリテラシー」 を持っています。
本書では、新型コロナウイルスの「mRNAワクチン」に対する著者の判断プロセスが紹介されています。
著者は、いわゆる「反ワクチン派」の言説の多くが、「素人が思いつきと妄想で書き散らかしたブログ」の域を出ず、確たるエビデンスもロジックもないと判断しました。
一方で「ワクチン推奨派」の議論は、専門家を中心に、臨床試験の結果というエビデンスに基づき、透明性と反証可能性(間違いを検証できる仕組み)が担保されていました。
これは「専門家が言うことはすべて正しい」ということではありません。重要なのは、「情報の発信源」、つまり「どのような作業手続きと環境でその知識が生産されたか」を見極めることです。
ビジネスシーンで溢れる情報やデータを扱う際にも、このリテラシーは不可欠です。
有名なエピソードとして、第二次世界大戦中の「戦闘機の被弾箇所」の話があります。
空軍が、基地に「生還した戦闘機」の被弾箇所を分析したところ、翼や胴体に弾痕が集中していました。では、そこを強化すればよいのでしょうか?
答えは「ノー」です。
統計学者は、「見えないもの」、すなわち 「生還できなかった戦闘機」 に目を向けました。翼や胴体が撃たれても帰ってこれたということは、そこは致命傷ではなかった。本当に強化すべきは、弾痕がなかった箇所(=撃たれたら墜落してしまう致命的な箇所) だったのです。
私たちは目に見えるデータ(生存バイアス)に惑わされがちです。「成功事例」だけを分析しても、本当の成功要因は見えてきません。「見えないデータ(失敗事例や、市場に出なかったアイデア)」に目を向ける批判的な思考こそが、教養ある態度なのです。
「意見がない」を卒業する。自分の頭で考える技術
「あなたはどう思う?」と聞かれて、言葉に詰まってしまう。
日本人は、教育や同調圧力の影響で、自分の意見を持つことや表明することが苦手とされています。
しかし、著者は「意見は正解である必要はない」と断言します。意見とは、思考の「終着点」ではなく「出発点」 なのです。
本書では、意見を形成するための具体的なトレーニング法がいくつも紹介されています。
トレーニング法1:「HOW」ではなく「WHY」を問う
例えば、「第一次世界大戦は『いかに(HOW)』起こったのか?」という問いの答えは、「サラエボ事件が引き金となり…」という事実確認(知識の消費)で終わってしまいます。
しかし、「第一次世界大戦は『なぜ(WHY)』起こったのか?」と問われれば、どうでしょう。
帝国主義、同盟関係、ナショナリズムなど、様々な要因を考察し、自分なりに「戦争が起こるメカニズム」を考える(知識の生産)必要があります。
「HOW」ではなく「WHY」を問うことが、思考を深め、意見を生み出します。
トレーニング法2:よくある問いを「逆側から」問う
選挙シーズンになると、「なぜ人々は投票に行かないのか?」という問いが溢れます。しかし、これには「投票に行くのが当然」という前提が隠されています。
ここで、問いを「逆側から」立ててみます。
「そもそも、なぜ人々は投票に行くのか?」
この「行く動機」(例:自分の1票で結果が変わりそう、お祭りとして楽しい)を考えることで、初めて「行かない理由」(=その動機が欠如している)が見えてきます。
これはビジネスにも直結します。
「なぜ、この新製品は売れないのか?」と嘆く前に、「そもそも、なぜ顧客は(ライバル商品ではなく)これを買うのだろうか?」 という「買う動機」を深く問い直すことが、本質的な課題発見につながるのです。
まとめ:教養は、あなたの人生を「格段におもしろくする」
本書が提示する教養とは、知識の量を競うものではありません。
それは、複雑で正解のない世界の中で、常に「自分の中心」に立ち返り、「自分にとっての正解」を導き出すための知的体力です。
時には、知ることで「知らなければ考えずに済んだこと」を考えなくてはならなくなる、苦しい道かもしれません。
しかし、学ぶことで目に映る世界の輪郭はより鮮明になり、人生の選択肢は確実に広がります。
著者は、かつて公衆衛生学を学んだ知識が、十数年後、自身が経営する塾でパンデミックに対応する際に思いがけず役立った経験を語ります。
何がいつ役に立つかわからない。だからこそ、「役に立つこと」だけを学ぶのではなく、好奇心に従って学び続ける。その蓄積こそが教養であり、「未来を見通す力」となります。
本書のゴールは、単なる物知りではなく、「Good Thinker(よき思考者)」になること。
専門知識という名の「ペットボトルの水」に依存するのをやめ、自ら「井戸を掘る」力を身につけることで、あなたの人生は格段におもしろくなるはずです。