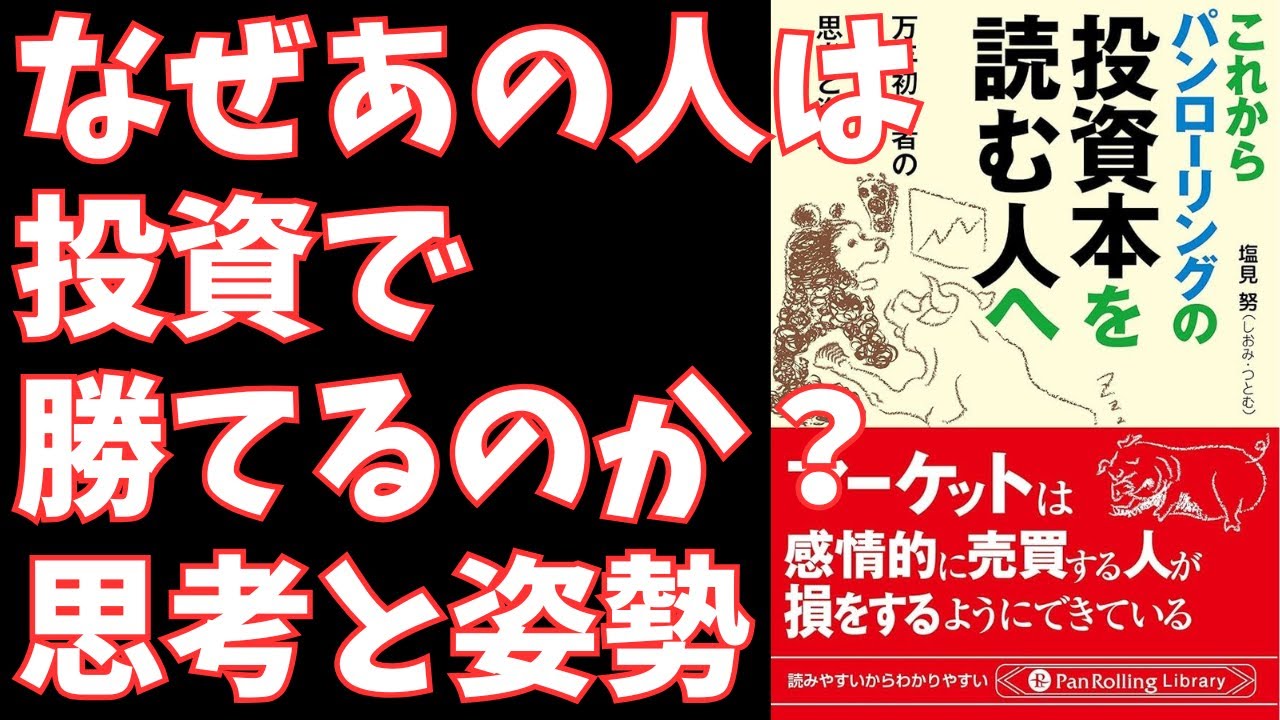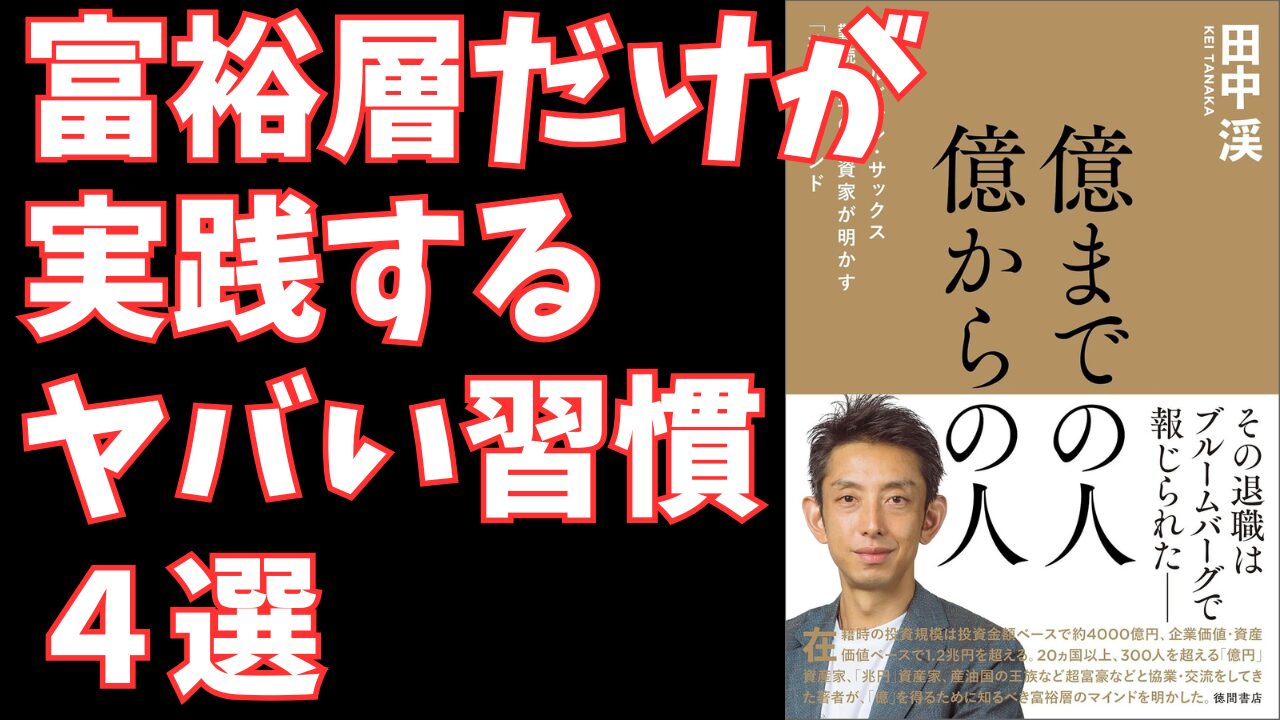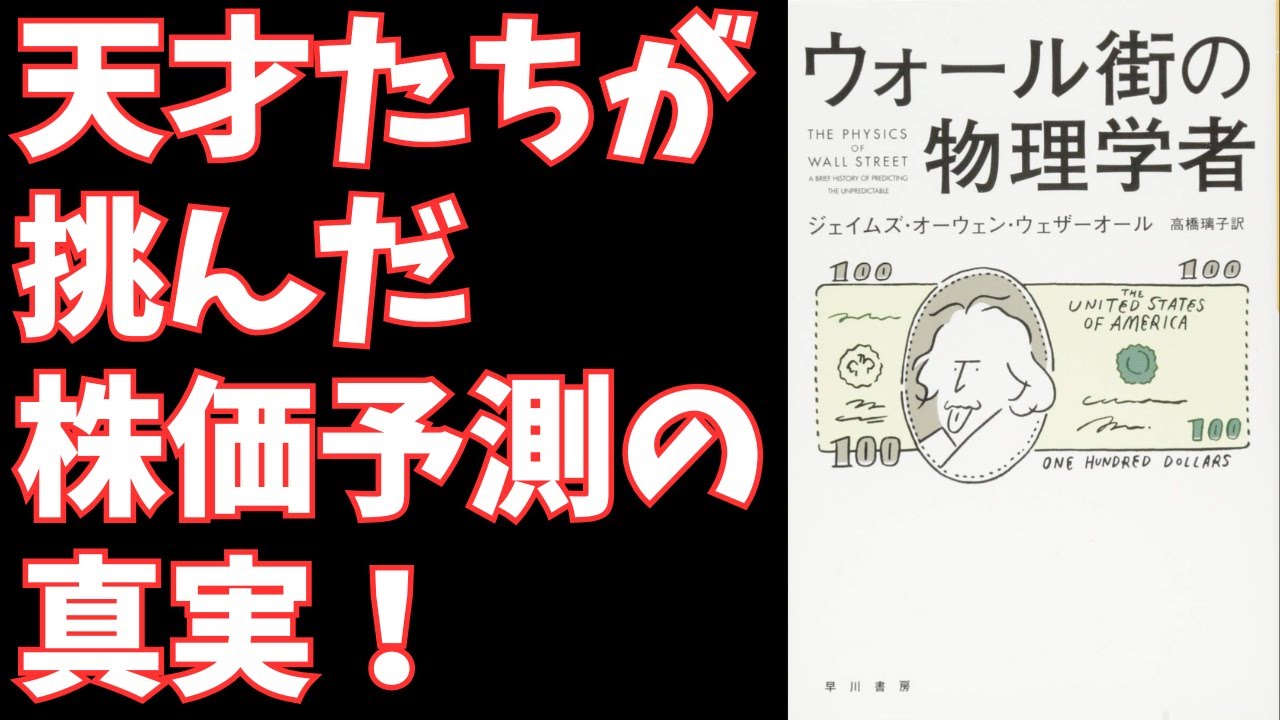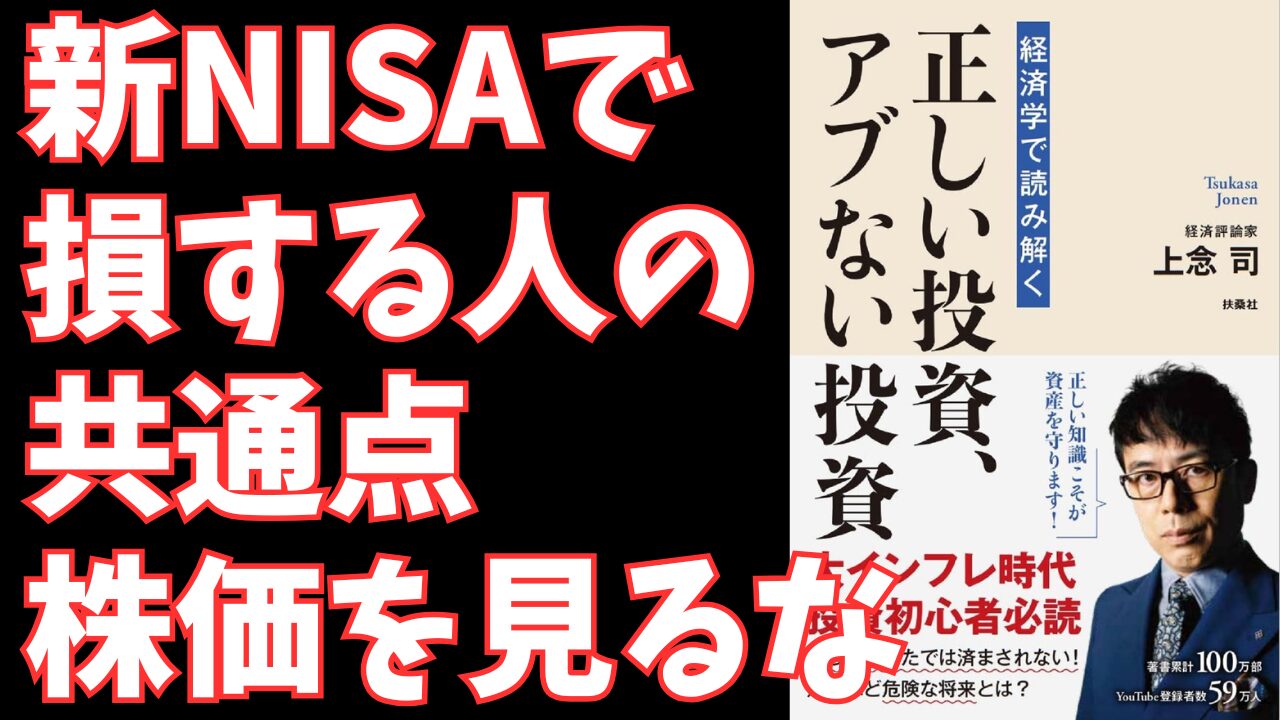円安は日本経済の最強の追い風!『円安好況を止めるな!』から学ぶ金利と為替の真実
本書は、数量政策学者である髙橋洋一氏が、世間に蔓延する「悪い円安論」をデータと経済理論を用いて論破し、「円安こそが日本経済回復のチャンスである」と説いた一冊です。マスコミが煽る不安とは裏腹に、円安は輸出企業だけでなく日本政府にも莫大な利益をもたらし、GDPを押し上げる要因となります。本書では、為替や金利の正しいメカニズム、中国ビジネスのリスク、そして個人が資産を守るための投資リテラシーまで、忙しいビジネスパーソンが知っておくべき経済のファクトが網羅されています。
本書の要点
- 円安は「近隣窮乏化政策」であり、自国のGDPにとってはプラス要因である。
- 円安の最大の受益者は、膨大な外貨準備を持つ「日本政府」である。
- 安易な利上げは経済を冷え込ませるだけであり、日本は金融緩和を継続すべきである。
- 中国へのビジネス展開はカントリーリスクが高く、撤退または慎重な判断が必要である。
- 金融機関のポジショントークを鵜呑みにせず、正しい金融リテラシーを持つことが資産防衛の鍵となる。
「悪い円安」は大嘘? 円安が日本経済を救う理由
連日のニュースで「円安で日本経済は危機的状況だ」「物価高で生活が苦しい」といった報道を目にしない日はないでしょう。しかし、著者の髙橋氏はこれらを「マスコミによる印象操作」だと一刀両断します。
経済の基本原則として、自国通貨安はGDP(国内総生産)を押し上げるプラス要因です。これは国際経済学の常識であり、OECDの経済モデルでも「10%の円安で、1〜3年以内にGDPが0.4〜1.2%増加する」と分析されています。
円安になると、輸出主導のエクセレントカンパニー(優良企業)の業績が向上します。確かに輸入コストは上がりますが、日本経済全体で見ればプラスの方が大きいのです。実際に、2021年度の法人企業統計では、全産業の経常利益や利益剰余金が過去最高を記録しました。これは円安の恩恵を受けた結果です。
著者は、円安によって日本経済は「成長ゲタ」を履かせてもらっている状態だと表現しています。このチャンスを活かしきれていないのは、円安そのもののせいではなく、その果実(増えた税収など)を適切に再分配できていない政府の失策にあるのです。
円安の最大の勝者は「日本政府」
円安で誰が一番得をしているのでしょうか。輸出企業はもちろんですが、実は最大の受益者は日本政府です。
日本政府は「外国為替資金特別会計」として、約120兆円もの外貨(主に米国債)を保有しています。円安が進むと、この外貨資産の円換算価値が跳ね上がります。例えば、1ドル100円で買った資産が1ドル140円になれば、それだけで40兆〜50兆円もの含み益が生まれる計算になります。
著者はこの外貨準備を「埋蔵金」と呼び、国民のために売り払って還元すべきだと提言しています。しかし、財務省やマスコミはこの「政府のぼろ儲け」については一切触れず、「円安は大変だ」と不安ばかりを煽っています。ビジネスパーソンとしては、こうした「バランスシートの裏側」を見抜く視点を持つことが重要です。
「金利を上げろ」という無知な大合唱
米国FRB(連邦準備制度理事会)が利上げを行う中、「日本も利上げして円安を止めるべきだ」という意見が多く聞かれます。しかし、著者はこれを「無知の極み」と厳しく批判します。
為替レートは、基本的に日米のマネタリーベース(市場に供給されているお金の量)の比率で決まります。無理に金利を操作して為替をコントロールしようとするのは危険です。
特に参考すべき悪例として、ロシアのケースが挙げられています。ウクライナ侵攻後のルーブル急落に対し、ロシア中央銀行は金利を大幅に引き上げましたが、結果として国内経済に大打撃を与えました。日本も同様に、コストプッシュ型のインフレ(原材料高による物価上昇)に対して利上げを行えば、景気を冷やし、不況を招くだけです。
正しい処方箋は、金融緩和を継続して雇用を守りつつ、ガソリン減税や消費減税といった財政政策で物価高に対応することです。金融機関は金利が上がると利ザヤで儲かるため利上げを歓迎しますが、彼らのポジショントークに騙されてはいけません。
中国ビジネスは「海を渡るな」
グローバルビジネスにおいて、著者が強く警鐘を鳴らすのが「中国リスク」です。
円安の今は国内回帰の好機ですが、それ以上に中国という国の構造的リスクを理解する必要があります。
- 資本規制のリスク: 中国は共産主義国であり、投下した資本を自由に回収できません。最悪の場合、資産が没収される可能性があります。
- 不透明な統計: 中国のGDP統計は実態とかけ離れており、信用できません。失業率などの重要なデータも隠蔽されています。
- 中所得国の罠: 一人当たりGDPが1万ドルを超えると成長が鈍化する「中所得国の罠」に直面しており、かつてのような高度成長は見込めません。
これからの世界経済は、民主主義国と専制主義国のデカップリング(分断)が進みます。サプライチェーンを中国に依存し続けることは、経営上の致命的なリスクになり得ます。著者は「円安下の今こそ、海外ビジネス投資支援ではなく、国内回帰を推進すべきだ」と説いています。
個人投資家が持つべき「金融リテラシー」
最後に、私たち個人がどのように資産を守り、増やしていくべきかについて触れます。
岸田政権は「貯蓄から投資へ」と掲げていますが、著者は銀行や証券会社の言いなりになることに注意を促しています。
1. 金融機関の「おすすめ」は疑え
銀行や保険会社が勧める投資信託や変額保険は、手数料が高いだけで顧客にとってメリットが薄い商品が多いのが現実です。特に「貯蓄性のある保険」などは手数料の塊であり、著者は「保険は掛け捨て、資産運用は別で行うべき」と断言しています。
2. 株式投資の難しさを知る
株価は将来の収益予想と金利で決まりますが、その予測はプロでも困難です。安易にマスコミの情報や証券会社のセールストークを信じて短期売買を繰り返せば、手数料で損をするだけです。
3. おすすめの投資先は「国債」
著者が唯一、金融商品として推奨するのが「個人向け国債」です。
* 手数料がほとんどかからない。
* 元本割れのリスクがない。
* 銀行預金よりも金利が高いことが多い。
銀行は、自分たちが低金利で集めた預金で国債を買って運用し、その利ザヤで儲けています。ならば、個人が直接国債を買ったほうが合理的です。銀行が窓口で国債を積極的に売りたがらないのは、自分たちの儲けが減るからに他なりません。
また、不動産についても「持ち家より賃貸」を推奨しています。これからの日本で土地価格が上がり続ける保証はなく、多額のローンを背負って流動性の低い不動産を持つことはリスクが高いからです。
本書は、マスコミが垂れ流す悲観論を一掃し、データに基づいた明るい未来への道筋を示してくれます。
円安という「追い風」を嘆くのではなく、そのメカニズムを正しく理解し、ビジネスや投資に活かすことこそが、現代のビジネスパーソンに求められる姿勢なのです。
この要約を読み、より詳細な経済データや、著者の鋭い分析に触れたいと感じた方は、ぜひ本書を手に取ってみてください。世界経済の霧が晴れ、今やるべきことが明確に見えてくるはずです。