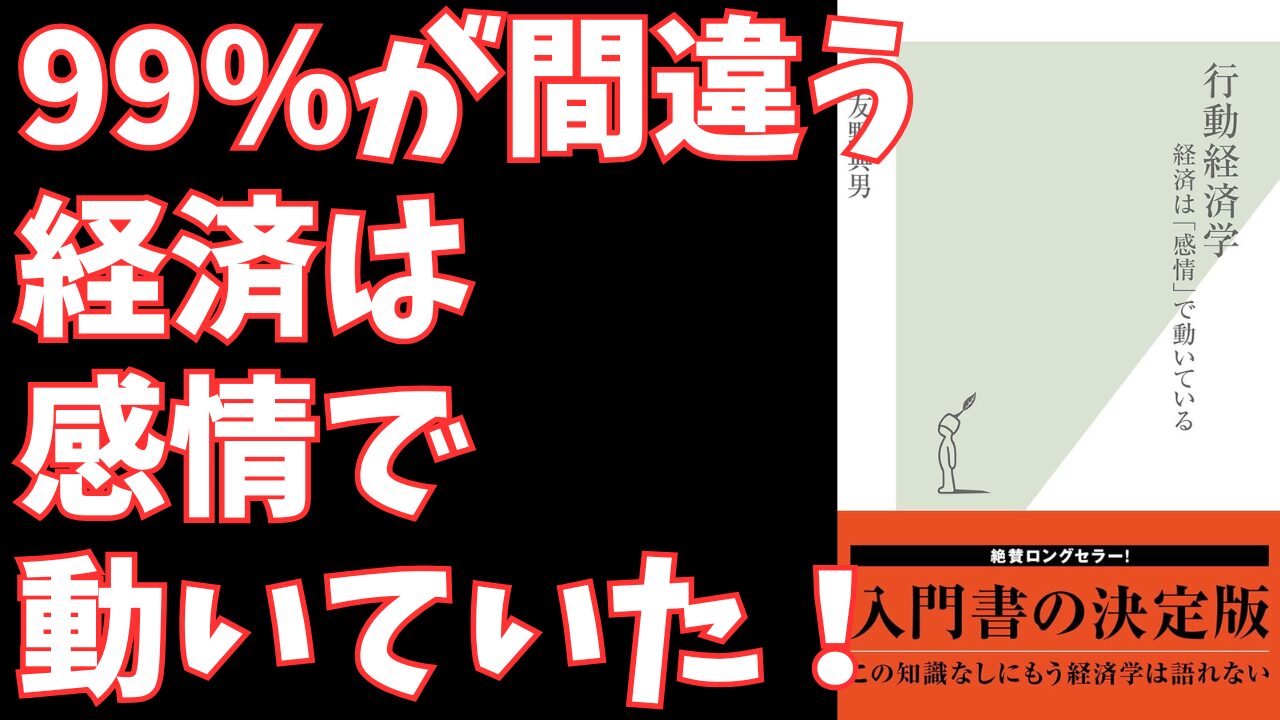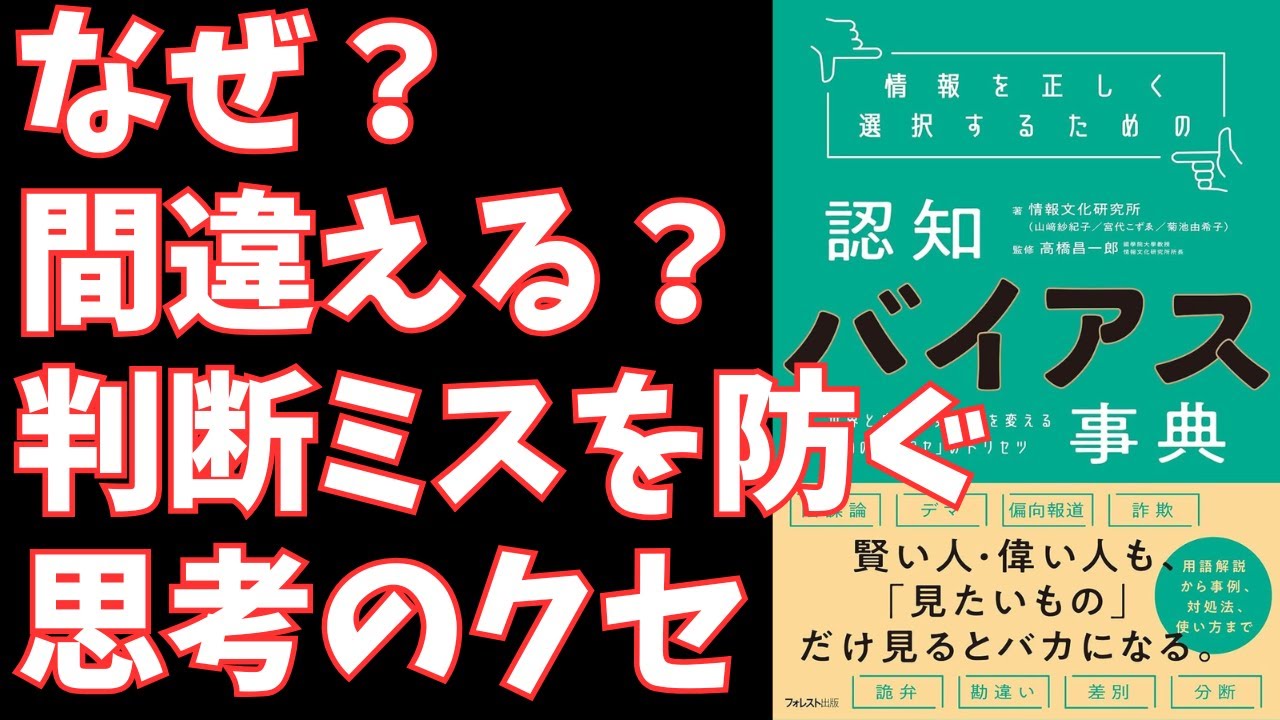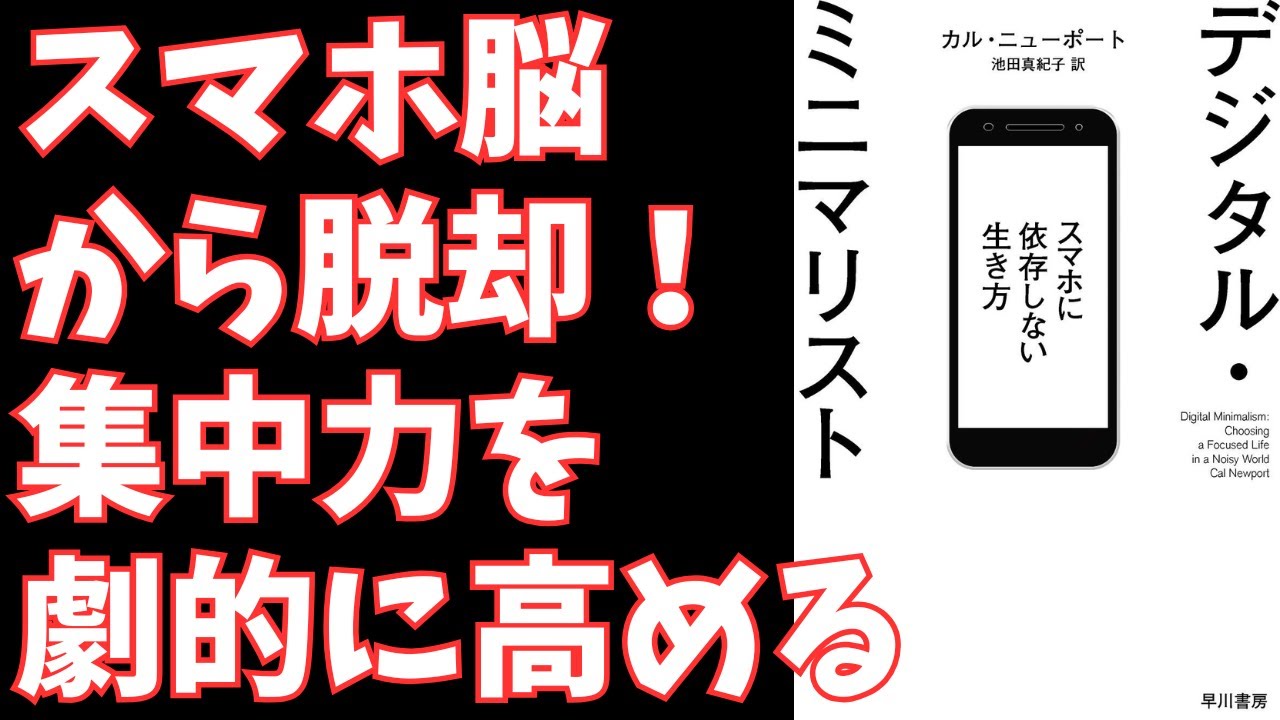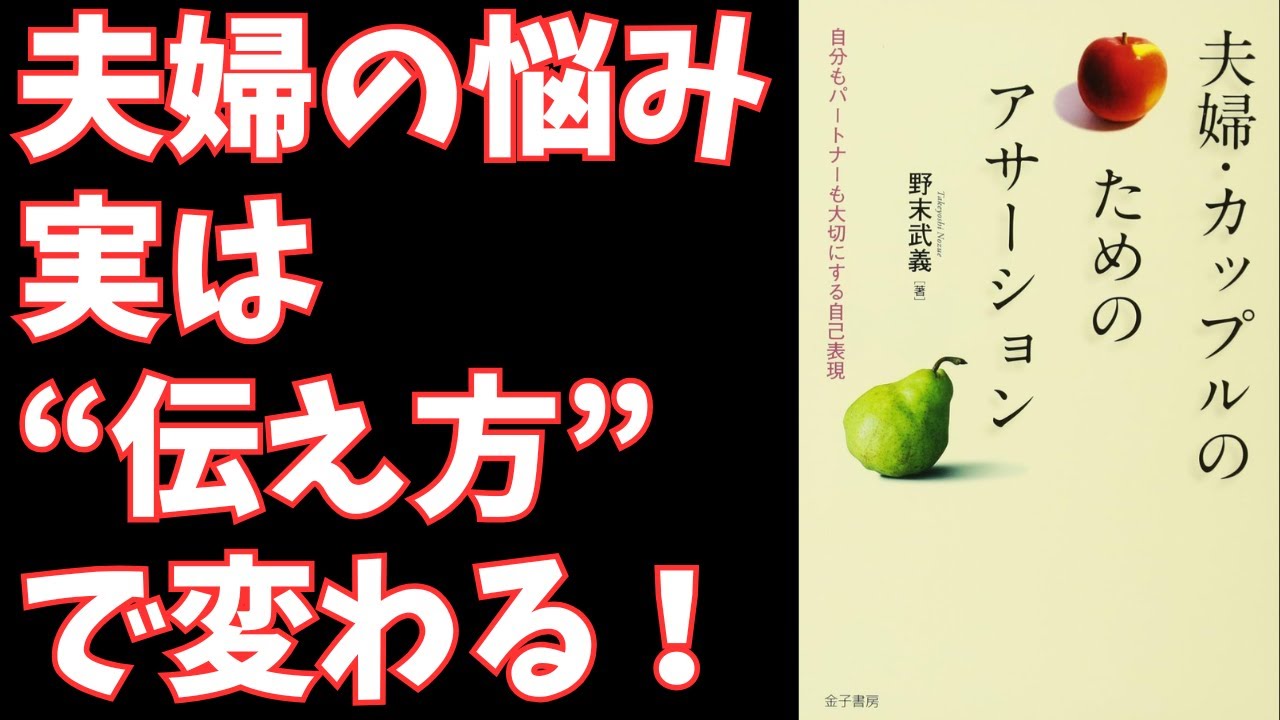自分を操り、不安をなくす!ビジネスでも活かせるマインドフルネス思考法
本記事では、常に悩みや不安を抱えてしまう方が、自分の心を客観視し、上手にコントロールしていくための考え方と具体的なテクニックを解説します。単なるポジティブ思考とは異なり、不安を消そうとするのではなく正しく理解し、うまく使うことがカギです。また、瞑想やマインドフルネスを取り入れることで、脳のパフォーマンスを高めながら心を安定させる方法を紹介します。さらに、失敗を恐れないメンタルのつくり方、嫉妬や完璧主義が生み出す問題点の乗り越え方など、仕事やプライベートに活かせる実践的な内容をまとめました。
悩みを生む「自分の見えなさ」を知る
仕事や人間関係などで、必要以上に悩み続けてしまうのは、自分のことを客観視できていない状態に原因があります。たとえば、周囲の何気ない行動が気になって仕方がないとき、本当は自分の心が過剰に反応しているだけかもしれません。外部環境そのものよりも、自分のとらえ方が大きく影響しているのです。
「ソロモンのパラドックス」と他者視点
自分の悩みに限って、冷静な判断を下せなくなる現象を「ソロモンのパラドックス」と呼びます。友人や部下が同じ悩みを抱えていたら、わりと適切なアドバイスができるのに、自分だと不安や焦りに飲み込まれてしまうのです。
そこで有効なのが、他人視点で考えるセルフアドバイス。まるで友達の悩みに答えるつもりで、自分の問題に対して助言をしてみると、案外、解決策がすんなり見えてくる場合があります。
自分をコントロールするための「心理対比」
「心理対比」とは、ポジティブな未来を思い描きつつ、その未来がダメになる最悪の状況も同時に想定する方法です。最高の状態と最悪の状態を両方イメージしておくことで、必要以上に楽観的にも悲観的にもならず、現実的な計画が立てられるようになります。
- 目標を達成したらどんなメリットがあるかを考える
- メリットのなかでも、最も魅力的なものを鮮明にイメージ
- いちばん起こってほしくない最悪の事態を想定
- その最悪の事態を、どんな対処によって回避するかを考える
心理対比を習慣化すると、不安に流されずに目標への具体的な道筋を描きやすくなります。
自分の脳が「不安」を生む理由
不安には、外的要因ではなく自分自身の思考パターンが大きくかかわっています。そもそも人間は不安を感じやすくできており、何も感じない状態だと危機回避が遅れ、生存に不利な面があったのだとも考えられます。
不安脳を鍛える「記憶力」の効果
不安やうつになりやすい脳の特徴を「不安脳」といいますが、記憶力を刺激するようなタスクを行うと、不安が軽減されるという研究があります。暗算や神経衰弱のように、頭をしっかり使うタスクを継続すると、脳の前頭前野が活性化して気持ちを整理する力が高まり、メンタルが強化されます。
つまり、難しい問題に挑戦したり、新しいスキルを身につけたりすると、不安感が弱まり、ネガティブな感情に翻弄されにくくなるのです。
不安をコントロールする呼吸
人間は無意識に呼吸をしていますが、意識的に深呼吸をすると副交感神経が優位になってリラックスしやすくなります。特に、緊張するときは「まず吐く」ことを意識しましょう。息を吸うときは交感神経が働き、余計に体が強張りやすいからです。「ふう〜」としっかり吐き切り、自然に空気が入ってくるのを感じるだけでも、ストレスや不安を鎮める効果が期待できます。
「根拠のない自信」から始める挑戦
未来が不透明だからこそ、いきなり大きな根拠ある計画を立てても、かえって不安を呼びやすくなります。しかし、根拠のない自信がある人ほど、大胆なチャレンジをして成功を引き寄せる確率が高まるという事実があります。多くの成功者を見ても、初期段階では「自分ならやれる」「どうにかなるはずだ」という感覚だけを頼りに行動し、結果として根拠が生まれていくケースが少なくありません。
失敗を恐れずに学ぶ姿勢
失敗を重ねることは、学習を重ねているという証拠です。失敗しないのは、ただ安定した範囲だけで動いている証ともいえます。わかりやすい例として、補正下着メーカー「スパンクス」を創業し、莫大な資産を築いたサラ・ブレイクリーさんは、子供の頃に父親から「どんな失敗をした?」と聞かれ、それを褒められて育ちました。失敗するイコール挑戦している証拠だと教え込まれ、失敗への免疫がしっかり身についたのです。
他己目標(コンパッションゴール)を立てる
根拠のない自信を育てるときに意外と大事なのが、「自分のため」より「他人のため」を目標にすることです。自分の欠点を直したい、自分の魅力を高めたい、という自己目標だけに注力すると、なかなか自尊心は育ちません。逆に、誰かを助ける、他人を喜ばせるという他己目標に取り組むと、不思議とモチベーションが安定し、結果的に自分の自信にもつながります。
嫉妬と完璧主義を正しく扱う
人間関係においては、嫉妬と完璧主義がストレスや悩みを増やす大きな要因になりやすいです。いずれも、どうとらえるかによって前向きな力にも後ろ向きな破壊力にもなります。
嫉妬は「自分が欲しいもの」を教えてくれる
嫉妬してしまうのは、相手が自分が本当に欲しいものを手にしているからです。つまり、嫉妬には「自分が求めている目標や価値観を明確化する」メリットがあります。
たとえば、自分は心底お金に興味がないと思っていても、大きな収入を得た同僚を見てモヤモヤするのなら、実はお金や物質的な豊かさに魅力を感じているかもしれません。こうした気づきを活かし、「どうすれば自分もそれを手に入れられるか」と行動に移せば、嫉妬はモチベーションへと変換されます。
完璧主義がもたらす三つのリスク
- ネガティブ感情に振り回されやすい
失敗を過剰に恐れ、ほんの少しのミスや指摘で強く落ち込みます。 - 誠実性が損なわれる
真面目に見えて、実はコツコツと計画的に進める力が弱いケースが多いです。 - 挑戦機会を逃しやすく失敗が増える
完璧な準備が整わないと動けず、変化の時代に対応しづらくなります。
完璧主義をやめたいのに抜け出せないときは、なぜ自分が完璧であろうとするのかを掘り下げることが大切です。「他人に嫌われたくない」「すべてを成功させたい」という強い恐怖が背景にある場合、その恐怖の正体を理解し、失敗が成長や学びになると腑に落とすステップが欠かせません。
失敗を力に変えるための具体策
失敗を避けられないとわかっていても、実際に挫折を味わうと心が折れそうになります。そんなとき、どう乗り越えればいいのでしょうか。
マインドセット:「失敗=学習」
仕事上のミスなどで打ちひしがれたとき、無駄に自分を責めないのが重要です。人間は失敗の痛みによって記憶を刻むので、失敗するほど学習できるというのが本来の仕組み。単にやる気が足りないなどの理由で自分を責めるのではなく、「この失敗はどんな学びを与えてくれたのか」をきちんと振り返りましょう。
二次的コントロールで環境を受け止める
仕事の環境を自分の努力で根本から変えようとする「一次的コントロール」に固執すると、思うようにならないときに大きなストレスを抱えがちです。いっぽう、「二次的コントロール」とは、自分の感じ方やアプローチを変えて環境に適応しようとする方法。
嫌な仕事を振られたり、会社に不満があっても、いきなり組織を変えるのは難しいものです。まずは、自分自身の見方や行動パターンを変えて、やりづらさや不満を減らしてみる。そうすると意外にも自分のパフォーマンスが上がり、会社や上司の態度が自然と変化する場合もあります。
マインドフルネスと瞑想の実践
先の見えない時代を生き抜くうえで、「いまここ」に集中する力が求められています。マインドフルネスや瞑想は、自分の思考や感情を客観視できるようにするテクニックとして幅広く注目されています。
マインドフルネスのABC
- A:アウェアネス(Awareness)
いま自分が何をしているのかを、ありのままに意識する。 - B:ビーイング(Being)
その行動が良い悪いと判断せず、ただ存在していると認める。 - C:クラリティ(Clarity)
起きている現象を明確にとらえ、どんな感情が生まれているのか把握する。
とくに大事なのが、「判断を下さない」という点です。物事を早急に良し悪しで決めつけるのではなく、「そういう状態なんだな」と受け止め、どう感じるかを冷静に見つめる力がマインドフルネスの核心にあります。
呼吸を重視した簡単な瞑想
瞑想は難しく感じるかもしれませんが、まずは呼吸に意識を向けるだけでも十分に始められます。静かな場所に座って、目を軽く閉じ、ゆっくり吸ってゆっくり吐く。そのとき、頭に雑念が浮かんできても排除しようとせず、「雑念が浮かんでいるな」と客観的に眺めるだけでOKです。
歩行瞑想(ウォーキング・メディテーション)
座ったままの瞑想が苦手な人は、歩きながら呼吸や足の裏の感覚に意識を向ける方法を試してみましょう。自分の足が地面につく感覚、空気の温度、周囲の音などを細かく感じ取ることが狙いです。
自分の弱みを「強みに変える」思考
コンプレックスや苦手意識を、ただ避けていては成長はありません。発想を切り替えて、弱みを逆手に取る視点をもつことで、長所に変えてしまう方法もあります。
なぜ体を鍛えるとメンタルが安定するのか
メンタルを強くする定番の方法の一つが「筋トレ」や「運動」です。体を変えるプロセスがわかりやすいため、自己効力感(自分の力で人生を変えられる感覚)を得やすいのです。運動を続けると、実際に体型が変わったり疲れにくくなったりと、可視化しやすい成果が出ます。
そうすると、「できなかったことでも訓練次第で変えられる」と肌で実感でき、仕事や学習へのモチベーションにも良い影響が及ぶのです。
超常刺激を減らして集中力を高める
現代はスマホやネットの普及により、脳がとにかく刺激を受けすぎる状態ともいえます。ポルノやジャンクフード、ゲームなど、人間の本能を強烈に刺激する要素(超常刺激)が多すぎるため、注意力が散漫になり、不安が増幅しやすいのです。
そこで、SNSやアプリの通知をオフにする、ジャンクフードを減らすなど、余計な刺激を意図的に制限するだけでも、マインドフルネスに適した脳の状態を取り戻しやすくなります。
「いま」を楽しみ、未来につなげる心構え
人間は本来、「いま」を楽しむのが苦手な生き物です。未来を楽観視しすぎたり、過去を美化しすぎたりして、結果的にいまがいちばん不幸だと感じる傾向があります。しかし、それを素直に受けとめたうえで、いまに集中する練習を続ければ、自分らしい幸福感を得ることは十分可能です。
自分の成果や感情を記録する
その日どんなことに悩み、どんな感情が生まれたのかをメモする習慣は、過去を客観的に見るうえでとても役立ちます。人はどうしても、いま感じる不安や不満を過剰に評価しがちですが、1年前の悩みを読み返すと「大したことなかった」と思える場合が多いものです。
また、達成したことや得られた成果を記録しておくと、少しずつ自信の土台が築かれていきます。
まとめ:マインドフルネスを味方につける生き方
不安や焦りは、根本的には消し去ることが難しい感情です。しかし、その感情を正しく理解して活かしていけば、自分を成長させる原動力に変えられます。
自分が欲しているものを嫉妬から見極める、完璧主義を手放して失敗を学びに変える、他人視点で自分を客観的にアドバイスするといった具体的ステップを踏むことで、悩みや不安への対処ははるかに楽になります。
さらに、マインドフルネスや瞑想を取り入れれば、ストレスを和らげつつ集中力を維持しやすくなり、仕事や日常生活でのパフォーマンスも上がるでしょう。
忘れてはいけないのは、自分を責めすぎず、適切に甘やかさないこと。「いま」の自分を認めながら、小さな一歩を積み重ねることが、遠回りのようでいて確実に前進するコツです。
ぜひ、本記事で紹介した考え方やテクニックを日常のなかで試し、悩みや不安をうまくコントロールしてみてください。自分を操る術を得たとき、人は思いのほか自由に動き出せるものです。