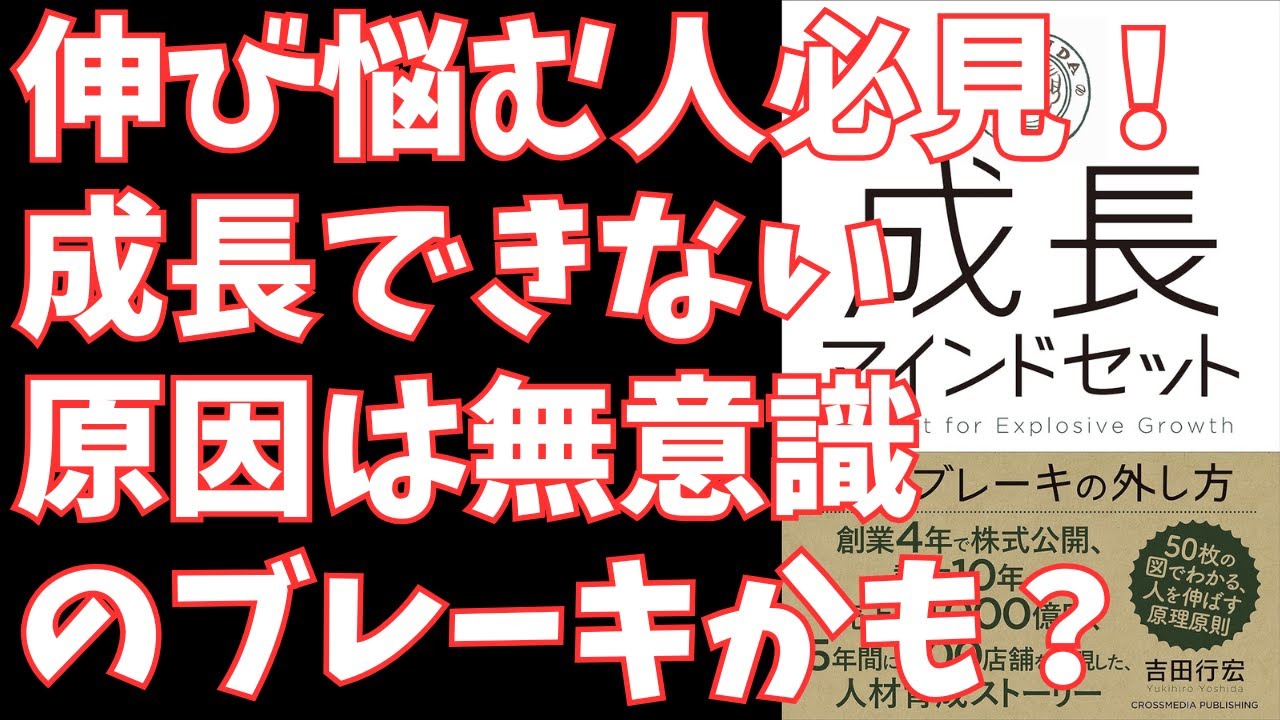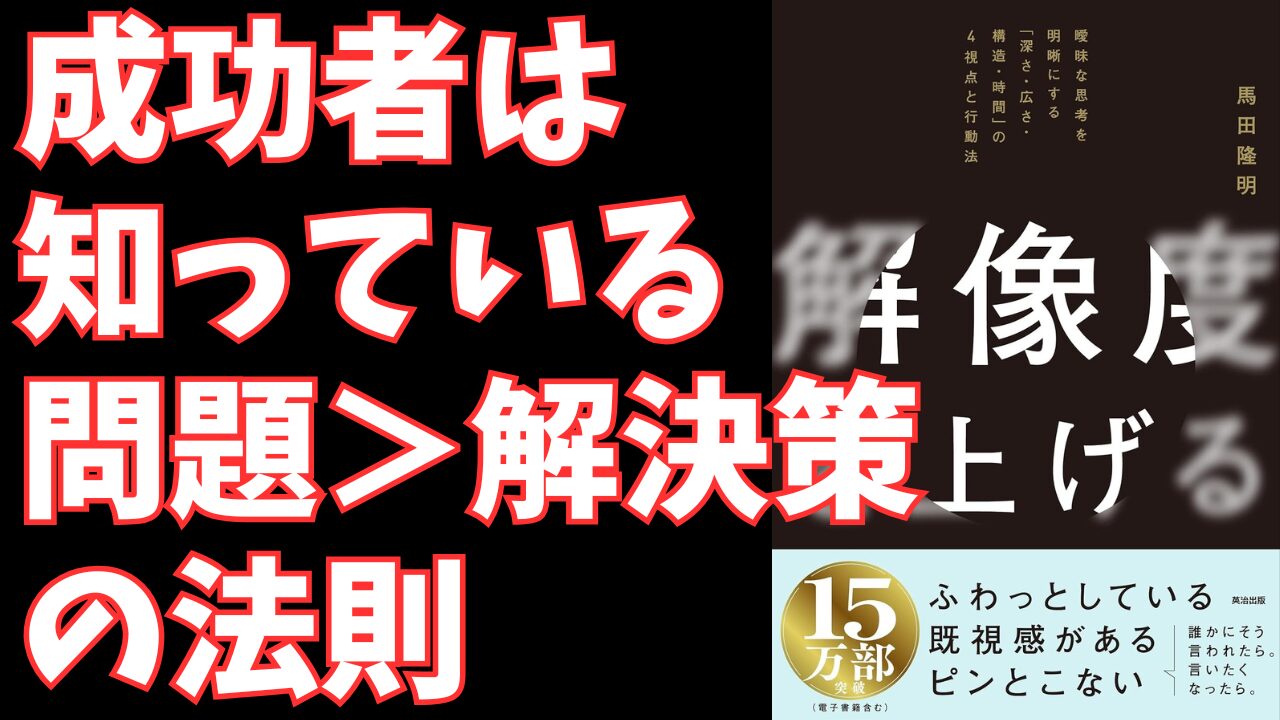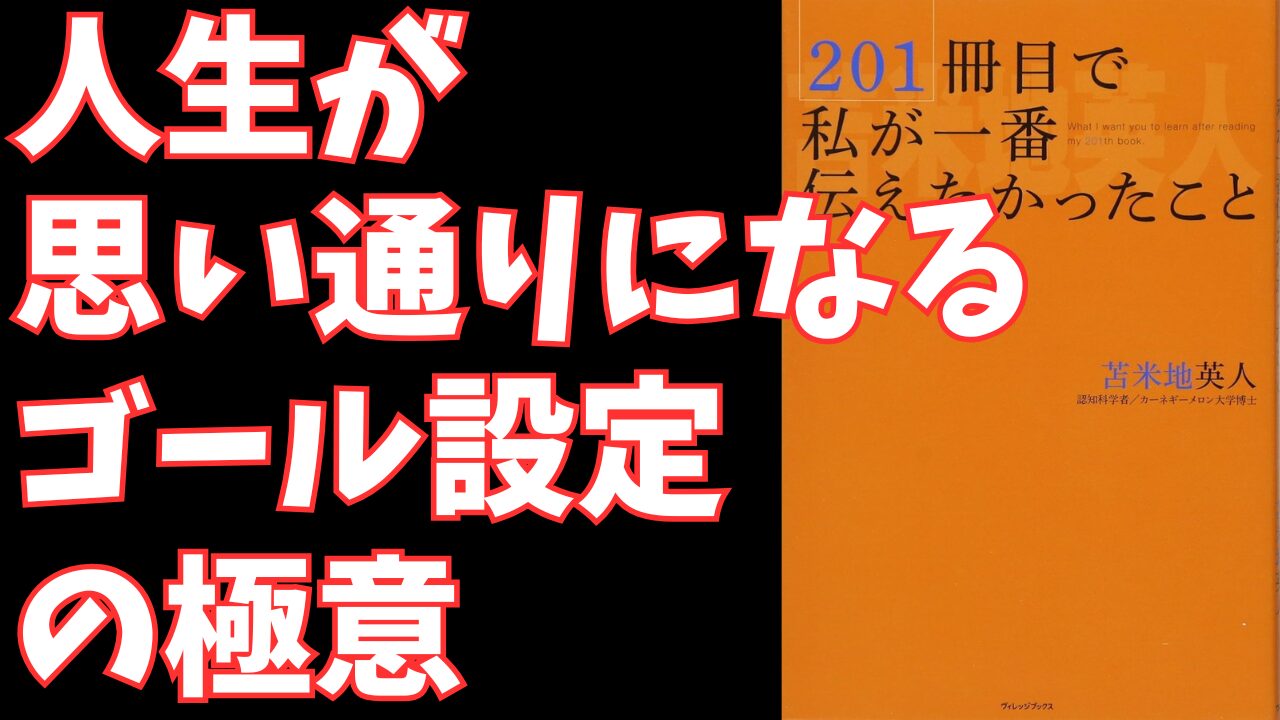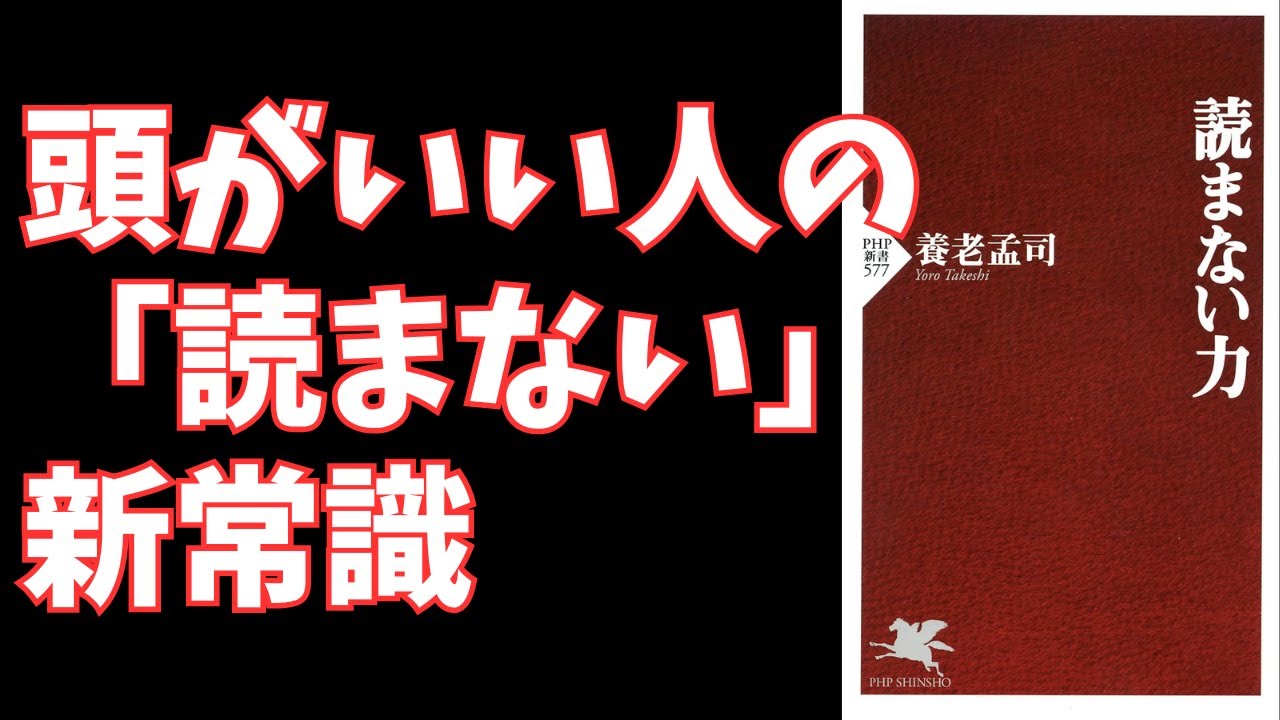Why型思考トレーニング 書評|仕事を変える「なぜ」の力とは?AI時代に必須の思考法を徹底解説
本書『Why型思考トレーニング 自分で考える力が飛躍的にアップする37問』は、現代のビジネスパーソンにとって不可欠な「Why型思考」の重要性を説き、その具体的な実践方法を提示する一冊です。AI技術が進化し、単純な情報収集や問題解決が自動化される現代において、 「そもそも何が問題なのか?」という問いを立てる力、すなわち問題発見能力の重要性が増しています。 本書は、この「Why型思考」を、指示されたことをそのまま実行する「What型思考」と対比させながら、豊富な事例とともに解説し、読者が自ら考える力を養うためのトレーニングを提供します。
本書の要点
- AI時代においては、与えられた問題を解く力(What型思考)よりも、 そもそも何が問題なのかを発見する力(Why型思考) が人間にとってより重要になる。
- 「Why型思考」とは、物事の理由や背景、本質を問い続ける思考法であり、「What型思考」とは、目に見える事象や形式のみにとらわれる思考停止の状態を指す。
- 私たちの身の回りや職場には、本質を見失った「WhyなきWhat病」が蔓延しており、これが非効率や思考停止を生んでいる。
- Why型思考を実践することで、問題解決能力、コミュニケーション能力、提案力が向上し、仕事の質が大きく変わる。
- Why型思考は、日々の意識的なトレーニングや心構えによって鍛えることができる。
はじめに:AIの進化と「なぜ?」を問うことの重要性
現代社会は、スマートフォンの普及やSNSの浸透、そしてChatGPTに代表される生成AIの急速な発展など、テクノロジーによって目まぐるしく変化しています。このような変化の激しい時代において、 自ら考えることの重要性はますます高まっています。 かつてのように過去の知識や経験を蓄積する「受動的知識・経験型」の価値観から、変化に柔軟に対応し能動的に挑戦するための「能動的思考力」へと、求められる能力の重心が移りつつあります。
特にAIの進化は、「考えること」への大きな影響を与えています。かつてはネット検索が思考停止を招く要因とされていましたが、今やAIが「何でもまとめて答えを出してくれる」時代です。これにより、人間の思考停止はさらに加速する一方で、AIを使いこなす人とそうでない人の間には大きな差が生まれる「残酷な二極化」が進むと著者は警鐘を鳴らしています。
このような時代だからこそ、 「問いを立てる力」、すなわち「問題発見の力」が重要になります。 AIが与えられた問題を解決する能力で人間を凌駕していく中で、人間に求められるのは「そもそもAIに何の問題を解かせるのか?」を考えることです。これはAIと人間の役割分担の問題であり、自らの選択した人生を歩むためには、何を解決すべきかを人間が考えることが必須となります。そのために必要なのが、本書のテーマである「Why型思考力」なのです。
「Why型思考」と「What型思考」の違いとは?~あなたはどっち?10のチェックリスト~
本書では、「Why型思考」を実践する人を「なぜなぜくん」、「What型思考」に陥りがちな人を「そのままくん」と名付け、その行動特性の違いを明確にしています。あなたはどちらのタイプに近いでしょうか?以下の10項目のチェックリストで、ご自身の思考回路を確認してみましょう。
- 現状は踏襲するためにあるか、否定するためにあるか?
- そのままくん:現状維持を最優先し、規則やルールを律儀に守る。
- なぜなぜくん:現状を必要に応じて否定し、より良いものに変えようとする。規則やルールも、その背景や目的を理解し柔軟に対応する。
- 規則は守るためにあるか、それとも「打ち破る」ためにあるか? (質問1と同様の趣旨)
- 資料は厚ければ厚いほうがよいか、薄くても気にしないか?
- そのままくん:目に見えるカタチを重視し、資料の厚さ(量)を気にする。
- なぜなぜくん:資料の裏にある「メッセージ」を重視し、量よりも質を求める。
- 他者(社)の事例は真似するためにあるか、真似しないためにあるか?
- そのままくん:うまくいっている事例を「そのまま」真似しようとする。
- なぜなぜくん:「人真似」を嫌い、他者の成功理由を分析し、自分流にアレンジしてより良いものを目指す。
- 過去の経験を「そのまま」教訓とするか?
- そのままくん:過去の経験を、現在の状況を考慮せずに「そのまま」適用しようとする。
- なぜなぜくん:過去の経験が今の状況でも通用するかを疑い、必要に応じて変化を加える。
- 今の状況を考えてヒネリを入れるか? (質問5と同様の趣旨)
- 言われたことをそのままやるか、理由を考えて一度「押し返す」か?
- そのままくん:上司などから言われたことを「そのまま」実行する。
- なぜなぜくん:指示の背景や理由を理解するために、一度相手に「押し返し」、真の目的を明らかにしてから最適な手段を考える。
- 選択肢は一つで安心するか、複数想定して常にもっといいものを探すか?
- そのままくん:一つの「正解」を求め、一つの選択肢で安心してしまう。
- なぜなぜくん:目的を達成するための複数の選択肢を考え、その中から最善のものを選ぼうとする。
- 問題解決とは与えられた問題を解くことか、自分で発見・定義してから解くことか?
- そのままくん:問題を与えられることから問題解決をスタートする。
- なぜなぜくん:「そもそも問題そのものが間違っていないか?」を問い、真の問題を「発見・定義し直す」ことに重きを置く。
- 質問するのが得意か不得意か?
- そのままくん:知らないことは恥ずかしいと考え、質問をためらう傾向がある。
- なぜなぜくん:「なぜ?」という本質に迫る質問を得意とし、考えることの出発点と捉える。
いかがでしたでしょうか。もし「そのままくん」側の項目が多く当てはまるようであれば、知らず知らずのうちに「What型思考」に偏っているかもしれません。しかし、心配は無用です。Why型思考は意識とトレーニングによって誰でも鍛えることができるのです。
職場にはびこる「WhyなきWhat病」とその具体例
本書では、Why型思考の欠如が引き起こす問題を「WhyなきWhat病」と呼び、その具体的な症状を職場によくある事例とともに紹介しています。
- 職場の「そのままくん」 :お客様の言葉を鵜呑みにする御用聞き営業マン、上司の指示をそのまま実行して後で文句を言う逆切れ部下、マニュアル通りの対応しかできないマニュアル人間など、 思考停止に陥り、言われたことや目に見えることしか対応できない人々 のことです。彼らは、物事の背景や本質を考えないため、しばしば問題を引き起こしたり、成長の機会を逃したりします。
- オレオレプレゼン :聞き手のことを考えず、自社や自社製品の「すごさ」を一方的にアピールするプレゼンテーションのことです。 「説明すること」自体が目的化してしまい、聞き手にどうしてほしいのかという本来の目的(Why)が欠落しています。 専門用語の羅列や、自慢話に終始し、結果として聞き手には何も響かないという事態を招きます。
- 前例主義 :「以前やったことがあるか」「実績はあるか」といった言葉に縛られ、新しい挑戦を阻む考え方です。長年続いていること自体が重要なのではなく、 なぜそれが続いてきたのかという背景や理由(Why)が意識されず、変化への対応を遅らせます。
- 成功体験、失敗体験の誤用 :過去の成功体験に固執し、環境変化を無視して同じ方法を繰り返したり、過去の失敗体験から「どうせうまくいかない」と新しいアイデアを葬り去ったりすることです。 成功や失敗の背景にある「なぜそうなったのか」(Why)を分析せず、表面的な結果(What)だけにとらわれている状態 です。本書では「猿とバナナ」の寓話(ある実験で、バナナを取ろうとすると冷水を浴びせられる経験をした猿たちが、その後、冷水シャワーがなくなってもバナナを取りに行かなくなる。新しく入ってきた猿も、理由を知らないまま先輩猿に止められバナナを取りに行かなくなるという話)を引用し、組織における「誰もWhyを知らないWhat」が引き継がれる危険性を示しています。
- 「作り手視点」のみの商品 :顧客ニーズ(Why)を無視し、技術力(What)だけに偏った商品開発です。開発者の自己満足に陥りやすく、市場に受け入れられないリスクが高まります。
- 形骸化したマニュアルやテンプレート :作成された当初の目的(Why)が忘れ去られ、マニュアルを埋めること自体が目的化(What)してしまうことです。本来不要な作業に時間を費やすなど、非効率を生み出します。
- メッセージなきドキュメント :情報量は多いものの、「何を伝えたいのか」というキーメッセージ(Why)が欠落した企画書や報告書です。作成者の意図と異なる解釈をされたり、誤用されたりする危険性があります。
これらの「WhyなきWhat病」は、私たちの日常業務の様々な場面に潜んでいます。これらに気づき、Why型思考で対処していくことが、仕事の質を高める第一歩となります。
Why型思考が今、求められる理由
では、なぜ今、これほどまでにWhy型思考が求められるのでしょうか。本書では、主に二つの環境変化を挙げています。
一つ目は、 世界における日本の立ち位置の変化 です。かつて日本は欧米を手本とし、それを改善することで経済成長を遂げてきました。しかし、新興国の台頭やビジネスパラダイムの変化により、このモデルは限界を迎えています。今求められるのは、「今あるもの」から発想するのではなく、 「そもそも何をすべきか」という本質的な議論、すなわちWhy型思考 です。
二つ目は、 インターネット革命 です。情報が容易に入手できるようになった現代では、単なる知識や情報の断片(What)だけでは価値を生み出しにくくなりました。重要なのは、 入手した情報を鵜呑みにせず、その文脈や背景(Why)を読み解き、自らの頭で加工していく思考力 です。
このような環境変化の中で、定型業務をこなすWhat型思考だけでは対応が難しく、非定型な業務、新しい価値創造が求められる場面でWhy型思考の重要性が高まっています。特に、歴史の浅いベンチャー企業や、大企業でも新規事業部門などでは、Why型思考を持つ人材がより活躍できるでしょう。
Why型思考をビジネスに応用する
Why型思考は、具体的なビジネスシーンでどのように役立つのでしょうか。本書では、問題解決、コミュニケーション、提案という三つの側面から、その応用例を解説しています。
- 問題解決に生かすWhy型思考:御用聞き型からの脱却
お客様から「商品Aが欲しい」と言われた場合、What型の「そのままくん」は「はい、わかりました」と即座に対応しようとします。しかし、Why型の「なぜなぜくん」は、「なぜ商品Aが必要なのですか?」「どのような用途でお使いになりますか?」と 一度「押し返す」ことで、お客様の真のニーズ(Why)を探ります。 その結果、商品Aよりもお客様に適した商品Bを提案できたり、関連商品を合わせて提案することで、より高い顧客満足と売上向上を実現できる可能性があります。
この「押し返す」という行為は、上司からの指示に対しても有効です。指示の背景にある目的(Why)を理解することで、より本質的な解決策を導き出し、手戻りを減らすことにも繋がります。 - コミュニケーションに生かすWhy型思考:上司と部下のギャップ解消
上司と部下の間でコミュニケーションギャップが生じる一因は、それぞれが注目しているものが異なるためです。上司は経験から物事の「考え方」や「背景」(Why)に目を向けがちですが、部下は目の前の「具体的な事象」(What)にとらわれがちです。
例えば、上司が部下に「もっと視野を広げてほしい(Why)」と抽象的な指示を出した場合、What型の部下は「具体的に何をすればいいのかわからない」と戸惑ってしまいます。逆に、上司が「100冊本を読め(What)」と具体的な指示を出した場合でも、Why型の部下はその意図(Why)を汲み取り、「視野を広げるために、どのような分野の本を読むべきか考えます」と能動的に行動できます。
お互いがWhyとWhatのどちらのレベルで話しているのかを意識し、必要に応じてすり合わせることが、円滑なコミュニケーションには不可欠です。 - 提案に生かすWhy型思考:真のニーズに応える「松」竹梅の提案
お客様の要望に対して、代替案を出す際にもWhy型思考は役立ちます。- 梅の対応(What型) :お客様の要望(What)に対して、自社の売りたい商品(別のWhat)を脈絡なく提案する。
- 竹の対応(ややWhy型だが不十分) :「流行っているから」「理論的にはこうだから」といった一方的な理由(Why)で別の案(What)を提示する。お客様の最初の案を無視した形になりがち。
- 松の対応(Why型) :お客様の最初の案(What)の背景にある 真の意図(Why)を丁寧にヒアリングし、そのWhyに合致する最適な選択肢(What)を再提案する。 これにより、お客様は納得感を持ちやすく、より満足度の高い結果に繋がります。
さらに上級の「ウルトラ松」では、質問を重ねることでお客様自身に最適な選択肢に「気づかせる」アプローチを取ります。
Why型思考を鍛えるためのヒント
では、どうすればWhy型思考を鍛えることができるのでしょうか。本書では、具体的な勉強法や心構えが紹介されています。
- 勉強法:「覚える」から「考える」へ
- What型の勉強:知識や情報をひたすら「覚える」ことを重視。
- Why型の勉強:得た情報を材料に、その理由や背景を「考える」ことを重視。 本を読んだりセミナーを受けたりする際も、単に情報をインプットするだけでなく、そこから何を学んだのか、自分の仕事にどう活かせるのかを深く考えることが重要です。 本書では、コンサルティング会社の入社試験で用いられる「フェルミ推定」(例:シカゴにピアノ調律師は何人いるか?)も、答えそのもの(What)ではなく、そこに至る思考プロセス(Why)を鍛えるためのツールとして紹介されています。
- 心構え
- 天邪鬼になれ! :人と同じことを鵜呑みにせず、あえて反対のことを考えたり、物事を疑ってかかったりする姿勢がWhy型思考を刺激します。「それは本当か?」と常に問いかけることが第一歩です。
- 性格悪くなれ!? :周りの人の発言に対して、安易に同調せず、「なぜそう言えるのか?」と心の中で問いかける習慣をつけましょう。(ただし、TPOはわきまえる必要があります)
- 全て自分の責任にする :うまくいかないことを環境や他人のせいにすると思考は停止します。「なぜそうなったのか?」「自分はどうすべきだったのか?」と自責で考えることで、思考回路が起動します。
- 「無精者」のススメ :常に「いかに楽をするか」「本当にそれは必要なのか?」と考えることは、無駄を省き、本質を見抜くWhy型思考に繋がります。
- 「答えがない状態」と「考える孤独」に耐えよ :Why型思考は、すぐに明確な答えが出ない問いに向き合い続けることです。 もやもやとした「考えるプロセス」そのものを楽しむ姿勢が大切です。 すぐに答えを求めたり、具体例がないと理解できないという受け身の姿勢ではなく、自ら考え抜く力を養いましょう。
まとめ:Why型思考で未来を切り拓く
本書『Why型思考トレーニング』は、変化の激しい現代において、私たちが身につけるべき本質的な思考法を提示してくれます。AIにはできない「なぜ?」と問い続ける力、物事の深層にある本質を見抜く力こそが、これからの時代を生き抜くための強力な武器となるでしょう。
忙しいビジネスパーソンにとって、日々の業務に追われる中で立ち止まって「なぜ?」と考えることは難しいかもしれません。しかし、本書で紹介されている数々の事例やトレーニングは、特別な時間を設けなくても、普段の仕事の中でWhy型思考を意識し、実践していくためのヒントに満ちています。
「もっと考えて仕事をしろ!」という漠然とした指示に戸惑うのではなく、本書を手に取り、具体的な「考える」技術としてのWhy型思考を身につけることで、仕事の質は格段に向上し、より創造的で本質的な課題解決に取り組むことができるようになるはずです。AIとの共存が当たり前になる未来に向けて、人間ならではの思考力を磨き、自らの手で未来を切り拓いていきましょう。