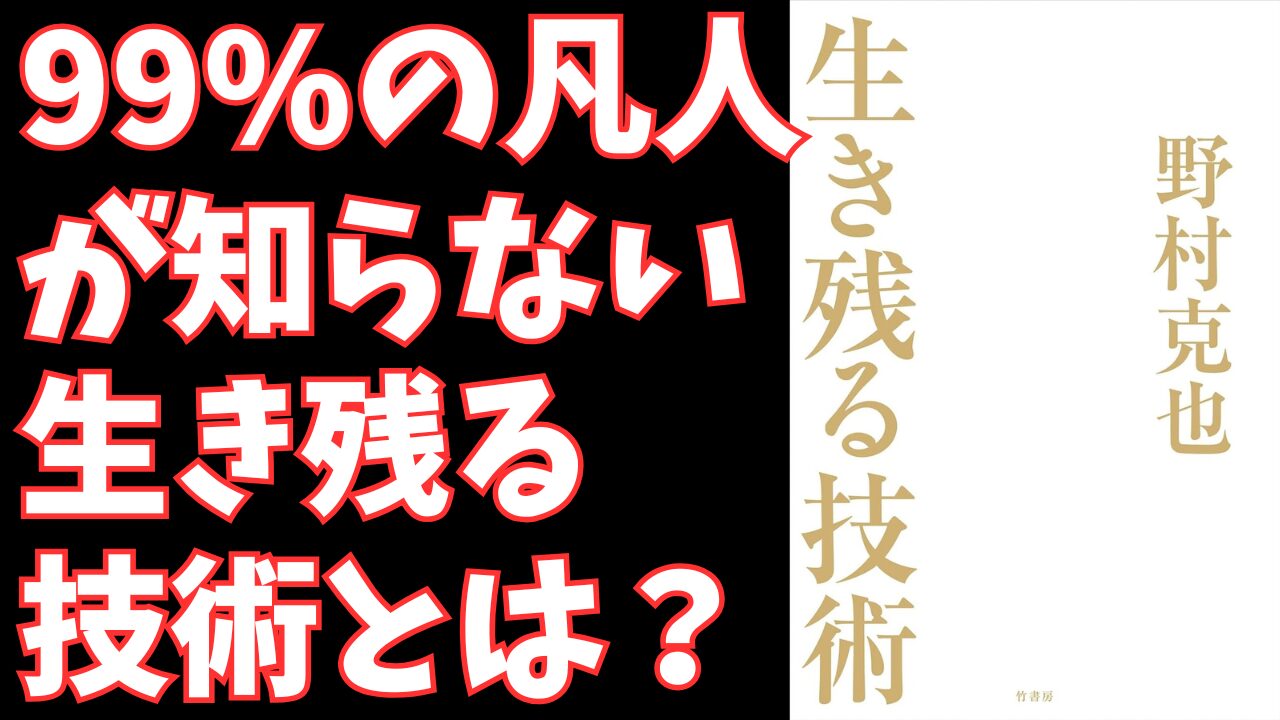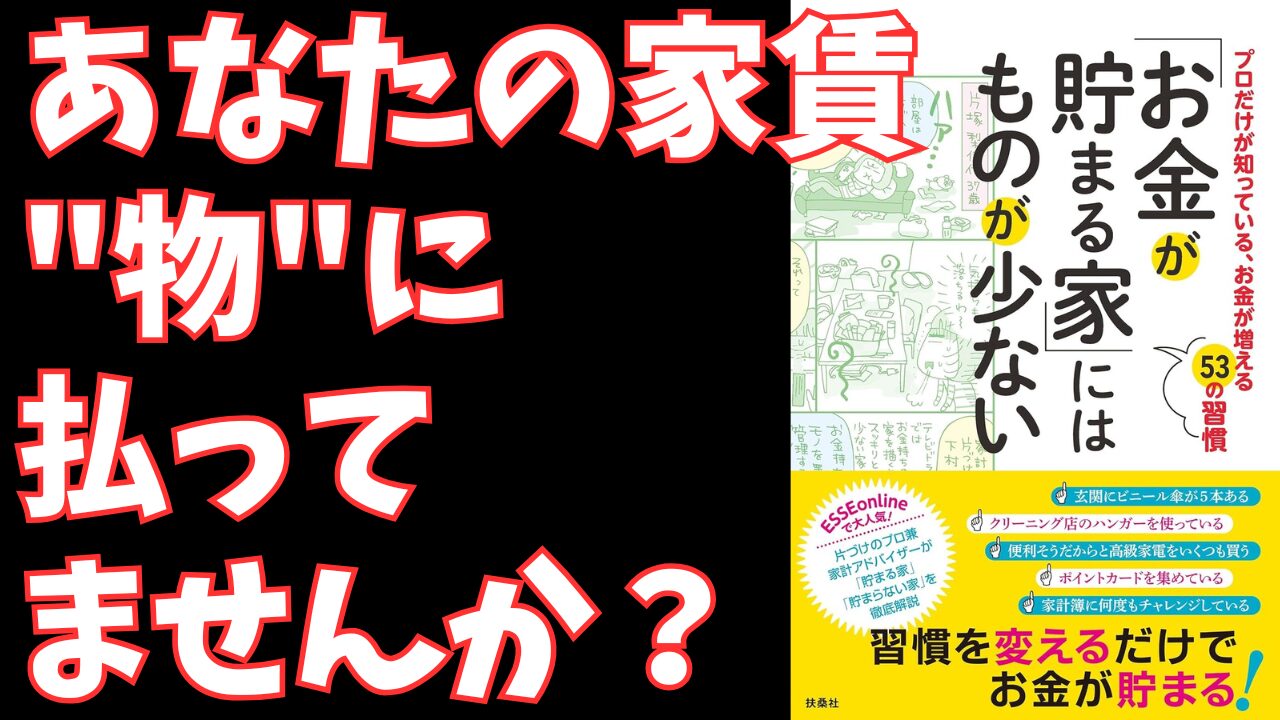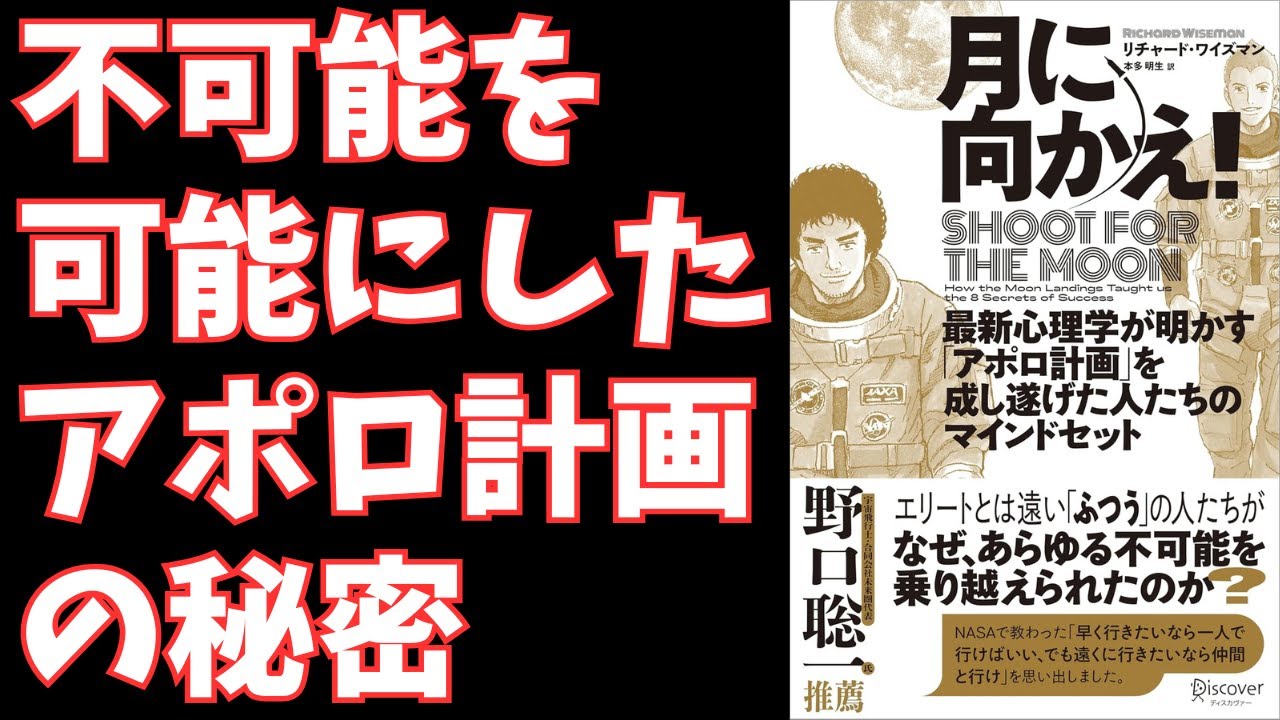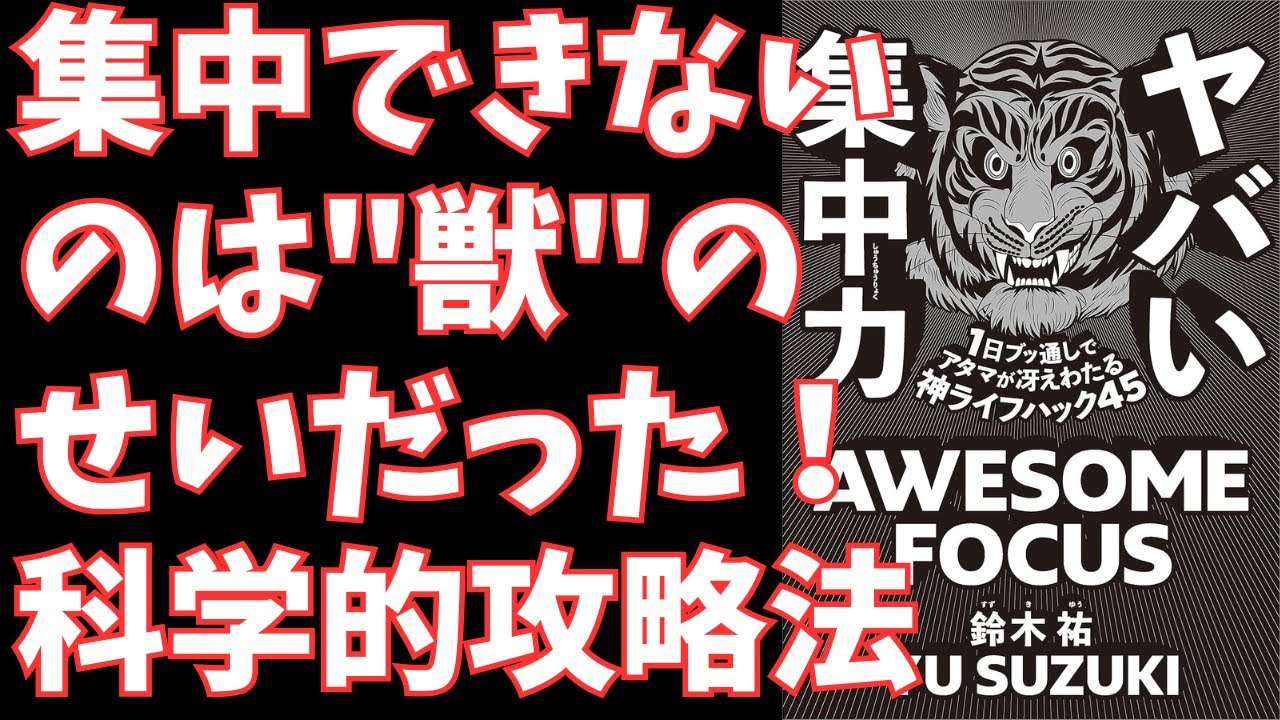【必読書評】広がる「レンジ」が切り開く未来──デイビッド・エプスタイン『RANGE』を徹底解説
デイビッド・エプスタインの著書『RANGE(レンジ)』は、専門性にとらわれずに多領域を経験し、多角的な視点から問題を捉えることが新しい価値を生み出すと説いた一冊です。タイガー・ウッズとロジャー・フェデラーの対比から始まり、早期の専門特化型ではなく、幅広く学んで徐々に専門に絞り込む「遅咲き」のメリットを豊富な事例を交えて紹介します。従来の「1万時間の法則」や「早期教育至上主義」への疑問を提示し、幅広い経験こそが複雑化する現代を生き抜くための武器となることを示す刺激的な内容です。
はじめに:多様性がもたらす力
現代のビジネス社会では、「一点特化が最短距離の成功をもたらす」 という見方が根強くあります。幼児のうちから英才教育を行い、他人をリードして抜きん出る。その象徴として挙げられるのがゴルフ界のタイガー・ウッズです。生後半年からゴルフクラブを握り、幼少期から徹底的に特化した練習を重ねた結果、比類なき成果を残しました。
しかし、本書『RANGE(レンジ)』で示されるもうひとつのモデルは、全く逆のルートをたどったテニス選手のロジャー・フェデラーです。幼い頃に複数のスポーツを掛け持ちし、10代になって初めてテニスに集中した彼のような「遅めの専門特化」型アスリートは、長期的に見ると多分野の経験による幅広い適応力を強みに活躍しています。これこそが本書の核であり、「幅の広さ」=レンジの持つ力 なのです。
1章:早期特化の常識を疑う
「モーツァルトは3歳で作曲した」「タイガー・ウッズは2歳でショー出演」など、幼少期から同じ活動に打ち込む天才の物語が世の中に溢れています。こうしたサクセスストーリーから、「何か一つに集中すれば最短で成功へ駆け上がれる」という幻想が広がっています。
しかし、本書ではさまざまな研究や事例を引用しながら、早期特化のメリットは限られた分野にとどまる 可能性が高いことが示されます。特にゴルフやチェスなどの「ルールが明確で繰り返し構造が変わらない」分野なら、早期特化が奏功しやすいのは確かですが、それを複雑な世界のあらゆる仕事や学問に当てはめるのはリスクが大きいと著者は警鐘を鳴らします。
2章:意地悪な世界と親切な世界
本書で頻出するキーワードのひとつが、「親切な学習環境」と「意地悪な学習環境」です。チェスやゴルフは「親切な学習環境」 で、ルールやフィードバックが明快で、定型的なパターンをいち早く獲得し磨き上げることでエキスパートになれます。
一方、ビジネスや新規事業立案、創造的な研究などは「意地悪な学習環境」 とされ、ルールが流動的で、すぐに正解のフィードバックが返ってくるとは限りません。このような環境では、一つの狭い専門知識だけに頼ると、予期せぬ変化に対応できず失敗するリスクが高まるのです。
3章:ポルガー三姉妹とフィーリエ・デル・コーロ
早期教育の成功例として、チェスの天才であるポルガー三姉妹 がよく挙げられます。彼女たちは幼少期から膨大な練習を積み、女子チェスの常識を覆した偉業を残しました。しかし、よく知られた天才姉妹の物語だけがすべてに当てはまるわけではありません。
対照的な歴史的事例として、本書で語られるのが18世紀のベネチアにあった「フィーリエ・デル・コーロ」 という孤児院の少女たちです。彼女たちは一つの楽器に固執せず、複数の楽器を習得し、さらに自ら楽器を改良するという試行錯誤を重ねながら、新しい音楽の可能性を切り開きました。いわば専門外の領域を積極的に取り入れ、新奇な組み合わせを生み出す姿勢 が、バロック期の音楽革命に大きなインパクトを与えたのです。
4章:幅の広い学習が生むアイデアの飛躍
ビジネスや技術革新の世界でも、深い専門特化の向こう側にある多様な経験 が大きな発見をもたらしてきました。たとえば、クラウドサービスやSNSなど、ITの急速な発展領域では、異なる学問領域や産業が組み合わさり、予想もしなかったイノベーションが起こります。
多様な経験は、いくつもの視点を行き来して「本質」をつかみやすくする働きがあります。歴史的に見ても、クロード・シャノンが哲学のクラスで学んだブール論理が情報理論の基礎になった 話などは有名で、まさに異分野の結合が生んだ新たな領域と言えるでしょう。
5章:遅咲きは不利なのか
「遅いスタートでは成功に届かない」という不安は誰しも抱きがちです。学校教育でも、比較的早い段階で進路や専攻を決めるよう求められるため、一貫した専門性がないと評価が下がる傾向が見受けられます。しかし、本書では、遅めの専門特化 は決してハンデにならないと強調されます。
むしろ、20代・30代は経験の幅を広げるための貴重な期間 です。複数の職種を渡り歩いたり、ジャンルの違う仕事にチャレンジしたりした結果として、そこで培った知見を後年に統合し、より大きな成果を生むケースが少なくありません。
6章:最適解を求めすぎる危険性
人は往々にして、ひとつの方法で成功すると、それを絶対視してしまいがちです。専門家はその知識やスキルを頼りに直感的な判断を下せる強みがありますが、状況が変化すると「金槌を持つ者にはすべてが釘に見える」 状態に陥りやすくなります。これは変化の速いビジネス環境で特に危険です。
医療や金融などでも、専門家が長年の経験に頼りすぎて、新しい問題に正しく対処できず大失敗を招く事例があります。いわゆる「専門の罠」で、広い視野を得るためには、あえて他分野の知識やアマチュア精神 を取り入れることが大切なのだと、本書は示唆してくれます。
7章:効率的に「非効率的な学習」をする
心理学の研究では、学習効果を最大化するには「非効率」な遠回りが有効 だと示されています。すぐに答えが分かってしまう学習方法は、一時的には成績が良くても、長期的な応用力や柔軟な発想力に欠けやすいのです。
何度も異なる場面で試行錯誤し、失敗と再挑戦を繰り返す過程こそが、複雑な世界の本質を捉える力を育みます。深く狭い専門領域に早期に引きこもってしまうと、長期的には問題に対処する柔軟性が養われず、思わぬ壁にぶつかる可能性が高まるのです。
8章:幅広い経験を武器にするための具体策
本書の終盤では、レンジを広げるための具体的なヒントがいくつも示されています。いずれも、「一度身に着けた専門技能だけに安住しない」 という姿勢が前提です。主なポイントを挙げてみます。
- 職業体験や副業を活用する
多様な仕事を経験することで、思いもよらないスキルが掛け合わさり、新たなアイデアにつながります。 - 趣味や学習分野を広げる
ノーベル賞受賞者など、世界的な成功者の多くは本業とは別の芸術やスポーツに親しんでいたという研究もあります。一見無関係に見える活動が思考を柔軟にし、創造性を引き出す のです。 - 「何を学ぶか」より「どう学ぶか」を重視
大学や教育機関で、単に専門科目を詰め込むのではなく、フェルミ推定や批判的思考、計算論的思考など汎用的な思考法を習得することで、未知の問題を自力で切り開く術を手に入れられます。 - 生涯を通じてキャリアを変化させる覚悟
本書に登場する退役軍人の例のように、社会人になってからキャリアチェンジをしても決して遅くはありません。むしろ、そのときまでの専門知識やリーダーシップが新しい分野で大きく花開くケースが多いのです。
9章:まとめ──複雑な世界ほど「レンジ」が活きる
世界が複雑化し、意地悪な学習環境が当たり前になりつつある現代、狭い専門知識だけに頼るリスク は増大しています。もちろん、特定の専門性が必要不可欠な場面もありますが、それだけでは対応できない未知の課題が次々と出現するのがビジネス社会です。
本書のメッセージは明確です。早くからひとつのことに固執するのではなく、さまざまな興味や経験を組み合わせることで、複雑な問題に革新的な解を導き出せる力を養う──これこそが「レンジ(幅)」の力なのです。
タイガー・ウッズ型の成功は目立ちますが、フェデラー型の緩やかなキャリア形成が、むしろ大多数の人にとっては有効な戦略となるでしょう。社会も企業も、すでに決まった正解がある仕事よりも、未知の課題に対処する柔軟性を求めています。その変化に応えるために、「専門家」を超える広い視野と多彩な経験を武器にすることこそ、新時代を生き抜く鍵ではないでしょうか。
本書は、専門特化が当たり前とされてきた常識への挑戦状であり、これからのキャリアや学び方を真剣に考える方々に、大きな示唆を与えてくれるはずです。