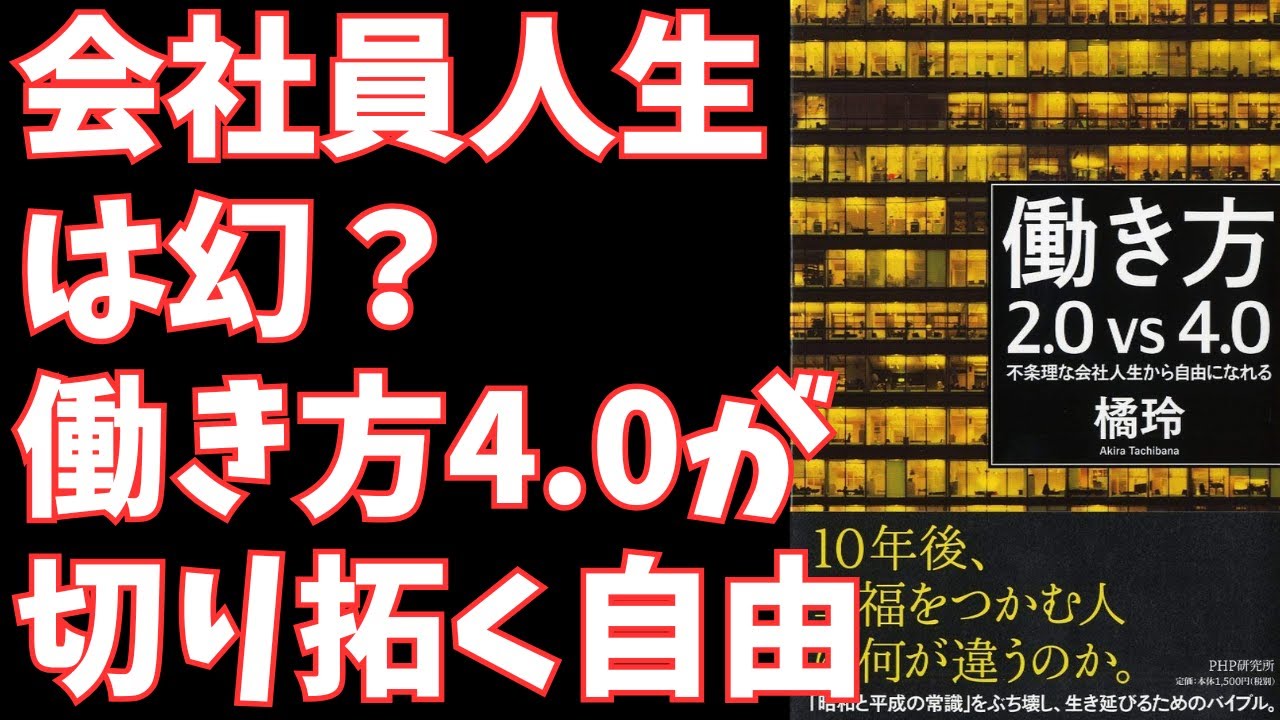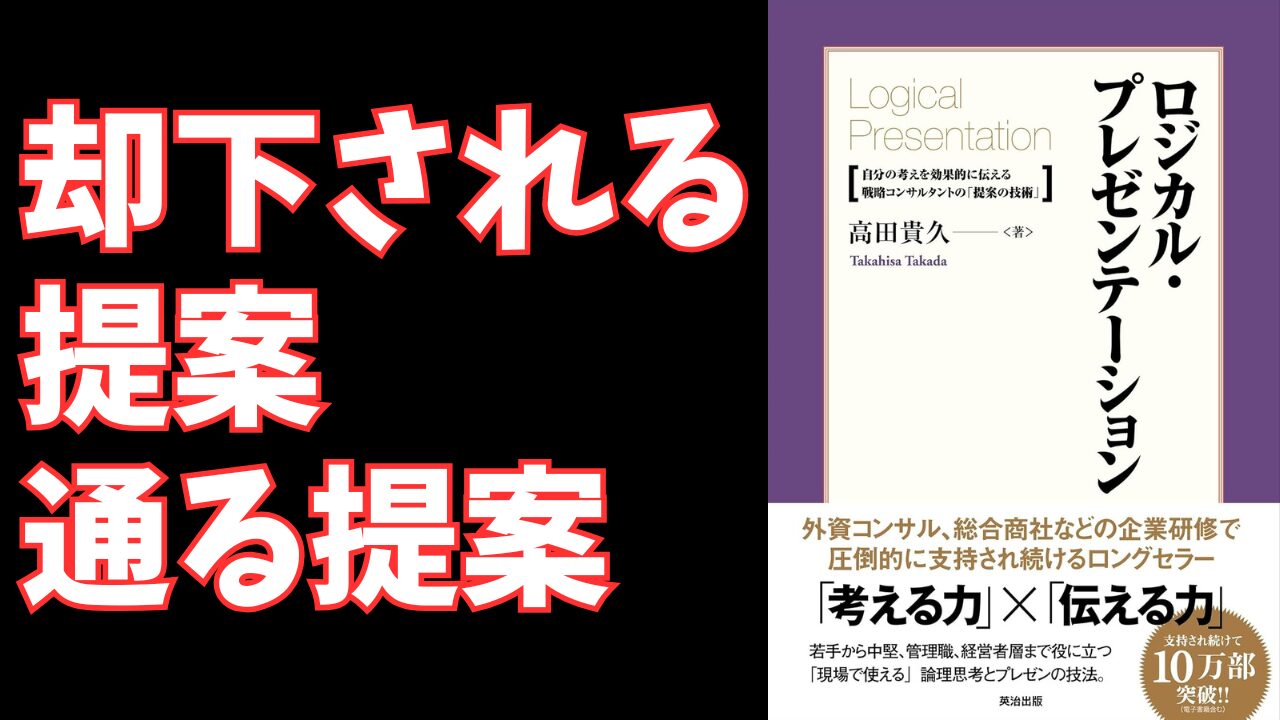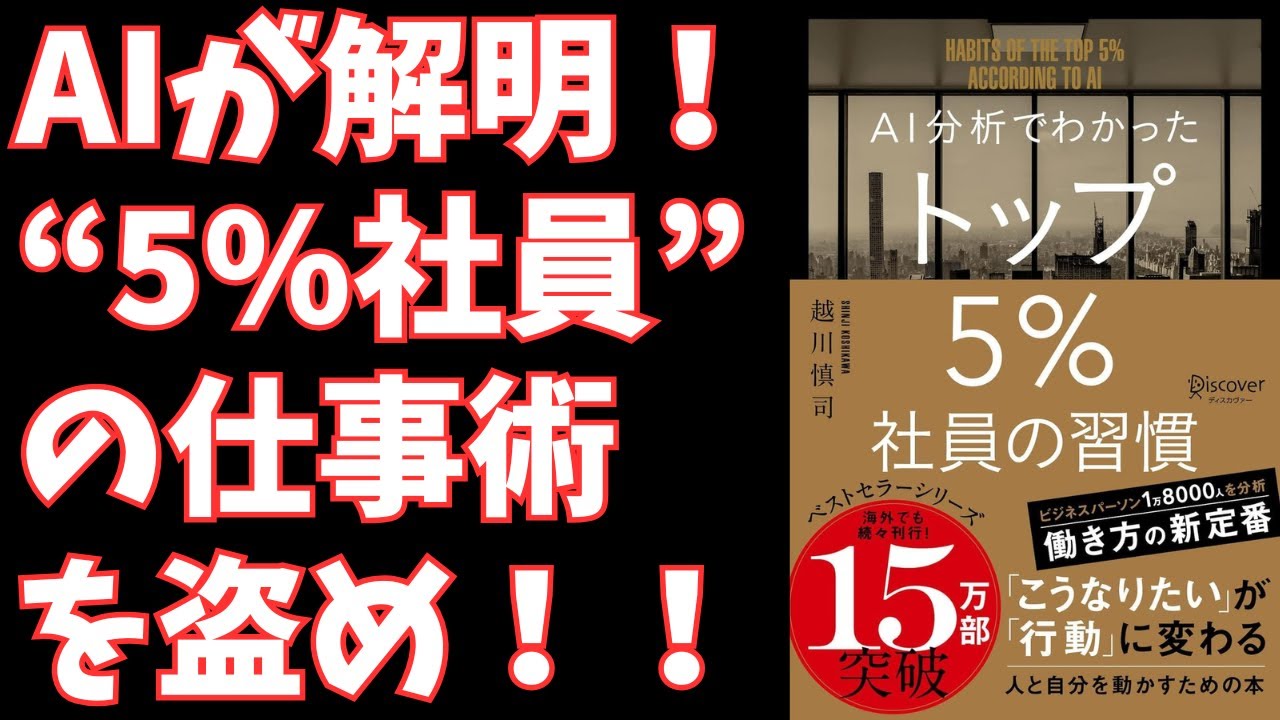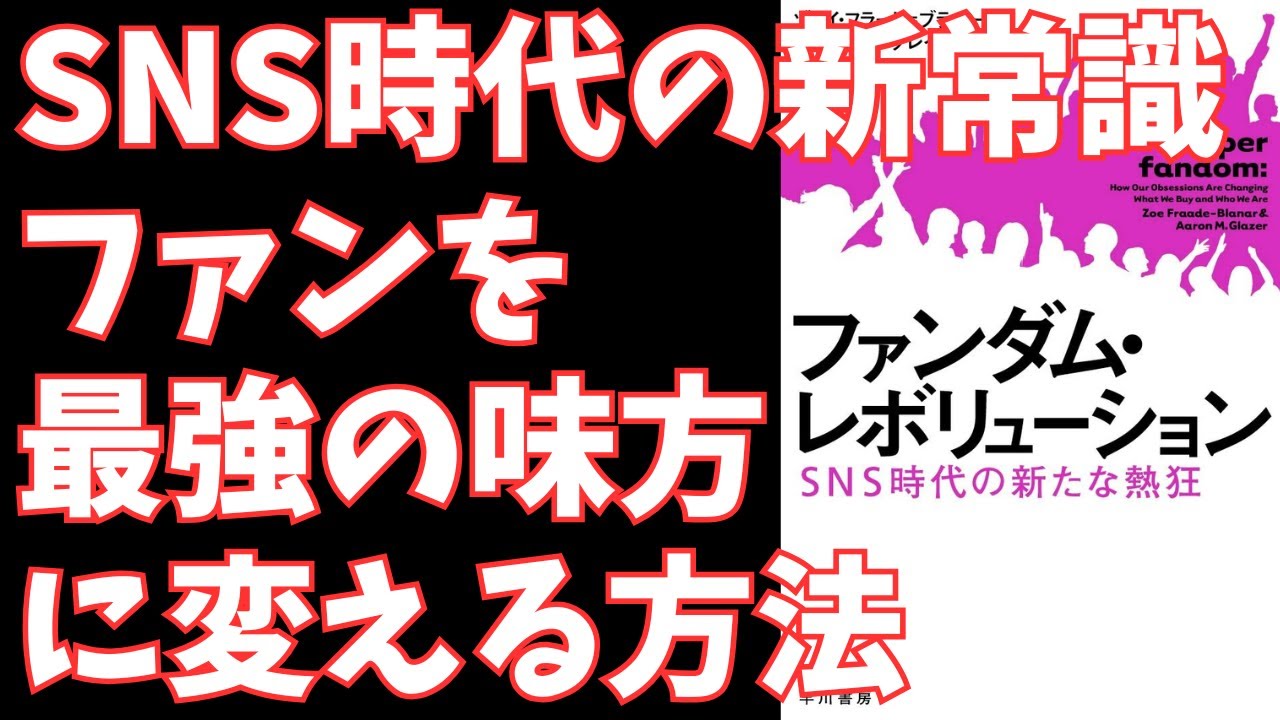アラビアの荒野から見た日本の大志~揺れ動く時代を切り開いた若き冒険者の物語
『アラビア太郎』は、明治から大正期にかけての激動の時代に生きた青年・山下太郎の人生を追った物語です。札幌農学校で大志を抱き、酒や恋に揺れ動きながらも、時代の波を果敢に渡り歩きます。彼は農業開拓から事業投資へと軸足を移し、好景気に沸く大正期の日本で大きな成功を得ました。しかし一方で、その投機的な手法や派手な生活が周囲との衝突を生み、やがて彼の姿は満洲やアラビアの砂漠へと続いていきます。青年期の苦闘と、燃え盛るような向上心、そして世界へ踏み出してゆく挑戦の記録が、本書を通じて描かれています。
青年期:札幌農学校と大志の目覚め
物語は山下太郎という青年が、札幌農学校へ入学する場面から生き生きと始まります。海を渡る船の甲板で、大声をあげて北海道への期待と興奮を表現する彼の姿が印象的です。慶應出身で都会育ちながら、自然の広大さに心を打たれ、北海道にこそ自らの未来を見いだそうとする情熱を抱いていました。
札幌農学校はアメリカ人・クラーク大佐の意志を継ぐ教育方針をもち、英語が公用語のように使われ、キリスト教精神が脈々と受け継がれています。内村鑑三や新渡戸稲造など、輩出された先達の偉業は学生たちの憧れの対象でした。若き山下太郎もまた「大志を抱け」というスローガンに強い影響を受け、後に海外へ飛び出していく下地を培います。
しかし、農学校といえどもすべてがクリスチャンの倫理一色ではありません。荒々しい気質をもつ学生や、実家が農家で切実に技術を学ぶ者、単に官費留学生として利用する者など、人間模様は多彩です。乗馬に熱中し、牛馬を自在に扱う者がいれば、昼夜勉強に打ち込む者もいる。山下太郎はどちらかというと、学問よりも行動力と社交性が際立つタイプであり、華やかな場面に目を輝かせ、やがて恋や酒に溺れそうになる姿も見せます。
開拓か、実業か
札幌農学校の卒業後、彼は一度は農場開拓を志します。しかし、泥まみれの現場作業を苦手とする気質や、家族や周囲との衝突などが重なり、開拓への熱が揺らぎ始めます。一方で、産業が急激に発展していく時代背景に触れ、資本や工業製品の売買といった大きな商いに強い関心をもち始めるのです。農学校でありながら、投資や海外貿易などの情報に大志を燃やす彼の姿は、すでに「大地を耕す青年」から「新時代を切り開く起業家」へと傾斜していました。
同時に、山下家の血筋としては“楠木正成の末裔”を標榜しつつも、家そのものは没落気味で、父との意見の食い違いは絶えません。父正治が築き上げようとした財も、投機の波に翻弄されがちで、太郎自身も学費や事業資金をどう工面するか苦悩します。結局、彼は軍隊へ入ることになり、兵営でいじめに遭いながらも、「人に使われたくない」という気持ちを募らせていくのでした。
酒と恋がもたらす若き苦悩
山下太郎の青春を彩るのは、何よりも恋の熱と酒の誘惑です。学生寮である青年寄宿舎は、禁酒・禁煙を厳しく掲げていましたが、窮屈な規律から飛び出してしまう場面は痛快でもあります。彼は恋人を夜中に寄宿舎へ忍び込ませるなど、まるでロメオとジュリエットさながらの大胆さを示しました。
しかし恋は儚く、ひそやかに逢瀬を重ねた彼女は突然、親の都合で遠くへ嫁いでしまいます。自尊心の強い山下太郎も、さすがに心を大きく傷つけられ、しばらく精神が沈んでしまう。そんなときに友人が飲み会へ誘い、勢いでどんぶりに酒を注いでしまったのが命取りになり、寄宿舎からの即日退寮へ発展。己の感情をうまくコントロールしきれない若さが、痛ましくも鮮烈に描かれます。
飲めば酔い、酔えば大胆な行動に出てしまう。恋も酒も豪快な行為を生む反面、彼の中にある理想や夢を押しとどめる要因でもあります。これらの要素が絡み合うことで、「人を恋うる」という章では、人間の欲望と精神的な葛藤が鮮明に表現されているのです。
東京への帰還と初めての冒険
札幌農学校を卒業し、兵役を経て、山下太郎は再び東京へ戻ります。母の実家である秋田県横手の菓子屋に身を寄せ、そこで「ふきこぼれたお粥の膜」の性質から、オブラート製造のヒントを得るエピソードは印象深い部分です。
このオブラート製造法は、単なるアイデアに留まらず、特許を申請し、商売として形にしていくまでの過程が丁寧に描かれます。周囲の反対を押し切り、資金調達に四苦八苦し、ようやく「山元オブラート」として世に出すものの、大手の菓子製造会社からは思うように相手にされないジレンマ。けれども「人をだまさない」「誠実に商売をする」というキリスト教的な倫理観を、山下太郎自身が心に刻んでいたことがのちの事業拡大につながります。
最終的に特許権を売却して資金を得る道を選び、彼はさらなる勝負に出ようとします。この過程では、流行する投機や立身出世の風潮にのりながらも、彼が「学問よりも現場」「理論よりも度胸」を重視する姿勢が鮮明に出てきます。
大正期の好景気と成金の時代
やがて世界が第一次世界大戦の渦中に巻き込まれると、日本国内の経済は一時停滞を見せつつも、のちに「大戦景気」と呼ばれる未曾有の好況に突入します。山下太郎も、ここで一気に大勝負を仕掛けていきます。
彼が目をつけたのはロシア・ウラジオストックのサケ缶の滞貨や、アメリカからの肥料(硫安)輸入でした。大手商社がためらうようなリスクの高い案件にも、度胸をもって踏み込み、為替取引や現地官憲の対応を交渉力で乗り越える。「投機」と揶揄されながらも、時流を捉えたやり口で莫大な利潤を得るのです。
特に、ウラジオストックのサケ缶在庫を激安価格で買い取り、革命の混乱で失いかけたところを日本政府や外務省の意向をフル活用して勝ち取る場面は、痛快ながらも危うい綱渡りを印象づけます。
自動車を買い、料亭で豪奢な宴会を開き、芸者をあげる――いわゆる「成金」の象徴的行動に山下太郎も身を染めますが、その裏には常に危険と隣り合わせの投機があり、失敗すれば夜逃げの可能性すらあったと繰り返し強調されます。
新たな舞台:満洲への挑戦
国内の景気で荒稼ぎした彼は、さらに視野を海外へ向けます。父親や知己からの「満洲の鉄道・開発事業へ参入してはどうか」という話が持ち上がり、植民地化の流れに乗るようにして彼は満洲へ足を伸ばしていくことになるのです。
満洲は農地の開拓だけではなく、鉄道利権、石炭・鉄鉱石などの地下資源、中国東北部の広大な土地など、巨大なビジネスチャンスの宝庫に見えました。山下太郎はここでも「実地で動き、交渉し、時には無謀ともいえる企てをして大金を得る」スタイルを崩しません。
しかし、そのやり方には「山師」「ハッタリ屋」という批判が常につきまとい、若くして財をなしたものの、失敗すればまた振り出しに戻る不安と背中合わせでした。実際、投資が軌道に乗ったかと思えば、政情不安や国内外の政治的な動きで安定せず、彼が苦境に陥る場面は少なくありません。そのたびに度胸と巧みな話術を駆使して切り抜けていくところに、この物語の躍動感があります。
満洲から世界へ:アラビアの油田を目指す
物語の後半では、世界のバランスが大きく変化していく中、山下太郎はさらに遠い地へと野心を広げます。鉄や船舶、穀物の取引を経て「この地球には無限の資源と可能性がある」と確信するようになり、ついにはアラビアの油田へ触手を伸ばそうと考えるのです。
日本国内ではまだそれほど認知度の高くなかった石油の将来性をいち早く察知し、技術と資金をどうかき集めて採掘事業に乗り出すかを模索する山下太郎の姿には、かつて札幌農学校で大志を唱えたクラーク大佐の精神が影響を与えているようにも見えます。農業でも鉱業でも、自らの手で理想を切り開く――この突飛ともいえる行動は、幼い頃からの「狭い場所にじっとしていられない」性格とも結びついています。
地元との対立、家族との確執
その反面、秋田の祖父や父との間では溝が広がり続けます。もともと没落した家系を再興させたいという意識が強かった祖父や父親にとっては、豪快な勝負に出る太郎の振る舞いは、理解しがたいものでもありました。ときに父親が正論を説いても、太郎は「無茶が人生を拓く」と意に介さない。儲かった金を派手に使っては「まるでバクチだ」と言われ、またも衝突する――そんな構図が繰り返されます。
それでも彼は「成功すればよい」とばかりに投資や交渉に突き進み、商機を逃さず世界を舞台に立ち回るのです。
“血ある者は泣き”――情熱と倫理のはざまで
物語を通じて強調されるのは、彼が学生時代に出会ったキリスト教的人物、江原素六から受けた言葉です。「血ある者は泣き、涙なき者は笑う」という一節が、山下太郎の人生を象徴しているように描かれます。どんなに大きな成功をおさめても、周囲の人に配慮し、誠実さを捨てないこと――これが彼なりの倫理観となり、ときに外部からは矛盾しているように映る行動でも、根本にある純粋さを感じさせます。
札幌農学校におけるクラーク大佐の「Boys, be ambitious.」に触発された若者が、投機まがいのビジネスで巨利を得て、さらに海外を舞台に大博打を打つ。いわば欲望に忠実な豪快さと、人のために尽くそうとするクリスチャン精神の融合こそが、彼という人間の魅力と危うさを両立させていました。
物語の余韻と学べること
青年期の挫折、恋の痛み、軍隊での苦闘などを経ながらも、「狭い世界に閉じこもりたくない」「人生は一度きり」と突き進む姿に、読者は一種の羨望と同時に怖さも覚えます。現に、彼は投機や不安定な海外情勢によって幾度も転落を味わいかけ、そのたびに紙一重で成功を手にします。
この物語が読者に訴えかけるのは「人生は危険とチャンスに満ちている」という現実です。安定を求めるか、リスクを承知で思いきった行動に出るか――登場人物たちの多彩な選択とその結果が、当時の日本社会のまばゆい変化を鮮やかに映し出しています。
山下太郎のように突飛な行動は真似できないとしても、未知の分野へ踏み出していく勇気や、大胆な決断力の大切さを教えてくれる作品です。酒と恋に惑いながらも、失敗を重ねて学び、最後にはアラビアの砂漠へ向かうというスケールの大きさは、そのまま「クラーク大佐の教えを体現している」とも言えましょう。
一方で、身近な家族や友人の苦言や反発、伝統的な価値観との軋轢、さらには国内外の政情不安が、いつも彼を襲います。成功と失敗が紙一重の世界において、彼が辛うじて信じ続けたのは「誠実」「神への信仰」「人を愛する」こと。いくら派手な行動に出ようと、根底には「血ある者は泣く」という言葉が据わっていたからこそ、周りの人も完全には彼を見放せなかったのではないでしょうか。
まとめ
『アラビア太郎』は、単なる冒険物語でも、単なる実業家の成功譚でもありません。激動の明治・大正期の空気と、主人公の豪快なエピソードの数々が織り成されて、読む者に人生の大きな可能性と危うさを同時に感じさせます。
北海道の大地から世界へ飛び出し、ロシア革命下の市場で稼ぎ、満洲での開発に踏み込む。そして最終的にはアラビアの油田へと向かう――その行動力と時代を読む鋭さは、現代にも通じる“先を見据える力”を私たちに示唆してくれるように思えます。
克服しきれない葛藤や矛盾、家族との対立を抱えながらも、自分の信じる道を貫いた山下太郎の物語は、まさに「Boys, be ambitious.」を地で行った物語の体現と言えるでしょう。