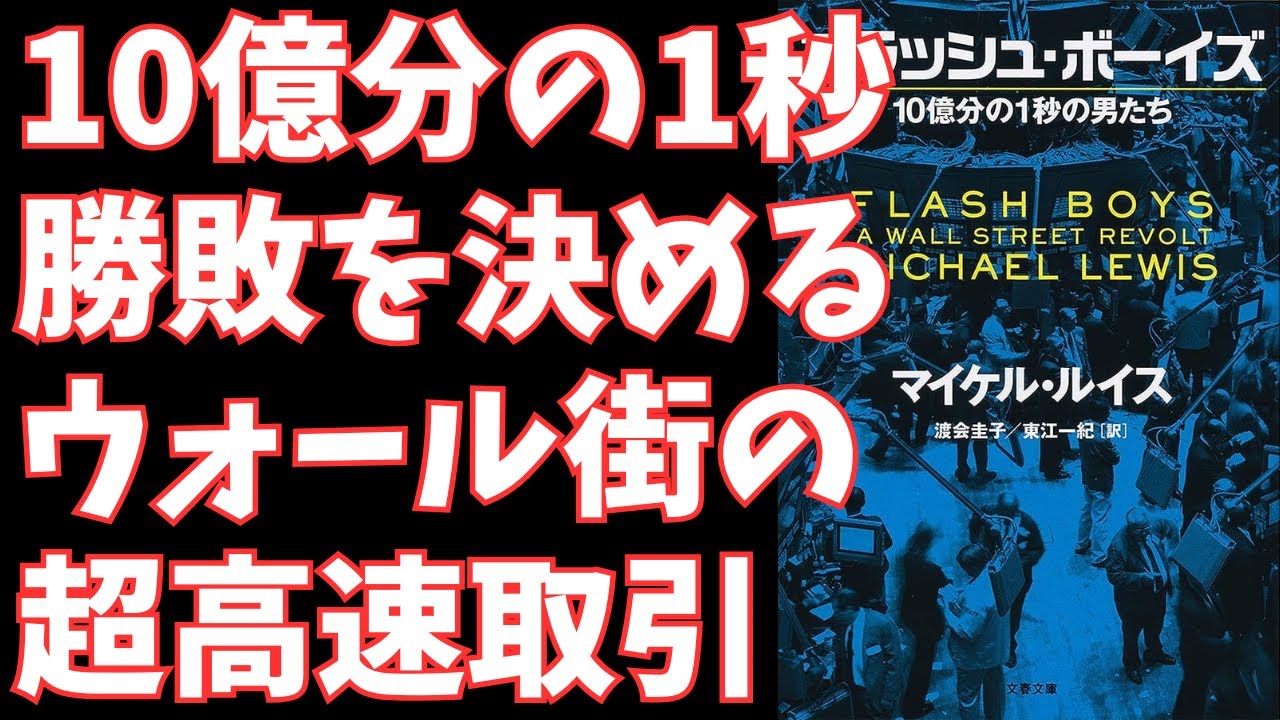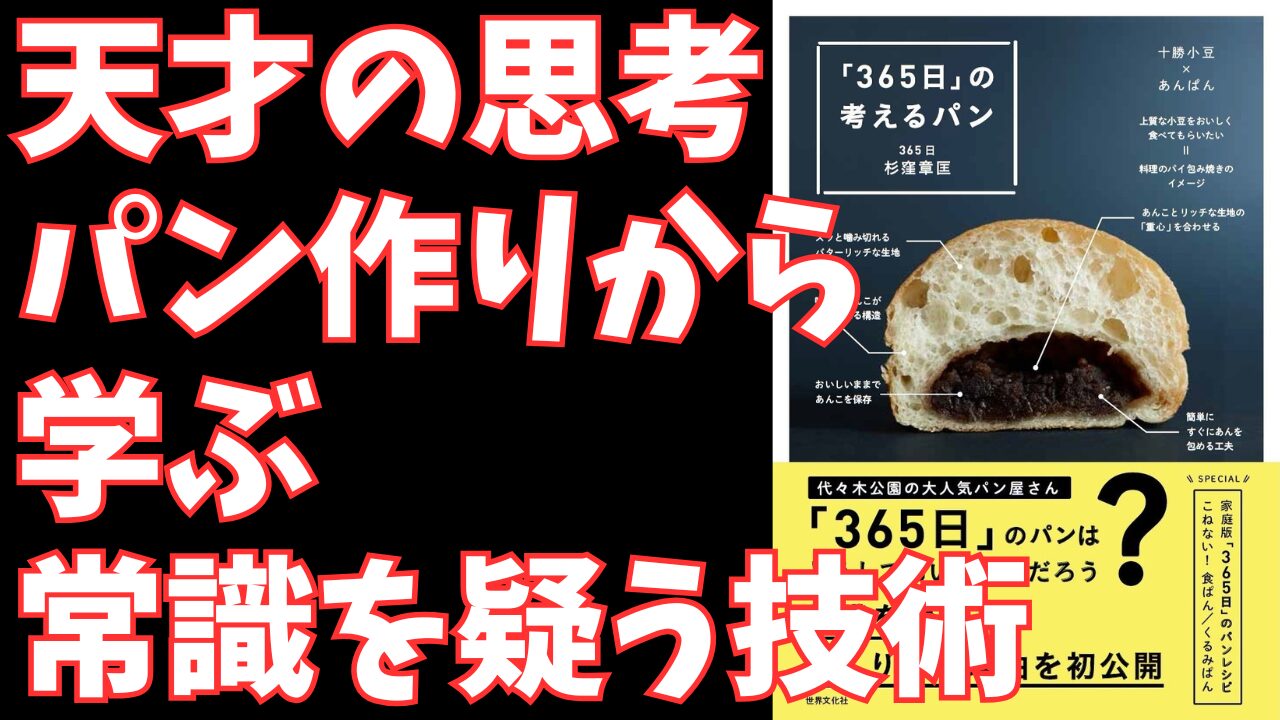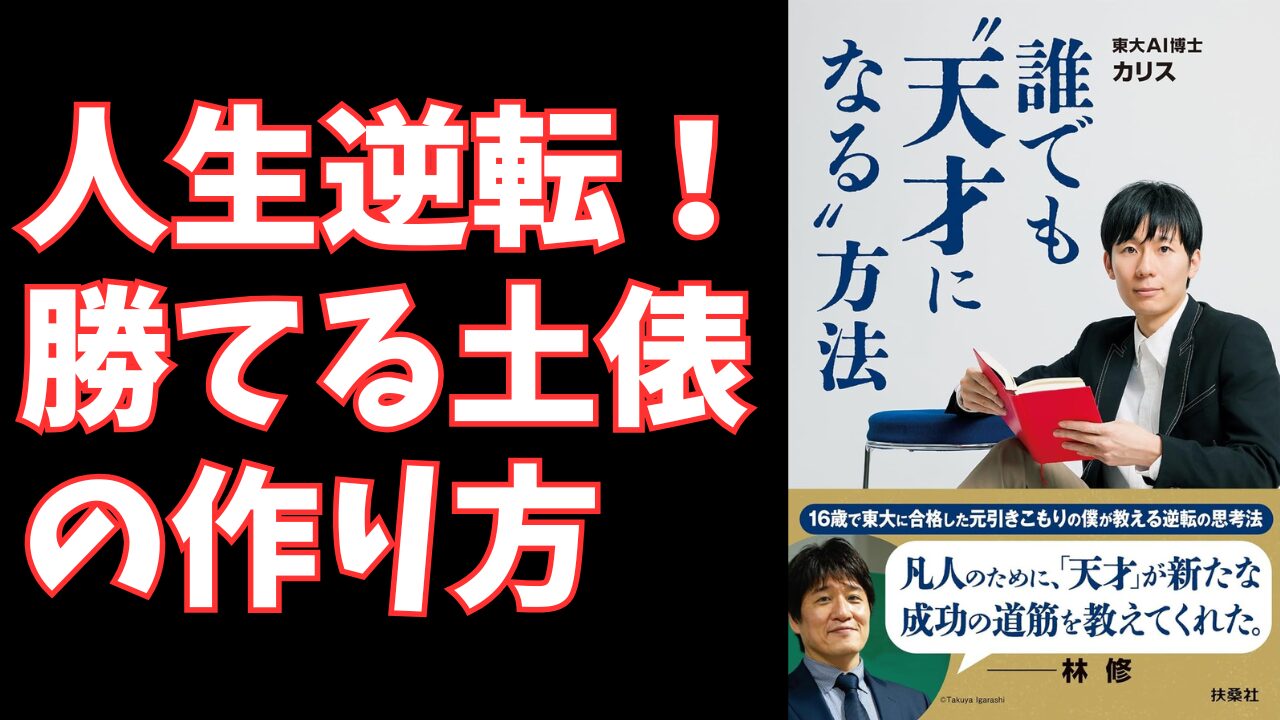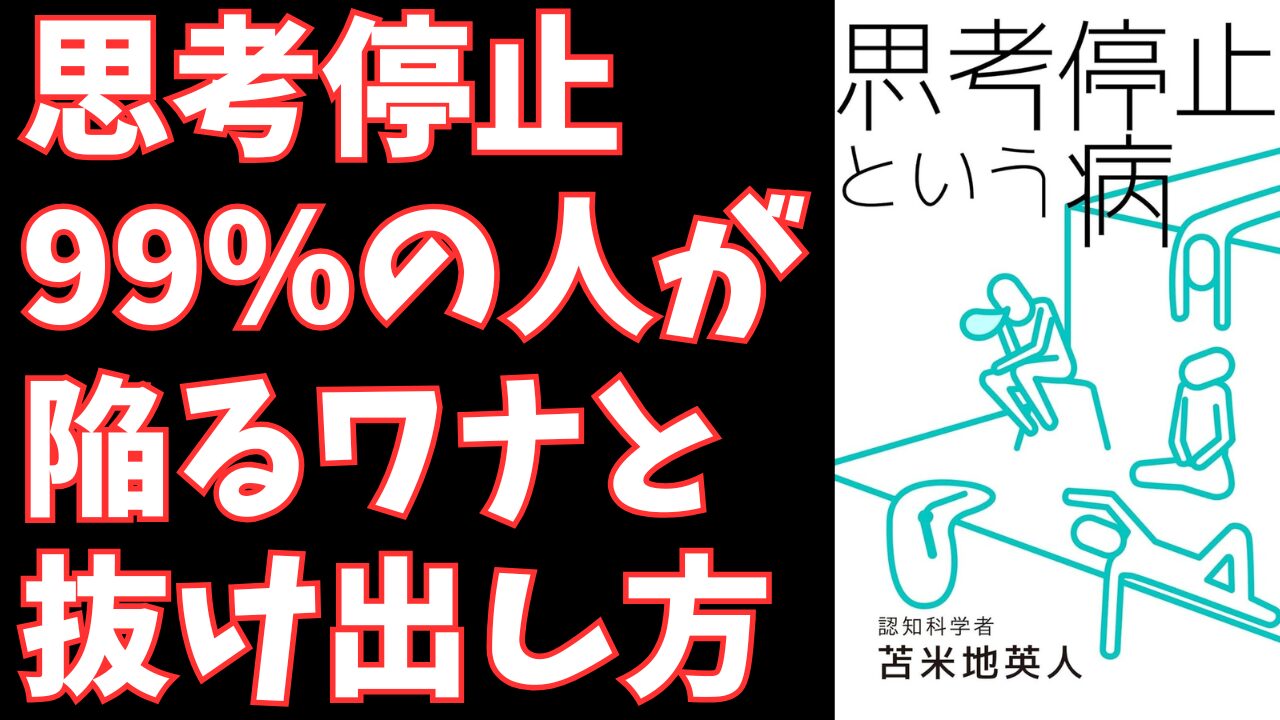オードリー・タンが語る未来の働き方と社会変革──『まだ誰も見たことのない「未来」の話をしよう』から学ぶ、多忙なビジネスパーソンのための「希望の創り方」
台湾のデジタル担当大臣、オードリー・タン氏が、自身の未来観について語った書籍『まだ誰も見たことのない「未来」の話をしよう』。
本書では、「未来は希望のほうが多い。なぜなら、私たち自身が未来を創っていけるからです」という力強いメッセージのもと、テクノロジーが社会や働き方に与える影響、AIとの向き合い方、そして台湾で実践されている「デジタル民主主義」や「ソーシャルイノベーション」の具体的な取り組みが明かされています。
この記事では、本書の内容に基づき、多忙なビジネスパーソンが未来を切り拓くために知っておくべき「デジタルの本質」「AIの活用法」「社会課題の解決アプローチ」、そして「個人としての在り方」を深く掘り下げて解説します。
本書の要点
- デジタルの本質は「人と人をつなぐ」ことであり、IT(機械と機械をつなぐもの)とは明確に異なる。
- 台湾で実践される「デジタル民主主義」は、市民に選択権を委ね、「Fast(速さ)」「Fair(公平さ)」「Fun(楽しさ)」の3Fで推進される。
- 社会問題は、立場や場所を超えて人々が協力する「ソーシャルイノベーション」によって解決し、誰もが参加できるオープンな社会を目指す。
- AIは「Authoritarian Intelligence(権威的知能)」ではなく、「Assistive Intelligence(補助的知能)」、すなわち「ドラえもん」のような存在として活用すべきである。
- 未来は私たちが創るものであり、一人ひとりが「まだ鳴ることのできる鐘を鳴らす」ことで社会変革に参加できる。
なぜ今、オードリー・タンの言葉に耳を傾けるべきか
「10年後、私たちの仕事はどうなっているだろうか?」
「AIに仕事を奪われるのではないか?」
「加速する社会の変化に、どう適応すればいいのか?」
テクノロジーの急速な進展、超高齢社会、環境問題。未来を想像するとき、希望よりも不安を感じてしまうビジネスパーソンは少なくないでしょう。
そんな現代において、台湾のデジタル担当大臣オードリー・タン氏は、一貫して「未来は希望のほうが多い」と語ります。なぜなら、「私たち自身が未来を創っていけるから」 です。
オードリー・タン氏は、35歳という史上最年少で台湾の閣僚に就任し、新型コロナウイルス禍では「マスクマップ」の開発や「ショートメッセージ実聯制」の導入を主導し、台湾の防疫対策に大きく貢献した人物として世界的に知られています。
しかし、その思想の根底にあるのは、単なるテクノロジーの推進ではありません。あくまで「人」を中心(Human-Centered)に据え、テクノロジーを用いて「誰も取り残さない」社会を実現しようとする強い意志です。
本書『まだ誰も見たことのない「未来」の話をしよう』は、そんなタン氏の哲学と、台湾での具体的な実践例が詰まった一冊です。この記事では、多忙なビジネスパーソンが明日からの仕事や生き方に活かせるエッセンスを、本書から抽出して詳しく解説します。
「デジタル」と「IT」の決定的な違い──テクノロジーの真の価値
あなたは「IT」と「デジタル」の違いを明確に説明できるでしょうか?
オードリー・タン氏は、この二つを明確に区別します。
- 「IT(Information Technology、情報技術)」:機械と機械をつなぐもの。
- 「デジタル(Digital)」:人と人をつなぐもの。
タン氏が台湾で「IT大臣」ではなく「デジタル担当大臣」と呼ばれたい理由は、ここにあります。タン氏の仕事は、機械を自動化することではなく、テクノロジーを用いて「多様性に富んだ社会において人間同士のコミュニケーションをより促進すること」なのです。
例えば、かつてのエレベーターは操作員がいましたが、今は自動化されています。これはIT(機械と機械のつながり)です。しかし、デパートのエレベーターにいるスタッフは、操作が目的ではなく、ゲストにサービスを提供し、コミュニケーションをとることが仕事です。
タン氏は、反復性が高い仕事はITや機械に任せ、人間はお互いのコミュニケーションに注力していこう、というのが今の風潮だと述べています。
タン氏自身のジョブディスクリプション(職務記述書)は、その哲学を象徴しています。
- 「モノのインターネット」を見たら、「人のインターネット」に変えていこう。
- 「バーチャルリアリティ」を見たら、「共有現実」に変えていこう。
- 「マシンラーニング」を見たら、「協業学習」に変えていこう。
- 「ユーザー体験」を見たら、「人間体験」に変えていこう。
- 「シンギュラリティ(技術的特異点)が近い」と聞いたら思い出そう。「プルーラリティ(複数性)」がすでにここにあることを。
すべてのテクノロジーの向こうには、必ず「人」がいる。この視点こそが、デジタルのコアバリューです。
AIは「ドラえもん」である──AIを「補助的知能」にするための向き合い方
ビジネスパーソンにとって最大の関心事の一つが「AI」でしょう。「AIに仕事が奪われる」という不安に対し、タン氏は明確に答えます。
「私にとってAIとは『Assistive Intelligence(補助的知能)』であり、『理想のAIはドラえもん』です」
タン氏は、AIが人類に取って替わる「Authoritarian Intelligence(権威的知能)」、すなわち『ターミネーター』のような世界を恐れる人々の気持ちも理解できるとしつつ、AIの未来は私たちが創っていけると信じています。
「Assistive Intelligence(補助的知能)」は、「あなたにとってよきように」という出発点に立ち、なぜその決定をしたのかを人間に説明してくれます。
その具体的な例が、コロナ禍の台湾で行われた中央感染症指揮センターの毎日(土日祝含む)の記者会見です。台湾は多様な言語社会であり、主流の中国語が第一言語ではない人も多いため、会見には同時手話通訳とAI字幕が導入されました。
しかし当初、AI字幕は誤字が多かったのです。そこで、まずはAIが文字起こしを行い、それに対して人間が編集者のように誤字を正す というハイブリッドな方法が取られました。
AIは学習能力を備えていますが、データがたまるまでには時間がかかります。タン氏は、AIには「学習段階」と「発揮段階」があり、私たち人間が歌を練習する時(学習段階)に努力が必要なのと似ていると説明します。
AIが万能であるかのように恐れるのではなく、現状のAIの特性を理解し、人間のサポートと組み合わせることで、「協業学習」を進めていく。AIは仕事を奪う脅威ではなく、私たちの能力を補助してくれるパートナー(ドラえもん)として付き合っていくべきだとタン氏は説いています。
台湾に学ぶ「デジタル民主主義」のリアル──“3つのF”が鍵を握る
オードリー・タン氏の仕事の核心の一つが「デジタル民主主義」の推進です。これは、デジタルを用いて民主主義をより前進させる取り組みを指します。
タン氏は自らを「公僕(公務員)の公僕」と宣言し、政府の縦割り組織を超えて協業しています。その働き方は、書類をインターネット上でシェアし、異なる時間・場所で「共同執筆」するオープンソースコミュニティのスタイルそのものです。
このデジタル民主主義の成功要因として、タン氏は“3つのF”を挙げています。
- Fast(速さ):政府がまず速やかに対応する。
- Fair(公平さ):情報の通達や政策は公平に行う。
- Fun(楽しさ):ユーモアを持って行う。
この3Fは、台湾の防疫対策において見事に発揮されました。
事例1:ショートメッセージを利用した実聯制(店舗登録システム)
台湾ではコロナ禍で公共の場所に入る際、実名制登録が義務づけられました。当初は紙への記入でしたが、不便さや個人情報保護の懸念が市民から指摘されました。
そこでタン氏が発案したのが、携帯電話のショートメッセージを使ったシステムです。場所ごとに割り当てられたQRコードを読み取り、SMSを「1922」(感染症相談ダイヤル)宛に送るだけ。これなら簡単で、個人情報が店舗に残る不安もありません。
重要なのは、ここでも「選択権を市民に委ねた」ことです。
紙で登録したい人は紙を、通信会社を信頼する人はショートメッセージを、と利用者が好きな方法を選べるようにしました。もし政府が権威的であれば、一つの方法を強制したでしょう。これが「Assistive(補助的)」なデジタル民主主義の姿です。
事例2:フェイクニュース対策とユーモア
台湾はフェイクインフォメーション(故意に捏造された偽情報)への対策でも世界から注目されています。
行政院では、「故意・危害・虚偽」の三つの条件が揃ったフェイクインフォメーションに対し、各省庁の〈即時対策チーム〉が 60分以内に正しい情報を発信 します(Fast)。
その際、「2・2・2の原則」(見出し20文字以内、図版2点、本文200文字)という分かりやすいガイドラインが適用されます(Fair)。
そして最も重要なのが「Fun(楽しさ)」です。
タン氏は「正しい情報」というだけでは見てくれないかもしれない、と指摘します。「ユーモアは怒りと同じくらい拡散されやすく、かつ、怒りより共有する満足度が高い」 からです。
政府がただ「それはデマです」と否定するのではなく、ユーモラスな画像やキャッチコピー(例えば、行政院長がコミカルなポーズでお尻を守る画像と共に「トイレットペーパーの原料はパルプです。マスクと同じ原料ではありません。お尻は一つしかありません」と呼びかけるなど)を使って対抗することで、人々は楽しみながら正しい情報を拡散してくれます。
報道の自由を制限することなく、ユーモアでフェイクインフォメーションを抑える。これもまた、“3つのF”が機能したデジタル民主主義の実践例です。
日本のDXの課題「2025年の崖」をどう乗り越えるか?
日本のビジネスパーソンにとって喫緊の課題である「DX(デジタルトランスフォーメーション)」。経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」(老朽化したレガシーシステムがDXの足かせとなり、多大な経済損失を生む問題)について、タン氏は二つの側面から解決策を提示しています。
第一に、問題は古いシステムそのものではなく、「若いエンジニアが学べる環境がないこと」だと指摘します。タン氏自身、銀行のコンサルタント時代に20~30年前の古いシステムを扱った際、自身のPC上で学習環境を再現できたといいます。学びたいと思う若者に、実際の環境を体験させる方法を提供することが重要です。
第二に、解決策としての「Open API」の活用です。
API(Application Programming Interface)とは、外部から接続するためのインターフェース(窓口)です。これをオープンにすることで、システムの基幹部分(安定性が最重要)に触れることなく、新しいサービス(例えばスマートフォンのアプリやVR)を柔軟に開発できます。
これは、電力システム本体を変えずに、変圧器(API)を使って新しい電化製品(新サービス)を使えるようにすることに似ています。
台湾の金融業界(FinTech)ではOpen APIが普及し、銀行の基幹システムを使わなくとも、外部のエンジニアが残高確認や会計管理ソフトウェアを開発できるようになりました。
「Open API」がなければ、古いシステムを知るベテランと、新しい技術を持つ若者の創造力が争うことになっていたでしょう。すべてをオープンにしたからこそ、多様な人々が創造力を発揮できるようになったのです。これは日本のDX推進においても非常に重要な示唆となります。
「ソーシャルイノベーション」とは何か?──社会課題を解決する“ハッカー精神”
タン氏が自らに課したミッションの一つが「ソーシャルイノベーション」の推進です。これは、従来とは異なる創造的な解決法によって社会問題や課題を解決するという概念です。
タン氏は「すべての人が孤独に闘うのではなく、助け合いながら社会を変えていく」在り方が大事だといいます。
事例:〈総統杯ハッカソン〉と〈g0v〉
台湾では、市民が課題を提議し、政府のオープンデータを活用して解決案を模索する〈総統杯ハッカソン〉が毎年開催されています。プログラマーだけでなく、公務員や一般市民も参加します。
驚くべきことに、このハッカソンに賞金はありません。それでも多くの提案が寄せられるのは、グランプリ受賞プランの9割が政策として実行に移されているからです。
- 離島エリアの緊急医療を改善:衛生福利部(厚労省に相当)の職員が発起人となり、ヘリ搬送の情報を関係者全員で共有できるプラットフォームを構築。6つの法律の壁を突破し、実現しました。
- 農地工場からの汚染をなくす:NPOが、農地の違法工場による汚染問題の徹底調査を経済部(経産省に相当)に要求。政府が調査情報の公開を開始しました。
- 奉茶行動(お茶を振る舞う習慣):民間の社会的企業が、台湾中の無料給水機の位置情報をリアルタイムで把握できるアプリを開発。ペットボトル削減に貢献しています。
こうした活動の背景にあるのが、タン氏も設立から参加するシビックハッカー(社会問題の解決に取り組む民間のエンジニア)コミュニティ〈g0v(ガヴ・ゼロ)〉です。
彼らのスローガンは「なぜ誰もやらないんだと嘆くより、まずは自分がその〝誰もやらないうちの一人〟であるということを認めよう」です。
政府のデジタル化が進んでいなかった2012年頃、「政府がうまくできないなら、自分たちが手本を見せよう」と立ち上がりました。コロナ禍で活躍した〈マスクマップ〉も、元々は〈g0v〉のメンバーが徹夜で作ったものが始まりです。
ハッカー精神とシビックマインド
この「ソーシャルイノベーション」の根底には、タン氏が16歳で出合った「ハッカー精神」があります。
ハッカーというと悪いイメージがあるかもしれませんが、タン氏の言うハッカーとは「新しい物事を創造し、今そこにある問題を解決する。そして自由と共有の価値を信じる」人々です。
タン氏は、ハッカーにとって大切な5つの心得を紹介しています。
- 世界には面白い問題がたくさん待っている。
- 問題を解決したら、他の人が同じ問題で時間を無駄にしないよう、解決方法をシェアしよう。
- 単調でつまらないことは機械に任せよう。
- 自由とオープンデータを追求し、権威主義に抵抗しよう。
- 勤勉に鍛錬し、絶えず学習しよう。
この「シェアする」精神が、ソーシャルイノベーションの鍵です。「自分一人で解決しようとしても永遠に一部分しか解決できない」からです。
この「シビックマインド(市民の公共精神)」が台湾で高まったきっかけは、2014年の〈ひまわり学生運動〉だったとタン氏は振り返ります。政府が国民に説明なく協定を締結しようとしたことに大規模な抗議運動が起こり、「政治は国民が参加するからこそ前に進めるのだ」という発見が社会全体に広がりました。
「同温層」は悪くない──分断を乗り越えるコミュニケーション術
デジタル化が進む一方で、SNSでの「炎上」や「分断」は深刻な問題です。ビジネスシーンでも、意見の対立に悩む人は多いでしょう。
タン氏は、インターネット上のコメント欄の設計も「大切な政治の一つ」だといいます。
台湾のオンライン討論プラットフォーム〈vTaiwan〉では、賛成・反対のボタンを押すと、自分のアイコンが同じ意見の場所に位置づけられ、意見の分布が可視化されます。これにより、極端な意見が目立ちやすい現実の場とは異なり、多数派がどこにいるのかが分かります。また、自分の友人や家族が違う意見を持っていることに気づいても、「意見が違っても友人は友人、家族は家族」と認識できます。
「ガラスのハート」にならない
タン氏は、ネット上の言い争いの原因の多くは「ガラスのハート」にあると指摘し、「ガラスのハート」にならないようアドバイスします。台湾では「地雷を踏む」というそうです。
もし不快な地雷を踏まれても、心のマッサージ(あるいは長く睡眠をとる)をすればよい。そして、ネガティブなことがあってもユーモアを持って対処することが大切だといいます。
トークイベントでマイクの音が出なかった際、タン氏は「私の脳波が強すぎたためでしょうか」と言い、2歩前に出て直った時には「自分から前に数歩進んでこそ、コミュニケーションはスムーズになります」と言いました。もしスタッフを叱責していたら、不快な状況になったでしょう。
「同温層」と「事実の共有」
台湾には「同温層(トンウェンツェン)」という言葉があります。同じ興味を持つコミュニティ(いわゆる「タコツボ」)に閉じこもることを皮肉った表現ですが、タン氏はこれを悪いものだとは思いません。
なぜなら、そこではお互いに励まし合えるからです。タン氏自身もハッカー、詩人、翻訳者など多くの「同温層」に所属しています。「主流しかない世界は恐ろしい」とタン氏は言います。重要なのは、異なるコミュニティ間の橋渡しをすることです。
意見の合わない人とどう付き合うか?
ある日本の地方議会議員が「LGBTQを法律で保護すると日本は滅亡する」と発言した事例について問われたタン氏は、「共通の価値観を築くには、事実を共有することが大事」だと答えます。
子どもを産まない選択はLGBTQに限りません。また、生殖医療の進歩(事実の共有)によって、同性カップルが子どもを持つことも不可能ではなくなるかもしれません。「人口の減少は客観的な事実ですが、異性愛者だけが子どもを育てることができるわけではないということもまた、客観的な事実です」。
お互いに客観的な状況(事実)を理解し合った上で、対話を始めることが重要なのです。
忙しい私たちが「未来を創る」ためにできること──個人へのQ&A
本書の最終章は、日本の皆さんからの悩み相談にオードリー・タン氏が答えるQ&A形式になっています。多忙なビジネスパーソンの心にも響く、珠玉のアドバイスをご紹介します。
Q:自分がすべきことをどのように見つけていけばよいかわかりません。
A:まだ鳴ることのできる鐘を鳴らそう。
これはタン氏が愛するレナード・コーエンの歌『Anthem』の一節です。〈SDGs〉のような大きな目標を見て「自分には鳴らせない」と思うかもしれません。しかし、今のあなたにも小さな鐘、例えば〈SDGs〉について学んで誰かに教える、といったことはできるはずです。「あなただからこそできることはあります」。
Q:さまざまなニュースを見ると、世の中が悪い方向に進む気がして無力感を感じます。
A:ニュースが報じているのは「結果」で、それを変えるのはほぼ不可能です。一方で「問題が発生する前に防ぐ」能力は、すべての人に備わっています。
大きな構造的問題を一人で解決することはできません。それはすでに起きてしまった「結果」だからです。しかし、自分の身に問題が起こったら、その原因を考え、再び同じことが起こらないように行動することはできます。
Q:なかなか自分を優先できません。会社や家族のために自分を犠牲にしてきました。
A:自分を大切にすることは、他の人を大切にするための練習です。
人の世話をするために自分を犠牲にして倒れてしまったら、元も子もありません。自分の精神や健康と引き換えにするのではなく、自分の心と身体を大切にしながら、人を大切にする能力をコントロールしていくことが重要です。
Q:若い頃のように「何かに挑戦しよう」というパワーがなくなってきました。
A:純粋に楽しむために続けてもよいのではないでしょうか。
歳を重ねれば、熱意や衝動よりも経験値が上がってきます。コーチとして若い人をサポートするなど、角度を変えて継続することもできます。これまでやってきたことを捨てる必要はありません。
Q:これからの世界を生きていくために、持っておきたい価値観はありますか?
A:社会が用意した脚本通りに振る舞わなくてもいい時代です。
「父だから」「女性だから」「部長だから」といったラベル(身分)に従って行動するのは、本当の意味で社会と付き合っているとは言えません。
私たちはラベルにとらわれず、「私にはこういう経験があり、あなたにはどういう経験があるか」という実質的な状態によって理解し合える関係であるべきです。そのほうが、きっと自由でいられるはずです。
結論:未来は「創る」もの
オードリー・タン氏の言葉は、終始一貫して「オープン」であり、「インクルーシブ(誰も取り残さない)」であり、そして「希望」に満ちています。
タン氏は自身の著作を持たず、発言はすべてオープンソース(CC0、いかなる権利も保有しない)にしています。なぜなら、自分自身をオープンにすることで、多くの人がその考えを広め、二次利用し、そこから新たなイノベーションが生まれることを知っているからです。
未来は、誰かが予測し、私たちがそれに従うものではありません。未来は、オードリー・タン氏のような一人の天才が創るのでもありません。
未来は、私たち一人ひとりが「まだ鳴ることのできる鐘を鳴らし」、事実を共有し、ユーモアを持って連帯し、創り上げていくものです。
本書をきっかけに、あなたも「一緒に未来を創っていく人」の一人になってみてはいかがでしょうか。