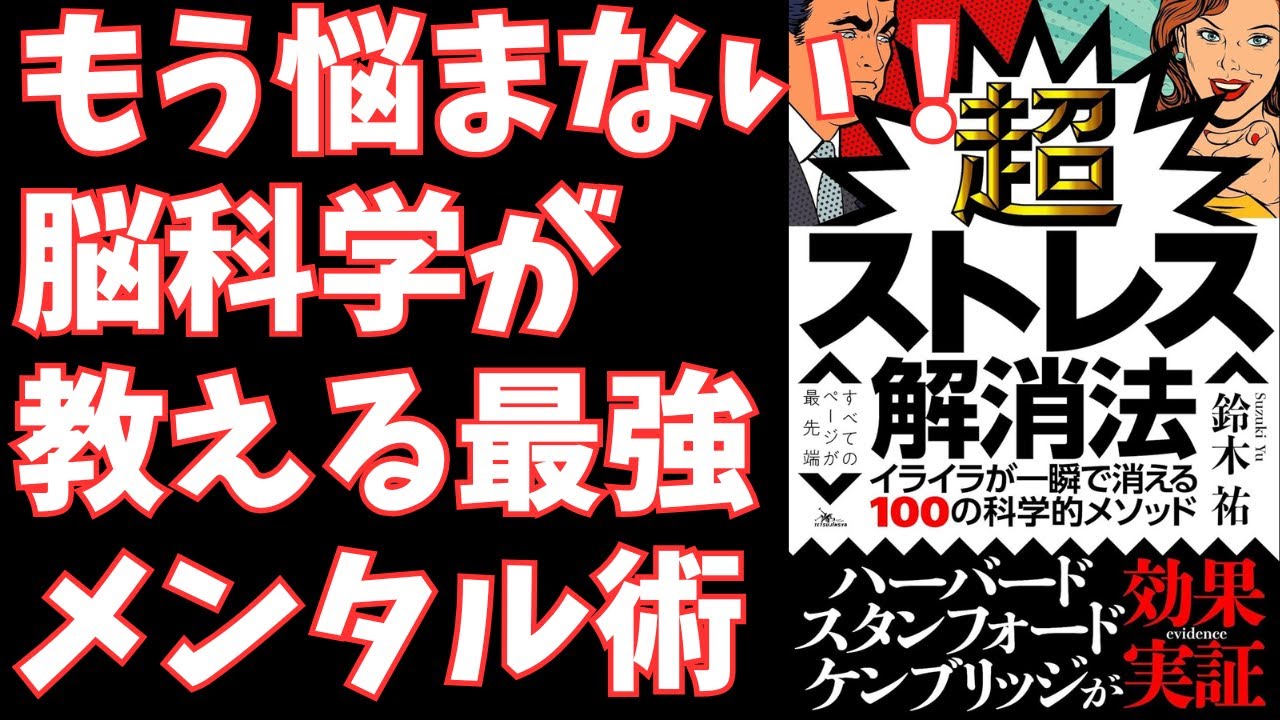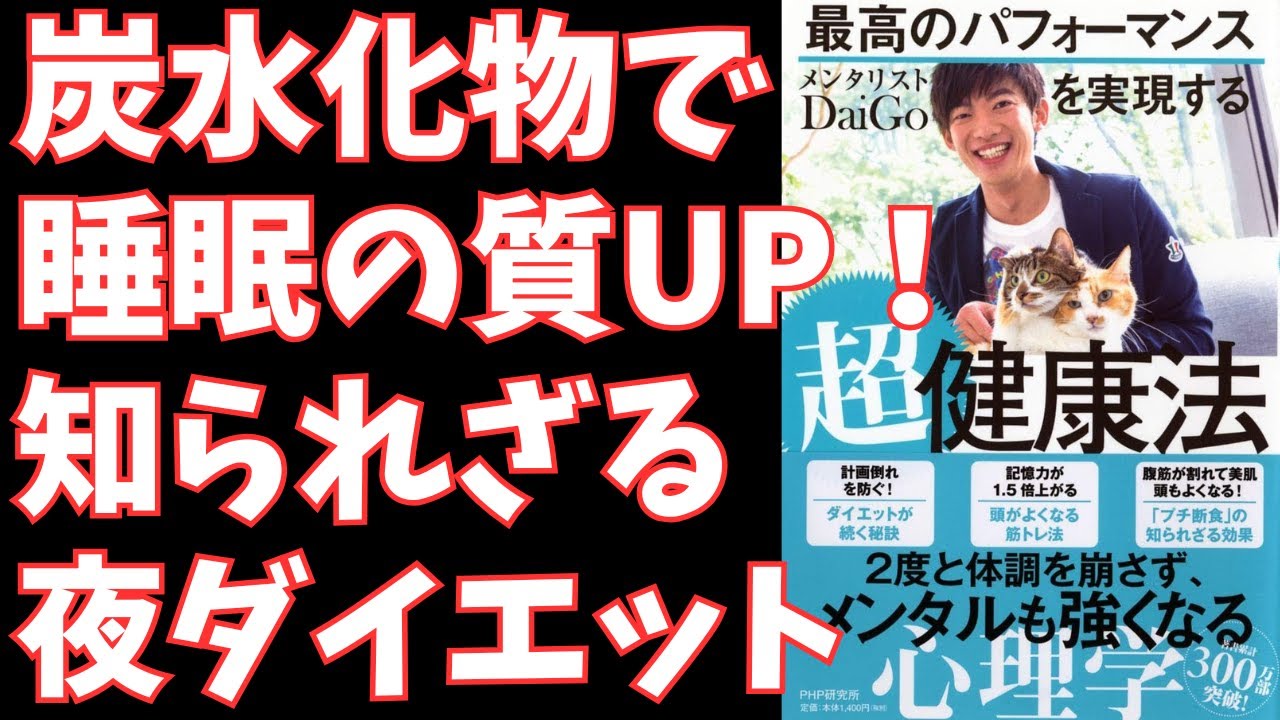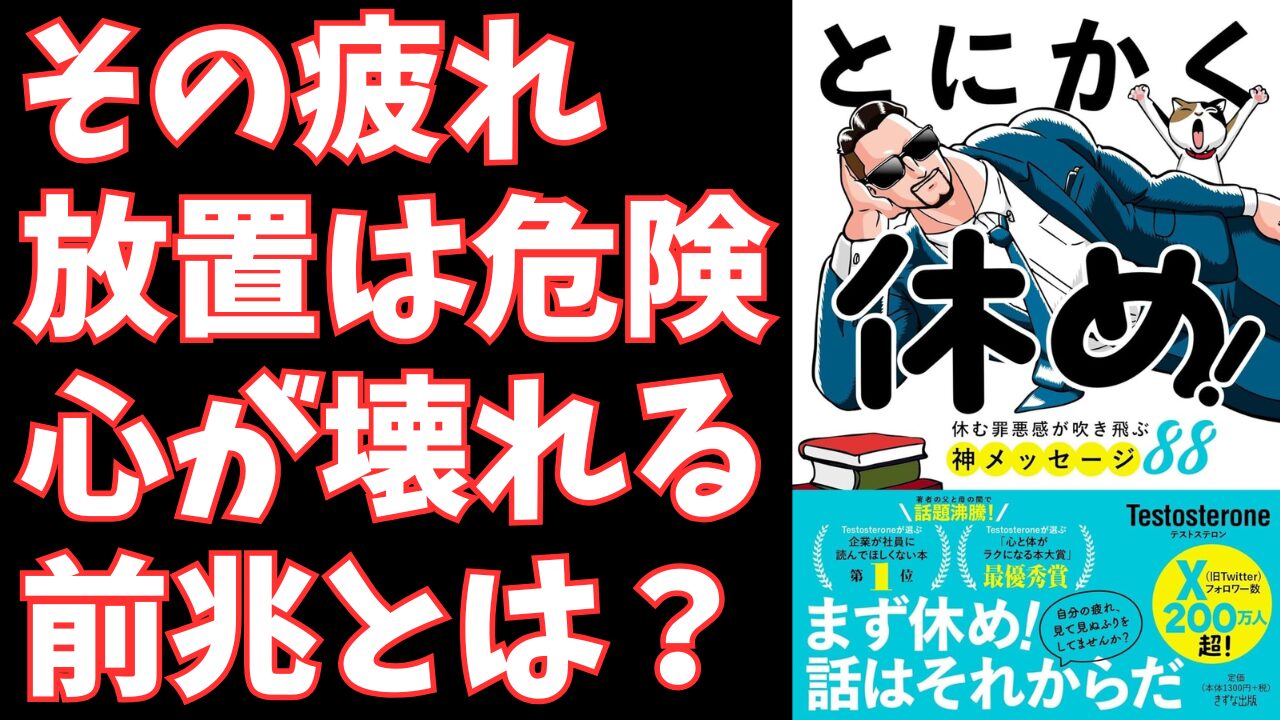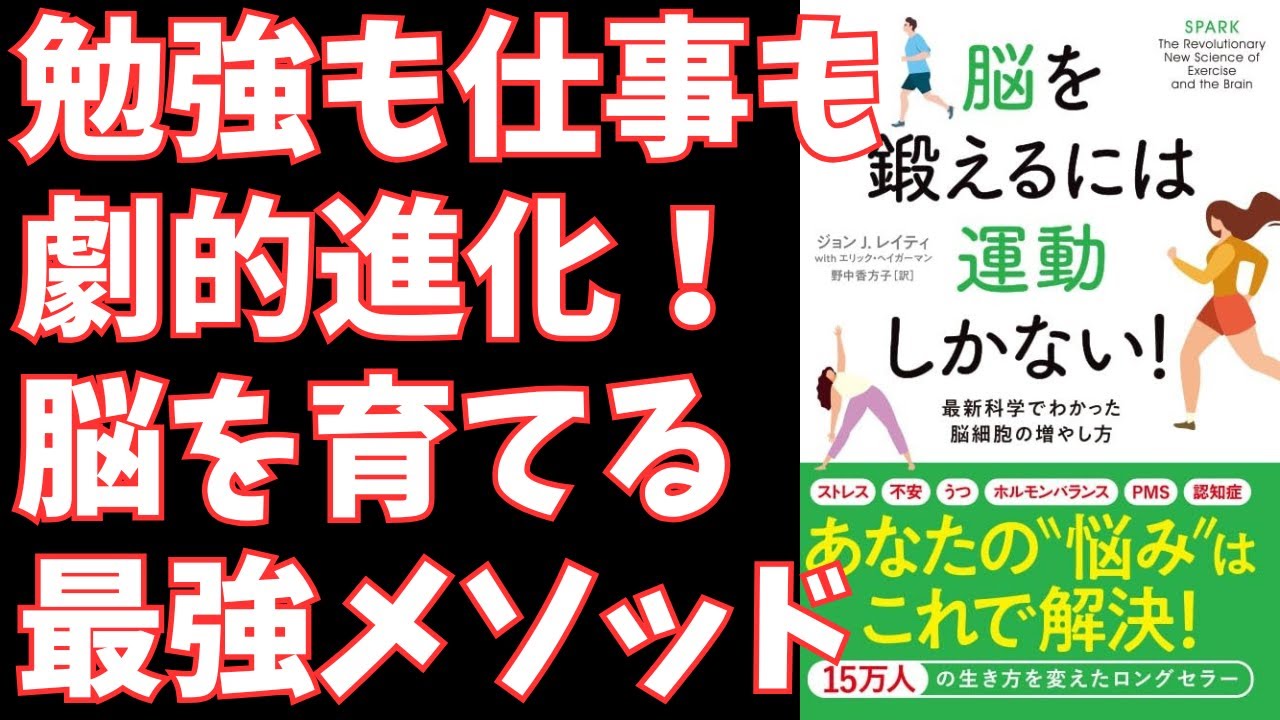最高のパフォーマンスを取り戻す!現代人のための「進化医学」的ライフスタイル
本書は、「進化医学」という視点を軸に、現代人特有の不調を根本から改善するアプローチを提案しています。人類は長い年月をかけ、狩猟採集を中心とした環境で生活してきました。しかし近代化によって生活様式が激変し、私たちの体と心はその変化にうまく適応しきれていません。本書では、このミスマッチこそが肥満や慢性疲労、不安障害、鬱病など、多くの不調の原因だと説きます。
特に重要なのは、体内の「炎症」と、現代人が抱える「不安」。この2つが密接に絡み合うことで、私たちの体調とメンタルは一気に悪化します。そこで本書は、腸内環境の改善や自然とのふれあい、友人との良好な関係づくりなど、狩猟採集時代のライフスタイルを部分的に取り戻す具体的な方法を紹介。さらに、必要に応じた睡眠の再設定やストレスへの応急処置テクニックも提示し、総合的に「最高の体調」を目指すためのヒントを与えてくれます。
以下では、炎症と不安の基礎知識、狩猟採集民の暮らしとの対比、腸内細菌や睡眠、自然環境、友人関係の重要性などを具体的に取り上げながら、忙しい現代を生きる私たちが少しでも体と心を整えるためのアイデアを紹介していきます。
第1章 文明病と進化医学
文明病とは?
現代人は食料や情報を豊富に得られる反面、肥満や慢性疲労、不眠、鬱病などに悩まされるケースが増えています。こうした症状の総称を、本書では「文明病」と呼んでいます。かつての人類は、狩猟採集民として自然のなかで暮らし、限られたカロリーを求めて移動しながら生きていました。しかし、農耕による余剰生産や都市化、テクノロジーの発展などにより、私たちは狩猟採集時代と全く異なる生活を送っています。
これほど環境が変われば、人類の体は当然混乱します。飢えを防ぐために進化してきた脳は、カロリー過多に対応できず肥満を招きやすく、文明が発達したにもかかわらず慢性的な不安を抱えるようにもなりました。そうした問題を解決すべく提唱されているのが「進化医学」であり、「ダーウィニアンメディスン」とも呼ばれています。
人類の進化は長い
骨や遺跡の研究によると、我々の祖先はおよそ600万年にわたって狩猟採集スタイルで暮らしてきたとされます。農耕が始まったのはたかだか1~2万年前で、その後も現代に至るまで、わずかな時間で都市生活や加工食品などが普及しました。つまり、600万年の大半を「低カロリー環境」で暮らした体が、唐突に「高カロリー環境」「情報過多環境」に放り込まれたわけです。
本書では、こうした環境変化の「多すぎる」「少なすぎる」「新しすぎる」という3つの観点を用いながら、私たちが抱えるストレスや不調の原因を探っていきます。例としては以下のようなものが挙げられます。
- 多すぎる:カロリー、精製糖、トランス脂肪酸 など
- 少なすぎる:睡眠時間、自然とのふれあい、運動量、友人との交流 など
- 新しすぎる:都市化の進行、スマホやSNS、孤独 など
身体面だけでなく心まで蝕む文明病
過剰なカロリー摂取や運動不足は、脂肪の蓄積と密接に関わり、結果として「炎症」を引き起こします。また、豊かな生活を維持できるはずの先進国で、鬱病や不安障害が増え続けている背景には「時間感覚の変化」や「孤独」などの問題が存在し、それも体に慢性炎症をもたらすリスク要因になります。こうした「炎症」と「不安」が複雑に絡み合った結果、現代人の体調はさらに悪化していくというわけです。
第2章 炎症と不安 ──2大要因が心身を破壊する
炎症が身体を内側から燃やす
炎症といえば、ケガをしたときの腫れや赤みを想像するかもしれません。しかし本書で扱われる「炎症」の多くは、体内に潜む慢性的なもので、いわば表面化しにくい“とろ火”のような状態です。例えば内臓脂肪が増えると、免疫システムが絶えず出動し、じわじわと周辺組織を攻撃してしまいます。これが長引くと、高血圧や糖尿病、動脈硬化や鬱病など、さまざまな不調の元凶となるのです。
不安は警戒システムの誤作動
一方で、不安自体も人間にとっては必要な感情です。本来なら猛獣の襲撃や火事など、緊急の危機を想定して行動を促すために進化したアラームでした。しかし、狩猟採集民時代の脅威と異なり、現代の不安は「いつ起きるのかわからない」「漠然としている」ものが増えています。こうした「ぼんやりした不安」は、扁桃体を過剰に刺激し、ホルモンバランスを乱し、結果として炎症までも引き起こすのです。
ダブルパンチを防ぐには?
このように「炎症」と「不安」の間には強い相互作用があります。不安で生まれたストレスホルモンが炎症を加速し、炎症レベルの上昇がさらに不安を呼び寄せる……という悪循環。これを断ち切るには、まずは「腸」「環境」「ストレス」などに働きかけ、徐々に生活を狩猟採集民のライフスタイルに近づけていく必要があります。本書では、そのための具体策が各章で解説されています。
第3章 腸を整える ──腸内細菌があなたを守る
腸内細菌という最古の友人
人類の体内には、無数の腸内細菌が住みつき、免疫システムと連携して害ある菌の侵入を防いだり、栄養素を合成したり、炎症を抑えたりしています。しかし近年、抗生物質や抗菌グッズの乱用や、高脂質・低食物繊維食が当たり前になったことから、私たちの腸内には有益な菌が生きにくい環境が生まれています。その結果、「リーキーガット」のような腸壁の破れが進行し、毒素が血管内に侵入して慢性炎症が進むという問題が起こるのです。
腸内細菌と仲直りするには
- 発酵食品を取り入れる:キムチ、味噌、ヨーグルト、納豆などをまんべんなく食べ、腸内の有用菌を増やす
- プロバイオティクスの活用:ビフィズス菌や乳酸菌のサプリを試し、悪玉菌の勢力が勝ちすぎた腸内フローラをリセットする
- 食物繊維の摂取:特に水溶性食物繊維を増やす。根菜や海藻、果物に多く含まれ、腸内細菌のエサになる
- 抗菌製品の使いすぎをやめる:手指や身の回りのすべてを殺菌し続けると、善玉菌も減ってしまう
- 空気清浄にも注意:カビ毒などを放置せず、環境の湿度管理や換気を徹底する
過度に清潔すぎる生活は免疫機能を狂わせ、「アレルギーや炎症リスク」を上げる可能性があります。古代の人類は、野菜や果物を通じて自然発酵食品を口にしてきたし、狩猟採集民の生活は少し汚いくらいが当たり前でした。現代ではできる範囲で「再野生化」を意識し、腸内細菌と友好関係を築き直すことが重要だと説かれています。
第4章 環境を整える ──自然と友人が人生を変える
なぜ自然が必要か
グーグルが社内で行った有名な実験では、ちょっとした配置の違いが人間の行動を左右することが判明しました。これは私たちがいかに環境の影響を受けやすい存在かを示しています。なかでも人間が進化を遂げてきた自然環境とのつながりを断絶するのは、大きなミスマッチを引き起こします。
- 自然のなかにいると副交感神経が優位になり、体の修復モードに入りやすい
- 都市の喧騒は「興奮」と「脅威」のシステムを刺激しやすいが、緑豊かな環境は「満足」の感情を引き出す
一部の研究では、「森林浴」や「公園散策」を週に30分ほど行うだけで鬱病リスクが下がり、高血圧の症状が改善したという報告もあります。人工の自然音や自然映像だけでもリラックス効果が得られることが分かっており、観葉植物をデスクに置くのも推奨されています。
友人との交流が生命を救う
狩猟採集時代、人間は少人数のコミュニティの中で濃密な人間関係を築いてきました。安心感に包まれた「互恵的な」つながりこそが生き延びる鍵だったからです。孤独感が強まると免疫システムが疲弊し、炎症レベルも高まることがわかっています。孤独は喫煙や肥満と同レベルの健康リスクだという調査結果も出ているほどです。
とはいえ、SNSでいくら知り合いを増やしても実感的な安心にはつながりにくいのが実情です。大切なのは「時間をかけて顔を合わせる頻度を増やし、自然と親密度を高める」こと。狩猟採集民が1つのコミュニティで終生を過ごしていたように、現代でも親密な相手と一定以上の時間を共有することで、お互いの脳が警戒モードから満足モードへ切り替わりやすくなるのです。
また、絆を深めるうえで重要なのは「同期行動」。合唱やダンス、スポーツなど、同じ動きを同じタイミングでする行為は、古くからコミュニティの結束力を高めてきました。「友人を増やすのが苦手」という人は、そうした同期行動が多い場に参加してみるのもおすすめです。
第5章 ストレスと向き合う ──応急処置と根本治療
ストレスという現代の猛獣
現代人は、仕事や人間関係、情報の洪水など、慢性的なストレスにさらされています。ストレス反応として分泌されるコルチゾールやアドレナリンは、本来であればサバンナの猛獣から逃れるための一時的な興奮剤にすぎません。しかしそれが常に稼働しっぱなしの状況になると、体は自律神経のバランスを失い、やがて心疾患や鬱病のリスクが高まります。
応急処置のリアプレイザル
ストレスが極まった瞬間に即座に使えるテクニックとして、「リアプレイザル」が本書で紹介されています。例えば、人前でプレゼンをする直前、心臓がどきどきしてきたら「興奮してきたぞ!」とあえてポジティブな言葉を発してみる。これは脳の誤作動を逆手に取った方法で、「緊張」も「興奮」も体の反応としては同じであるため、自分で解釈を変えてしまうのです。
睡眠で負債を返済する
ストレスホルモンによるダメージを修復する重要な時間が「睡眠」。夜しっかり眠れないと、どんなに健康的な生活を心がけても炎症やメンタルの乱れは治まりにくいと指摘されています。キャンプで自然光を浴びながら2日過ごすだけでメラトニン(睡眠ホルモン)の分泌リズムが改善する報告もあり、なるべく太陽のリズムに沿う暮らしを取り戻すことが望ましいのです。
さらに、日常生活では15~30分の昼寝を活用するのがおすすめ。NASAの研究で、パイロットが40分の昼寝を取ると注意力が100%回復し、生産性が34%も上昇したというデータが示されています。狩猟採集民でも季節に応じて昼寝を取り入れていた事例もあり、短時間の仮眠は慢性的な睡眠不足を補う有効な方法になりえます。
第6章 人生の価値観を再定義する
ぼんやりした不安への根本対処
何をしても不安が完全には消えない――そう感じるときは、そもそも人生観や価値観が曖昧なことが原因かもしれません。本書では、自分の「価値」を明確にし、それに沿った形で日常を設計していくことで、不安をコントロールしやすくなると説きます。
- ぼんやりした不安:将来への漠然とした心配事。常に脳の警戒スイッチが入る
- はっきりした不安:猛獣の襲撃や目先の借金など、具体的で対処法がわかりやすいもの
前者は根本的に目的や軸がないと解消されにくいといわれています。そのためにも、「本当に自分が得たいのは何か?」「どんな貢献や活動に喜びを感じるか?」といった問いを繰り返し、自分の人生の意味づけを再確認していく作業が重要となるのです。
第7章 死と向き合う ──限りある生の視点
本書の終盤では、人類が根源的に怖れる「死」について触れられます。死の不安は、古代の狩猟採集民にとっても大きなテーマだったはずですが、彼らには未来へのあまりに長い予測や計画は存在しませんでした。人類が農耕を開始し、蓄えや財産が増えてから「先の先を考える」生活が始まり、死の不安が強く意識されるようになったと推測されています。
しかし、死を想うことは必ずしもネガティブな面だけではありません。死を意識することで人生の充実度が増し、いまこの瞬間に集中できる場合もあるからです。古代仏教の瞑想やアフリカの原始的な儀式など、「死を考える」行為と「生を全うする」行為は表裏一体と本書は説きます。
第8章 遊び ──「いま」を味わう力
現代人の多くは「忙しさ」を言い訳に、純粋な遊びに費やす時間を極端に削ってしまいがちです。しかし、人類の歴史を振り返ると、狩猟採集民には相当量の余暇が存在し、遊び心や娯楽を存分に楽しんでいました。
- 遊びのメリット
- 目の前の行為に集中する力が育まれる
- 「いまここ」に没頭する習慣が、漠然とした不安を和らげる
- 社会性や仲間との連帯感が育ち、孤独や孤立から遠ざかる
仕事と遊びを明確に切り分けるだけでなく、ゲーム化(ゲーミフィケーション)することで作業効率が高まるケースもあるように、遊びは脳のリフレッシュだけでなくモチベーション維持にも役立ちます。
まとめ ──柔軟に実践し、狩猟採集民のDNAを取り戻す
本書のメッセージは「現代を否定して昔に戻ろう」というものではありません。むしろ、科学的根拠を踏まえたうえで、少しずつ狩猟採集民のライフスタイルを取り戻すよう提案しています。腸内細菌を増やし、自然のなかでリラックスし、睡眠を最適化し、孤独を減らす――この一つひとつはどれも難しくないはずです。
ただし、私たちは急激にライフスタイルを変えることは難しいかもしれません。そこで、本書では「すべてをやらなくてもいいから、できるところから始める」ことをすすめています。自然音の音源を流しながら仕事をする、小さな鉢植えをデスクに置く、散歩や昼寝の習慣を作る――こうした小さな工夫であっても、私たちが持つ600万年のDNAの声に沿った方向へ少しずつ近づけるはずです。
忙しいビジネスパーソンにとっては、日々の業務をこなすだけでも手いっぱいでしょう。しかし、体や心のパフォーマンスが落ちてしまえば、結局は仕事の効率も下がってしまいます。本書が紹介する進化医学の知見は、その不毛な悪循環から抜け出し、「最高の体調」を取り戻すための大きなヒントになるはずです。
ぜひ、自分のできる範囲で、思い当たるアイデアから少しずつ試してみてください。古代と現代の両方の知恵を活用し、あなたが本来持っているパフォーマンスを引き出すことが、この本がめざすゴールなのです。