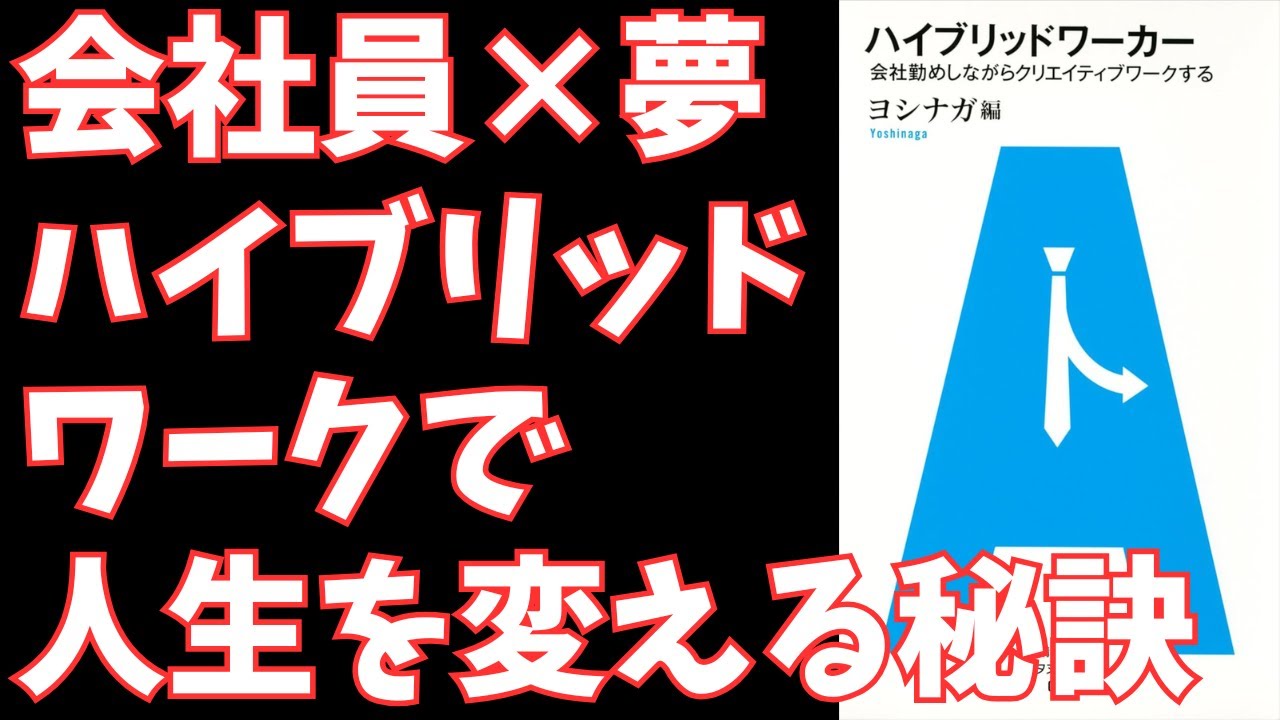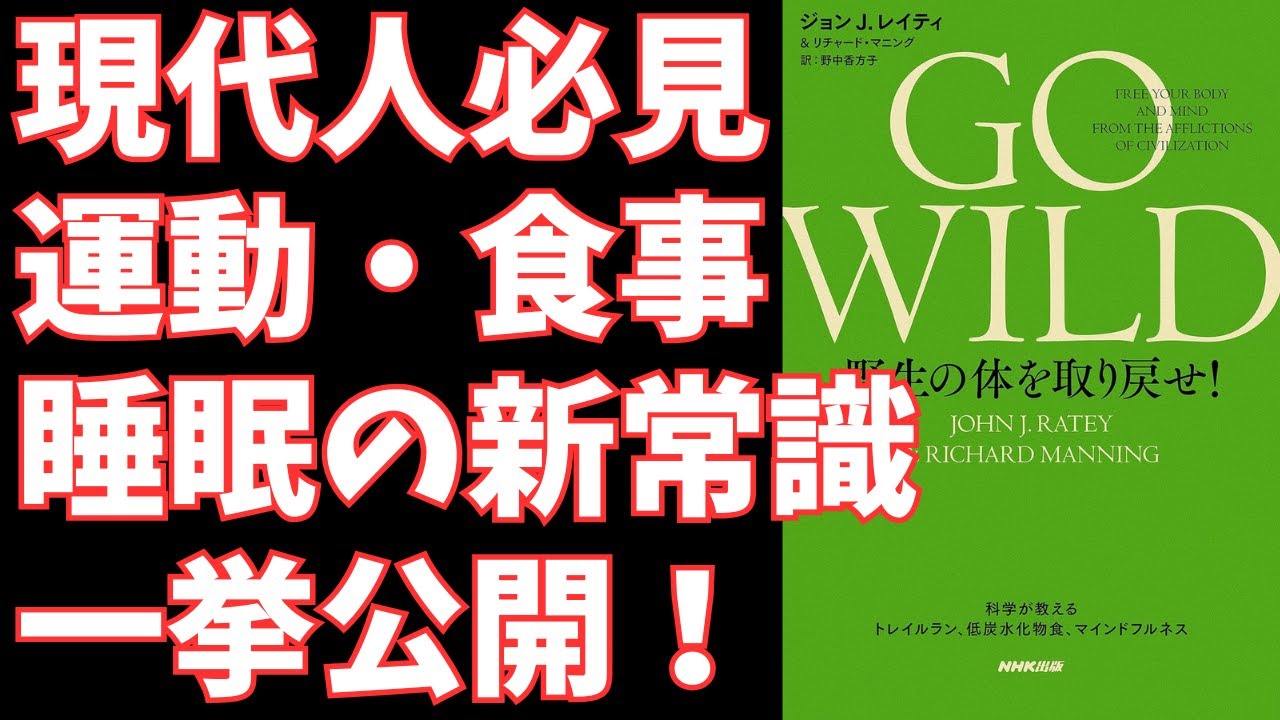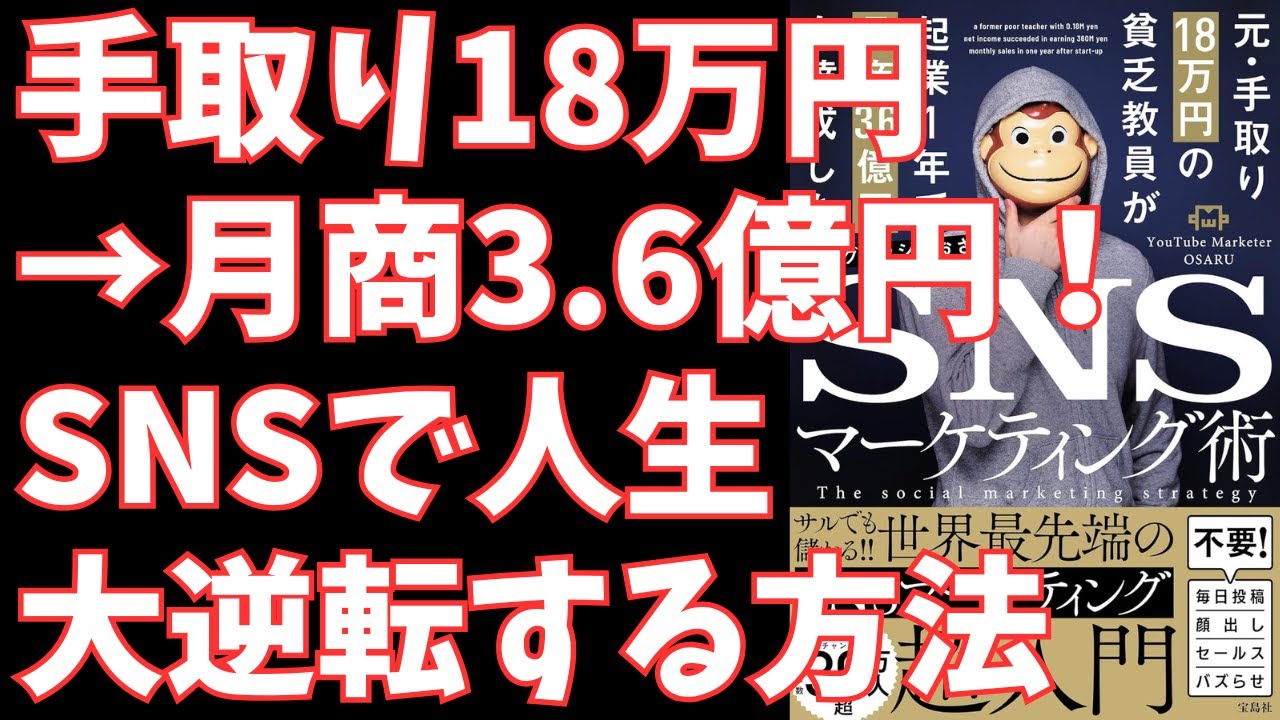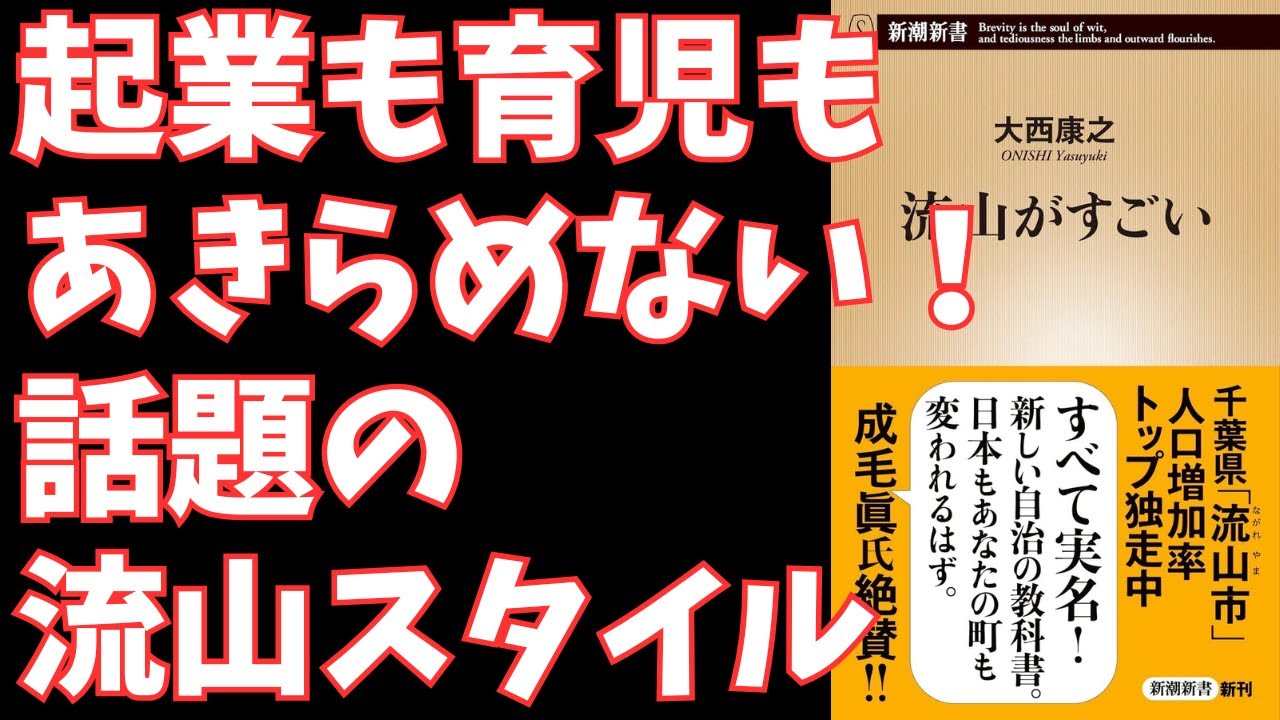『ビジネス書ベストセラーを100冊読んで分かった成功の黄金律』— 100冊読んだ結論は「矛盾」と「アート」だった
「成功したい」と願うビジネスパーソンが手に取るビジネス書。しかし、「Aという本では『努力しろ』と書いてあるのに、Bという本では『努力は無駄』と書いてある…」と感じたことはありませんか?
本書『ビジネス書ベストセラーを100冊読んで分かった成功の黄金律』は、そんなビジネス書の「矛盾」に正面から切り込んだ一冊です。
著者の堀元見氏は、ベストセラーとなったビジネス書100冊を実際に読破し、そこに書かれた教えを比較・検討。その結果見えてきた「驚きの結論」を、ユーモラスかつ痛烈な筆致で解き明かしていきます。
この記事では、本書で紹介される「矛盾だらけの教え」の具体例と、著者が最終的にたどり着いた「成功の黄金律」の意外な正体を、忙しいあなたのために要約してご紹介します。
本書の要点
- ベストセラーとなったビジネス書100冊の教えを比較検討(シントピカル読書)し、その共通点や相違点、矛盾点を探求している。
- 「早起きすべきか」「雑談で何を話すべきか」「怒るべきか否か」など、多くのビジネス書の教えが互いに真っ向から矛盾していることを具体的な書名と共に暴露している。
- 著者はこれらの矛盾をユーモラスに提示し、読者に「絶対的な正解」を押し付けるのではなく、笑い飛ばしながら思考の材料を提供する。
- 最終的に、本書自体がビジネス書への探求プロセスを描いた「現代アート」であると結論づけ、読者自身に「自分の頭で考える」ことを強く促す。
「ビジネス書、全部言うこと違くない?」この疑問がすべてのはじまり
忙しい日々の中、自己成長や成功のヒントを求めてビジネス書を読む人は多いでしょう。しかし、1冊読み終えて「なるほど!」と思っても、次の本ではまったく逆のことが書かれていて混乱する…そんな経験はないでしょうか。
著者は、1冊の本に書かれている情報は「著者の偏見から逃れられない」と指摘します。だからこそ、同じテーマについて書かれた複数の本を読む「シントピカル読書」が重要だと説きます。
そして、この手法を「ビジネス書」に応用したらどうなるか?という探求から本書は生まれました。
「血を吐はくほど努力しろ」と「結果を出すまで1日も休むな」はほとんど同じ教えだが、「ムリは絶対しちゃダメ」や「自分の心をじっくり休めよう」とは矛盾する。
でも、こういうものを全部並べて、整理して、比較してみたら、何か素晴らしい発見にたどり着けるんじゃないだろうか?
こうして始まった著者の「ビジネス書100冊、全部読み比べ」プロジェクト。100冊の教えをすべてスプレッドシートにまとめた結果、見えてきたのは「成功の黄金律」というより、むしろ「壮大な矛盾」の数々でした。
矛盾だらけの「成功法則」博覧会
本書の最大の魅力は、誰もが一度は聞いたことのある「成功法則」が、いかに互いに矛盾しているかを暴き出す点にあります。ここでは、本書で紹介されるいくつかの爆笑必至の矛盾をご紹介します。
例1:「早起き」は本当に得か?
多くのビジネス書が「早起き」を推奨します。「『超早起き』は、30億円の価値を生む」と書く本もあれば、「早朝には永遠が見える」とポエティックに語る本もあります。
朝の習慣として「コーヒーをテイクアウトする」「身だしなみを整える」「豪華な朝食を摂る」などが推奨され、朝はやることが盛りだくさんです。
しかし、この「朝食を摂る」という常識に対し、GACKT氏は『GACKTの勝ち方』で真っ向から異を唱えます。
大半が三食つねに食べている。
無駄に口にモノを放り込んでいる。朝食の時間だから、昼食の時間だからと……家畜のように食べなきゃとやたらと口にモノを詰め込んでいるヤツが世の中に多すぎる。
この強烈な批判に対し、著者はこう結論づけます。
「朝食は摂った方がいい(あなたがGACKTでない場合に限る)」
もはや清々しいほどの投げやり感ですが、確かにGACKT氏のような生き方を目指さない限り、朝食を抜く必要はなさそうです。
例2:混沌(カオス)を極める「雑談」の技術
コミュニケーション能力が重視される現代、「雑談力」をテーマにした本も多数あります。しかし、ここでも教えは混乱を極めます。
- 『超雑談力』:雑談に結論は不要。「食べ物の好き嫌い」のような、意味のない話でOK。
- 『読みたいことを、書けばいい。』:「あたしブロッコリーすっごく嫌い」と語る人間は「つまらない人間」であり、「幼児性が強い」と一刀両断。
- 『超一流の雑談力』:『超雑談力』と酷似したタイトルにもかかわらず、「雑談とは、意味のないムダ話をすることではありません」と真逆の主張。
著者は、ここまで矛盾する『超雑談力』と『超一流の雑談力』の著者がもし出会ったらどうなるか、と思いを馳せます。
幸い(?)、この2冊には「意見が食い違ったら、戦わずに会話を終わらせろ」という唯一の共通点がありました。
きっとこの2人が出会ったら、
「うかつでした!」
「ありがとうございました」
という会話が即座に行われることだろう。
もはやコントです。
例3:「怒り」との向き合い方 — 戦うか? 叫ぶか?
人間関係の悩みもビジネス書の主要テーマです。
「嫌な人とはちゃんと戦う」ことを推奨する『賢く「言い返す」技術』のような本もあれば、「定期的にキレる」と宣言するホリエモンのような人物もいます。
その一方で、「アンガーマネジメント」もブームです。『頭に来てもアホとは戦うな!』では、アホと戦うのは時間とエネルギーの無駄だと説きます。では、怒りはどう発散すればいいのか?
よく使っていたのが、風呂場に防水テレビを持ち込んで大音量で流すという方法だ。そのあと、相手を叩きのめすイメージで思った言葉を徹底的に口に出した。完全にマナー違反の放送禁止用語だらけだが、それだけですっきりした。
なんと、風呂場で放送禁止用語を叫ぶことが推奨されています。
さらに『アンガーマネジメント入門』では、怒りを記録する「アンガーログ」を推奨。著者は「叫んだ放送禁止用語も記録する」必要があると解釈します。
一方で、『反応しない練習』では仏教的に「怒りを作り出さない」ことが正解とされ、「すぐに外に出ること。散歩することです」と、かなりマイルドな対処法が提示されます。
これらの教えを、著者は見事に(?)統合します。
怒りそうになってしまった場合、取るべき行動は、
①まず散歩する。1時間でも2時間でも、歩けるところまで歩いてみる
②それでもダメなら、風呂場に防水テレビを持ち込んで放送禁止用語を叫ぶ
③叫んだ放送禁止用語を記録する以上である。参考にされたい。
もはや読者を笑わせに来ているとしか思えません。
AI時代、ホリエモン、そして「祈る力」
本書は、ビジネス書の「あるある」ネタも容赦なく切り刻みます。
ホリエモン全否定本?
例えば、「多動力」で知られる堀江貴文氏。「99%の会議はいらない」「大事な会議でスマホをいじる勇気をもて」「会社に辞表を出すときだって、2行のLINEで構わない」といった過激な主張は有名です。
しかし、著者は『Think CIVILITY 「礼儀正しさ」こそ最強の生存戦略である』という本が、これらの主張をピンポイントで全否定していることを発見します。
- 「誰かと会って話をする時は、ノートパソコンやスマートフォンは脇へ置こう」
- 「人事に関わる用件などでは、絶対に本人に会って話すようにする必要がある」
著者は、統計データなどを基に礼儀正しさの重要性を説くこの本を「ホリエモンキラー」と呼び、その対立構造を楽しんでいます。
AIに仕事を奪われないために必要な「祈る力」
「AIに仕事を奪われる」というフレーズは、近年のビジネス書の「脅し文句」として定番です。そして、その解決策として「読書をしろ」「地頭力を鍛えろ」といった凡庸な答えが提示されがちです。
しかし、著者は数ある教えの中から、ひときわ異彩を放つ「黄金律」を発見します。
それは、『成功している人は、なぜ神社に行くのか?』に書かれていた、
「人工知能にはできない! 『祈る力』の時代がやってきた」
という衝撃的な一文でした。
人を見守り育てる仕事(保育士など)はAIに代替されにくいとし、その本質は「祈り」であるため、「祈る力」こそがAI時代に最も大事なスキルになる、という(やや強引な)論理展開です。
AIに仕事を奪われると怯える我々に残された最後の希望は、まさかの「神頼み」だったのです。
結論:ビジネス書は「現代アート」である
これほどまでに矛盾し、時には突拍子もない教えが並ぶ中で、私たちは何を信じ、どう行動すればよいのでしょうか。
本書は、最後の教えとして「自分の頭で考える」ことの重要性を説きます。
『Think clearly』という本を引用し、「私たちの意見は洋服と同じようなもので、そのときの流行りのものをただ身にまとっているだけだ」と指摘します。『多動力』が流行れば多動力を自称し、『メモの魔力』が流行ればメモをSNSにアップする…。そんな「流行」に流されるな、と。
そして、著者は本書の驚くべき正体を明かします。
『「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考』という本を引き合いに出し、本書の制作プロセスそのものが「アート」であると宣言するのです。
- 興味のタネ:「ビジネス書って矛盾だらけで虚しくない?」という疑問。
- 探求の根:実際に100冊読み比べ、スプレッドシートにまとめるという探求。
- 表現の花:本書『ビジネス書ベストセラーを100冊読んで分かった成功の黄金律』。
著者は、この本が書店のビジネス書の棚に並び、「結局何をしたらいいのか分からなかった。星ひとつ」といったAmazonレビューがつくことまで含めて、すべてが「現代アート」なのだと言い切ります。
まとめ:成功本に振り回されないために
本書は、あなたに「これをやれば成功する」という明確な「黄金律」を与えてはくれません。
むしろ、無数の「正解」が氾濫する現代社会において、「絶対的な正解などない」という厳しい(しかし笑える)現実を突きつけます。
忙しいビジネスパーソンにとって、本書は「成功の答え」を教えてくれる本ではありません。
しかし、ビジネス書に振り回されず、「自分の頭で考える」ための最高の思考トレーニングであり、最高に知的なエンターテイメントです。
「教えを真に受けて、明日から風呂場で叫んでみる」のもよし。
「ビジネス書なんて無意味だ」とニヒルに笑うのもよし。
「矛盾だらけで面白い」と、本書を探求のプロセスごと楽しむのもよし。
鑑賞方法は、あなた次第です。まずはこの「現代アート」を手に取り、めくるめくビジネス書の世界に飛び込んでみてはいかがでしょうか。