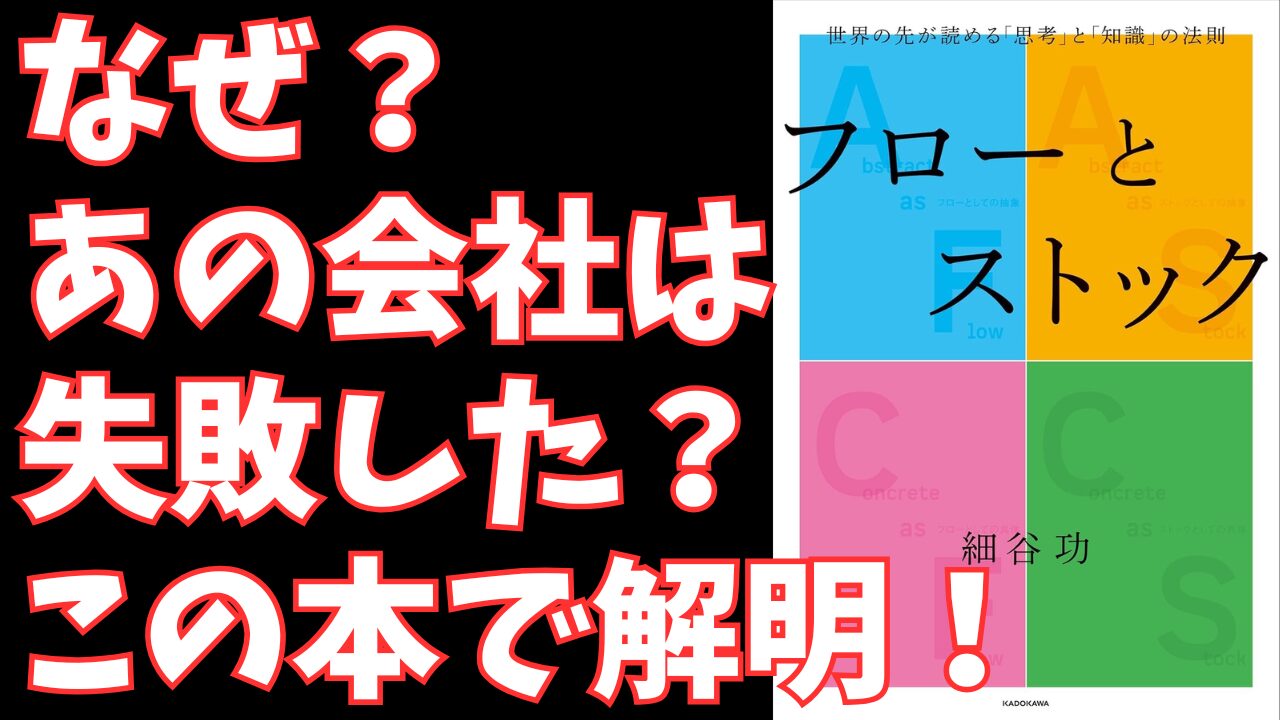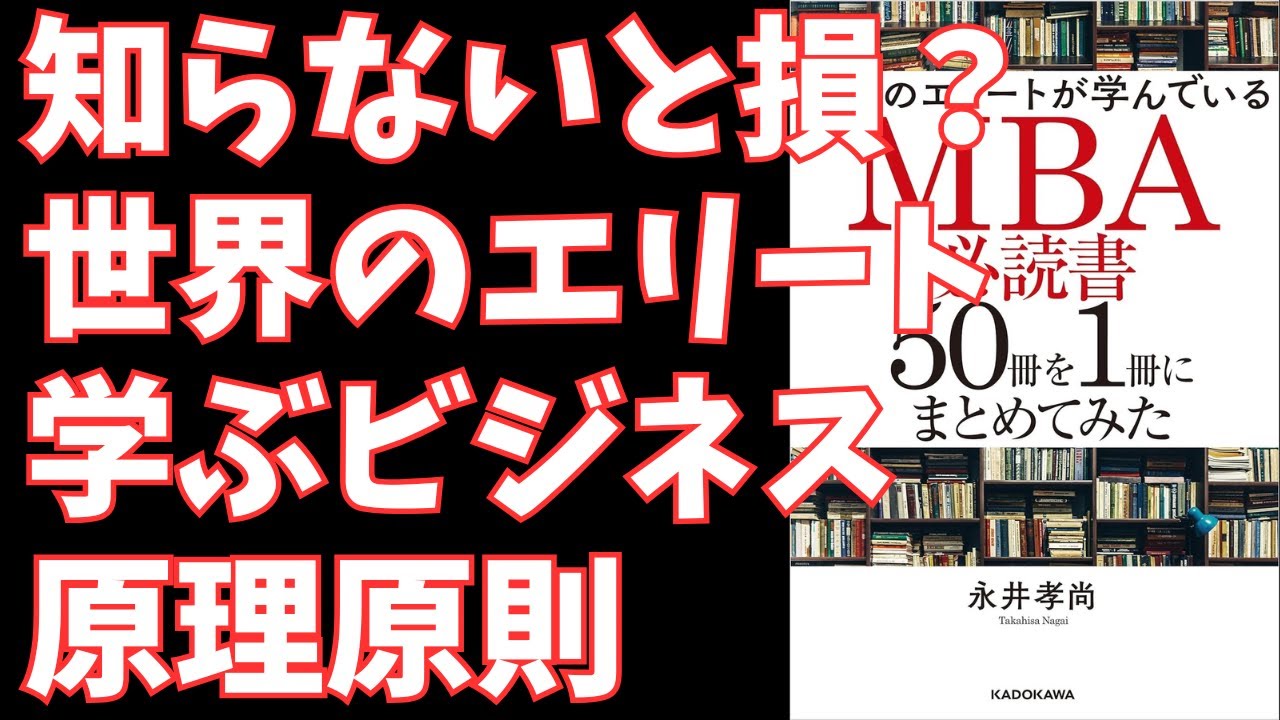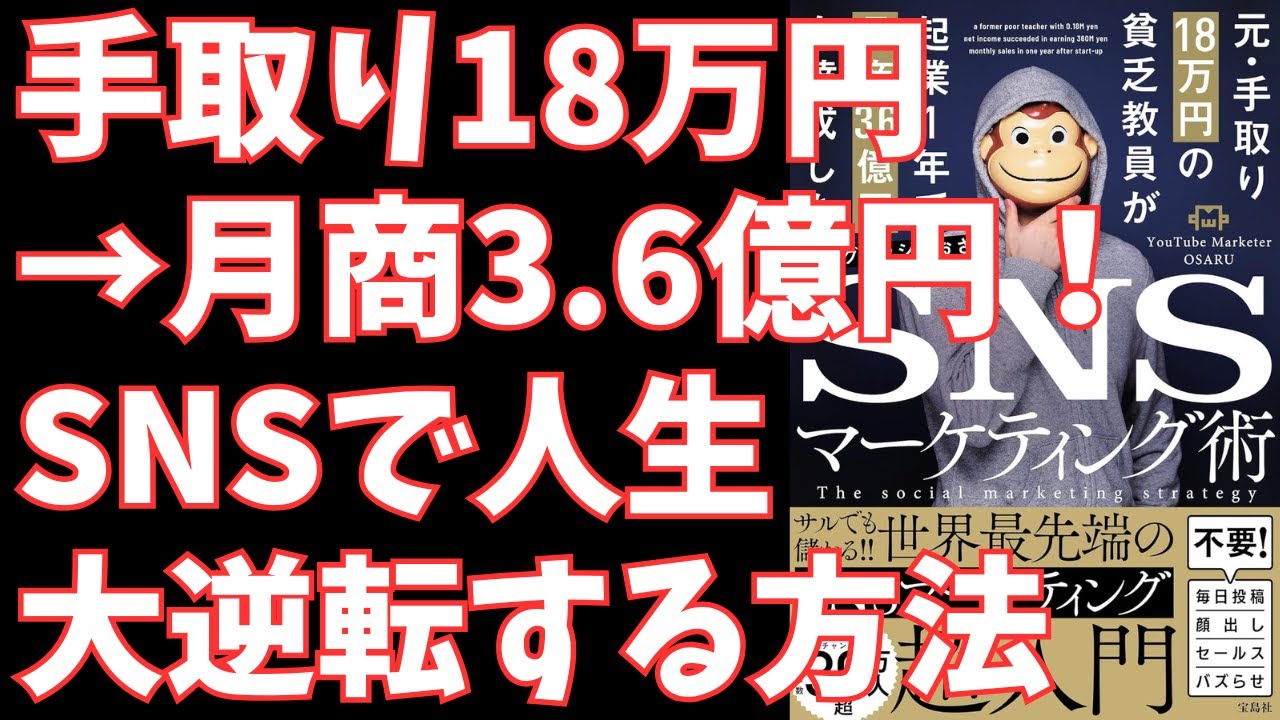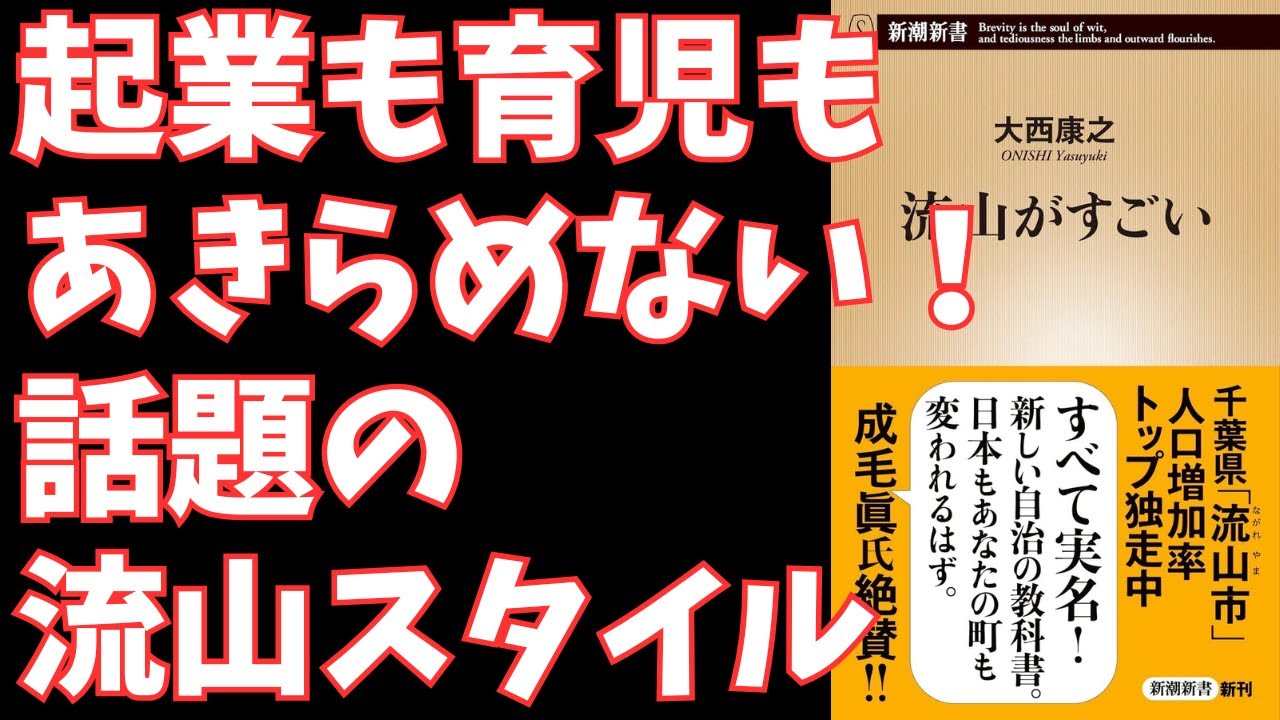山奥ビジネス最前線!“ハイバリュー・ローインパクト”で地域を変える方法
本記事では、藻谷ゆかり著『山奥ビジネス 一流の田舎を創造する』の内容を中心に、山奥で多様なビジネスを展開している事例や、それを支える自治体・地域の取り組みを詳しく紹介する。キーワードとなるのは、ハイバリュー・ローインパクト、SLOC(Small, Local, Open, Connected)シナリオ、そして越境学習である。高速通信網や物流の進化、テレワークの普及が進む今、都会だけでなく山奥でも多様な働き方や事業の可能性が拡がっている。本記事では、熊本県山都町の酒造がIT企業を誘致するまでの経緯や、石川県能登町で世界一に輝いたジェラート職人の挑戦、北海道の山奥で地域を変えるパン工房やアートプロジェクト、さらには世界遺産・石見銀山に育まれた老舗アパレルメーカーなど、各地で生まれ続ける事例を紹介しながら、豊かな自然や土地の文化を守りつつ事業を育てる要点を読み解いていく。
はじめに:山奥ビジネスの時代
山間地域というと、「不便」「過疎」「高齢化」など、ネガティブなイメージが先行しがちだ。しかし近年は情報インフラの整備や高速道路の発達、新型コロナウイルスの流行に伴うテレワークの普及などを背景に、山奥でも多彩なビジネスが育つ環境が次第に整いつつある。
著者が紹介する「山奥ビジネス」は、かつて林業や鉱山などで栄えた場所が衰退後の道を見出すために、外部からの移住者や地域資源を活かした新産業を誘致し、同時に「ハイバリュー・ローインパクト」を実践していく取り組みだ。高品質な財やサービスを提供しながら、自然や土地の文化への負荷を低く抑える。これが山奥でのビジネス存続を左右する大きな鍵となる。
山奥にある企業だからこそ、生み出せる豊かな発想や技術。遠くから訪れてでも体験したいと感じる高付加価値の商品やサービス。そして現地の環境を守り、次世代に継承していく姿勢。これらが組み合わさった事業には、都市部にはないアピールポイントが潜んでいる。
ハイバリュー・ローインパクトとは何か
まず押さえておきたいのが、ハイバリュー・ローインパクトという考え方だ。これはブータンの観光政策に由来し、価値の高いサービスや商品を提供しながら、環境や歴史文化に悪影響を与えないことを目指す理念である。
- ハイバリュー:優れた体験や商品を適正な価格で提供し、質を追求する
- ローインパクト:自然・文化へ配慮し、資源を持続的に利用する
山奥の小さな酒蔵や農園、アパレルブランドなどが、規模は小さくともその土地でしか味わえない希少性やブランド力を生かすことで、高価格帯の商品を展開しながら丁寧なものづくりを維持する。地域の自然や伝統に根ざしたスタイルを崩さず、なおかつ都会の消費者に訴求する付加価値を生み出しているのが大きな特徴である。
SLOCシナリオと山奥ビジネス
もう一つの重要なキーワードが、エツィオ・マンズィーニが提唱するSLOC(Small, Local, Open, Connected)シナリオだ。ここではスローフード運動や地域の食文化保護が例示されているが、山奥ビジネスにも通じる要素が多い。
- Small:小さくスタートし、地域で小回りの利く事業
- Local:地元資源を活かしたローカルな生産・サービス
- Open:外部に対してオープンマインドを保ち、多様な交流を促す
- Connected:ほかの地域とも連携し、互いに学び合う
たとえば山奥で生まれる小さなパン屋やレストランが、SNSやネット通販を活用して世界へ開かれた場になる。あるいはテレワーク対応のシェアオフィスを整備することで、都会からの専門人材を呼び込み、新たな企業誘致を進める。このように地方が持つ個性を失わず、地域内外のネットワークを活かしてビジネスを広げる姿が、SLOCシナリオの理想像となる。
越境学習が生む新しいアイデア
越境学習とは、育った地域を出て学びや仕事の経験を積み、新しい知見を得るプロセスを指す。本書では「山奥ビジネス」の人々が、都会や海外で得た技能や視点をふるさとに持ち帰るケースを多数紹介する。
一方で、都会に暮らしていた人が山奥に移住して学ぶというパターンも含まれる。著者自身も横浜市出身ながら長野県へ移住し、20年以上にわたり地方のビジネス事例を取材・研究してきた。外の文化を吸収し、既存の価値観にとらわれないクリエイティブな発想を生み出すのが越境学習のメリットだ。
熊本県山都町:老舗酒蔵とIT企業の化学反応
最初の事例は、熊本県中央部の山都町だ。ここには1770年創業の老舗・通潤酒造がある。もともと海外輸出や免税店での販売に取り組み、バブル崩壊後も新たな販路を確保してきた蔵元だが、さらに転機となったのが「蛍丸」という日本酒の商品化。
オンラインゲームに登場する伝説の刀「蛍丸」が実は山都町の歴史に由来することから、全国のファンがネット通販で購入するようになった。また熊本地震で酒蔵が甚大な被害を受けた際、全国から支援と注文が殺到。高付加価値化やブランディングの重要性を痛感したことで、通潤酒造は観光酒蔵をさらに進化させ、有料試飲や利き酒セットを揃えた「酒蔵エンターテイメント業」へと生まれ変わった。
さらに、山都町にはIT企業「MARUKU」が本社を構え、光ファイバー回線の整備や空き家改修を進めている。東京から移住した若者たちが熊本各地を拠点に働き、協力企業を続々と誘致しながら、廃校や古民家をシェアオフィス化する活動を活性化。人口1万人台の山間地域であっても、インターネットとオープンな姿勢があれば多様な企業が集まり、新たな雇用が生まれる例として注目されている。
ポイント
- 老舗酒蔵が新たな商品開発やブランドづくりに挑戦
- 全国・海外からの通販や観光客を呼び込む積極性
- IT企業の誘致とインフラ整備で多様な働き方を実現
石川県能登町:ジェラートで世界一
奥能登の高台で「マルガージェラート」を運営する柴野大造は、イタリアで開催されたジェラート大会で総合優勝し、世界チャンピオンとなったことで知られる。人口1万6,000人ほどの能登町から飛び出した若者は、大学在学中に実家の生乳に改めて目を向け、地元でジェラート店を起業。「ふきのとう」「奥能登のミルク」など地域ならではの風味を武器に、驚くほどの人気を集めている。
一方で、ショッピングモールへの出店は一切せず、石川県内の限られた店舗で販売。あくまで本拠地にこだわり、世界チャンピオンの味を「わざわざ食べに来たくなる」ブランドに磨き上げている。地元資源を大切にし、全国的な認知度を獲得する好例だ。
ポイント
- 地元の放牧牛乳から生まれる高品質ジェラート
- 伝統や自然を大切にしながら、イタリア語や製菓技術を独学で習得
- 来店体験を重視し、都会への量産展開を拒むビジネスモデル
北海道岩見沢市美流渡(みると):パンとアートが変える山奥
北海道でも有数の豪雪地帯、岩見沢市の山奥にある美流渡地区は、かつて炭鉱で栄えた人口400人弱の小さな集落だ。そこで「ミルトコッペ」というパン工房を営む中川夫妻は、築60年以上の古民家をDIYで改修し、長時間発酵と薪窯で焼いた素朴なコッペパンを朝1回だけ販売。山奥にもかかわらず行列が絶えない人気店となっている。
また、美術出版社で働いていた來嶋路子や画家のMAYA MAXXなど、芸術に携わる移住者も増え、廃校の美流渡中学校をアートの拠点に再生するプロジェクトを進行。廃校の窓板を巨大キャンバスに見立てて絵を描くなど、土地の人々とアーティストが一体になって山奥を盛り上げる。
ポイント
- 不便さを「冒険のような生活」と捉え、逆手にとって事業を磨く
- アーティストの移住によるユニークなアートプロジェクト
- 既存の資源(空き家、廃校)をコミュニティの核へと変える柔軟な発想
島根県大田市大森町:石見銀山の文化を守り発信する
世界遺産・石見銀山にある大森町は、かつて人口20万人ともいわれた隆盛を誇ったが、今は人口400人弱にまで減少。しかしここには全国に30店舗以上を展開する「石見銀山 群言堂(ぐんげんどう)」が本社を置き、大人向けアパレルや生活雑貨・食品などの製造小売業を展開している。
創業者の松場大吉・登美夫妻は雑貨ブランドから一転、「群言堂」として衣食住を総合的に提案するビジネスへシフトし、全国のデパートに直営店をオープン。古民家を宿泊施設やパン工房、アトリエに再生し、多様な人材を呼び寄せることで大森町には移住者が増え、保育園や小学校の維持にもつながっている。
ポイント
- 「ハイバリュー・ローインパクト」を地で行く大量生産に頼らない製造小売業
- 古民家の再生や独自の世界観づくりで観光客や移住者を誘致
- 地域全体が一つの「暮らしの美」を伝える舞台に
魅力的な地域がビジネスを呼び込む
山奥ビジネスが根付くには、地域そのものの魅力を高める取り組みが大きく関わってくる。例えば新潟県十日町市の「大地の芸術祭」は、広大な里山を「屋外美術館」に見立て、3年に一度世界中のアーティストを招き、廃校や棚田・空き家などを舞台に多彩な作品を創出。過疎化に苦しむ農村を、アートによる国際的な観光地へと転換した。
同様に北海道東川町は、水道がない代わりに大雪山系の伏流水を利用できる豊かな環境を活かし、「写真の町」宣言や高校生写真甲子園、町立日本語学校などを設立。人々が面白がって訪れたくなる“多様性”を築き上げた。人口8,500人にもかかわらず移住者が増え続け、町が活性化している。
そして山梨県小菅村では「源流の村」をコンセプトに、子育て移住支援やタイニーハウスプロジェクトなどを進め、都心からわずか2時間弱で山深い自然を体感できる観光地として、同時に「村全体がホテルになる」取り組みを拡大。都市圏からの流入を図りながら、人口を数値目標にしない独自路線を歩んでいる。
これらの自治体に共通するのが、明確なコンセプトと「外から来る人を歓迎し、彼らが事業を展開できる土台を整備する」という姿勢だ。企業が移転する際に必要な物件や補助金、行政手続きなどをスムーズに行えるよう、自治体や地元の人々が積極的に協力する。こうして初めて「山奥ビジネス」として根付き、継続的な発展が見込める。
地方経済活性化と観光業の新しいかたち
本書の終盤では、地方経済を活性化するために観光産業の重要性が強調される。山奥の観光は大型リゾート開発ではなく、自然や歴史文化を大切にする「ハイバリュー・ローインパクト」路線が有効とされる。
- 石見銀山のように、既存の歴史・景観を守りながらゲストを呼び込む
- 山奥の廃校や古民家をリノベーションし、地元住民と観光客をつなぐスペースを作る
- イベントや芸術祭などで、地元のお年寄りや若者が協力し、外から来た人をもてなす
こうした事例を成功させるには、地域のリーダーたちが「自分たちの土地の価値を再発見し、外からの目線を取り入れる」オープンな姿勢が不可欠だ。「地元を見直すきっかけ」としても観光振興は機能し、結果的に農業や工芸など地場産業の見直しにもつながる。
若い世代・女性の移住を促進するには
著者は女性や若い世代の力なくしては、地方の再生は難しいと断言する。実際、地方から流出する若年女性の多さがその地域の将来を左右するという統計結果もある。
では、どのように若い世代や女性を呼び込むか。熊本県山都町や石見銀山、大田市大森町の事例に見られるように、外から来た人のアイデアや働き方を受け入れる柔軟さが大きい。単に農業や観光の求人を出すだけでなく、テレワークができる拠点整備や複業OKの環境づくり、起業支援・子育て支援などを組み合わせることがカギとなる。
地域の議会や行政にも若い女性が参画しやすい風通しのよさや、越境学習を行った人材を温かく迎え入れるカルチャーがあるかどうかが問われる。女性が自由に挑戦できる場所は若い男性にとっても魅力的であり、総合的に人口流入の底上げに寄与する。
おわりに:山奥ビジネスが導く未来
山奥ビジネスとは、単に「観光客を呼ぶ」「都会の企業を誘致する」という表面的な施策ではない。地域に暮らす人が自らの手でビジネスを創造し、それを目当てに外からの人々が集い、文化が交わりあってさらなる発展を生むプロセスだ。
- ハイバリュー・ローインパクト:質の高いサービスをつくり、地域環境を壊さず維持する
- SLOCシナリオ:小さなプロジェクトがオープンかつ多方面と連携し、外へ広がる
- 越境学習:都会から地方へ、地方から海外へと飛び出して得た経験を、再び地域に持ち帰る
こうした循環によって、人口が減り続ける日本の山間地域にも新しい風が吹き込み、「ここでしかできない」クリエイティブな事業が花開く。決して大規模ではなくとも、サステナブルに発展していく「山奥ビジネス」の数々は、疲弊した地方に大きな可能性を与えているといえよう。
今、山奥は都会とは異なる価値観を生み出す最前線になりつつある。魅力的な自然や歴史を継承し、独自のビジネスを形にする人々の奮闘が、新しい日本の地方経済モデルを示しているのだ。あなたの街にも、そんな未来を呼び寄せるヒントがきっと潜んでいるはずである。