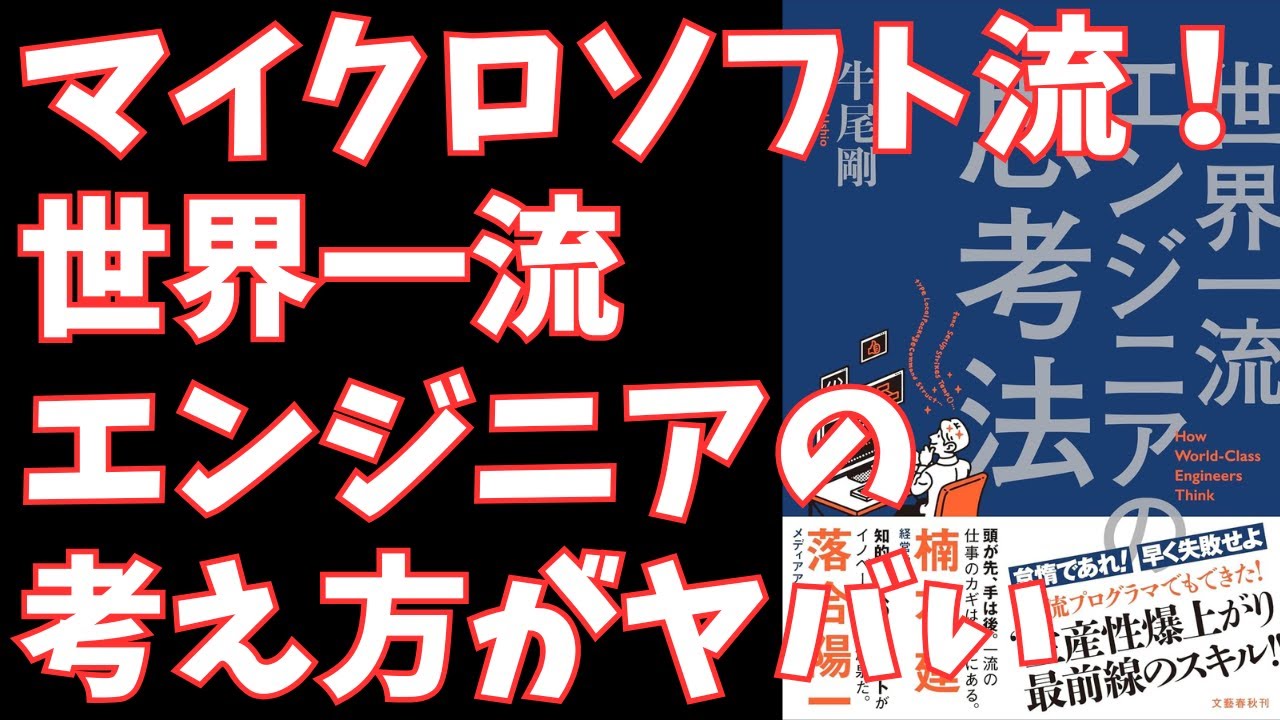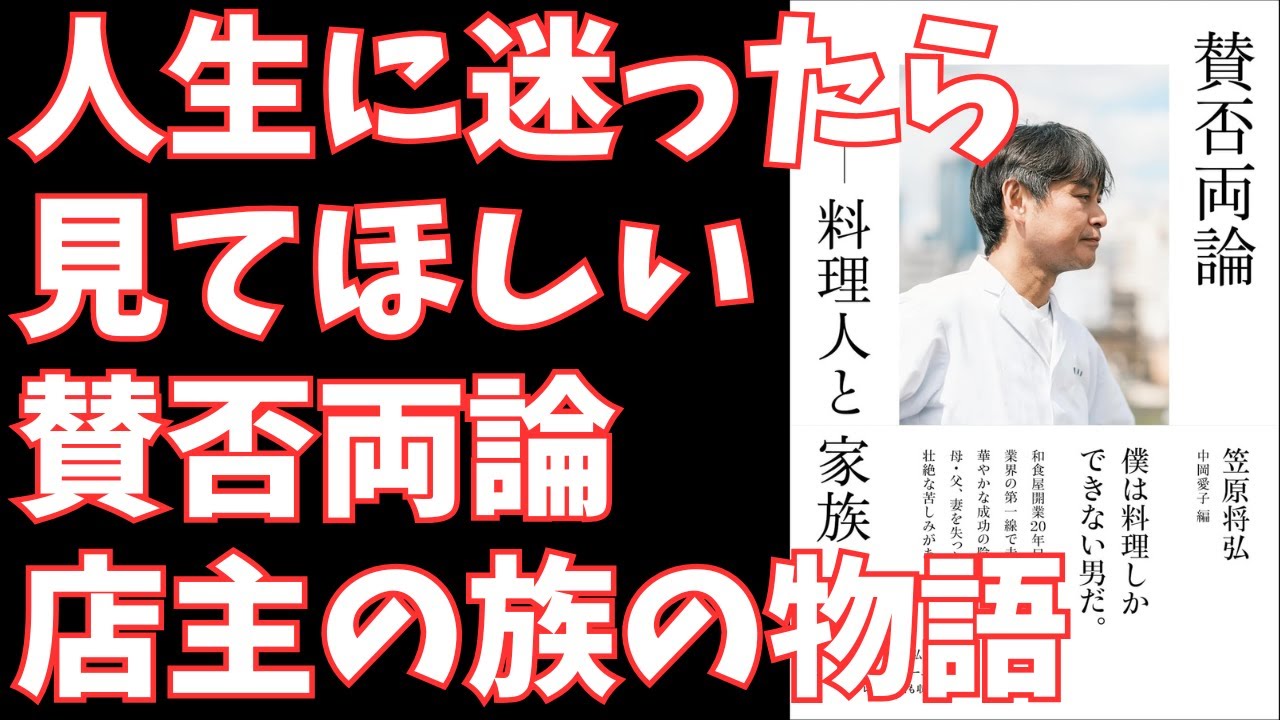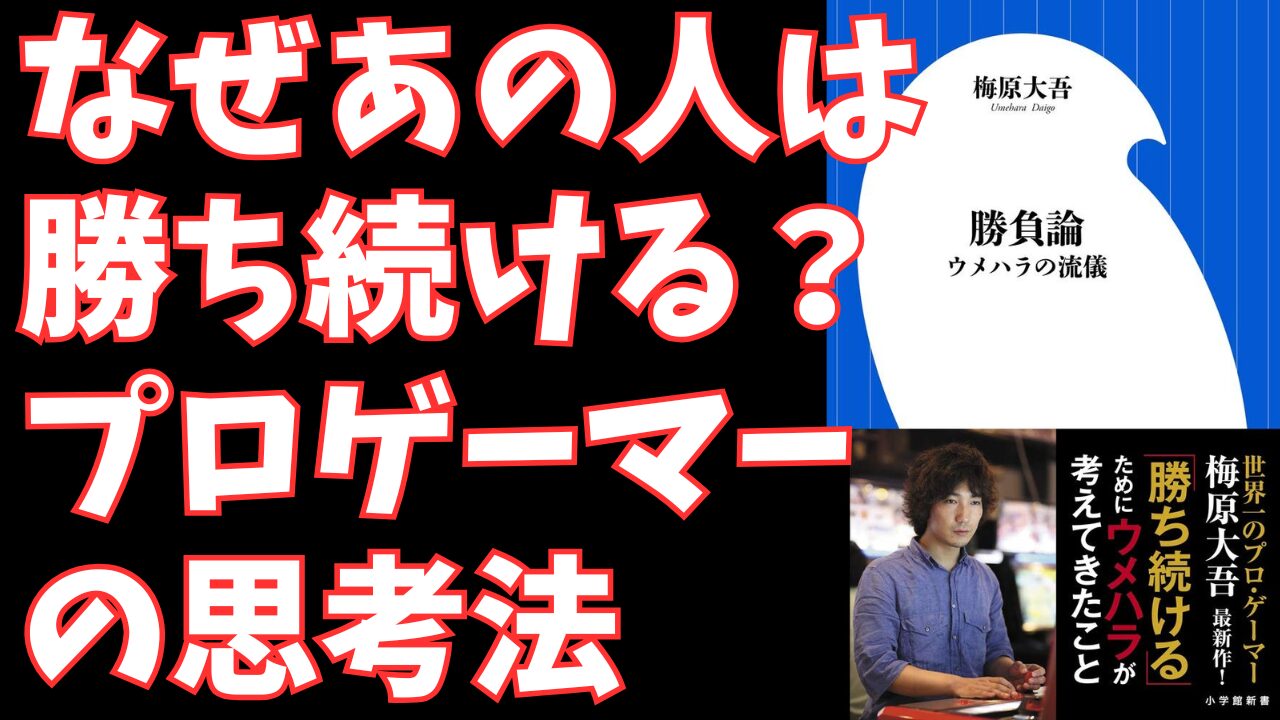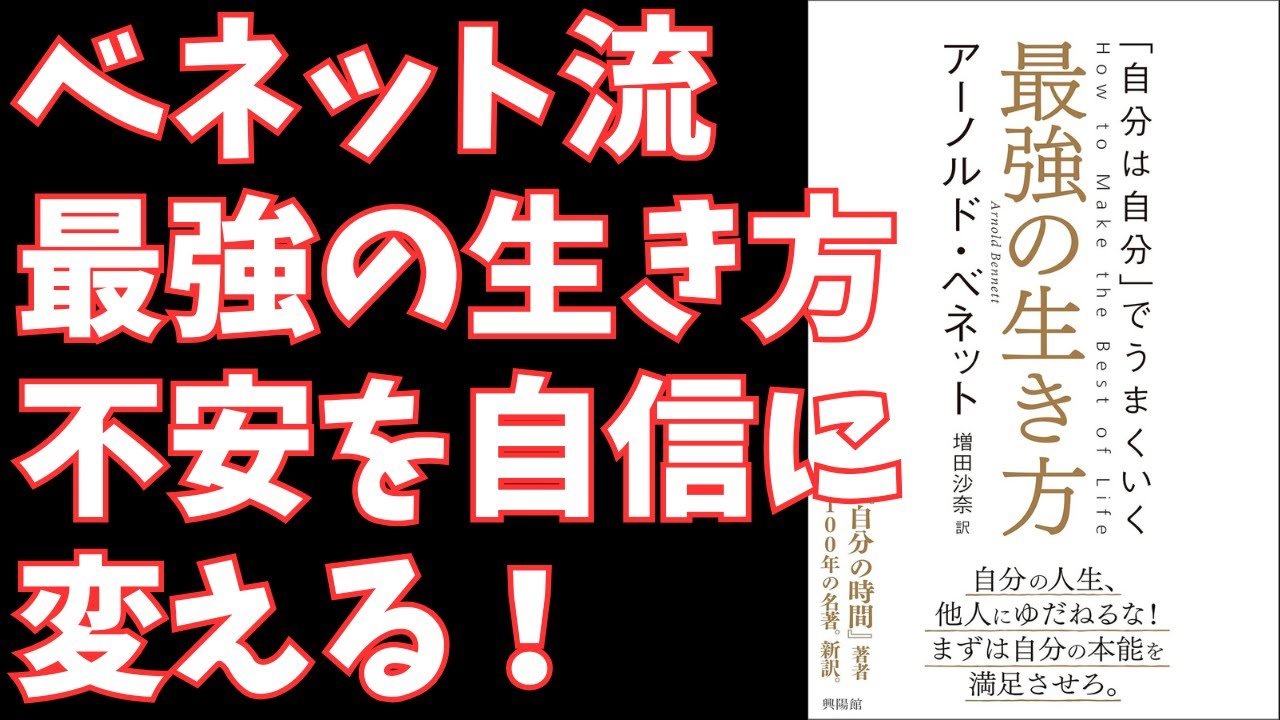山崎元氏が癌になって気づいた、お金と人生の本質 – 終活と意思決定
本書は、経済評論家である山崎元氏が2022年に食道癌(ステージⅢ)と診断された経験をもとに、お金、仕事、人間関係、そして人生そのものについて深く考察した記録です。癌という予期せぬ出来事に直面し、「不確実性下の意思決定」という投資と共通する課題に向き合った著者が、がん保険の是非、医療情報の取捨選択、身辺整理、合理的な終活、そして「お金よりも大切なもの」に気づくプロセスを、自身の体験や具体的な事例を交えながら率直に語ります。多忙な日々を送るビジネスパーソンにとって、自身の価値観や優先順位を見つめ直し、より良く生きるためのヒントが詰まった一冊です。
本書の要点
- 癌と投資は「不確実性下の意思決定」で似ている:限られた情報と時間の中で最善の選択をする必要があり、情報収集と取捨選択、そして割り切りが重要となる。
- がん保険は基本的に不要:日本の公的医療保険制度は手厚く、高額療養費制度などを活用すれば、標準治療の自己負担額は貯蓄で十分対応可能。治療費よりも仕事ができない期間の「機会費用」の方が大きなコストになり得る。
- 癌を機に「捨てる」ことで本質が見える:物(衣類、書籍、ガジェット)だけでなく、不要なこだわり(ヘアスタイルなど)、仕事、人間関係を見直し、捨てることで、時間、お金、精神的な余裕が生まれ、本当に大切なものに集中できる。
- 終活はシンプルかつ合理的に:老後の住まいは利便性の高い場所に縮小し、介護はプロ(施設)に任せることを検討。相続は早めに明確にし、お墓や葬儀も形式にとらわれずシンプルに行うことで、遺族の負担を減らせる。
- お金は「使い方」が重要、幸福は「承認」から:お金は貯めること以上に、「経験」に投資するなど、幸福度を高める使い方を意識すべき。そして、人間の幸福感の根源は他者からの「承認」(人気≒モテ)にあり、お金や自由と同様に重要な要素である。
はじめに:経済評論家、癌になる
本書の著者、山崎元氏は、経済評論家として資産運用を中心に多方面で活躍されてきました。歯に衣着せぬ物言いと、本質を突く鋭い分析で知られ、多くのビジネスパーソンから支持を集めています。
そんな山崎氏が、2022年の夏、食道癌(ステージⅢ)と診断されました。これまで大きな病気の経験がなかった著者にとって、癌の罹患は人生の大きな転機となります。本書は、特定の治療法を推奨するものでも、医療情報の専門的な解説書でもありません。著者が癌という現実を前に、 何を考え、どのように情報を集め、どんな意思決定を下してきたのか 、そのプロセスを克明に記録したものです。
そこには、お金、仕事、人間関係、そして人生そのものに対する、深く、そして時にユーモラスな洞察が散りばめられています。多忙な日々を送るビジネスパーソンにとって、自身の生き方や価値観を見つめ直す、多くのヒントを与えてくれるでしょう。
第1章 癌患者と投資初心者は似ている? – 不確実性下の意思決定
山崎氏は、癌患者が直面する状況は、 投資初心者が直面する問題とよく似ている と指摘します。その共通点は「 不確実性下の意思決定 」を迫られる点にあります。
癌発覚と情報収集のジレンマ
2022年6月頃からの喉の不調をきっかけに、いくつかの病院を経て、8月にステージⅢの食道癌と診断された山崎氏。告知を受けた際、大きな精神的ショックはなく、「これから、どうするかに集中するしかない」と即座に考えたと言います。これは、氏が職業柄、「サンクコスト」(埋没費用)を無視し、未来に変えられることに意識を集中する習慣があったためです。
しかし、治療方針を決めるにあたり、大きな壁にぶつかります。それは、 溢れかえる癌情報 です。ネット、書籍、そして周囲からの善意によるアドバイス。しかし、玉石混交の情報の中から、自分にとって本当に有効な情報を見極め、限られた時間の中で判断を下すことは容易ではありません。
これは、投資を始めようとする初心者が、どの情報を信じ、どの金融商品を選べば良いのか迷う状況と酷似しています。情報が多すぎると、かえって判断を誤らせたり、時間を浪費したりする可能性があるのです。
情報の取捨選択と信頼できる相談相手
山崎氏は、情報の「量」よりも「質」と「取捨選択」が重要だと考え、以下の行動をとりました。
- 情報源の限定: 国立がん研究センターのウェブサイトや、各学会が発行する「診療ガイドライン」など、信頼できる情報源に絞る。
- 相談相手の厳選: 自身と直接利害関係がなく、信頼できる医療専門家(医師、学者など)数人にアドバイスを求める。
- 不要な情報の遮断: 個別性の高い体験談や、根拠の薄い民間療法などの情報は、判断を迷わせる可能性があるため、意識的に遠ざける。治療方針が固まるまで、自身の癌について公表を控える。
特に、「診療ガイドライン」を読み込み、標準治療の内容や予後(自身の5年生存率を「50%弱」と見積もる)を把握したことは、医師とのコミュニケーションを円滑にし、冷静な意思決定に繋がったと述べています。
意思決定のプロセス:標準治療の選択
海外の治療法や、保険適用外の治療法も存在する中で、山崎氏は自身の情報理解力や時間的制約を考慮し、 「標準的な治療でベストだと思えるものでいい」 と割り切ることにしました。
治療方針は、抗がん剤治療後に手術か放射線治療かを選択するものでした。5年生存率は手術の方がやや高いものの、声への影響(反回神経麻痺のリスク)も考慮する必要がありました。最終的に、信頼できる放射線科医の意見も参考に、手術を選択します。
このプロセスは、投資において、インデックスファンドのような「標準的」で再現性の高い手法を選択し、個別の情報に振り回されずに長期的な視点で判断することの重要性と通じるところがあります。
山崎氏は、「 上機嫌な癌患者でありたい 」と語ります。病状に一喜一憂するのではなく、与えられた条件の中で最善を尽くし、機嫌良く過ごすこと。これは、不確実な市場に向き合う投資家にも求められる姿勢かもしれません。
第2章 がん保険はやっぱり要らなかった – コストと合理的な判断
山崎氏は以前から「がん保険は不要」と主張してきましたが、自身が癌になってみて、その考えはより強固なものになりました。
実際にかかった治療費は?
山崎氏が食道癌の診断から手術後、治療が一段落するまで(約3ヶ月間、入院約40日)に支払った医療費は約235万円でした。
しかし、その内訳を見ると、 約160万円は個室代 (1日4万円)であり、これは著者が仕事などの都合で選択した「贅沢」であって、治療上必須ではありませんでした。
残りの約75万円が、高額療養費制度を適用した上での自己負担額です。もし国民健康保険加入者であれば、この金額が実質的な負担となります。
さらに、山崎氏が加入していた東京証券業健康保険組合には付加給付制度があり、最終的に 著者が負担した「どうしても必要だった医療費」は約14万円 に過ぎませんでした。
多くの健康保険組合には同様の付加給付制度があり、自己負担額の上限が設けられています。サラリーマンの方は、自身の加入する健保組合の制度を確認しておくことが推奨されます。
がん保険不要論の根拠
上記の経験から、山崎氏は次のように結論づけています。
- 公的保険で十分:日本の健康保険制度は手厚く、高額療養費制度や健保組合の付加給付により、標準治療を受ける限り、自己負担額は貯蓄で十分賄える範囲(数十万円~多くても200~300万円程度)に収まる可能性が高い。
- 保険は「損な賭け」:保険会社は営利企業であり、保険商品は加入者全体で見れば損するように設計されている。確率的に損であり、かつ貯蓄で対応可能なリスクに対して、保険料を払い続けるのは合理的ではない。
- 保険加入は「必要性」で判断:保険は「不安だから」入るのではなく、「万一の際に経済的に破綻するリスクがあり、他の手段で備えられないか」という 必要性 で判断すべき。がん保険はこの条件を満たさない。
- 最大のコストは「機会費用」:治療のために働けない期間の収入減(逸失利益)こそが、実は最大のコストとなり得る。山崎氏の場合、約3ヶ月間の機会費用を数百万円と試算しています。
もちろん、これは山崎氏のケースであり、個々の状況によって判断は異なります。しかし、「不安を煽るマーケティング」に流されず、冷静にコストと必要性を分析することの重要性を示唆しています。
加入していい保険とは?
山崎氏は、基本的に必要な保険は限定的であるとし、以下の条件を挙げています。
- 滅多に起こらない
- 起こった場合の損失が破滅的に大きい
- 他に代わる手段がない
具体的には、自動車の対人・対物賠償に備える 自動車保険(任意保険) や、 火災保険 などが該当します。生命保険が必要なケースは、扶養家族がいる稼ぎ手の 死亡保障(掛け捨ての定期保険) や 所得保障保険 くらいだとしています。
保険を検討する際は、FP(ファイナンシャル・プランナー)に相談するのも手ですが、 保険商品を販売しない中立的なFP を選び、セカンドオピニオンを取ることを勧めています。そして、「 人間には相談しても、人間からは(直接)買わない 」ことが鉄則だとしています。
第3章 癌になって分かった、どうでもいいことと大切なこと
癌という病気は、山崎氏に「持ち時間」と「体力」の制約を突きつけました。それは同時に、これまで抱え込んできた物、仕事、人間関係などの中から、 「実はどうでもいいこと」 を見極め、手放す機会にもなりました。
こだわりは案外どうでもいい:ヘアスタイルの呪縛
抗がん剤治療による脱毛は、多くの癌患者が経験することです。山崎氏も脱毛を経験し、当初はウィッグやニット帽で隠すことを考えました。しかし、最終的にバリカンで坊主頭にしたところ、意外にも気分がすっきりし、やがて自分の姿に見慣れていきました。
そして気づいたのは、 「他人は自分の髪型など気にしていない」 ということ。これまで時間とお金をかけてヘアサロンに通い、似合わない髪型に悩んでいたのは、業界のマーケティングと自身の過剰な自意識による「呪縛」だったのではないか、と。
坊主頭でいることのメリット(時間とお金の節約、手入れの楽さ)を実感し、 「実はどうでもいいこと」へのこだわりを捨てることの解放感と経済効果 を痛感したと言います。これは、ファッションや人付き合いなど、他の様々な場面にも当てはまるでしょう。
物欲との決別と身辺整理
山崎氏は、自身を「物欲が旺盛で浪費家」だったと振り返ります。特にガジェット類、時計、カメラ、鞄などを多く所有していました。
しかし、癌になり、持ち時間と体力の制約を意識したことで、本格的な身辺整理に着手します。
- 衣類: 体重減少もあり、スーツは夏冬1着ずつを残して処分。似合わない服、不要な服を大幅に減らす。
- 書籍: 数千冊をPDF化していたが、読み返す時間は限られていると悟り、電子書籍で入手可能なものや再入手可能なものは処分。思い入れのある専門書や書き込みのある本だけを残す。
- ガジェット・カメラ: パソコンやタブレットの多くをデータ消去業者に依頼して処分。カメラも大半を譲渡し、必要最低限(iPhoneとMacBook Air)に絞る。
物を手放すことで、 「肩の荷が下りたように気分が楽になった」 と語ります。所有することのコスト(物理的スペース、管理の手間、精神的負担)から解放されたのです。
仕事と時間の使い方:優先順位の変化
癌の再発により、「持ち時間」の想定が当初の「数年」から「半年~1年」、さらに「数ヶ月」へと短縮されていく中で、仕事に対する考え方も変化します。
- 効率より「やりたいこと」: 体力的な制約から、移動の多い講演などの仕事は断るように。代わりに、本当にやりたい仕事、面白いと思える仕事に集中する。
- アウトプットの再構築: これまでの知識や経験を体系的にまとめた本を出版するなど、「残す」ことを意識した仕事に取り組む。
- 「今」を大切にする: 先の見通しが立たない状況だからこそ、締め切りに追われながらも連載を続けるなど、日々の仕事があること自体が張り合いになっている。
限られた時間の中で何をすべきか、という問いは、私たちに 本質的な価値基準 を問いかけます。
人間関係の最適化:「会いたい人」にだけ会う
時間と体力が限られてくると、人間関係も「選択と集中」が必要になります。山崎氏は、 「自分から頼んで時間を貰いたいと思う相手にだけ会う」 ことを基本方針としました。
一方で、以下のような相手との時間は、癌でなくても避けるべき「時間の無駄」だと指摘します。
- 自分の話を聞いてほしいだけの人
- 「詳しい話は会ってから」と、事前に用件を伝えない人
- 目的もなく「お時間を下さい」とアポを取ろうとする人
- 昔話ばかりする人(未来志向でない)
癌患者に対しては、周囲は善意から様々な情報提供やアドバイスをしがちですが、それがかえって負担になることもあります。山崎氏は、 「癌患者には親切にしないで」 と半ば本音で語り、 「聞きたいことがあったら何でも聞いてね」と声をかけて放っておいてくれる人 が一番ありがたい、としています。
オンラインミーティングの効率性を再認識しつつも、気楽に話せる相手とのコミュニケーションの難しさも吐露しており、人間関係の最適化の複雑さも示唆しています。
第4章 山崎式・終活のセオリー6箇条 – 合理的に、シンプルに
人生の手仕舞い、すなわち「終活」は、誰にとっても避けられないテーマですが、考えるのが億劫だったり、いざという時に判断力が低下していたりして、難しい問題です。山崎氏は、自身の経験や実家の事例をもとに、 シンプルで合理的な終活 の考え方を提示しています。
山崎家の終活セオリー
- なるべく長く働く: 経済的な安定だけでなく、社会との繋がりや生きがいのためにも重要(例: 75歳くらいまで)。
- 住居は縮小し、モノを減らしてシンプルに暮らす: 子育て後の広い家は負担。適切なサイズに住み替え、持ち物も厳選する。
- 便利な場所に暮らす: 交通の便が良い場所は、外出や人との交流を促し、老後の活動性を維持する上で重要。車の運転卒業も見据える。
- 介護が必要になったら、施設へ: 自宅介護は家族の負担が大きい。プロの手に委ねる方が効率的であり、子供の活動を制約しない。親の介護方針は子供が決める(山崎家のルール)。
- 相続は、本人のアタマがしっかりしているうちに、明確に決める: 財産の所在、額、分け方を明確にし、記録や遺言に残す。「争族」を避ける。 親の金融資産状況を把握し、不適切な取引から守る ことも重要(「親のお金を守れ!」)。
- お墓・お寺と縁を切って、弔いはシンプルに: 宗教や形式にとらわれず、故人とゆっくり別れを惜しむ時間を大切にする。
実践例:山崎家の相続と弔い
山崎氏は、父親が亡くなった際の相続で、母親の資産を守るために以下の対策を講じました。
- 金融機関との取引整理: 対面証券会社に対し、母親への運用商品の勧誘停止を要請。
- 「2世代運用」: 母親自身の意向だけでなく、相続人(子供たち)のリスク許容度も考慮し、低コストのインデックスファンド(ETF)や個人向け国債で運用。
- 認知症への備え: 母親と妹の間で「財産管理等委任契約」と「任意後見契約」を締結。
また、弔いに関しては、父親が亡くなる以前から、 お墓を撤去し(墓じまい)、遺骨を散骨 。お寺との関係も解消していました(檀家離れ)。父親が亡くなった際も、 通夜や告別式は行わず、家族だけで自宅でゆっくりと別れの時間を過ごし 、火葬のみを行いました。費用は約37万円だったとのことです。
この「 墓なし・坊主なし 」のシンプルな弔いは、費用面だけでなく、 遺族が心身ともに消耗せず、故人との別れに集中できる 点で大きなメリットがあったと述べています。
これらの方法はあくまで一例ですが、従来の慣習にとらわれず、自分たち家族にとって何が最も合理的で、心を満たす形なのかを考えることの重要性を示唆しています。
第5章 お金より大事なものにどうやって気づくか
山崎氏は、お金に関する情報発信を生業としながらも、「お金に興味がない」と公言します。お金はあくまでも目的を達成するための「手段」であり、それに感情を振り回されるべきではない、というのが一貫した主張です。
お金は「増やし方」より「使い方」
『DIE WITH ZERO』という書籍に触発され、山崎氏は お金の「使い方」の重要性 を再認識します。特に、以下の点が重要だと指摘します。
- 経験に投資する: モノ消費よりも、良い思い出として長く価値を発揮する「経験」にお金を使う。
- 適切な時期に使う: 人間の「楽しむ能力」は年齢と共に変化する。若い頃にしかできない経験にお金を惜しまない。
- 貯蓄至上主義への疑問: 若い頃に極端な節約をして早期リタイア(FIRE)を目指す生き方は、人的資本への投資不足や、貴重な経験の機会損失に繋がりかねない(「守銭奴型FIRE」への警鐘)。
ただし、将来への備えが全く不要というわけではありません。ある程度の金融資産は、保険への過度な依存を避けたり、転職などの自由度を高めたりする上で有効です。 「稼げる人材」としてのスキルや評判 を磨くことと、 「ある程度の金融的備え」 をバランス良く持つことが重要だとしています。
幸福を決める要素:「お金」「自由」「人気(≒モテ)」
お金は、行動の選択肢を増やす「自由」をもたらします。しかし、それだけでは幸福は完成しません。山崎氏は、人間の幸福にとって 「他人からの承認」 、すなわち 「人気(≒モテ)」 が決定的に重要だと論じます。
- お金と自由: お金で自由は買えるが、限界はある。
- お金と人気: お金で人気をある程度買うことはできるが、自由ほど直接的ではない。むしろ人気がある方がお金を稼ぎやすい側面もある。
- 自由と人気: この二つが幸福の主要な構成要素。
結局、 「幸せになるには、他人に好かれるような人(人気者≒モテる人)になるのが近道だ」 という、ある意味で平凡な結論に至ります。
お金の呪縛から逃れるスイッチ:「怒り」
では、「お金よりも大事なもの」に、私たちはどうすれば気づけるのでしょうか? お金は比較尺度として強力であり、「貨幣の物神性」とも言える特別な力を持つため、一度お金の損得勘定にとらわれると、なかなか抜け出せません。
山崎氏は、その 呪縛を打ち破る唯一のスイッチが「怒り」 である、という驚くべき結論を提示します。
「こんなことが許されてたまるか」「俺のことを舐めるなよ」といった、損得勘定を超えた強い感情(怒り)こそが、私たちに お金よりも優先すべき価値(正義、プライド、信用など) に目を向けさせるきっかけになる、と。
山崎氏自身、過去に銀行員時代の不正を内部告発した際、その根底にあったのは損得を超えたファンドマネージャーとしての「プライド」と「怒り」だったと述懐します。
ただし、 「怒り」はあくまでも「きっかけ」 であり、そのままにしておくのは危険です。怒りの感情は判断を誤らせやすいため、 「信用」「共感」「プライド」といった、より安定的で建設的な理由へと昇華させる 必要があります。
必要な時には正しく怒る感受性を持ちつつ、その怒りをより高次の価値へと転換していくこと。それが、お金の呪縛から逃れ、本当に大切なものを見出す鍵となるのかもしれません。
最終章:癌の記・裏日記 – 最後まで上機嫌に
本書の最終章とあとがきでは、癌との闘いの中で見えてきた死生観や、最後まで「上機嫌」でいることの重要性が語られます。
制約の中の最適化ゲーム
癌によって「持ち時間」という制約が明確になったことで、かえって 「この制約の下で、自分の目的を最大化する」 というゲームを楽しめるようになった、と山崎氏は語ります。
漠然とした未来よりも、限られた時間の中で何ができるか、何をすべきかを考える方が、日々の価値を見出しやすく、むしろ張り合いのある日々を送れる、と。
最期の日の幸福論
「もし今日が最後の日だとしても、今からやろうとしていたことをするだろうか」というスティーブ・ジョブズの言葉を引くまでもなく、「今日を大切に生きる」ことは、癌患者でなくても重要な視点です。
山崎氏は、 「最期の日のぎりぎりまで幸福は追求できる」 と断言します。なぜなら、過去の業績や評価(他人からの評価)は死後に持っていくことはできず、本人にとっては「サンクコスト」に過ぎないからです。
「過去は他人のもの、最期の一日は本人のもの」 。この割り切りこそが、最後まで自分らしく、機嫌良く生きるための秘訣なのかもしれません。
自己決定権と愛嬌
治療においても、患者には想像以上に 「自己決定権」 があります。医療者の提案を受け入れるだけでなく、時には自分の意思で治療を選択したり、中断したりすることも可能です。病院側のコンプライアンス(訴訟リスク回避)も、結果的に患者の自己決定権を尊重する形になっています。
そして、山崎氏が最後に付け加える人生のコツは 「愛嬌」 。威張らず、自分を笑える心の余裕を持つこと。愛嬌のある人は、人生の様々な場面で得をする、と。
経済評論家・山崎元氏が、自身の癌体験を通してたどり着いた、お金と人生の本質。それは、不確実性を受け入れ、合理的に意思決定し、不要なものを手放し、限られた時間の中で本当に大切なことを見極め、そして、最後まで「上機嫌」に生き抜くこと、と言えるでしょう。