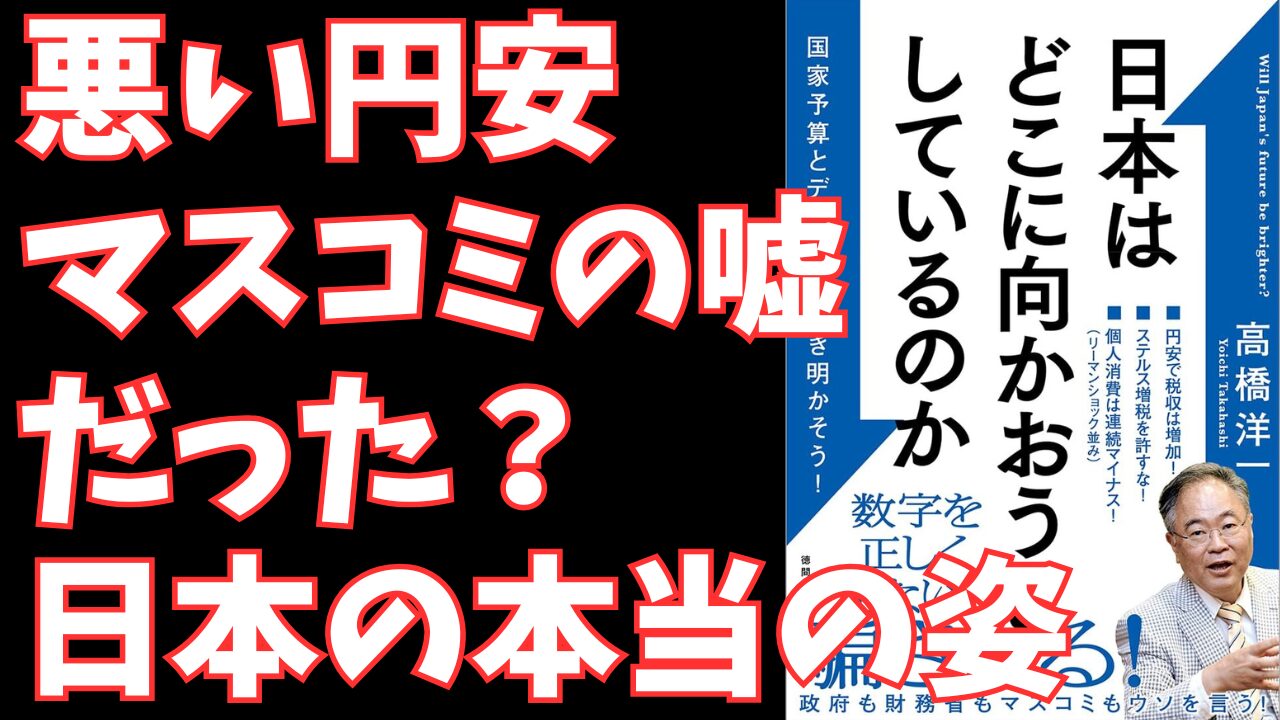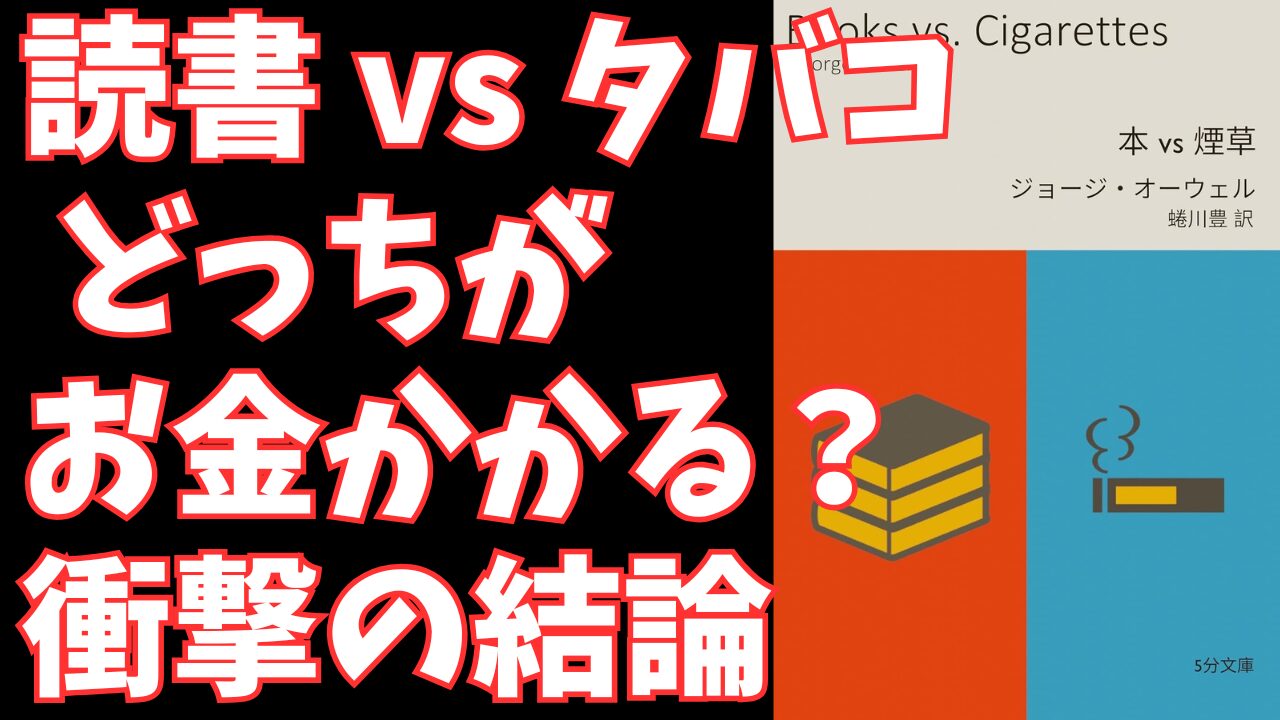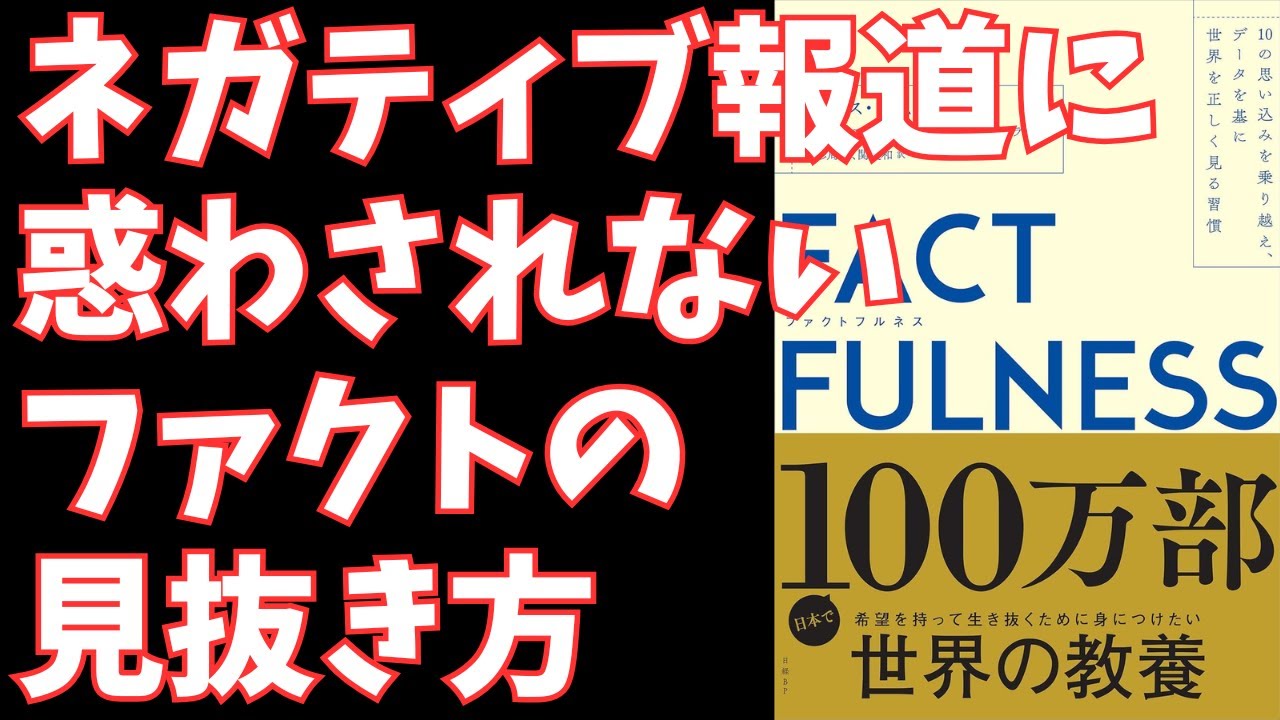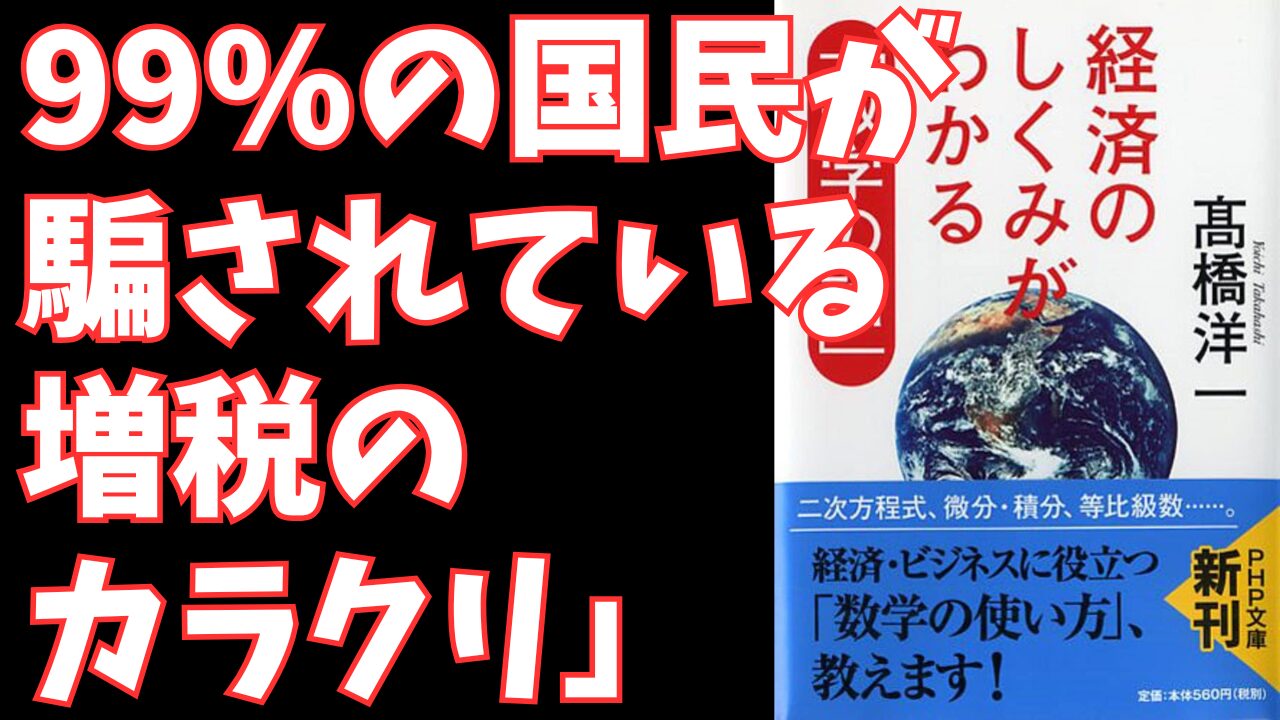『世界のビジネスエリートは知っている教養としてのコーヒー』- 一杯から学ぶ世界史、経済、そして仕事の本質
本書『世界のビジネスエリートは知っている教養としてのコーヒー』は、アジア人初の世界バリスタチャンピオンである井崎英典氏が、コーヒーを軸に世界史、経済、文化、そしてビジネスの神髄を解き明かす一冊です。
コーヒーがイスラム世界からヨーロッパへ伝播し、コーヒーハウスが近代市民社会や保険制度の揺りかごとなった歴史的背景から、現代のコンビニコーヒーに隠された熾烈なビジネス戦略、さらにはサステナビリティといった最新のビジネストレンドまで、一杯のコーヒーの裏側にある壮大な物語を紐解きます。
本書は、単なるコーヒーの知識にとどまらず、なぜ一流のビジネスパーソンはコーヒーを嗜むのか、その本質的な理由を教えてくれます。それは、ディテールへのこだわりが仕事の質を決定づけること、そしてグローバルな共通言語としてのコーヒーが、多様な人々とのコミュニケーションを円滑にすることを、彼らが知っているからです。この記事では、忙しいビジネスパーソンのために本書の要点を凝縮し、明日からの仕事とコーヒーライフをより豊かにするヒントをお伝えします。
本書の要点
- コーヒーは歴史、経済、文化を動かしてきた「知恵の実」である。 イスラム圏での流行、ヨーロッパのコーヒーハウス文化の勃興、アメリカ独立のきっかけなど、コーヒーは常に世界の重要な局面に関わってきた。
- 「たかがコーヒー」にこだわる姿勢が、一流の仕事を生み出す。 世界のトップシェフがコーヒーのディテールに徹底的にこだわるように、細部への配慮が仕事全体の質を大きく左右する。
- 一杯のコーヒーの裏側には、複雑なサプライチェーンと現代ビジネスの縮図がある。 栽培、生産処理、価格決定、流通に至るまで、コーヒーはグローバル経済、サステナビリティ、ブランド戦略といった課題を学ぶための絶好のケーススタディとなる。
- 日本のコーヒー文化は、世界に影響を与える独自の進化を遂げている。 「喫茶店文化」が育んだドリップ技術や、缶コーヒー・コンビニコーヒーに代表される高い開発能力は、世界から注目されている。
- コーヒーを深く知ることは、グローバルな共通言語を手に入れ、ビジネスコミュニケーションを豊かにする。 世界中のエリートたちが愛するコーヒーは、人種や文化を超えて人と人とを繋ぐ強力なツールとなり得る。
なぜ、できるビジネスパーソンはコーヒーを飲むのか?
「コーヒーの貿易取引総額は、石油に次いでなんと2番目」
この事実を聞いて、驚く方も多いのではないでしょうか。世界では一日に20億杯ものコーヒーが飲まれており、私たちの日常に深く根付いています。しかし、世界のビジネスエリートたちがコーヒーを愛飲する理由は、単なる眠気覚ましや習慣だけではありません。彼らは、一杯の漆黒の液体の背後にある、壮大な物語と教養を知っているのです。
本書の著者、井崎英典氏は、高校を中退後、バリスタの道へ進み、2014年にアジア人として初めて「ワールド・バリスタ・チャンピオンシップ」で世界一に輝いた異色の経歴の持ち主です。彼はコーヒーを通じて「学ぶことの楽しさ」を知り、それが世界を舞台に活躍する礎になったと語ります。
井崎氏によれば、コーヒーは歴史、政治、経済、さらにはSDGsといった現代のビジネストレンドまでを内包する、非常に珍しい嗜好品です。この本質を理解することで、日々のコーヒータイムは自己を成長させる学びに変わり、グローバルな舞台でのコミュニケーションを円滑にする「共通言語」となり得ます。
この記事では、本書『世界のビジネスエリートは知っている教養としてのコーヒー』の中から、特に忙しいビジネスパーソンに知ってほしいエッセンスを厳選し、解説していきます。
コーヒーハウスが近代社会の礎を築いた
コーヒーの歴史を紐解くと、それが常に人々の思考を深め、議論を活発化させ、コミュニティを形成する役割を担ってきたことがわかります。
イスラム世界で生まれたコーヒー専門店「カフェハネ」は、人々の交流の場として機能しました。そして、その文化は17世紀のヨーロッパへと受け継がれ、「コーヒーハウス」として爆発的な流行を見せます。
特に当時のロンドンでは、コーヒーハウスは「ペニー・ユニバーシティ」とも呼ばれました。入店料1ペニーを払えば、身分や職業に関係なく誰でも入店でき、そこに置かれた新聞や雑誌を読み、様々な議論に参加できたからです。
アルコールを提供するエールハウス(パブ)と違い、コーヒーハウスでは人々は素面です。それどころか、コーヒーに含まれるカフェインが頭を冴えさせ、建設的な議論を後押ししました。ピューリタン革命を経て、市民が自らの力で社会を築こうとしていた当時のイギリスにおいて、コーヒーハウスはまさに民主主義を育む揺りかごとなったのです。
驚くべきことに、現代社会に不可欠な仕組みもコーヒーハウスから生まれています。
- 保険制度の発祥: 世界最大の保険市場である「ロイズ」は、エドワード・ロイドが開いたコーヒーハウスが発祥です。海運関係の情報が集まるこの店に船乗りや貿易商が集い、航海のリスクを複数人で分散して引き受けるシンジケート(保険組合)が自然発生的に生まれました。
- ジャーナリズムの発展: コーヒーハウスは情報収集の拠点でもありました。人々が持ち寄るゴシップや地域情報が新聞や雑誌のネタとなり、それがまた客を呼び込むという好循環が生まれていたのです。
コーヒーは単なる飲み物ではなく、人々の知性を刺激し、新たなビジネスや文化を創造する触媒として機能してきたのです。この歴史を知ることは、現代のカフェやコワーキングスペースが持つ「人々が集い、新たな価値を生み出す場」としての役割を、より深く理解することに繋がるでしょう。
一流の仕事は「ディテール」へのこだわりから生まれる
「誰も気にとめないディテールにどれだけ気を配ることができるか」
著者の井崎氏は、これが仕事の質を決定づける極めて重要な要素だと断言します。そして、その姿勢は「たかがコーヒー」へのこだわりにこそ現れると指摘します。
本書では、世界で活躍するトップシェフの事例が紹介されています。
例えば、世界中のVIPから愛されるWAGYUMAFIAの浜田寿人氏は、コーヒーに魅了されるやいなや、最新の焙煎機やグラインダーを躊躇なく購入し、水にまでこだわり抜き、自宅を改装してコーヒー専用ステーションを作るほどの徹底ぶり。
また、世界的に著名なレストラン「NARISAWA」の成澤由浩シェフは、自身の料理の余韻に合うコーヒーをブラジルから空輸し、自社で焙煎・抽出まで行っています。
なぜ彼らは、料理の専門家でありながら、そこまでコーヒーにこだわるのでしょうか。その答えはシンプルです。本当の一流は、細部にこそ神が宿ることを知っているからです。
コーヒー一杯にどれだけこだわれるか。それは、顧客へのプレゼンテーション、資料の隅々、日々のコミュニケーションといった、ビジネスにおけるあらゆるディテールに気を配れるかどうかの試金石となります。「たかがコーヒー」と侮るか、そこにまで最高の品質を追求するか。その小さな差が、最終的に大きな成果の違いとなって表れるのです。
この考え方は、あらゆるビジネスパーソンにとって示唆に富んでいます。自分の仕事において、つい疎かにしてしまいがちな「ディテール」は何か。そこに意識を向けることこそが、ライバルとの差別化を図り、仕事の質を一段階上へと引き上げる鍵となるでしょう。
コンビニコーヒーから学ぶ、勝つためのビジネス戦略
今や日本のコンビニエンスストアで、100円程度で高品質なコーヒーが手に入るのは当たり前の光景です。著者の井崎氏は、日本マクドナルドのコーヒーリニューアルを手掛けた経験から、この「100円プレミアムコーヒー」の裏側にある熾烈なビジネス戦略を解き明かします。
井崎氏がマクドナルドのコンサルティングを始めた際、まず行ったのは徹底的な現場観察でした。そこで彼が発見したのは、多くの顧客がコーヒーを単品ではなく、ハンバーガーやポテトとセットで楽しんでいるという事実でした。
これは、コーヒー単体の「最高の味」を追求するだけでは不十分であることを意味します。求められるのは、ハンバーガーやポテトと一緒に味わっても美味しく、さらに時間が経っても味が落ちにくいコーヒーだったのです。
この顧客インサイトに基づき開発された新しいコーヒーは、見事に市場の支持を得て、マクドナルドは100円コーヒー市場のシェアを大きく奪い返しました。
この事例から学べるのは、ビジネスにおける「価値」とは、絶対的な品質だけで決まるのではなく、顧客がどのような状況(TPO)でそれを消費するかによって定義されるということです。
では、なぜコンビニ各社は、利益度外視とも思えるほどの高品質なコーヒーを100円で提供できるのでしょうか。
それは、コーヒーを「撒き餌」として捉えているからです。美味しいコーヒーを求めて来店した顧客は、ついでにサンドイッチやお弁当、デザートなどを購入していきます。コーヒー単体では利益が出なくとも、店舗全体での売上向上に繋がる「販売促進費」と考えることができるのです。
この戦略は、Webサービスにおけるフリーミアムモデルにも通じます。まずは無料で高品質なサービスを提供して顧客を引きつけ、その後のアップセルやクロスセルに繋げる。コンビニコーヒーは、この古典的かつ強力なビジネスモデルを、リアル店舗で見事に実践している好例なのです。
自社の製品やサービスが、顧客にとってどのような価値を持っているのか。そして、その価値を最大化するために、どのようなビジネスモデルを構築すべきか。コンビニコーヒーの裏側には、そうした普遍的なビジネスの問いに対するヒントが隠されています。
「スペシャルティコーヒー」が示す未来のビジネスモデル
コンビニコーヒーのようなコモディティ(大衆商品)市場とは対極にあるのが、「スペシャルティコーヒー」の世界です。これは、生産者と販売業者が直接取引(ダイレクトトレード)を行い、豆の出自や運送の透明性(トレーサビリティ)が確保された、極めて高品質なコーヒーを指します。
スペシャルティコーヒーのビジネスモデルは、大量生産・大量消費を前提としたコモディティコーヒーとは全く異なります。その根底にあるのは、「良いものには、正当な対価を支払う」という考え方です。そして、この思想は、現代ビジネスにおいてますます重要性を増している「サステナビリティ(持続可能性)」という概念に直結します。
コーヒー産業は、歴史的に植民地主義の負の遺産を抱えてきました。消費国が安価なコーヒーを楽しむ裏側で、生産国の労働者が不当に安い賃金で働かされるという構造が長く続いてきたのです。
スペシャルティコーヒーのムーブメントは、こうした構造に一石を投じます。生産者が品質向上に努めれば、それが直接、収入の増加に繋がる。これにより、生産者は安定した生活基盤を得て、持続的に高品質なコーヒー栽培を続けることができるのです。これは、関わる人すべてが豊かになる「三方よし」の精神を、グローバルなサプライチェーンで実現しようとする試みと言えるでしょう。
さらに著者は、これからのビジネスには「ラディカルトランスペアレンシー(徹底的透明性)」が不可欠になると予測します。これは、原材料の価格やコスト、利益配分といった、これまでブラックボックスだった企業活動の裏側を、消費者にすべて開示する考え方です。
著者がコンサルタントとして関わったコーヒーノキの廃材を利用したシロップの開発プロジェクトでは、まさにこの徹底的透明性が実践され、廃材の買取価格から農家の利益まで、すべての数字が公開されています。
消費者の倫理観が高まり、「どのような企業を支持するか」が購買動機に大きく影響する時代において、こうした透明性の高い姿勢は、何よりの信頼とブランド価値を生み出します。スペシャルティコーヒーの世界で起きている地殻変動は、コーヒー業界に限らず、あらゆる産業の未来を占う羅針盤となるはずです。
明日から実践できる、できるビジネスパーソンのコーヒーライフ
本書で得た教養を、ぜひ明日からのあなたの日常とビジネスシーンで実践してみてください。著者が提案するコーヒーライフのヒントをいくつかご紹介します。
- 朝:ドリップコーヒーで精神を整える
忙しい朝こそ、少し早起きして丁寧にハンドドリップでコーヒーを淹れてみてはいかがでしょうか。お湯を注ぎ、豆が膨らむ様子を眺める一連の作業は、茶道や禅にも通じる儀式的な要素を持っています。心を落ち着け、目の前のものに集中する時間は、その日一日のパフォーマンスを高めてくれるはずです。 - 日中:コミュニケーションツールとして活用する
オフィスでの会議や商談の場に、美味しいコーヒーを用意しましょう。活発な議論を促すだけでなく、豆の産地や特徴などを会話のきっかけにすることで、場の雰囲気を和ませ、円滑なコミュニケーションを助けてくれます。 - 夜:デカフェで睡眠の質を高める
夜遅くまで仕事をする際、カフェインに頼りたくなる気持ちはわかります。しかし、良質な睡眠こそが最高のパフォーマンスを生み出します。夕方以降は、カフェインを取り除いた「デカフェ」に切り替えることを著者は強く推奨しています。近年は技術が進化し、風味を損なわない美味しいデカフェも増えています。「コーヒーを淹れる」という行為そのものが持つリラックス効果を享受しつつ、体を労りましょう。 - TPOに合わせた豆選び(フードペアリング)
常に同じコーヒーを選ぶのではなく、シーンに合わせて楽しむのが上級者です。例えば、フルーツタルトにはフルーティーな酸味を持つ浅煎りのコーヒーを、濃厚なチョコレートケーキにはコクのある深煎りのコーヒーを合わせる、といったフードペアリングを意識してみてください。この細やかな配慮が、相手に「おもてなしの心」を伝え、より豊かな時間を演出します。
一杯のコーヒーは、あなたの日常に彩りを与え、ビジネスにおける思考を深め、そして世界中の人々と繋がるための翼となります。本書を片手に、あなただけの豊かなコーヒーライフを探求してみてはいかがでしょうか。