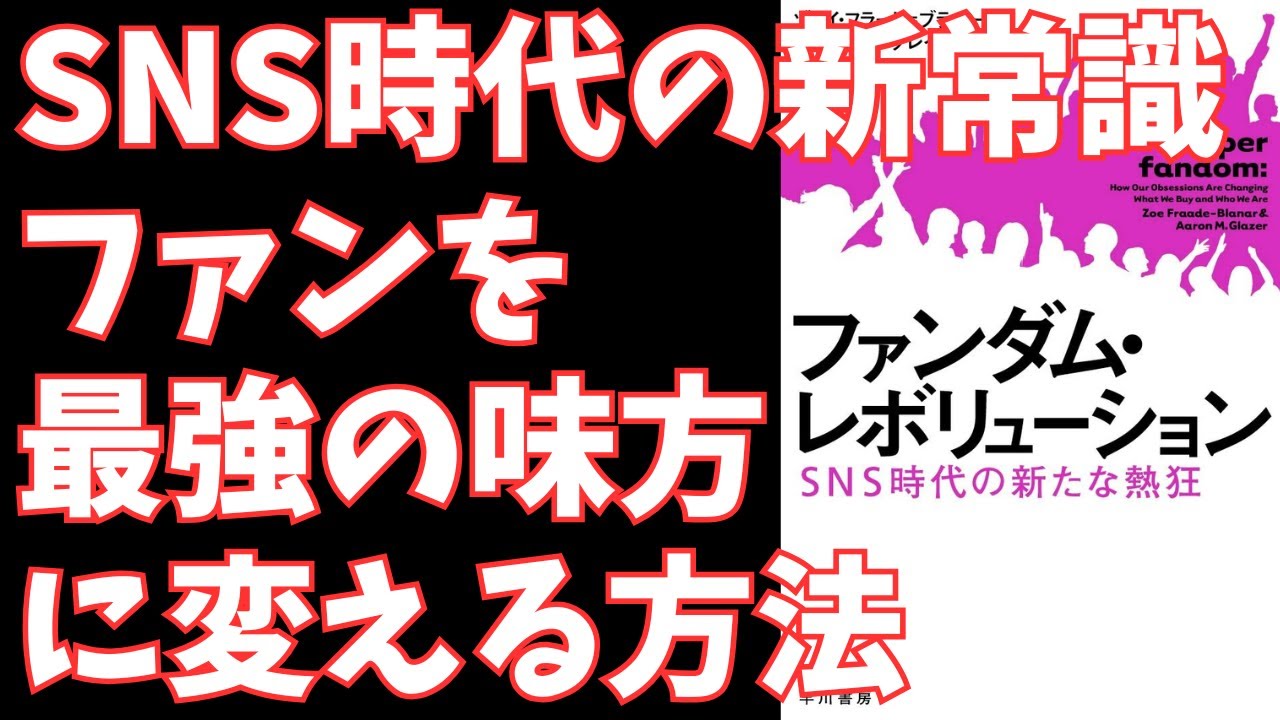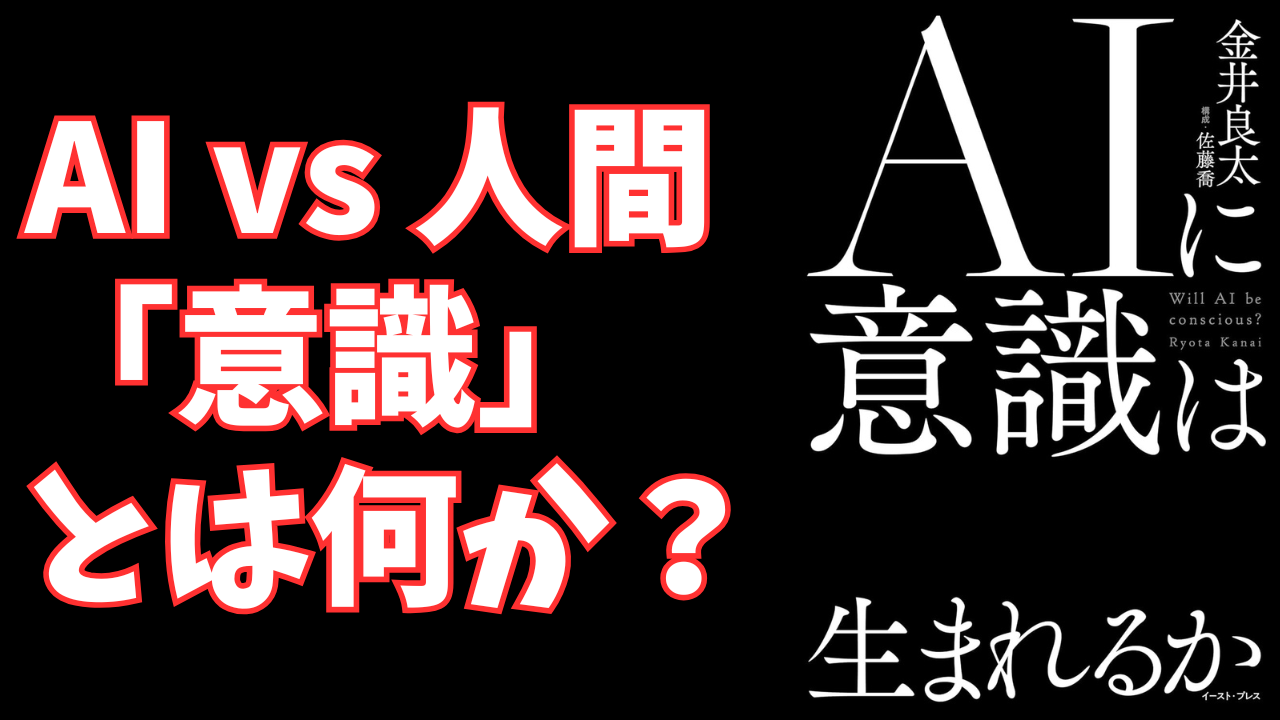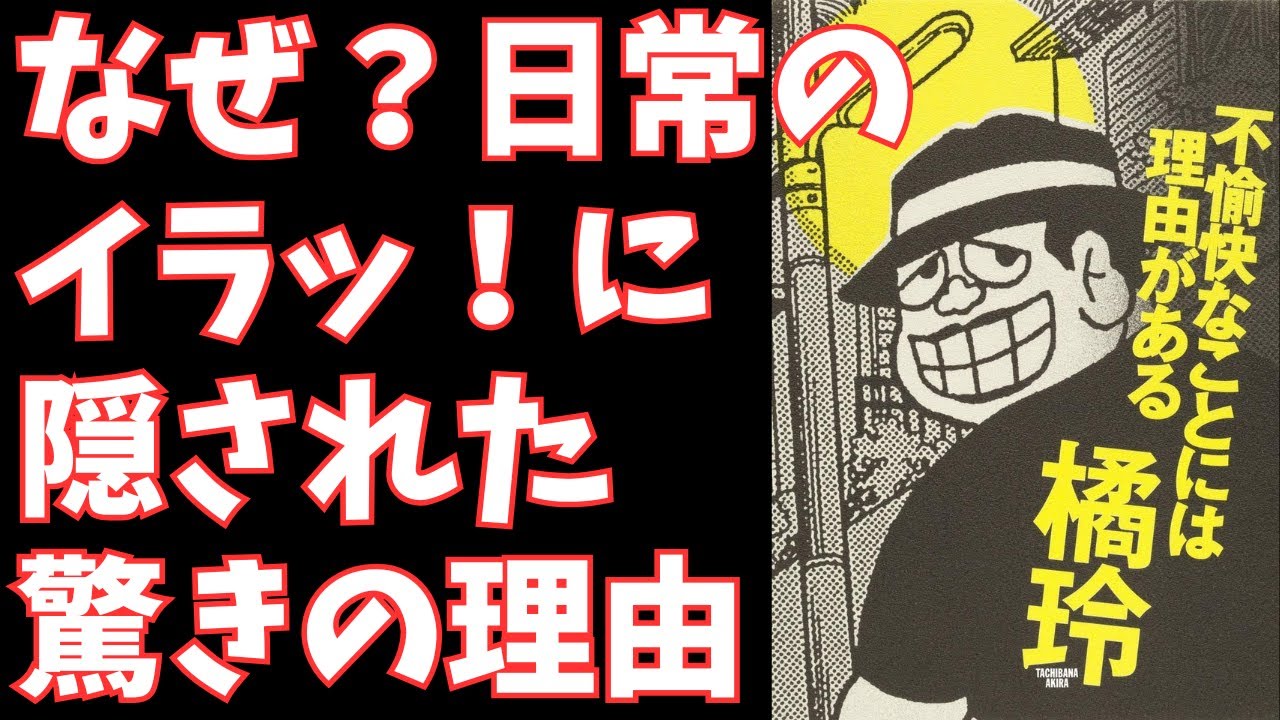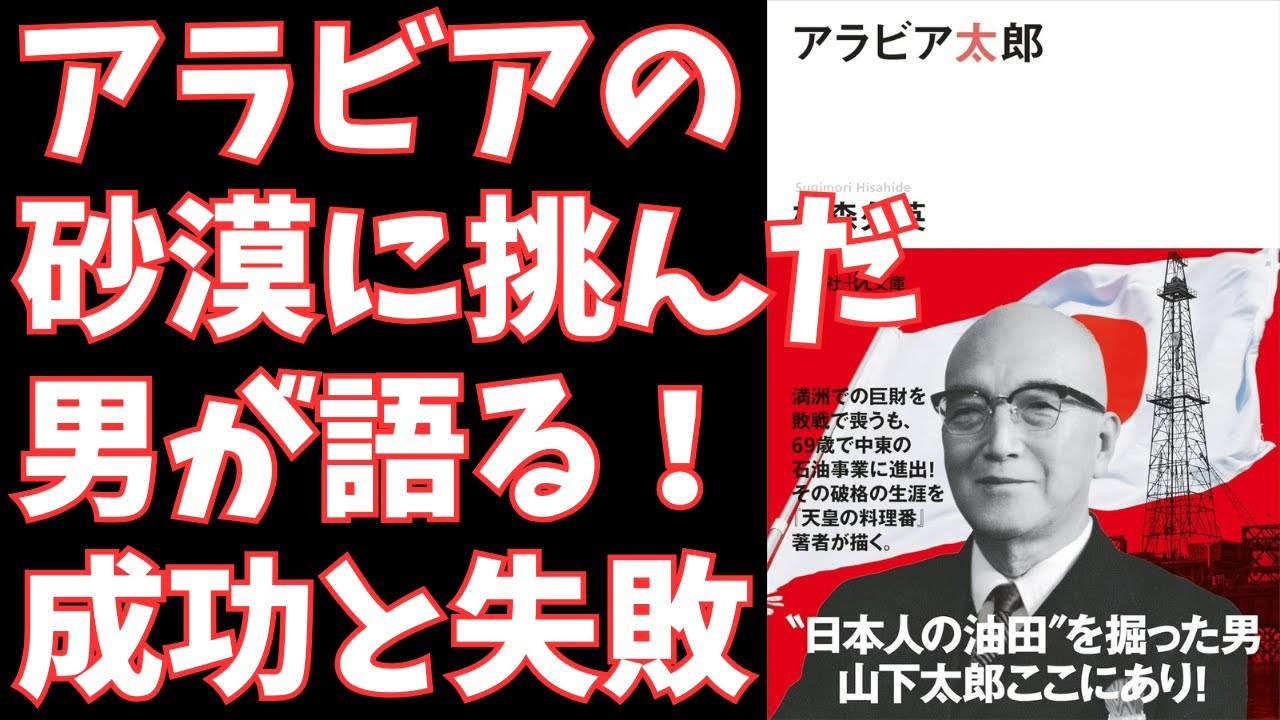新装版「エンタメ」の夜明けから学ぶ!エンターテインメントビジネスの革新と大衆を魅了する秘訣
本書『新装版「エンタメ」の夜明け』は、エンターテインメントという言葉がまだ日本で一般的ではなかった頃から、数多くの“仕掛け”を通じて大衆を熱狂させてきた先人たちの奮闘を描いています。中心にいるのは、毎日新聞や電通で活躍し、プロ野球パ・リーグ創設から民間ラジオ局の立ち上げ、大阪万博など数々のビッグプロジェクトを動かしてきた小谷正一。そして、彼の薫陶を受けながら東京ディズニーランド招致を成し遂げた堀貞一郎という“エンタメの仕掛け人”たちです。
彼らの活動は、闘牛からプロ野球、ラジオ放送、テレビ番組『シャボン玉ホリデー』や『11PM』、さらには国際イベントとなった大阪万博や世界のスター招聘など、多岐にわたります。そこには「観客を魅了し、心をつかむ」ための数々の工夫と大胆な発想が満ちており、日本のエンターテインメント・ビジネスがどのように誕生し成長してきたのか、その生々しい軌跡が記されています。本書を通じて、人を楽しませる本質や、そこで働く人々の熱い情熱と戦略を学ぶことができるでしょう。
エンタメの先駆者たちの足跡
本書の冒頭でクローズアップされるのは、闘牛を興行として成立させようとした話です。戦後まもなく、大衆は娯楽に飢えていました。そこで「宇和島の闘牛を都会でやれば当たる」とばかりに、大阪の西宮球場で大イベントを企画。しかし雨に祟たたられ大失敗に終わるという波乱の幕開けから、舞台裏のドラマが始まります。
この大胆な構想に関わったのが、当時毎日新聞の事業部長だった小谷正一。結果として借金を抱えるのですが、その失敗を一気に挽回するために今度は「アゴも足もかからない展示物、すなわち絵画展」を打ち出して成功させます。こうした「当て方の発想転換」こそが彼の真骨頂だったのです。
そして、戦後からのエンタメ勃興に欠かせない人物として登場するのが、GHQや読売新聞の正力松太郎らと渡り合いつつプロ野球パ・リーグの創設を成し遂げた姿です。「新聞の発行部数を伸ばすためにはプロ球団が必要だ」という戦略眼から、わずか数年で戦時下からのプロ野球を2リーグ制に再編させてしまう。その猛烈な行動力と“アタリを獲りにいく”姿勢が、小谷や周囲の仲間たちの仕事スタイルを決定づけていきます。
民放ラジオとテレビ番組の新時代
戦後間もない頃、放送といえばNHKのラジオ1局のみ。そこに、民間放送を立ち上げろと突然言い渡され、悪戦苦闘するのが小谷正一でした。
民放ラジオ第一号となる新日本放送では、スポンサー獲得のため電波料やCMの仕組みを一から考える必要がありました。広告代理店の電通社長・吉田秀雄の「放送局を維持するには最低いくらかかるのか、そこから算出せよ」というアドバイスにより、理屈ではなく「これだけの人間が生活するにはいくら必要か」と実務の数字を組み立て、それを企業にプレゼンして回ることで事業を成功させたのです。
その後、小谷がビジネスパートナーらと設立したのが「ビデオホール」。ここはテレビ番組の公開収録を可能にし、音楽ショーやジャズの生放送などを行う拠点として人気を集めました。このホールに集まった若手クリエイターや演出家、作家たちが日本のテレビ史を彩っていきます。
一方で、民放テレビの初期番組も画期的でした。『シャボン玉ホリデー』や『11PM』といった深夜帯のワイドショーが世間を賑にぎわした背景には、スポンサー企業と広告代理店、番組企画サイドが一体となり「大衆がどんな番組を観たいのか、あるいは観ればハマるのか」をトライ&エラーで探り当てる“総力戦”があったのです。
特に『シャボン玉ホリデー』は当初こそ視聴率が低迷しましたが、出演者のザ・ピーナッツやクレイジーキャッツ、そこに作家として合流した青島幸男のコントが爆発的人気を得て、一大“笑いと音楽の玉手箱”になりました。牛乳石鹼というスポンサーが思わぬ売れ行きを体験するなど、テレビのCM効果が企業のビジネスを飛躍させる大きな転機ともなったわけです。
プランニングセンターとアイディア産業
やがて広告代理店・電通では、吉田秀雄のもとで「プランニングセンター」が設立されます。ここはアイディア産業の先駆けと言うべき場所であり、ノルマを持たずにただ新しい企画を考え出すという“ティンカー・グループ”を手本とした実験的部署でした。
そこへ集められたのが堀貞一郎や岡田芳郎ら“企画の鬼才”たち。彼らはCMソングを自ら書き、タレントをキャスティングし、番組の構成まですべてワンストップで手がけるという今で言うマルチクリエイターの走りでもありました。
やがて堀は漫画雑誌とのタイアップを発案し、「ハリスの旋風」といった作品を通じてガムメーカーのイメージ向上を図るなど、枠を超えた企画を次々と成功させていきます。そんな新しい広告のかたちが認知されるにつれ、業界全体が「広告はもっと創造性を発揮してよい」と覚醒し始めるのです。
海外スターの招聘と“黒い蝶”のエピソード
小谷が“エンタメを輸入する”ことにも情熱を注いでいた話は、本書の大きな読みどころです。とりわけ、当時国交のなかったソ連からバイオリニストのダヴィッド・オイストラフを招いた逸話は圧巻でしょう。
役所の許可も下りないなか、様々なつてを使い、飛行機のタラップを降りてくる彼を本当に迎えられるのか、ずっと疑心暗鬼だった小谷。しかし最後は自腹でスポンサーを募り、宛名のない書類をスカンジナビア航空の乗組員に託し、ようやくオイストラフの滞在が実現します。
井上靖の小説『黒い蝶』は、この招聘劇をモチーフに描かれました。紆余曲折の末に開催された演奏会は大成功を収め、日本の音楽ファンにとっても画期的な出来事になったのです。これらの“できっこない”を実現させてしまう小谷の情熱に触れると、「世界を動かす」のは書類や理屈だけでなく、人と人との熱い思いだと痛感させられます。
大阪万博で花開くエンタメプロデュース
そしてクライマックスとも言えるのが、1970年の大阪万博です。万博そのものは国家プロジェクトでしたが、その中で小谷や堀は企業パビリオンのコンセプト決定や設計演出の陣頭に立ちました。住友童話館や電力館で、童話や竹田人形座の要素を組み合わせて幻想的な世界をつくり出す一方、引田天功(先代)による電気マジックのショーを構想するなど、前例のない試みに挑戦します。
ここでカギになったのが、アメリカのディズニーが手がけたニューヨーク万博を参考にした企画でした。ウォルト・ディズニーがフォードやGEなどの企業パビリオンに最新技術を活用したアトラクションを導入し、大成功を収めていたのを見て、「ああいう圧倒的にユニークな仕掛けこそが必要だ」と痛感するのです。
万博開幕中は、膨大な観客数に対応するため、どのパビリオンも連日大混雑。そんな過酷な環境のなか、「人々にどうやってわかりやすく、しかも感動を与えるか」ということを徹底的に考え抜きました。結果、住友グループや電力館の展示はトップクラスの人気を誇り、「芸術家やクリエイターにはきちんと対価を払うべきだ」という意識変革を企業の側にもたらしました。
テーマパークとしての究極形——ディズニーランドの誘致
万博が成功裏に幕を閉じたあと、小谷は「次はディズニーランドを日本に持ってこよう」と頻繁に口にするようになります。彼自身がロサンゼルスのディズニーランドを視察し、ウォルト・ディズニーの発想力に惚れ込み、「大人も子どもも王様のように楽しめる場所」を日本に根付かせたいと渇望していたからです。
しかし、すでに還暦を迎えていた小谷には時間がありません。一方、その弟子ともいうべき堀貞一郎が電通から出向し、浦安を中心とした“オリエンタルランド”の誘致プランを三井不動産と一緒に進めることになります。
物語の白眉は、堀が三菱グループによる富士山麓へのプランと激突する競合プレゼンで、ひときわ鮮やかなパフォーマンスを披露する場面。
ディズニー経営陣を羽田に出迎えてみても、三菱サイドはあまり力を入れず静か。ところが翌日の三井側のプレゼンでは、接客から移動バスまで徹底的に研究し、昼食もアメリカ人好みに仕立て、さらにヘリコプターを用意し東京湾の埋立地と都心の近さをアピール。ディズニートップはそのサービス精神と地理的優位性に驚き、「ノー・クエスチョン(何も聞くことはない)」の一言を残します。
結果、正式に浦安へのディズニーランド建設が決定し、東京ディズニーランドは1983年、年パスポート制など日本独特の工夫を組み込みながらオープンするに至りました。この圧倒的成功の裏には、万博での経験や“小谷イズム”とも言うべき観客をVIP扱いする姿勢が深く根づいていたのです。
小谷正一の人心掌握術
本書に散りばめられたエピソードで際立つのは、小谷の“ハッタリも辞さず”人の心をつかむ力でしょう。オイストラフの来日でも、フランスのマルセル・マルソー招聘でも、親交ある知人たちの車や会長室などを巧みに借りる“演出”でVIP待遇をアピールしました。
一見、芝居がかった手段にも見えますが、その背景には「相手への心遣い」があります。ソ連のオイストラフには、色違いのジャケットを全スタッフに着せ「あなたが滞在中、彼らがすべてをお世話します」と安心させ、マルソーにはNHK会長室を貸し切って高級ホテルのように錯覚させる…。これらすべての根っこには、彼の「最高の舞台で最高の演奏やパフォーマンスをしてほしい」という強い願いがあったからでしょう。
「少しぐらいハッタリをかませ」という小谷の口癖は、若い才能たちを自信づけ、“こんなの無理だ”と思える企画を次々と実現可能に変えていったのです。
人を動かす情熱とビジネスセンス
本書から学べるのは、たとえ昭和中期の話でも通用する“人間の心の動かし方”です。小谷や堀に共通するのは、「相手が本当に求めているものを察し、それを最大限に演出する」という理念でしょう。
また、彼らは世界を相手にする手段として、新聞、ラジオ、テレビ、万博、テーマパークなど、多岐にわたるプラットフォームを活用しました。新しいメディアや技術が登場すれば、ためらわず飛び込んでいく。ここには「一度の失敗で諦めず、次の手段を模索する」というビジネスセンスが詰まっています。
読者として驚かされるのは、今や常識となった施策がまったく前例のないところから生まれている点です。ゴールが見えない中で、スポンサー企業との交渉や関係づくり、さらに国際政治的障壁までも乗り越える執念と創造力が、当時の日本のエンターテインメント界を形づくりました。
おわりに
戦後から高度経済成長期に至るまで、日本人は失われたものを埋めるように多様な娯楽を求め続けました。そこで起こったのが、プロスポーツの台頭、テレビ放送の普及、海外文化の輸入、万博など、国際的大イベントの成功。そして最終的にはテーマパークとしてのディズニーランド誘致へと結実します。
本書『新装版「エンタメ」の夜明け』で描かれる先人たちの姿は、単なるノスタルジーではありません。当時の彼らが持っていた「どうすれば人の心を震わせられるか」という視点、それを実行に移す突破力、あえてハッタリをかます度胸、何より大衆を愛する情熱こそ、現代の私たちが学ぶべき核と言えるでしょう。
新しいテクノロジーが次々に生まれ、SNSや動画配信が当たり前となった今、ビジネスの中心には何があるのか。結局、人間が感動するかどうかが勝負なのは変わりません。本書はその原点を思い出させてくれる一冊であり、私たち自身も「エンタメを通じて人々を楽しませたい」と願うなら、たとえ無謀に思える企画であっても立ち上げられるヒントが見いだせるのではないでしょうか。