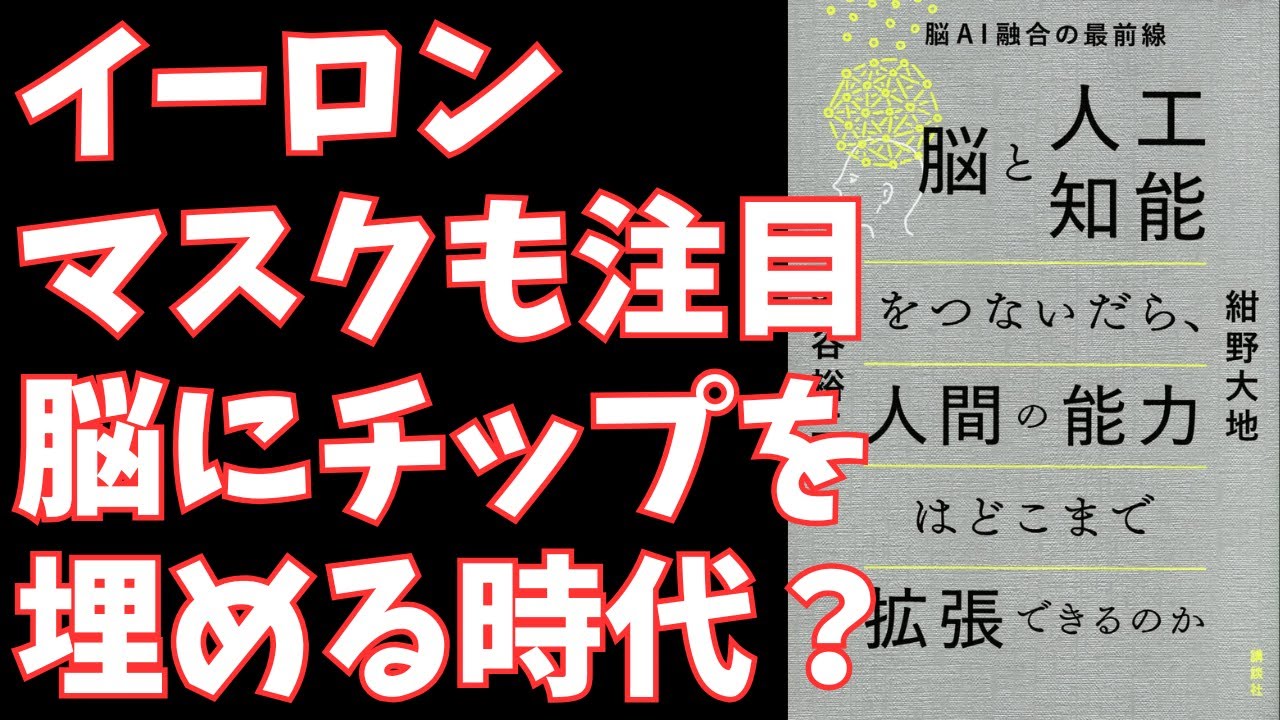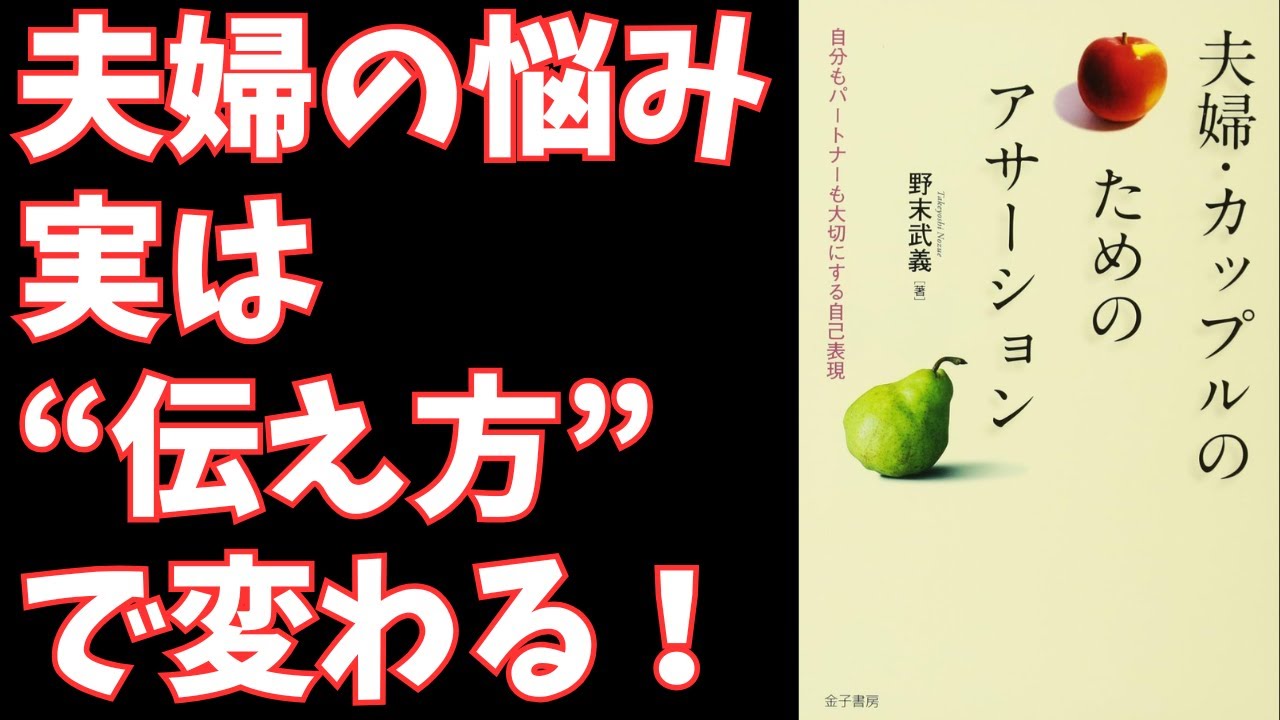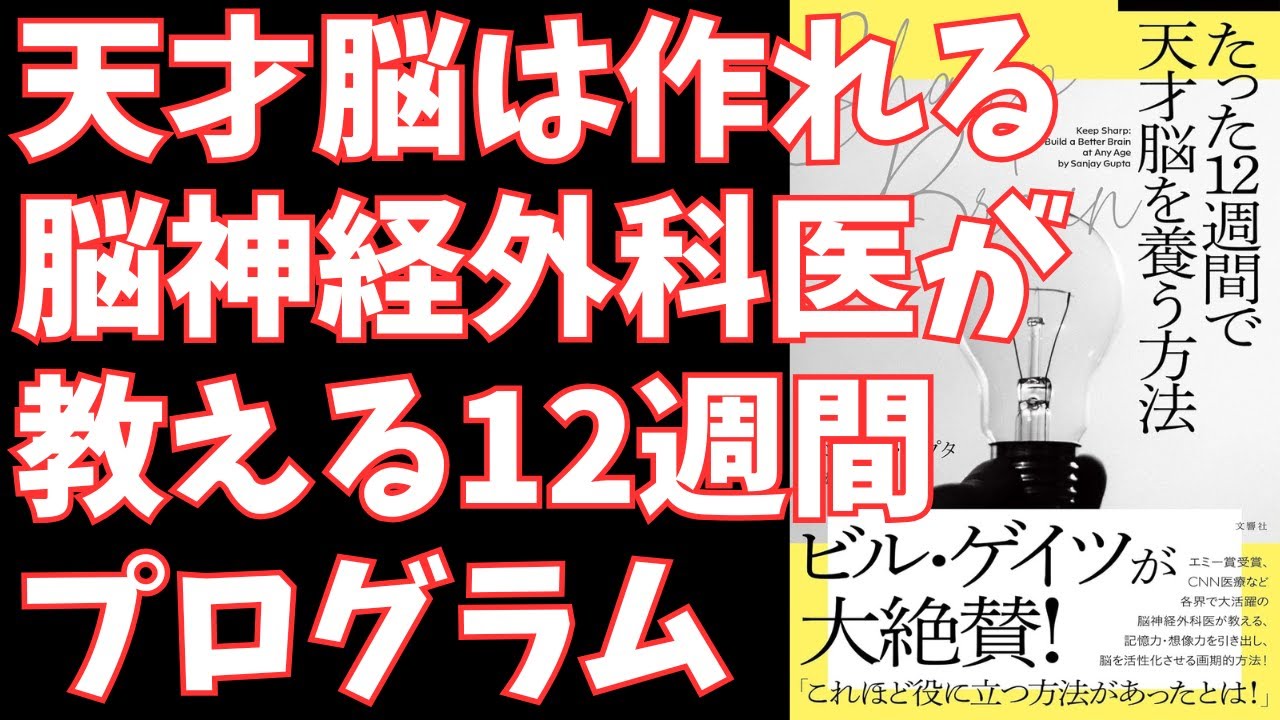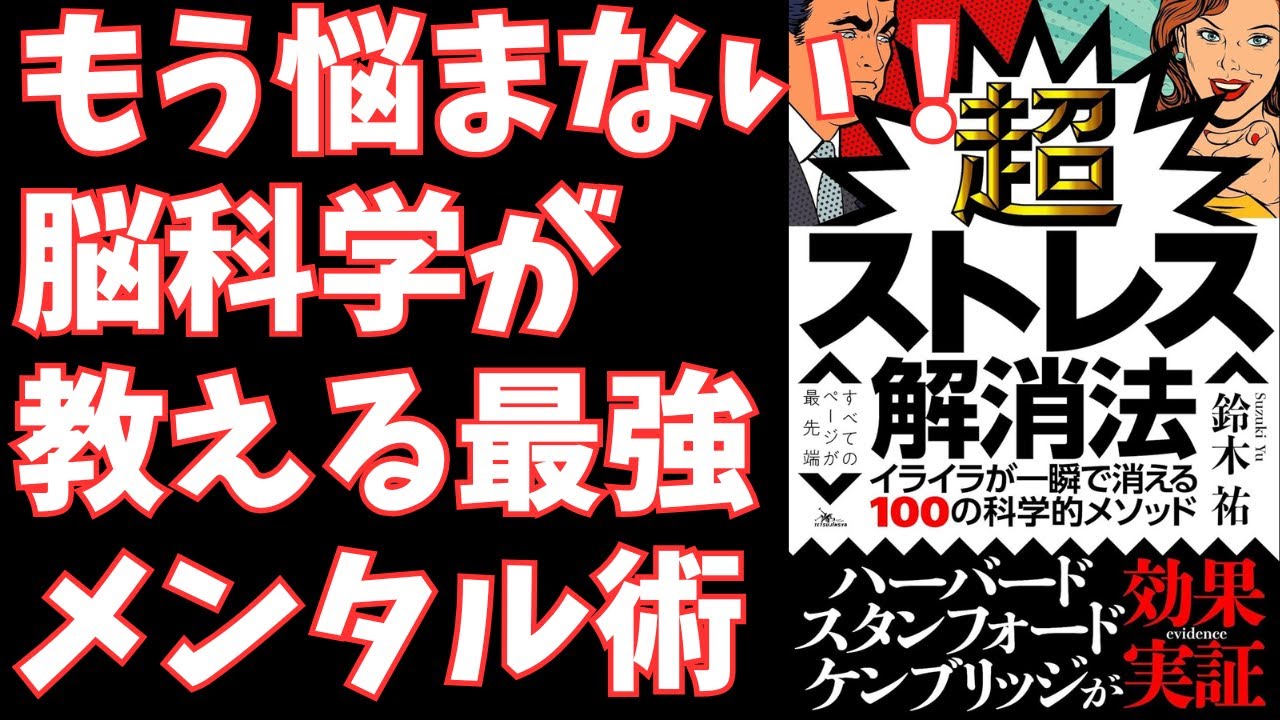エベレスト下の「デス・ゾーン」に挑む男の軌跡――“劇場”が映し出す人間の本質
本記事では、登山家として異色の存在だった栗城史多が示したエベレスト挑戦の実態と、その過程で明らかになった数々の逸話を取り上げる。舞台となる「デス・ゾーン」は高所ゆえの酸素不足だけではなく、人間ドラマを浮き彫りにする環境でもあった。彼が自撮りの映像を駆使して登山を“劇場”に変え、資金調達やメディアを巻き込みながら夢を語り続けた姿勢は多くの注目を集めた一方、虚偽表示や誇大広告と批判される一面も持ち合わせていた。本記事では、彼がエベレストを目指すに至るまでの資金集めや撮影手法、そして山で遭遇した悲劇や疑問を、書籍の具体例をもとに掘り下げる。山頂を「認定ピーク」で済ませた真意や、「ジャパニーズ・ガール」と呼ばれた遺体との対峙が示す“見たくない現実”、さらに彼がなぜ指を失っても挑戦をやめなかったのか。その葛藤を追う中で、人間が極限状態で見せる意外な本音や、ビジネスとしての登山が孕む矛盾が浮き彫りになる。最後まで読み進めることで、挑戦の本質、そして「なぜ人は山に登るのか」という根源的な疑問へと近づいていきたい。
序章:単独無酸素登頂というキャッチフレーズ
かつては「お笑い芸人になりたかった」という少年が、人生の目標として掲げたのが「単独無酸素での七大陸最高峰制覇」だった。五体満足で生まれてきたことを父に感謝しながらも、大きく歪んだ環境で育った背景が彼の原動力となる。父が幼少期に大ケガを負いながら障害を抱え生き抜いてきたように、自分も限界を超え続ければこそ道が拓ける――そう信じる姿勢が、本人の人生を突き動かしていった。
しかし「七大陸最高峰を無酸素で」という言葉は、実は誤解を招く表現でもある。そもそも酸素ボンベが必要となるのはエベレストなどごく限られた高所登山であり、ほかの峰では通常使わない。彼自身、その事実を把握しながらもあえてキャッチーな「単独無酸素」という言い回しを好んだ。その背景には、スポンサーをはじめとする外部からの資金を集めるための戦略が見え隠れする。
本稿では、そのような彼の言動や手法が正当だったのか、もしくは“虚偽”と断じられるものだったのかを検証しながら、最終的に見えてきた彼の姿を描いていく。
第1章:山と人を引き寄せたビジネス力
1-1. ニートのアルピニスト?
大学時代に登山を始めた彼は、当初「小柄で非力」なところからスタートした。にもかかわらず、北米大陸最高峰のマッキンリー(デナリ)にいきなり挑むなど、常人離れした行動力を見せ始める。マッキンリーは標高6190メートルと北米最高峰ながら、出発当時は入山申請や高所技術が整わないままの無計画さが目立った。それでも「奇跡」と呼ばれる形で無事登頂を果たしたことで、「自分は高峰を登るのに必要な資質があるのだ」と大きな自信を得たと言われる。
その後、南米アコンカグアやアフリカ・キリマンジャロなどを矢継ぎ早に踏破。いずれも標高は高いが、酸素ボンベの使用は不要な山である。これを「単独無酸素」でクリアした事実だけを並べた結果、「一見すごい」と思わせる巧妙なイメージ戦略が成り立った。
そしてビジネス面を支えたのは、大学教授や弁護士、企業経営者などの強力な支援者とのコネクションである。彼は講演をこなしながら、会合で人脈を広げ、さらには企業の営業マンのように動いて遠征費を獲得した。エベレストは入山料だけでも百万円以上、ネパール政府への撮影許可も含めれば数百万単位が飛んでいく。それを捻出するため、いかに巧みに“夢の共有”を売り込むかが最大のポイントになった。
1-2. 「山を劇場に変える」発想
単独行で山を撮影し、その映像をネットで配信する――本人いわく「山と視聴者の架け橋になる」ためであり、“冒険を共有”するのが狙いだった。そもそも登山中に自分を撮影するのは至難の業だが、彼は三脚をセットして自分の姿を撮影した後、一度カメラを取りに戻るという手間を苦にしなかった。幻覚を見るほど体力が限界でも「ここは撮っておかないと意味がない」とカメラを回し続ける。それはまさに「劇場を演出する」という意識にほかならない。
ネット配信とテレビのドキュメンタリーの需要が高まるにつれ、「彼なら視聴率が取れる」「面白い企画が作れる」と考えるメディアも増えた。本人も無自覚ではなく、積極的に“登山家”という商品をPRし、マスコミを味方につけていく。しかし、その戦略はときに「金のために山を利用している」という批判を浴び、かつ実際に放送する局同士で放映時期が競合するトラブルも起こった。
1-3. 営業も撮影も…“総合格闘技”的スタイル
通常、エベレストのような高所登山では登山経験や技術面の積み上げが第一に重視される。ところが彼の場合、各地での講演、スポンサー交渉、ウェブ配信の打ち合わせと実に多岐にわたる「裏方作業」を一身でこなしていた。その動きはまさに企業のプロデューサーのよう。多忙を極める一方、「普通の人はできない」行為をこなしていることで自己評価をいっそう高めていった節もある。
一方で、こうした“自己演出”に精力を注ぐ姿に対しては、本人が目標として掲げる「本当にエベレストの頂まで単独無酸素で登る力があるのか?」という疑念も徐々に沸き上がる。山岳関係者からは「準備が杜撰」「技術が足りない」という声が多く聞かれたが、彼は資金集めとメディア露出の巧みさで追い風を得るという手段を優先していた面が否めない。
第2章:凍傷と「ジャパニーズ・ガール」の衝撃
2-1. マナスルで出会った遺体の真相
エベレスト以外の8000メートル峰として、彼はマナスル(8163メートル)に挑戦した。当時、撮影映像やブログ更新を駆使して「自らの苦しむ姿」をリアルタイムで発信しようとしていたが、そこで目にしたのは氷雪に埋もれた一体の遺体だった。その遺体は「ジャパニーズ・ガール」と呼ばれ、誰もが「日本人女性が遭難したものか」と思い込んでいた。本人も当初は「自分がこの遺体を回収しなくては」と意気込んだが、実はスロバキア人男性の遺体であったことが判明する。
衝撃的なのは、ヒマラヤの標高7000メートル以上では、遭難者の遺体が放置されることが珍しくない点だ。雪崩や吹雪で埋もれ、そのまま“目印”のように見えてしまうという現実。プロであっても手を施せない場面が多々あり、その事実を自分の映像として収めたのが、彼の“劇場”を支える重要なシーンにもなった。皮肉にも「ジャパニーズ・ガール」の正体をめぐる誤解や悲しみは、専門家や遺族、周囲の登山家たちの気持ちを深くかき乱した。
2-2. 認定ピークと山頂の境界
マナスルを登る際、彼は頂上と呼ばれる地点でビデオカメラを回し、「登頂しました」と報告をした。しかしその場所は本当の山頂より少し手前の“コブ”だった。現地シェルパに「ここが頂上だよ」と言われると「ならばここでいいのか」と判断し、実際にそこを「認定ピーク」と称して降りてしまう。過去の登山家たちが「ニセピーク」と見抜いて最後まで行った事例と比べると、彼は天候悪化や疲労を理由に安全策を取ったとも言えるが、登山家にとって肝心な「頂への執念」が見られないと批判されるのも無理はなかった。
この一件は後々、彼が講演などで「マナスルにも無酸素で登った」と語る場面において、山岳関係者から「そもそも本当の頂に立っていない」という指摘を招く火種になる。映像が残っているからこそ、すべてが明るみに出てしまったわけだが、同時に彼の「自分は登頂した」という公言は修正されないまま広まってしまった。
2-3. 体と心を蝕む凍傷
さらに高所登山においては、「凍傷」が深刻な問題である。僅かな気温と体力の変化が指先や手足に大きなダメージを与え、重症化すれば切断が必要になる。彼自身、繰り返しエベレストに挑むなかで重度の凍傷を負い、手指を切断せざるを得ない状況にまで追い込まれた時期があった。しかし、最後まで「手術に踏み切らずリハビリで何とか克服したい」と言い続ける。そこには幼い頃、母がかいがいしく看病してくれた指を自分で切り離すことへの罪悪感があったという。
だが、指を失っても登山を続けられるわけではない。器具を扱いにくくなり、バランスや細かな作業が難しくなる。体への負担が増す一方で、周囲からは「なぜそこまでして登り続ける?」との疑問の声が高まっていった。
第3章:終わらぬ夢と“劇場”の幕引き
3-1. 「夢の共有」とインターネット中継
彼がエベレスト挑戦で新たな一手として掲げたのは「インターネット生中継」だった。単独行をしながら、ベースキャンプでスタッフがカメラを受け取り、編集や動画配信を行なうという試みである。講演でも「いよいよ新時代の冒険がはじまる」と意気込み、スポンサーやファンもこの最先端感に魅了された。
だが、現実には高所での通信環境は不安定だ。さらに降雪と強風が吹き荒れる夜間にカメラを起動することは危険を伴う。山頂アタックの核心部ほど撮影が困難になり、映像が途切れがちになるため、結局視聴者には断片的なシーンしか伝わらない。その隙間を“英雄的イメージ”で埋めるかたちになり、より一層「本当に登っているのか?」「苦境は誇張されていないか?」という疑念も膨らんでいく。
3-2. 指を失っても登り続けた理由
凍傷で指を失った後でも、山への執念を捨てなかったのは、周囲が驚くほどの「しつこさ」とでも呼ぶべき執拗な挑戦心だった。“諦めたらそこで終わり”という意志がありつつ、それは自身の講演や書籍で語り続けた「夢は口に出せば叶う」という啓発的メッセージと表裏一体だったといえる。
ただ、「実際に不可能へ挑む姿そのものが価値になる」という仕組みが、新たな遠征資金やメディアの注目を呼び込むことも事実だった。数度にわたるエベレスト挑戦が失敗に終わっても、むしろ話題性が増していく。指の切断という痛々しい代償を得てもなお「次こそはいけるはず」と信じる姿は、彼にとってビジネス的な循環になっていたとも言えよう。
3-3. 最後の滑落
2018年5月、彼は険しいルートからのエベレスト挑戦を試み、滑落死を遂げた。まだ35歳という若さだった。SNSや報道を通じてその訃報が流れた直後、ファンからは「夢をありがとう」「なぜ無理を?」といった哀悼や疑問の声が殺到した。一方、登山業界や批判的な層は「やはりこうなってしまった」というやるせない感情とともに、彼の姿勢に最後まで大きな疑問を抱いたままだった。
動画が残るのはすべて“撮影可能な局面”のみである。死に至る瞬間まで何があったのかは、いまもわからない。それでも彼の人生を丁寧に追いかけると「そうなる可能性を常にはらんだ危うさ」と「それでも挑戦に燃え続けた強烈なエネルギー」が同居していたことが見えてくる。
第4章:山が映す人間の本質
4-1. 何者として生きようとしたのか
元来、“登山家”とは純粋に山に登り、技術や経験、真摯な探究心によって成果を上げる職業とも言える。しかし、彼が重視したのは「ビジネスとしての冒険」であり、加えて「観客に見せるエンターテイメント要素」だった。最初は注目を集めたい、資金を得たいという動機が見え隠れしても、挑戦を重ねるうちに自分自身を“商品”としてプレゼンすることに慣れ、次第にそれを生きがいとするようになっていった。周囲がどれほど苦言を呈しても、単純に山をやめるわけにはいかなかったのである。
そもそも山頂に到達できるか否かの結果以上に、そこに行くまでの「物語」こそが商品化される――彼はそれを誰よりも早く理解し、活用した。それが世間の心を掴み、同時に彼への不信感や反発も増幅させていった。この二面性こそが、「山を劇場に変えた男」を語るときに欠かせない視点となる。
4-2. 遭難者の遺体が突きつける真実
マナスルで出会った「ジャパニーズ・ガール」(実はスロバキア人男性)に代表されるように、ヒマラヤには多くの遺体が残される。運び下ろすことが不可能なほどの荒天、高所環境の過酷さ――それは単に“冒険浪漫”に酔う登山家たちを現実に引き戻す。命がけの行為である以上、誰の身にも遭難の危険はある。
彼の死後、何度も議論になるのは「なぜ、そこまで厳しいルートを選んだのか?」という疑問だ。経験や技術を蓄えていたわけでもなかったが、“より過激なルート”こそが人々を魅了し、支援を得る材料になると考えた面は否めない。それは、まさしく“劇場”としての山に取り憑かれたようにも見える選択だった。
4-3. それでも残る「あの人は何者だったのか?」
故人となってしまった今、登頂記録や彼が残した映像だけが議論の材料として表面を漂う。実力不足を嘲笑う声もあれば、死の直前まで挑戦し続けた姿勢を尊敬する声もある。確かなのは、単純な“勇者”でもなければ“まがい物”でもない複雑さがあり、その行動力と発信力は同時代の多くの人々に衝撃を与えたということだ。
かつて本人がインタビューで「自分は強いわけじゃない。弱いからこそ挑みたいんだ」と語ったことがある。そこには、ただ無謀なだけの男ではなく、山に向き合う素朴な敬意があったのも事実だろう。広く批判されながらも支持者が絶えなかったのは、その人間臭さゆえかもしれない。
結び:挑戦が教えてくれるもの
人はなぜ山に登るのか。世界最高峰を目指す理由は何か。技術が未熟でも、周囲を巻き込んで挑戦を続ける動機はいったいどこにあるのか。“デス・ゾーン”という過酷な舞台に繰り返し立ち続けた姿は、単に英気あふれるヒーローか、あるいは虚像を追う愚か者か――評価は見る者の立ち位置によって大きく変わる。
だが一つだけ言えるのは、従来の「登山家」の枠組みを飛び越え、人生と事業を一体化した彼の生き方は、今後の冒険家や起業家たちに大きな問いを投げかけたことだ。山は確かに命を懸ける世界だが、それでも映像やメディアを通じた“物語”を多くの人に届けたことは、新しい価値の提示でもあった。
究極的に、山に関わる人が何を得て、何を失うかは当人にしかわからない。彼が最後まで「上を目指し続けた」その姿勢は、商業的・メディア的フィルターを差し引いても、私たちに「限界に挑む」という行為の光と闇を映し出している。だからこそ読む者・見る者に疑問と感動を残し、惜しみない拍手と厳しい非難の両方を浴びせられ続けるのだろう。
その残像が薄れないのは、単なる奇行の数々に終わらず、苦悩や矛盾を抱えつつも自分を鼓舞し、最後まで「自分を超える」という一点だけは譲らなかった姿勢にほかならない。それこそが「デス・ゾーン」における人間の本質を映し出す、一つの解答なのではないだろうか。