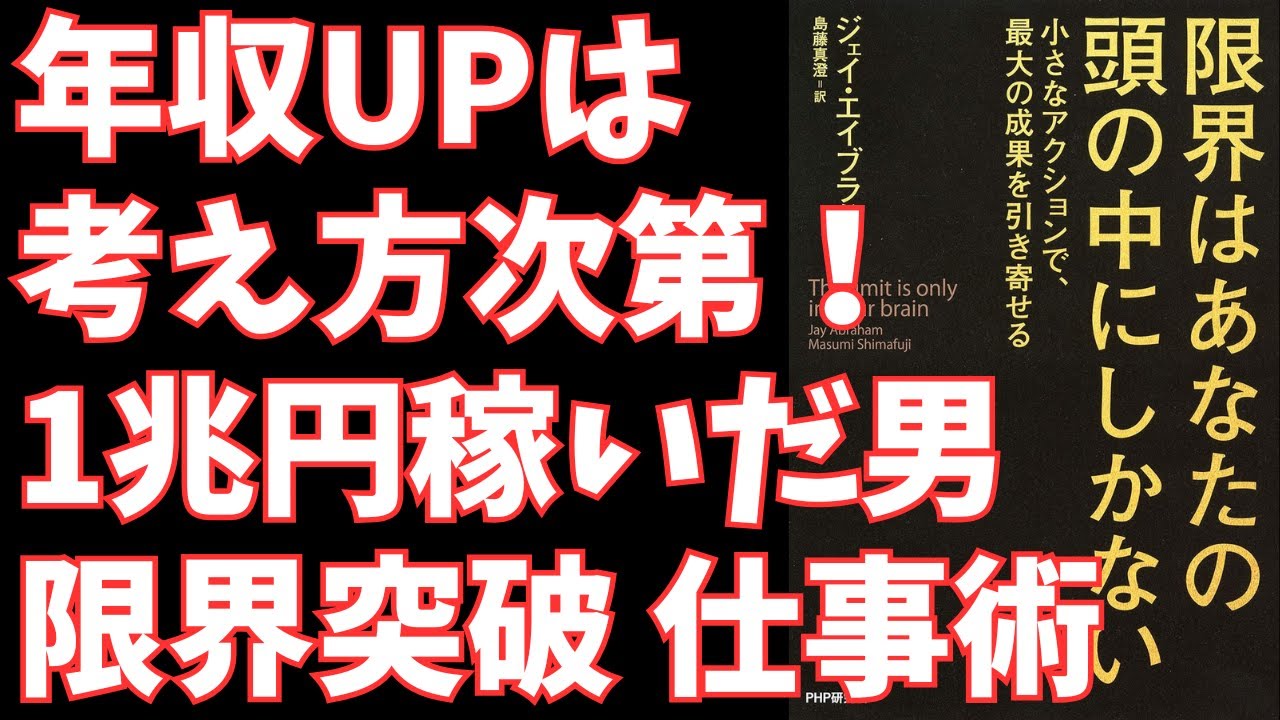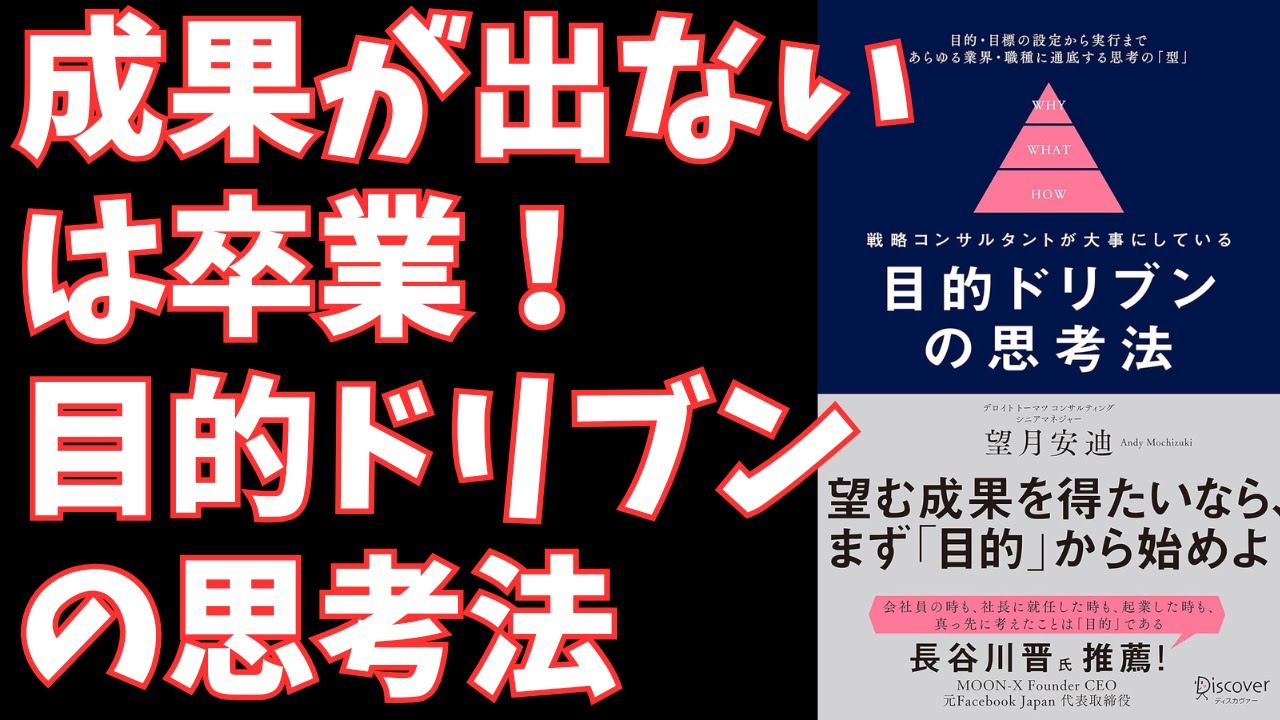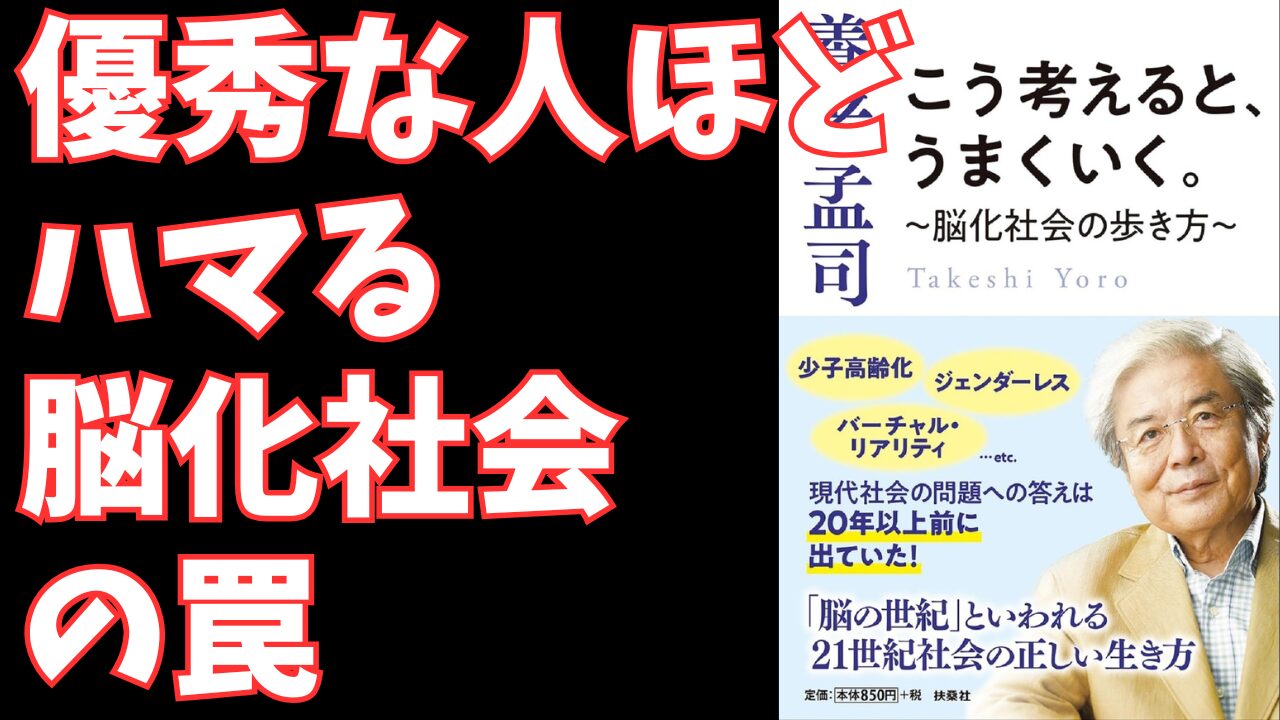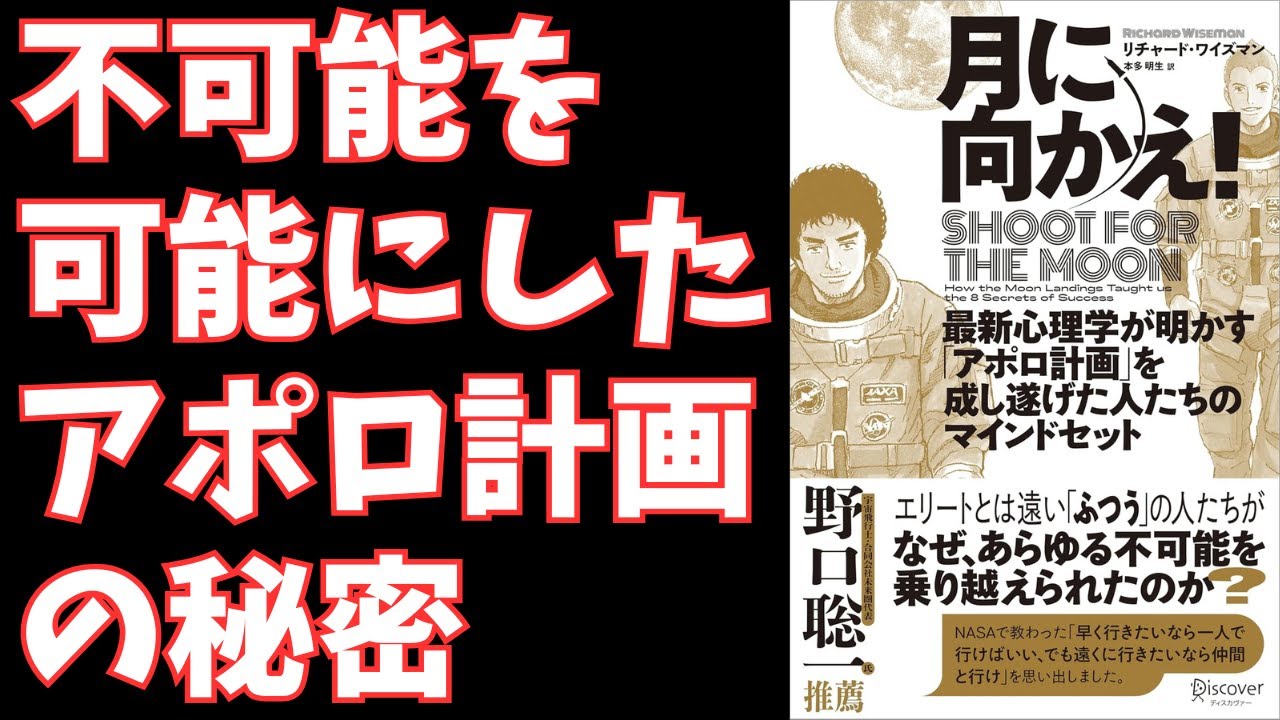仕事が終わらない」は卒業!【小さく分ける技術】で生産性を劇的向上させる方法|森本繁生『小さく分ければうまくいく』
森本繁生氏の著書『小さく分ければうまくいく』に基づき、仕事やタスクを「小さく分ける」ことの重要性と具体的な実践方法を、忙しいビジネスパーソン向けに解説します。多くの人が無意識のうちに行っている「大きくまとめる」ことの非効率性を、具体的な事例を通して浮き彫りにし、「小さく分ける」ことでいかに生産性が向上し、時間や心の余裕が生まれるかを示します。歯医者、製造業、IT企業、さらには市役所の災害対応まで、多岐にわたる事例を紹介。実践に伴う「不安」や「抵抗感」といった心理的な壁を乗り越えるための具体的なアプローチや、すぐに活用できる「小さく分けるための5つの法則」も提示し、読者が今日から実践できるヒントを提供します。
本書の要点
- 「大きくまとめる」は非効率: 仕事や課題を一気に片付けようとする「大きくまとめる」やり方は、一見効率的に見えても、実は多くの無駄や停滞を生み出している。
- 「小さく分ける」が鍵: 仕事、家事、プロジェクトなどを細かく分割し、一つずつ着実に進めることで、全体のスピードと質が向上し、精神的な負担も軽減される。
- ボトルネックの特定と対応:全体の流れを滞らせている「ボトルネック(制約条件)」を見つけ出し、そこに合わせた仕事の進め方(分割や投入タイミングの調整)をすることが極めて重要。
- 心理的抵抗への対処:「小さく分ける」ことへの不安や抵抗感は自然な反応。その感情を認識し、見える化・共有することで、前向きな行動へと繋げることができる。
- 個人から組織、社会へ:「小さく分ける」実践は、個人の生産性向上に留まらず、チームや組織全体の活性化、さらには持続可能な社会の実現にも貢献する可能性を秘めている。
はじめに:なぜ、あなたの仕事は終わらないのか?
「やるべきことが多すぎて、何から手をつければいいかわからない」
「毎日残業しているのに、仕事が一向に片付かない」
「仕事と家庭の両立がうまくいかず、常に時間に追われている」
多くのビジネスパーソンが、このような悩みを抱えています。高い目標を掲げ、一生懸命努力しているにも関わらず、なぜか行き詰まりを感じてしまう。その原因は、あなたの能力や努力不足にあるのではなく、仕事の進め方そのものにあるのかもしれません。
私たちは、無意識のうちに「効率的」だと思い込み、「大きくまとめて」物事を処理しようとする傾向があります。しかし、本書『小さく分ければうまくいく』の著者、森本繁生氏は、この「大きくまとめる」ことこそが、多くの問題を引き起こす罠なのだと指摘します。
多くの人が陥る「大きくまとめる」という罠
「まとめてやった方が効率がいい」「一気に片付けてしまいたい」——。こうした考えは、一見理にかなっているように思えます。しかし、本当にそうでしょうか?
キャベツ切りの実験が示す衝撃の事実
本書の序章で紹介されている「キャベツ切り」の実験は、この常識を覆す非常に示唆に富んだ事例です。
クイズ: あなたが八百屋さんの店長だとして、12個のキャベツを「切って、包んで、箱に入れる」作業を一人で行います。どちらの方法を選びますか?
- Aの方法: まず12個全部を半分に切る → 全部をラップで包む → 全部を箱に入れる
- Bの方法: 1個ずつ切って → ラップで包んで → 箱に入れる → これを12回繰り返す
直感的にはAの方法が効率的に思えませんか? しかし、広島のあるスーパーが実際に時間を計測したところ、Aの方法が8分20秒かかったのに対し、Bの方法は6分27秒と、Bの方が圧倒的に早かったのです。
多くの人が「まとめてやった方が効率的」という思い込みに囚われていますが、現実は逆でした。「小さく分ける」方が、結果的に早く、そしてスムーズに仕事が進むのです。
まとめ買い、一気呵成の仕事…日常に潜む非効率
この「大きくまとめる」罠は、キャベツ切りに限った話ではありません。私たちの身の回りにも溢れています。
- スーパーでのまとめ買い: 「お得だから」と大量に買い込んでも、使いきれずに腐らせてしまったり、冷蔵庫がパンパンになって管理が大変になったりしていませんか?
- 試験勉強の一夜漬け: 直前に一気に詰め込んでも、集中力が続かず、かえってミスを招いたり、体調を崩したりした経験はありませんか?
- 仕事の締め切り間際対応: 締め切りが近づくまで溜め込んで、焦って処理することで、ミスが増えたり、残業が常態化したりしていませんか?
- 製造業での大ロット生産: 「段取り替えの手間を省くため」と大量生産しても、過剰在庫を抱えたり、急な仕様変更に対応できなかったりしていませんか?
これらの例に共通するのは、「部分的な効率」にとらわれるあまり、「全体の目的」を見失っている点です。まとめ買いは「安く買うこと」が目的化し、本来の「必要なものを無駄なく使う」目的から離れています。仕事も「作業を早く終わらせること」に集中しすぎ、「質の高い成果を出す」「顧客に価値を届ける」といった本来の目的達成を妨げている可能性があります。
「小さく分ける」とは何か? 基本的な考え方
では、「小さく分ける」とは具体的にどういうことなのでしょうか? その根底にある重要な考え方を2つご紹介します。
ボトルネックを見つける:「流れ」を改善する第一歩
「ボトルネック」とは、文字通り「瓶の首」のこと。ペットボトルから水を出すとき、水の出る量は一番細い首の部分で決まりますよね。仕事や物事の流れも同じで、全体のスピードや成果は、最も滞りやすい部分(ボトルネック)によって制約を受けます。
居酒屋を例にとると、注文を取る人、ビールサーバー、厨房の調理能力、レジなど、様々な箇所がボトルネックになり得ます。どんなに席数が多くても、ビールサーバーが1台しかなく、注ぐ人が一人なら、お店全体の売上はそのボトルネックによって制限されます。
重要なのは、このボトルネックを意識することです。多くの人はボトルネックを無視して、その手前で仕事をどんどん「大きくまとめて」しまいがちです。大きな塊は、当然ボトルネックを通りにくく、結果として全体の流れを滞らせてしまいます。
逆に、仕事を「小さく分けて」ボトルネックをスムーズに通過できるようにすれば、全体の流れは格段に良くなります。トイレで大量の紙を一気に流すと詰まってしまいますが、適切な量に分けて流せば問題なく流れるのと同じ原理です。
「今、どこが一番詰まっているだろうか?」 この問いを持つことが、「小さく分ける」ための第一歩です。
待ち時間に注目する:隠れた時間泥棒を退治する
「小さく分ける」ことの真の威力は、「待ち時間」を劇的に削減できる点にあります。
私たちはつい「作業時間」そのものを短縮しようと努力しがちですが、実は仕事全体の時間の大半を占めているのは、作業と作業の間の「待ち時間」なのです。
本書によれば、世界最高レベルの効率性を誇るトヨタ自動車でさえ、部品の加工という実作業1時間に対して、約300時間もの「待ち時間(停滞時間)」が存在するといいます。部品の到着待ち、工程間の受け渡し待ちなど、様々な待ちが積み重なっているのです。
一般企業では、この待ち時間はさらに膨大になると考えられます。改善というとスキルアップによる作業時間の短縮に目が行きがちですが、作業スピードを2倍、3倍にするのは容易ではありません。しかし、待ち時間に着目すれば、改善の余地は遥かに大きいのです。
例えば、結婚式のウェルカムボードを制作していたあるデザイナーは、顧客とのデザイン確認のやり取りに時間がかかり、納期が1〜2ヶ月もかかっていました。顧客からの返信待ちがボトルネックとなっていたのです。そこで、漠然とした確認ではなく、「A案、B案、C案のうちどれがお好みですか?」といった具体的な選択肢を提示し、返信期限を設けるように「小さく分けた」ところ、顧客からの返信が格段に早くなり、納期を最短3日にまで短縮できたといいます。
「小さく分ける」ことで、工程間の滞留、確認待ち、承認待ちといった様々な「待ち時間」が削減され、仕事全体のスピードが劇的に向上するのです。
事例で学ぶ!ビジネスにおける「小さく分ける」実践法
「小さく分ける」考え方が、実際のビジネスシーンでどのように活かされ、驚くべき成果を生み出しているのか、本書に掲載されている豊富な事例の中からいくつかご紹介します。
事例1:歯医者さんの劇的改善 – 意外なボトルネック解消法
栃木県日光市にある沼尾デンタルクリニックでは、駐車場が常に満車で患者さんからクレームが出ている、という悩みを抱えていました。一見、診療そのものとは関係なさそうな「駐車場」が、実はクリニック全体の流れを滞らせるボトルネックだったのです。
従来は30分間隔で3〜4人の予約を入れていましたが、これでは来院時間が重なり、5台分の駐車場では足りなくなります。そこで、院長は予約の取り方を「小さく分け」、15分間隔で「2人、1人、2人、1人」というリズムに変更しました。
その結果、駐車場の混雑とクレームは解消。さらに、受付業務もスムーズになり、患者さん一人ひとりに丁寧な説明をする時間が生まれ、診療単価も向上。数百万円かかると見込んでいた駐車場増設も不要になったという、まさに一石三鳥の改善が実現しました。
事例2:社長がボトルネック? – 勇気ある宣言と権限移譲の効果
大阪府八尾市にある株式会社タカヨシジャパンの高島小百合社長は、研修中に「私がボトルネックです!」と宣言しました。パワフルで多くの仕事を抱える社長自身が、会社全体の仕事の流れを滞らせていることに気づいたのです。
社長は自身の仕事を棚卸しし、「本当に自分がやるべきか?」を見直しました。そして、カフェの運営を専任スタッフに任せるなど、仕事を「小さく分けて」信頼できる社員に段階的に移譲していきました。
すると、わずか1ヶ月で会社全体の雰囲気が変わり、社員の自主性が向上。社長にも余裕が生まれ、決算書にはっきりと黒字が現れるほどの成果が出たのです。ボトルネックが社長自身であるケースは、中小企業では決して珍しくありません。勇気を持って現状を認め、仕事を適切に「小さく分けて」手放すことが、組織全体の成長に繋がります。
事例3:製造業の常識を覆す – ロットサイズ縮小と値上げ戦略
タカヨシジャパンの工場では、マネージャーの松原さんが中心となり、製造業の常識を覆す改革が行われました。一度に生産するロットサイズを100本から40本へと大幅に縮小したのです。
段取り替えの回数が増えるため、一見非効率に思えますが、実際には作業場が整理され、作業者は集中力を維持しやすくなり、品質も安定しました。過剰な在庫を持つ必要がなくなり、キャッシュフローも改善されました。
さらに驚くべきは、外注先に対して「こちらから単価を上げる」提案をしたことです。誠意ある対応に感動した外注先は、優先的に仕事を引き受けてくれるようになり、材料の引き取りから納品まで一括で担ってくれるように。結果的にトータルコストの削減に繋がったのです。「コスト削減」という部分最適にとらわれず、全体最適の視点から「小さく分ける」(この場合はロットを小さくする、取引を分割する)ことで、Win-Winの関係を築き、大きな成果を生み出した好例です。
事例4:老舗石鹸工場のV字回復 – 目標・工程・仕事の入れ方を分ける
大阪府八尾市の木村石鹸株式会社では、コロナ禍という厳しい状況下で「小さく分ける」を徹底し、驚異的な業績改善を達成しました。
- 目標を小さく分ける: 経営者から新入社員まで、それぞれの立場での目標(利益、スキル獲得、技術継承など)を書き出し、「すべてできればいいよね」と統合することで、全員が目指す方向性を明確にしました。
- 業務工程を小さく分ける: 製造工程を細分化し、「シュリンク(フィルム包装)」工程がボトルネックであること、そして「そもそも箱詰めするなら不要では?」という気づきを得て、この工程自体を廃止。人員配置の最適化と設備投資(1500万円)の抑制に成功しました。
- 仕事の入れ方を小さく分ける: 営業が大量に受注するのではなく、製造のボトルネック(充填工程)が詰まらないように、利益率の高い自社ブランド商品を優先し、小さな塊で順番に製造指示を入れるように変更しました。
これらの結果、売上は前年比1億円増でありながら、売上総利益(粗利)は1億5000万円増という、常識外れの成果を達成しました。これは、利益率の高い自社ブランド商品の比率が大幅に向上したためです。「小さく分ける」を多角的に適用することで、劇的な改善が実現できることを示しています。
事例5:有名日本酒メーカーの秘密 – 徹底的な小分けが生む多大なメリット
人気日本酒「獺祭」を製造する旭酒造(現:株式会社獺祭)は、「小さく分ける」を徹底している企業としても知られています。
- 一年中製造: 従来の「寒造り」にとらわれず、温度管理されたビル内で一年中製造することで、冬にまとめて造るのではなく、生産を平準化(小さく分ける)しています。
- 小さなタンク: 大きなタンク数個ではなく、小さなタンクを多数(約300本)使用。これにより、少量ずつ常に出荷でき、酒屋さんの仕入れ負担を軽減。万が一、汚染などのトラブルが発生した場合のリスクも最小限に抑えられます。
この「小さく分ける」アプローチは、自社だけでなく、取引先(酒販店、ラベル印刷会社など)にとってもメリットがあり、サプライチェーン全体での効率化と安定化に貢献しています。
「小さく分ける」を阻む3つの壁と乗り越え方
「小さく分ける」ことの有効性は理解できても、いざ実践しようとすると、心理的な抵抗を感じることがあります。本書では、その代表的な壁と乗り越え方についても解説されています。
壁1:「不安」との向き合い方 – 見える化と共有が鍵
「本当にうまくいくのだろうか?」「失敗したらどうしよう…」「周りから反対されるのではないか?」
新しいことを始める際には、不安がつきものです。特に、従来のやり方を変えることには大きな抵抗を感じるでしょう。
この不安に対処する第一歩は、不安を「見える化」することです。感じている不安を具体的に書き出してみましょう。付箋やノートに書き出すだけでも、頭の中で漠然としていた不安が整理され、「これなら対処できるかも」と思えることがあります。
さらに効果的なのは、チームで不安を共有することです。「実はこんなことが心配で…」と打ち明けることで、「それは大丈夫だよ」「こうすれば解決できるんじゃない?」といった具体的な対策や、精神的なサポートが得られやすくなります。兵庫県のあるケーキ屋さんでは、スタッフ全員で不安を書き出し共有することで、「6個セットの焼き菓子」という売れ残りの原因となっていたボトルネックを特定し、「4個セット+季節限定品」という新たな人気商品を生み出すことに成功しました。
壁2:「高くつく」という思い込み – 全体最適の視点を持つ
「小さく分けたら、手間が増えてコストが上がるんじゃないか?」
これは非常によく聞かれる懸念です。確かに、ロットサイズを小さくすれば段取り替えの回数が増えたり、少量で仕入れれば単価が上がったりすることはあります。
しかし、ここで重要なのは「全体最適」の視点です。目の前のコスト(部分最適)だけにとらわれるのではなく、その判断が全体にどのような影響を与えるかを考える必要があります。
- 機会損失: 小ロット生産で単価が上がっても、売れ筋商品の欠品を防ぎ、販売機会を最大化できれば、トータルでの利益は増えるかもしれません。
- 在庫リスク: 大量仕入れで単価が安くても、売れ残って廃棄したり、保管コストがかさんだりすれば、結果的に高くつく可能性があります。
- 資金繰り: 小分けに仕入れることで、一度に大きな支払いをする必要がなくなり、キャッシュフローが改善されるメリットもあります。
- 品質・鮮度: 小さく分けて生産・仕入れすることで、品質管理がしやすくなったり、商品の鮮度を保てたりする価値も見逃せません。
ビールの輸入業者が、コンテナ満載にこだわらず半分の量で輸入するようにしたところ、送料は割高になっても、鮮度向上や品切れ減少、資金繰り改善といったメリットがそれを上回り、結果的に業績が向上した例もあります。「小さく分けると高くつく」という思い込みを捨て、隠れたコストや見えない価値まで含めて判断することが重要です。
壁3:「何か嫌だ」未知への恐怖 – 疑似体験と感情のメッセージ
理屈ではわかっていても、「やったことがないから怖い」「なんとなく気が進まない」といった、漠然とした抵抗感を感じることもあります。
このような未知への恐怖に対しては、「疑似体験」が有効です。本書の著者も活用している経営シミュレーションゲームのように、安全な環境で「小さく分ける」ことを試してみるのです。実際に在庫が減ったり、納期が短縮されたりする体験を通して、「これならできるかもしれない」という自信が生まれます。
また、「何か嫌だ」という感情そのものにも、大切なメッセージが隠されている場合があります。「家族との時間が減るのが嫌だ」「部下の負担が増えるのが嫌だ」「創造的な時間がなくなるのが嫌だ」…。これらの感情は、あなたが無意識のうちに大切にしている価値観(ワークライフバランス、チームワーク、創造性など)を教えてくれています。
その価値観に気づくことができれば、「小さく分ける」を実践する上で、その価値観を守るための工夫(例:テスト導入から始める、振り返りの時間を確保する、役割分担を見直す)を盛り込むことができます。感情を無視するのではなく、そのメッセージを受け止め、より良い方法を見つけるヒントにするのです。
今すぐ実践!「小さく分ける」ための5つの法則
本書で解説されている「小さく分ける」ためのノウハウは、以下の5つの法則に集約できます。日々の仕事や生活の中で、ぜひ意識してみてください。
- 法則1:ボトルネックを見つける
- 仕事や作業の流れ全体を見渡し、最も詰まっている(遅い、溜まっている)箇所を特定する。
- 法則2:作業単位を適切なサイズに分割する
- 一度に処理する量を、無理なく、集中力を保って、品質を維持できる大きさに分ける。
- 法則3:仕事を入れるタイミングを工夫する
- ボトルネックが詰まらないように、一気に投入せず、適切なペースで順次仕事を流す。重要度や利益率の高いものから優先する。
- 法則4:目標を具体的に分解する
- 大きな目標を、達成可能な小さなステップ(中間目標、具体的な行動)に分割する。
- 法則5:心理的な抵抗感に向き合う
- 不安や恐れといった感情を認識し、見える化・共有する。その感情が伝えるメッセージに耳を傾ける。
これらの法則は独立しているのではなく、相互に関連しています。例えば、ボトルネックを見つけた上で(法則1)、そこをスムーズに通過できるように作業単位を分割し(法則2)、投入タイミングを調整する(法則3)といった具合です。
まとめ:「小さく分ける」ことで、あなたの仕事と未来が変わる
本書『小さく分ければうまくいく』が示すのは、複雑に見える問題も、シンプルに「小さく分ける」ことで解決の糸口が見えるということです。
「大きくまとめる」という長年の習慣や常識から抜け出し、「小さく分ける」ことを意識するだけで、あなたの仕事は驚くほどスムーズに進み始めるかもしれません。
- 生産性の向上: 無駄な待ち時間が減り、作業効率が上がる。
- 時間的・精神的余裕: 残業が減り、焦りやストレスから解放される。
- 品質の向上: 集中力を維持しやすくなり、ミスが減る。
- 変化への対応力: 小回りが利くようになり、急な変更にも柔軟に対応できる。
- 組織の活性化: ボトルネック解消や権限移譲が進み、チーム全体の力が引き出される。
そして、「小さく分ける」ことの効果は、個人の仕事や家庭に留まりません。泉大津市役所の災害対応事例のように、地域社会の課題解決にも繋がります。さらには、資源の無駄遣いを減らし、エネルギー消費を抑えることで、持続可能な社会の実現にも貢献する可能性を秘めています。
本書を読んで、「これならできそう」「試してみよう」と感じたことが一つでもあれば、ぜひ今日から実践してみてください。どんなに小さな一歩でも構いません。「小さく分ける」というシンプルな行動が、あなたの仕事、そして未来を、より良い方向へと導いてくれるはずです。