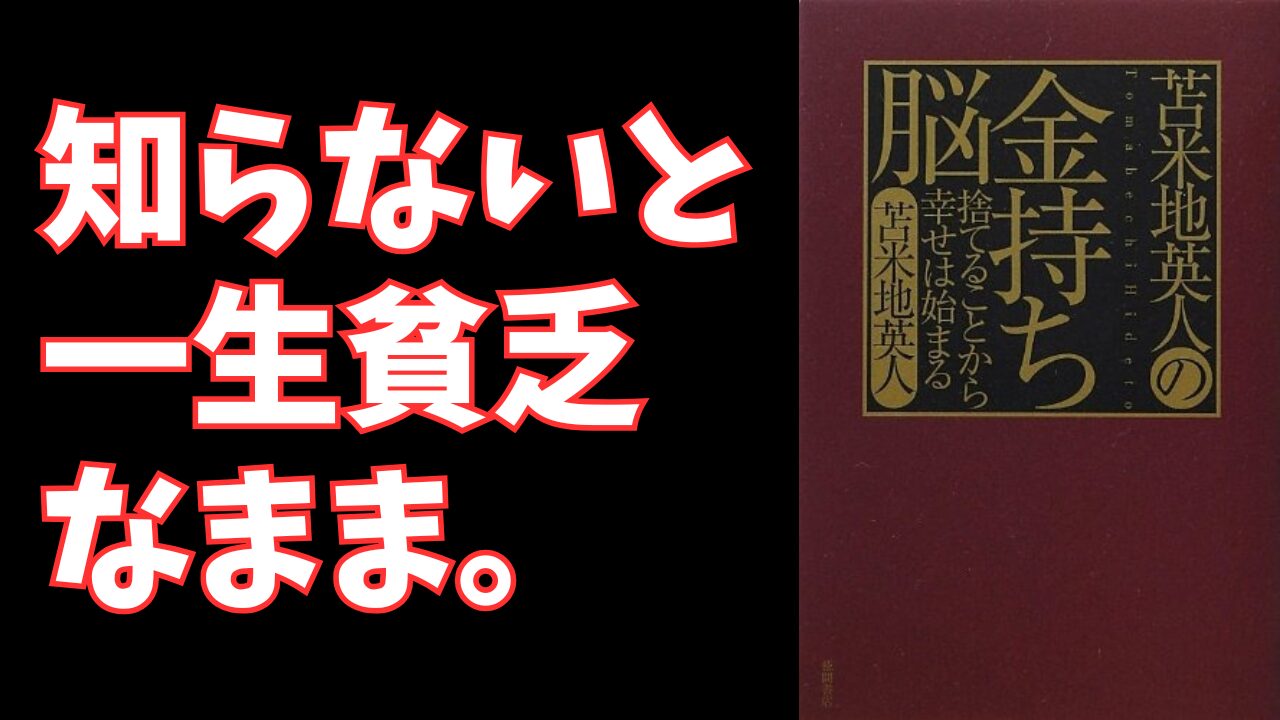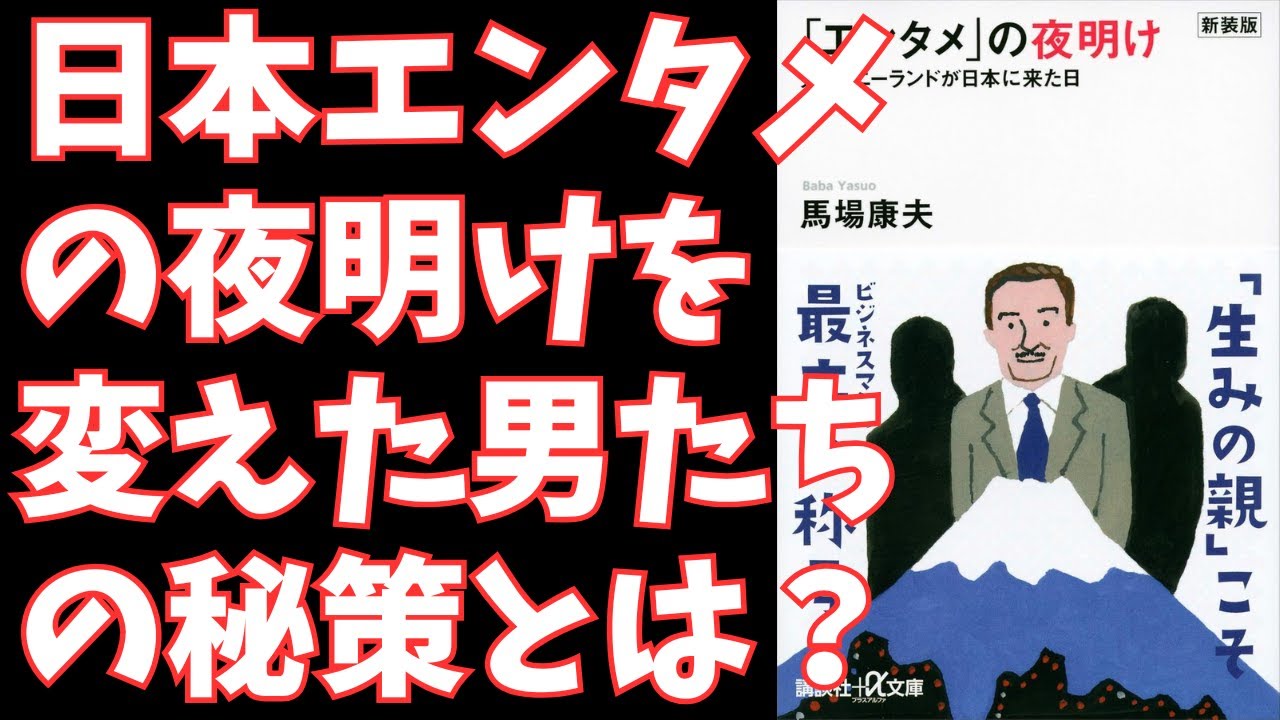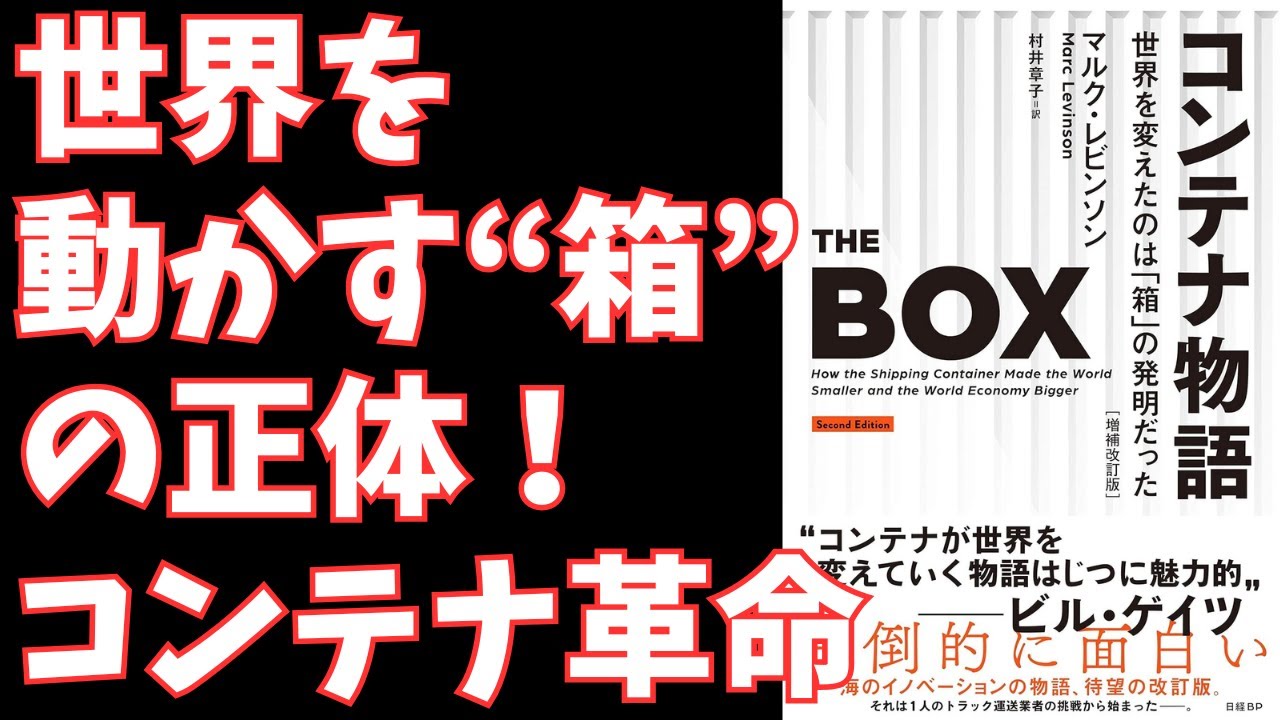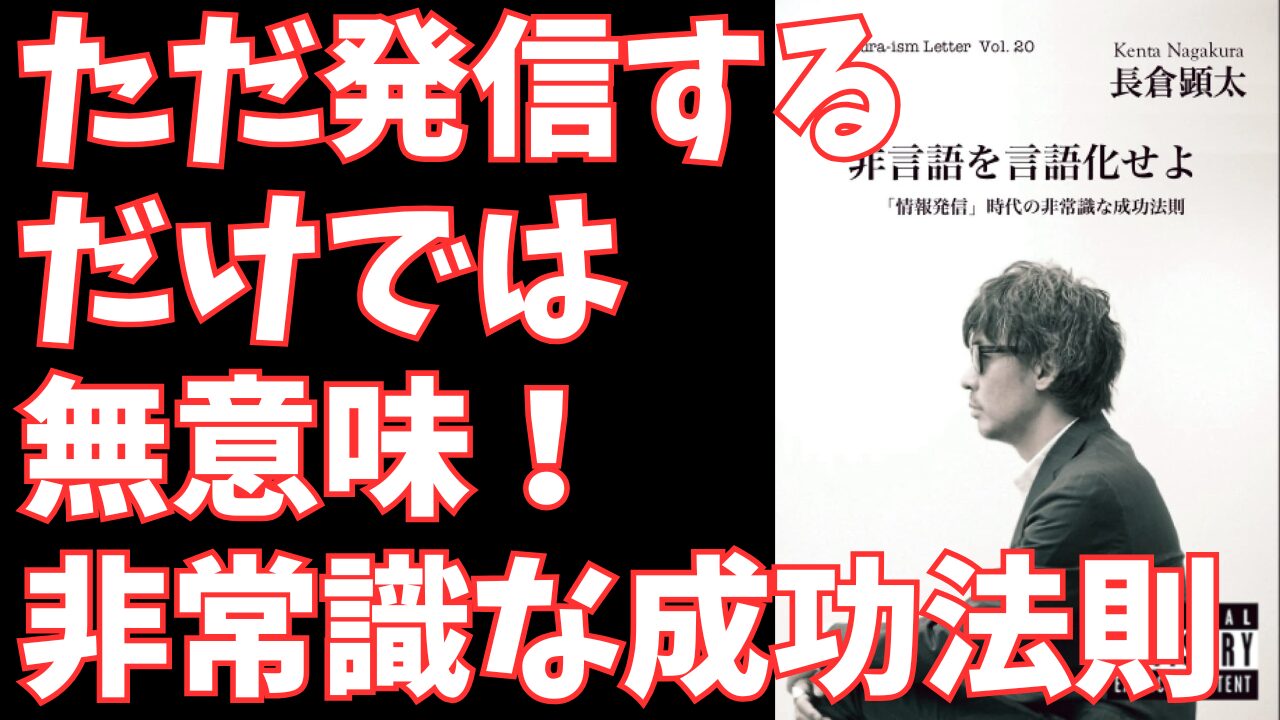未来が読める思考法「CAFSマトリックス」とは? 細谷功『フローとストック』をビジネスパーソン向けに徹底解説
「なぜ、会社は変われないのか?」「なぜ、理不尽なルールが残り続けるのか?」「なぜ、少し前までの常識が、ある日突然ひっくり返るのか?」
こうしたビジネスや社会における普遍的な問いに対し、本書『フローとストック 世界の先が読める「思考」と「知識」の法則』は、非常に明快な答えを提示します。
その鍵となるのが、「フローとストック」そして「具体と抽象」という2つの軸です。
本書は、これら2軸を組み合わせた新しい思考のフレームワーク「CAFS(キャフス)マトリックス」を提唱。このマトリックスを使うことで、世の中で起きている変化のメカニズムを構造的に理解し、次に何が起こるかを予測する「未来を読む思考法」を身につけることができます。
この記事では、本書の核心である「CAFSマトリックス」とは何か、そしてそれをビジネスや個人の思考にどう活かすのかを、書籍の具体例を交えながら徹底的に解説します。
本書の要点
- 世の中の事象は、変化や動きを示す「フロー(流れ)」と、その結果蓄積された状態を示す「ストック(蓄積)」に大別できます。
- 人間の思考は、五感で捉える「具体(見える世界)」と、概念や法則である「抽象(見えない世界)」の往復運動によって成り立っています。
- 本書独自のフレームワーク「CAFSマトリックス」(具体/抽象×フロー/ストック)は、これら2軸を組み合わせ、世の中の変化を4つの象限で構造的に説明します。
- 世界は「フローとしての具体」→「フローとしての抽象」→「ストックとしての抽象」→「ストックとしての具体」というサイクルで常に回り続けています。
- イノベーションや社会変革は、既存の「ストック(常識やルール)」と「現実(具体)」の間に生じる「歪み(ひずみ)」を解消するプロセスとして発生します。
はじめに:なぜ、あなたの会社は変われないのか?
「イノベーションのためには常識にとらわれてはいけない」と誰もが言うのに、多くの会社は旧態依然とした施策に固執してしまう。
「脱はんこ」が叫ばれても、なかなかハンコがなくならない。
「戦争は誰も望んでいない」はずなのに、なぜか戦争は繰り返される。
これらは一見バラバラな問題に見えますが、本書の著者・細谷功氏は、これらすべての問いに共通する構造的な法則が存在すると言います。
その構造を解き明かす鍵が、本書のタイトルにもなっている「フローとストック」と、人間の思考の根幹である「具体と抽象」です。
VUCA(変動性、不確実性、複雑性、曖昧性)の時代と言われる現代において、目の前の事象に振り回されるのではなく、その背後にあるメカニズムを理解することは、ビジネスパーソンにとって強力な武器となります。
まずは、この2つの基本的な「軸」から見ていきましょう。
第1章:「フロー」と「ストック」で世界を捉え直す
私たちは普段意識していませんが、世の中のほとんどの事象は「フロー」と「ストック」に大別できます。
- フロー (Flow): 「流れ」を意味します。水や人の流れ(目に見えるもの)だけでなく、お金や情報、時間の流れ(目に見えないもの)も含まれます。動きや変化そのものであり、「行為」(動詞)として表現されることが多いです。
- ストック (Stock): 「蓄積」を意味します。フローの結果として生じた状態であり、「状態」(名詞)として表現されます。
例えば、浴槽に水を貯める状況を考えてみてください。
蛇口から出る「流れる水」がフローであり、その結果、浴槽に「貯まった水」がストックです。
この関係は、あらゆるものに応用できます。
* お金:毎月の収入・支出(フロー)と、預金残高(ストック)
* 企業:入社・退社する人(フロー)と、従業員数(ストック)
* 勉強:日々の勉強(フロー)と、蓄積された知識(ストック)
* 信用:日々の他人とのやり取り(フロー)と、その人の信用(ストック)
ビジネスの世界では、この2つの違いは明確です。
企業の財務諸表で言えば、損益計算書(P/L)は一定期間の活動(フロー)を示し、貸借対照表(B/S)はある時点での蓄積(ストック)を示します。
ビジネスモデルにおいても、「売り切り型」の製品販売は「フロービジネス」であり、月額課金のサブスクリプションや、導入後のメンテナンスで収益を上げるのは「ストックビジネス」と呼ばれます。
「思考」はフロー、「知識」はストック
本書がユニークなのは、この「フローとストック」の概念を、人間の「頭の中」に適用する点です。
著者は、「思考」こそがフローであり、その思考の積み重ねによって蓄積された「知識」がストックであると定義します。
この定義に基づき、個人の思考回路を2つのタイプに分類します。
「フロー型思考」と「ストック型思考」
フロー型思考
* 重視するもの: 「イマ・ココ・コレ」。最新の情報や技術を使った合理性。
* 特徴: 変化に柔軟で、スピード重視。ゼロベースでの発想(ないものから考える)が得意。過去の経緯やしがらみを無視できる。いわば「攻め」の思考。
* イメージ: 即興型、あっさり(サラサラ)。
ストック型思考
* 重視するもの: 過去の経緯、伝統、しきたり、前例。
* 特徴: 変化を嫌い、安定を好む。過去の蓄積(あるものから考える)を最大限に活かそうとする。義理人情や絆(しがらみ)を大切にする。いわば「守り」の思考。
* イメージ: 用意周到型、ねっとり(ドロドロ)。
どちらが良い・悪いではありません。安定期には「ストック型」が強く、変化期には「フロー型」が活躍します。
本書で挙げられる「脱はんこ」の例は象徴的です。
コロナ禍でリモートワークが推進されても「脱はんこ」が進まなかったのは、多くの組織が「ストック型」だったからです。
「フロー型」の人は「デジタルの方が圧倒的に効率的で合理的」と考えますが、「ストック型」の人は「なんとなく、はんこがないと不安」という感情、すなわち過去から蓄積された「共同幻想」というストックを重視したのです。
また、イノベーターが「若者、馬鹿者、よそ者」と言われるのも、彼らが既存のしがらみ(ストック)を持たない「フロー型」だからこそ、新しい発想ができることを示しています。
第2章:「具体」と「抽象」なくして思考はできない
本書のもう一つの重要な軸が「具体と抽象」です。著者は、「考える」という行為の本質は、「具体」と「抽象」の往復運動であると断言します。
- 具体 (Concrete): 五感で感じられるもの。「目に見える世界」。個別の事象。犬、猫、リンゴなど。
- 抽象 (Abstract): 五感では感じられない概念。「目に見えない世界」。動物、果物など。
動物は「具体」の世界(目の前のエサ、敵)で生きていますが、人間は「抽象」の世界を扱えることで、まったく異なる社会を築いてきました。
人間社会の基礎となっている「数」「言葉」「お金」は、すべて抽象化の産物です。
「3」という数は、人間3人、猫3匹、椅子3脚という個別の具体から、「3つである」という共通の性質を抜き出した「抽象」です。
「抽象化」と「具体化」の往復運動
1. 抽象化(具体 → 抽象)
抽象化とは、複数の具体的なものから共通点を見出し、まとめることです。「馬」「犬」「猫」から「動物」という概念(パッケージ)を作ることです。
本書では、この抽象化の本質を「見えない線を引く」ことだと表現します。「動物であるもの」と「動物でないもの」を区別し、グルーピングすることです。
この「線引き」によって、私たちは世界を分類し、理解し、ルールを作ることができます。
2. 具体化(抽象 → 具体)
具体化とは、抽象的な概念(パッケージ)を、個別の事象に当てはめることです。「動物」という抽象的な知識を使って、目の前の「犬」の行動を理解することです。
私たちが「ルール」や「法律」(抽象)を守って社会生活を送れるのは、この具体化の能力があるからです。
ビジネスパーソンがよく「役に立たない」と揶揄する「教科書」や「理論」は、意図的に抽象度を高くして(パッケージングして)、あらゆる時代や場所で使えるように(汎用性を持たせて)あります。
それを自分の目の前の仕事という「具体」に適用(具体化)することこそが、「考える」ことの本質です。
第3章:最強の思考フレームワーク「CAFSマトリックス」とは?
ここからが本書の核心です。
第1章の「フローとストック」、第2章の「具体と抽象」。これら2つの軸を掛け合わせた、著者オリジナルのフレームワークが「CAFS(キャフス)マトリックス」です。
- 縦軸:具体 (C) ⇔ 抽象 (A)
- 横軸:フロー (F) ⇔ ストック (S)
この4象限マトリックスによって、世の中のあらゆる事象や変化のメカニズムが、驚くほどスッキリと説明できてしまいます。
四象限の解説
1. フローとしての具体(左下:C × F)
* ありのままの現実。
* 一切の解釈や「線引き」が入る前の、混沌とした状態。
* 私たちが五感で感じる、個別バラバラな生の事象すべて。
* すべての思考と変化のスタート地点です。
2. フローとしての抽象(左上:A × F)
* 個人の頭の中での試行錯誤。
* 「フローとしての具体」を観察し、「これはこういうことか?」「こう分類できるかも?」と考える、一時的なアイデアや仮説。
* まだ社会的に定着していない、揮発性メモリ(フロー)上の思考。
* イノベーターや科学者の頭の中は、この領域が活発に動いています。
3. ストックとしての抽象(右上:A × S)
* 固定化された抽象概念。
* 「フローとしての抽象」で生まれた仮説が検証され、社会に定着したもの。
* ルール、法律、常識、文法、企業のミッション、確立された理論など。
* 多くの人が無意識に共有している「共同幻想」とも言えます。これが「ストック」として固定化されているため、人々はこれを絶対のものと考えがちです。
4. ストックとしての具体(右下:C × S)
* 「常識」というフィルターを通して見た現実。
* 「ストックとしての抽象」(ルールや常識)という「見えない線」が引かれた状態で認識される現実。
* 「抽象つきの具体」とも言えます。
* 例えば、同じ人間の行動を見ても、「ストックとしての抽象(=道徳)」というフィルターを通して、「あれは善い行いだ」「あれは悪い行いだ」と無意識に判断している状態がこれにあたります。
* 多くの人が「ありのままの現実(=フローとしての具体)」だと思い込んでいる世界が、実はこの領域です。
「上向き」のフロー、「下向き」のストック
このマトリックスでさらに重要なのは、力の「向き」です。
- フローの世界(左半分)
- 現実(具体)を見て、そこから仮説(抽象)を生み出す。
- ベクトルは「上向き」(具体 → 抽象)。帰納的な思考です。
- ストックの世界(右半分)
- ルール(抽象)があり、それが現実(具体)を支配し、定義する。
- ベクトルは「下向き」(抽象 → 具体)。演繹的な思考です。
この「下向き」の力が、「既成概念」や「手段の目的化」を生み出します。
例えば、もともとは目的(フロー抽象)を達成するための「手段」だったはずの「予算」や「組織」が、一度固定化(ストック抽象)されると、それ自体を維持することが「目的」になってしまう(例:予算消化のための仕事、組織維持のための仕事)。これが「下向き」の力の作用です。
本書では、この「下向き」の発想の典型例として、以下の2つを挙げています。
- 仮想通貨は「通貨」か?「証券」か?
- 「仮想通貨」という新しい事象(フロー)に対し、「通貨」「証券」という既存の枠(ストック)に当てはめようとするのが「下向き」の発想です。
- 大谷翔平選手は「打者」か?「投手」か?
- 「二刀流」という新しい存在(フロー)に対し、「打者とはこうあるべき」「投手とはこうあるべき」という既存のルール(ストック)で議論しようとするのが「下向き」の発想です。
「フロー型」の発想(上向き)は、「仮想通貨は仮想通貨である」「大谷翔平は大谷翔平である」と、ありのまま(フロー具体)を捉え、そこから新しいルール(フロー抽象)を考えようとします。
第4章:CAFSマトリックスを「回す」ことで未来を読む
CAFSマトリックスは、静的な分類表ではありません。世界は常にこの4象限を時計回りに「サイクル」として回り続けています。この「回転」こそが、世の中の変化の正体です。
世界が変化する「4つのステップ」
ステップ1:フローとしての具体 → フローとしての抽象
* 【観察と仮説】
* 人々が「ありのままの現実(混沌)」を観察し、そこから何らかのパターンや法則を見出そうと試行錯誤します(抽象化)。
* 例:ドローンが自由に飛び交い、事故が起きる(フロー具体)→「危ないからルールが必要では?」と人々が考え始める(フロー抽象)。
ステップ2:フローとしての抽象 → ストックとしての抽象
* 【ルール化・常識化】
* 個人の頭の中にあった仮説が検証され、社会に共有され、定着します(ストック化)。
* 例:「ドローン規制法」というルールが制定され、社会の「常識」となる(ストック抽象)。
* ※この時、既存のストック(例:航空法)を持つ勢力からの抵抗が起こりがちです。
ステップ3:ストックとしての抽象 → ストックとしての具体
* 【ルールの適用】
* 定着したルールや常識(抽象)に基づき、人々が現実(具体)を解釈し、行動します。
* 例:「法律で禁止されているから、ここではドローンを飛ばさない」という行動が当たり前になる(ストック具体)。
ステップ4:ストックとしての具体 → フローとしての具体
* 【アンラーン(学びほぐし)】
* 時代が変わり、技術が進歩すると、ステップ3の世界に「歪み(ひずみ)」が生じます。
* イノベーターや「フロー型」の人は、この「歪み」に気づき、既存の常識(ストック)を疑い、「ありのままの現実(フロー具体)」をもう一度ゼロから見直そうとします(アンラーン)。
変化の原動力=「歪み」
なぜ、このサイクルは回り続けるのでしょうか?
その原動力こそが「歪み」です。
歪みとは、「ストックとしての抽象(ルールや常識)」と「現実(具体)」の間に生じるズレのことです。
ストック(ルール)は一度決まると固定化されますが、現実(具体)はフロー(流れ)であり、常に変化し続けます。このズレが時間とともに拡大し、無視できないレベルになった時、サイクルが次のステージへと回るのです。
- 技術による歪み:
- 生成AIが登場したのに、宿題は「自分で考えるもの」というルール(ストック)が残っている。
- スマートフォンが普及したのに、街のインフラは「前を向いて歩くもの」という前提(ストック)で作られている(=歩きスマホ問題)。
- 分類による歪み:
- アンケートの職業欄で、既存の分類(ストック)に当てはまらず、「その他」を選ぶ人が増えてくる。
- この「その他」が、次の時代の新しい職業(新しいストック)になっていきます。
イノベーションの本質とは、この「歪み」をいち早く察知し、既存のストック(常識やルール)をリセットして、新たな「フローとしての抽象(仮説)」を生み出すプロセスに他なりません。
この構造は、トーマス・クーンが『科学革命の構造』で提唱した「パラダイムシフト」とも一致します。
「通常科学(ストック)」がしばらく続くと、「アノマリー(歪み)」が発見され、それを説明するための新しい仮説(フロー抽象)が生まれ、「科学革命(サイクルの回転)」が起きて、新しいパラダイム(次のストック)が形成されるのです。
まとめ:あなたの「ストック」を疑うことから始めよう
本書が提示する「CAFSマトリックス」は、現代のビジネスパーソンにとって非常に強力な思考の武器となります。
VUCA時代とは、このCAFSマトリックスのサイクルが猛スピードで回転し、社会の至る所で「歪み」が発生している時代だと言い換えることができます。
私たちが「変われない」と感じる時、その原因はほぼ間違いなく、私たち自身が強力な「ストックとしての抽象」(=自社の常識、業界の慣習、過去の成功体験)に縛られ、その「下向き」の力に支配されているからです。
今、私たちに必要なのは、自分が無意識に依拠している「ストック」を自覚し、それを疑うことです。そして、意図的に「フローとしての具体」(=顧客の生の声、市場のありのままのデータ)に立ち返り、「上向き」のベクトルで思考を回し始めることです。
ジョン・レノンは『イマジン』で、「天国(と地獄)」「国家」「所有」がないと想像してごらん、と歌いました。本書の言葉で言えば、これらはすべて人類が作り上げてきた強力な「ストックとしての抽象」です。
彼は、その「ストック」をリセットし、「フローとしての具体」から世界を見直そう、と呼びかけたイノベーターだったのかもしれません。
まずはあなたの身の回りにある「歪み」—例えば、「技術は進んだのに、なぜこの業務プロセスは変わらないのか?」—を見つけることから始めてみてはいかがでしょうか。それこそが、未来を読む第一歩となるはずです。