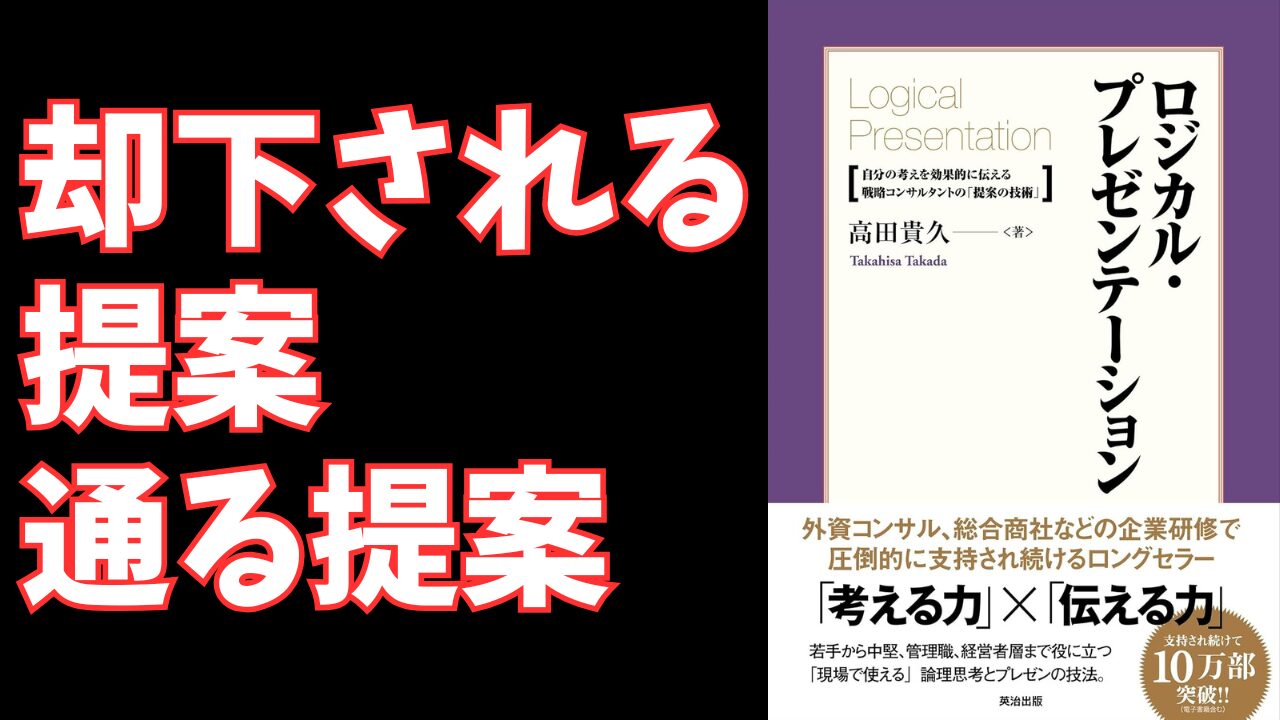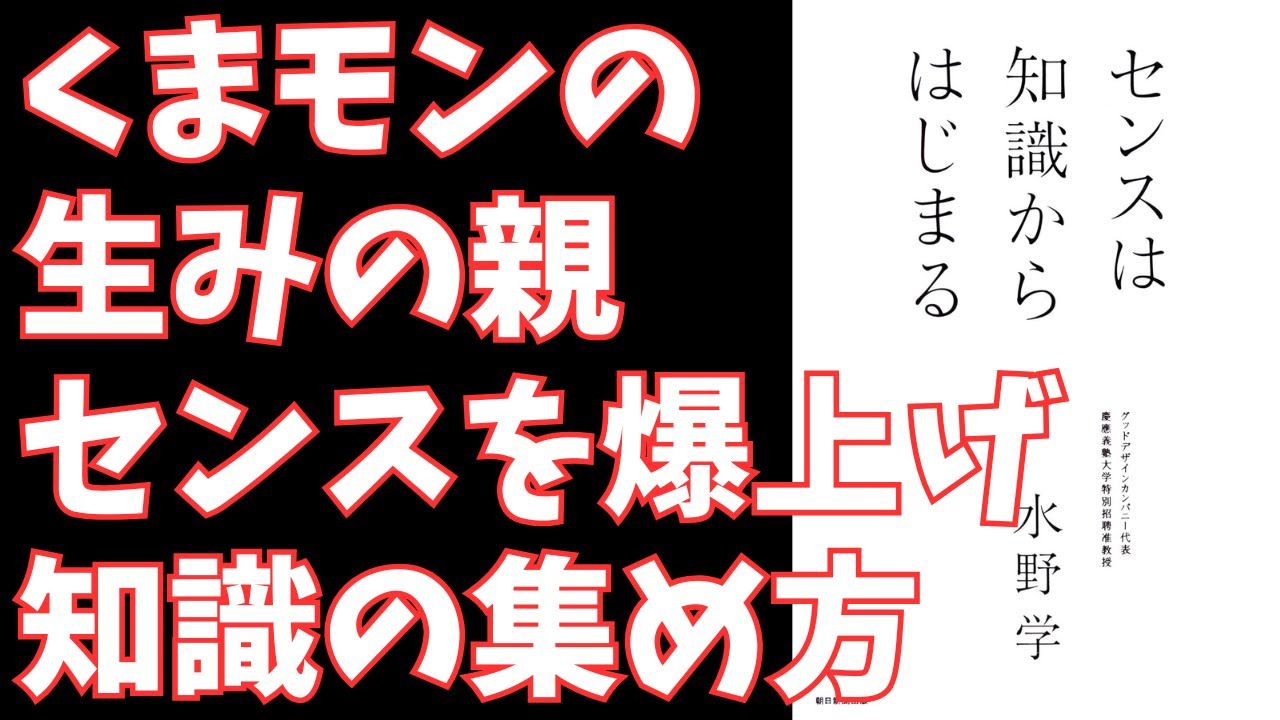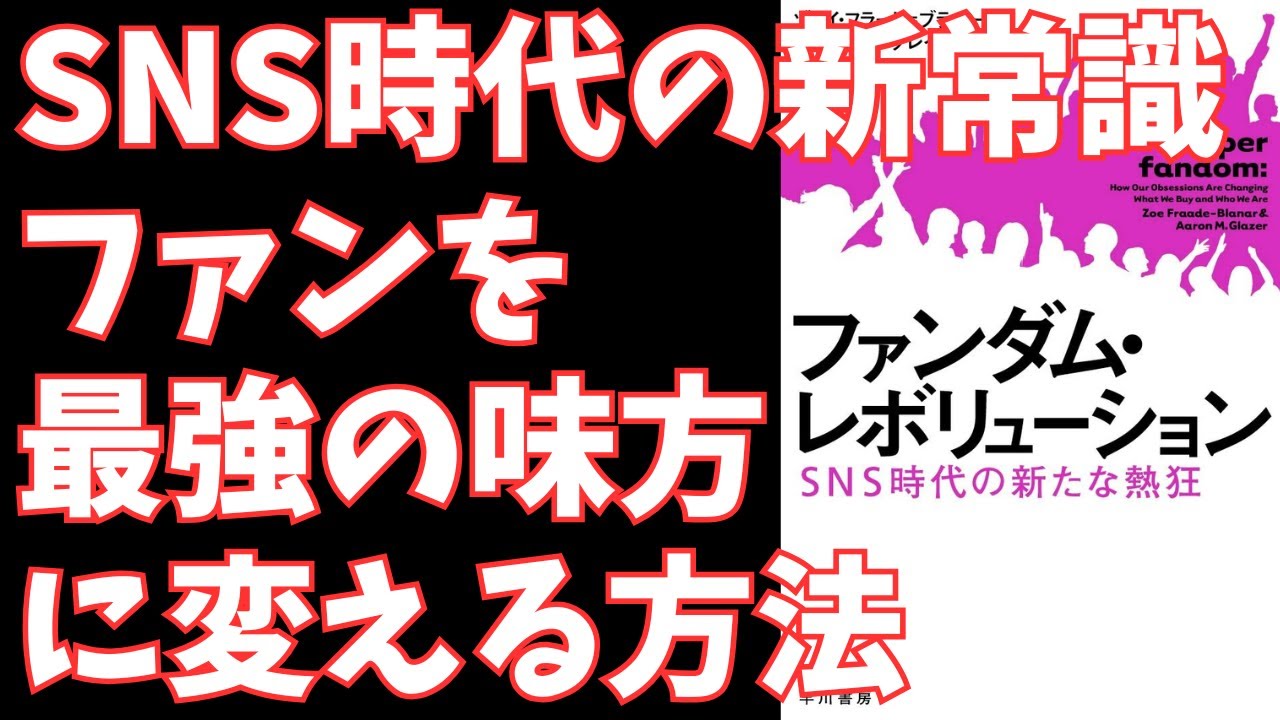GO WILDで人生を変える!現代を生き抜くための野生回帰メソッド
『GO WILD 野生の体を取り戻せ!』は、現代の生活様式がもたらすストレスや病気に対して、人類本来のライフスタイルを再発見することで解決の道を探る一冊です。著者ジョン・J・レイティとリチャード・マニングは、狩猟採集民の生活を例に挙げながら、人間が遺伝子レベルで備えてきた自己修復力を呼び起こすための具体的な方法を提案しています。その中でも特に、低炭水化物食やしなやかな運動、十分な睡眠、自然環境への接近やマインドフルネスの実践が重要なキーワードとして語られます。私たちが高度に文明化する過程で失ってきたものを見直し、意識的に取り戻すことで、より健康で満ち足りた人生を築くためのヒントが詰まっているのです。
野生を取り戻すための背景:文明病がもたらす苦しみ
私たちが普段何気なく過ごしている日常には、文明病と呼ばれる数多くの不調や病気が潜んでいます。肥満や2型糖尿病、高血圧、がん、うつ病などは、一見すると別々の問題に見えるかもしれません。しかし実は、狩猟採集民の時代にはほとんど見られなかった症状が、農業や都市化の進行とともに急増してきたという共通点があります。
著者たちは、それらの「現代病」の原因を高炭水化物中心の食事や身体活動不足、ストレスフルな生活リズムに求めています。本来、人間は身体を休めたり動かしたりしながら、多彩な栄養素を野生環境の中でバランス良く取り入れる生き物でした。しかし、農業の発展と定住生活による大量の穀物消費、急激な近代化によってストレスの質が変わり、私たちの身体には想定外の負担がかかっています。
狩猟採集民の暮らしとの比較
狩猟採集民のコミュニティは、農耕による安定的な食糧確保以前の人類のあり方を色濃く残しています。野生の果実や肉、魚、根菜などを必要な分だけ得る生活は、一日中デスクワークやスマホ操作ばかりに追われる私たちのライフスタイルとは対照的です。
調査によると、野生環境で暮らす狩猟採集民には、肥満やうつ病、心筋梗塞などが珍しく、多くの社会で恒常化しているストレス疾患も見られないと報告されています。そこには、現代人が置かれている環境が、いかに身体本来の設計とそぐわないかを示す明確なヒントがあるのです。
食事改革:炭水化物依存を断つ
炭水化物の摂りすぎがもたらす毒性
本書で強調されるのは、私たちの体が糖をうまく処理しきれなくなったときのリスクです。穀物やジャガイモなどのデンプン質は口に入れた瞬間からブドウ糖に変わり、血液中の糖濃度を急上昇させます。するとインスリンが大量分泌され、血糖値を下げようとします。
その過程が繰り返されすぎると、インスリン抵抗性が生まれて2型糖尿病の危険を高めたり、必要以上に脂肪を蓄積させて肥満を助長したりします。また、糖分を摂りすぎると免疫バランスが乱れやすくなり、自己免疫疾患や慢性炎症を引き起こす原因にもなります。
脂肪を怖がりすぎない
一時期は動物性脂肪やコレステロールを過度に敬遠し、バターよりもマーガリンを推奨する風潮が強くありました。ですが、最近の研究からは、工場的に加工されたトランス脂肪こそ心臓病や炎症を招くリスクが高いことが判明しつつあります。一方で、オメガ3脂肪酸を多く含む魚や牧草で育てられた動物性タンパク、ナッツ類などの脂肪はむしろ体の機能をサポートし、ホルモンや脳の健康維持に不可欠です。
「脂肪はすべて悪者ではない」という認識を持ち、甘いジュースやパン類よりも適切な脂質を選ぶことが、健康への第一歩なのです。
食物繊維と多様な栄養素の重要性
狩猟採集民は、さまざまな野草や果物、そして動物の肝臓や骨髄などの内臓も食べることで、多様なビタミンやミネラルを取り入れてきました。単一の主食を大量生産・大量摂取する農耕社会とは対照的に、元々の人類は食材のバリエーションを自然に確保していたのです。
特に現代社会では、炭水化物依存が根深いため、多彩な食材を心がけるだけでも栄養バランスを整える効果が期待できます。野菜や果物、肉・魚を中心にしながら、「適度な炭水化物+高品質な脂肪・タンパク質」の組み合わせを目指すことが推奨されます。
体を動かす:野生の動きが脳を高める
ランニングだけでなく多面的な動きを
人間は本来、ただ歩くためだけではなく、跳んだり投げたり登ったりと多彩な動作をこなせるように進化してきました。走ることは得意ですが、それだけに特化しているわけでもありません。体が持つ多機能性を活かすには、ウォーキングやランニングなどの有酸素運動に限らず、重量挙げやダンス、バランス運動、柔軟運動などを取り入れるのが望ましいのです。
脳と身体の密接なつながり
著者ジョン・J・レイティは脳科学の視点から、運動こそが脳の成長と精神状態の安定に大きな役割を果たすと指摘します。たとえばリズミカルなジョギングは、血流を促し脳内の神経ネットワークを活性化させるだけでなく、ストレス軽減や気分の改善にも寄与します。実際に、定期的に運動を行うことで落ち込みや不安が軽くなる例は数え切れません。
さらに、現代的な「ジムでの単調な筋トレ」だけに縛られず、外に出て自然と触れ合いながら走ったり歩いたりするほうが、人間の深い部分に組み込まれた生理的メリットを得やすいといいます。森や山道の不規則な地面を走ると、足裏からの刺激やバランス調整が脳をより複雑に動かすからです。
良質な睡眠:回復とリセットの鍵
狩猟採集民の生活を観察すると、昼間にエネルギッシュに活動した分、夜は家族や仲間で過ごしながら自然と睡眠に入りやすい環境を作っていることがわかります。一方、電気のある社会ではスマホやPC、夜勤などによって睡眠リズムが乱れやすいのが現状です。
睡眠不足が続くと、食欲をコントロールするホルモンバランスが崩れ、食べすぎによる体重増加や、気分障害、免疫力の低下などの問題が顕在化します。著者たちは、できるだけ自然光のリズムを意識し、寝る前の強い光や電子機器使用を控えるなど、シンプルな対策が効果的だと説いています。
マインドフルネス:野生の心に気づく
現代人のストレスと瞑想
情報過多で常に頭がフル回転しがちな現代人には、マインドフルネスや瞑想という行為が大きな助けになると著者たちは言います。これは宗教的な儀式でも、特殊なスピリチュアル体験でもなく、「いまここ」に集中する思考習慣の再学習です。
脳科学の研究では、マインドフルネスや瞑想の継続で脳の特定部位が変化し、ストレス耐性や感情制御能力が高まることが示されています。過去や未来の不安に引きずられず、自然と呼吸を合わせて今の身体感覚に焦点をあてることは、ストレスホルモンの減少や集中力の向上をもたらし、結果的に日常生活の質を高めます。
オキシトシンと共感の力
人が人をサポートし合うときに多く分泌されるホルモンにオキシトシンがあります。オキシトシンは人間の脳が社会的に協力し合うための鍵を握る物質ですが、ストレス環境が強すぎるとその働きが狂いやすい側面があります。
瞑想や深呼吸、安心できる仲間との触れ合いは、このオキシトシン分泌を促すとされ、著者たちは「人とのつながり」こそが野生の精神を取り戻すために不可欠だと強調しています。孤立していたり、インターネット越しのコミュニケーションばかりになると、この大切なホルモンの恩恵を受け損ねるというわけです。
バイオフィリア:自然との再結合
自然欠乏障害と脳
「自然欠乏障害」という言葉が取り上げられるように、私たちの脳や身体は本来、自然環境の中で最適に働くようデザインされています。公園や森などの景色を見るだけでもストレスが緩和されるという調査結果は数多く報告されています。
都市化やデジタル化が進むにつれ、私たちは自然との接点を意図的に持たなければすぐに失ってしまいます。しかし、野生環境での軽いウォーキングや森林浴は、自律神経のバランスを整え、コルチゾール(ストレスホルモン)を下げる作用があるともいわれています。
過酷さと喜びの境界
狩猟採集民や古くからアウトドア文化を持つ人々は、自然の厳しさや危険を含めて、それを「喜び」として捉えるマインドを育んできました。山道を必死で走り抜けるとき、私たちの五感は研ぎ澄まされ、周囲の音や気温、光の具合に敏感になります。
これは単にリラックスするだけでなく、心身に適度な負荷をかけることで体の回復力を引き出す効果をもたらします。危険から逃れるために走る狩猟採集民のように、自然環境で身を動かす行為は、ホルモンバランスや免疫力の向上にもつながると著者たちは説いています。
同族意識:人との絆が心身を守る
孤独化する現代社会
「同族意識トライブ」という言葉で、著者たちは現代人が失いつつある人間同士の強い結びつきを指摘します。狩猟採集民は協力がなければ生きていけない環境に身を置いており、自然と相互扶助と共感の精神を育んできました。
一方、都市に住む多くの人々は、隣人と顔を合わせる機会すらほとんどありません。オンライン上のつながりが増えたとはいえ、身体感覚を共有するような深いコミュニケーションは不足しがちです。このギャップこそが、私たちの不安や寂しさを増幅させ、メンタル面をも弱らせている原因だと考えられます。
ホルモンと集団の力
人間が集団の中で安心を得るとき、脳ではオキシトシンやエンドルフィンが分泌されます。これらは孤立した環境ではなかなか得られにくいホルモンです。
集団で同じリズムで動くダンスや合唱、スポーツ、あるいは祭りのような行事は、昔から心を一体化させる効果があると言われてきました。それは単なる気分の問題ではなく、ホルモンレベルで人同士を結びつけ、互いのストレスを和らげる科学的根拠があるのです。
野生の脳:心身をつなげるメカニズム
ホメオスタシスとアロスタシス
人間の身体には、ホメオスタシスという恒常性維持機能が備わっており、日々のストレスや消耗を乗り越えながらバランスを取り戻す働きをします。さらにアロスタシスという概念は、環境の変化に応じて身体の状態を変化させ、より高度な適応を目指す過程を示すものです。
著者たちは、農耕社会による定住生活以降、私たちのアロスタシスが歪みはじめ、無理な状態で生き続けていると警告します。炭水化物の過剰摂取や運動不足、睡眠障害など、現代社会特有の要因によって本来の回復能力が損なわれているというのです。
呼吸や瞑想で神経を整える
ストレスで急激に交感神経が高ぶると、呼吸が浅くなります。こうした緊張状態が長引くと、心拍数や血圧の上昇、ホルモンバランスの乱れが慢性化し、身体全体が慢性的な興奮モードに陥ります。そこに深い呼吸法やマインドフルネスを取り入れることで、副交感神経を優位にし、身体と心を穏やかな状態に導くことができます。
これは単なるリラクゼーションではなく、脳内の神経回路を調整し、免疫から代謝まで影響を与える総合的な回復システムを取り戻す行為なのです。
まとめ:野生の体を取り戻す処方箋
著者たちは、以下のようなライフスタイル変革を提案しています。
- 低炭水化物食を中心に、良質な脂肪とタンパク質を意識する
野菜や果物、牧草飼育の肉や魚、ナッツ類などを取り入れ、砂糖水や精製炭水化物を減らす。 - 多彩な運動を生活に組み込む
走るだけでなく、跳ぶ・投げる・登るなど多面的な動きを忘れずに。自然環境で体を動かす時間を意識的に確保する。 - 十分な睡眠を確保する
夜間の強い光源を避け、できる限り自然のリズムで就寝・起床する。睡眠の質を高める工夫を怠らない。 - マインドフルネスを実践する
日常の中で呼吸法や瞑想を取り入れ、「いまここ」に集中する時間を持つ。過剰な情報から意識的に離れる。 - 自然と再びつながる
森や海辺、公園を活用し、五感をフルに使って自然を味わう。アウトドア活動を趣味にするのもよい方法。 - 人との結びつきを大切にする
集団で行う運動や活動、家族や仲間との時間を重視し、オキシトシンが分泌されやすい相互コミュニケーションを増やす。
これらは決して特別な道具や極端な努力を必要とするものではなく、私たちのDNAに組み込まれた自然な働きを呼び覚ますためのステップです。一つひとつを実践することで、食事・運動・睡眠・心の状態が連鎖的に改善し、結果として人類に備わっている自己修復力を引き出せるのだと本書は説いています。
おわりに
文明社会の恩恵を否定するのではなく、その過剰な側面をコントロールしながら、祖先が長い年月をかけて育んできた野生の設計図に立ち返ること──それが『GO WILD 野生の体を取り戻せ!』の根本的なメッセージです。
忙しく、不規則なストレスにさらされている私たちにとって、自分の体や心に備わった自然な能力を正しく理解することは一種の冒険でもあります。農耕や都市化が進んだ道筋を知り、自らの生活を少しずつ「野生化」していく作業は、ちょっとした好奇心と工夫によって思いのほか充実した時間になるはずです。
本書に示された実践法は、単なる健康本の枠を超え、人間としての根源的な幸せを見つめ直す入り口となっています。体だけでなく心まで健やかに保つため、そして社会の中で他者としっかりつながっていくためにも、私たちが本来持っている野生の知恵を取り戻す旅をぜひ始めてみてください。