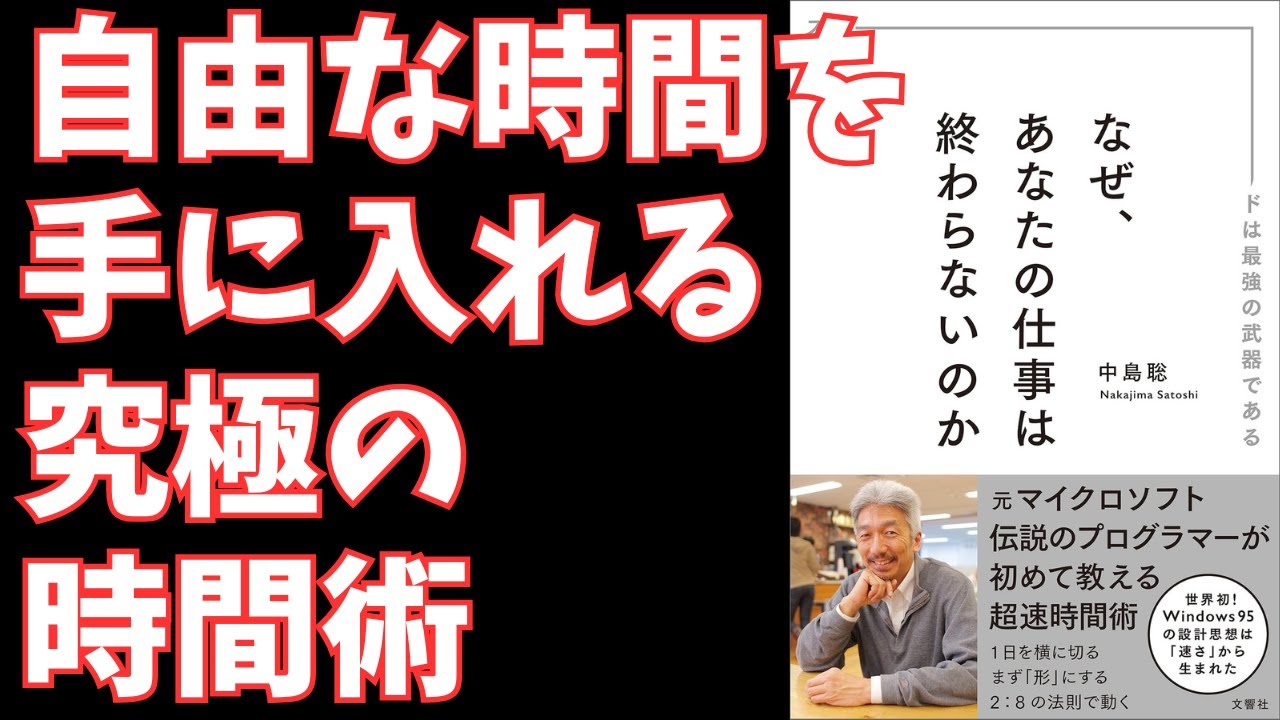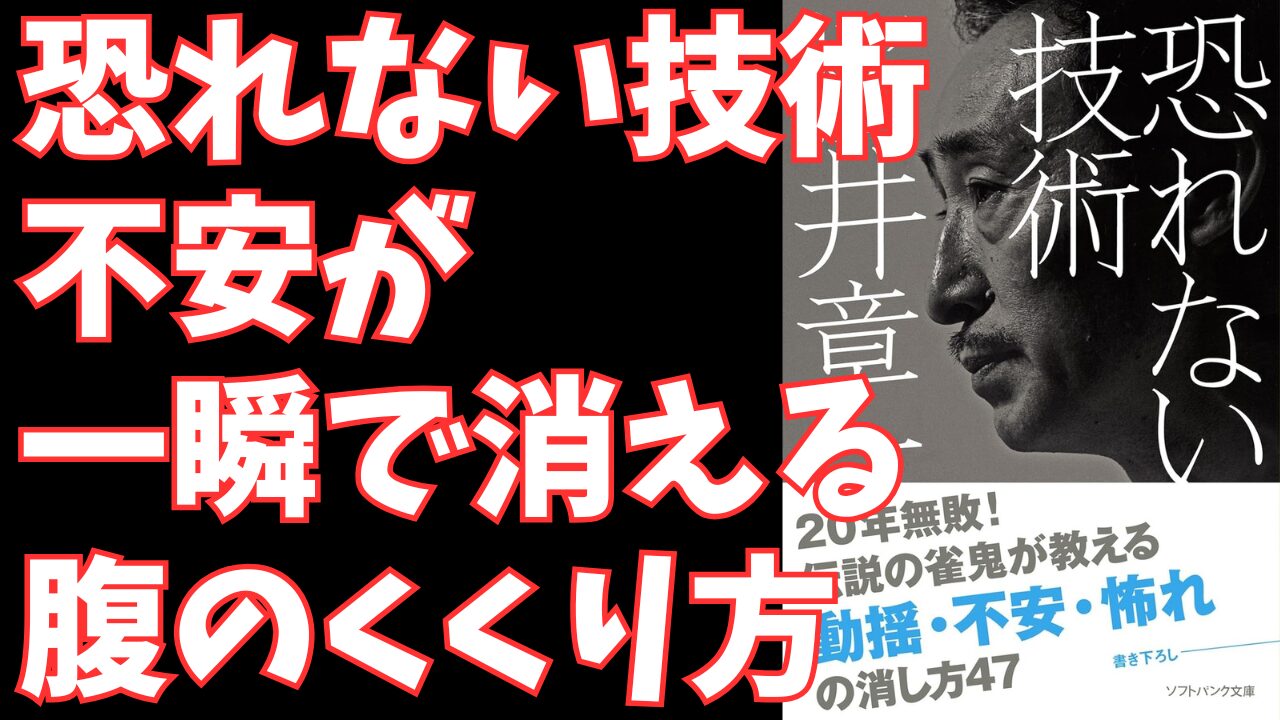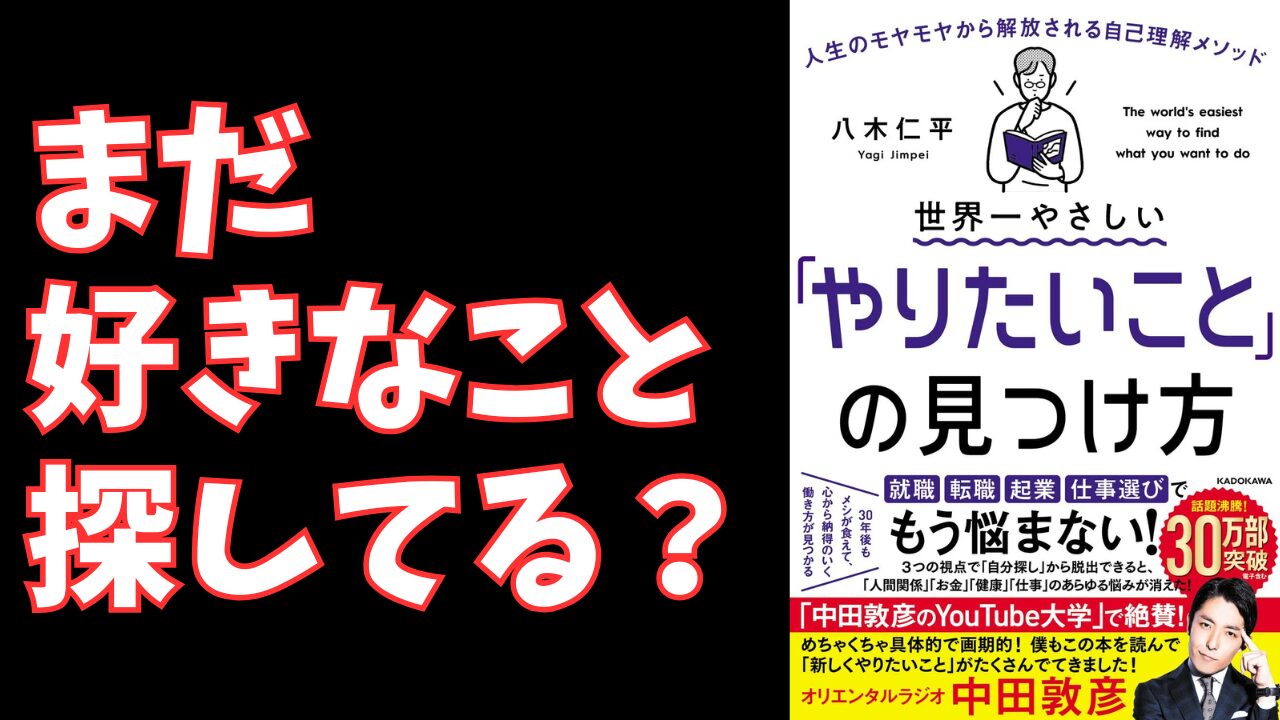ひろゆき『2035年最強の働き方』- 会社に縛られず、ラクに賢く生き抜くための思考法
本書『僕が若い人たちに伝えたい 2035年最強の働き方』は、著者のひろゆき氏が、これからの時代を生きる若い世代、そして変化の波に直面するすべてのビジネスパーソンに向けて、「いかにして幸せに、そして賢く働くか」というテーマを徹底的に掘り下げた一冊です。
「働くことは義務じゃない」「仕事で不幸になるならやめたほうがいい」という氏の哲学を基盤に、旧来の価値観や常識という「洗脳」から脱却し、人生の選択肢を増やすことの重要性を説きます。
日本の人口減少や経済停滞という厳しい未来予測を踏まえつつも、悲観論に終わるのではなく、「大卒資格」と「英語力」というコスパ最強の武器を手にし、さらには「海外」という広大なフィールドも視野に入れることで、「どんな状況になってもなんとかなる」という状態を目指すための、極めて実践的な戦略が語られています。
本書の要点
- 将来不安の解決策は「選択肢」を増やすこと。 社会がどう変わろうと、会社がどうなろうと、自分が幸せでいられる道を選べる状態こそが最強のセーフティネットです。
- 「大卒資格」と「英語力」は最強の武器。 これらは、国内でのキャリアはもちろん、海外という選択肢を現実的なものにするための、最もコストパフォーマンスに優れた自己投資です。
- 会社は「利用」するものと割り切る。 会社への過度な忠誠心は捨て、「ライスワーク(食べるための仕事)」と「ライフワーク(やりたいこと)」を区別し、いかに効率的に稼ぐかを追求することが重要です。
- 日本の常識に縛られず、世界に目を向ける。 日本の給与水準はもはや先進国とは言えません。海外での就労や移住は、もはや一部の特別な人のものではなく、誰にとっても現実的な選択肢となっています。
- 「開拓力」を身につける。 独学力、行動力、そして失敗を恐れない姿勢。この3つがあれば、どんな環境でも自分の道を切り拓き、生き抜いていくことができます。
はじめに:あなたの「働く」は、誰かのためのものになっていないか?
「働くことは、幸せになるための手段であるべきだ」
ひろゆき氏はこの本の中で、一貫してこのメッセージを投げかけます。しかし、多くの日本人は「働くために生きている」かのような状態に陥っていないでしょうか。
- 「人には働く義務がある」
- 「働かざる者、食うべからず」
- 「仕事にやりがいを感じなければならない」
こうした言葉は、まるで社会の常識のように私たちの周りにあふれています。しかし、ひろゆき氏はこれらを「日本人にかけられた洗脳」だと一刀両断します。 幼少期に団地で見た「働いていないけれど幸せそうな大人たち」の姿が、氏の仕事観の原点にあると言います。「人間は仕事をしていなくても、たくましく、幸せに生きられる」という気づきです。
本書は、このような凝り固まった価値観から私たちを解放し、「しんどくない稼ぎ方」を実践するための具体的なヒントに満ちています。この記事では、忙しいビジネスパーソンが明日から実践できる思考法や戦略を中心に、本書のエッセンスを深く掘り下げていきます。
第1章 時代遅れの「働き方の常識」を疑う
私たちは、知らず知らずのうちに古い働き方の価値観に縛られています。まずは、その「思い込み」から自由になることから始めましょう。
「人気就職先ランキング」を信じるな!ピークの会社は衰退するだけ
就職活動中の学生が参考にする「人気企業ランキング」。しかし、ひろゆき氏は「ランキング上位にある会社は現時点でピークにあって、これから衰退していく会社」と解釈できると指摘します。
なぜなら、ピークにある会社には「会社のブランド力で楽をしたい」「既得権益の甘い汁を吸いたい」と考える人材が集まりやすく、結果として組織が弱体化していくからです。 欧米企業のように成果の出ない社員を解雇できれば新陳代謝が図れますが、日本の企業は解雇規制が厳しく、一度入社した社員を守る傾向にあります。
本当に将来の安定を望むなら、選ぶべきは「これから伸びそうな業界・会社」です。それらは、まだ知名度が低く、ランキングには登場しないかもしれません。目先の人気やブランドイメージに惑わされず、10年後、20年後を見据えて自分の身を置く場所を選ぶ視点が不可欠です。
「就社」ではなく「就職」を意識せよ
日本の多くの企業が採用しているのは、新人を「総合職」として一括採用し、様々な部署を経験させる「メンバーシップ型雇用」です。これは、特定の「職(ジョブ)」に就くというより、会社という組織の一員になる「就社」と言えるでしょう。
この制度は、自分の適性がわからない若者にとっては様々な経験を積めるメリットがある一方で、自分のキャリアを会社の人事部に委ねてしまうという大きなデメリットも抱えています。優秀な人ほど、年功序列や意に沿わない異動に不満を感じやすい構造です。
これからの時代は、特定の職務内容を明確にして契約する「ジョブ型雇用」が主流になっていきます。
「自分のキャリアは自分でデザインしたい」「成果に見合った給与が欲しい」と考えるなら、特定のスキルを磨き、その道のプロフェッショナルを目指す「就職」の意識を持つことが、変化の時代を生き抜く鍵となります。
第2章 ひろゆき流「ラクして稼ぐ」の本質
「仕事は辛いもの」という前提を受け入れた上で、ひろゆき氏が提案するのは「いかにラクして稼ぐか」を追求することです。
「ライフワーク」と「ライスワーク」を切り離せ
「好きなことを仕事にしたい」と多くの人が願いますが、ひろゆき氏は、仕事に「やりがい」を求めすぎることの危険性を指摘します。 アニメーターのように、誰もがやりたがる仕事は給与が低くても人が集まるため、「やりがい搾取」の構造が生まれやすいのです。
そこで重要になるのが、「ライフワーク(人生をかけて成し遂げたいこと)」と「ライスワーク(食べていくための仕事)」を明確に分ける考え方です。
必ずしも両者を一致させる必要はありません。ライスワークは「楽しくはないけど、続けられそうだ」くらいの低い基準で、できるだけ効率的に稼げるものを選び、そこで得た時間とお金を自分のライフワークに注ぎ込む。この方が、多くの人にとって現実的で幸せな生き方ではないか、とひろゆき氏は問いかけます。
「ラクして稼ぐ」=「頭を使って効率化する」こと
「ラクして稼ぐ」と聞くと、ズルいことのように感じるかもしれません。しかし、ひろゆき氏の言う「ラク」とは、「効率的」であり「要領よく」という意味です。
- 会社の仕組みを理解し、最小の努力で評価される方法を探す。
- 同じ仕事でも、自分を高く評価してくれる市場で働く。
- 手間のかかる作業は、自動化やマニュアル化で二度とやらないようにする。
これらはすべて、頭を使わなければ実現できない「ラク」です。思考停止で「真面目にコツコツ」働くのではなく、常に「どうすればもっと効率的に、賢く稼げるか」を考えることこそが、資本主義社会を生き抜く本質だと氏は語ります。
第3章 日本の未来と「選択肢」の重要性
個人の努力だけではどうにもならない、マクロな視点も必要です。日本の未来を冷静に見据え、今から備えるべきことは何でしょうか。
避けられない「人口減少」と「経済の縮小」
日本の人口は2004年をピークに減少の一途をたどり、この流れは今後も加速します。 人口減少は、そのまま経済規模の縮小に直結します。市場が小さくなり、税収が減り、インフラや行政サービスの維持が困難になる未来が予測されます。
さらに深刻なのが「超高齢化」です。現役世代が高齢者を支える負担は増え続け、社会保障制度の維持はますます厳しくなります。 このような状況で、日本国内だけでキャリアを完結させようとすることは、沈みゆく船に乗り続けるようなものかもしれません。
「スキルが身につかない仕事」のリスク
将来の不確実性が高まる中で、いざという時に自分を守ってくれるのは「他社でも通用するスキル」です。
ひろゆき氏は、「刺身のパックにタンポポを置くような仕事」を例に挙げ、誰にでもできる、あるいはその会社でしか通用しない仕事に安住するリスクを警告します。 AIの進化は、単純作業だけでなく、これまで安泰とされてきた知的労働の領域にも及んでいます。
10年後、今の仕事がなくなった時に、自分には何が残るのか?常に自問自答し、ポータブルなスキルを意識的に身につけていく戦略が不可欠です。
第4章 最強の武器を手に入れろ!「大卒」と「英語力」
では、具体的にどんなスキルを身につければいいのか。ひろゆき氏が、数ある選択肢の中で「絶対に有利だ」と断言するのが「大卒資格」と「英語力」です。
なぜ今「大卒カード」が最強なのか
「大学不要論」を唱える人がいますが、それは学歴に頼らずとも自力で稼げる「強者の論理」だとひろゆき氏は看破します。 世の中の多くの凡人にとって、「大卒」という資格は、人生の選択肢を広げるための最もコスパのいいチケットなのです。
- 就職の選択肢が広がる: 未だに多くの企業や公務員の応募資格で「大卒以上」が求められるのが現実です。
- 海外への扉が開く: 先進国の多くでは、就労ビザの取得に大卒資格が必須条件となっています。
- ラクに取れる: 日本の大学は、入学してしまえば比較的容易に卒業できる構造になっています。厳しい言い方をすれば、多大な努力をせずとも「学士」という国際的に通用する資格が手に入ります。
たとえFラン大学であっても、専門学校卒や高卒とは比較にならないほど、キャリアの選択肢を広げてくれるのです。
「英語力」がもたらす圧倒的な機会と情報
AI翻訳技術の進化は目覚ましいですが、「英語の勉強は不要」と考えるのは早計です。自動翻訳は単なる「情報交換」には使えても、「信頼関係」の構築には不十分だからです。
英語を身につけることのメリットは計り知れません。
- 働く場所が世界に広がる: ワーキングホリデーでの出稼ぎブームが象徴するように、日本の数倍の給与を得られる求人が世界には無数にあります。英語力があれば、そうしたチャンスを掴みやすくなります。
- 国内でも市場価値が上がる: 「専門スキル × 英語力」という掛け算は、あなたを希少な人材にします。プログラマ、接客業、マーケターなど、どんな職種でも英語力は強力な武器となります。
- 得られる情報量が桁違いになる: インターネット上の情報の約半分は英語です。日本語のコンテンツ(約4.9%)とは比較になりません。最新の知識やスキルを学ぶ上で、英語で情報収集できる能力は圧倒的なアドバンテージになります。
第5章 日本脱出も視野に。「海外」という究極の選択肢
本書の最も刺激的な提案の一つが、「海外で働く、暮らす」という選択肢を本気で検討することです。
もはや海外移住は夢物語ではない
かつて海外移住は一部の富裕層やエリートのものでした。しかし、時代は大きく変わりました。
- デジタルノマドビザの普及: 世界の約半数の国が、リモートワーカー向けに長期滞在を許可するビザを導入しています。PC一台で稼げるスキルがあれば、世界中を旅しながら働くことが可能です。
- 多様な就労ビザ: 現地企業にスポンサーになってもらうだけでなく、寿司職人のように日本のスキルが引く手あまたの職種もあります。ひろゆき氏は「もしスキルがない状態から一発逆転を狙うなら、英語を学び、寿司職人になってアメリカに行く」と語るほどです。
- 教育移住という選択: 日本の画一的な教育を避け、子どもの個性を伸ばすために海外の教育環境を選ぶ親も増えています。
日本での生きづらさを感じているなら、あるいはもっと高い報酬や異なる価値観を求めるなら、「別に日本にこだわらなくてもよくない?」と視点を変えてみることが、突破口になるかもしれません。
海外で暮らすための心構え
ただし、海外生活はいいことばかりではありません。ひろゆき氏は、成功のコツとして「加点主義」でいることを勧めます。日本の高いサービスレベルや治安を基準にすると、海外では不満ばかりが目についてしまいます。「この国のいいところはどこだろう?」と良い面に目を向け、「悪いところは仕方ない」と受け流す柔軟さが大切です。
まずは旅行や短期留学でもいいので、一度外の世界を体験してみること。「こんなにゆるくても社会は回るんだ」という気づきが、あなたを日本の窮屈な価値観から解放してくれるはずです。
まとめ:自分を最優先に、ラクして賢く生きよう
ひろゆき氏が本書を通して伝えたいメッセージは、非常にシンプルです。
「自分が一番幸せになれるように、好きに生きるといいよ」
そのために、古い常識や他人の価値観に縛られるのではなく、常に「選択肢を増やす」ことを意識する。その最強の武器が「大卒資格」と「英語力」です。
会社に人生を捧げる時代は終わりました。会社はあくまで自分が幸せになるための「手段」として利用し、いかにラクをして効率的に稼ぎ、自分の好きなことに時間を使うかを追求する。もし日本が窮屈に感じたら、ためらわずに世界に飛び出してみる。
未来への不安は、行動することでしか解消できません。本書は、その最初の一歩を踏み出すための、強力な羅針盤となる一冊です。