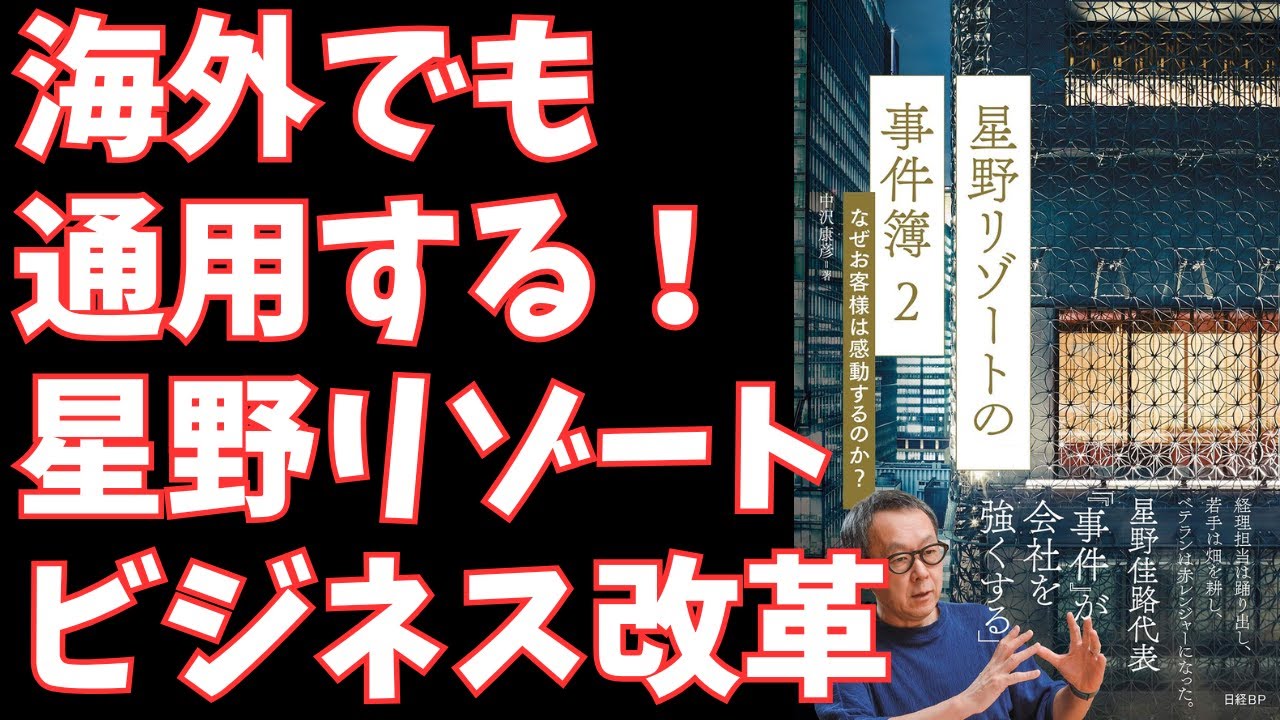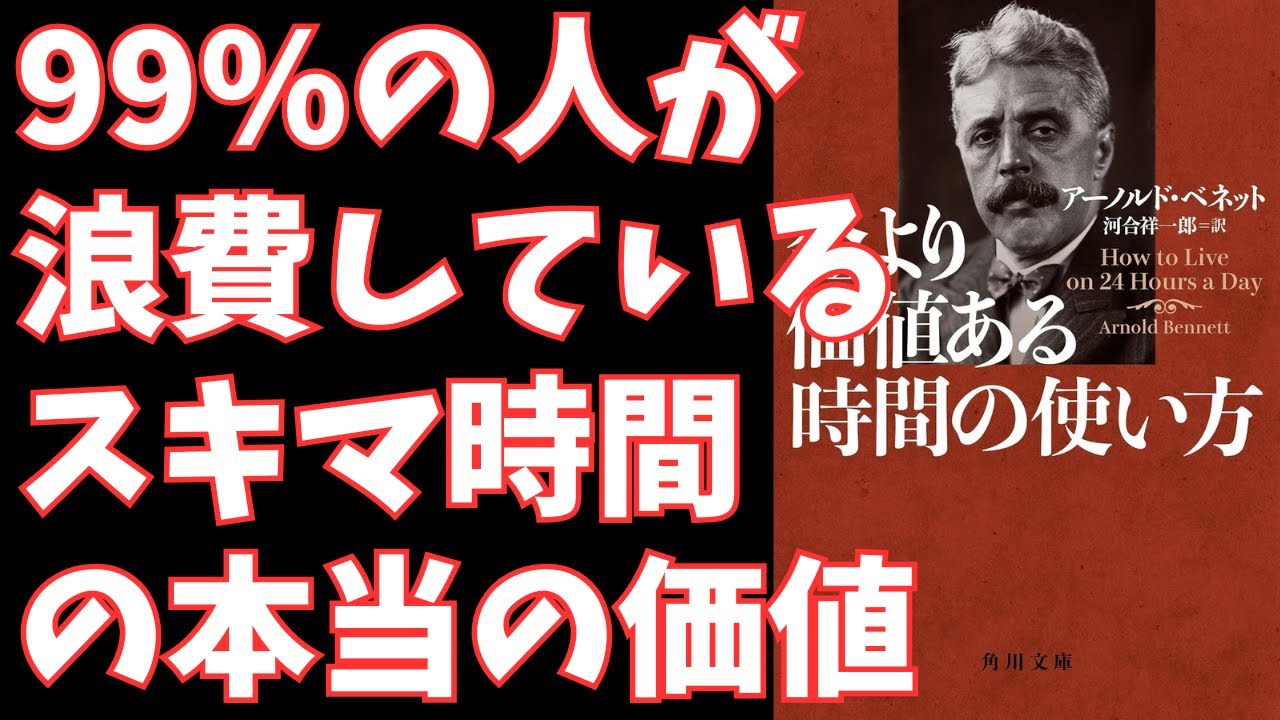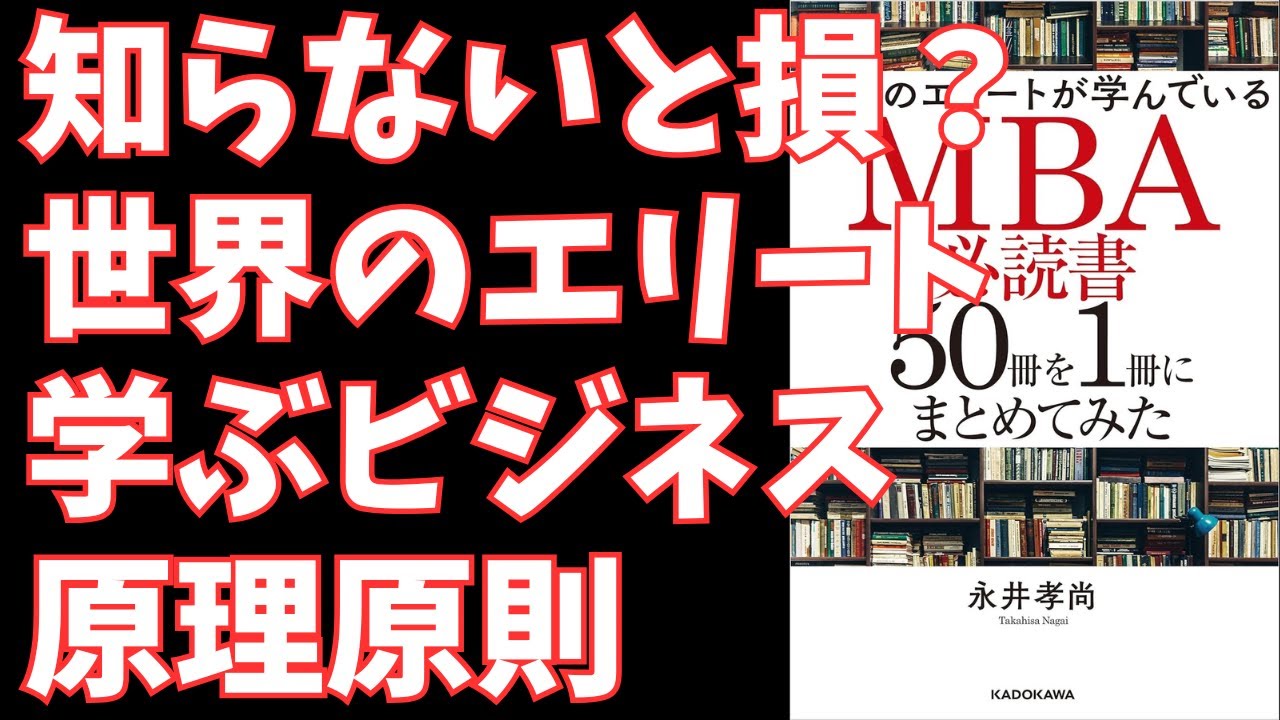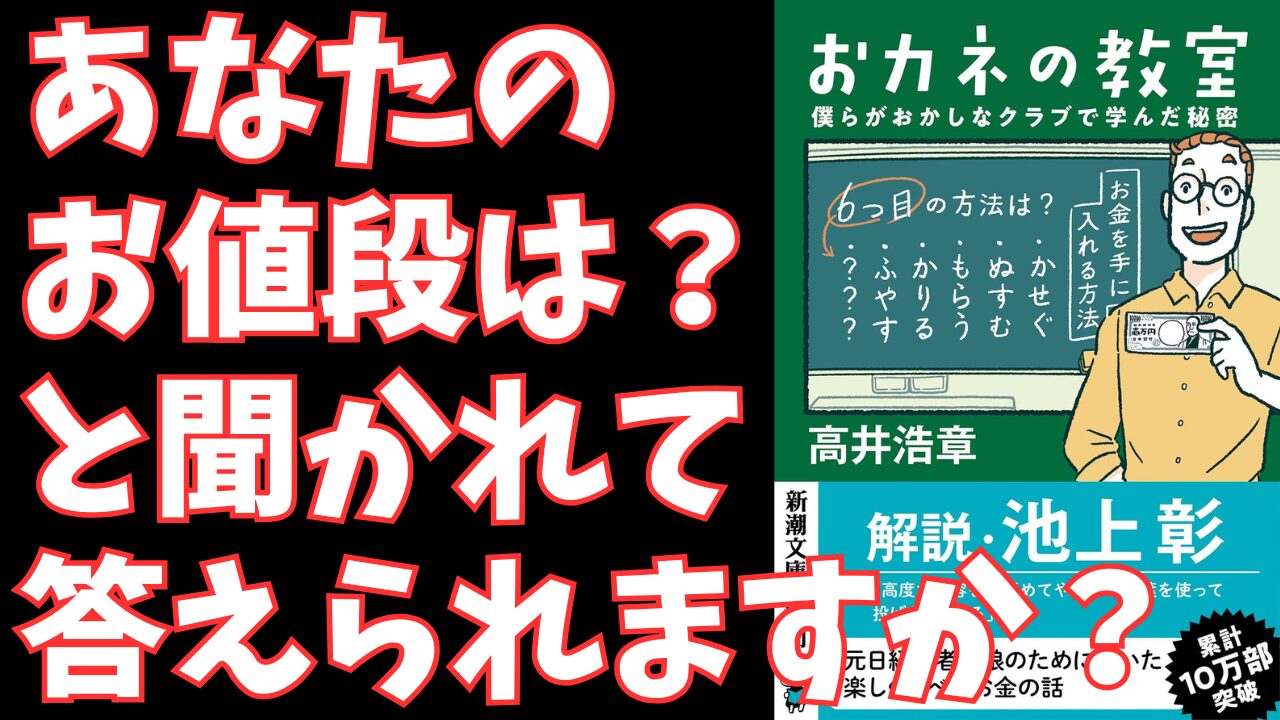仕事・勉強・AI活用の「勝ち筋」を見抜け。『誰でも”天才になる”方法』から学ぶ、ビジネスパーソンが成果を出す思考法と実践術
本書『誰でも”天才になる”方法』は、韓国での壮絶な虐待やいじめを乗り越え、16歳で東大に合格し、現在はAI博士・起業家として活躍するカリス氏による、「一発逆転思考」の教科書です。
本書の核心は、世の中の「勝ち組」と「負け組」を分けるものは、才能や環境以上に「自分で勝てる枠組みを築けるかどうか」という「要領の良さ」にある、という点です。
この記事では、忙しいビジネスパーソンの皆さまに向けて、本書で提唱されている思考法の中から、特に「仕事」「勉強」「AI活用」「自己改造」に焦点を当て、明日から実践できる具体的なノウハウを詳しく解説します。
本書の要点
- 負け組は他人の枠組みに従い、勝ち組は自分で勝てる枠組み(勝ち筋)を築きます。
- 仕事は「好きな仕事」ではなく「勝てる仕事」を選び、明確なゴールからの逆算思考で成果に集中します。
- 勉強は「作業」をやめ、「小さな目標達成」と「科学的に正しい勉強法」で自信と結果を手に入れます。
- 自己肯定感を高める鍵は「今を受け入れ、好きに生きる」こと。劣等感は克服せず、武器に変えます。
- AI時代には「常識人間」は淘汰されるため、ChatGPTを駆使し、自分だけの「異端」な価値を追求します。
なぜ今、私たちは「天才」になる必要があるのか?
「天才」と聞くと、生まれ持った特別な才能を持つ、自分とは縁遠い存在だと感じるかもしれません。しかし、本書の著者である東大AI博士カリス氏は、「誰でも“天才になる”方法は、必ずある」と断言します。
著者自身の経歴は壮絶です。韓国で生まれ育ち、父からの暴力や学校でのいじめに苦しむ日々。しかし彼は「一発逆転思考」を武器に、高校に進学せず16歳で東大に合格(※日韓理工系学部留学制度を利用)、日本政府から「天才認定」を受け、医療AI分野で若手日本一の研究業績を上げ、現在はカリスト株式会社のCEOを務めています。
彼が言う「天才になる方法」とは、「既存の枠組みに疑問を持たず従う『負け組』の思考を捨て、自らが勝てる枠組みを築く『勝ち組』の思考を持つこと」です。
彼はその好例として、メタルダンス・ユニットのBABYMETALを挙げています。彼女たちが世界で成功したのは、単に歌やダンスが上手いからではありません。「アイドルとメタルの融合」という独自の枠組みを築き、その中でオンリーワンかつナンバーワンになったからです。
AIが急速に進化し、これまでの「常識」や「当たり前」が通用しなくなる現代。私たちビジネスパーソンもまた、会社や社会が用意したレールの上を歩くだけでは、AIに代替される「常識人間」で終わってしまいます。
今こそ、自分だけの「勝ち筋」を見つけ、自分なりの「天才」になるための思考法と実践術が必要です。本書は、そのための具体的な羅針盤となる一冊です。
成果を出す思考法:「好き」より「勝ち」を選ぶ仕事術
ビジネスパーソンにとって最も多くの時間を費やす「仕事」。ここで成果を出せるかどうかは、「勝ち組」になるための重要な分岐点です。
1. 好きな仕事ではなく、「勝てる仕事」をする
著者は、「好きな仕事をする」という言葉に潜む「甘え」を厳しく指摘します。
「人々が仕事で幸福であるためには三つのことが必要だ。その仕事に向いていること。その仕事をやりすぎないこと。その仕事で成功すると感じていること」
──ジョン・ラスキン(英国の評論家・社会思想家)
大好きな仕事でも、負け続けて苦しめば嫌いになります。逆に、大嫌いな仕事でも、勝ち続けて周りから価値が認められ、高い報酬を得られれば、自然と仕事は面白くなると著者は言います。
著者自身もAI研究者ですが、「別にやりたい研究をしているわけではない」と語ります。「2~3年後に世に大きなインパクトを与えるような研究」を選び、毎回100回以上引用される論文を生み出すことに全力を注いでいます。その結果、高い評価を得て起業にも繋がりました。
「やりたいこと」ではなく、勝ち筋のある「やるべきこと」を見つけて全力投球する。これがプロフェッショナルの思考法です。
2. 「逆算思考」で時間を制圧する
成果を出すためには、闇雲な努力は無意味です。著者が徹底しているのは、ゴールから逆算する「逆算思考」です。
多くの人は「英語やらなきゃ」「会議に出なきゃ」と、やるべきことを「足し算」で考え、忙しさに忙殺されます。
しかし、できる人は「引き算(逆算)」で考えます。
1. 目標設定:明確な成功のイメージを創り上げます。
2. 現状把握:能力、リソース、残り時間といった現状を把握します。
3. 逆算:目標と現状のギャップから「絶対すべきこと」を見極め、それ以外を捨てます。
著者は時間を無駄にするのが大嫌いで、東大の授業も3割しか出ず、仕事を依頼されても3割しか引き受けなかったと言います。
3. 「不急だが、大切な仕事」に注力する
仕事は「緊急かつ大切」「不急だが大切」「緊急だが些細」「不急かつ些細」の4つに大別されます。
多くの人が「緊急かつ大切な仕事」(日々のオペレーション、クレーム対応など)に追われていますが、本当に人生を変えるのは、「不急だが大切な仕事」です。
- 読書
- 勉強、研修
- 中長期計画
- サイドプロジェクト
- 運動
これらは緊急ではありませんが、長期的に自分の可能性を広げるために不可欠です。「タイパ」が叫ばれる時代ですが、時間の使い方は「命の使い方」そのもの。著者は、自分の名前を冠した「カリスト株式会社」を創業したことに触れ、「一度きりの人生、どうせなら主役になったほうが良い」と説きます。
AI時代を勝ち抜く「異端」の仕事術:ChatGPTで生産性を高める
これからの時代、「常識人間」はAIに淘汰されます。著者は「労働集約的な『常識人間』が通用しなくなった現代では、行為そのものではなく意味を売る『異端』になるしかない」と強調します。
1. AIは「想いを具現化する道具」である
AIの本質は「データを活用して価値を創出し、人間の能力を拡張すること」です。特にChatGPTのような生成AIは、私たちの「想いや意志を具現化してくれる道具」です。
「これがやりたい」という明確な意志さえあれば、AIが労働を肩代わりしてくれます。つまり、AIありきの時代では、適切な問題設定と解釈ができる者(=意志の強い者)が勝つのです。
石器時代は石不足で終わったのではなく、鉄器に取って替わられました。変化をもたらすのは常に新しいテクノロジーです。
2. ChatGPT 業務活用術
著者は、ChatGPTの活用によって仕事の速さが5倍になり、質も大幅に向上すると述べ、自身の活用法を紹介しています。
- 企画・戦略:アイデア出し、評価項目・基準策定、競合分析。「こんな潜在顧客がいそうだけど、他にはどう?」と聞けば、アイデアを壁打ちできます。
- 文書作成・編集:メール文作成、議事録作成、プレゼン資料作成、文章添削。著者はメール返信文のドラフトは常にChatGPTに書かせているそうです。
- 情報処理・分析:作業自動化、情報収集、要約、データ分析。「こんなプログラムを書いて」と言えば、作業を自動化するPythonコードを一瞬で生成してくれます。
3. ハルシネーション(虚偽情報)の見抜き方
AIを使いこなすには、その限界も知らねばなりません。AIはもっともらしい嘘(ハルシネーション)をつくことがあります。
- 得意な領域:数学、英語、プログラミングなど、明確な解があり情報が豊富な領域。
- 苦手な領域:主観やニュアンスが重要な領域、複数の解が存在する領域、ウェブ上に情報が少ない領域。
頓珍漢な回答だと感じたら鵜呑みにせず、AIに指摘したり、原データを確認したりするリテラシーが求められます。
大人のための「科学的」勉強法:作業をやめて、自信をつける
ビジネスパーソンにとって「学び直し」は不可欠です。しかし、多くの人が非効率な「作業」で満足してしまっています。
1. 勉強の最重要ファクターは「自信」
著者は「勉強は『自分との戦い』だ。だから、勉強において最重要なのは『自信』である」と断言します。
著者の周りの東大生も、8割は「ごく平凡な人」であり、地頭が良いわけではないと言います。それでも彼らが常勝するのは、「勉強はして当たり前」「結果は出て当たり前」という圧倒的な「自己効力感(自信)」を持っているからです。
自信をつけるためには、「小さな目標から達成し、自信をつける」ことが重要です。
著者は「東大合格なんて、コンビニにお茶を買いに行く程度の難易度」というハッタリ(野心的な目標)を立て、それを「達成可能な小目標」に分解し、次々と達成し続けることで、16歳での東大合格を実現しました。
2. それ、「勉強」ではなく「作業」です
多くの人が「頑張っているのに結果が出ない」のは、「勉強」ではなく「作業」をしているからです。
- 勉強:脳に負荷をかけること(知識習得、理解度向上、知識応用)。
- 作業:脳に負荷をかけないルーチンワーク(再読、ノート作成、単語帳作成)。
脳には、直観的で「怠惰」なシステム(作業に使われる)と、逆算的で「勤勉」なシステム(勉強に使われる)があります。単純作業を繰り返しても、使われるのは「怠惰」なシステムであり、「短期記憶」にしかならず、学びは得られません。
あえて「心地悪い場所」に身を置き、「勤勉」なシステムを駆使して脳に負荷をかけることだけが、本物の「勉強」です。
3. 科学的に「間違った」勉強法と「正しい」勉強法
著者は、科学的に非効率性が証明されている「間違った勉強法」を捨てるべきだと主張します。
▼間違った勉強法(作業)
1. テキストをひたすら何度も読む:内容ではなく「順序」を覚えてしまい、理解度の低い箇所に気づきにくい。
2. 下線を引いたりハイライトする:単なる遊び。内容が頭に入るわけではない。
3. 意図を持たずにノートを取る:教科書や参考書の劣化版を作っているに過ぎない。
▼科学的に正しい勉強法(勉強)
1. 勉強する「前」に模擬試験を行う:
何も知らない状態で過去問を解くと、当然間違えまくります。しかし、これにより試験に出る内容への感度が非常に高まり、暗記に必要な労力が3割程度に減ります。また、脳は間違えた事柄を強く記憶する(ハイパーコレクション)ため、理にかなっています。
2. 間隔を空けて練習と模擬試験を繰り返す(想起学習):
忘れそうなころに積極的に思い出すことで、短期記憶が長期記憶に移行します。テキストを再読する代わりに、キーワードだけを見て「自分の言葉で説明してみる」練習が効果的です。
3. 質問形式でメモする:
授業や自習中に「縄文時代の人の平均身長は?」といったクイズ形式でメモしておくと、後で効率的に想起学習(復習)ができます。
著者は「参考書の3割くらいしか読まないし、難しすぎる問題も解かない」と言います。手間を惜しむための手間を惜しまず、要領良くやれば、勉強は難しくないのです。
「自分はダメ」を抜け出す自己肯定術
どれだけ優れたスキルを持っていても、自己肯定感が低ければ、成功はおぼつきません。
1. 「自分はダメ」ではなく、「まだできないだけ」
「どうせ自分には無理」「うまくいくわけがない」という言葉は、変われない自分を正当化する「思考停止状態」です。
著者は、人生は「覇気」と「発想力」で好転させられると説きます。
「できる」と「一度でできる」は同義ではない。やってみて、できなかったら、「まだできないだけ」である。
大事なのは、ハッタリをかまして、それに追いつくことです。ハッタリは嘘ではなく、「覚悟の表れ」です。ケネディ大統領が1961年に「月に人を送る」と宣言したハッタリが、アポロ計画に繋がったように、大きなハッタリこそが自分を追い込み、実績を後から引き寄せます。
2. 劣等感は克服せず、「武器」に変える
コンプレックスは「ないものねだり」であるため、基本的には克服できません。だから著者は「克服する代わりに、武器に変えて利用する」ことを推奨しています。
本書では、「9浪早稲田合格男」としてはまい氏との対談が収録されています。
- 解消法1:強みとして捉え直す
はまい氏は幼少期、自分の顔にコンプレックスを感じていましたが、今は「親しみやすい等身大の顔」という強みとして捉えています。著者も「早口」をコンプレックスに感じていましたが、「優秀かつ自信家に見えて説得力が上がる」と実感してからは武器にしています。 - 解消法2:弱みを受け入れ、別の強みの足掛かりにする
はまい氏は「理数系が苦手」という弱みを受け入れ、言語力や暗記力が問われる別の教科に集中することで合格を勝ち取りました。
3. 失敗は存在しない。「成功」か「試行」があるだけ
多くの日本人は失敗を過度に恐れています。しかし著者は「そもそも失敗なんて、存在しない」と断言します。
世の中には「成功」か「失敗」があるのではなく、「成功」か「試行」があるだけです。うまくいかなくても、そこから学びを得て「Nice Try!」と捉えればいいのです。
著者は、海外(韓国・英国・ドイツ・イタリア)のほうが「Nice Try!」と応援し合う文化があり、挑戦する人が多いと指摘します。
不安になりやすい人は、わざと小さなバカをやらかしてみる(コンビニで「アイス温めてください」と言うなど)ことで、失敗しても大して問題ないと実感でき、過度な不安がなくなるとも勧めています。
まとめ:「天才」とは「自分の勝ち筋」を歩み続ける人
本書は、成功の決め手を「運7割・才能2割・努力1割」だと喝破します。人生は「運ゲー」です。
しかし、その運を活かせるかどうかは「才能」にかかっており、その才能を活かし、運に遭遇する回数を増やすのが「努力」です。
私たちは、自分の才能(少しやったら、うまくいったこと)を見極め、それをプロデュースし、評価される環境を選ぶ必要があります。
そのために必要なのが「冷静な狂気で、自分の勝ち筋を見つける」ことです。自分の強みと環境を掛け算し、奇抜なアイデア(狂気)を、その真価(冷静)で見極めるのです。
そして、勝ち筋が見つかったら、「2年で、人生を変える大勝負に出る」。
専門性を身につけ「希少価値」を生み出すには、約2000時間かかると言われます。毎日3時間かければ、約2年です。そして、人間の意欲(ドーパミン)が続くのも約2年です。この2年間、脇目もふらず大勝負に出れば、人生は変えられます。
本書の最後は、天才の定義で締めくくられています。
天才 = 志 × 目標 × 戦略
本書は、この3つを自分の手で構築するための、強力な思考法と実践術に満ちています。「自分も変われるかもしれない」ではなく、「自分は変わる」と決意させてくれる一冊です。