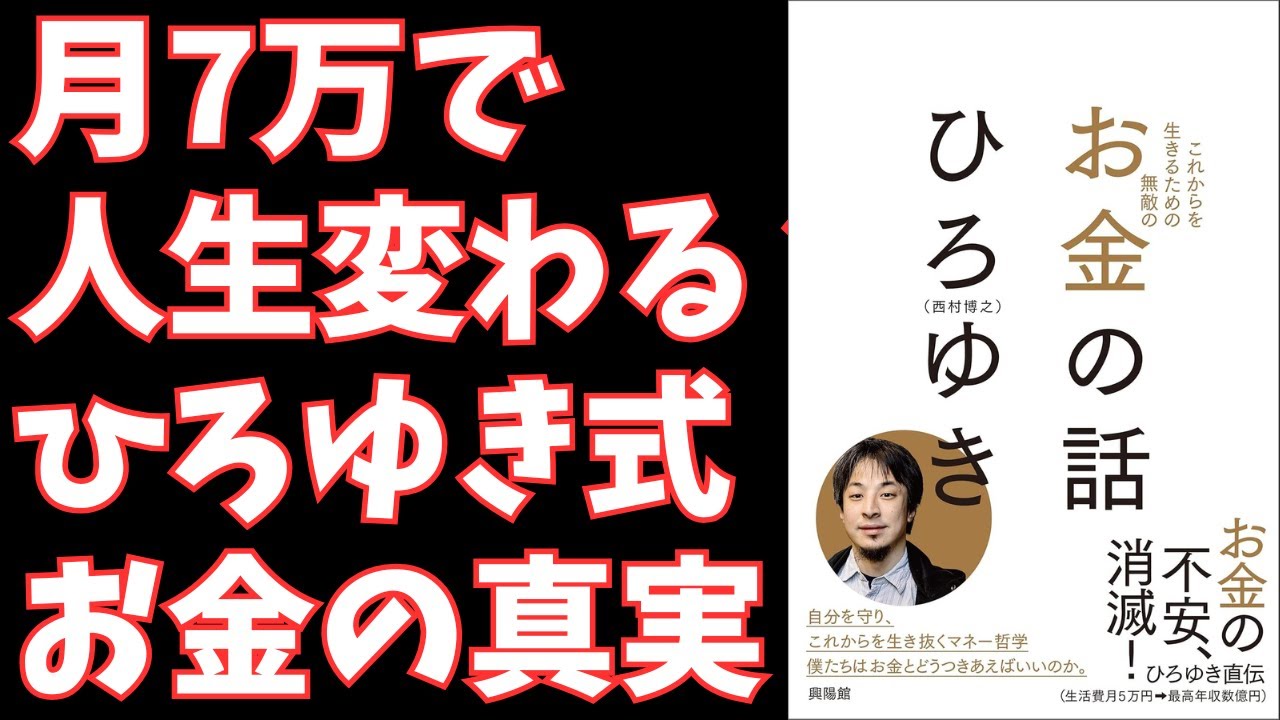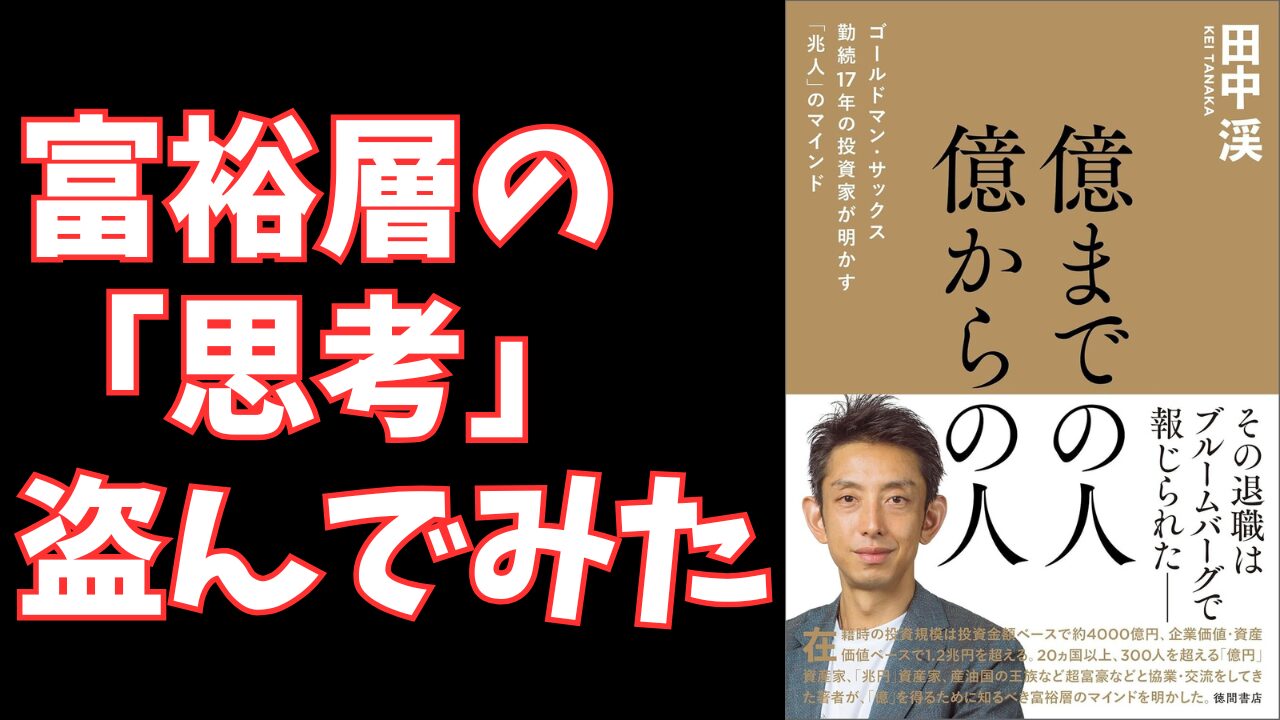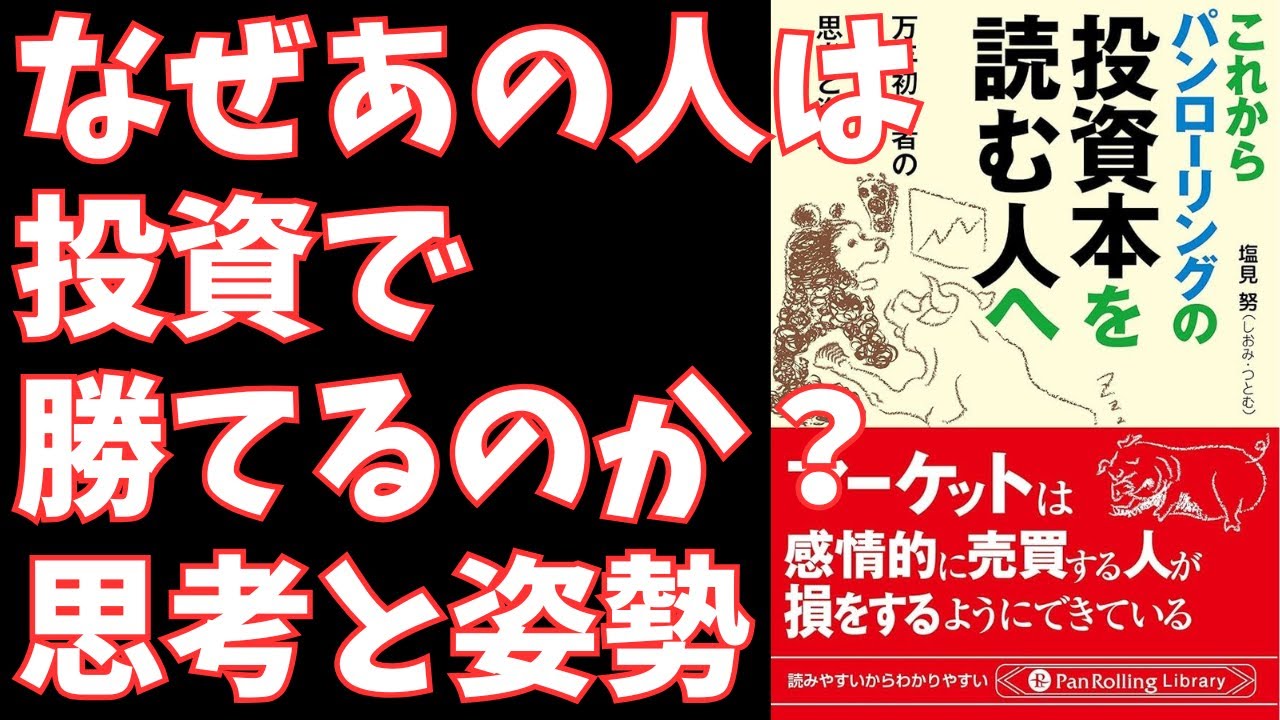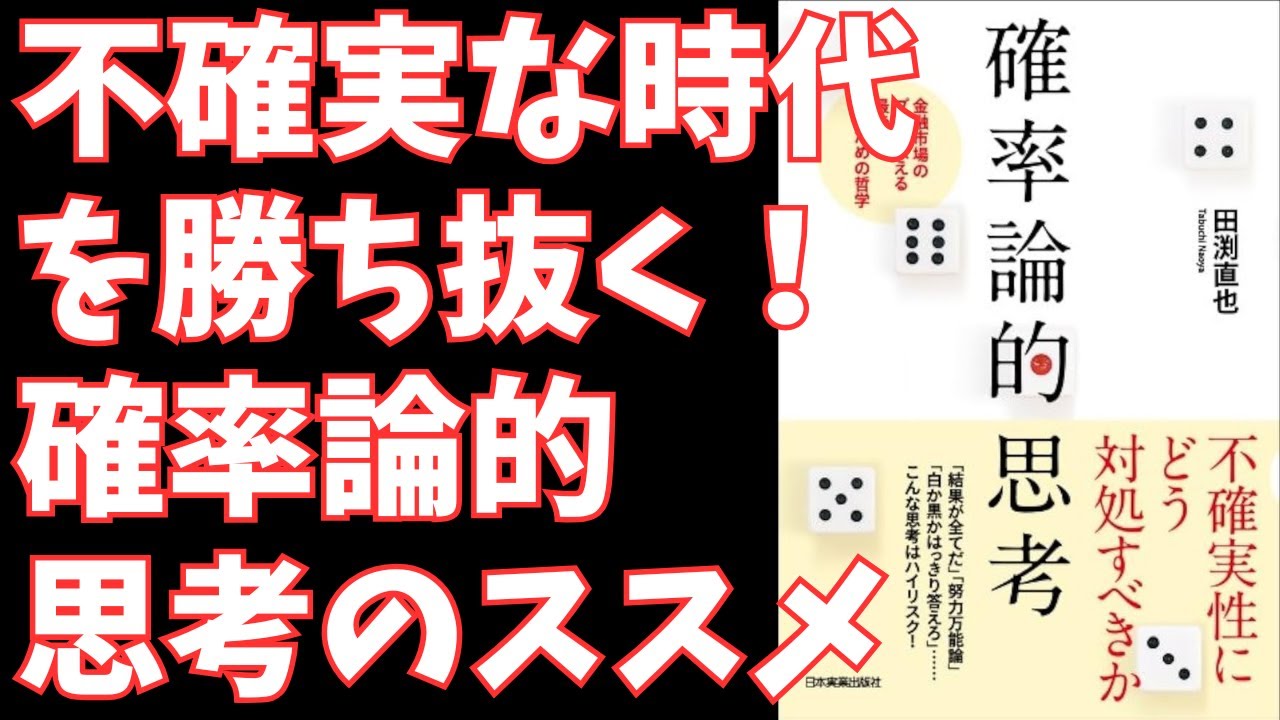忙しいビジネスパーソンが知るべき「金持ちになるための濃ゆい理論」とは?上念司氏が教える資産形成のマインドセット
経済評論家の上念司氏が説く『誰も教えてくれなかった 金持ちになるための濃ゆい理論』は、単なる投資テクニック本ではありません。本書は、なぜ多くの人が金持ちになれないのか、その根本的なマインドセット(思考法)と経済の「流れ」の読み解き方に焦点を当てています。
この記事では、忙しいビジネスパーソンが明日から実践できる「金持ちになるための思考法」を、書籍の具体的なエピソードと共に解説します。「地位財」と「非地位財」による幸福度の違い、あなたが今いる「キャッシュフロー・クワドラント」の領域、そして「マイホームは負債である」という衝撃的な事実まで、あなたの資産戦略を根本から見直すヒントを提供します。
本書の要点
- 「非地位財」の追求: 他人との比較で得られる「地位財(お金、モノ)」の幸福は続かない。自分だけの「非地位財(自由、健康、愛情など)」、すなわち「自分教」を持つことが成功の第一歩である。
- キャッシュフロー・クワドラントの移行: 世の中にはE(従業員)、S(自営業)、B(ビジネスオーナー)、I(投資家)の4種類の仕事がある。金持ちになるには、EやSから「仕組み」で稼ぐBや「お金」で稼ぐIへの移行を意識する。
- 「資産」と「負債」の区別: 金持ちは「資産(キャッシュを生むもの)」を買い、貧乏人は「負債(キャッシュを食うもの)」を買う。その典型例がマイホームであり、金持ちになるプロセスでは最大の障害となり得る。
- リスク管理としての「3分割」: 資産やビジネスは「3分割」する。1つが失敗しても残り2つでカバーでき、全滅を避ける。これは「トカゲのしっぽ」理論であり、再起可能な状態を維持することが重要。
- 経済サイクルとメディアリテラシー: 経済には約10年周期の危機(ピンチ)があり、それは同時にチャンスでもある。新聞やテレビなどのメディア情報を鵜呑みにせず、ファクトを自分で調べ、流れを読むことが成功の鍵となる。
あなたの幸福は本物?「地位財」と「非地位財」という罠
忙しく働くビジネスパーソンであるあなたは、何のために働いていますか?
「もっとお金が欲しい」「社会的地位を上げたい」「良い車や良い家に住みたい」——これらは誰もが持つ自然な欲求です。しかし、著者の上念氏は、経済学者ロバート・フランクの定義を引き合いに出し、そこに警鐘を鳴らします。
フランクは、幸福につながる財を2種類に分けました。
- 地位財(ちいざい): お金、社会的地位、モノなど、他人との比較によって満足が得られる財。
- 非地位財(ひちいざい): 健康、自主性、自由、愛情、社会への帰属意識など、他人との比較とは関係なく満足が得られる財。
本書が指摘する重要な点は、「地位財」による幸福は長続きしないということです。
高級車を手に入れても、その喜びは一瞬で薄れ、すぐに次のモデルが欲しくなります。これは、他人との比較に基づいているため、上には上がおり、終わりがないからです。
一方で、「非地位財」による幸福は長続きします。
著者は、自身の「非地位財」として、大学時代の弁論部の仲間たちとの関係を維持・発展させる「永遠の4年生」プロジェクトを挙げています。後輩を応援し、イベントに協賛することは、他人から見れば何のリターンもない自己満足(アホなこと)かもしれません。しかし、著者にとってはそれがアイデンティティに深く根差した、他人との比較を許さない絶対的な幸福(非地位財)なのです。
金持ちになるための第一歩は、この「地位財」の無限ループから抜け出すことです。そして、自分にとってのプライスレスな「非地位財」が何かを見極めること。著者はこれを「自分教」を持つと表現しています。
あなたが心の底から達成したい「着地点」は何でしょうか? それが明確になれば、目先の「地位財」に惑わされず、長期的な資産形成への強いメンタルを持つことができます。
あなたはどの領域で働く? 金持ち父さんの「キャッシュフロー・クワドラント」
「自分教」という着地点が見えたら、次に考えるべきは「どうやってそこへ到達するか」です。本書は、ロバート・キヨサキ氏のベストセラー『金持ち父さん貧乏父さん』の第2弾に出てくる「キャッシュフロー・クワドラント」を紹介しています。
世の中の仕事は、収入の得方によって以下の4種類(ESBI)に分類されます。
- E (Employee / 従業員): 給料をもらって働く人。時間が固定され、収入は安定するが上限がある。
- S (Self-employed / 自営業): 自分で働く人。弁護士や医師、フリーランスなど。働けば収入は増えるが、自分が働かなければ収入はゼロになる。
- B (Business Owner / ビジネスオーナー): 仕組み(ビジネスシステム)を作り、その仕組みで稼ぐ人。自分が働かなくても収入が入る。
- I (Investor / 投資家): お金がお金を生む仕組みで稼ぐ人。
多くの人はE(従業員)からスタートします。著者の上念氏も、最初は銀行員(E)でした。しかし、彼はEの最大のメリットを「給料が保証されていること」ではなく、「給料をもらいながら、タダでビジネスの勉強ができること」だと指摘します。
彼は銀行員時代に「流れに乗らない規制産業(銀行)は、親方日の丸でも生きていけない」ことを学び、転職した塾業界で「月額課金ビジネスの本質」を叩き込まれました。その経験が、現在のオンラインサロンやフィットネスジムといったB(ビジネスオーナー)としての成功の基盤となっています。
あなたが今E(従業員)だとしても、その場所で何を学び、将来どのようにS(自営業)、B(ビジネスオーナー)、I(投資家)へと移行していくかを意識することが、金持ちへの道筋を描く上で不可欠です。
“悪魔祓い” ―― 金持ちになる最大の障害「マイホーム」という負債
金持ちになるプロセスには、「悪魔の誘惑」が潜んでいます。その最大の誘惑が「マイホーム」です。
なぜマイホームが危険なのでしょうか? それは、ロバート・キヨサキ氏の有名な定義に集約されます。
- 資産とは、キャッシュを生むもの(あなたのポケットにお金を入れてくれるもの)
- 負債とは、キャッシュを食うもの(あなたのポケットからお金を奪うもの)
この定義に当てはめると、あなたが住むためのマイホームは、キャッシュを生みません。それどころか、住宅ローン、固定資産税、維持費といった形で、毎月あなたのポケットからお金を奪い続ける、典型的な「負債」なのです。
多くの人は「家賃よりローンが安い」という悪魔のささやきに騙されます。しかし、住宅ローンという長期固定の支払いは、あなたがビジネスに挑戦したり、転職したりする際の最大の足枷となります。
著者は、金持ちになるためには「じゃんけんで100回勝ちたければ、最低300回勝負する」という試行錯誤が必要だと言います。しかし、住宅ローンを抱えていると、失敗した時のダメージが大きすぎ、「じゃんけん(=チャレンジ)」を続けることが精神的にも経済的にも困難になります。
本書は、資産の大半がマイホームになっている状態を「貧乏父さん」と呼びます。一方で、「金持ち父さん」は、複数の資産(BやI)からのキャッシュフローで余裕を持って、道楽としてマイホームを買います。
金持ちになるまでは、見栄や「一人前」という昭和的な価値観で負債を買ってはいけません。まずはキャッシュを生む「資産」を買うことに集中すべきです。
ピンチはチャンス! 経済は「10年周期」で動いている
ビジネスで成功するためには「流れ」を読むことが重要です。そして、その流れは一定ではありません。本書は、経済には「約10年周期」で大きな危機(ショック)が訪れると指摘します。
- 1973年 第一次石油危機
- 1986年 円高不況
- 1991年 バブル崩壊
- 2000年 ITバブル崩壊
- 2008年 リーマンショック
- 2020年 コロナショック
多くの人にとって、これらの危機は「ピンチ」です。しかし、金持ちになる人にとって、このピンチは「チャンス」です。
なぜなら、経済危機はそれまでの「既得権益」を破壊し、業界のルールをリセットするからです。
例えば、1991年の牛肉とオレンジの自由化。当時マスコミは「日本の農家は全滅する」と大騒ぎしました。その報道を鵜呑みにした農家は廃業しました。しかし、流れの本質を見抜き、「安い牛肉との競争」ではなく「高品質な和牛ブランド」へと逆張りした畜産業者は、自由化の勝者となりました。
著者が起業したのも2001年、まさにITバブル崩壊の直後でした。危機(逆風)の真っ只中に起業するからこそ、ライバルは少なく、安く居抜き物件が手に入るなどのメリットがあります。
重要なのは、危機を耐え抜き、次の上昇気流を待つことです。そのために必要なのが「低空飛行」、つまり「儲からなくてもいいので損のない状態(売上で経費をカバーできる状態)」をいち早く作ることです。
低空飛行でも飛び続けていれば、10年に一度のチャンス(上昇気流)が来たときに、一気に飛躍できるのです。
メディアの情報を鵜呑みにするな! 情弱から脱却する思考法
経済のサイクル(流れ)を読む上で、最大のノイズとなるのが「マスコミ(新聞やテレビ)」です。
本書は、メディアリテラシーの重要性を厳しく説いています。
例えば、バブル絶頂期の1989年末、日銀が利上げを始めている(=景気引締めのシグナル)にもかかわらず、日経新聞をはじめとするマスコミは「日経平均株価は今後5万円に達する」と煽り立てました。結果はご存知の通り、翌年に大暴落です。
なぜメディアは間違うのでしょうか?
著者は、新聞記者は経済の専門家ではなく、単なるサラリーマンであり、「記者クラブ制度」によって情報源(財務省や大企業)に都合の悪いことを書けない構造になっていると指摘します。
彼らの書く市場解説は、上がったら良いニュースを、下がったら悪いニュースを拾ってくるだけの「後講釈」に過ぎません。
では、何を信じればいいのでしょうか?
それは、自分でファクトを調べることです。
例えば、「日本の財政は破綻する」というメディアの論調に対し、著者は「簿記3級」の知識を推奨します。政府の負債(国債)だけを見るのではなく、貸借対照表(バランスシート)を見て「資産」も見るべきだと。そうすれば、日本政府が世界有数の資産国であることが分かります。
また、市場の反応(ファクト)を見ること。もし本当に日本が財政破綻するなら、日本国債の金利は(リスクを反映して)高騰しているはずです。しかし現実は、世界最低水準の低金利(=大人気)です。
著者は、メディア(日経新聞)を「情弱(情報弱者)が何を考えているか知りたかったら、新聞を読め」という目的で購読しているとまで言い切ります。
メディアの情報を鵜呑みにせず、常にファクトを疑い、自分で検証する姿勢こそが、金持ちになるための「濃ゆい理論」なのです。
まとめ:「自分教」を持ち、賢くリスクを取る
『誰も教えてくれなかった 金持ちになるための濃ゆい理論』は、金持ちになることは「一攫千金」ではなく、「長期計画」と「マインドセット」の結果であると教えてくれます。
著者は、独立間もない頃、毎朝新橋駅のホームレスを見て「これは未来の俺の姿だ」と恐怖する「ネガティブ・シンキング」を実践したと言います。最悪を想定するからこそ、そうならないための具体的な行動(長期計画)が生まれます。
本書の教えは一貫しています。
まず、他人との比較(地位財)から抜け出し、あなたの「自分教(非地位財)」という着地点を明確にする。
次に、E(従業員)の立場に甘んじず、B(ビジネスオーナー)やI(投資家)への移行を常に意識する。
その過程で、「マイホーム」という名の負債に手を出す「悪魔の誘惑」を断ち切る。
そして、資産を3分割してリスクを管理し、「10年周期」の経済サイクルと「メディアの嘘」を見抜き、ピンチをチャンスに変える。
この「濃ゆい理論」は、今日の不安定な経済状況を生き抜くビジネスパーソンにとって、強力な羅針盤となるはずです。