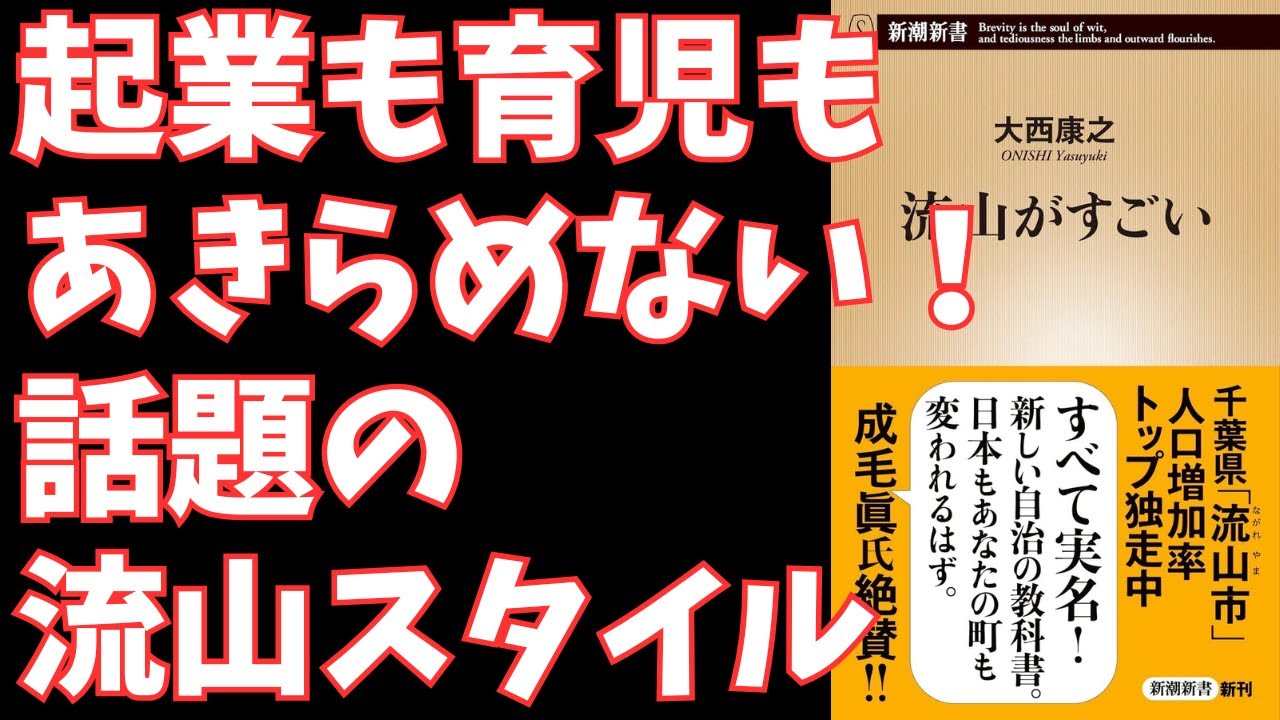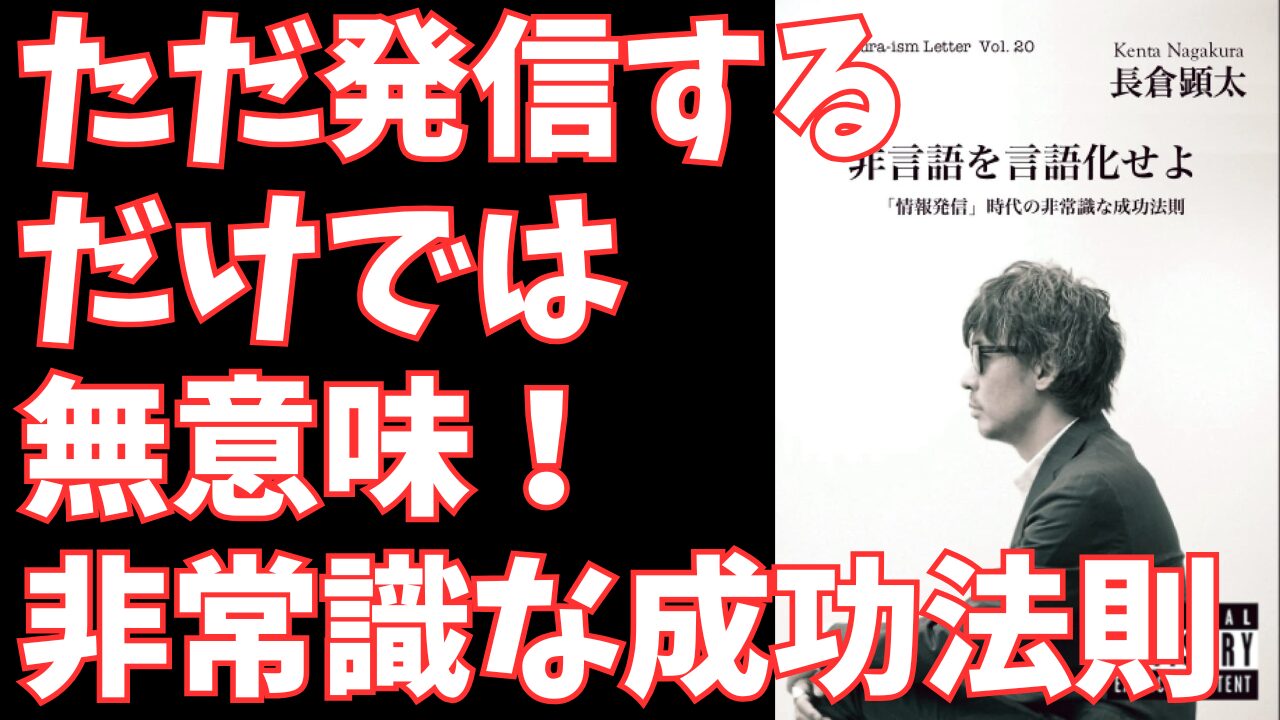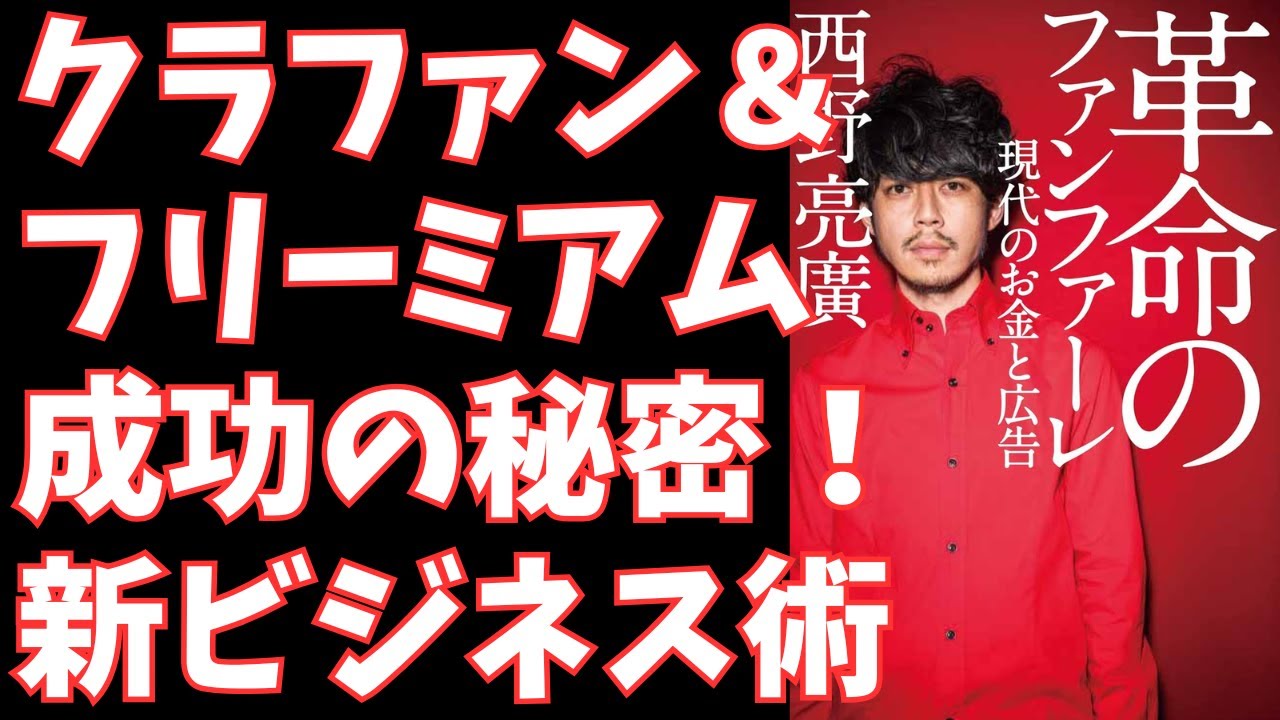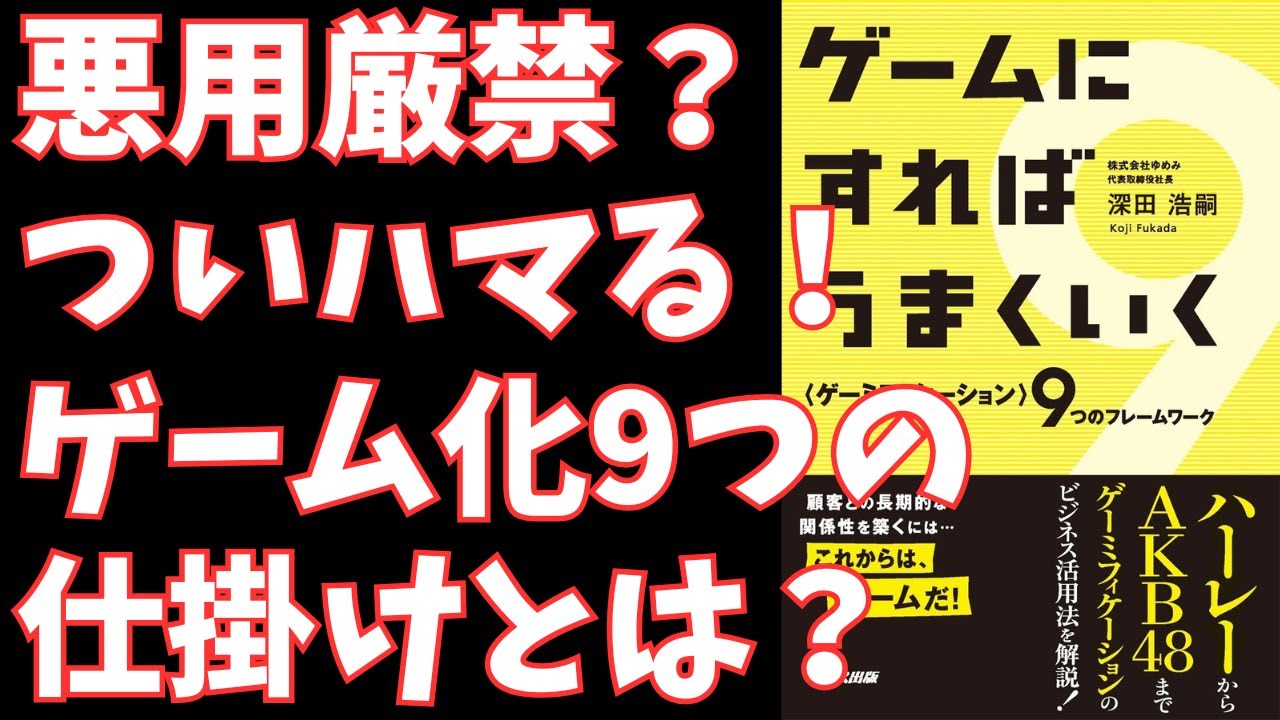『書ける人だけが手にするもの』齋藤孝|文章が苦手なビジネスパーソン必見!思考がクリアになる書き方のコツ
本書『書ける人だけが手にするもの』は、明治大学教授の齋藤孝氏が、文章を書くことの本質と具体的な技術を解説した一冊です。多くの人が抱える「書けない」という悩みは、「人のために書こうとする」ことから生じると指摘。本書では、書くことは本来 「自分のため」に行う自己発見のツール であると位置づけ、「考えてから書く」のではなく 「書きながら考える」 という画期的なアプローチを提唱しています。
この記事では、忙しいビジネスパーソンが明日からすぐに実践できる本書の要点を中心に、具体的な文章の「型」や準備のコツ、そして「書く力」の土台となる「読む力」の鍛え方まで、書籍中の豊富な事例を交えながら詳しく解説します。
本書の要点
- 書くことは自己理解のツールである: 文章とは、曖昧な自分の内面を照らし出すランタンのようなもの。書くことで思考や感情が明確になり、自分自身を深く知ることができる。
- 「考えてから書く」は間違い: 「書きながら考える」「話すように書く」ことで、文章作成のハードルは劇的に下がる。思考と表現を同時に行うことで、自然な文章が生まれる。
- 良い文章には「フック」と「型」がある: 読者の関心を引く「?」や、自身の体験談である「エピソード」などをフック(引っかかり)にすることで、文章は格段に書きやすくなる。
- 文章は準備が9割: 書くテーマは日常の中に転がっている。日頃からアンテナを張り、箇条書きやメモで思考の材料を整理しておくことが、質の高い文章への近道となる。
- 「書く力」は「読む力」に比例する: 優れた文章に触れ、特に「音読」を通じてそのリズムを身体に染み込ませることが、自身の表現力を豊かにし、書く力を飛躍的に向上させる。
なぜ、私たちは「書くこと」が苦手なのか?
「企画書をまとめるのに時間がかかりすぎる」
「部下への指示メールが、うまく伝わっているか不安」
「SNSで自分の考えを発信したいけれど、何を書けばいいかわからない」
多忙な日々を送るビジネスパーソンにとって、「書く」という行為は避けて通れないスキルです。しかし、多くの人が文章を書くことに苦手意識を持っているのではないでしょうか。本書の著者、齋藤孝氏は、その根本的な原因を 「人のため」に書いているからだ と指摘します。
「おもしろいと思ってもらいたい」「自分の考えを正確に伝えたい」と、読み手の評価を気にするあまり、筆が重くなってしまうのです。しかし、齋藤氏は「本来、書くことは、他でもない 自分のため にすることです」と断言します。
書くことは、自分を知るための冒険
頭の中に渦巻く思考や感情は、そのままにしておくと形にならずに消えてしまいます。それらを書き言葉として目に見える形にすることで、私たちは初めて「自分は今、こんなことを考えていたのか」「こんな気持ちだったのか」と客観的に自分自身を捉えることができます。
本書では、文章を 「曖昧模糊とした自分の内面をくっきりと照らし出すランタンのようなもの」 と表現しています。 書くという行為は、暗闇の洞窟を探検するように、自分の内面を一つひとつ照らし出し、新たな発見を繰り返していくプロセスなのです。
この「自分を知る」という最大のメリットを理解すれば、書くことへのプレッシャーは軽くなるはずです。誰かに評価されるためではなく、自分自身と対話し、理解を深めるために書く。このスタンスこそが、文章術の第一歩となります。
「考えてから書く」という思い込みを捨てる
多くの人が陥りがちなのが、「まず何を書くか頭の中で完全にまとめてから、書き始める」という思い込みです。しかし、齋藤氏はこの順序を真っ向から否定し、 「考えてから書くのではなく、書きながら考えればいいのです」 と提唱します。
パソコンのキーボードを打ちながら、あるいはペンを走らせながら、言葉を探し、思考を巡らせる。実はこの「書きながら考える」プロセスこそが、思考を深め、整理するための最も効果的な方法なのです。書くという行為そのものが、思考の一部であると捉え直すことで、文章を書くことへのハードルは一気に下がります。
発想の転換!「話すように書く」という新常識
「書きながら考える」と言われても、まだピンとこないかもしれません。しかし、私たちは日常的に「思考と表現を同時に行う」という高度な作業を自然に行っています。それが 「話す」 という行為です。
友人と会話するとき、いちいち原稿を用意する人はいません。その場で言葉を探し、思考を組み立てながら話しているはずです。この感覚を、そのまま書くことに応用するのが「話すように書く」というアプローチです。
「書く」と構えるから難しくなるのであって、「話す」ことの延長線上にあると考えれば、肩の力が抜け、もっと気軽に文章と向き合えるようになります。
「読む」→「話す」→「書く」で文章の基礎体力をつける
とはいえ、話し言葉をそのまま書き起こしただけでは、稚拙で伝わりにくい文章になりがちです。話し言葉には表情や声のトーンといった非言語情報が伴いますが、書き言葉は文字だけで全てを表現しなければならないからです。
そこで齋藤氏が推奨するのが、文章の基礎体力をつけるための3ステップトレーニングです。
【ステップ1】好きな本を読み、キーワードをピックアップする
まずは、好きな本やコラムを読み、「これは誰かに伝えたい」と感じた部分のキーワードをいくつか書き出します。
【ステップ2】読んだ感想を人に話す
次に、ステップ1で選んだキーワードを使いながら、本の内容や感想を身近な人に話します。ポイントは、 本に書かれていた「書き言葉」を意識的に使って話すこと。 これにより、普段の会話とは少し違う「書くように話す」トレーニングになります。
【ステップ3】話した内容をもとに書いてみる
最後に、人に話した内容を思い出しながら文章にまとめます。一度、口に出して話すことで、頭の中が整理され、伝えたいポイントが明確になっているため、驚くほどスムーズに文章が書けるはずです。
このトレーニングを繰り返すことで、話し言葉と書き言葉の距離が縮まり、豊かで的確な表現を使いながら、自然体で「話すように書く」ことができるようになります。
誰でもスラスラ書ける!文章の「型」を使いこなす
書くことへの心理的なハードルが下がったら、次は具体的な技術です。本書では、良い文章には必ず「フック」があると述べられています。フックとは「素通りすることができない引っかかり」のことで、これを軸にすることで、文章は格段に書きやすくなります。
ここでは、ビジネスシーンでも応用できる、代表的な文章の「型」を4つご紹介します。
1. 「?」で始まり、「!」で終わる文章術
最もシンプルかつ強力なフックが 「?」(問い) です。「なぜ〇〇は△△なのか?」と問いを立てることで、書き手自身もその答えを探すために思考が動き出し、読み手も「確かに、なぜだろう?」と答えを知りたくなり、文章に引き込まれます。
例えば、ベストセラーになった『さおだけ屋はなぜ潰れないのか?』は、まさにこの「問い」をタイトルにした好例です。「さおだけ屋はどうやって商売を成り立たせているのか?」という素朴な疑問から始まり、その答えを探求していく過程で、会計学の知識が自然と身につく構成になっています。
この型は、 最初に「?」という問いを提示し、文章の最後で「!」という発見や驚き、納得感のある結論に着地させる のがポイントです。 企画書やプレゼンの冒頭で、聞き手の興味を引く「問い」を投げかけるなど、ビジネスの場でも非常に有効なテクニックです。
2. 魅力的なエッセイの方程式「エピソード+自分の考え」
日常の出来事を単なる「日記」や「記録」で終わらせず、人を惹きつける「エッセイ」に昇華させる型です。その方程式は 「エピソード+自分の考え」 というシンプルなもの。
古典の名作『徒然草』に出てくる「仁和寺にある法師」の話が、その良い例です。石清水八幡宮へお参りに行ったお坊さんが、山の上にある本殿の存在を知らず、麓のお寺だけを拝んで満足して帰ってきてしまった、といううっかり話(エピソード)。これだけで終わればただの面白い話ですが、作者の兼好法師は最後に 「ほんのささいなことにも案内人(先達)は必要なのである」 という一文(自分の考え)を加えます。
この締めの一文があることで、個別のエピソードが普遍的な教訓へと昇華され、読者は「なるほど」と深く納得するのです。ビジネスシーンにおいても、具体的な成功事例や失敗談(エピソード)を紹介した上で、そこから得られた学びや法則(自分の考え)を示すことで、説得力のある報告書やプレゼン資料を作成できます。
3. 文豪の力を借りる「引用+自分の経験談」
教養とオリジナリティを両立させたい場合に有効なのが、 「名文の引用+自分のエピソード」 という型です。本を読んで心に響いた一文をフックにし、そこに関連する自身の体験談を組み合わせることで、文章に深みと独自性が生まれます。
例えば、梶井基次郎の『檸檬』にある「つまりはこの重さなんだな」という一文。主人公がレモンの重さに「すべての善いものすべての美しいものを重量に換算して来た重さ」を感じる場面です。 この一文を引用し、「私にとっての『この重さ』は、膝の上で眠る愛猫の重さだ」といったように、自分自身の経験と結びつけて語ることで、読者の共感を呼ぶオリジナルな文章が生まれます。
有名な経営者や思想家の言葉を引用し、それを自社の状況や自身の経験に当てはめて語ることで、スピーチやコラムに説得力と個性を加えることができます。
4. 思考を深める「概念+3つの事例」
より論理的で説得力のある文章を書きたいなら、この型が役立ちます。まず、具体的な出来事から 「概念」 を抽出します。概念とは、「民主主義」「美しさ」のように、物事を見るための視点を与えてくれる抽象的な言葉のことです。
例えば、「今朝、寝坊して遅刻した」という出来事があったとします。これを単なる報告で終わらせるのではなく、「遅刻」という概念をフックにします。すると、
- 「遅刻をしても憎まれない人は何が違うのか?」
- 「歴史上、遅刻が原因で大きな機会損失をした人物は?」
といったように、書くべきテーマが次々と見えてきます。
テーマが決まったら、次はそのテーマを裏付ける 具体例を「3つ」 探します。なぜ3つかというと、1つや2つでは説得力に欠け、4つ以上だと冗長になりがちだからです。3つは、物事をシンプルかつ丁寧に説明するのに最もバランスの取れた数なのです。
この「概念化」と「3つの具体例」を組み合わせる力は、物事の本質を捉え、ロジカルに説明する能力に直結するため、ビジネスパーソンにとって必須のスキルと言えるでしょう。
文章は「準備」が9割!書く前の段取り術
優れた文章は、書き始める前の「準備」でその質がほぼ決まります。いきなり書き始めるのではなく、いくつかのステップを踏むことで、書く作業は驚くほどスムーズになります。
テーマは「探すもの」でなく「拾うもの」
「書きたいことがない」と悩む人は多いですが、それは日常をぼんやりと眺めているからかもしれません。腕利きの料理人が市場で最高の食材を探すように、 「何か書くネタはないか」というアンテナを立てて日常を過ごす だけで、世界は途端にビビッドに見え始めます。
読んだ本、観た映画、同僚との雑談、通勤途中の風景など、書く材料はいたるところに転がっています。「叩けよ、さらば開かれん」という言葉の通り、「書きたい」という意識を持つことで、ネタは向こうから飛び込んできてくれるのです。
「箇条書き」で思考の材料を並べる
書きたいテーマが見つかったら、いきなり文章を書き始めるのではなく、まずはそのテーマについて思いつくことを 箇条書きでひたすら列挙 していきます。
この段階では、話の脈絡や順序は気にする必要はありません。頭の中にある思考や感情、関連するエピソードなどを、とにかく全て吐き出すのです。この「列挙力」こそが、文章の骨格を作るための重要な準備となります。
著者の齋藤氏自身、小学生の頃、温泉旅行の作文を書くために事前に材料を箇条書きにしていたおかげで、そのメモを家に忘れたにもかかわらず、電話で読み上げてもらうだけで作文を完成させられた、というエピソードを紹介しています。 事前に材料が整理されていれば、文章を書く作業は格段に楽になります。
「書き手の立場」をはっきりさせる
文章を書く前に、「自分はいったい何者として、どんな立場で書くのか?」を明確に意識することも重要です。人は誰でも、「30代の会社員」「一児の父」「営業部のマネージャー」「特定の趣味のマニア」など、様々な属性を持っています。
その中から 今回はどの立場で書くのかを一つに絞る ことで、文章の論点が明確になり、進むべき道筋が見えてきます。
齋藤氏がニュース番組でコメンテーターを務める際、専門外の話題であっても、必ず「教育者」という自身の立場に立ち返ってコメントをすると言います。 このように立場を明確にすることで、語るべきことが自然と見つかり、文章に一貫性と説得力が生まれるのです。
「書けない…」を解決する具体的な処方箋
本書では、文章に関する具体的な悩みへの処方箋も提示されています。ここでは、特にビジネスパーソンが直面しがちな3つの悩みへの解決策を見ていきましょう。
悩み1:長文が書けない
ある程度まとまった量の文章を書くには、「ドライブスルー式文章術」が有効です。これは、 思考も書く手も止めずに、とにかく一定時間書き続ける という方法です。
人間の思考は直線的に進むのではなく、あちこちに寄り道しながら広がっていくものです。その思考の流れを止めずに、思いつくままに言葉を連ねていきます。最初は文章の断片の寄せ集めでも構いません。まずは量を確保することが目的なのです。
ある程度のボリュームが書けたら、そこから推敲作業に入ります。不要な部分を削り、足りない部分を補い、構成を整えていく。この方法なら、「量の恐怖」を乗り越え、長文作成への苦手意識を克服できます。
悩み2:伝わる文章になっているか不安
自分の書いた文章が独りよがりになっていないか不安なときは、 「特定の誰かに手紙を書くように書いてみる」 のがおすすめです。『アンネの日記』が世界中の人の心を打つのは、アンネが「キティー」という架空の友人に語りかける形で書いていたから、という側面があります。 伝えたい相手を具体的に想定することで、言葉は熱を帯び、自然と伝わる文章になります。
また、 読み手の視点からセルフツッコミを入れる のも効果的です。「今の説明は少しわかりにくかったかもしれませんね。具体的に言うと…」というように、読者が疑問に思いそうな点を先回りして文章に組み込むことで、より親切で理解しやすい文章になります。
悩み3:メールにも時間がかかってしまう
ビジネスメールを効率よく、かつ的確に書くためのコツは2つあります。
1つ目は、 「うまい定型文を集める」 こと。仕事相手から届いたメールの中で、「この挨拶は素敵だな」「この断り方は丁寧だ」と感じた表現があれば、ストックしておき、自分のメールにも活用するのです。 優れた表現を真似ることは、文章上達の近道です。
2つ目は、 「結論をしっかり書く」 こと。ビジネスメールには必ず「用件を伝える」という目的があります。相手に何をしてほしいのか、イエスなのかノーなのか、その結論を最初に明確に書くことで、相手はすぐに意図を理解し、次のアクションに移ることができます。これは、相手の時間を奪わないためのビジネスマナーでもあります。
「書く力」は「読む力」から生まれる
ここまで様々な「書く」技術を紹介してきましたが、その全ての土台となるのが 「読む力」 です。書くことで物事を深く捉える「認識力」が磨かれますが、その認識力自体もまた、読むことによって培われるのです。
優れた文章は、書き手の鋭い認識力が生み出した表現の宝庫です。例えば、三島由紀夫は1964年の東京オリンピックの飛び板飛び込み競技を、「人体が地球の引力に抗して見せるあの複雑な美技」「自然(引力)へのもっとも皮肉な反抗」と表現しました。 このようなハッとする表現に触れるたびに、私たちの認識力は鍛えられ、自分自身の表現力も豊かになっていきます。
名調子を身につける「音読」のススメ
読む力を書く力に変換するために、齋藤氏が特に推奨するのが 「音読」 です。優れた文章は、音楽のように心地よいリズムを持っています。目で追うだけでなく、声に出して読むことで、そのリズムを身体で感じ取ることができます。
作家の古井由吉氏は、執筆の調子が上がらないときに夏目漱石の小説を音読することで、文章的な「音痴」をチューニングすると言います。 名文を音読し、そのリズムが身体に染み付くと、自分が文章を書くときにも自然と心地よいリズムが生まれるようになります。
また、音読は書き手との一体感を生み出します。文豪が紡いだ言葉を自分の声でなぞることで、まるでその作家が乗り移ったかのような感覚になり、書くことへの勇気と自信が湧いてくるのです。
まとめ
『書ける人だけが手にするもの』は、単なる文章作成のテクニック本ではありません。書くという行為を通じて 「自分とはどんな人間なのか?」を発見し、より豊かに生きるための哲学書 とも言えます。
本書で一貫して語られるのは、書くことは決して特別な才能ではなく、正しい心構えとトレーニングで誰でも身につけられるスキルだということです。
- 人の評価を気にせず、自分のために書く。
- 完璧を目指さず、まずは話すように書き始める。
- 先人の知恵である「型」を借りて、思考を整理する。
- 日常にアンテナを張り、書くことを楽しむ。
これらのメッセージは、文章作成に悩む全てのビジネスパーソンにとって、強力なエールとなるはずです。まずは本書で紹介されている「読む→話す→書く」の3ステップや、身近な出来事を「エピソード+自分の考え」でまとめることから始めてみてはいかがでしょうか。
書くことを通じて思考がクリアになれば、仕事のパフォーマンスが上がるだけでなく、自分自身の人生をより深く、主体的に歩んでいくことができるでしょう。