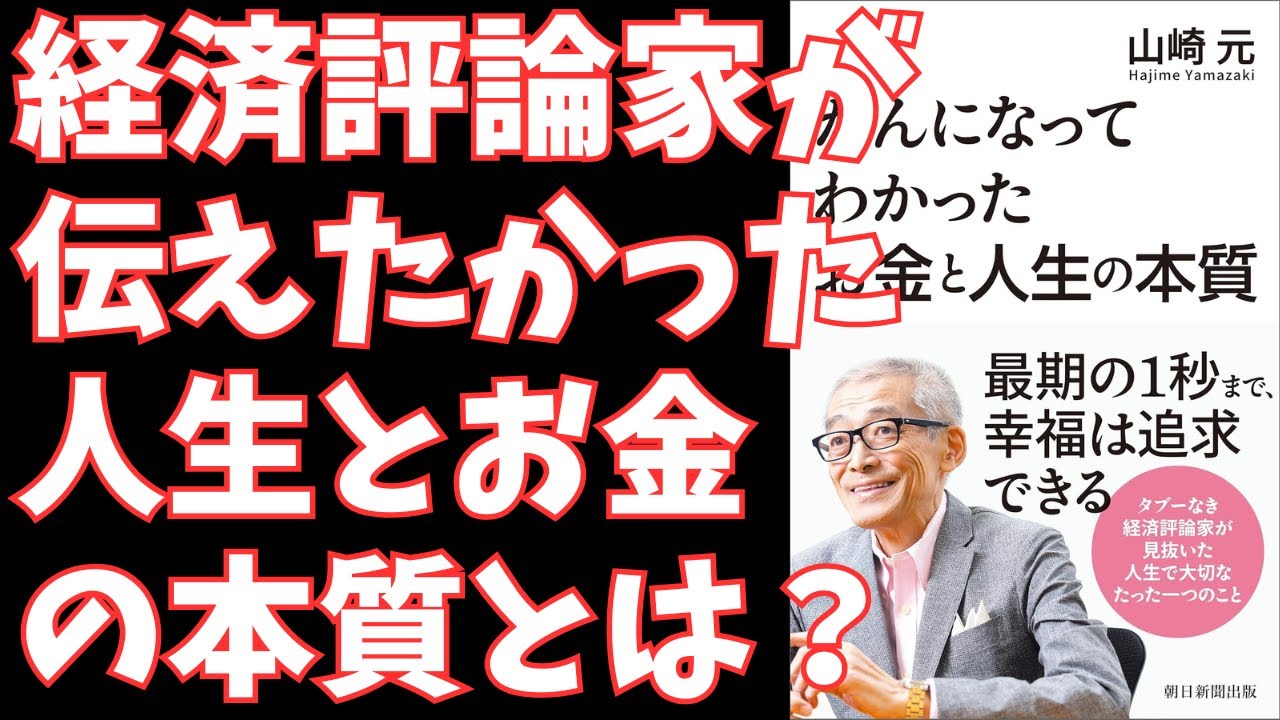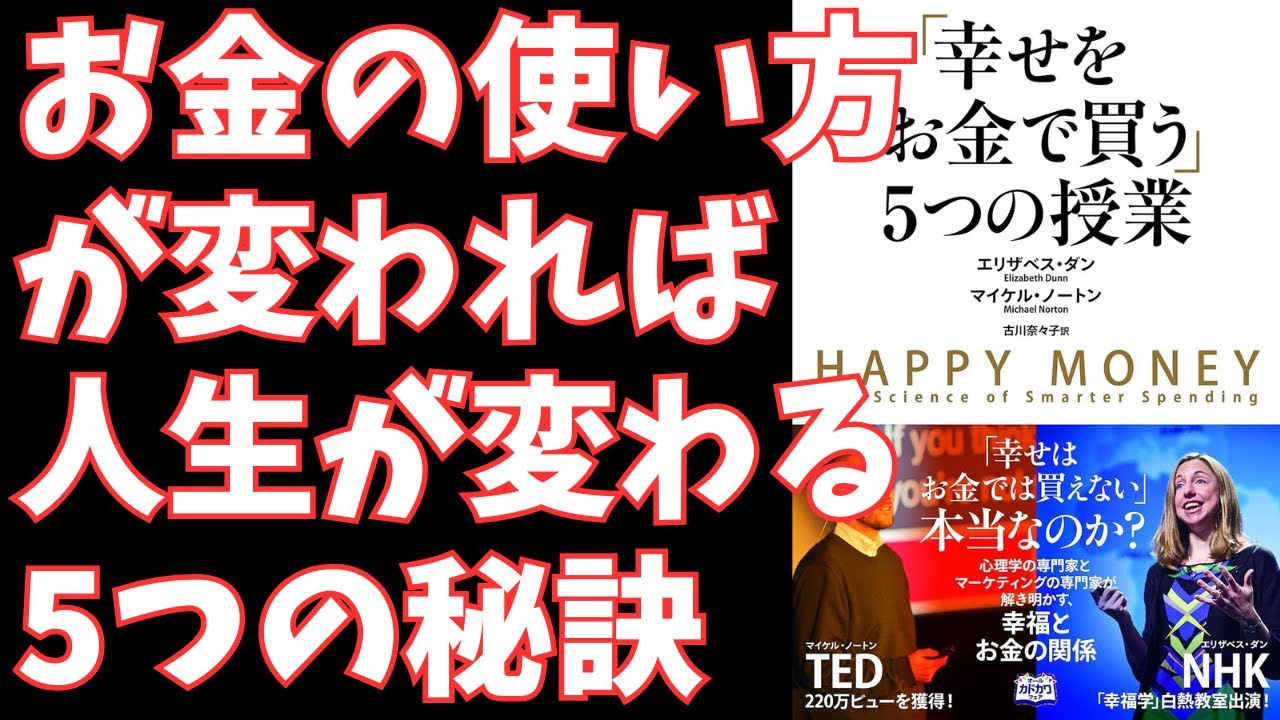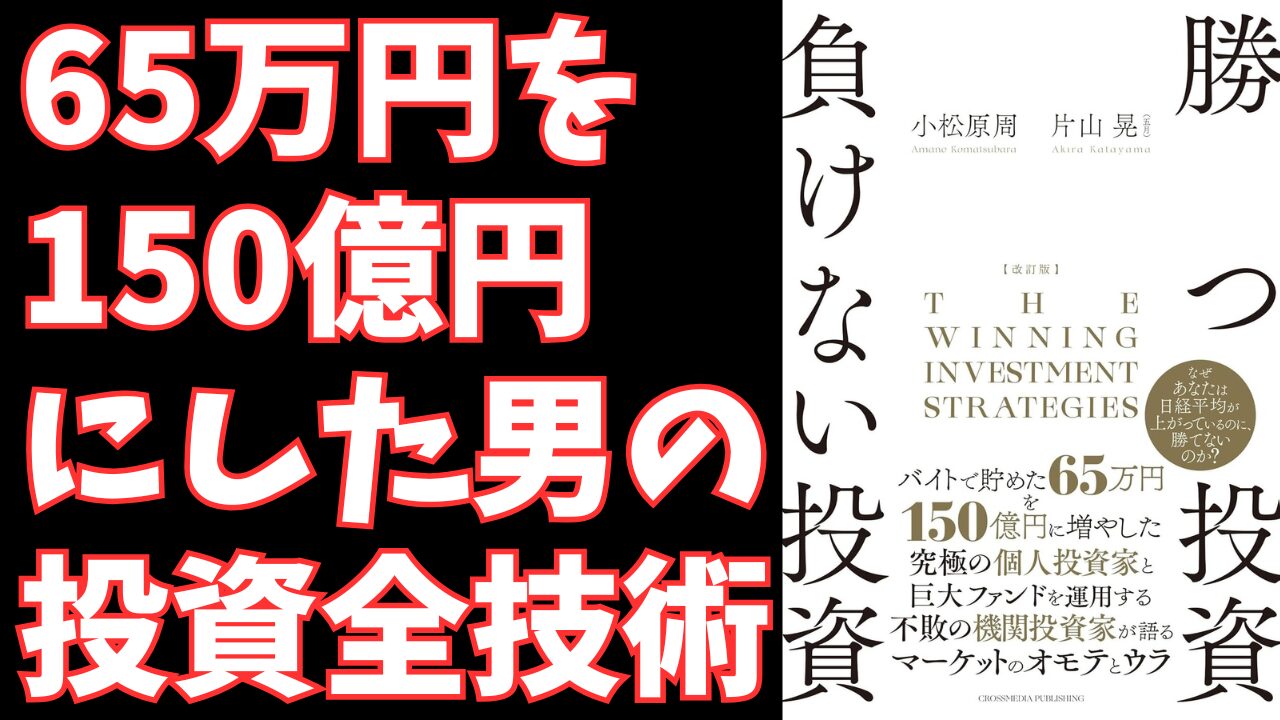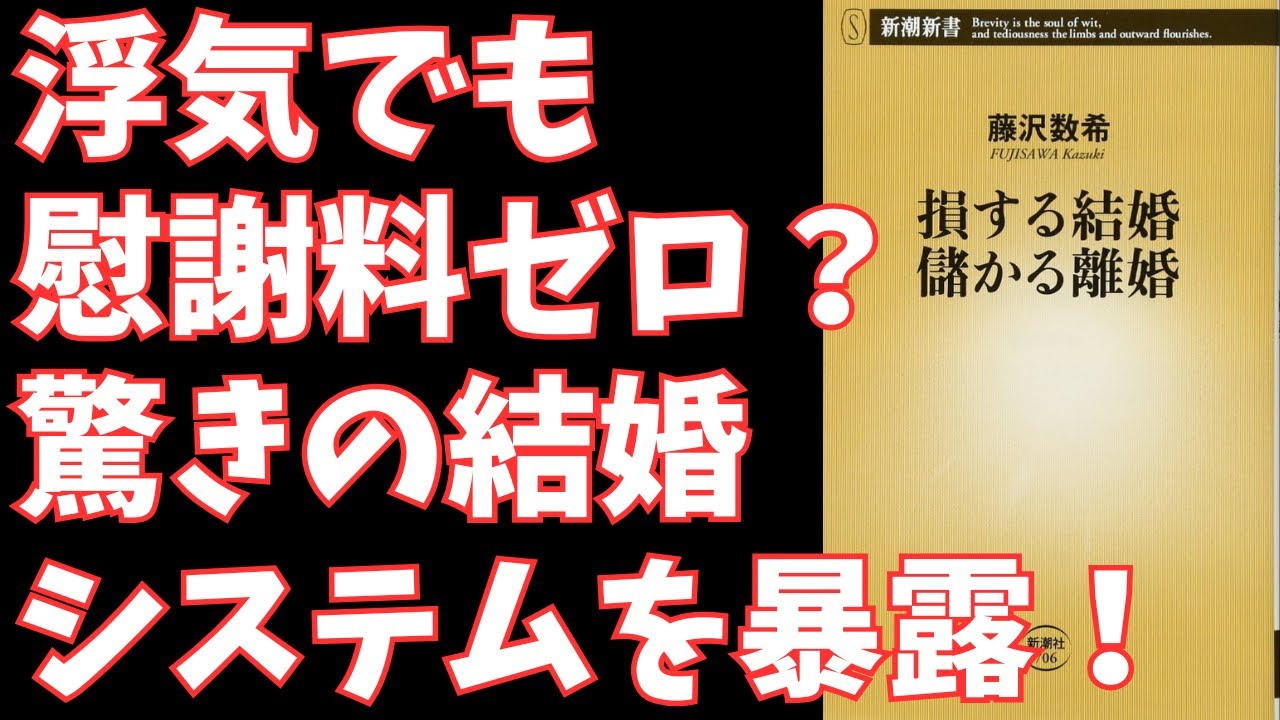『おカネの教室』5万部ヒットの裏側―兼業作家が実践したKindle個人出版から商業出版までの全戦略
5万部を超えるベストセラーとなった『おカネの教室 僕らがおかしなクラブで学んだ秘密』。この作品が、もともとは著者が娘のために書き始めた「家庭内連載」だったことをご存知でしょうか。
本書『「おカネの教室」ができるまで』は、その家庭内連載が、いかにしてKindle個人出版で1万ダウンロードを達成し、さらには商業出版の壁を突破して多くの読者に届く「本」になったのか、その全軌跡を赤裸々に綴った奮闘記です。
本業を持つビジネスパーソンが「兼業作家」として直面する苦悩、個人出版のリアルなマーケティング戦略、そして編集者との「本づくり」を巡る熱い議論まで。本書から、コンテンツ制作に情熱を注ぐすべてのビジネスパーソンに役立つヒントとノウハウを抽出します。
本書の要点
- 家庭内連載の「筆任せ」執筆術: 当初は娘のためだけに執筆。プロットを固めず、キャラクターを自由に動かす「スティーブン・キング方式」で、作者の予想を超える物語が生まれた。
- Kindle出版は「実験場」: 商業出版に不向きな「変な本」の価値を証明するため、KDP(Kindle Direct Publishing)を選択。1万ダウンロードの実績が最強の「企画書」となった。
- KDPヒットの鍵は「無料」と「Unlimited」: 戦略的な無料キャンペーンで露出を最大化。収益の9割はコンテンツ購入(売り切り)ではなく、読み放題サービス(Unlimited)の既読ページ数から生み出された。
- 「商品にする」という発想転換: 商業出版にあたり、編集者から「4割カット」という非情な要求を受け入れる。読者ターゲットと価格帯を意識し、「作品」を「商品」へと磨き上げた。
- 「初速」への全集中: 無名の新人が生き残るため、発売直後の売上(初速)に全力を注ぐ。そのために「初版の印税放棄」という荒業を使い、プロモーション費用に充てた。
すべては「娘に経済を教える良い本がない」から始まった
『おカネの教室』の出発点は、著者である高井浩章氏の父親としての悩みでした。
2010年、長女が小学5年生になり、お小遣いの管理を始める時期に。「そろそろ経済の基礎を教えねば」と考えた高井氏は、書店で適切な本を探します。しかし、手堅くまとまっていても、「腹に落ちる」ような読書体験が望めないものばかりだったのです。
教科書的な解説書では、興味のない娘は読まない。馬を水辺に連れて行けても、水を飲ませることはできない。「いい本ないし、もう、自分で書いちゃおう」。経済記者という本業のスキルと、以前にも子供向けに物語を書いていた経験から、執筆はごく自然な決断でした。
深夜のヒラメキ「6つの方法」
とはいえ、何をどう伝えるか。構想を練る中で、ある深夜、決定的なアイデアが閃きます。
ふと、「『かせぐ』とか『ぬすむ』みたいな和語の動詞で経済活動を分類すれば、小学生でもとっつきやすいんじゃないか」というアイデアが浮かんだ。
そして、「お金を手に入れる方法って、いくつあるのかな」と数えてみた。
すぐに思いつくのは、上記の2つに「もらう」「かりる」「ふやす」を加えた5つ。
そして、ちょっと考えて、6つ目の方法も思い浮かんだ(ネタバレは避けます)
この「6つの方法」を物語の縦軸に据えることを決め、タイトルと設定は愛読書だった『無限論の教室』から拝借。「おカネの教室」というタイトルと、「おかしな講師が講義をする」という設定が決まりました。
「筆任せ」でキャラクターが暴走する
執筆にあたり、高井氏が採用したのは「スティーブン・キング方式」でした。これは、詳細なプロット(筋書き)を決めず、状況設定とキャラクターだけを用意し、あとは「筆任せ」で物語を進める手法です。
キング曰く、プロットは「登場人物から躍動感を奪う有害な縛り」。高井氏も、この方式で「書いている自分自身が先が読めない面白さ」を実感します。
当初は平凡な語り手のはずだった少年サッチョウさんは、勝手に大富豪の令嬢ビャッコさんに恋心を抱き始めます。作者の分身と思われがちな顧問のカイシュウ先生も、事前設定になかった過去(クオンツ)が判明し、作者の思惑を超えて物語に深みを与え始めます。
この場面は、完全に作中人物たちにストーリーテリングの主導権を握られてしまい、私は書記兼第一読者という状態で、あっという間に書きあがった。
キャラクターが勝手に動き出す「きわめて幸福な状況」。しかし、それは同時に、経済の基礎をサクッと教えるという当初の目的から、物語が「暴走」し始めたことも意味していました。
なぜ7年も? サラリーマン兼業作家の苦悩と「死の接吻」
この家庭内連載は、2010年から2016年まで、実に7年もの歳月を要しました。理由はシンプルで、著者が本業を持つ「サラリーマン記者」だったからです。
2012年末のアベノミクス相場の到来でマーケット報道チームの責任者となると、文字通り忙殺状態に。その後も未経験の部署への異動などが続き、執筆ペースは著しく低下。2014年から15年にかけては、ついに完全な「長期休載」に陥ります。
高井氏は、これをスティーブン・キングの言葉を借りて「死の接吻」と表現します。
毎日こつこつ書きつづけていないと、頭の中で登場人物が艶を失い、薄っぺらになってしまう。(中略)こうなると、仕事は苦役と変わりなくなる。大方の作家にとって、それは死の接吻に等しい。
1年も物語から離れれば、再開は「苦役」でしかありません。読者である娘の「取り立て」も甘く、提出期限のない宿題を抱えたまま日々は過ぎていきました。
転機はロンドン赴任
この「死の接吻」状態を破ったのが、2015年末に決まったロンドン赴任でした。
新しい環境、そしてまさかの「Brexit」(英国のEU離脱)という歴史的瞬間に立ち会う多忙さ。しかし、人間とは不思議なもので、忙しくなるほど、逆に「何か仕事以外で発散したい」という思いも強くなります。
ロンドンでの仕事は東京との時差もあって勤務時間は「ホワイト」で、平日夜や週末に執筆時間が確保できました。
「今、書けなかったら、自分は一生、小説を書きあげることはできないだろうな」。そんな思いが、執筆中断に伴う「苦役」に立ち向かう力をくれた。
久しぶりに原稿を読み返すと、「これ、面白いじゃないか」と我ながら感心し、凍り付いていた物語が再び動き出します。
そして、ハイライトであるピケティの格差問題に触れるシーン。高井氏自身、のけぞるほど驚いたといいますが、3人の会話の中から自然と「ピケティの不等式」が飛び出してきたのです。
この瞬間、著者は「あ、これ、本になるかも」と、家庭内連載に初めて商業出版の可能性を感じました。7年越しの物語は、ロンドンでついに完結を迎えます。
Kindle個人出版という「実験場」―1万ダウンロード達成の裏側
原稿は完成しましたが、高井氏はすぐに出版社に持ち込むことはしませんでした。
「こんな変な本は出版社からは出せないだろう」。小説のようであり、経済解説書でもある。「書店のどのコーナーに並ぶか想像できない」本は、商業出版には向かないと冷静に判断したのです。
そこで選んだのが、Kindleでの個人出版(KDP)でした。Kindleなら、この「変な本」が本当に市場価値を持つのか、読者の反応を「数字」で確かめることができます。
リライトの極意:「寝かせて、削る」
個人出版とはいえ、7年間の連載で書き散らかした原稿をそのまま出すわけにはいきません。高井氏はまず、徹底的なリライトに取り掛かります。
ここでもスティーブン・キングの教えが生かされます。それは、原稿を「寝かせる」こと。
執筆直後の原稿は、いわば我が子同然。客観的に手を入れることは困難です。高井氏は原稿を1か月寝かせ、あえて「他人になる」儀式を経ました。
いつだって、自分が愛している者より、他人が愛している者を切り捨てる方が気が楽だ。(キングの言葉)
1か月後、「他人」の目で原稿に向き合った高井氏は、冗長な描写や独白をバサバサと削り、初稿21万字超を17万字弱へと、実に2割も圧縮します。
削るだけでなく、「穴」を埋める作業も重要でした。筆任せで書いたため、キャラクター(ビャッコさん)の性格にブレが生じていたり、講義内容に混乱があったりした部分を、徹底的に修正していったのです。
KDP戦略①:「表紙」はケチるな
リライトを終え、いよいよKDPでの出版準備に入ります。KDPはAmazonアカウントさえあれば誰でもほぼノーコストで参入できる、驚くほどお手軽な仕組みです。
しかし、お手軽だからこそ「罠」があります。それは「表紙」です。
Kindleストア内で、商業出版とKDPの表紙のクオリティの違いは小さなサムネイルでも歴然としている。自分で回遊してみて「表紙が安っぽいKDP」は絶望的に読む気が起きないと悟った。
高井氏は、デザインセンスのある長女をアートディレクターに起用。ネットで素材写真を購入し、無料アプリを駆使して、商業出版に引けを取らない「顔」をわずか500円ほどのコストで作り上げました。この「顔」の良さが、後のヒットに大きく貢献したと分析しています。
KDP戦略②:レビューの光と闇
2017年3月、ついに『おカネの教室』はKindleストアに並びます。しかし、無名の新人の個人出版など、誰も気づきません。
最初に頼りになるのは「口コミ」と「レビュー」です。高井氏はここで、Amazonレビューの「闇」にも触れています。
白状しよう。私も最初、サクラを動員した。無料配布で読んでくれた友人や親類など数人に「レビューを書いて」と頼み込んだ。
これは「評価を盛りたい」というより、最初のレビュー(呼び水)がないと、他の読者が感想を書き込みにくいためです。
この「サクラ」と「グレーなお願い」によって、「ちょっと面白そうなコンテンツかも」という体裁が整いました。しかし、このレビュー戦略は諸刃の剣でもあります。
読者が広がり、順調に売れていた矢先、「爆弾」が落ちます。「1つ星レビュー」の登場です。たった1件の低評価レビューが目立つ位置に表示された途端、ダウンロード数は目に見えて3割も減少しました。Amazonレビューが売上をいかに左右するかを痛感する出来事でした。
ヒットの鍵は「無料キャンペーン」と「Unlimited」
レビューのダメージを回復させ、さらに露出を増やすために、高井氏はKDPの武器である「無料キャンペーン」を打ちます。
リリースから約1週間後、前編を対象に3日間の無料キャンペーンを実施。これが大当たりします。
- キャンペーンを週末にぶつけた。
- 事前にFacebookでターゲット層(FPや投資家など)と繋がっておいた。
- ツイッターのbotが「無料キャンペーン中」と拡散してくれた。
結果は3日間で300ダウンロード超。無料部門の総合ランキングで上位に食い込み、露出は格段に上がりました。
Amazonランキング「100位の壁」
キャンペーンの真の狙いは、その後の「露出の好循環」を生むことでした。
Amazonのランキングは、100位以内をキープすることが極めて重要だ。書影のサムネイルがランキング画面に表示されるからだ。
無料キャンペーンで知名度が上がり、有料に戻った後もランキング100位以内をキープ。すると「ベストセラー」のタグが付き、「この本を読んだ人は~」というオススメ機能にも乗る。この好循環が回り始めたのです。
KDPの収益構造:「ポチっと」から「ペラっと」へ
そして、この好循環が最も大きな影響を与えたのが、読み放題サービス「Kindle Unlimited」でした。
『おカネの教室』は、コンテンツ購入よりも、Unlimited経由での読者が爆発的に増えました。高井氏が得たロイヤリティー収入(1年強で約80万円)の実に9割は、このUnlimitedの分配金が占めていたのです。
Unlimitedの分配金は、読者が「初めてその本を読んだページ数」に応じて支払われます(1ページあたり約0.5円)。
この事実は、KDPのコンテンツ作りに重要な示唆を与えます。
端的に言えば、「エロい表紙で読者を釣っても銭にならん」のである。
購入型サービスなら「ポチっと」させれば儲かる。
KDPではそれは通じない。読者が10ページで放り出せば、作者には5円ほどしか入ってこない。最後までページをめくってもらえるコンテンツでなければ、もうからない。
「ポチっと(購入)」から「ペラっと(読了)」への革命。コンテンツの「中身」が問われる世界で、『おカネの教室』は読者に受け入れられました。
このKDPでの「1万ダウンロード突破」という圧倒的な実績は、商業出版への最強の「企画書」となったのです。
コネゼロからの挑戦―商業出版の厚い「壁」
KDPでの成功を受け、高井氏は2017年5月、ついに商業出版化へ動き出します。
本業のグループ内出版社から出す、という「簡単な道」もありましたが、彼はあえて「他社」から「ペンネーム」で出す道を選びます。
- 身内ではないプロの目で価値を測ってもらいたかった。
- この本を「業務」ではなく、最高の「遊び」にしたかった。
- 「著者・高井浩章」という別の世界を持ちたかった。
しかし、「ツテ・コネゼロ」の著者を待っていたのは、冷たい現実でした。
大手の出版社はほぼすべて「持ち込みお断り」だったのだ。(中略)各社のスタンスは「無名の新人はまずウチの文学賞に応募してこい」というものだった。
問い合わせフォームから連絡しても、返ってくるのは「持ち込みは受け付けていません」というテンプレばかり。
全公開!ヒット実績を武器にした「出版企画書」
高井氏は戦略を切り替え、「出版提案・持ち込みはこちらから」という窓口を持つ出版社をリストアップ。売り込み先を7社に絞ります。
その際、武器となったのがKDPの実績です。彼が送った企画書には、「概要」や「著者プロフィル」に加え、「3カ月で読み放題で60万ページ以上が読まれ、ダウンロード数換算で約6000冊のヒットを記録」という具体的な数字が盛り込まれていました。
この企画書には数社から好反応がありましたが、高井氏が「ダメ元」で送っていたミシマ社からも連絡が入ります。
「早い者勝ち」戦略とミシマ社の即断力
複数の出版社から「出版に前向き」という反応を得て、著者は想定外の「モテ期」を迎えます。
同業者として編集者の多忙さを知る高井氏は、各社を天秤にかけるような失礼はせず、「早い者勝ち」、つまり「最初に出版を確約してくれた会社から出す」と決め、その旨を各社に伝えました。
期せずして「企画会議通したモン勝ち短距離走」がスタート。他の出版社が社内プロセスを進める中、見事な差し脚でゴールしたのは、ダークホースのミシマ社でした。
弊社の場合、企画会議に社長が必ず出るのと、社長がゴーと言わないかぎり企画が動かないので、ひとまず社長のゴーサインは出ている状況です。
少人数体制ならではの、シンプルでスピード感のある意思決定プロセスでした。こうして、『おカネの教室』はミシマ社とインプレスの共同レーベル「しごとのわ」から発売されることが決定したのです。
編集者との「バトル」―「商品」として本を磨き上げるということ
出版は決まりましたが、本当の「本づくり」はここからでした。編集アライ氏との、妥協なき「バトル」の始まりです。
盲点だった「商品にする」発想
リライト作業中、編集者から不穏なメールが届きます。
1ページを39字×15行づめにすると380ページoverという状態でして、読み物ビジネス書だと、ページ数がいっても240ページかな…というところなので、けっこうざっくり、カットする必要がありそうです。
これは実質「4割削り」という要求。「それは、ない!」と強硬に反論する高井氏に対し、編集者は2つのポイントを指摘します。
- 「経済初心者」には400ページはハードルが高い。
- 価格を1500~1600円にしたい。400ページでは1800円程度になる。
高井氏は、この指摘に「盲点だった」と衝撃を受けます。
要は、私には「本を商品として仕上げる」という思考が欠けていたのだ。
ほぼノーコストで出版できて、価格も適当に付けられる個人出版と「商品としての本を作る」商業出版は、全く別の世界なのだった。
「作品」への愛着を断ち切り、「商品」としてターゲット読者に届ける。この覚悟を決めた高井氏は、KDP版からさらに3割を削るという大規模なリライトに取り掛かります。
リライトという「とんかち仕事」の快感
この作業は、苦痛どころか「実に楽しかった」と高井氏は振り返ります。
村上春樹氏が言うところの「とんかち仕事」。文章を音読し、リズムを確かめ、語順を入れ替え、また書き直す。
「とにかく削らねば」という必要に迫られて始めた作業だったが、「同じ削るなら、徹底的にリズムがあって読みやすく、分かりやすい、一気読みできるものにしてやろう」と取り掛かると、それは知的なゲームへと変わった。
この徹底的なリライトにより、『おカネの教室』は、まったりとした読み物から、スピード感のある「一気読みコンテンツ」へと生まれ変わりました。
タイトル論争:「おカネの教室」以外あり得ない!
原稿が固まる一方、最大のバトルが「タイトル」を巡って勃発します。
編集者から「『おカネの教室』だと、いわゆる金融入門みたいなイメージが湧いてしまうので、タイトルはやはり、要検討かなと…!」という提案が来たのです。
長年親しんできたタイトルであり、KDPでの実績もある。高井氏は即座に反論します。しかし、編集者の「この本が青春経済小説であるようなことがなんとなく伝わり、数多くあるお金本のなかで、抜けだすことができる」タイトルを考えたい、という熱意に押され、苦悩のタイトル探しが始まります。
考え抜いた末、高井氏は「やはり『おカネの教室』は替えがきかない」という確信を深めます。
「小説のタイトルは『問い』であり、本文はそれに対する答えだ」
このタイトルには、登場人物たちの造形や言動を引っ張る引力があり、彼らが動き回れる「教室」という空間を形作ってきた。この「答え(作品)」に対して、これ以外の「問い(タイトル)」はあり得ないと。
最終的に、編集者が書店員に「現場の声」を聞きに行くという足で稼ぐ調査も行い、「おカネの教室」という幹は残しつつ、「僕らがおかしなクラブで学んだ秘密」という、物語性を感じさせるサブタイトルを付けることで決着しました。
発売即重版!「初速」を生んだマーケティング戦略
2018年2月、発売まで約1か月。ロンドンから一時帰国した高井氏は、編集者・版元と対面し、「この変な本をどうやって売り込むか」という作戦会議に臨みます。
荒業・「初速」への全集中
会議で繰り返し出たキーワードは「初速」でした。
新陳代謝の激しいビジネス書の中で、無名の新人の本が生き残るには、発売直後のスタートダッシュがすべて。書店に「置けば売れる本」と認識させなければ、すぐに店頭から消えてしまいます。
この「初速」を最大化するため、高井氏はかねてある「武器」の投入を提案していました。
「武器」とは、初版分の印税のことだ。私は「初版分は印税はいらないので、それをプロモーションに投入してほしい」と提案していたのだった。
この「燃料」を元手に、特製ポスターや数万枚のしおり、特製名刺の作成など、プロモーション施策が次々と決まっていきます。
「真剣にやれ! 仕事じゃねーんだぞ!」という名文句がある。「遊ぶ」なら。本気でやらないと楽しめない。
著者の「本気の遊び」が、チーム全体の「熱」を高めていきました。
デザインと「縁」の力
この熱量は、デザインにも表れます。超売れっ子の佐藤亜沙美氏が手掛けた装丁と、ウルバノヴィチかな氏が描いたイラスト。
特にキャラクター画が届いた時の衝撃を、高井氏はこう語ります。
私が驚いたのは、サッチョウさんの寝ぐせだった。
見た瞬間、「これだ! こいつが、サッチョウさんだ!」とイメージが一気に固まった。
作者の中でさえ明確でなかったキャラクター像に、イラストレーターが命を吹き込んだ瞬間でした。
「面白いは正義」―なぜこの本はビジネスパーソンにも刺さるのか
『おカネの教室』には、「小説としては浅い」という批判も寄せられるといいます。
著者は「ごもっとも」と認めつつ、「だが、しかし」と続けます。
高井氏にとって小説とは、小難しい「深さ」や芸術性ではなく、「読んでいる間、その世界や文章に浸り、引き込まれてページをめくってしまう読み物」でしかありません。
「面白いなー」と読み進めて、最後までページをめくって「面白かった!」と思えれば、それは良い小説だ。
『おカネの教室』は、「経済解説がストーリーの軸になっている青春小説」です。もしビジネス書としてリライトしていたら、「ありふれた経済入門書」になっていたでしょう。
「変な小説」のまま世に出たからこそ、類書のないユニークな本として、普段ビジネス書を読まない層にまで届きました。
インタビューで著者が語った「お金は怖くて、面白い」という言葉。この両面性を、退屈な解説ではなく、血の通った物語として描いたこと。それこそが、多忙なビジネスパーソンの心にも響く、最大の理由なのかもしれません。
8年の時を経て、家庭内連載は「本」となり、著者の夢は叶いました。この『「おカネの教室」ができるまで』という物語は、ひとつのコンテンツが熱量と戦略によって磨き上げられていく、最高の「本づくりの教科書」と言えるでしょう。