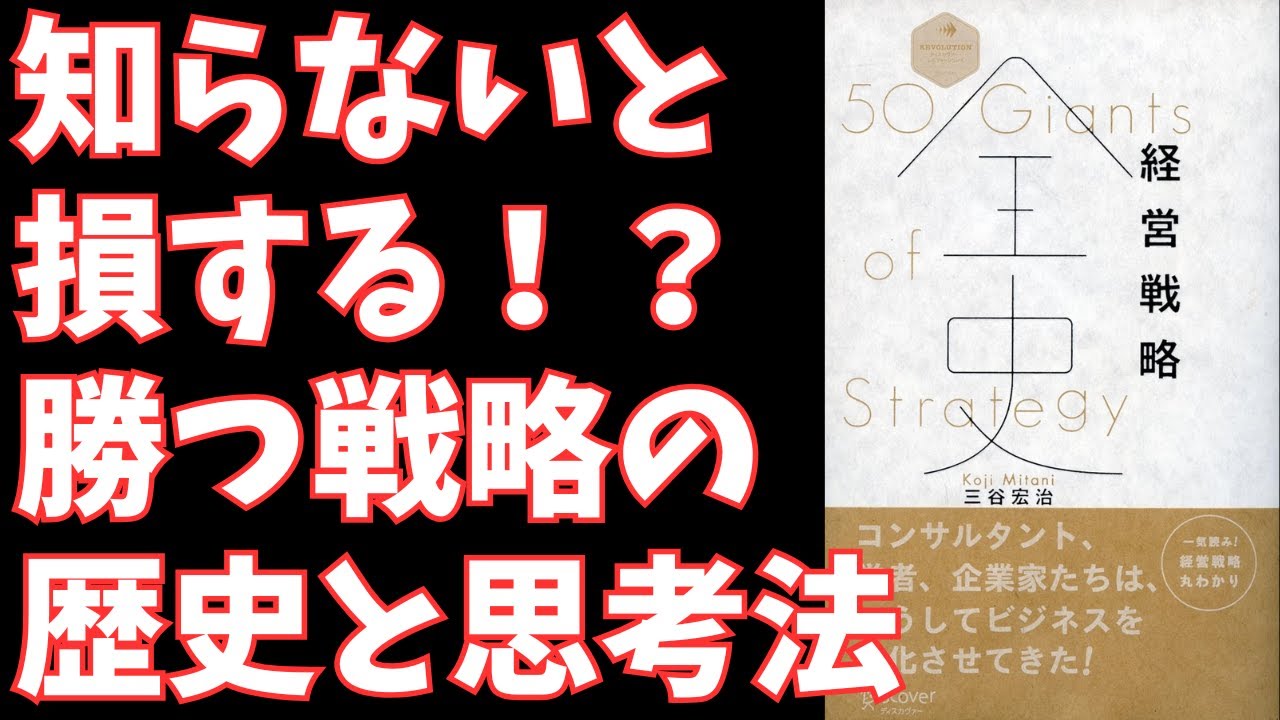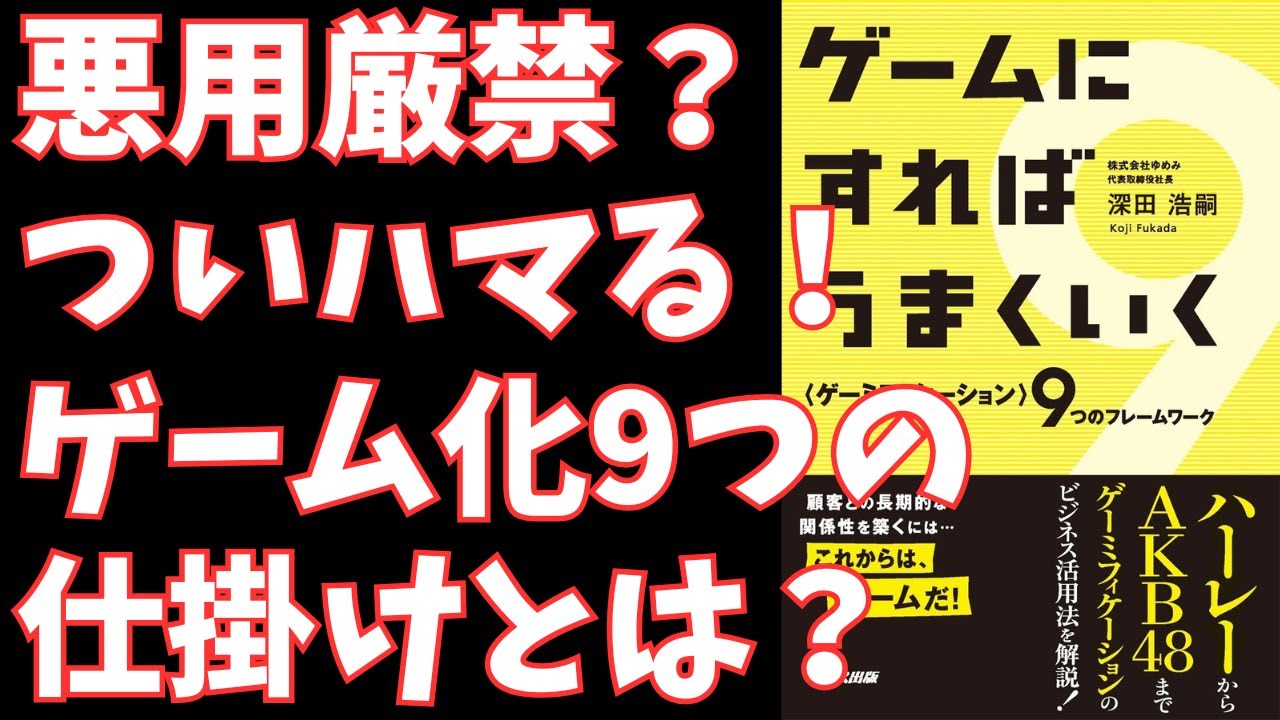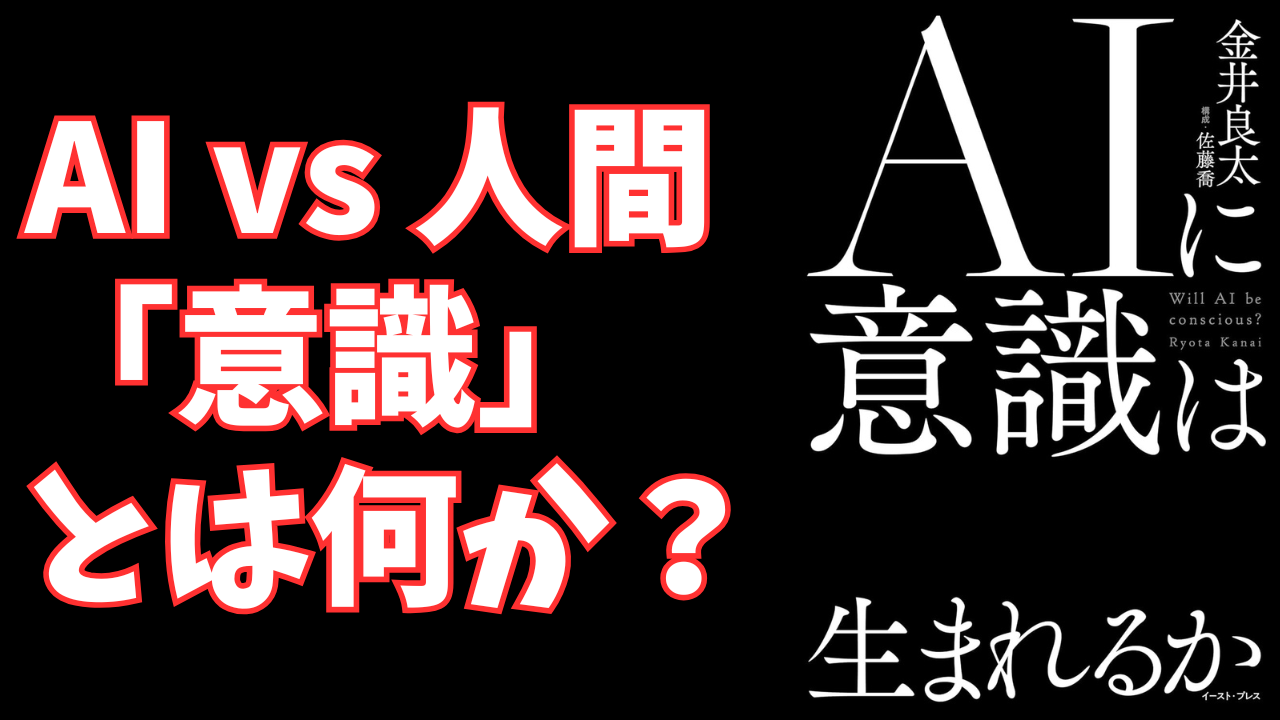『おカネの教室』はビジネスパーソンの必読書!物語で学ぶ金融リテラシーの神髄
本書『おカネの教室 僕らがおかしなクラブで学んだ秘密』は、中学2年生の少年少女が、謎のクラブ活動を通じてお金の本質を学んでいく物語形式の経済入門書です。著者は20年以上の経験を持つ経済記者、高井浩章氏。
難解な金融の仕組みや経済のカラクリが、登場人物たちの対話を通して、驚くほど分かりやすく解説されています。本記事では、この物語に散りばめられた核心的な教えを、日々忙しく働くビジネスパーソンの視点から深掘りし、明日からの仕事や人生に活かせる学びをお届けします。
本書の要点
- お金を手に入れる方法は「かせぐ」「もらう」「ぬすむ」「かりる」「ふやす」「つくる」の6つに本質的に分類できる。
- 真に「かせぐ」とは、単に利益を上げることではなく、社会全体の富を増やし、世の中を豊かにすることに貢献する行為である。
- 市場経済は「神の見えざる手」によって最適化されるが、その根幹をなすのは人々の「信用」であり、それが失われると経済は機能不全に陥る。
- 世の中にはギャンブルや売春といった、なくすことのできない「必要悪」も存在し、理想論だけでは語れない現実を直視する必要がある。
- お金そのものの本質は、誰もがその価値を信じているという「信用」に基づく共同幻想であり、この理解こそが金融リテラシーの出発点となる。
「そろばん勘定クラブ」で問われる、あなた自身の値段
物語は、主人公である中学2年生の木戸隼人(サッチョウさん)が、不人気で誰も来ない「そろばんクラブ」に仕方なく入部するところから始まります。そこに現れたのは、規格外の巨体を持つ顧問のエモリ先生(カイシュウさん)。彼は「そろばんはいりません」と言い放ち、クラブ名を「そろばん勘定クラブ」へと書き換えます。
そして、サッチョウさんと、もう一人の部員であるお嬢様の福島乙女(ビャッコさん)に、最初の問いを投げかけます。
あなたのお値段、おいくらですか?
この突拍子もない問いに、あなたならどう答えるでしょうか。
サッチョウさんは、ごく一般的なビジネスパーソンのように考えます。大学を出て40年働き、平均年収500万円を稼ぐと生涯賃金は2億円。そこから生活費などを引いて、「1億円ぐらい」と答えます。これは、自分の「労働」を価値の源泉と捉える考え方です。
一方、裕福な家庭に育ったビャッコさんは、全く異なる視点から答えます。
「わたしが誘拐されたら、祖母がそれぐらいの身代金なら払うと思います」
その金額は、「10億円ぐらい」。これは、他者(この場合は祖母や誘拐犯)が自分に付けるであろう価値、つまり「資産」としての価値から値段を弾き出したものです。
カイシュウ先生は、この二人の答えから、お金を手に入れる最初の3つの方法を提示します。
- かせぐ(サッチョウさんのアプローチ)
- ぬすむ(誘拐犯の視点)
- もらう(ビャッコさんの相続という隠れた視点)
このクラブは、このように日常的な視点からお金の本質をあぶり出していく、知的で刺激的な冒険の場なのです。ビジネスの現場で日々数字と向き合っている私たちも、改めて「自分の価値の源泉は何か?」と問われると、即答するのは難しいかもしれません。本書は、そんな根源的な問いから、私たちをお金の探求の旅へと誘います。
「かせぐ」と「ぬすむ」を分ける境界線とは?
クラブの議論は、「かせぐ」と「ぬすむ」の違いは何か、というテーマに進みます。サッチョウさんの父親は消防士。これは文句なしに「かせぐ」仕事です。では、世の中に数多ある職業の中で、その境界線はどこにあるのでしょうか。
二人は「その仕事が世の中の役に立つかどうか」という基準を打ち立てます。そして、それぞれが「役に立つ仕事」「立たない仕事」の例を挙げていく中で、物語は核心に迫ります。
ビャッコさんが「役に立たない仕事」として挙げたのは、「高利貸し」「パチンコ屋」「地主」の3つ。そして、衝撃的な事実を告白します。その3つはすべて、彼女の家族が営む家業だったのです。
「誰も幸せにならない仕事だからです」
彼女は、自らの家業をそう断じます。お金に困って借金をする人、パチンコにのめり込む人、そして生まれつき土地を持っているだけで儲かる不公平さ。ビャッコさんの悩みは、多くの人が資本主義社会に対して抱く素朴な疑問や違和感を代弁しています。
あなたの仕事は、胸を張って「世の中の役に立っている」と言えるでしょうか。利益を追求するあまり、誰かを不幸にしてはいないでしょうか。本書は、ビャッコさんの苦悩を通して、ビジネスにおける倫理とは何かを鋭く問いかけます。
リーマンショックの教訓 – 金融マンはなぜ「ダニ軍団」になったのか
物語は、カイシュウ先生が挙げた職業「銀行家」の議論を通して、2008年に世界を震撼させたリーマンショックの本質に迫ります。なぜ、世の中の役に立つはずのエリート集団である銀行家が、世界経済を破綻寸前にまで追い込んだのでしょうか。
カイシュウ先生は、そのカラクリを「たちの悪い『ジジ抜き』」と表現します。
危機の根源は、所得の低い人々への無謀な住宅ローンでした。しかし、銀行はさらに悪質なことを行います。「証券化」という金融テクノロジーを使い、貸し倒れのリスクを細切れにして世界中の投資家に売りさばいたのです。
本質は、優秀な銀行家たちがなぜそんなバカなマネをしたのか、です。(中略)本当に優秀な人間は、こんなことはいつか破綻するとわかっていながら、やっていたんです。
その理由はたった一つ。「もうかるから」です。
銀行自体が最終的に大損をしても、破綻する前に担当者個人が巨額のボーナスを手にしてしまえば関係ない。まさに「もうけは銀行家、損は国民に」という構図です。
そして、カイシュウ先生は衝撃の告白をします。
「なぜなら、ワタクシもかつてダニ軍団の一員だったからです」
物理学の研究者を志すも挫折し、金融の世界に飛び込んだカイシュウ先生。彼は「クオンツ」と呼ばれる高度な数学を駆使する金融マンとして巨万の富を稼ぎましたが、その仕事が社会に何の価値ももたらさないことに気づき、業界を去った過去を持っていたのです。
彼の言葉は、金融業界の内部にいた者だからこそのリアリティと重みを持っています。ビジネスパーソンとして高い専門性を追求することは重要ですが、そのスキルが社会に対してどのような価値を生むのか、常に自問自答する必要があることを、このエピソードは教えてくれます。
「フツー」が世界を豊かにする – GDPと「持ち場を守る」ということ
議論が深まるにつれ、「役に立つ・立たない」という二元論では割り切れない問題が浮上します。そこでカイシュウ先生が投入する新兵器が「もらう」を「フツー」と位置づける考え方です。
- かせぐ → とても役に立つ(公園を綺麗にする人)
- もらう → フツー(自分のゴミは片付ける人)
- ぬすむ → 役に立たない(公園を汚す人)
彼は、「人間、フツーで十分なんです」と説きます。なぜなら、一人ひとりが「かせぐ」レベルでなくても、多くの人が「フツー」に社会に参加し、自分の役割を果たすだけで、国全体の豊かさ(GDP)は増大していくからです。
この「フツー」の価値を象徴するのが、社会見学で訪れた食品トレー工場の光景です。そこでは、多くの知的障害を持つ人々が働いていました。彼らが担当するのは、リサイクル材料を仕分ける単純作業。健常者にとっては精神的に厳しい仕事ですが、彼らは驚異的な集中力を発揮します。
彼らの仕事ぶりについて、現場のリーダーである梅村さんはこう評します。
「フツーだね」
彼らは障害を持ちながらも、自分の得意な仕事で社会に貢献し、世間並みの報酬を得ています。カイシュウ先生は、こうした人々も「もらう」に含まれる「フツー」なのだと語ります。
ビジネスの世界では、常に卓越した成果を出す「かせぐ」人材がもてはやされます。しかし、社会全体を支えているのは、自分の「持ち場を守る」大多数の「フツー」の人々です。この視点は、組織のマネジメントやチームビルディングにおいても、非常に重要な示唆を与えてくれるでしょう。
投資の本質 – 「神の見えざる手」のお手伝いとは?
物語の後半、クラブは「かりる」と「ふやす」というテーマに挑みます。その応用編として訪れたのは、カイシュウ先生の知人・高山さんが経営する資産運用会社でした。
高山さんの仕事は、顧客から預かったお金を「いい会社」に投資し、その成長を応援すること。彼は、投資先を徹底的に調査し、企業の20年後の未来予想図まで描きます。なぜ、そこまでやるのか。高山さんはその理由をこう語ります。
「我々の仕事が、神様のお手伝いだからです」
これは、経済学の父アダム・スミスが提唱した「神の見えざる手」という概念につながります。
市場に参加する企業や投資家が、それぞれ自分の利益を追求して行動すると、結果的に、社会全体にとって最も効率的な資源配分(良い会社にお金が流れること)が、まるで神の見えない手が導いたかのように実現される、という考え方です。
高山さんの仕事は、まさにこの「神の見えざる手」が正しく機能するように、資本(ビジネスの元手)を最適な場所に届けるお手伝いなのです。
企業は資本を使って『かせぐ』に値する富を生み出すからです。市場経済の主役は企業です。リスクを取って企業に大事なお金を投じる投資家は経済成長を支える陰の主役です。投資でもうけたいだけであっても、それが世のため人のためになる。
この説明を通して、サッチョウさんとビャッコさんは、不動産や株式への投資もまた、リスクを引き受けて経済成長に貢献する、まっとうな「かせぐ」行為なのだと理解します。
投資と聞くと、マネーゲームのような虚しいイメージを持つ人も少なくありません。しかし、その本質は、未来を担う企業を応援し、社会全体の富の増大に貢献する極めて重要な経済活動なのです。
格差はなぜ広がる? 地主は「かせぐ」人か
投資が「かせぐ」行為であるという結論に至ったものの、サッチョウさんとビャッコさんの中にはモヤモヤが残ります。それは、「投資という『かせぐ』道は、元手のある金持ちにしか開かれていない」という不公平感です。
ここでカイシュウ先生は、現代経済学の最重要テーマの一つである、経済学者トマ・ピケティの不等式を紹介します。
r > g
これは、資本収益率(r)は、経済成長率(g)よりも大きいことを意味します。平たく言えば、資産運用(投資)でお金が増えるペースは、労働で給料が上がるペースよりも速いということです。
この不等式が意味するのは、一度まとまった資産を築いた富裕層は、複利の効果も相まって雪だるま式に富を増やしていく一方、資産を持たない庶民との格差はますます拡大していく、という残酷な現実です。
カイシュウ先生は、この構造的な問題に加えて、「相続税」の問題や、富裕層や大企業が税金を逃れるために利用する「オフショア(租税回避地)」の存在が、格差問題をさらに深刻化させていると指摘します。
これらの問題は、一国の努力だけでは解決が難しい、現代のグローバル資本主義が抱える根深い課題です。本書は、単純な答えを示すのではなく、ビジネスパーソンとして、また一人の社会人として、この複雑な現実を直視し、考え続けることの重要性を教えてくれます。
最後の謎解き – お金の本質は「つくる」ことにある
物語のクライマックス、カイシュウ先生は最後の宿題を出します。お金を手に入れる6番目の、そして最も本質的な方法とは何か。
サッチョウさんとビャッコさんは、駄菓子屋で見つけた「こども銀行券」からヒントを得て、ついに答えにたどり着きます。
その答えは、「つくる」でした。
お金がなければ、作ってしまえばいい。この一見単純な答えは、実はお金の根源的な性質を突いています。
カイシュウ先生は、銀行の「信用創造」という仕組みを解説します。
銀行は、預金者から集めたお金の一部(準備金)だけを手元に残し、残りを企業や個人に貸し出します。貸し出されたお金は、回り回って別の銀行に預金され、その預金がまた新たな貸し出しを生む。この連鎖によって、社会全体のお金の量は、最初に存在した現金の何倍にも膨れ上がるのです。
これは、まさに銀行ネットワークが信用(貸し借り)を通じてお金を「つくる」行為に他なりません。
では、なぜただの紙切れや電子データであるお金に価値があるのでしょうか。
お金とは共同幻想なのです。みんながお金に価値があると幻想をいだいている。だからお金がお金たり得る。
その幻想を支えているのが、ビャッコさんが看破した「約束」であり「信頼」です。「このお札を出せば、誰もがモノやサービスと交換してくれるだろう」という社会全体への信頼感こそが、お金の価値の源泉なのです。
お金というものは、人間が互いに支え合わないと生きていけない存在であるが故に生まれた、知恵の結晶だと思います。
この結論は、私たちがお金に対して抱くべき姿勢を示唆しています。お金は単なる交換の道具ではなく、人間社会の信頼関係そのものを映し出す鏡なのです。だからこそ、私たちはそれに惑わされることなく、しかし大切に扱い、より良い社会を築くために活用していくべきなのでしょう。
『おカネの教室』は、単なる金融入門書ではありません。それは、私たちが生きる資本主義社会の光と影を描き出し、その中でいかにして豊かに、そして正しく生きていくべきかを問いかける、現代人のための哲学書と言えるかもしれません。