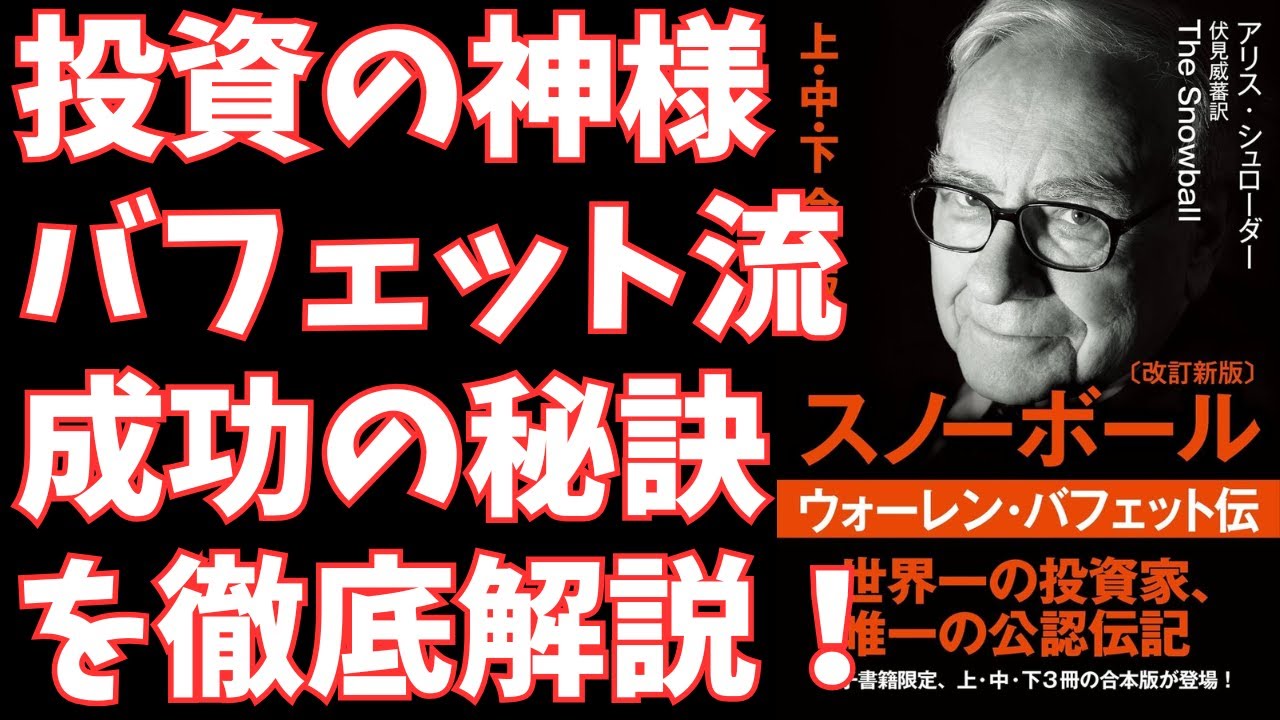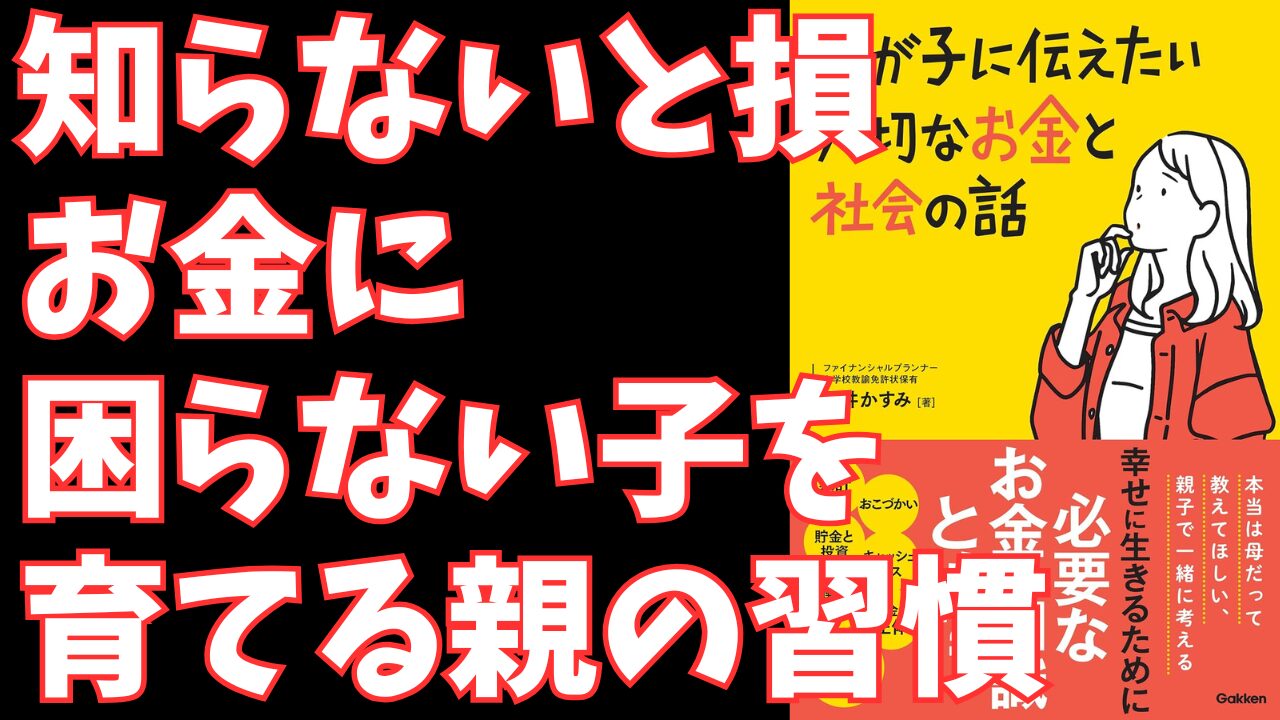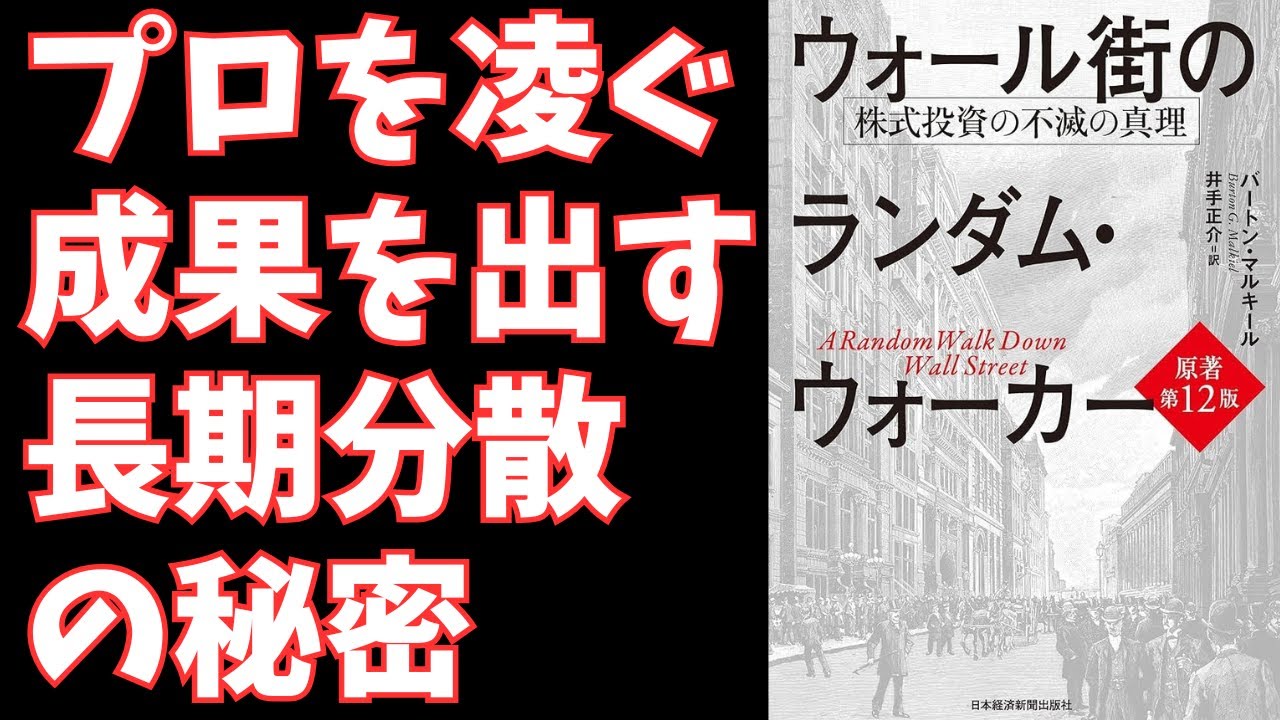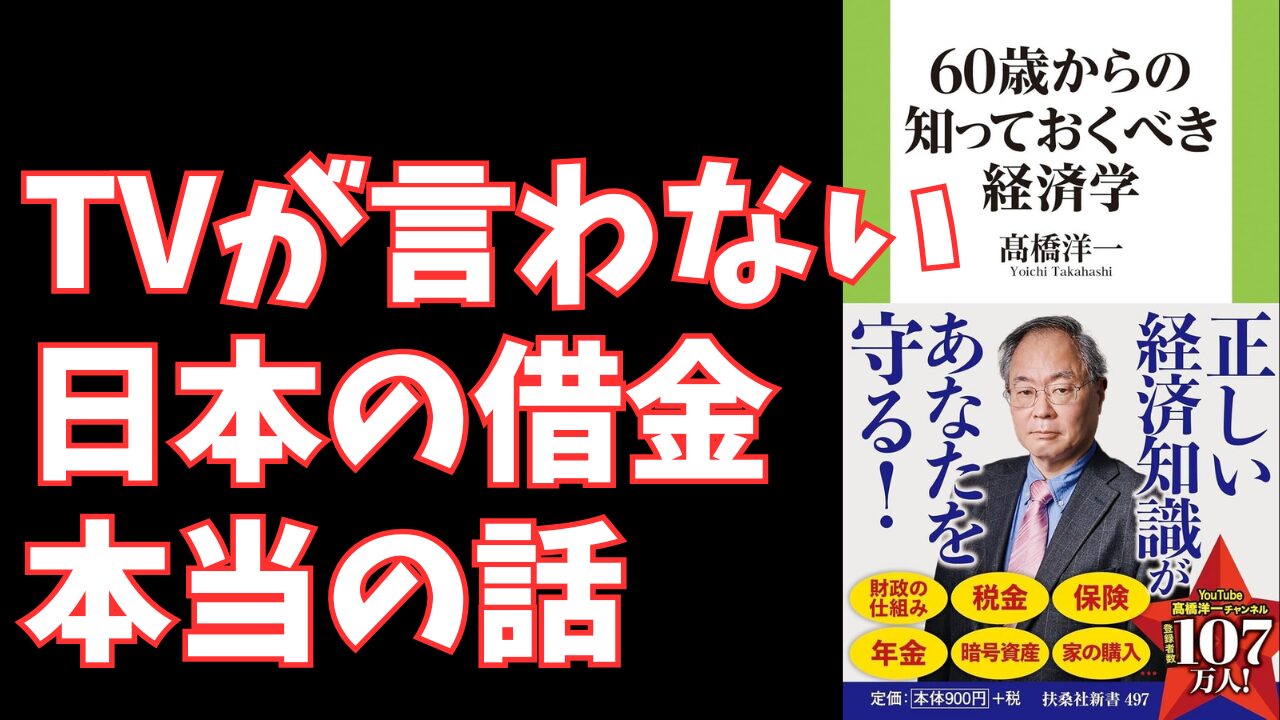『億までの人 億からの人』から学ぶ富裕層の思考法|ゴールドマン・サックス元幹部が明かす「兆人」のマインド
本書は、ゴールドマン・サックス証券で17年間、投資部門のトップまで務めた著者・田中渓氏が、300人以上の超富裕層との交流から学んだ「億を超える人」の思考法、習慣、哲学を解き明かす一冊です。
具体的な投資銘柄を推奨するノウハウ本ではなく、 富裕層のマインドセットそのものを学ぶこと に主眼が置かれています。 なぜなら、人は想像できないものにはなれないからです。 本書を通じて富裕層の生態系をリアルに知ることで、誰もが「億を超える人」になれる可能性が生まれます。
この記事では、忙しいビジネスパーソンが明日から実践できる本書の核心的なエッセンスを、具体的なエピソードと共に詳しく解説していきます。
本書の要点
- 「お金に働かせる」のが常識:富裕層は「給与以外の収入ゼロ」を最大のリスクと捉え、投資をしない人はいません。お金は眠らせず、働かせることが大前提です。
- 「確実性」より「スピード感」を重視:億を超える人は、意思決定の速さを最優先します。たとえ間違っていても、迅速に行動し、失敗から学ぶことで圧倒的な経験値を積み上げます。
- 「時間」を最強の武器にする:誰にも平等に与えられた有限の資源である「時間」を最も重要視します。ルーティンや仕組み化によって時間を捻出し、自己成長のための学習や経験に投資します。
- すべての出費は「投資」か「消費」か:お金を使う際は、その出費が将来のリターンを生む「投資」か、単なる「消費」かを常に問いかけます。人脈や知識、経験といった無形資産につながるお金の使い方を徹底しています。
- 「信頼貯金」で人脈を築く:人間関係も分散投資と捉え、複数のコミュニティに属します。日々の小さな行動で「信頼貯金」を積み重ね、それが良質な人脈と新たな機会を引き寄せます。
なぜ今「富裕層マインド」を学ぶべきなのか?
「会社が明日終わるかもしれない」――。
著者の田中渓氏は、入社1年目で経験したリーマンショックの衝撃をこう語ります。 部署の9割の人員が削減され、ボーナスゼロという壮絶な環境を生き抜いた末に、投資部門のトップである日本共同統括にまで上り詰めました。 その17年間の会社員生活で交流したのは、20か国以上の社内外300人を超える「億円」資産家、「兆円」資産家、産油国の王族といった超富豪たちです。
本書は、彼らの哲学や思考、習慣といった「生態系」を解き明かし、誰でも実践可能な「富裕層マインド」を伝授するものです。
多くの人は、富裕層を「特別な能力や環境に恵まれた人」と考えがちです。しかし著者は、 「実際の多くの富裕層は、『普通のことをやっている普通の人たち』です」 と断言します。
ただし、決定的な違いが一つあります。それは、誰でもできる当たり前のことを 「圧倒的」に「やる」 という点です。
挑戦しなければ、成功の可能性はゼロのままです。しかし、挑戦さえすれば、たとえ失敗しても経験値は残り、成功の可能性が生まれます。 本書で語られる富裕層マインドは、挑戦するすべてのビジネスパーソンにとって、その可能性を大きく高めるための羅針盤となるでしょう。
「億を目指さないと、億は手に入らない」富裕層の思考の原点
ウォルト・ディズニーの「想像したことは現実になる」という言葉は有名ですが、著者は「想像すらできていないことは実現しようがない」とも言います。
「年収1,000万円を目指そう」と思えば、そこがゴールになります。その人が1億円を手にすることはまずありません。 しかし、 「年収1億円を目指そう」と決意した瞬間から、脳は「どうすれば達成できるか?」と具体的な道筋を探し始めます。 億の世界をどれだけリアルに想像できるかが、すべてのはじまりなのです。
著者がいた投資業界では、会社にもたらした利益に対して、自分がもらえる報酬をおおよそ計算できました。 「年収1億円」というゴールを設定すれば、そこから逆算して「今月何をすべきか」「今日何をすべきか」が明確になります。
もし目標を達成できなければ、それはゴール設定が間違っていたか、そこへの道筋が誤っていたか、あるいは努力が不足していたかのいずれかです。 まずは目標を大きく持ち、そこへ向かうための想像力を働かせ、確実に行動に移す。これが富裕層の思考の基本です。
「給与以外の収入はゼロ」はハイリスク
稼ぐ人たちが当たり前に実践していること、それは 「お金にお金を稼がせること」 、つまり運用です。 彼らは、お金を運用しないこと自体がリスクだと知っています。
「収入は給与のみ」という状況には2つの大きなリスクがあります。
- 収入源が断たれるリスク:会社の倒産や自身の健康問題で働けなくなれば、収入はゼロになります。
- インフレ耐性がないリスク:物の値段が上がり、相対的にお金の価値が下がるインフレが進むと、銀行に預けているだけのお金の実質的な価値はどんどん目減りしていきます。
お金を運用せず、日本円だけで保有している状態は、数ある投資選択肢の中から、あえて100%「日本円」という一つの金融商品に全力投資しているのと同じことなのです。 「億を超える人」たちは全員、このリスクを理解し、お金に働かせています。
富裕層への2つのルート:「金融エリート系」と「ベンチャー経営者系」
著者は、これまで出会ってきた富裕層を大きく2つのパターンに分類できると述べています。 それが「金融エリート系」と「ベンチャー経営者系」です。
金融エリート系:ミドルリスク・ミドルリターンで着実に登る
東大、京大、あるいは海外の一流大学を卒業し、投資銀行やコンサルティングファームを渡り歩く人々。 彼らは非常に優秀ですが、給与収入だけでは「5,000万円の壁」を超えるのは難しいと言われています。
彼らが億の壁を超えるきっかけは、 完全成果報酬型のファンドへの転職 です。 会社の資金で投資を行い、利益に応じた成功報酬を得ることで、億単位の収入を実現します。 彼らの特徴は、大きな失敗を避けること。会社の資金で投資するため、個人で大きな借金を背負うリスクは限定的です。 いわば、ミドルリスク・ミドルリターンの王道を、圧倒的な熱量で突き進むことで富を築く「ブックスマート」的な富裕層です。
ベンチャー経営者系:ハイリスク・ハイリターンで道を拓く
20代後半から40歳くらいで成功を収めることが多いこのタイプは、学生起業やスピンアウトなど、多様なルーツを持ちます。 彼らが富を掴むきっかけは、 自ら起こした事業の上場(IPO)や企業買収(M&A) です。
これはハイリスク・ハイリターンな道であり、成功するまで何度でも立ち上がる精神力が求められます。 そして一度成功すると、その実績が信用の証となり、「あの成功者が出資している企業なら」と、次の有望なスタートアップへの投資話が舞い込んできます。 彼らのお金には「色」がつき、お金がお金を呼ぶ無限ループに入っていくのです。 これは、ストリートで戦いながら道を切り拓く「ストリートスマート」的な富裕層と言えるでしょう。
あなたはどちらのタイプに近いでしょうか?自身の性格や目指す方向性を見極め、戦略を立てることが重要です。
【事例】金融リテラシーがあれば2,000万円のマンションが1億円で売れる
本書には、著者のリアルな体験談が数多く登場します。中でも、金融リテラシーの重要性を象徴するのが、ある不動産取引のエピソードです。
著者は都内に2,000万円程度で中古マンションの一室を投資用に保有していました。 ある日、ポストに不動産会社から「2,800万円で買います」という手紙が入ります。 40%の利益なので、通常なら喜んで売却するところでしょう。
しかし著者は、その手紙が手書きで、わざわざ自宅ポストに投函されていたことに違和感を覚えます。 自分で調査した結果、マンション周辺で「地上げ」が進行中であることを突き止めました。 もし地上げが成功すれば、土地の価値は4~5倍になる可能性がありました。
つまり、不動産会社は2,800万円で買い取っても、全く損をしない計算だったのです。
著者はしばらく静観を続けます。すると、案の定「3,500万円で」と次の連絡が。 それでも著者は動かず、いよいよ自分の部屋だけが残る状況になってから、交渉のテーブルにつきました。
そして、 「1億円以下では売るつもりはありません」 と告げ、最終的にその価格で売却することに成功したのです。
「何か事情がありそうだ」と気づく観察眼。お得な話に飛びつかない冷静さ。自分で調べ、事実を把握する行動力。そして、フェアバリューを見極め、強気に交渉する力。これらすべてが、 金融リテラシー のなせる業です。知識があるかないかだけで、結果にこれほど大きな差が生まれるのです。
その出費は「投資」か「消費」か?富裕層のお金の使い方
富裕層は、お金を使うときに常に自問します。 「その出費は、投資か、消費か?」 と。
これは、単なる節約とは全く異なる概念です。
例えば、ホリエモンこと堀江貴文氏と寿司を食べる15万円のイベントがありました。 ただ寿司を食べるだけなら、これは高額な「消費」です。しかし、自分のビジネスプランを彼にぶつけ、フィードバックを得るという明確な目的を持って参加するなら、それはキャリアを大きく変える可能性を秘めた「投資」になり得ます。
富裕層は、たとえ1兆円持っていたとしても、不当にお金が抜かれるようなビジネスにはお金を使いません。 彼らは、その値段がフェアかどうかを常に見極めています。
高級車フェラーリを買う理由も同じです。単なる見栄で乗るのではなく、「資産価値が落ちにくいため、リセールバリューが高い」という投資的な側面や、「オーナーズクラブを通じてしか得られない特別な人脈が手に入る」という価値を重視します。
日常生活においても、 「自分の時間とお金をそこに費やすなら、もっと効率のいい方法はないか?」 を考えます。 家事をハウスキーパーに頼み、そこで生まれた時間を自己投資や家族との時間にあてる。これは、人的リソースにレバレッジをかける「投資」なのです。
あなたも明日から、お金を使う際に「これは投資か?消費か?」と自問してみてはいかがでしょうか。その意識を持つだけで、お金の使い方の質が劇的に変わるはずです。
「習慣化」は最強の武器である
もし、人生で何か一つだけ強力な武器を身につけられるとしたら、それは 「習慣化」の技術 だと著者は確信しています。
「お金が貯まったら」「時間に余裕ができたら」という言葉は、実行しないための言い訳に過ぎません。 しかし、一度「習慣」にしてしまえば、意思の力を使わずに、当たり前のように行動を継続できます。
著者は365日、毎朝3時45分に起床し、「25km走る」「60km自転車に乗る」「7000m泳ぐ」のいずれかをこなす生活を6年以上続けています。 ここまで極端でなくとも、学習を習慣化するだけでも、人生は大きく変わります。
人間の脳は、学んだことを1日後には74%も忘れてしまうと言われています(エビングハウスの忘却曲線)。 しかし、繰り返し復習することで記憶は定着します。
習慣化を成功させる3つのコツ
- 死ぬほどハードルを下げる:「毎日1時間勉強する」ではなく、「毎日15分、参考書の1ページを読む」から始めます。 物足りないくらいが丁度いいのです。
- 仕組み化する:意思の力に頼らず、「電車に乗ったら英語アプリを開く」のように、毎日の行動とセットにして条件反射で動けるようにします。
- 他人の力を利用する:「毎日ランニングする」と周囲に宣言してしまえば、「サボると格好悪い」という心理が働き、モチベーションを維持しやすくなります。
何かを始めて1年以上継続できる人は、全体のわずか4%しかいないという研究結果もあります。 つまり、 習慣化できるだけで、あなたは上位4%の存在になれるのです。 この最強の武器を身につけない手はありません。
「勝ち癖」を身につける生活習慣
億を稼ぐ人々は、生活習慣においても自らにルールを課し、それを守ることで小さな成功体験を積み重ねています。 これが 「勝ち癖」 となり、自己肯定感を高め、さらなる挑戦への意欲を生み出すのです。
例えば、運動、食事、睡眠といった日常の行動一つひとつに、「これでいいや」と妥協するのではなく、「こうする」という能動的な選択を持ち込みます。
富裕層は「カネ→カラダ→ココロ」の順番で整える
メンタルに不調を感じたとき、多くの人は心の問題に直接アプローチしようとします。しかし富裕層は、まず 「カネ(経済的基盤)」 を整え、次に 「カラダ(健康)」 を整え、最後に 「ココロ(精神)」 に向き合います。
経済的な余裕がないと、心身の健康を損ないやすくなります。 まずは本書で語られるような方法で経済的な安定を確保する。その上で、体の健康を整える。運動や良質な睡眠、自分に合った食事は、心身のパフォーマンスを最大化するための土台です。
著者は、アレルギー検査によって、好物だと思っていたショウガが実は体に合っていなかったことを発見。 食生活を改善したところ、長年悩まされていたアレルギーや体調不良が劇的に改善したといいます。
「困ってからの絆創膏」ではなく、平時から自分の体をメンテナンスする。これも重要な自己投資です。 体が整えば、心も自然と安定し、高いパフォーマンスを維持できるのです。
人間関係も分散投資。富裕層コミュニティの作法とは?
人間関係の不安を解消する秘訣は、 「所属するコミュニティを複数持っておくこと」 です。 人間関係も分散投資が基本。会社だけの関係に依存していると、そこで問題が起きた時に逃げ場がなくなってしまいます。
趣味のサークル、地域の活動、学習コミュニティなど、利害関係のない場所を持つことで、心理的な安全性が確保されます。
そして、より高みを目指すなら、富裕層のコミュニティに入ることも視野に入れるべきです。世の中の「おいしい話」は、信頼できる人々の間でしか共有されないのが現実だからです。
では、どうすればその輪に入れるのか? 著者は5つのステップを提示しています。
- 自分の引き出しを増やす:日頃から学習し、どんな話題にも対応できる基礎力をつけておく。
- 相手を徹底的に調べる:会いたい相手が決まったら、その人の書籍やSNSなどを読み込み、思想や好みを把握する。
- 共感を伝える:会った際には、リサーチで得た情報を基に、なぜ会いたかったのか、どこに共感しているのかを具体的に伝える。
- 自分が与えられることを考える(Give):相手の時間をいただく以上、自分は何を提供できるかを真剣に考え、惜しみなく差し出す。
- 自分から誘う:一緒にできることを見つけ、勇気を出して「一緒にやりましょう」と提案する。
最も重要なのは、日々の小さな行動で 「信頼貯金」 を積み重ねることです。 頼まれなくても議事録を作成して共有する、相手のために資料を調べてまとめておく。こうした誰にでもできるけれど、誰もやらないことを率先して行う人が、最終的に信頼を勝ち得ます。
ただし、絶対にやってはいけないのが、 お金のために人脈を売ること。 これをすれば、築き上げた信頼は一瞬で崩壊します。「人脈を売る」のではなく、「人脈を活かして」さらなる価値を生み出す。この違いを理解することが、億からの人になるための鍵です。
まとめ:今日から始める「億を超える人」への第一歩
本書『億までの人 億からの人』が示す道は、決して一部の天才だけが進める特別なものではありません。
「普通のことを、誰にも真似できないくらい圧倒的にやる」
その先に、「億を超える人」の世界が待っています。本書で語られる数々のマインドセットや習慣は、どれも今日から、今この瞬間から始められることばかりです。
経営コンサルタントの大前研一氏は、「人間が変わる方法は3つしかない。『時間配分』を変える。『住む場所』を変える。『付き合う人』を変える」と述べました。 著者はこれに、4つ目の方法として 「習慣化」 を加えたいと言います。
何げなく過ごしている日常の行動を、目標を持ったアクションに変える。そして、それを「習慣化」する。その小さな積み重ねが、やがてあなたの運命を大きく変えていくはずです。
この本を手に取った今が、あなたの人生で一番若い日です。まずは一つでもいい、本書で紹介されている思考法やアクションを、今日からあなたの生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。それが、あなたを「億までの人」から「億からの人」へと押し上げる、確かな一歩となるはずです。