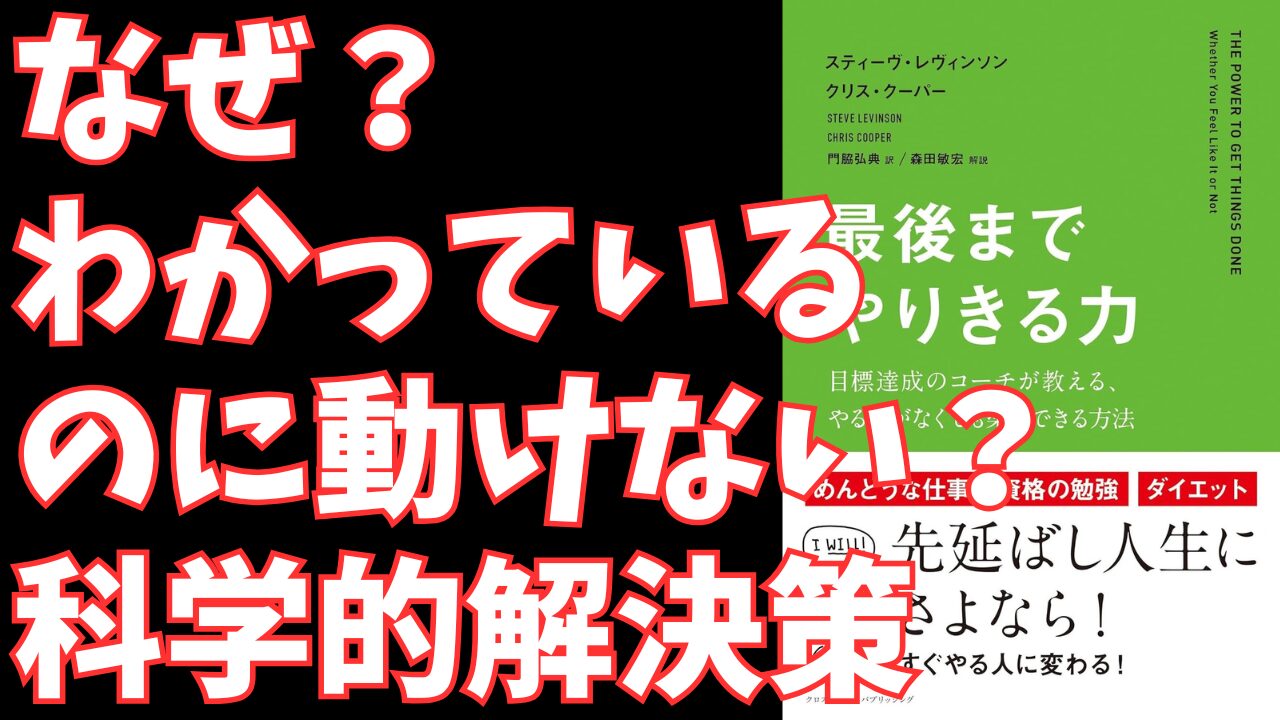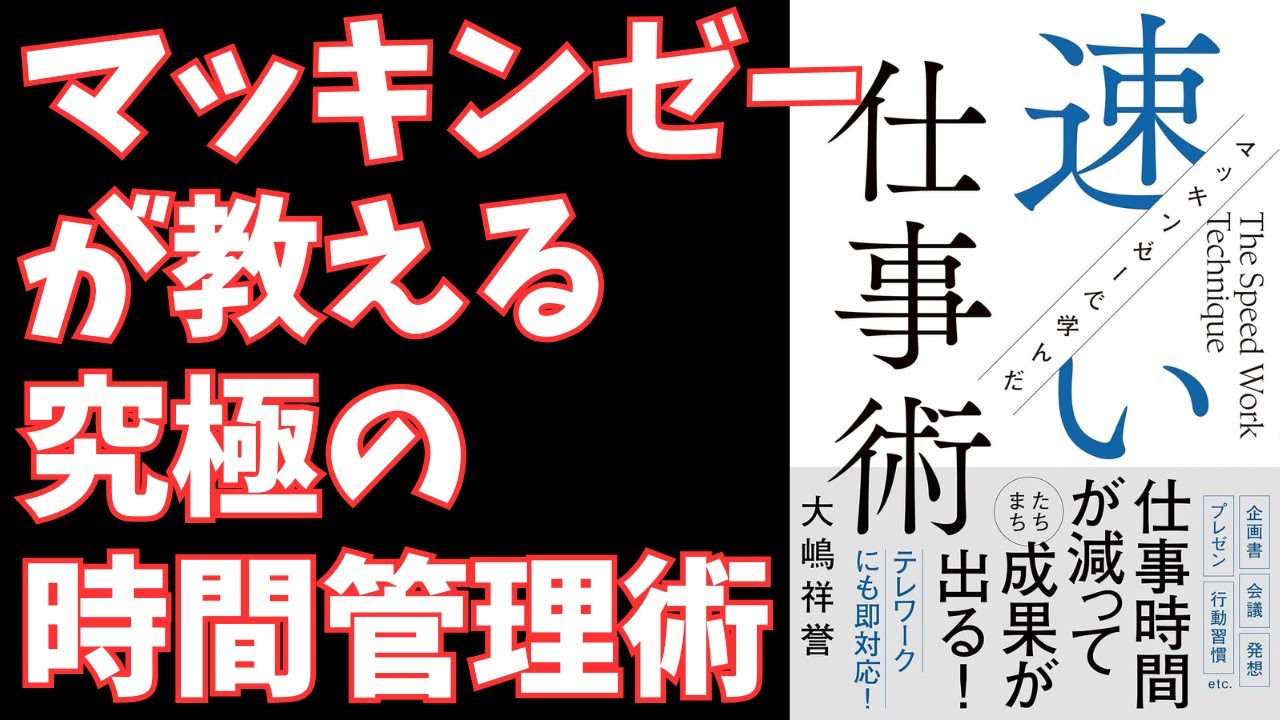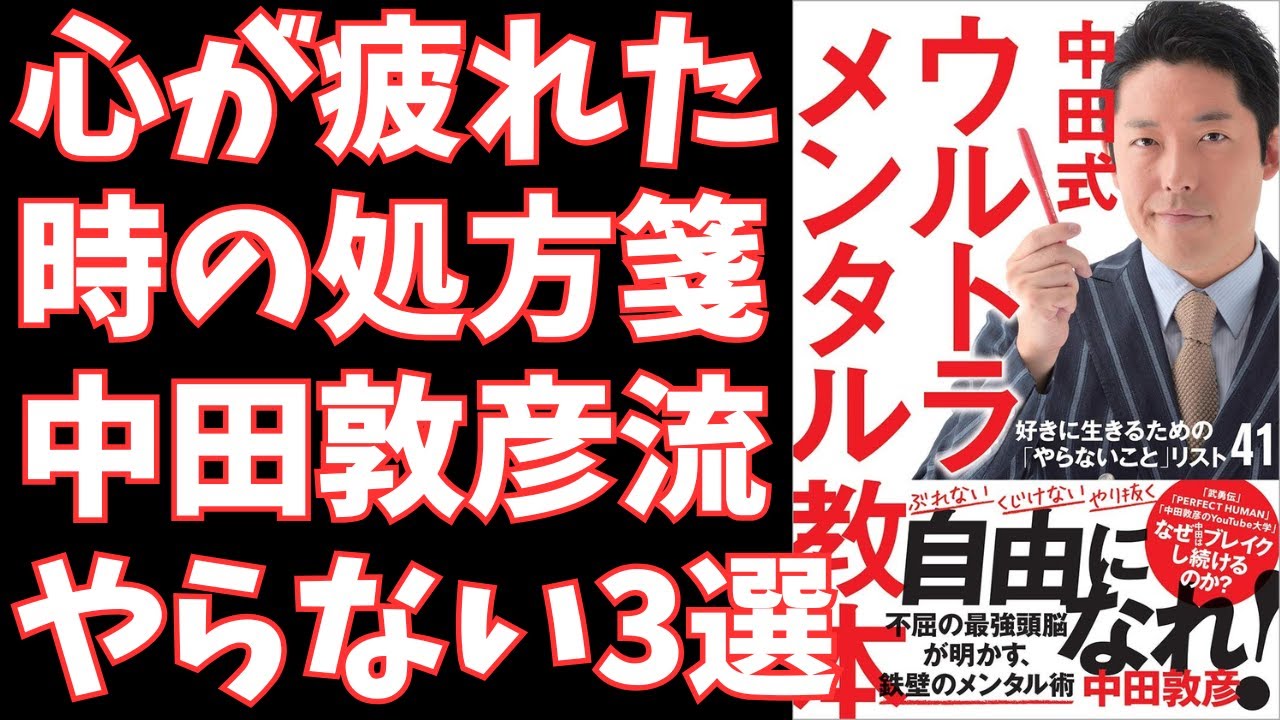不安を一掃!桜井章一『恐れない技術』に学ぶ、ビジネスパーソンのための「動じない心」の作り方
「明日、大事なプレゼンがある」「上司にミスを報告しなければならない」「このまま会社にいて大丈夫だろうか」……。
私たちビジネスパーソンは、日々さまざまな「不安」や「プレッシャー」にさらされています。
本書『恐れない技術』は、20年間無敗の「雀鬼」として裏社会の修羅場を生きてきた桜井章一氏が、なぜ自身が「恐れなかった」のか、その根本的な心の持ちようを説いた一冊です。
この記事では、本書の中から特に忙しいビジネスパーソンに響く「不安の正体」と「動じない心の作り方」を、具体的なエピソードと共に徹底的に解説します。この記事を読めば、あなたの心を縛る「恐れ」の正体がわかり、明日から実践できる「腹をくくる」技術が身につくはずです。
本書の要点
- 人が恐れる根本原因は「明日を考えすぎること」と、安全な社会で「危険察知能力が低下」したことにある。
- 「恐れ」とは、想定外の事態に「不安」を感じ、それが「恐怖」に変わり、心が柔軟性を失って「強張る(こわばる)」状態である。
- 恐れないためには「腹をくくる」こと。つまり「すべて自己責任」と捉え、他人のせいにせず、「今を生きる」ことが重要。
- 他人に過度に「期待せず」、会社での「肩書(化けの皮)」を捨て、「ダメな自分」も丸ごと認めることで、心は強くなる。
- 人生は「勝ち負け」ではなく「負けない」ことを目指す。目の前の試練すら「おもしれえじゃないか」と楽しむ感覚を持つ。
はじめに:「会長は、恐いと思ったことってあるんですか?」
本書は、道場生からのこんな素朴な疑問から始まります。
著者の桜井章一氏は、大学時代から裏プロの雀士としてデビューし、以来20年間無敗。「雀鬼」の異名をとった伝説的な人物です。雀荘で背後から日本刀を突きつけられたり、暴力団風の男たちに拉致されて生き埋めにされそうになったり……まさにVシネマのような修羅場をくぐり抜けてきました。
そんな著者でも「そりゃあ、あるさ」と答えます。人間ですから、驚きもすれば恐れも感じる。
しかし、その反応が他の人と比べて圧倒的に小さいのです。妻に「俺がお前の前で驚いたことってあるか?」と聞けば、「ないわねぇ」と即答されるほど。著者いわく、その妻こそが、重い病気にかかったり、勝手に他人の借金の保証人になったりして、著者自身を一番驚かせてきた張本人だというのですから、説得力が違います。
では、なぜ桜井氏はこれほどの経験をしながら「恐れる」ことがなかったのか。
それは、彼がたまたま勇気や度胸があったからではありません。彼は、その理由を「心の持ちよう」に関係している、と断言します。
第1章:なぜ、あなたは「恐れてしまう」のか?
「今月のノルマ、達成できるだろうか」「あのクライアントを怒らせてしまった」「リストラされたらどうしよう」……。
私たちの不安は尽きません。なぜ、これほどまでに「恐れ」てしまうのでしょうか。
不安が恐怖に変わるメカニズム
著者は、「不安」が「恐怖」に変わるプロセスを、非常にわかりやすいたとえで説明します。
たとえば、君がどこかで財布を落としたとする。
「あっ、財布がない!」
ここまでは単なる「事実」です。
ところが、ここから頭がぐるぐる回転し始めます。
「いくら入っていた?」「どこで落とした?」「警察に届けたら、大事な取引に遅れる」「部長に怒られる」「この取引が失敗したら、次の人事異動で飛ばされるかも」「子どもは受験なのに、地方転勤になったらどうしよう……」
気づけば、ただ財布を落としたという事実が、上司の顔、妻子の顔、自分の将来への絶望にまで連鎖しています。これが「不安」が「恐怖」に変わる瞬間であり、著者はこの状態を「精神の不整脈」と呼びます。
心がこうなると、柔軟性が一気に失われ、「強張って」しまいます。著者が恐れなかったのは、恐怖を感じなかったのではなく、この「心の強張り」がなかったからだと言います。彼は危険な状況でも「こいつはおもしろくなったぞ」と客観視し、「まぁ、死ぬなんて別に大したことじゃないさ」と腹をくくれたのです。
現代人が恐れやすい理由1:「明日」を考えすぎている
私たちが恐れる最大の理由は、「明日」のことを気にしすぎているからだと、著者は指摘します。
本書に登場する編集者の鈴木氏は、初めて「ぎっくり腰」になっただけで、「このまま動けなかったら会社に行けない」「もうダメだ」と、人生の絶望感すら味わいます。
しかし、冷静になれば、ぎっくり腰は命に関わる病気ではありません。彼が絶望したのは、「明日どうなるか」という妄想を自分で膨らませたからです。
「明日のことなど誰にもわかりはしない。それなのに、なぜか現代人は必死で知ろうとする。それも悪い方へ、悪い方へと考えがいくのだから不思議だ」
著者は、「動じる」「恐れる」の反対語は、「腹をくくる」ことだと言います。
腹をくくるとは、「今を生きる」こと。つまらないこと、イヤなことはいちいち考えない。明日の心配は明日すればいいのです。
現代人が恐れやすい理由2:安全ボケによる「危険察知能力の低下」
もう一つの理由は、私たちが「安全な社会」に住みすぎた結果、動物としての「危険察知能力が低下」してしまったことです。
ジャングルの動物は、常に危険と隣り合わせだから油断しません。しかし人間は、危険なものを徹底的に避けようとします。
著者は「使いにくくなった百円ライター」を例に出します。子どもの火遊びを防ぐため、ライターは点火しにくいように「改悪」されました。しかし、著者は「子どもにだってライターの火の熱さを肌で感じさせておけば、それからは触ろうとしない」と言います。
危険なものにフタをし、遠ざかることで、わずかな不安や危ういことにもオロオロし、簡単にパニックに陥る人間が増えたのです。
現代人が恐れやすい理由3:「制度」や「規則」への依存
私たちは、「動く生物(動物)」です。動けば、必ず何かにぶつかります。これは自然なことです。
しかし、人間は「規則」や「制度」を作り、自分たちを縛り付けました。学校の「校則」、会社の「社則」。これらは、人間を自由に動き回ると困るから、統治しやすいように作られたものです。
私たちはいつの間にか「制度や規則に縛られるのが当然だ」と思い込み、そこからはみ出すことに「不安」や「恐怖」を感じるようになりました。
しかし、著者は問いかけます。
会社が倒産した時、君がリストラされた時、「社則」が君の家族を守ってくれるだろうか?
「いざという時、慌てふためきパニック状態に陥る前に、『自分の身は自分で守る』という動物としての当たり前の『ルール』をまず確立しておくべきだ」
第2章:今日から実践する「恐れない」ための心の技術
では、具体的にどうすれば「恐れない」心を持てるのでしょうか。著者が示す「心の技術」は、非常にシンプルかつ強力です。
1. すべて「自分のせい」だと思えるか(自己責任)
著者はかつて、ゴルフ場でマンホールの蓋がずれているのに気づかず、片足を突っ込んで骨折したことがあります。
普通なら「ゴルフ場の管理ミスだ!」と大騒ぎするところです。しかし、著者が最初に頭に浮かんだのは、「いけねえ、みんなが楽しんでいるのに、ヘマやっちまった」でした。
彼は足を引きずりながらラウンドを続け、結局、手術もせずにその骨折を自分で治して(正確にはグシャグシャのままくっつけて)しまいました。
なぜこんなことができるのか。
「誰のせいにもしない。すべて自分の責任」と覚悟を決めているからです。これが「腹をくくる」ということです。
他人のせいにした瞬間に心は動揺しますが、すべて自己責任だと思えば、動揺すらしないのです。
2. 「不調こそ、わが人生」と思えるか
私たちは「好調」が当たり前だと思っています。だから、少しでも「不調」になると、「どうしよう」と恐れてしまいます。
著者は「調子が悪い、いろんなことがうまくいかないのが当たり前なんだ。好調はたためま、不調こそ人生」と道場生に言っているそうです。
人生なんて順風満帆ではなく、困難のオンパレード。だからこそおもしろい。
うまくいっているときこそ浮かれず、「備えあれば、憂いなし」の精神で、不調な時のことを意識しておく。そうすれば、いざという時に平然としていられます。
3. 他人に「期待をするな」
ビジネスシーンで心が大きく動揺する瞬間の一つが、信頼していた相手からの「裏切り」です。
しかし、著者は「裏切り」とは、単に相手の「考えが変わった」だけだと捉えます。
「ある人が『こうしようと思った』が、『そうはできなくなった』だけのことだ」
なぜ、裏切られると動揺するのか。それは、「なまじ、相手に期待をするから」です。
著者は「ハナから何かに期待をしていない」と言い切ります。
「自分の会社に過度の期待をしない方が賢明だし、まして、己の将来の夢などに囚われすぎるのもどうかと思う」
会社は簡単につぶれるし、夢は必ず叶うとは限らない。それが「現実」です。期待を手放せば、心は動揺しなくなります。
4. 「ダメな自分」も全部認める
恐れないためには、まず「自分とは何か」を知る必要があります。
自分の良いところ、ダメなところ。強い部分、弱い部分。それらすべてを認識し、「なるほど、それが俺なんだ」と丸ごと受け入れてしまうのです。
特にエリート意識が強い人ほど、小さなミスを指摘されたときに「これで全否定されてしまうのではないか」という恐れを抱き、心を病んでしまいがちです。
「ダメでも別にいいじゃないか──。」
この感覚を持つことが大切です。君は君以上でもなければ、君以下でもないのですから。
5. 「失う練習」ができるか
私たちは「得る」ことに快感を覚えますが、著者は「得たものは、必ず失う」という摂理を忘れるな、と言います。
財産、仕事、地位、家族、そして命。人生は「得る」ことより「失う」ことの方が自然です。
ならば、「得る」ために躍起になるより、「失う」ことを恐れないための「練習」をすべきです。
「リストラに遭ったらどうするか」「預金通帳に残金がなくなったらどうするか」。
普段からシミュレーションしておくのです。
「人生、何も失うものがない」と心に決めた男ほど強いものはない、と著者は言います。「捨て身」になって腹さえくくれれば、オロオロしないで生きていくことができます。
第3章:ビジネスシーンで役立つ「恐れない」ための対人術
本書で語られる「恐れない」技術は、そのまま会社の人間関係にも応用できます。
威張る上司に「つぶされない」方法
あなたの職場にも、威張りくさっている上司や先輩がいないでしょうか。
こういうタイプは、要するに「俺を特別扱いしろ」と言いたいだけです。
ここで相手の土俵に乗ってムキになったり、逆にビクビクしたりすると、相手の思うツボです。
著者が示す最善の方策は、「決して上司に媚びないこと」。
ゴマもすらず、ミエミエのお世辞も言わない。ただ、つねに「堂々としている」こと。
こちらに敵対する意思がないとわかれば、相手も手を出してきません。
「威張った相手とはわざわざ戦わない。その代わり一歩も引かない」。この毅然とした態度こそが、あなたを恐怖から守ります。
プレゼンで動揺しない:「わかったつもり」を捨てる
大事なプレゼンで、途中で言葉に詰まり、頭が真っ白になる……。
この動揺の原因は、完璧主義のくせに、話す内容を「わかったつもり」になっているからです。単なる丸暗記だから、一つ詰まると次が出てこないのです。
演説が上手な人は、本当に自分が理解している大事なことしか話しません。
わからないところは、わからないから無理に話さない。やたらと完璧を目指さない。
これだけで気持ちはかなり楽になるはずです。
「固定給」の本当の意味を知る
著者は、会社という存在を「法人」、すなわち「法律上、存在する人」であり、血が通っていないと喝破します。
そして、私たちがもらう「固定給」とは、最低限の賃金などではなく、「法人」が「社員」を「固定」するための金だと言います。
「私の言う通りにしなさいよ」と人を縛りつけるための金。
「法人」が「カラスは白い」と言ったら、「白いですね」と言わなければならないためにもらっている。
会社員である以上、会社や上司がぶれれば、社員もぶれざるを得ない。まずはその構造を知っておくことが、会社に振り回されない第一歩です。
第4章:「乱」の時代を生き抜くために
著者は、現代を「これまでの常識がまるで通じない」「乱」の時代だと定義します。
会社に依存して生きていけるか?
終身雇用は崩壊し、絶対につぶれないと言われた大企業の経営が次々と悪化しています。
「今勤めている会社は、いつかなくなる──。」
少なくともそう考えることは、この「乱」の時代を生きるビジネスパーソンにとって不可欠です。
会社に依存するのではなく、会社にいる間に「自分一人で生きることができるための力」を鍛えておく。
「クビになったらどうしよう」という恐怖心から解き放たれるには、それしかありません。
「化けの皮(肩書)」を剝がせるか
会社員は、「課長」「部長」といった「肩書」を持っています。著者はこれを、自分をきれいに見せるための「化粧」だと言います。
肩書という化粧で勝負をしていると、本当の自分、つまり「素顔」の部分はどんどん弱くなり、劣化していきます。
そして、リストラや定年でその化粧(肩書)が剝がれたとき、「素顔」の自分だけがポツンと残されます。
「素顔」の自分で生きられない人間が、一番「恐れ」を抱えているのです。
そうならないためにも、今から自分の化粧を落とし、「素顔」のままの自分になれる時間や、損得など無関係でいられる仲間を大事にすべきです。
人生は「勝ち負け」ではない
著者は、将棋の羽生善治名人との対談で出た「勝つとか負けるとか、そうした勝負を超えたところに本当の勝負がある」という言葉を紹介します。
「勝ちたい」という欲望に支配されると、精神は卑しくなり、平気で汚いこともやるようになります。
勝負で大事なのは、「どうやったら勝つか」ではなく、「いかに、いい勝負ができるか」です。
これは人生も同じです。
「君の人生も勝つよりも、負けないことを目指せばいい。そう考えられれば、君は人生にまるで『恐れる』ことなどなくなるはずだ」
まとめ:求めるべきは、安住ではなく試練である
著者は最後に、飛行機とバスのたとえを出します。
「勝ちたい」「出世したい」という上昇志向(飛行機)を持ち続ける限り、常に「墜落するかもしれない」という不安と恐怖がつきまといます。
一方、著者は今、かつての修羅場を離れ、雀荘の親父として地に足が着いた(バスのような)生活を送っています。そこには「不安」も「恐怖」もないと言います。
「恐れない」とは、「自分との勝負」です。
出世争いに負けてもいい。金儲けに敗れてもいい。自分にだけはウソをつかず、自分との勝負に負けなければ、恐れる必要など何もないのです。
著者は、私たち読者にこう呼びかけます。
「自分を襲ってくるさまざまな試練を『おもしれえなあ』と楽しめ」
「動じるな。ぶれるな。求めるべきは、安住ではなく試練である」
『恐れない技術』は、単なる精神論ではなく、修羅場を生き抜いた人間の「腹のくくり方」を学ぶ、ビジネスパーソン必読の書と言えるでしょう。