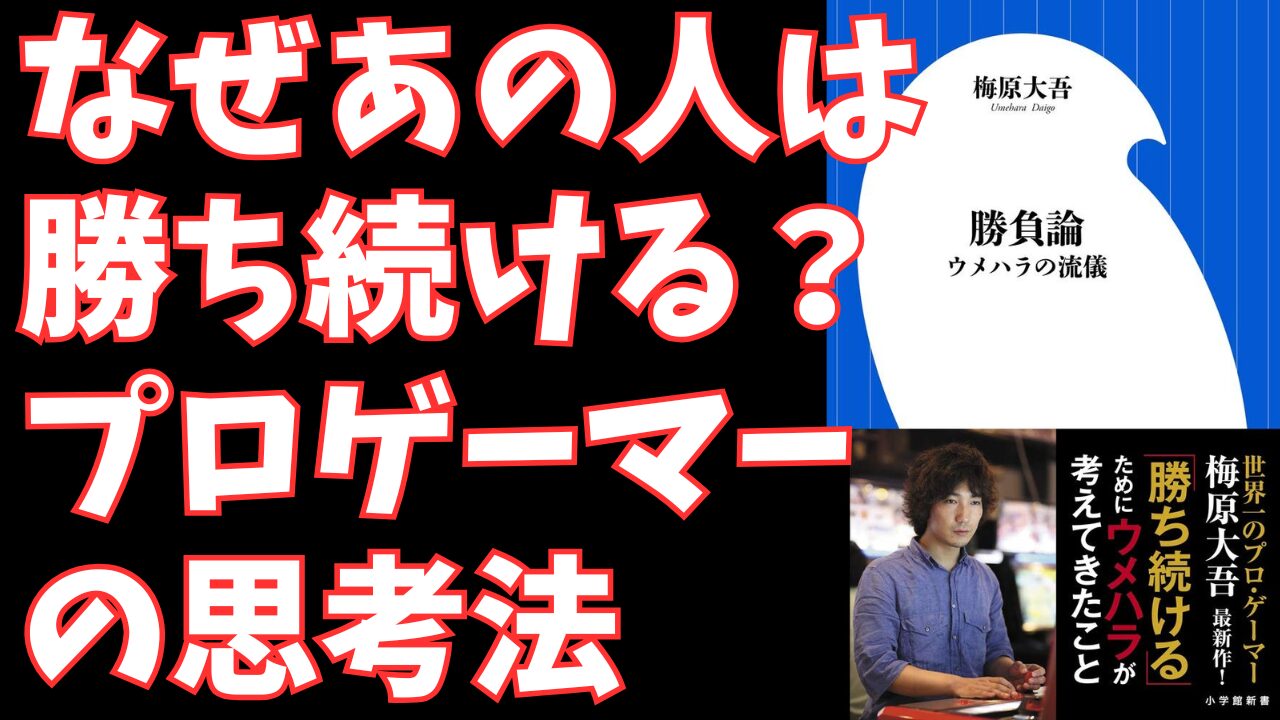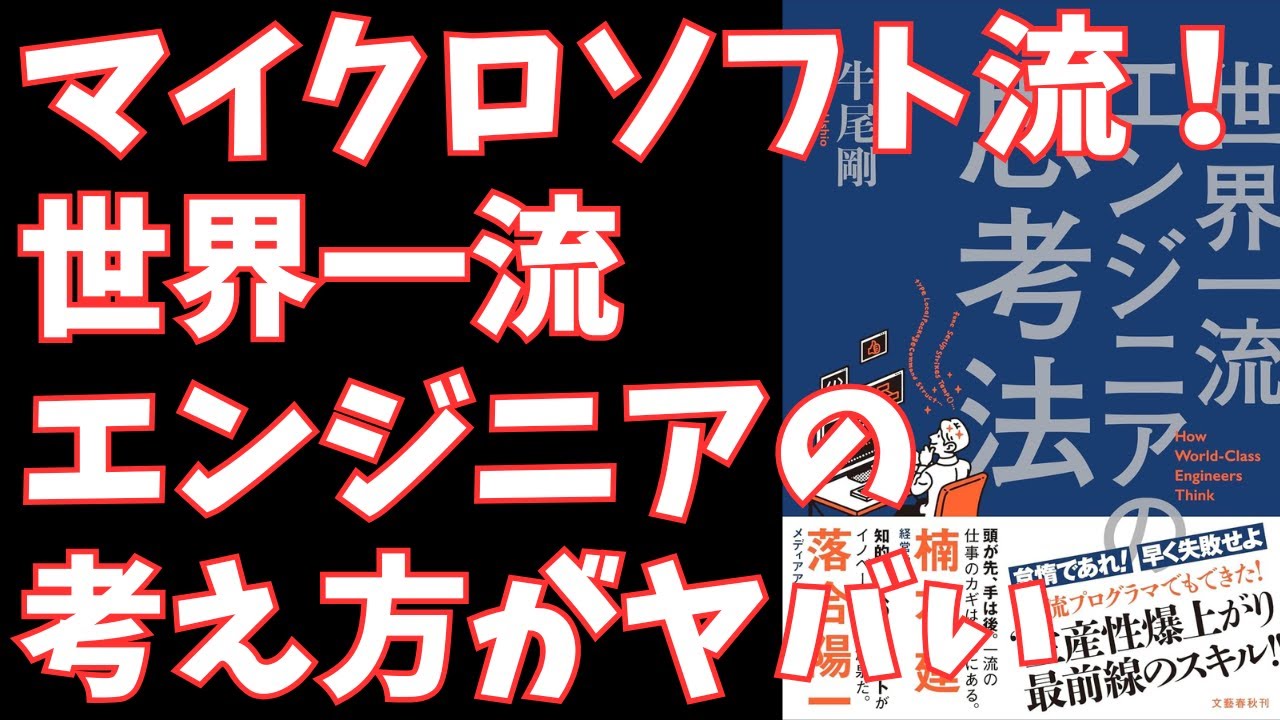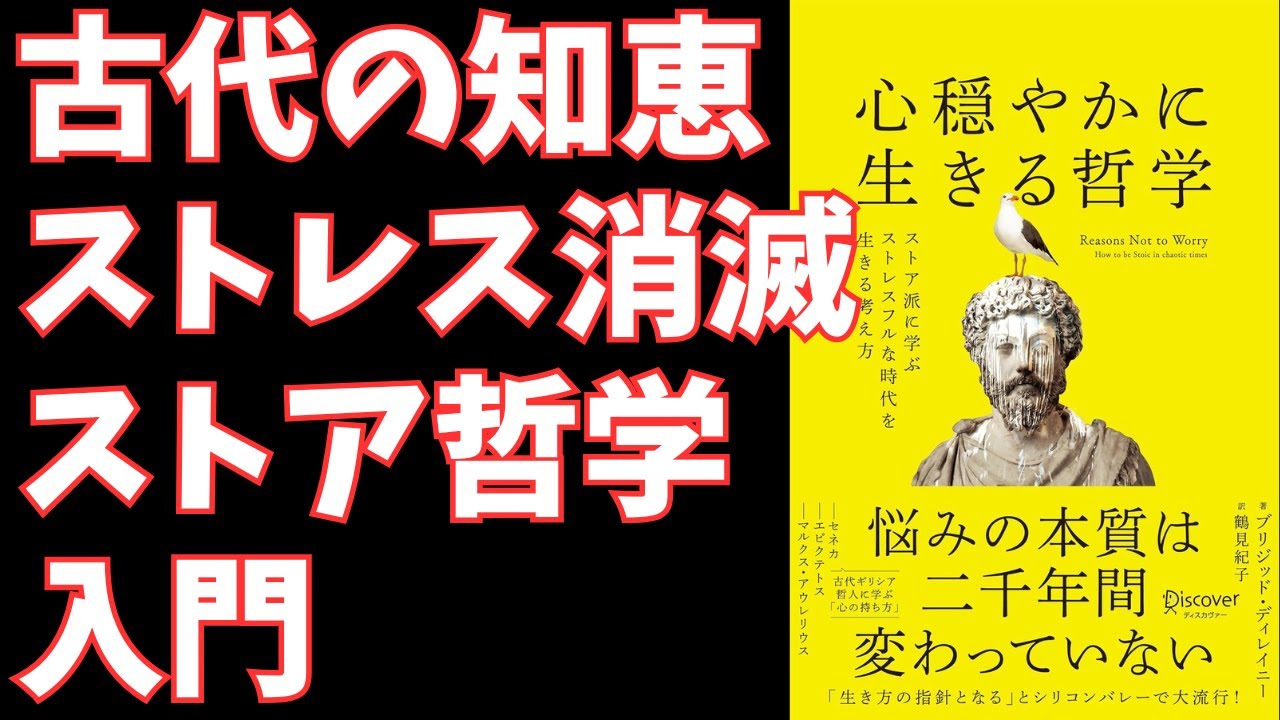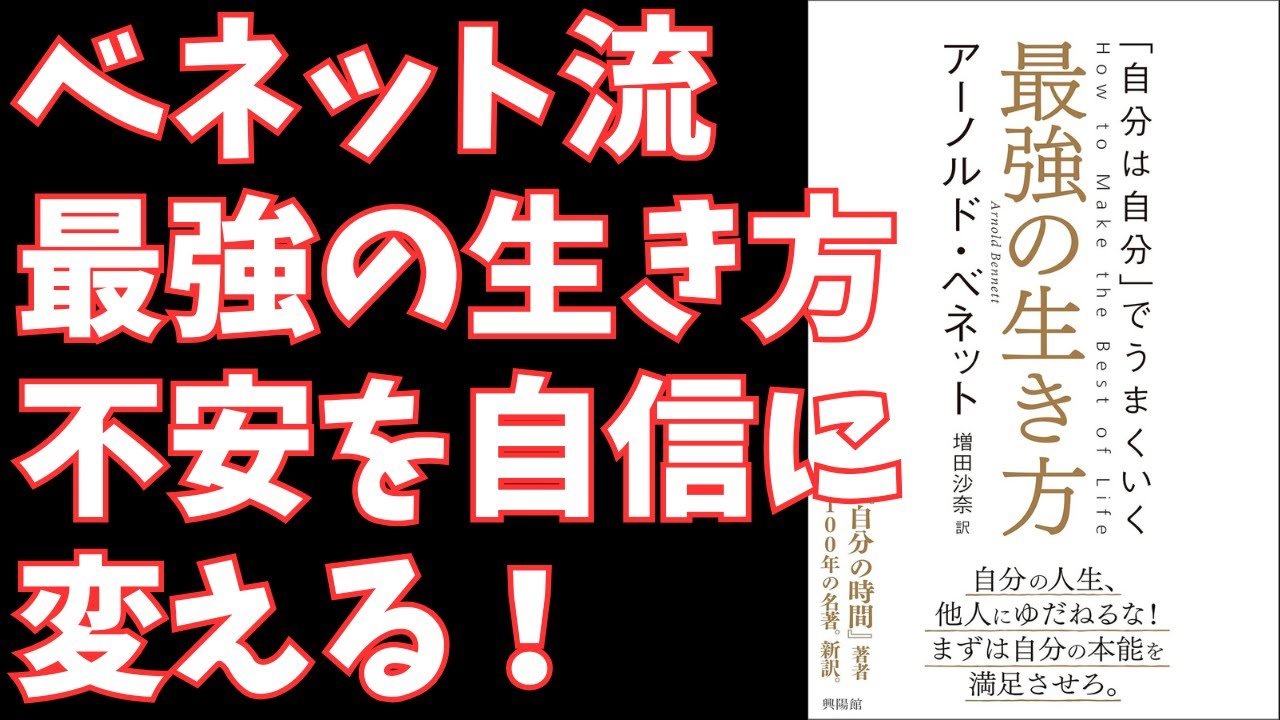センスの哲学 千葉雅也 | 忙しいビジネスパーソンが「意味から強度へ」シフトする思考法
本書『センスの哲学』は、哲学者・作家である千葉雅也氏が、「センス」という捉えどころのない概念を哲学・芸術論と結びつけ、生活や仕事にも応用可能な形で解き明かす一冊です。センスとは単なる生まれつきの才能ではなく、「直観的にわかる」力であり、特に「リズム」として物事を捉える感覚であると定義します。本書は、意味や正解に囚われがちな現代人に対し、意味から離れて物事の「強度」や「リズム」を感じ取ることの重要性を説き、それによってより自由で豊かな捉え方、すなわち「センスの良い」状態に至る道筋を示します。最終的には、センスの良し悪しを超えた「アンチセンス」の領域にまで踏み込み、人間の複雑さや「どうしようもなさ」をも肯定する視座を提供します。
- 本書の要点
- 「センスがいい」の正体とは? 掴みどころのない感覚を哲学する
- 直観力としてのセンス:考える前に「わかる」感覚
- 文化資本とセンスの関係:後からでも身につけられる?
- センスの目覚め:「モデルの再現」から降りる勇気
- 上手い<ヘタウマ:センスの本質は「ズレ」にある
- 世界を「リズム」で捉える:意味から強度へのシフト
- 多重録音(マルチトラック)としての世界
- 最小限のセンスの良さ:リズムの面白さに気づくこと
- リズムの深層:「いないいないばあ」の原理
- サスペンスと日常:あらゆる経験は「いないいないばあ」
- 「意味」のリズム:言葉や概念もデコボコで捉える
- 感動には二種類ある:大まかな感動と構造的感動
- 並べることの自由:何をどう並べてもいい
- 偶然性とセンス:余らせ方を肯定する
- 時間と人間:可能性の溢れを生きる
- アンチセンス:どうしようもなさの反復と魅力
本書の要点
- センスとは「直観的にわかる」力であり、訓練によって後天的に獲得・拡張が可能である。
- センスの第一歩は、モデル(正解)の再現を目指すことから降り、意味よりも物事それ自体の「リズム」や「強度」に注目することである(意味から強度へ)。
- リズムとは「うねり」と「ビート」の二重性を持つ。不在から存在へ(0→1)の切実なビートと、複雑に絡み合う生成変化のうねりを同時に感じ取る。
- 意味さえも「リズム」として捉えることができる。言葉や概念の関係性を「距離のデコボコ」として感じ取り、構造的な面白さを見出す。
- 真のセンスは、バランスの取れた美しさだけでなく、個人の「どうしようもなさ」に根差す反復(アンチセンス)をも内包する。
「センスがいい」の正体とは? 掴みどころのない感覚を哲学する
「あの人、センスいいよね」
私たちは日常的に「センス」という言葉を使いますが、その実態は曖昧で、どこか生まれつきの才能のように感じられがちです。「服のセンス」「お店選びのセンス」「会話のセンス」「仕事のセンス」……様々な場面で使われるこの言葉は、努力ではどうにもならない、その人固有の感覚を指しているように思えます。
しかし、哲学者・作家である千葉雅也氏は、著書『センスの哲学』において、センスとは決して固定的なものではなく、むしろ育て、変えていけるものだと主張します。本書は、哲学や芸術論をベースにしながらも、専門用語に頼りすぎず、具体的な例を豊富に用いることで、センスの本質を誰にでも理解できるように解説しています。
では、千葉氏の言う「センス」とは一体何なのでしょうか?
直観力としてのセンス:考える前に「わかる」感覚
千葉氏はまず、センスを「直観的にわかる」ことだと定義します。「直観」とは、論理的に段階を追って考えるのではなく、「なんとなく」「パッと」「全体的に」わかる感覚のことです。
私たちは日常生活において、無意識のうちに多くの直観的な判断を下しています。慣れた道を歩くとき、いちいち地図を確認したりはしません。言葉の意味も、多くの場合、瞬時に理解しています。こうした「深く考えなくてもわかる」能力が、センスの基礎にあるのです。
ただし、センスが問われるのは、服選びや音楽選びといった特定の分野だけではありません。千葉氏は、センスを「いろんなことにまたがる総合的な判断力」と捉えます。つまり、ある分野でセンスを発揮できる人は、他の分野でも同様の感覚を応用できる可能性がある、ということです。
文化資本とセンスの関係:後からでも身につけられる?
センスの良し悪しは、しばしば幼少期からの経験、いわゆる「文化資本」に左右されると考えられています。裕福な家庭に生まれ、幼い頃から多くの芸術や文化に触れる機会があった人は、自然とセンスが磨かれる、というわけです。
しかし、千葉氏はこの考え方に異を唱えます。文化資本は「あとから育成することが可能だ」と断言するのです。
文化資本が豊富であるということは、膨大な量の情報(ビッグデータ)に触れ、それを処理する能力が高いということです。AIが大量のデータを学習して新たなものを生成するように、多くの経験を積むことで、自然と判断力が養われます。
しかし、後から文化資本を形成しようとする場合、物量で勝負するのは困難です。そこで千葉氏が提案するのが、「判断力の原理を先に考えてしまう」というアプローチです。量をこなす中で得られるであろう「センスのポイント」を先に学び、それを意識しながら経験を積んでいく。これこそが、民主的な教育であり、誰もがセンスを磨くことができる道筋だと千葉氏は考えます。
センスの目覚め:「モデルの再現」から降りる勇気
では、具体的にどうすればセンスは磨かれるのでしょうか? 千葉氏は、その第一歩として「モデルの再現から降りること」を挙げます。
私たちは、何かを判断したり、作り出したりする際に、無意識のうちに「理想的なモデル(お手本)」を設定し、それを再現しようとしがちです。例えば、絵を描くときには「写真のように上手く描きたい」、部屋をコーディネートするときには「雑誌に載っているようなおしゃれな部屋にしたい」といった具合です。
しかし、この「再現志向」こそが、センスを無自覚な状態に留めてしまう原因だと千葉氏は指摘します。モデルを完璧に再現しようとすればするほど、現実とのギャップ(=ズレ)が「下手さ」として際立ってしまうからです。
例えば、ヨーロッパ風の高級感を目指して、アンティーク「風」の家具やシャンデリア「っぽい」照明を集めても、どこかチグハグで、かえって「本物ではない感」や「生活感」がにじみ出てしまうことがあります。これは、「高級感」という記号(意味)にとらわれ、個々のアイテム自体の魅力や、全体の調和(リズム)を見ていないからです。
そこで重要になるのが、「ヘタウマ」という考え方です。
上手い<ヘタウマ:センスの本質は「ズレ」にある
「上手い」がモデルの正確な再現を目指すものであるのに対し、「ヘタウマ」は、再現性を第一目標とせず、むしろ作り手自身の自由な運動性や個性が前面に出ている状態を指します。ピカソの絵画や、味のあるイラストなどを思い浮かべると分かりやすいでしょう。
千葉氏は、「センスとは、上手よりもヘタウマである」と断言します。モデルに完璧に合わせようとする窮屈さから解放され、自分なりの「ズレ」を肯定するところに、センスの萌芽があるのです。
これは、芸術に限った話ではありません。インテリア選びにおいても、完璧なモデルルームを目指すのではなく、自分の感覚に従って、少々不格好でも心地よいと感じるものを選び、配置していく方が、結果的に「センスの良い」空間になる可能性があります。
「モデルの再現から降りる」。これは、既存の価値観や評価軸(上手い/下手)から自由になり、自分自身の感覚を信じて、新たな土俵で勝負するということです。この姿勢の変化こそが、センスを目覚めさせるための鍵なのです。
世界を「リズム」で捉える:意味から強度へのシフト
モデルの再現から降り、ヘタウマを肯定する。その次に千葉氏が提案するのが、物事を「リズム」として捉えるという視点です。
私たちは通常、物事を「意味」で理解しようとします。「この絵は何を伝えたいのか?」「この服はどんな印象を与えるか?」「この行動にはどんな目的があるのか?」といった具合です。
しかし、千葉氏は、意味に囚われることから一旦離れ、物事がそれ自体として持つ「強度」や「リズム」を感じ取ることの重要性を説きます。これは、社会学者の宮台真司氏が提唱した「意味から強度へ」という考え方にも通じます。
「強度」とは、強い/弱いといった単純な二元論ではなく、強弱の変化、すなわち「リズム」のことです。例えば、会話の盛り上がりと静寂、音楽の音量の変化、料理における味のコントラストなど、あらゆる事象はリズムとして捉えることができます。
千葉氏は、スタンドライトの形状を例に挙げます。下部のどっしりとした台座(強)から、細く伸びる支柱(弱)、そして傘の部分で再び広がる(強)。このように、物の形もデコボコ(凸凹)のリズムとして認識できるのです。
さらに、餃子の味わいもリズムとして分析します。熱さ、皮のパリパリ感(強)、中の餡の柔らかさ(弱)、肉汁の旨味、ニンニクの風味、タレの酸味や辛味…。これら複数の感覚(熱、食感、味覚、嗅覚など)が、時間経過と共に複雑に絡み合い、変化していく様は、まさに音楽のようです。
多重録音(マルチトラック)としての世界
音楽制作では、異なる楽器の音を別々の「トラック」に録音し、それらを重ね合わせる「多重録音(マルチトラック)」という手法が用いられます。千葉氏は、私たちの経験もこのマルチトラックのように、複数のリズムの流れが重なり合って構成されていると捉えます。
餃子の例で言えば、「熱さのトラック」「硬さ・柔らかさのトラック」「塩味のトラック」「酸味のトラック」などが同時に進行し、それぞれのトラックで音量(強度)が変化する波形を描いている、というイメージです。
このように世界をリズムとして捉える視点を持つと、あらゆるジャンルの事象を、共通の土俵で理解し、比較することが可能になります。音楽と料理、ファッションと建築、文学とビジネス…一見無関係に見えるもの同士の間に、抽象的なリズムの共通性を見出すことができるのです。
最小限のセンスの良さ:リズムの面白さに気づくこと
千葉氏は、「ものごとをリズムとして捉えること、それがセンスである」と定義します。そして、センスの良さとは、その「リズムの配置の面白さ」を理解し、感じ取れることだと述べます。
しかし、最初から高度なリズム感を求める必要はありません。千葉氏によれば、「意味を実現しようとして競うことから降りて、ものごとをリズムとして捉える。このことが、最小限のセンスの良さである」のです。
つまり、「これは何の意味があるのか?」と問う前に、「このデコボコ(リズム)は面白いか?」と感じる回路を開くこと。それだけで、あなたはすでにセンスの良い状態への第一歩を踏み出しているのです。
この視点は、20世紀の芸術運動「モダニズム」とも深く関わっています。モダニズムとは、伝統的な意味や物語性から脱却し、色や形、音といった要素それ自体の面白さ(=リズム、形式)を追求した動きです。本書は、いわば「日常で実践できるモダニズム入門」であり、ラウシェンバーグの抽象絵画も、美味しい餃子も、同じ「リズムの面白さ」という地平で味わうことを可能にしてくれます。
リズムの深層:「いないいないばあ」の原理
リズムとは何か? 千葉氏はさらにその本質に迫ります。リズムは単なる表面的なパターンの繰り返しではありません。それは、人間の根源的な経験と結びついた、深い意味を内包しています。
その鍵となるのが「いないいないばあ」の原理です。
「いないいないばあ」は、物が隠された状態(不在=0)から現れる状態(存在=1)への転換であり、「不安と安心」の基本的なリズムを象徴しています。赤ちゃんがこの遊びを喜ぶのは、母親(あるいは保護者)が一時的にいなくなることへの不安を、遊びというコントロール可能な形で経験し、乗り越えるプロセスだからです。
精神分析の創始者フロイトは、人間はこうしたリズム形成(遊び)によって、根源的な欠如(母親の不在など)に耐えられるようになると考えました。
リズムとは、「0と1のビートをうねりに巻き込む」ことであり、根本的な寂しさや不安を、完全になしにするのではなく、潜ませながら乗り越えるための人間の知恵なのです。
サスペンスと日常:あらゆる経験は「いないいないばあ」
物語における「サスペンス」も、この「いないいないばあ」の原理で説明できます。大切なものが失われたり(0)、隠された謎が明らかになったり(1)する展開は、まさに不安と安心のリズムです。私たちは、この0→1の移行(ビート)に感情移入し、ハラハラドキドキするわけです。
しかし、サスペンスの面白さは、単なる0→1の繰り返しだけではありません。解決に至るまでの「宙づり」状態(=遅延)の中で、小さな謎や伏線が複雑に絡み合い、豊かな「うねり」を生み出す点にあります。
この「サスペンス=いないいないばあ」の構造は、物語だけでなく、絵画や音楽鑑賞、さらには日常の些細な行為にも見出すことができます。
例えば、「丁寧な暮らし」で推奨されるような、時間をかけてコーヒーを淹れる行為。これは、「コーヒーを飲む」という目的達成を意図的に遅らせ、その途中のプロセス(豆の膨らみ、香り、湯気など=リズムのうねり)を楽しむ行為であり、一種のサスペンスと言えます。
芸術作品もまた、目的達成(意味の理解)を遅らせ、鑑賞者を意図的に「宙づり」状態に置くことで、豊かなリズム(うねりとビート)を体験させる装置なのです。
「意味」のリズム:言葉や概念もデコボコで捉える
本書はこれまで、「意味から離れてリズムへ」という方向で議論を進めてきました。しかし、千葉氏はさらに踏み込み、「意味」そのものもリズムとして捉え直すことを試みます。いわば「意味の脱意味化」です。
言葉の意味は、基本的に「近さ/遠さ」の関係性によって成り立っています。例えば、「赤」という言葉は、「りんご」「トマト」「火」「血」といった言葉としばしば一緒に使われる(=近い)一方で、「青」とは対立的な関係(=遠い)にあります。
ChatGPTのような大規模言語モデルは、まさにこの言葉同士の「近さ/遠さ」(=距離、確率)だけを計算して、人間が自然だと感じる文章を生成しています。AIは「赤」という色のイメージを理解しているわけではなく、膨大なテキストデータから学習した「赤という言葉の周辺にある言葉の配置(リズム)」を再現しているにすぎません。
このAIのアナロジーを用いることで、私たちは、小説や映画における意味の展開(物語)さえも、言葉や概念の「距離のデコボコ=リズム」として捉えることが可能になります。
例えば、登場人物の心情の変化や、状況の対比(明暗、静動、善悪など)は、意味における0→1のビートとして感じ取れます。同時に、微妙な感情の揺れ動きや、一見矛盾するような表現(例:「燃えるような青」)は、複雑な意味の「うねり」として味わうことができます。
感動には二種類ある:大まかな感動と構造的感動
意味をリズムとして捉える視点は、「感動」のあり方も変えます。千葉氏は、感動を二種類に分けます。
- 大まかな感動:「いい話だった」「悲しかった」といった、作品全体のメッセージや感情のインパクトに基づく感動。
- 構造的感動:作品の細部(ディテール)に注目し、要素がどのように組み合わされ、リズムを形成しているかの「構造」そのものに面白さを見出す感動。
多くの人は、まず「大まかな感動」を求めがちです。しかし、千葉氏は、「大まかな感動を半分に抑え、構造的感動ができること」こそが、より深いセンスのあり方だと主張します。
そのためには、「小さな、ささやかなことを言語化する練習」が必要だと述べます。家具の形、料理の味、会話の間など、重要そうに見えないディテールを観察し、言葉にする。これは、「無駄口」を豊かにする練習であり、それ自体が批評であり、創造的な行為なのです。
並べることの自由:何をどう並べてもいい
センスとはリズムを捉えることであり、リズムとは要素の「並び」です。第五章以降、千葉氏は「並べる」という行為、すなわち「制作」の視点からセンスをさらに掘り下げます。
映画における「ショット(映像の断片)」と「モンタージュ(ショットの組み合わせ)」を例に、あらゆる表現は「要素をどう並べるか」の問題だと論じます。
通常、モンタージュは、観客が意味を理解しやすいように、自然なつながりを意識して作られます。しかし、ゴダールのような前衛的な監督は、あえて意味のつながらない、飛躍したモンタージュを試みます。
一見、意味不明に見えるショットの連続。例えば、「海の映像」の次に「都会の喧騒」が来る。これは、観客の「予測」を裏切る行為です。脳は、この「予測誤差」を埋めようと、必死に意味や物語を探し始めます。
この「予測誤差」こそが、驚きや面白さ、そして時には「かっこよさ」の源泉となります。予測が裏切られる不快感と、それを乗り越えようとする脳の働きが、一種独特の快感(ラカンが言う「享楽」)を生み出すのです。
重要なのは、「つながる/つながらない」は絶対的なものではなく、観る側の「設定次第」だということです。抽象度を上げれば、どんな要素も何らかの共通項で見出すことができます。家も段ボールも「箱」である、というように。
だから、作り手は「何をどう並べてもいい」という最大限の自由から出発すべきだと千葉氏は主張します。ルールや規範に縛られるのではなく、まず自由に並べてみて、そこから面白いリズムを探していく。その過程で、偶然性が重要な役割を果たします。
偶然性とセンス:余らせ方を肯定する
センスの良いリズムとは、一般的に「反復と差異(逸脱)のバランスが良い」状態(=美)を指します。しかし、千葉氏は、それだけでは人間の創造性は捉えきれないと指摘します。むしろ、バランスを崩し、予測不可能な「偶然性」が強く働く状態(=崇高)にこそ、芸術的な魅力や個性が宿る場合があるのです。
完璧なモデルを目指して「届かないズレ」を生むのが「下手」であるのに対し、自由な偶然性から出発し、結果的にモデルから「超過するズレ」を生むのが「ヘタウマ」であり、センスなのです。
絵を描くときも、ピアノを弾くときも、文章を書くときも、最初から完璧を目指すのではなく、まず偶然性に身を任せ、自由に手を動かしてみる。その「余剰」の中から形を絞り込んでいく。この「偶然性ベースのゆるい状態から締めていく」アプローチが、個性的なセンスを育む上で重要になります。
そして、「自分に固有の、偶然性の余らせ方を肯定する」ことが大切だと千葉氏は説きます。完璧ではない技術と、自分の中から湧き出る偶然性が合わさって生まれるものこそが、その人固有の表現であり、それを信じること。それが、創造性を解き放つ鍵となるのです。
時間と人間:可能性の溢れを生きる
芸術は、「時間をとること」そのものである、と千葉氏は述べます。効率や目的達成が重視される現代において、芸術は、一見「無駄」に見える時間の中に身を置き、そのプロセス(リズム)を味わうことを教えてくれます。
フランスの哲学者ベルクソンは、生物、特に人間は、外部からの刺激に対して即座に反応せず、「遅延」する能力を持つと考えました。この「遅延=迷う時間」こそが、人間の自由であり、多様な可能性を生み出す源泉です。
しかし、この「可能性の過剰」は、時に私たちを不安にさせ、何をすべきか分からなくさせます。芸術は、この溢れる可能性を、作品という「有限な形(リズム)」に仮固定することで、私たちに束の間の安定と、多様な生き方への肯定を与えてくれるのです。
アンチセンス:どうしようもなさの反復と魅力
最終章で千葉氏は、これまで論じてきた「センス」の概念をさらに深め、「アンチセンス」という考え方を提示します。
AIは、バランスの取れた美しいリズムも、偶然性の強い崇高なリズムも生成できるかもしれません。しかし、人間にあってAIにないもの、それは「生きることからくる反復の必然性」、すなわち「どうしようもなさ」だと千葉氏は考えます。
ある作家が繰り返し描くモチーフ、ある音楽家が好んで使う響き。それは、単なる技術やスタイルではなく、その人が抱える「問題」の表れであり、無意識的な「反復」です。この、理屈では説明できない、時に「野暮ったい」とさえ思えるような個人的なこだわり(=アンチセンス)が、バランスの取れた「センス」を突き破る時、私たちはそこに抗いがたい魅力や深みを感じるのです。
センスの良さとアンチセンス。洗練と野暮ったさ。自由な生成変化と、どうしようもない反復。これらが拮抗し、混ざり合うところにこそ、人間のリアルな生があり、芸術の豊かさが生まれるのではないでしょうか。
一人暮らしの雑然とした部屋にも、高級ホテルの洗練された空間とは違う、その人固有の「問題」と「リズム」が刻まれています。センスは、アンチセンスという陰影を帯びてこそ、真の輝きを放つのかもしれません。
本書『センスの哲学』は、単にセンスを良くする方法を教えるだけでなく、意味や正解に縛られた窮屈な世界観から私たちを解放し、物事のリズムを感じ、偶然性を受け入れ、そして自分自身の「どうしようもなさ」さえも肯定的に捉え直すための、深く豊かな視座を提供してくれる一冊です。