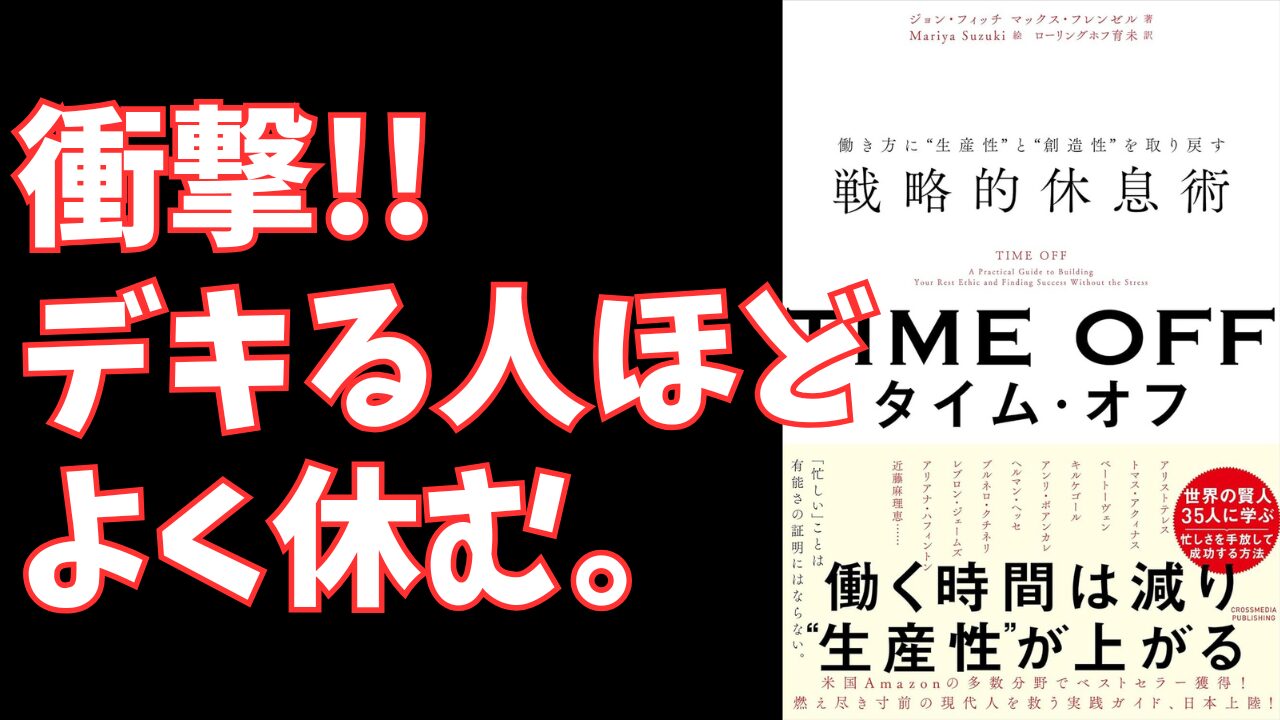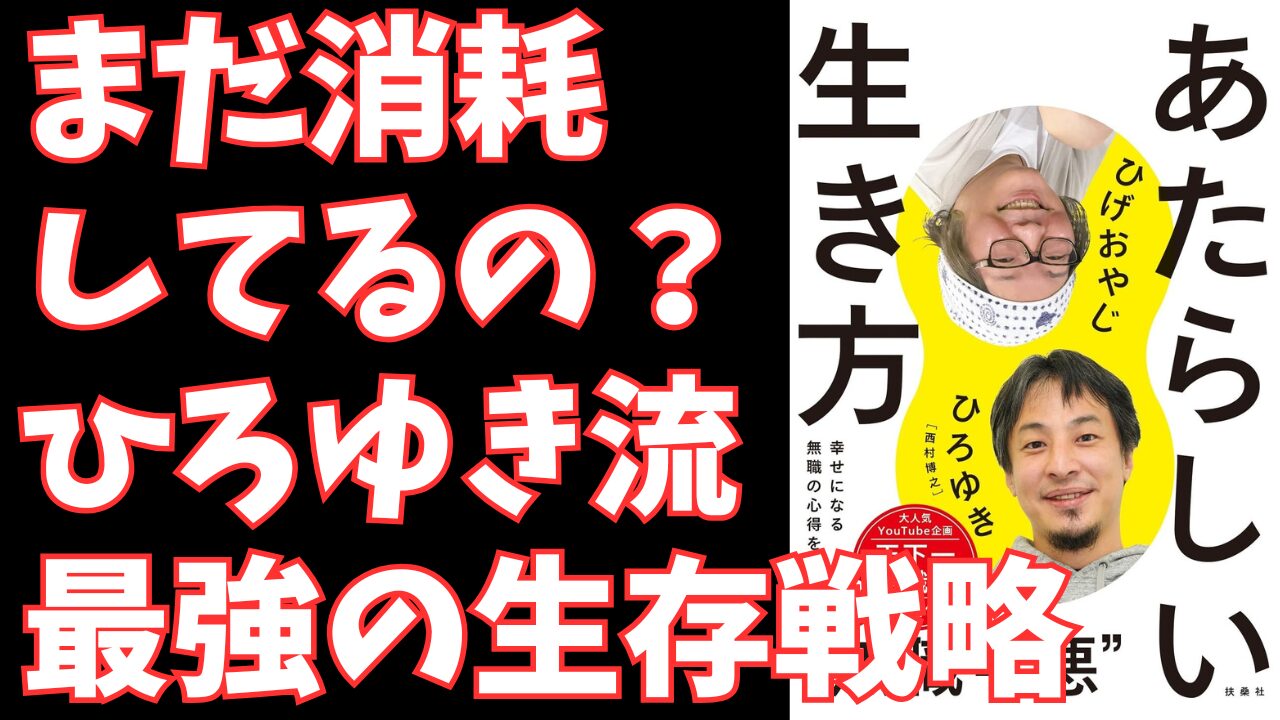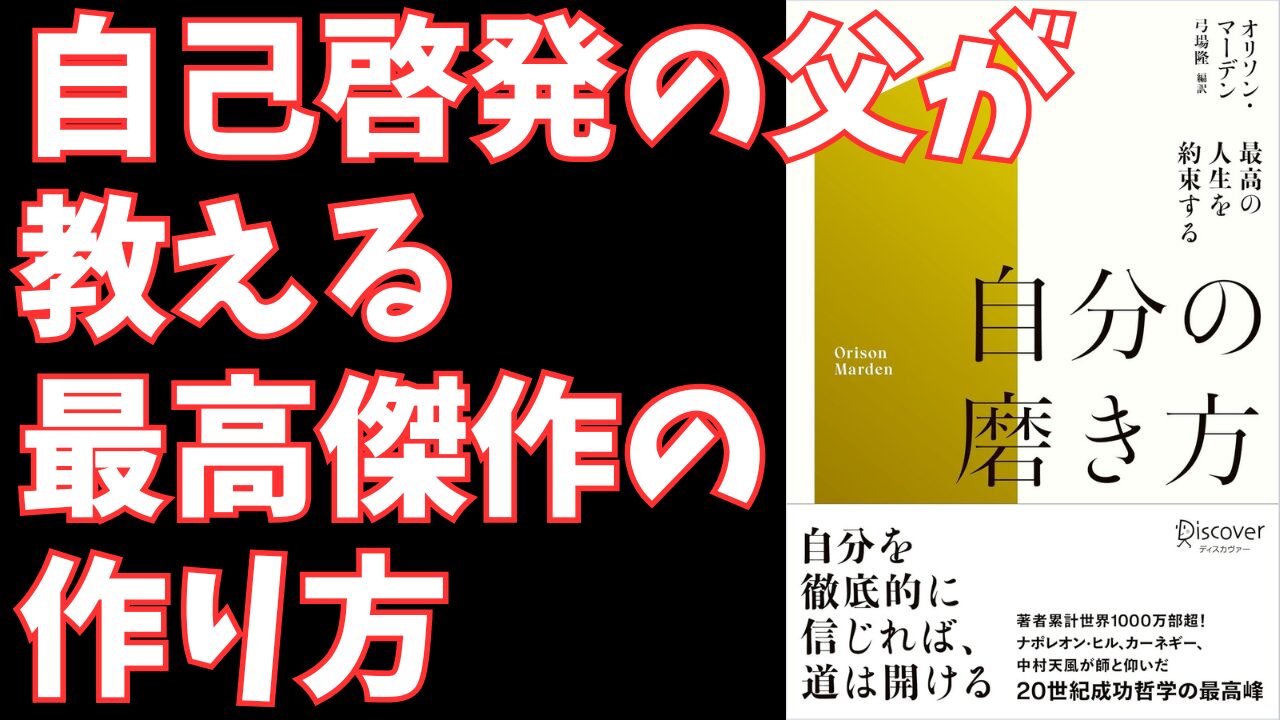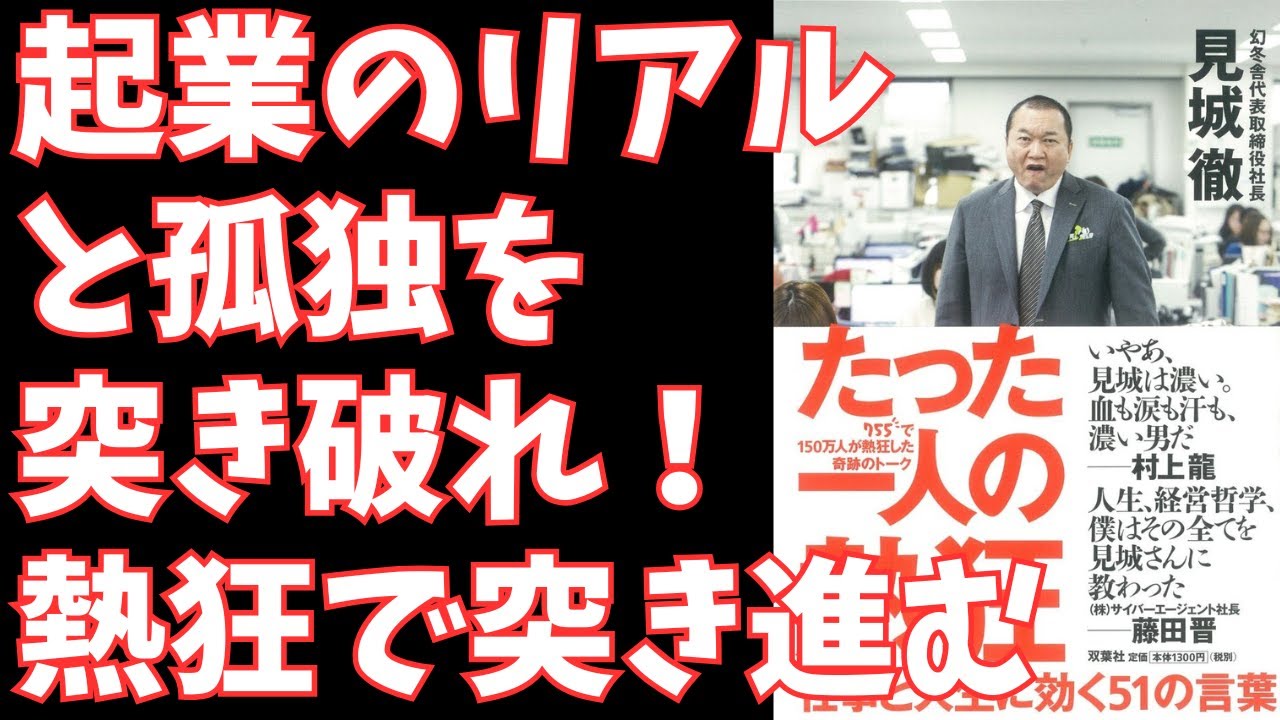齋藤孝が教える!ビジネスパーソンのための「本物の教養」6選 – 激動の時代を生き抜く思考法
本書『20歳の自分に教えたい本物の教養』の著者である齋藤孝氏は、教養とは単なる知識の詰め込みではなく、知識同士が「つながる」ことで人生に豊かさと奥行きをもたらすものだと説いています。
この記事では、本書に基づき、なぜ現代の忙しいビジネスパーソンにこそ教養が必要なのか、そしてその土台となる「お金と資本」「宗教」「哲学・思想」「歴史」「芸術」「言葉と文学」という6つの必須教養について、具体的な事例とともに詳しく解説します。
本書の要点
- 教養とは、クイズのような1対1の知識ではなく、多様な知識が結びついた「つながり」である。
- 教養は、他者と知的な会話を楽しむための「ラリー」の土台であり、人生に豊かさと奥行きを与える。
- 現代を生き抜くためには「お金と資本」「宗教」「哲学・思想」「歴史」「芸術」「言葉と文学」の6つの柱が必須教養となる。
- スマホ検索(お堀)と新書(本丸)の両方をうまく使いこなし、自分だけの教養の砦を築くことが重要である。
- 教養を身につけることで、情報過多の時代でも物事の本質を見抜き、自己肯定感を高め、希望を見出す力となる。
なぜ今、ビジネスパーソンに「本物の教養」が必要なのか?
「教養」と聞くと、あなたはどのようなイメージを持つでしょうか。単なる知識量や、クイズ番組で役立つ雑学のようなものを想像するかもしれません。
しかし、著者である齋藤孝氏は、教養とは 「クイズのように1対1の対応関係で答えるようなものではなく、知識のつながり」 だと断言します。
たとえば、「ミケランジェロが制作した有名な彫刻は?」という問いに「ダビデ像」と即答できても、それは単なる知識に過ぎません。
「ミケランジェロが彫刻で表現した『旧約聖書』の英雄モーセ像を、フロイトは『動きをテクニックで表す他の彫刻とは一線を画している』と評価した」というように、『旧約聖書』、ミケランジェロ、フロイトといった異なる分野の知識がつながってこそ、初めてそれは「教養」となり、人生に豊かさと奥行きを与えてくれるのです。
教養は「知的な会話」の土台
ビジネスシーンにおいても、教養は不可欠です。教養がある者同士の会話は、卓球の「ラリー」を楽しむようなものだと齋藤氏は言います。
たとえば、会話の中で「まるでバベルの塔みたいだね」という比喩が出たとき、「それって何ですか?」といちいち躓いていては、話が弾みません。共通の土台(教養)があるからこそ、高度なアンサンブルのような知的な会話が可能になります。
逆に言えば、教養がなければ、深みのあるコミュニケーションは楽しめません。
“知の貧困”に陥らないために
現代は、スマホ一つで膨大な情報にアクセスできる時代です。しかし、SNSで自分と同じレベルの人とばかりコミュニケーションを取っていては、新たな知識や教養は身につきにくいものです。
齋藤氏は、こうした状態を「お金の貧困」よりも心配な 「教養(知)の貧困」 と呼んでいます。
では、どうすれば教養を身につけられるのか。齋藤氏は「スマホ検索」と「新書読み」を推奨します。
わからないことがあればその場でスマホ検索する。検索を繰り返すうちに、宗教的な意味から芸術作品、言語の問題まで、知識の「つながり」が見えてきます。
- インターネット上の情報 = お堀(入れ替わりながら流れている)
- 新書で得る情報 = 本丸(専門分野の入門書として情報が網羅されている)
この両方を活用し、自分だけの「教養の砦」を築いていくことが、現代を生きる私たちには求められています。
柱①「お金と資本」– 資本主義社会を生き抜く必須知識
本書が教養の第一の柱として挙げるのが「お金と資本」です。
「教養というと、お金の話は無粋だ」と感じる人もいるかもしれません。しかし、私たちが生きるこの社会は「資本主義社会」です。お金とどうつきあうかは、豊かな人生を生きるための重要なテーマであり、精神の安定にもつながります。
なぜマルクスの『資本論』が今も重要なのか
齋藤氏が大学生だった頃、マルクスの『資本論』を中心とした社会主義理論は必須の教養でした。現代ではマルクスを知らない人も増えましたが、資本主義を深く理解するためには『資本論』は押さえておきたい教養の書だと述べています。
マルクスが指摘したのは、資本主義における「搾取」の構造です。
労働者は、自分の生活費(労働力の価値)以上の価値(例えば1万円)を生み出しても、給料として支払われるのは生活費分(例えば5千円)だけ。残りの5千円は資本家の儲け(剰余価値)となります。
これがマルクスの言う「搾取」であり、資本家はより豊かになり、労働者は豊かになれないという問題点です。
この構造を知ることは、現代の日本が抱える問題、例えば「なぜ日本はこの30年間、ほとんど給与が上がらなかったのか」を理解する助けにもなります。パートタイマーやアルバイトといった労働力が多く流入したことで、企業は賃金水準を上げずに済んできた、という見方もできるのです。
資本主義の「精神」を体現した2人の巨人
資本主義を考える上で欠かせない重要人物として、本書はベンジャミン・フランクリンと渋沢栄一を挙げます。
1. ベンジャミン・フランクリン(アメリカ資本主義の父)
「時間は貨幣(タイム・イズ・マネー)」という言葉で知られるフランクリンは、「倹約し、勤勉であれ」と説き、ビジネスで成功しました。
彼の背景にはプロテスタンティズムの倫理観がありました。マックス・ヴェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』にもあるように、フランクリンは個人の利益よりも公共心をもって事業を行う「資本主義の精神」を体現していました。
2. 渋沢栄一(日本資本主義の父)
フランクリンにとっての『聖書』が、渋沢栄一にとっての『論語』でした。
渋沢は、日本初の銀行設立など約500もの企業設立に携わりましたが、その根底には「『論語』の精神で経済をやる」という強い信念がありました。
お金儲けを卑しいものと見なす風潮に対し、渋沢は「金銭を取り扱うが何ゆえ賤しいか。君のように金銭を卑しむようでは国家は立たぬ」と反論しています。経済発展のためには高い倫理観が必要だという彼の経営哲学は『論語と算盤』にまとめられています。
投資の神様・バフェットから学ぶ「企業分析」
教養のバランスを取る意味で、現代の経済の動きを知る「投資術」の本も有効です。
「投資の神様」ウォーレン・バフェットは、師であるベンジャミン・グレアムから「バリュー投資」(株を安く買って高く売る)を学びました。
当初、バフェットは財務諸表などを分析する「定量分析」を重視していましたが、やがてフィリップ・フィッシャーの理論を取り入れ、「定性分析」も重視するようになります。
定性分析とは、事業内容や経営者の資質など、数字に表れないものを評価することです。
1963年の「サラダオイル事件」でアメリカン・エキスプレスが倒産の危機に瀕した際、多くの投資家が株を売りました。しかしバフェットは、実際にレストランなどを調査し、「顧客の信用は落ちていない」と判断。巨額の投資を行い、大きな利益を上げました。
これは、投資家だけでなく、企業の本質的な価値を見抜く目が求められるビジネスパーソンにとっても非常に示唆に富むエピソードです。
柱②「宗教」– 世界の”今”と対立を理解する鍵
「日本人は無宗教だ」とよく言われます。しかし、齋藤氏は、今の時代だからこそ宗教を学ぶ意義は大きいと指摘します。
なぜなら、世界で起きていること(例えば宗教間の対立や、特定の宗教の人口増加)は、宗教を知ることで初めて深く理解できるからです。
例えば、ムスリム(イスラーム教徒)の人口は急増しており、2100年にはキリスト教徒を抜いて最大勢力になると予測されています。この事実を知らずに、9.11テロなどのイメージだけで「イスラーム=危険」と短絡的に考えるのは、教養ある態度とは言えません。
まずは5大宗教の「全体像」をつかむ
宗教の世界も広大です。まずは「世界三大宗教」(キリスト教、イスラーム、仏教)に、ヒンドゥー教とユダヤ教を加えた5つの宗教の全体像をマップのように把握することが推奨されます。
- キリスト教: 世界最大の宗教。唯一神ゴッドを信奉。イエスは神の子。
- イスラーム: 唯一神アッラーを信奉。ムハンマドは「最後にして最大の預言者」。キリスト教、ユダヤ教とルーツは同じ。
- 仏教: 神ではなく、個人が「悟り」を得ることを目指す。開祖はゴータマ・シッダールタ(釈迦)。
- ヒンドゥー教: インドを中心に信仰される多神教(一神教的な側面も)。世界最古の宗教とも言われる。
- ユダヤ教: ユダヤ人の「民族宗教」。唯一神ヤーヴェに選ばれたという「選民思想」を持つ。
聖典から「本質」に触れる
全体像をつかんだら、聖典に触れてみましょう。
『旧約聖書』
キリスト教、ユダヤ教、イスラームの聖典でもあります。「アダムとエバ」「ノアの方舟」「バベルの塔」といった有名な物語は、西洋絵画や文学を理解する上でも必須の知識です。
また、「出エジプト記」のモーセが海を二つに割るシーンは、映画「十戒」などで映像化されており、物語として楽しむこともできます。
ブッダのことば
仏教は経典が多いですが、最も古いとされる「スッタニパータ」や「ダンマパダ」がおすすめです。
「ものごとは心にもとづき、心を主とし、心によってつくり出される」
「苦しみは執着から生まれる」
といったブッダの言葉は、現代人の悩みにも通じる普遍的な真理を突いています。
『コーラン』
イスラームの聖典『コーラン』は、『聖書』のような物語ではなく、神からの細かい戒律が記されています。礼拝や食事の規定だけでなく、商取引、結婚、遺産相続まで、あらゆる指示があります。
これは、イスラームが「信仰+行動様式+法体系」であることを示しています。また、「人間はみな平等(神の前の平等)」という先進的な概念が7世紀にすでに唱えられていたことも注目に値します。
柱③「哲学・思想」– 情報の海で”本質”を見失わないために
哲学は、いわばニュースの対極にあるものです。「そもそも〇〇とは何か?」と物事の根本に立ち返って考える営みです。
情報が溢れ、変化のスピードが速い現代において、自分を見失いそうになったとき、根本に立ち返る「哲学・思想」は、思考をスッキリさせ、気持ちを落ち着かせてくれます。
ソクラテス:「無知の知」と「知を愛する」こと
古代ギリシャの哲学者ソクラテスは、「自分は何も知らない」ということを知っている(無知の知)点で、知っていると思い込んでいる他者より賢いと考えました。
哲学(フィロソフィー)の語源は「フィロソフィア(知を愛する)」です。「本当は何なのだろう?」と驚き、気づく瞬間こそが哲学の始まりです。
デカルト:「我思う、ゆえに我あり」
近代哲学の父デカルトは、数学的な思考法を哲学に持ち込みました。
彼は、目に見えるものも含め、あらゆるものを疑いました。そして、すべてを疑った末に、たった一つだけ確かなものを見つけます。それが、「疑うという作業をしている自分の意識」の存在でした。
「我思う、ゆえに我あり」という言葉は、キリスト教的な思想から脱却し、「近代的な自我の目覚め」を宣言する画期的なものでした。
カント:「コペルニクス的転回」
カントは、「対象」と「認識」の関係をひっくり返す大発見をしました。これを彼は「コペルニクス的転回」と呼びました。
私たちは「対象(モノ)があるから、それを認識できる」と考えがちです。
しかしカントは、「人間は、もの自体を正しく認識することはできない」と言います。私たちが見ているのは、自分の認識システム(例えば、近眼の人の見え方、犬の嗅覚、ダニの世界)を通して構成された「現象」に過ぎません。
つまり、「対象があるから認識する」のではなく、「認識が先にあって、対象をそのように構成する」のです。この考え方は、私たちの常識を揺さぶります。
ニーチェ:「超人」と「永劫回帰」
ニーチェは、キリスト教的な価値観を批判し、人間はもっと自由に、能動的に生きるべきだと説きました。
彼が言う「超人」とは、スーパーマンではなく、既存の価値観にとらわれず、新しい価値を生み出す人間のことです。
たとえ人生がどんなに辛く、不条理であっても、「よし、もう一度」と自らその運命を引き受ける。何度でも繰り返してやろうという強さ。これが「永劫回帰」の思想です。
ニーチェの哲学は、私たちにチャレンジする勇気を与えてくれます。
柱④「歴史」– 人類の失敗と成功から未来を構想する
「歴史は繰り返す」と言われるように、人間は同じようなことを繰り返しています。だからこそ、私たちは歴史に学ぶ必要があります。過去のパターンを知ることで、未来を予測し、備えることができるのです。
忘れてはならない人類の失敗
世界史を学ぶとき、まず直視すべきは人類の「負の歴史」です。
1. 支配と殺戮の歴史(大航海時代)
1492年、コロンブスが新大陸に到達して以降、スペインやポルトガルは中南米に進出し、アステカ帝国やインカ帝国を滅ぼしました。先住民を虐殺・奴隷化し、財産だけでなく言語や宗教まで支配しました。
労働力が不足すると、アフリカから黒人奴隷を「貿易」するという、人間を商品として扱う残酷な行為も行われました。
2. 帝国主義の時代
18世紀後半の産業革命以降、イギリスをはじめとする欧米列強は、資本の力で弱い国を支配する「帝国主義」政策をとりました。
植民地(例えばインド)は原料供給国とされ、自国で製品を作ろうとすると罰せられるなど、徹底的に搾取されました。
3. 日本の大失敗
帝国主義の波は日本にも及びました。ペリー来航後、日本は不平等条約を結ばされます。
この危機感から明治維新を成し遂げ、近代化に成功したところまでは良かったのです。しかし、日本は「支配される側」ではなく「支配する側」に回ろうとしてしまいました。
欧米にやられた不平等条約を、今度は自分たちが朝鮮に対して結ばせる(日朝修好条規)。
齋藤氏は、これを『論語』の最も重要な教えである「己の欲せざるところ人に施すことなかれ(自分がやられて嫌なことを人にするな)」に反する行為であり、日本の大失敗だったと厳しく指摘します。
現代の国際情勢を歴史から読み解く
21世紀の今、ロシアによるウクライナ侵攻という悲劇が起きました。
国際平和を維持するための国際連合(国連)ですが、その中心である常任理事国(ロシア)が戦争を仕掛けたことで、国連はその限界を露呈しました。
この問題を考えるときも、歴史的な背景が不可欠です。
ウクライナはロシアにとって「兄弟」のような特別な国でした。そのウクライナが、ロシアに対抗する軍事同盟であるNATOに接近したことが、侵攻の一因とされています。
また、米英がウクライナを支援する構図を、「ウクライナの人たちを使った代理戦争的な面がある」と見る視点(エマニュエル・トッド氏など)もあります。
こうした複雑な国際情勢を理解し、日本の防衛問題(憲法第9条と自衛隊のあり方)について現実的に考えるためにも、歴史の教養は不可欠なのです。
柱⑤「芸術」– 人生を豊かにし、魂の栄養を満たす
教養の柱として「真・善・美」という言葉がありますが、「美」を扱うのが芸術です。
芸術は人の心を動かし、ひらめきや刺激を与えてくれます。情報社会や資本主義社会で疲弊しがちな現代人にとって、本物の芸術に触れることは、「魂の栄養」として、ますます重要になっています。
美術:ものの見方を変える力
- レオナルド・ダ・ヴィンチ「モナ・リザ」
この作品のすごさは、輪郭線がない「スマフート」という技法にあります。ぼやけているようであり、くっきりとも見える。まるで本物の人間がそこにいるかのようなリアルさを生み出しています。 - 印象派(モネ、セザンヌ)
それまでの写実主義的な絵画を乗り越え、画家の「目に映った世界(印象)」を描こうとしました。モネの「印象・日の出」は、絵画の世界の「ものの見方」そのものを変えました。 - パブロ・ピカソ
対象をさまざまな角度から捉え、幾何学的に再構成する「キュビスム」を生み出し、絵画のルールを根底から覆しました。
音楽・演劇:時を超える感動
- クラシック音楽
同じ曲(例えばモーツァルトのピアノ協奏曲第20番)を、違う指揮者や演奏者で聴き比べることで、その違いや奥深さがわかります。 - オペラ
モーツァルトの「魔笛」に出てくる「夜の女王のアリア」は、人間の業とは思えない超高音のアリアです。YouTubeの解説動画などを見れば、その音楽が何を表現しているか(例えば、復讐心による狂気)を知ることができ、より深く楽しめます。 - ミュージカル
「オペラ座の怪人」や「レ・ミゼラブル」は、音楽の素晴らしさ、物語の重厚さにおいて、まさに傑作です。 - 歌舞伎・能
歌舞伎の「外郎売」や「白浪五人男」の七五調のリズミカルなセリフ、能の「腰肚文化」に裏打ちされた身体感覚など、日本の伝統芸能には独自の面白さがあります。
柱⑥「言葉と文学」– 思考の基盤であり、文化の守り手
日本語は、日本人の教養のベースとなるものです。
思考は言葉を使って行われます。語彙が乏しければ、思考も狭くなってしまいます。
語彙が豊富であれば、表現が豊かになるだけでなく、見える世界そのものが変わるのです。
古文は「音読」で楽しむ
古文が苦手な人は多いですが、齋藤氏は文法を覚えるより「音読」を推奨します。
『平家物語』などを音読すると、琵琶法師によって磨き抜かれた「語り」のパワーとリズムの良さを実感できます。意味は優れた現代語訳で先に理解しておけば十分です。
『源氏物語』という奇跡
日本文学の最高峰であり、1000年以上前に書かれた『源氏物語』を読まないのはもったいない、と齋藤氏は言います。
当時の貴族社会は、和歌のセンスや手紙の文章で相手を判断する、まさに 「人は教養が9割」 の世界でした。
紫式部は、和歌の才能、漢学の素養、そして物語の構成力すべてにおいて傑出していました。ドナルド・キーン氏が日本文学に惚れ込むきっかけとなったのも『源氏物語』です。
俳句・短歌:世界最短の詩
五七五の俳句は、世界最短の詩です。松尾芭蕉が芸術の域に高め、小林一茶は現代人にも通じる感覚的な句を詠みました。
現代の歌人、河野裕子さんと永田和宏さん夫妻が40年間にわたり詠み続けた恋歌(『たとへば君』)は、伝統的な文学が今もなお深く人の心を打つことを証明しています。
日本語と文化を守る意識
日本の近代文学(夏目漱石、幸田露伴、宮沢賢治など)は、世界レベルの優れた作品の宝庫です。
しかし、作家の水村美苗氏は『日本語が滅びるとき』で、英語が普遍語となる現代において、日本語の文学的水準が維持できなくなるのではないかと警鐘を鳴らしました。
もちろん英語も重要ですが、日本語でしか表現できない世界、日本語でしか味わえない豊かさがあります。
『雪国』の冒頭「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」という主語のない文章の味わいは、英訳では失われてしまいます。
日本語を母語とする私たちは、その豊かさを享受するとともに、日本語とそれが育んできた文化を守っていく意識を持つ必要があるのです。
まとめ:教養の道を歩み、豊かな人生を手に入れる
齋藤氏は大学で学生たちにこう語りかけるそうです。
「君たちには2つの道がある。教養のある道と、教養のない道だ。私は、君たちと教養のある道をともに歩んでいきたい」
本書で紹介された6つの教養は、その道を歩むための入り口です。
何か一つでも深めれば、知識同士が次々につながり、世界の見方が変わっていく面白さを体験できるでしょう。
教養は、他者と深い共感を生み出します。それは自己肯定感だけでなく、「人類はこんなに素晴らしいものを生み出してきたんだ」という人類全体への肯定感にもつながります。
教養を身につけることは、ときに歴史の暗い部分を直視することでもありますが、それ以上に、困難な時代においても希望を見出す力を与えてくれます。
忙しいビジネスパーソンであるあなたも、ぜひ「教養の道」を歩み始め、仕事にも人生にも深みと豊かさをもたらしてみてはいかがでしょうか。