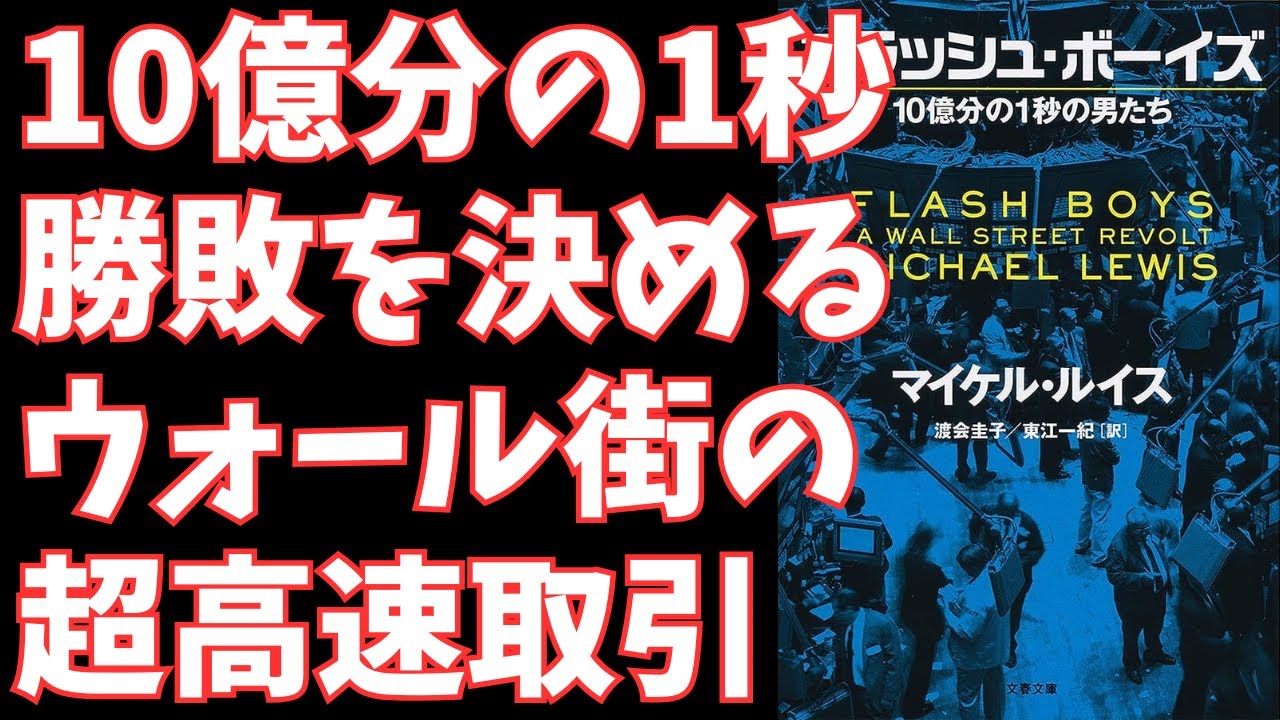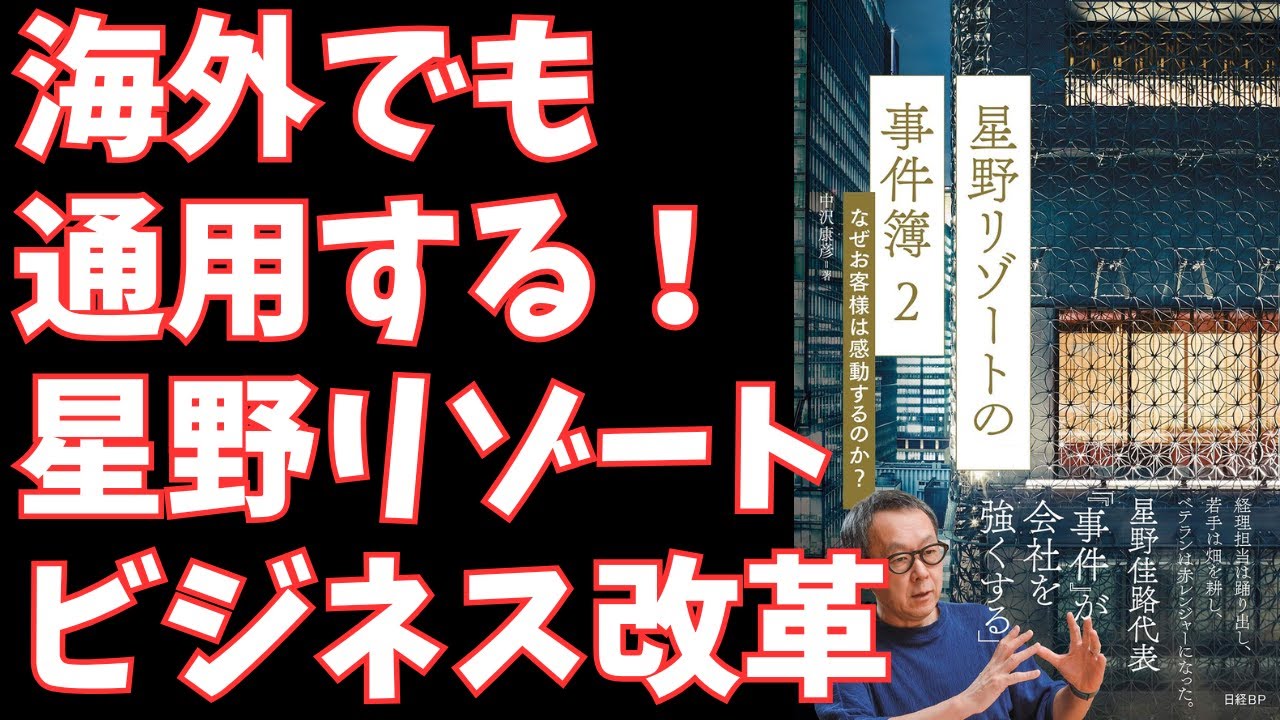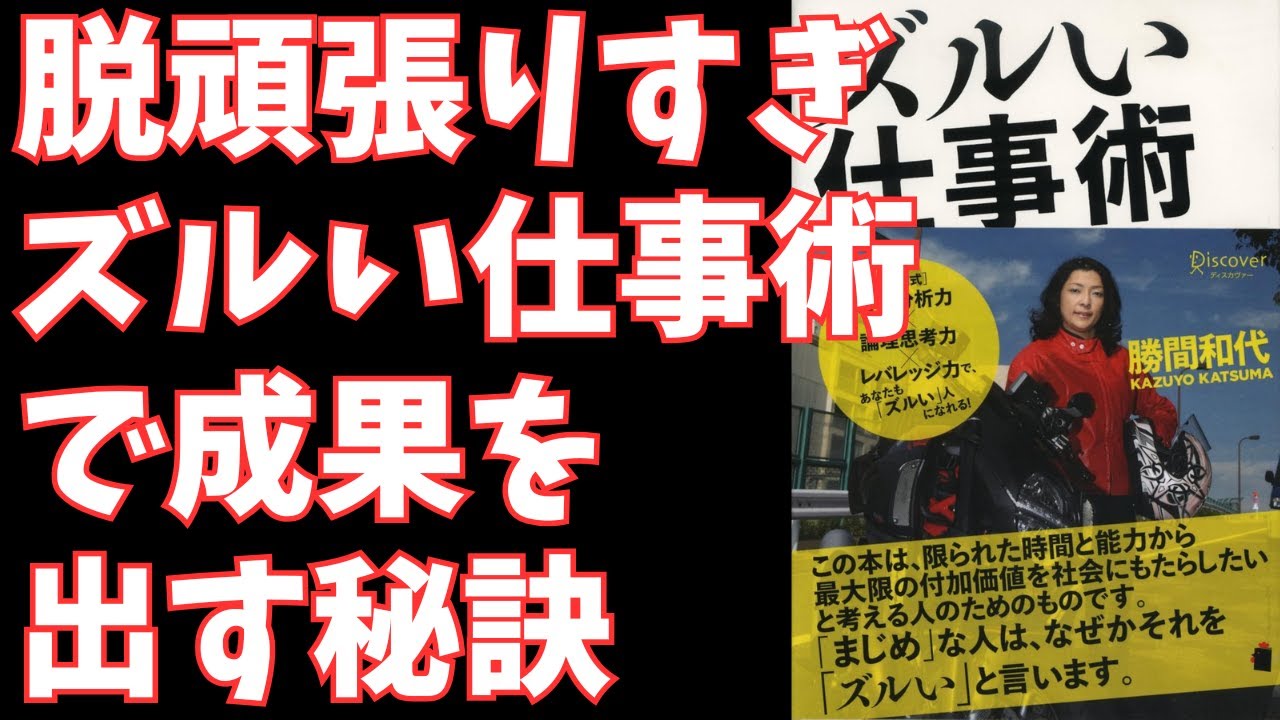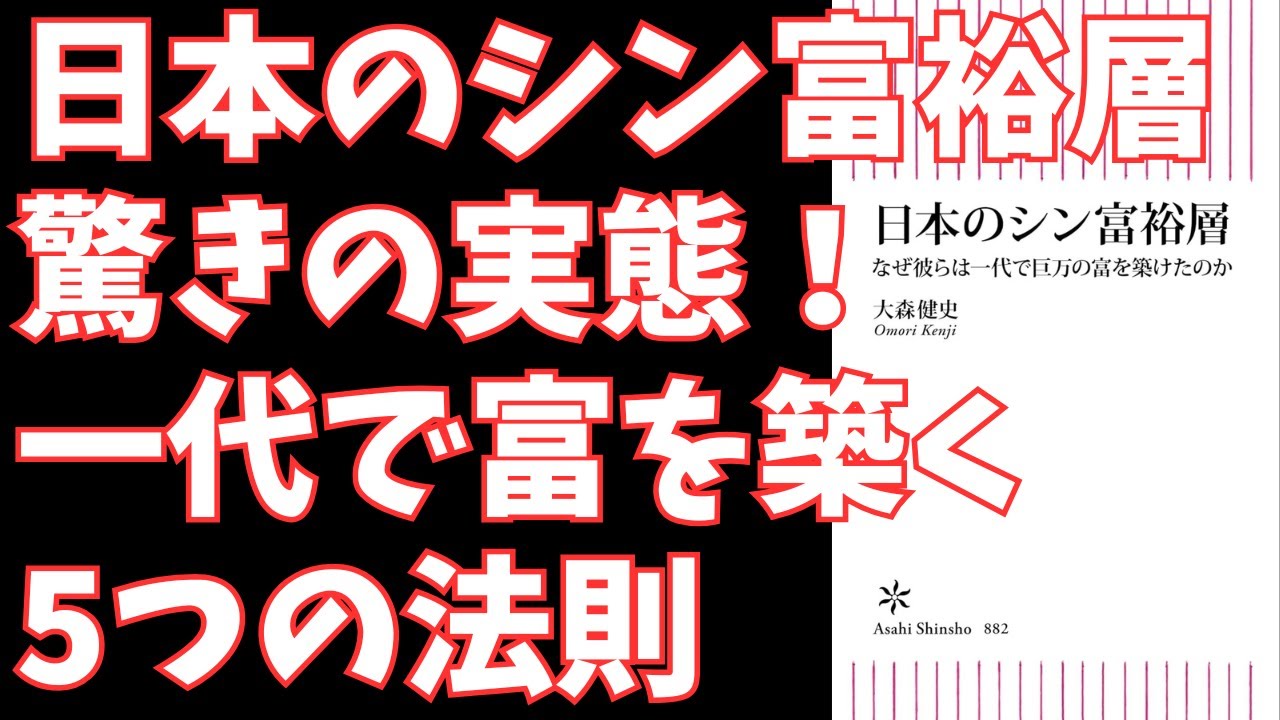センスは知識から始まる:ビジネスで差をつける「最適化」スキルを磨く方法
本書『センスは知識からはじまる』は、クリエイティブディレクターの水野学氏が、「センスは特別な才能ではなく、知識の集積によって後天的に獲得できるスキルである」という独自の定義を提唱し、その具体的な磨き方やビジネスへの応用方法を解説した一冊です。センスとは「数値化できない事象を最適化する能力」であり、その根幹には客観的な「知識」が必要不可欠であると説きます。本書では、知識を効率的に収集し、それをセンスへと昇華させて仕事や日常に活かすための具体的な思考プロセスやトレーニング方法が、豊富な事例とともに紹介されています。「センスがない」と思い込んでいるビジネスパーソンにとって、新たな視点と実践的なヒントを与えてくれるでしょう。
本書の要点
- センスは才能ではなく、知識の集積によって後天的に磨かれるスキルである。
- センスとは「数値化できない事象を最適化する能力」であり、その基盤は客観的な知識である。
- センスを磨くには、まず「普通」を知り、客観的な情報を集めることが重要である。
- 知識を効率的に得るには、「王道を知る」「流行を知る」「共通項を探る」というステップが有効である。
- 日常の小さな工夫(いつもと違う行動、読書、人との対話など)で、センスは鍛えられる。
はじめに:「センスがない」は思い込み?
「あの人はセンスがいい」「自分にはセンスがないから…」私たちは日常的に「センス」という言葉を使いますが、その正体は何なのでしょうか?多くの人は、センスを「生まれつきの才能」や「特別なひらめき」のように捉えがちです。
本書の著者であり、NTTドコモ「iD」や「くまモン」のデザインなどを手がけたクリエイティブディレクターの水野学氏は、こうした考え方に真っ向から異を唱えます。センスは、決して一部の特別な人だけが持つ魔法のようなものではなく、方法を知り、必要な努力と時間をかければ、誰でも身につけられる後天的なスキルであると断言するのです。
水野氏は、自身のアイデア創出プロセスやクリエイションの「手の内」を、講演会や大学の講義、書籍などで積極的に明かしています。それは、特別な才能ではなく、実践的な方法論に基づいているからです。しかし、どれだけ方法論を伝えても、「結局はセンスの問題でしょう?」という反応が返ってくることが多いと言います。
例えば、慶應義塾大学での講義で、売れる商品を作るための「~っぽい分類」という方法論を解説した際、学生からは「斬新な企画には分類はそぐわないのでは?」「センスやひらめきがどう生まれるか教えてほしい」といった質問が相次ぎました。これは、「アイデアとは、生まれながらのセンスによるとんでもないひらめきから誕生する」という根強い思い込みの表れだと水野氏は指摘します。
ビジネスの現場でも、「水野さんみたいにセンスが良くないから無理」「ひらめきの神様が降りてこないかな」といった言葉が聞かれます。しかし水野氏は、「ひらめきの神さまなど、どこにもいやしない」とはっきり述べています。
確かに、水野氏のアウトプットには突飛に見えるものもあります。しかしそれは、地道なインプットと段階的な思考の末に生まれたものであり、決して天から降ってきたものではありません。日々の筋トレや助走があってこそのジャンプなのです。
本書は、この「センス」という曖昧な概念を解き明かし、誰でもセンスを鍛え、仕事や人生に活かすための具体的な方法論を提示します。もしあなたが「自分にはセンスがない」と思い込んでいるなら、その呪縛から解き放たれるきっかけになるはずです。
センスとは何か?:「数値化できない事象」を最適化する力
では、水野氏が定義する「センス」とは具体的に何でしょうか?
「センスのよさ」とは、数値化できない事象のよし悪しを判断し、最適化する能力である。
これが本書におけるセンスの定義です。
ファッションのセンスが良い、経営のセンスが良い、バッティングセンスがある…これらはすべて、数字だけでは測れない価値判断を含んでいます。例えば、経営センスが良い会社とは、単に業績が良いだけでなく、従業員や社会との関わり方など、数値化できない要素も含めて「最適化」されている状態を指します。
数値化できないからこそ、センスは曖昧で分かりにくいものと捉えられがちです。しかし、センスを磨く上で最も重要なのは、「普通」を知ることだと水野氏は言います。
「普通」とは、大多数の意見や常識のことではなく、「良いもの」と「悪いもの」の両方を知った上で、「一番真ん中」がわかる状態を指します。この「普通」という基準(定規)を持つことで、私たちは様々な事象を測り、その場にふさわしい「最適化」を行うことができるのです。
例えば、音楽のプロである坂本龍一氏がビートルズを「すごい」と言うのと、熱狂的なビートルズファンが言うのとでは、説得力が異なります。坂本氏は古今東西の音楽を知り尽くした上で、多角的にビートルズを評価しているからこそ、その言葉には重みがあります。これが「普通」を知っている状態です。
多くの人が「センスは特別なもの」と感じてしまう背景には、幼少期の美術教育の影響もあると水野氏は指摘します。絵や歌、運動などを「うまい/へた」という実技だけで評価され、「自分にはセンスがない」と思い込んでしまうケースが多いのです。しかし、美的センスは実技能力とイコールではありません。絵が描けなくても優れた審美眼を持つ画商がいるように、センスは知識や理解によっても養われます。
美術も本来は、歴史や技法といった「学科」と、絵を描く「実技」の両面から学ぶべき学問です。背景知識を知ることで、作品の見方や表現方法は深まります。例えば、マルセル・デュシャンの便器の作品も、「レディ・メイド」という概念を知ることで、単なる落書きではなく、芸術へのアンチテーゼとして理解できるようになります。
センスは、特別な才能ではなく、知識を学び、多角的な視点を養うことで、誰でも鍛えることができる能力なのです。 まずは、「普通」を知ることから始めましょう。
なぜ今、ビジネスに「センス」が必要なのか?
「自分はデザイナーじゃないし、センスなんて関係ない」そう思っているビジネスパーソンもいるかもしれません。しかし、水野氏は「センスが必要とされない仕事など一つもない」と言い切ります。現代において、センスは個人のスキルアップはもちろん、企業の存続すら左右する重要な要素になっているのです。
かつての高度経済成長期は、「質より量」の時代でした。とにかくモノを作れば売れ、技術力が企業の価値を決めました。しかし、技術が成熟し、どの企業も高品質なものを作れるようになると、「質の良いもの」はコモディティ化し、付加価値を生み出しにくくなります。技術力だけでは差別化が難しくなった現代において、新たな価値を生み出す鍵となるのが「センス」なのです。
水野氏は、現代と安土桃山時代が似ていると指摘します。戦国時代に鉄砲伝来という技術革新が起こり、世の中が安定した安土桃山時代には、千利休のようなクリエイティブディレクターが登場し、「侘び茶」という新たな美意識(センス)を確立しました。技術がピークを迎えると、人々は美しいものや新たな価値観を求めるようになるのです。産業革命後のアーツ・アンド・クラフツ運動も、大量生産品への反動として手仕事の美しさを見直す「センスの時代」への揺り戻しでした。
現代もまた、IT革命という技術革新を経て、「センスの時代」に突入していると水野氏は見ています。スティーブ・ジョブズが率いたアップルは、単なる技術力だけでなく、優れた美意識とセンスによって、コンピュータという製品に新たな価値を与えました。
しかし、多くの日本企業は、いまだに「ものづくり信仰」から抜け出せず、市場調査に依存しがちです。市場調査は、既存の価値観に基づいた意見しか集められず、真に新しい価値や「センスのいい」ものを生み出す妨げになる可能性があります。iPhoneのような革新的な製品は、市場調査からは生まれにくいのです。
日本企業に今必要なのは、スティーブ・ジョブズのような「経営者のセンス」であり、企業価値をセンスによって高める「クリエイティブディレクター」の視点だと水野氏は主張します。クリエイティブディレクターは、商品開発だけでなく、ロゴ、社屋、制服、さらには経営戦略に至るまで、企業のあらゆる側面を「最適化」する役割を担います。これは外部の専門家だけでなく、経営者自身や社内の人材でも担うことが可能です。
センスは、クリエイティブ職に限らず、あらゆるビジネスパーソンに求められています。例えば、会議資料を作成する際も、情報を的確に整理し、視覚的に分かりやすく伝える「センス」がなければ、内容は良くても相手に響きません。経理担当者であっても、書類の整理整頓や分かりやすい資料作成といった「見え方のコントロール」が信頼につながります。
どんな仕事であれ、アウトプットの見え方を最適化する「センス」が、その価値を高め、個人の評価や企業のブランド力を向上させるのです。 センスはもはや特別な能力ではなく、ビジネスにおける必須スキルと言えるでしょう。
センスの源泉は「知識」にある
では、どうすればセンスを身につけることができるのでしょうか?水野氏は、その答えは極めてシンプルだと言います。
センスとは知識の集積である。
これが本書の核心的なメッセージです。センスは、天から降ってくるひらめきや感覚的なものではなく、地道な知識の積み重ねによって形成されるというのです。
例えば、文章を書く場合、「あいうえお」しか知らない人よりも、五十音すべてを知り、さらに多くの語彙や表現方法を知っている人の方が、豊かで分かりやすい文章を書ける可能性が高いのは明らかです。知識が多ければ多いほど、表現の幅は広がり、より良いアウトプットを生み出す土壌となります。
企画を考える際、多くの人は「誰も見たことのない斬新なアイデア」を求めがちです。しかし水野氏は、まず「誰もが見たことのあるもの」、つまり過去の事例や既存の知識を徹底的に蓄えることが重要だと説きます。
世の中には「あっと驚く企画」が溢れていますが、その多くは「あっと驚く売れない企画」です。「あっと驚くヒット企画」はごく僅か(水野氏のイメージでは2%程度)。むしろ、「あまり驚かないけれど売れる企画」(同20%程度)の方が多いのです。iPhoneも、全くのゼロから生まれたのではなく、固定電話や携帯電話という既存の知識の延長線上にあります。
イノベーションとは、ゼロから何かを生み出すことではなく、既存の知識(A)と知識(B)を掛け合わせて新しい価値(C)を生み出すことなのです。そのためには、AやBに関する豊富な知識、さらにはD、E、F…といった多様な知識を持っていることが不可欠です。
知識は、過去を学ぶだけでなく、未来を予測するためにも役立ちます。優れた経営者が「勘」で市場の先行きを読むように見えるのも、実は膨大な知識と経験に基づいた「知識にもとづく予測」の結果であることが多いのです。風水が単なる占いでなく、気候や地形に関する知識に基づいた都市計画であったように、センスとは知識に裏打ちされた合理的な判断なのです。
水野氏自身、代官山に事務所を構える際、更地の段階で契約を決めたのは、単なる直感ではなく、「高台で日当たりが良い」「第二種中高層住居専用地域だから将来も静か」といった知識に基づいた予測があったからでした。
ただし、どんな知識でも良いわけではありません。センスを磨く上で最も重要なのは「客観的な情報」です。ファッションで言えば、単に流行を追うだけでなく、自分の体型や個性を客観的に把握し、それに合わせて服を選ぶことがセンスの良さにつながります。ビジネスにおいても、主観や思い込みを排し、客観的なデータや事実に基づいて判断することが、最適化への道を開きます。
センスの最大の敵は「思い込み」です。意識的に自分の主観を疑い、客観的な情報を集める努力を続けること。膨大な客観的知識の集積こそが、揺るぎないセンスを形作るのです。
知識を「センス」に変え、仕事を最適化する方法
センスの源泉が知識にあることを理解した上で、次はそれを具体的に仕事へ活かす方法を見ていきましょう。闇雲に知識を集めるのではなく、効率的なアプローチと活用法を知ることが重要です。
まず大前提として、「流行っているもの=センスがいいもの」ではないことを肝に銘じる必要があります。アサヒビールの「クリアアサヒ」は、その「ビールらしさ(シズル)」を見事に表現したパッケージデザインで大ヒットしましたが、その表面だけを模倣した商品は消費者に受け入れられませんでした。うわべだけの模倣ではなく、本質を捉えることが重要なのです。また、センスには「賞味期限」があることも忘れずに、常に情報をアップデートしていく必要があります。
では、効率よく知識を増やし、センスとして活用するにはどうすればよいのでしょうか?水野氏は3つのステップを提案しています。
- ① 王道を知る:
まず、その分野における「定番」「一番いいとされるもの」「ロングセラー」といった「王道」を深く理解することから始めます。王道には、その製品らしさ(シズル)が凝縮されており、最適化の指標となります。水野氏が共同運営するブランド「THE」では、「定番のボールペンとは何か?」を徹底的に議論し、未来の定番となりうる「フリクション」を選びました。王道を探求する過程で、そのジャンルに関する幅広い知識が自然と身につきます。 - ② 今、流行しているものを知る:
王道を押さえたら、次に「流行」を把握します。雑誌、特にコンビニに並ぶ多種多様な雑誌に目を通すのが効率的です。王道と流行という両極を知ることで、知識の幅は一気に広がります。 - ③ 「共通項」や「一定のルール」がないかを考えてみる:
集めた知識を分析し、自分なりの法則やルールを見つけ出すプロセスです。水野氏はショップインテリアを手がける際、多くの店舗を観察し、「入りやすいお店(繁盛店)は床の色が暗い」「雑貨店は少しごちゃごちゃしている方が良い」といった独自のルールを発見しました。これは、日本人の文化や顧客心理といった知識に基づいた分析の結果です。
これらのステップで得た知識は、選択や決断の場面で大きな力を発揮します。例えば、パッケージデザインを選ぶ際も、「色(同系色か補色か)」「文字(書体の歴史や背景)」といった知識があれば、デザイナーの提案を鵜呑みにせず、客観的な判断を下す助けになります。
さらに、知識の「精度」を高めることも重要です。iPhoneの背面が歪みなく美しいのは、通常の製造プロセスでは考えられないような、コストと手間をかけた「精度」へのこだわりがあるからです。消費者はその製造プロセスを知らなくても、製品から伝わる「精度の高さ」を感覚的に「かっこいい」「センスがいい」と感じ取ります。デザインやブランドは細部に宿るのです。
水野氏が手がけた「フランダースリネン」の事例は、知識をセンスに変え、ビジネスを成功させた好例です。
- ネーミング: 「フランダース」という言葉が持つ『フランダースの犬』のイメージ(素朴さ、優しさ)と、ターゲット層(リネン好きの20代後半~40代半ば女性)の特性を結びつけ、「フランダースリネンプレミアム」と命名。
- ロゴデザイン: リネンの歴史(活版印刷以前から存在)と高級感を考慮し、古い書体であるカッパープレートを採用。フランダース地方が3カ国にまたがることから、それぞれの国の王冠をモチーフに使用。
- 商品開発(トートバッグ): 「リネン」のシズル(薄さ、軽やかさ)と「トートバッグ」のシズル(丈夫さ)を両立させるため、リネンが綿の2倍の強度を持つという知識に基づき、あえて薄手でくたっとした生地を採用。
これらのプロセスは、決して特別なひらめきではなく、徹底した知識の収集、分析、そして最適化に基づいています。「感覚的にこれがいい」ではなく、なぜそう言えるのかを論理的に説明できること。それが、真に「売れる」ものを生み出すセンスなのです。
日常でできる!センスを磨く8つの習慣
センスは知識から始まり、日々の意識と実践によって磨かれていくものです。特別な訓練は必要ありません。忙しいビジネスパーソンでも、日常の中で簡単に取り入れられるセンスアップのヒントを8つご紹介します。
- ① 「好き」を深掘りする:
自分の「好き」という感情の根源を探ってみましょう。例えば「青色が好き」だとしたら、なぜ好きなのか?「子供の頃に見たゴレンジャーのアオレンジャーが好きだったから」というように掘り下げると、単なる色ではなく、キャラクター、物語、時代背景といった、より深い情報が見えてきます。この深掘りが、ターゲットのインサイトを探るヒントになります。 - ② 「好き嫌い」ではなく具体例で考える:
何かを評価する際、「好き」「嫌い」といった主観的な言葉ではなく、「誰が、どんなときに、どんな場所で使うのか」という具体的な状況を設定し、客観的な視点で考えましょう。例えば新しいグラスを開発するなら、「25歳の○○な女性が、□□な場面で使うとしたら…」と具体的にイメージすることで、より的確な判断ができます。 - ③ 狭い分野の知識も武器になる:
たとえニッチな分野でも、深い知識を持っていれば、それは強力な武器になります。「鉄道に詳しい」「海の生物なら何でも知っている」といった知識を、自分の仕事に結びつけてみましょう。「海の生物チョコ」のような、ユニークな発想が生まれるかもしれません。自分の得意な土俵で考えることで、仕事が楽しく、効率的になります。 - ④ 日常の「当たり前」を疑う:
無意識に行っている日常のルーティンを意識的に変えてみましょう。歯を磨く順番を変える、お風呂に逆向きで入る、いつもと違う通勤ルートを通る、普段読まない雑誌を手に取る。こうした小さな「いつもと違うこと」が、固定観念の枠を外し、思考の柔軟性を高めます。 - ⑤ 書店を活用する:
書店は知識の宝庫です。通勤途中などに立ち寄り、5分でいいので店内を高速で一周し、「あれっ」と少しでも気になった本を手に取ってみましょう。購入して読むのが理想ですが、立ち読みでも構いません。これを習慣にすれば、知的好奇心が刺激され、知識の幅が自然と広がっていきます。 - ⑥ 「幼児性」を取り戻す:
赤ちゃんが驚異的なスピードで成長するのは、見るもの聞くものすべてに驚き、強い感受性と好奇心を持っているからです。大人になると失われがちな「感じる力」を意識的に取り戻しましょう。「感受性+知識=知的好奇心」という公式を胸に、子どものように純粋な目で世界を見てみることが、知識の吸収と自由な発想を促します。 - ⑦ 人生の先輩と話す:
少し勇気を出して、年上の人に話を聞いてみましょう。経験豊富な人生の先輩は、知識、知恵、経験といった「センスのかたまり」です。彼らの話に耳を傾けることで、自分の視野は大きく広がります。たとえ面倒に感じても、それを上回る学びがあるはずです。 - ⑧ 「服選び」で客観視と最適化を練習する:
毎日の服選びは、センスを磨く絶好の練習機会です。「好き嫌い」ではなく、「自分の体型や特徴(客観情報)」「TPO(最適化の条件)」「目指すイメージ(ゴール)」を考慮して服を選んでみましょう。自分自身を客観的に分析し、最適化するプロセスは、ビジネスにおけるセンスの応用にもつながります。
これらの習慣は、どれもすぐに始められるものばかりです。日々の小さな積み重ねが、あなたのセンスを確実に向上させていくでしょう。
まとめ:「センス」という宝物は、あなたの中にある
水野学氏の『センスは知識からはじまる』は、「センス」に対する私たちの固定観念を打ち破り、それが誰にでも習得可能なスキルであることを力強く示してくれました。
センスとは、特別な才能やひらめきではなく、客観的な知識をベースにした「最適化」の能力です。そしてその能力は、日々の学びと実践によって、着実に磨いていくことができます。
私たちは皆、知らず知らずのうちに自分自身を「ガラパゴス島」のような狭い世界に閉じ込めてしまいがちです。しかし、ほんの少しの勇気を出して、日常の当たり前を疑い、新しい知識に触れ、多様な価値観に触れる「冒険」を始めれば、その島から抜け出すことができます。
- いつもと違う道を歩いてみる。
- 普段読まない本を手に取ってみる。
- 異なる分野の人と話してみる。
こうした小さな一歩が、あなたのセンスを刺激し、視野を広げ、仕事や人生をより豊かにしていくはずです。
技術が成熟し、変化の激しい現代において、幅広い知識に裏打ちされた「センス」は、ますます強力な武器となります。それは、単に良いものを作るだけでなく、その価値を的確に伝え、人々の心に響かせ、ビジネスを成功へと導く力となるでしょう。
「自分にはセンスがない」という思い込みは、もう捨ててください。センスという宝物は、すでにあなたの中に眠っています。 本書で示されたヒントを参考に、今日から「センスを磨く冒険の旅」を楽しんでみてはいかがでしょうか。