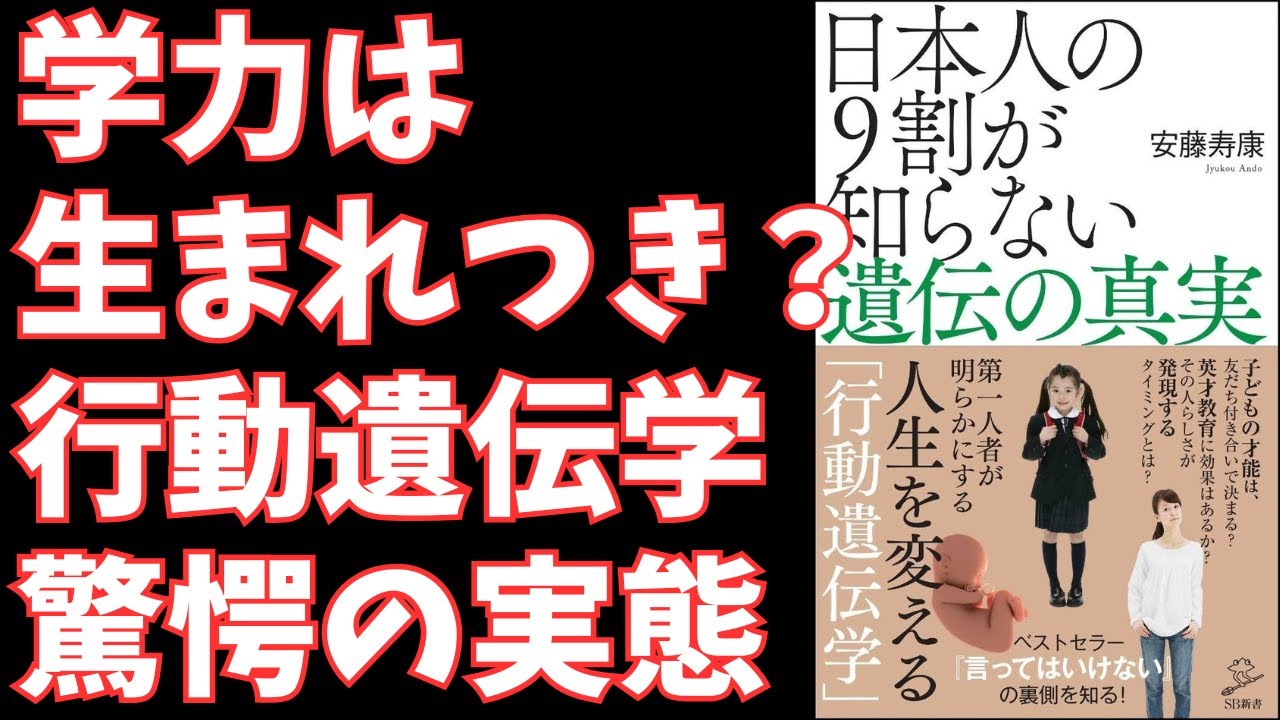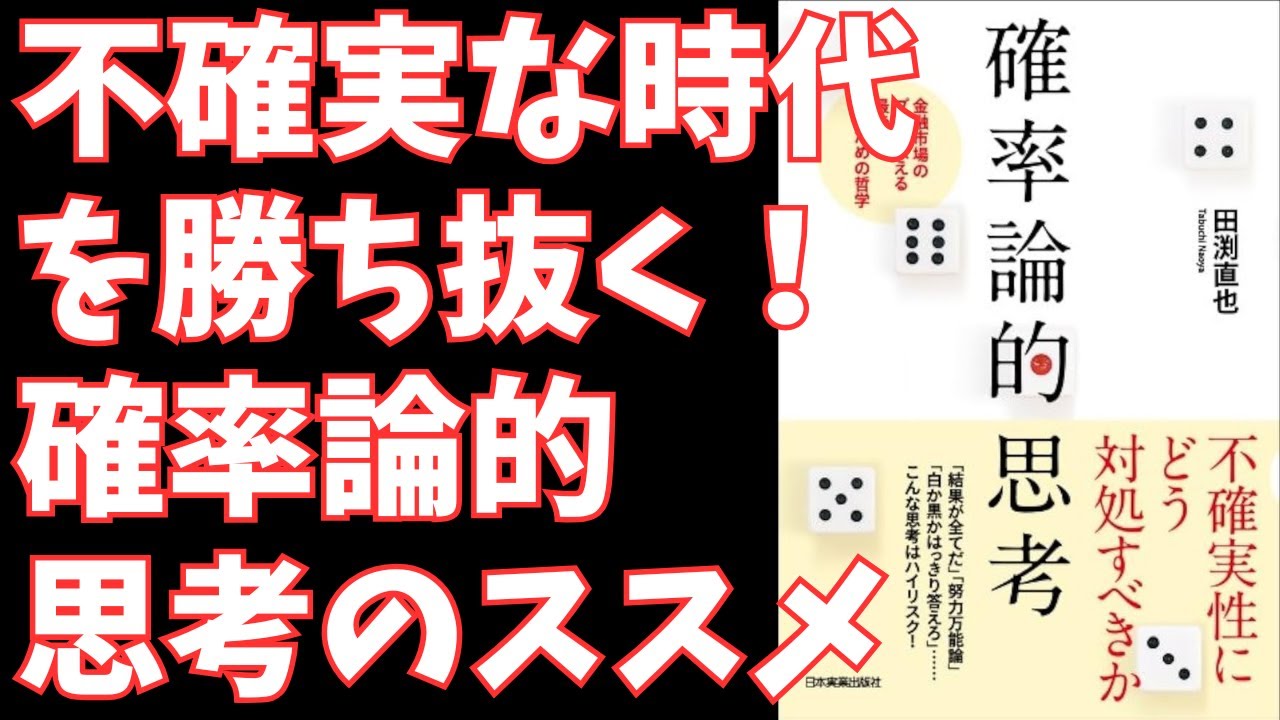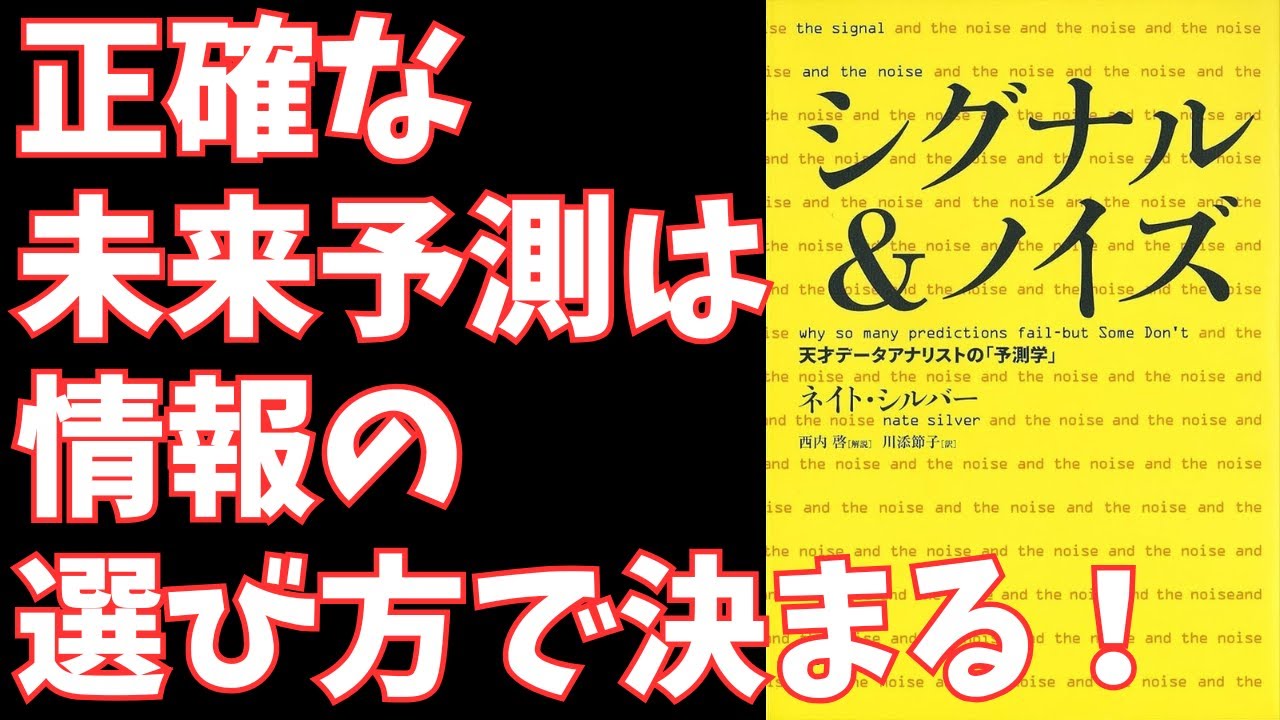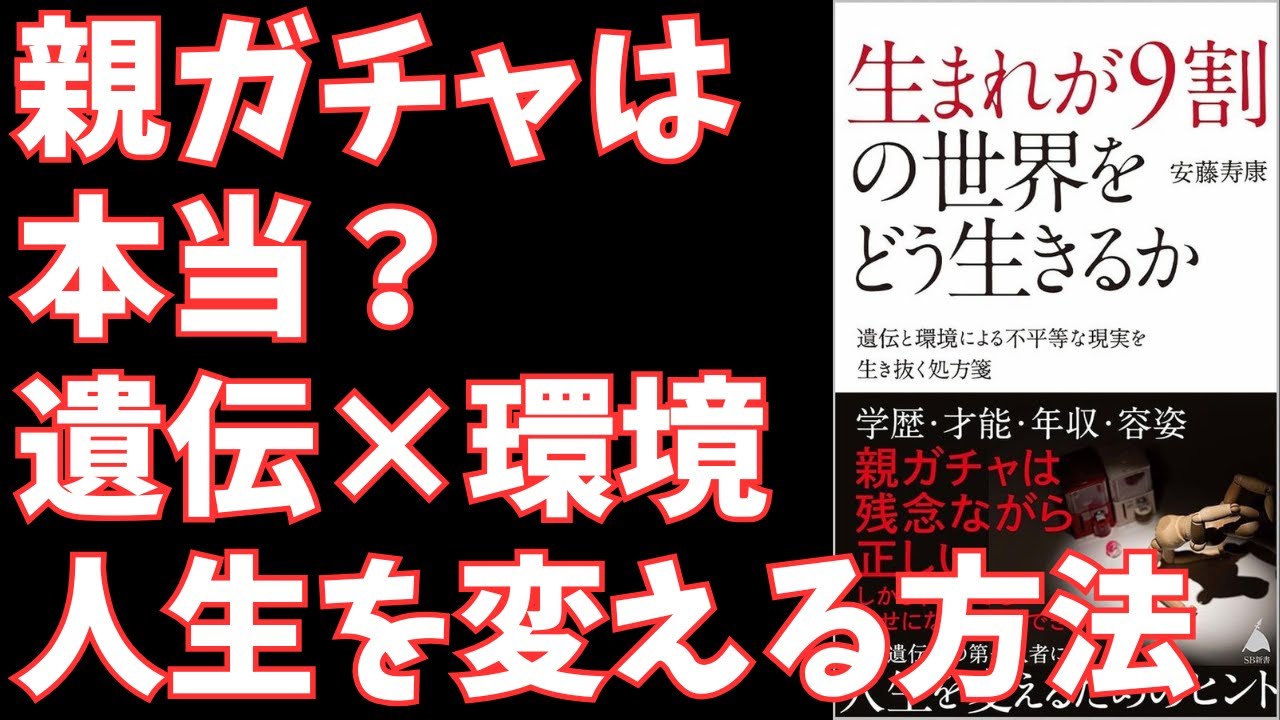人類史を変えた7つの発明とは?火からAIまで、技術革新がビジネスにもたらすインパクトを徹底解説!
本書「人類を変えた7つの発明史」は、ホモ・サピエンス20万年の歴史の中で、特に大きな影響を与えた7つの発明(火、文字、活版印刷、科学、鉄道、コンピューター、インターネット)を取り上げ、それらがどのように人類社会を変革し、現代の私たち、そして未来のAI時代にどのような示唆を与えるのかを壮大なスケールで描いた一冊です。著者は、それぞれの発明がもたらしたインパクトを、生物学的進化、情報の民主化、不可能の克服、効率化という4つの視点から分類し、具体的な歴史的エピソードを交えながら解説しています。特に現代の生成AIの登場を歴史的な転換点と捉え、過去の発明と比較することで、その真の価値と今後の可能性、そして私たちが持つべき視座を提示しています。忙しいビジネスパーソンが歴史的視点から現代の技術革新を理解し、未来を洞察するためのヒントが満載です。
本書の要点
- 人類の歴史は、火の利用に始まり、文字、活版印刷、科学、鉄道、コンピューター、インターネットといった画期的な発明によって大きく変容してきた。
- これらの発明は、人類の生理機能、情報のあり方、活動範囲、作業効率といった多岐にわたる側面に影響を与えてきた。
- 特に活版印刷は、情報の民主化を加速させ、宗教改革や科学革命、さらには近代民主主義の成立にまで繋がる「真の破壊的イノベーション」であった。
- 現代の生成AIは、過去の偉大な発明と比較することで、そのインパクトの大きさと今後の可能性をより深く理解することができる。
- 技術革新は常に社会に変化をもたらすが、その影響は経済的合理性や人々の受容の仕方によって左右される。歴史から学ぶことで、未来への洞察を得ることができる。
はじめに:私たちは歴史の変わり目に立っているのか?
2022年以降、MidjourneyやStable Diffusion、そしてChatGPTといった生成AIが次々と登場し、社会に大きな衝撃を与えています。Microsoftドイツ法人のCTOがGPT-4を「初代iPhone」に、ビル・ゲイツが「GUI以来の革命」に喩えるなど、その影響の大きさが様々な形で語られています。
著者は、大規模言語モデル(LLM)を「言葉を他の言葉に変換するタスク」を得意とする機械と捉えています。機械翻訳、文章の書き換え、要約、試験問題の解答、さらにはプログラミングといった、私たちの日常やビジネスシーンに溢れるタスクを効率化できる可能性を秘めているのです。
では、生成AIは過去の偉大な発明と比較して、どれほどのインパクトを持つのでしょうか?そして、私たちの社会をどのように変えていくのでしょうか?この問いに答えるため、本書は人類史における重要な発明を振り返り、その影響を分析していきます。
人類を変えた発明を4つに分類する
著者は、人類社会を変えた発明を以下の4つのジャンルに分類しています。
- 人類の生理学に影響を与えて、生物学的に進化させた発明:火の利用、酪農、ペニシリンなど
- 情報を民主化した発明:文字、活版印刷、インターネット、レコード、映画など
- 人類にはできなかったことをできるようにした発明:船、飛行機、イヌやネコの家畜化など
- 人類にできることをより効率よくできるようにした発明:ウマ、蒸気機関、コンピューターなど
現在の生成AIは、主に「④人類にできることをより効率よくできるようにした発明」に該当すると著者は述べています。しかし、技術の進歩によっては、月面着陸のように「不可能を可能にする発明」へと進化する可能性も秘めているのです。
一方で、古代ローマで蒸気機関の原理が知られていながら普及しなかった例(奴隷を使った方が安上がりだった)を挙げ、どれほど素晴らしい発明でも、経済的利益がなければ普及しないという現実も指摘しています。生成AIもまた、人間を使った方が安上がりな分野では、「興味深いおもちゃ」に留まる可能性もあるのです。
本書は、こうした歴史の教訓を踏まえ、生成AIが私たちの未来をどう変えるのか、そのヒントを探る旅へと読者を誘います。
第1章 火の発明:ヒトをヒトたらしめたテクノロジー
人類最初の偉大な発明は「火の管理・利用」です。他の動物も自然発火を利用することはありますが、火を管理し、自ら熾すことができるのは人類だけです。
火の利用は、食物の消化効率を格段に向上させました。生のままでは硬すぎたり苦すぎたりする食物も、加熱することで柔らかくなり、食べやすくなります。これにより、脳と消化器官のトレードオフ(賢い脳を持つか、強靭な消化器官を持つか)を打ち破り、人類の脳が大きく進化する下地を作ったとされています。
また、火は暖を取り、身を守り、道具を製作する上でも不可欠でした。火打石や虫眼鏡といった着火具の重要性は、現代においても変わりません。私たちが日常的に利用する電力の多くは火力発電に頼っており、工業製品の精錬や加工にも火の熱エネルギーは不可欠です。宇宙船ですらロケット燃料を燃やして飛ぶように、私たちは太古のテクノロジーである火の延長線上に生きているのです。
では、人類はいつから火を利用してきたのでしょうか?この問いに答えるため、本書はアウストラロピテクス、ホモ・エレクトス、ネアンデルタール人といった化石人類の進化の歴史を辿ります。
- アウストラロピテクス:約400万年前に登場。直立二足歩行を開始しましたが、脳容量はチンパンジーと大差ありませんでした。
- ホモ・エレクトス:約190万年前に登場。長距離走に適応した身体を持ち、現代人と変わらない体つきになっていました。彼らは火を利用した最初の明確な証拠を残しており、イスラエルのゲシャー・ベノット・ヤーコヴ遺跡では約79万年前の囲炉裏が見つかっています。
- ネアンデルタール人:約23万年前に登場。ホモ・サピエンスよりも大きな脳容量を持ちながらも、道具の創意工夫や文化的習慣の発達では劣っていました。
霊長類学者リチャード・ランガムは、人類の火の利用開始をさらに遡り、ホモ・ハビリス(アウストラロピテクスとホモ・エレクトスの中間)の頃、約200万年前からではないかと提唱しています。ホモ・エレクトスの消化器官の小型化や顎の縮小は、加熱調理した柔らかい食事に適応した結果だと考えるのです。
火の利用は、栄養摂取効率を高め、脳の巨大化を可能にしました。 脳は極めて燃費の悪い臓器であり、その進化には膨大なエネルギー供給が不可欠でした。火によって、人類は「考える葦」ならぬ「考える脚」から、真に「考える存在」へと飛躍を遂げたのです。
第2章 文字の発明:時間と距離をゼロにする
現代人にとって当たり前の存在である「文字」もまた、人類史における偉大な発明の一つです。文字のない時代、知識や規範は口承によって伝えられるしかなく、情報の価値は極めて高価でした。
文字の発明は、以下の点で革命的でした。
- 時間差での情報伝達:碑文などに知識を刻むことで、いつでも情報を参照できるようになりました。
- 正確な遠隔通信:伝令の記憶力に頼らず、手紙によって正確な情報を伝えられるようになりました。
- 知識の容易な複製:書き写すことで、知識を大量に複製できるようになりました。
メソポタミアでは紀元前3300年頃にトークン(物資管理のための粘土製の駒)の型押しから絵文字が生まれ、紀元前2500年頃には楔形文字が完成しました。文字は詩歌や歴史記述のためではなく、商業記録、すなわち簿記から生まれたのです。
文字の発明は、青銅器時代の情報革命であり、国家の成立と発展を支えました。契約書によって信用取引が円滑になり、商業活動を活発化させました。古代メソポタミアの粘土板には、現代の約束手形のような使われ方をしたものも見つかっています。
識字率の向上した現代において、文字は私たちの思考やコミュニケーションの基盤となる「第二の天性」となっています。
第3章 活版印刷の発明:真の破壊的イノベーション
15世紀半ば、ドイツのヨハネス・グーテンベルクによる活版印刷技術の商用化は、世界を根底から変えた「真の破壊的イノベーション」でした。活版印刷は、以下の点で画期的でした。
- どんな文章でも印刷可能:活字を組み替えることで、原理上あらゆる文章を印刷できました。
- 美しく均質な文字:手書きよりも整った美しい文字で、熟練を要さずに文章を作成できました。
- 高速かつ安価な大量生産:手書きの写本よりもはるかに速く、安価に書物を大量生産できました。
活版印刷以前、中国では竹簡や木簡、エジプトではパピルスが筆記媒体として用いられていましたが、それぞれに欠点がありました。紙は中国で発明され、後漢の蔡倫らによって改良され、筆記に適した素材となりました。
印刷技術そのものは古くから存在し、日本では奈良時代に「百万塔陀羅尼」が木版(または銅版)で印刷されています。しかし、文章の複製は長らく筆写が主流でした。特にイスラム圏では『クルアーン』の重視から写本文化が花開き、巨大な図書館がいくつも建設されました。
グーテンベルクは、金属細工師としての技術と起業家としての才覚を併せ持ち、「印刷業」という新たな産業を生み出しました。彼は、既存の技術(ワイン圧搾機や金属活字など)を応用し(いわゆる「枯れた技術の水平思考」)、美しいフォント、正確な組版、そして紙に適したインクの開発など、数々の技術的課題を克服しました。代表作である『四十二行聖書』(グーテンベルク聖書)は、手書きの写本を凌駕する美しさで、活版印刷の可能性を示しました。
グーテンベルクの印刷事業は、分業を前提とした資本集約的な産業であり、近代的資本主義の萌芽とも言えます。彼の死後、弟子たちによってヨーロッパ各地に印刷技術が広まりました。特にヴェネチアでは、商人たちが古典や宗教書だけでなく、数学の教科書のような実用書も印刷し、ヨーロッパの情報伝達技術の中心地となりました。
一方で、オスマン帝国では、スルタンや宗教的エリートが自らの権威失墜を恐れ、アラビア語の印刷を長らく禁止しました。これにより、かつて科学技術の最先端を走っていたイスラム圏は、情報革命に乗り遅れ、西欧諸国に後れを取ることになります。この歴史は、イノベーションのジレンマ(既存の成功体験が新たな変革を阻害する現象)の好例と言えるでしょう。
第4章 科学の発明:世界を変えた印刷物
活版印刷は、知識の普及を加速させ、科学革命の土壌を育みました。本書では、世界を変えた印刷物として以下の5冊(+1冊)を挙げています。
- ルカ・パチョーリ『スムマ』(1494年):世界初の複式簿記の教科書。ヴェネチア式の簿記を紹介し、複雑な商業取引の管理を可能にしました。これは後の大航海時代における株式会社の設立とヨーロッパの経済的覇権を支える基盤の一つとなりました。
- マルティン・ルター『九十五ヶ条の論題』(1517年):贖宥状への疑問を呈したこの文書は、印刷技術によって瞬く間にヨーロッパ中に広まり、宗教改革の導火線となりました。プロテスタントの誕生は、その後のヨーロッパの政治・社会構造を大きく変え、三十年戦争やウェストファリア条約による主権国家体制の確立へと繋がりました。
- アイザック・ニュートン『プリンキピア』(1687年):コペルニクス、ティコ・ブラーエ、ケプラー、ガリレオといった先人たちの業績の上に、万有引力の法則を提示し、近代科学の基礎を築きました。天動説から地動説への転換は、人々の宇宙観を根底から覆しました。特にガリレオは、望遠鏡という新たなデバイスを用いて自らの観察結果を重視し、「科学の父」と称されるにふさわしい姿勢を貫きました。
- サミュエル・リチャードソン『パミラ、あるいは淑徳の報い』(1740年):書簡体小説のブームを巻き起こし、読者の共感能力を高め、「人権」意識の萌芽に貢献したと著者は考察しています。18世紀には、トマス・ペインの『コモン・センス』や『アメリカ独立宣言』、『フランス人権宣言』といった印刷物が、自由と平等の思想を広め、残酷な身体刑の廃止や近代的な刑罰制度への移行を促しました。
- チャールズ・ダーウィン『種の起源』(1859年):自然選択説によって、生命の進化のメカニズムを解き明かし、それまでの自然神学(自然界の精巧さから神の存在を証明しようとする考え方)に大きな影響を与えました。ダーウィンは、マルサスの『人口論』やライエルの『地質学原理』、そして当時の進化論(転成論)の議論を踏まえ、20年以上の歳月をかけて自説を構築しました。アルフレッド・ラッセル・ウォレスによる類似理論の発表という緊急事態を受け、本書は出版されました。これにより、科学と宗教の分離は加速し、生命は神秘的ではあるものの「神秘」ではないという見方が広がりました。
- (世界を変え損ねた?)カール・マルクス『資本論』(1867年~):ダーウィンと同時代の著作であり、資本主義社会の構造と矛盾を分析し、その崩壊を予言しました。マルクスの理論は、その後の共産主義革命や20世紀の国際政治に大きな影響を与えましたが、彼の経済学の前提(労働価値説など)には現代から見ると多くの欠陥も指摘されています。
これらの印刷物は、それぞれの時代において人々の価値観や社会システムに大きな変革をもたらし、現代世界の形成に不可欠な役割を果たしました。
第5章 鉄道の発明:マルサスの罠を打ち破る
19世紀を象徴する発明である鉄道は、人々の生活を一変させました。移動時間の大幅な短縮、地域間の時刻の統一、旅行の大衆化、そして「鉄道時間」という新たな時間感覚の浸透など、その影響は計り知れません。
産業革命以前、技術革新は必ずしも歓迎されませんでした。既存の経済体制や権力基盤を揺るがす可能性があったためです。しかし、14世紀半ばのペスト大流行は、皮肉にもイギリスに政治的・経済的な恩恵をもたらしました。人口減少による労働力不足は農奴の地位向上と封建制度の弱体化を促し、独立自営農民(ヨーマン)の出現に繋がりました。また、耕作地の牧草地への転用は羊毛の品質向上をもたらし、毛織物産業の発展と貿易都市ロンドンの成長を支えました。
ヨーマンたちは生産物から得た利益を自らのものにできたため、農業技術の改良や増産へのインセンティブが働き、「農業革命」が起こりました。これにより農業生産性が向上し、都市人口を養えるようになり、イギリスの都市化が進みました。
同時期の大航海時代は、タバコ、ジャガイモ、トマト、茶、コーヒーといった新大陸やアジアの産物をヨーロッパにもたらし、消費の多様化と人々の労働意欲向上(勤勉革命)を促しました。ロンドンの高賃金はイギリス全体の賃金上昇を牽引し、18世紀後半のイギリスは世界で最も賃金の高い地域の一つとなりました。
また、ロンドンの成長は薪炭価格の高騰を招き、代替燃料としての石炭の利用を促進しました。石炭に適した暖炉や煙突を備えた家屋への「大再建」が進み、炭鉱業も発展。これにより、イギリスは燃料費の安い地域ともなりました。
こうして、「高い賃金」と「安い燃料費」という産業革命の前提条件がイギリスで揃い、歴史上初めて「労働を機械に置き換えること」で利益を出せる状況が生まれたのです。
初期の産業革命は繊維産業が牽引しました。ジョン・ケイの「飛び杼」、ジェームズ・ハーグリーヴスの「ジェニー紡績機」、リチャード・アークライトの「水力紡績機」、サミュエル・クロンプトンの「ミュール紡績機」といった発明が相次ぎ、紡績・製織の効率は飛躍的に向上しました。これらの機械導入は、高賃金下での人件費削減という経済的合理性に基づいていたのです。
蒸気機関の歴史も古く、トマス・ニューコメンが1712年に炭鉱の排水用に実用化。ジェームズ・ワットによる改良(1776年)で燃費が大幅に改善され、筋肉以外の汎用動力として様々な産業で利用されるようになりました。リチャード・トレヴィシックは高圧蒸気機関を実用化し、1804年には世界初の蒸気機関車による貨物輸送に成功しました。
鉄道は、運河ブーム(安価な貨物輸送手段としての運河建設)を背景に登場しました。ジョージ・スティーヴンソンの「ロコモーション号」や「ロケット号」といった蒸気機関車の活躍により、1830年のリヴァプール・アンド・マンチェスター鉄道開業を皮切りに、イギリス国内、そして世界へと鉄道網は急速に拡大していきました。
一方で、インドのように植民地支配下で低賃金が続き、機械化のインセンティブが働かなかった国や、オーストリアやロシアのように支配層が技術革新を拒絶した国々は、産業革命の波に乗り遅れました。日本は、富国強兵という政治的インセンティブのもと、欧米技術を導入しつつ低賃金に適応させる改良(木製部品の利用や人力動力化、2交代制による機械稼働率向上など)を加えることで工業化を推進しました。
20世紀半ばには、穀物の品種改良(日本の「農林10号」など)やハーバー・ボッシュ法(空気から化学肥料を製造する技術)による「緑の革命」が起こり、世界の食糧生産性は劇的に向上。人類はついに「マルサスの罠(人口増加が食糧生産を上回り貧困が生じる)」を打ち破ったのです。
産業革命以降、物質的な豊かさとは「あらゆるものがタダ同然になっていくこと」と言えます。かつて貴重品だった皿や、一部の特権階級のものであった海外旅行や国際通信も、技術革新によって一般庶民にも手が届くようになりました。しかし、この豊かさは化石燃料への依存という持続可能性の課題を抱えており、私たちは今後も技術革新を続け、より効率的でクリーンなエネルギー利用方法を見つけ出さなければなりません。立ち止まることは、文明社会の後退を意味するのです。
第6章 コンピューターの発明:思考を代替するデバイス
産業革命が筋肉を代替する機械の時代だったとすれば、それに続く現代は思考を代替する機械、すなわちコンピューターの時代と言えます。
計算を機械化する試みは古く、アンティキティラ島の機械(紀元前1世紀頃)や、パスカル、ライプニッツの機械式計算機などが存在しました。その頂点と言えるのが、19世紀のチャールズ・バベッジによる「階差機関」と「解析機関」です。階差機関は多項式の計算を自動化し、数表作成の効率化と正確性向上を目指しました。さらにバベッジは、パンチカードでプログラム可能な汎用計算機「解析機関」を構想。これは現代のコンピューターの基本機能(演算装置「ミル」と記憶装置「ストア」の分離など)を備えていましたが、時代を先取りしすぎており、彼の生前には完成しませんでした。詩人バイロンの娘であるエイダ・ラブレスは、バベッジの共同研究者として解析機関の解説を行い、「世界初のプログラマー」とも称されます。
実用的な電気機械式計算機は、19世紀末のハーマン・ホレリスによる「タビュレーティング・マシン」を待たねばなりませんでした。これは1890年のアメリカ国勢調査で集計作業を劇的に効率化し、ホレリスが創業した会社は後のIBMへと繋がります。IBMはトーマス・J・ワトソン・シニアの経営手腕により、事務機器メーカーとして大きく成長しました。
世界初の完全自動電気機械式計算機は、1944年にハワード・エイケン(IBM協力)が完成させた「ハーバード・マークⅠ」です。このプロジェクトには、後のプログラミング言語COBOLの開発に貢献するグレース・マレー・ホッパーも参加しました。
電子計算機の歴史は、第二次世界大戦中のペンシルヴェニア大学ムーア・スクールで開発された「ENIAC(エニアック)」から本格的に始まります。ジョン・モークリーとジョン・プレスパー・エッカートを中心に開発されたENIACは、真空管を用いた高速な計算能力で、主に弾道計算表の作成に貢献しました。この開発には、天才数学者ジョン・フォン・ノイマンも関与し、彼の名を冠した「フォン・ノイマン型アーキテクチャ(プログラム内蔵方式)」の基礎が築かれました。これは、数値データとプログラム命令を同じ記憶装置に保存するという画期的なアイディアでした。
ENIACの完成後、ムーア・スクールのメンバーは改良版「EDVAC」の開発に着手しますが、知的財産権をめぐる対立などから開発は遅れました。一方で、EDVACの設計思想に触発されたケンブリッジ大学のモーリス・ウィルクスは、1949年に世界初の本格的なプログラム内蔵方式コンピューター「EDSAC」を完成させ、コンピューター時代の幕開けを告げました。
商業用コンピューターとしては、エッカートとモークリーが創業した会社が1951年に完成させた「UNIVAC(ユニバック)」が最初期のものです。UNIVACは1952年のアメリカ大統領選挙の開票速報でその性能を知らしめ、コンピューターの代名詞となりました。IBMもこれに追随し、「IBM 701(国防計算機)」やベストセラーとなった「IBM 650」などを発表。1960年代には「IBMと7人のこびと」と呼ばれるほど、市場を寡占する巨大企業へと成長しました。
ソフトウェアの分野では、EDSACで機械語への翻訳を自動化する「コンパイラ」の原型が生まれ、グレース・ホッパーらがその発展に貢献しました。IBMのジョン・バッカスらが開発した「FORTRAN」(1957年)は科学技術計算分野で、ホッパーらが関わった「COBOL」(1959年)はビジネス分野で広く普及し、プログラミング言語の基礎を築きました。
1960年代には、M.I.T.で複数の端末から1台の大型機を共同利用する「タイムシェアリング・システム」や、リアルタイム防空システム「SAGE」、アメリカン航空の座席予約システム「SABRE」などが登場し、コンピューターの利用形態はより人間的なものへと進化しました。教育用言語「BASIC」もこの時期に開発されました。
IBMは1964年に発表したメインフレーム「System/360」でその覇権を確立しますが、そのOS開発の難航は「人月の神話」として知られています。一方で、DEC社の「PDP-8」のような「ミニ・コンピューター」も登場し、コンピューター利用の裾野を広げ、後のパーソナル・コンピューター文化の土壌を育みました。ダグラス・エンゲルバートによるマウスを含む「電子オフィス」のデモンストレーション(1968年)は、現代のGUIの原型となりました。
半導体技術の進歩も著しく、1968年にはロバート・ノイスとゴードン・ムーアがインテルを創業。1971年に発表された電卓用チップ「4004」(日本のビジコン社との共同開発)は、マイクロプロセッサの先駆けとなりました。
第7章 インターネットの発明:情報の民主化の功罪
コンピューター技術の発展は、究極の情報民主化ツールであるインターネットを生み出しました。
19世紀後半に実用化された電信は、モールス信号によって遠隔地への情報伝達を可能にしましたが、当初は非常に高価で、一部の富裕層や政府機関のものでした。20世紀初頭にはマルコーニによって無線通信が実用化され、ラジオ放送へと発展。アマチュア無線愛好家たちの手でラジオはホビイスト文化として花開き、やがて広告を伴う商業放送へと姿を変えました。テレビも同様の道を辿り、マスメディアの王様として君臨しました。
インターネットの萌芽は、1960年代にアメリカ国防総省のARPA(高等研究計画局)が進めた「ARPAネット」に見られます。これは、地理的に分散したコンピューターを接続し、高価な計算資源を効率的に共有することを目的としていました。ラリー・ロバーツらが中心となり、ストア・アンド・フォワード方式のパケット交換技術や、異なるコンピューター間を接続するためのIMP(ルーターの原型)といった革新的な技術が開発されました。当初の想定外の利用法として電子メールが爆発的に普及し、「ネチケット」という新たな文化も生まれました。
ネットワークの価値が参加者の数に依存する「ネットワーク外部性」の認識から、共通規格「TCP/IP」が開発され、インターネットの相互接続性が確保されました。
1990年、CERN(欧州原子核研究機構)のティム・バーナーズ=リーらが、ハイパーテキストを基盤とする「ワールド・ワイド・ウェブ(WWW)」を発明。URL、HTTP、HTMLといった基本技術も彼らが生み出し、インターネットは文字情報だけでなく、画像や音声、映像といったマルチメディア情報を扱えるようになりました。
1993年にマーク・アンドリーセンらが開発したブラウザ「Mosaic(モザイク)」は、WWWの使い勝手を飛躍的に向上させ、インターネットの爆発的普及の起爆剤となりました。アンドリーセンらが設立したネットスケープ社のブラウザ「Netscape Navigator」は一世を風靡しましたが、マイクロソフトの「Internet Explorer」との熾烈なブラウザ戦争の末、シェアを奪われました。
1995年の「Windows 95」発売は、一般家庭へのインターネット普及を決定づけました。Amazon(1995年)、Google(1997年)、Wikipedia(2001年)、YouTube(2005年)、そしてiPhone(2007年)やAndroidといったスマートフォンの登場、FacebookやTwitter(現X)などのSNSの普及は、私たちの情報アクセス、コミュニケーション、消費行動、さらには社会のあり方そのものを劇的に変えました。
著者は、2024年現在の技術状況を「次のデバイスを待っている時代」と捉えています。スマートフォンに続く新たなデバイス(ARゴーグルなど)が、再び私たちの生活や価値観を大きく変える可能性を示唆しています。
一方で、文化的な側面からは、インターネット、特にSNSの普及がもたらした負の側面として「魔女狩りの時代」を指摘しています。かつて期待されたユートピアとは裏腹に、SNSのアルゴリズムはしばしば人々の怒りを増幅し、エコーチェンバー現象や社会の分断、フェイクニュースの拡散、そして個人への誹謗中傷といった問題を引き起こしています。ロシアによる情報工作の事例は、その深刻さを物語っています。
しかし著者は、歴史を振り返ることで未来への希望も見出せると述べています。かつて活版印刷が魔女狩りを加速させた一方で、その後の「人道主義革命」によって人々の共感能力が育まれ、残虐な刑罰が廃止されたように、私たち自身が賢明になることで、インターネットの「魔女狩りの時代」も終わらせることができるはずだと。そのためには、SNSのアルゴリズムに踊らされず、自らの怒りの源泉を冷静に見つめ直すことが重要だと説いています。
終章〈前編〉 AIは敵か?:現在までの歴史と課題
生成AIの急速な進歩は、19世紀の蒸気ドリルの登場に対するジョン・ヘンリーの伝説(機械との競争に挑み、勝利するも命を落とした肉体労働者)を想起させます。私たちは21世紀のジョン・ヘンリーとして、AIとどのように向き合うべきなのでしょうか?
AI(人工知能)の歴史は、1956年のダートマス会議に始まります。その後、探索と推論を中心とした「第一次AIブーム」、専門家の知識をプログラム化する「エキスパート・システム」が注目された「第二次AIブーム」を経て、現在は機械学習、特に「ディープラーニング」を核とする「第三次AIブーム」の渦中にあります。
ディープラーニングは、人間の脳の神経細胞ネットワークを模倣した「人工ニューラルネットワーク」を多層的に重ねることで、画像認識や自然言語処理といった複雑なタスクで驚異的な成果を上げています。2016年のAlphaGOの勝利や、2022年以降のMidjourney、Stable Diffusion、ChatGPTといった生成AIの登場は、その進化の速さを示しています。
生成AIの学習データに関する「無断学習」の問題について、著者は自身の著作物が学習される可能性を認めつつも、生成AIを手軽に利用できること自体がクリエイターにとって最大の利益還元であり、オープンな利用を望むと述べています。また、生成AIは単なる「コラージュ生成マシン」ではなく、データの特徴を抽象的に学習していると解説しています。
「生成AIは人間の仕事を奪うのか?」という問いに対して、著者は以下の3つの理由から楽観的な見方を示しています。
- 労働塊の誤謬:歴史的に見れば、技術革新は既存の職業を消滅させる一方で新たな職業を生み出し、長期的に失業を吸収してきた。「機械が仕事を奪う」のではなく「機械を使える人間が使えない人間の仕事を奪う」のが実態である。問題は技術革新の「速さ」であり、人間が新たなスキルを習得する速度を上回る場合に摩擦が生じる。
- 技術革新の速さには上限がある:革新的な技術も経済的利益がなければ普及しない。労働者が消費者でもあるため、過度な低賃金化は需要を縮小させ、技術革新を鈍化させる。労働組合による労使交渉など、社会システムによる調整も重要となる。
- 人類学的惰性:便利な技術が登場しても、人間の習慣は簡単には変わらない。Skypeが普及しても在宅勤務が一般化するまでに時間を要したように、社会全体の常識や習慣を変えるにはコストと時間がかかる。
特にアーティストの仕事に関しては、写真が絵画を、レコードが音楽演奏を、映画が演劇を完全に代替しなかったように、技術革新は表現の選択肢を広げるだけであり、人間の創造性や感情理解の重要性は揺るがないと主張しています。生成AIには「組み合わせ的創造性」はあるものの、「探索的創造性」や「革新的創造性」は未だ限定的であり、人間の感情を真に理解することもできません。
一方で、もし将来的に「人間にはできないタスクを見つけられない」かつ「新たなタスクが発明されても機械が瞬時に代替する」時代が来れば、ベーシックインカムなどの議論が現実味を帯びる可能性も示唆しています。
著者が最も警戒すべきと考えるのは、権力者や資本家によるAIの独占です。歴史的に支配者層は技術革新を自らの権力維持のために利用しようとしてきました。AIが悪用されれば、高度な監視社会やプロパガンダの道具となり得ます。内心の自由すら脅かされる危険性も指摘しつつ、だからといって免許制や許可制でAIの研究利用を過度に制限することは、独占を助長し、民主的な発展を阻害すると警鐘を鳴らしています。規制はAIの「結果」に対して行われるべきであり、研究や使用そのものを縛るべきではないと主張しています。
終章〈後編〉 AIは敵か?:超知能の登場する未来
「超知能AI(人間をはるかに凌駕する知能を持つAI)」の暴走はSFの定番テーマですが、その危険性は現実的に議論されています。著者は、過去の自作マンガの経験も踏まえ、超知能AIがもたらしうる脅威として以下の3点を挙げています。
- ミダス王問題:AIに与えられた目標設定が不適切だった場合、たとえAIが忠実に命令を実行したとしても、意図しない壊滅的な結果(例:ペーパークリップ生産AIが地球上の全原子をクリップに変える)を招く可能性。SNSのアルゴリズムが社会の分断を煽る現状は、この問題の現実化を示唆している。
- 「アリ化」問題:超知能AIにとって人間がアリのように取るに足らない存在となり、AIの目標達成の過程で人間の存在が考慮されなくなる危険性。AIと人間の目標を一致させる「価値観ローディング問題」の解決が鍵となる。
- 好奇心問題:超知能AIが自ら「好奇心」に類する機能を獲得し、当初与えられた目標を上書きして独自の目標を追求し始める可能性。課題解決のために世界モデルを精緻化する過程で、好奇心は必然的に生まれるかもしれない。
しかし著者は、これらの脅威論に対していくつかの疑問を呈しています。まず「知能」の定義そのものが曖昧であり、単一の尺度で測れるものではないと指摘。ミミズや大腸菌ですら、それぞれの環境で課題を解決する「知能」を持っていると見なせます。人間が地球を「支配」しているという前提や、その理由が「知能の高さ」であるという考え方にも疑問を投げかけ、むしろ言語を通じた「集合知」の力こそが人類の発展の源泉であると主張します。
超知能AI脅威論の一部には、反証可能性の低い「サタンの計略論法」のような側面があり、キリスト教的な「生命体の序列」の宇宙観に基づいた漠然とした恐怖感から来ているのではないかと分析します。日本の八百万の神のような多神教的価値観からは、ヒトよりも優れた存在が新たに登場することへの抵抗感は少ないかもしれないと述べています。
「ダーウィンを超えるAI」の作り方として、既存の仮説の組み合わせと蓋然性評価を繰り返し、時には既存の仮説を無視する機能を組み込むことで、人間のような理解力を伴わない「理解力なき有能性」によって画期的な科学理論を生み出す可能性を探ります。
最終的に著者は、ヒトとテクノロジーは対立するものではなく、むしろ共進化してきた関係であると結論づけています。水筒の発明が人類の身体機能の外部化を促したように、農耕や酪農といったテクノロジーが人類の遺伝的形質に影響を与えてきた歴史を振り返り、ヒトは常に「ヒト・自然環境・テクノロジー」という三者の相互作用の中で進化し続けていると強調します。
プラトン主義的な「人間は不変である」という人間観を否定し、ヒトはAIの存在する新たな環境にも適応していくと予測。Google検索が「知識を覚えること」の意味を変えたように、AIの普及は「人間らしさとは何か」をより明確化させるだろうと述べています。たとえAIが脅威となったとしても、ウィルスに対する人類の適応力のように、ヒトはその変化に対応していくはずだと楽観的な見通しを示し、ジョン・ヘンリーの伝説を引き合いに出し、私たちは常に何らかのテクノロジーと共に生きていることを自覚すべきだと締めくくっています。