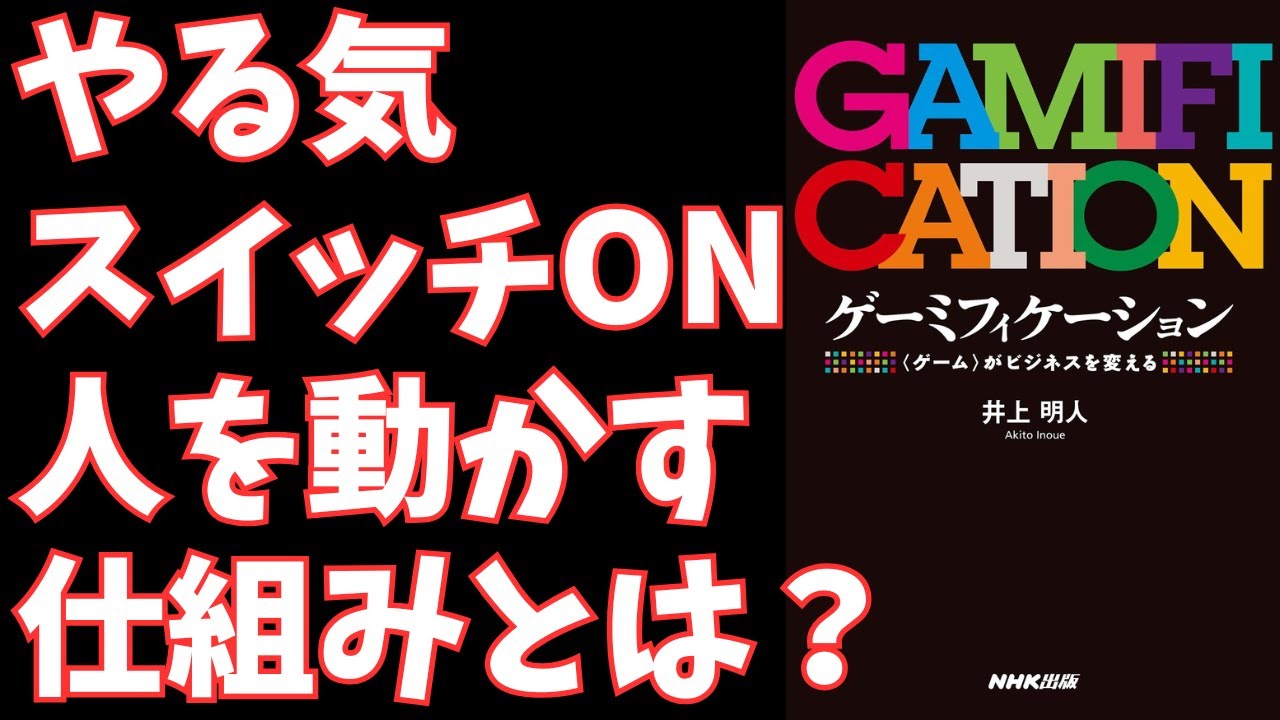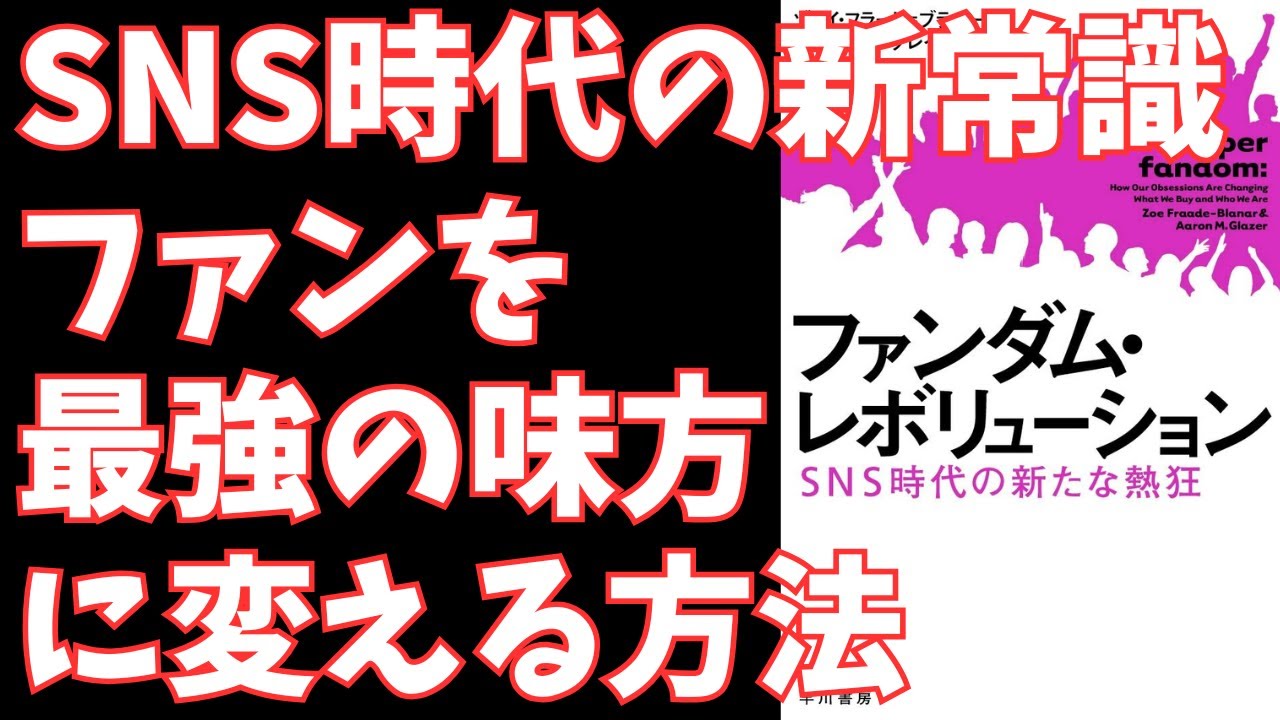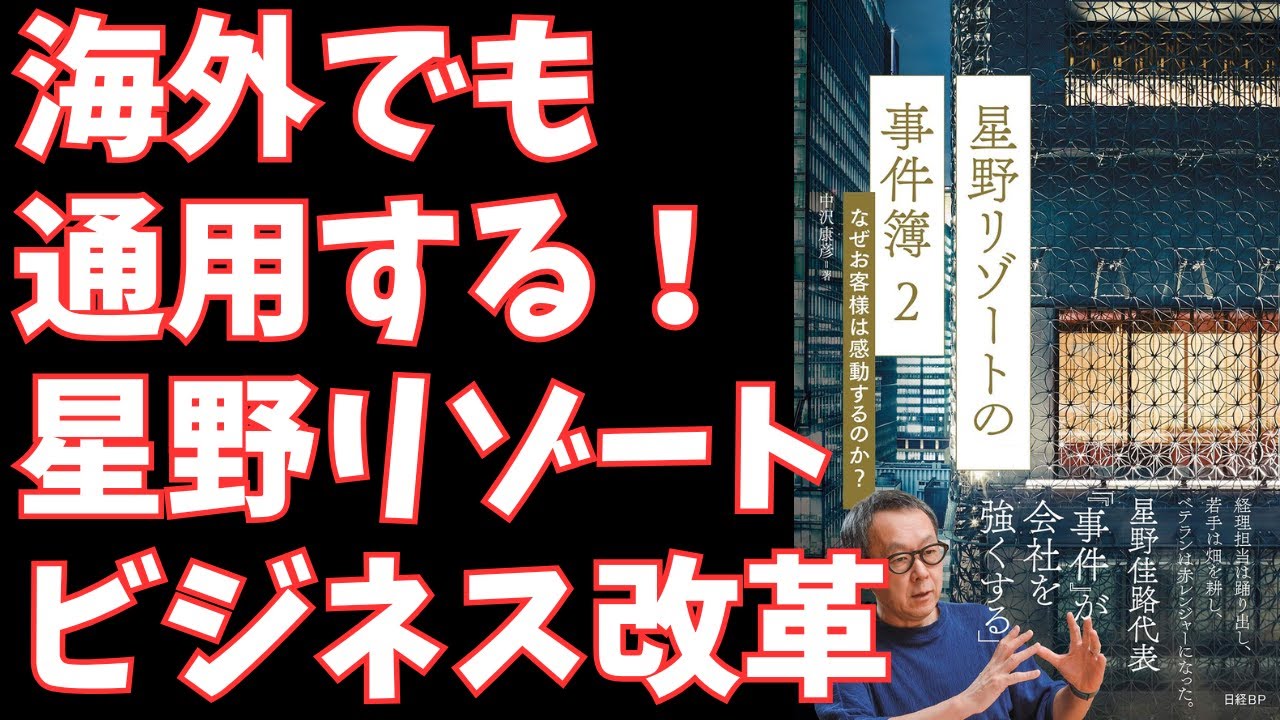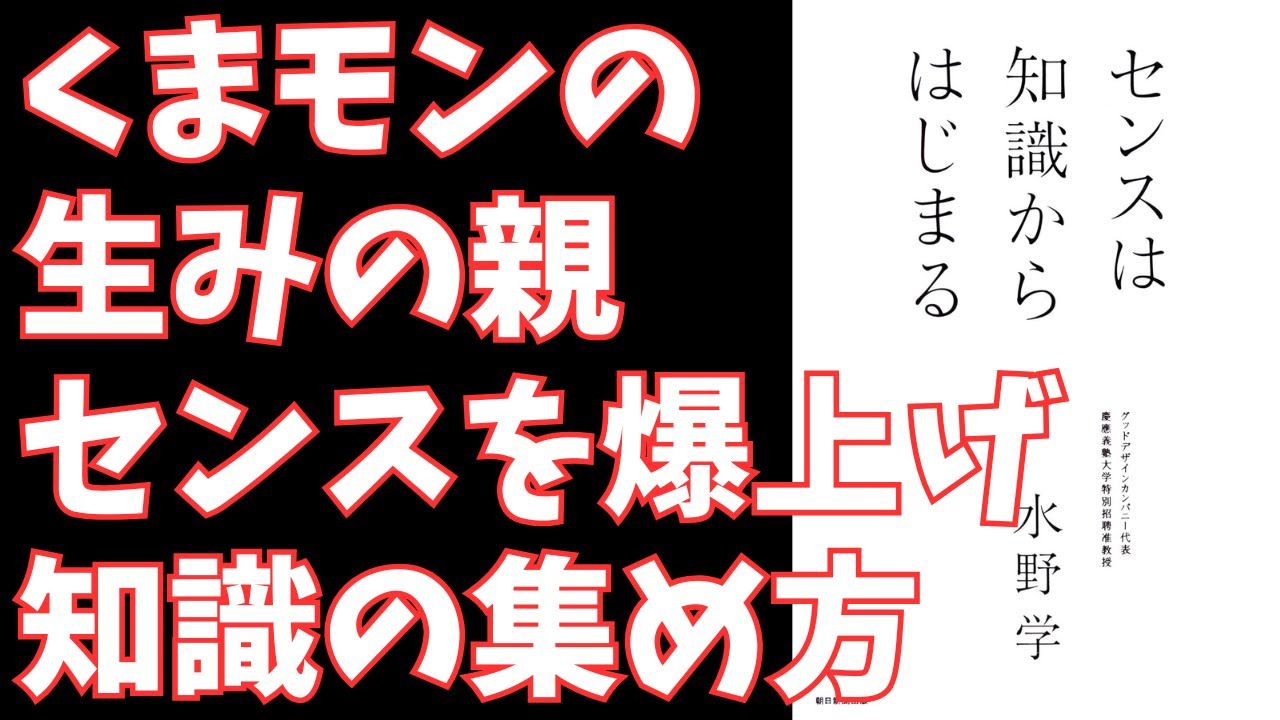苫米地英人『思考停止という病』|あなたの脳を覚醒させる「自分の頭で考える技術」
本書『思考停止という病』は、現代社会、特に日本のビジネスシーンに蔓延する「思考停止」という問題に鋭く切り込み、その原因と具体的な克服法を提示する一冊です。著者は、認知科学者である苫米地英人氏。
多くのビジネスパーソンが「自分の頭で考えろ」と言われながらも、なぜ思考停止に陥ってしまうのか。その根本原因を「前例主義」「知識不足」「ゴールがない」という3つの観点から解き明かします。
そして、思考を再起動させるための鍵として、現状の外側にある強烈な「ゴール設定」、思考の土台となる「圧倒的な知識の獲得法」、さらには最強の論理ツール「トゥールミンロジック」や、脳のパフォーマンスを最大化する「並列思考」といった具体的な技術を、脳科学と認知科学の知見を基に徹底的に解説しています。
この記事では、本書のエッセンスを抽出し、忙しいビジネスパーソンが日々の業務や人生において「自分の頭で考え抜き、最高の成果を出す」ための実践的な方法論を詳しくご紹介します。
本書の要点
- 思考停止の正体は「創造的な問題解決活動」の放棄であり、その根本原因は日本の社会構造に根差した「前例主義」、物事を認識するための「圧倒的な知識不足」、そして思考の原動力となる「ゴールがない」ことにある。
- 自分の頭で考える力を起動させる最も重要な鍵は「ゴール設定」。現状の自分では達成不可能なほど強烈なゴールを持つことで、脳のフィルタリング機能(RAS)が働き、スコトーマ(心理的盲点)が外れ、世界の見え方が一変する。
- 思考の質とスピードは「知識の量」に比例する。先入観を排し、著者になりきり、関連性を意識しながら複数の本を同時に読む「苫米地式読書術」は、思考の土台となる知識を爆発的に増やすための強力な武器となる。
- 客観的で強固な思考を構築するために、情動を切り離し、「データ」「ワラント(論拠)」「クレーム(主張)」で構成される「トゥールミンロジック」を習得することが不可欠である。
- 真の創造性は、思考の抽象度を上げる「ヒルクライミング」によって生まれる。脳の並列処理能力を鍛え、最高のコンディションを維持することで、目の前の課題解決だけでなく、本質的なイノベーションを生み出す「考え続ける脳」を手に入れることができる。
なぜ、優秀な若手も3年で「ただの人」になるのか?
「十で神童、十五で才子、二十歳過ぎればただの人」ということわざがありますが、著者はこれを現代のビジネスシーンに当てはめ、「入社して3年たてばただの人」と指摘します。
学生時代は優秀で、高いポテンシャルを秘めていたはずの若者が、なぜ数年で輝きを失い、指示待ちの「ただの人」になってしまうのでしょうか。
その原因は、日本の多くの企業文化にあります。
入社当初は、会社のやり方を覚えることが最優先され、先輩や上司の指示に従うことが求められます。言葉では「自分で考えろ」と言われながらも、独自の判断で行動すれば「勝手なことをするな」と叱責される。報告・連絡・相談を徹底され、失敗は許されない。
こうした環境に3年も身を置けば、かつて抱いていた「何か新しいことをやってやろう」「業界を変えてやろう」という気概は消え失せ、いつしか「言われたことしかやらない」「面倒なことは避ける」という思考停止状態に陥ってしまうのです。
これは、思考の生命線である「自分で考える訓練」を全くしなくなった結果に他なりません。
かつての高度経済成長期であれば、思考停止していても会社の成長と共に給料は上がり、安泰な人生を送れたかもしれません。しかし、大企業でさえ経営危機に陥る現代において、その常識はもはや通用しません。
会社や業界という「群れ」の中に安住し、思考停止を続けることは、個人の進化を放棄し、変化の激しい時代を生き抜く力を自ら手放しているのと同じなのです。
「思考停止」の正体とは?あなたの脳で起きていること
そもそも、本書でいう「思考停止」とは何でしょうか。
著者は、思考には2つのレベルがあると言います。
- 物理的な脳の活動
- 創造的な問題解決活動
1つ目の「物理的な脳の活動」は、私たちが生きている限り停止することはありません。たとえぼーっとしていても、脳は常に情報を処理し、エネルギーを消費し続けています。
著者が警鐘を鳴らす「思考停止」とは、2つ目の「創造的な問題解決活動」を放棄している状態を指します。具体的には、「分析する」「意思決定する」「問題を解決する」「仮説をつくる」といった、クリエイティブな思考活動を放棄して生きている状態です。
思考とは「進化」そのものである
著者は、数学者グレゴリー・チャイティンが提唱した「メタ・バイオロジー(超生物学)」の概念を引用し、思考を生命現象の一部として捉えます。
チャイティンによれば、生命の進化とは、ある情報空間の中で、予測不能な突然変異(ランダムウォーク)を繰り返しながら、より高い次元へと登っていく(ヒルクライミング)プロセスです。
思考もこれと全く同じで、脳という情報空間の中で、様々な知識や記憶をランダムに結びつけながら、抽象度をダイナミックに変化させていく運動行為なのです。
つまり、思考停止に陥るということは、自らの「進化」を止めてしまうことに等しいのです。
多くのビジネスパーソンは、まるでイワシの群れのように、周りに合わせて同じように行動することで安心感を得る「スクールオブフィッシュ」の状態にあります。群れの中にいれば安全かもしれませんが、そこに個人の進化、つまり創造的な思考は存在しません。
群れから抜け出し、「陸を目指そう」と決意した魚のように、現状の外側へと踏み出す意思こそが、思考停止から脱却し、進化を始める第一歩なのです。
なぜ私たちは「自分の頭で考える」ことができないのか?3つの根本原因
では、なぜ多くの日本人は創造的な思考活動を停止させてしまうのでしょうか。著者は、その根本原因を3つ挙げています。
原因1:根深い「前例主義」と暗記教育の弊害
日本社会に深く根付いているのが「前例主義」です。「昔からこのやり方でやってきたから」という理由だけで、現状のやり方を疑うことすらしません。
特に出版業界のような斜陽産業では、業界全体が思考停止に陥り、有効な手を打てずに衰退していく様子がその典型例として挙げられています。
この前例主義の根底にあるのが、小学校から叩き込まれる「前へならえ」の精神です。集団の和を乱さず、目上の人に従うことが正しいとされ、自分の頭で判断する機会を奪われてきました。
さらに、日本の学校教育が「知識の暗記」に偏重していることも大きな問題です。教科書や先生の言うことを疑わずに記憶することだけが評価され、「君はどう考えるのか?」という問いが投げかけられることはほとんどありません。これでは、思考する力ではなく、ただ覚えるだけの能力しか育たないのです。
原因2:世界を歪める「圧倒的な知識不足」
思考停止のもう一つの大きな原因は、「絶対的な知識量の不足」です。
著者は、「脳は知っているものしか認識できない」と断言します。
私たちの脳にはRAS(網様体賦活系)というフィルタリング機能があり、自分にとって「重要だ」と認識された情報だけを取り入れ、それ以外は意識に上らせません。この「見えているのに認識できていない」状態が、スコトーマ(心理的盲点)です。
知識がなければ、そもそも何が重要かすら判断できません。経済や政治のニュースが流れてきても、関連知識がなければ右から左へ受け流すだけ。つまり、知識がない人は、スコトーマだらけの世界で生きているのと同じなのです。これでは、物事の本質を見抜いたり、問題を正しく分析したりすることは到底不可能です。
原因3:思考のエンジン「ゴール」がない
そして、思考停止における最大かつ最も重要な原因が、「ゴールがない」ことです。
思考とは、現状の外側にあるゴールに向かって進むためのエネルギーです。あなたが本気で成し遂げたいと願う「ゴール」を設定して初めて、脳は「現状ではダメだ」と認識し、ゴール達成に必要な情報が「重要」なものとして認識されるようになります。
つまり、ゴールがスコトーマをずらし、思考を駆動させるエンジンとなるのです。
しかし、多くのビジネスパーソンが持つ「今の会社で出世したい」「社長になりたい」といった目標は、著者に言わせれば本当のゴールではありません。それは「現状の延長線上」にある目標であり、むしろ「このままでいい」と現状を肯定する力として働いてしまいます。
思考をしていない人とは、すなわちゴールがない人なのです。問題意識を持たず、現状を疑わないため、思考が始まるきっかけすらないのです。
思考を起動させる鍵「ゴール設定」の技術
思考停止から脱却し、自分の頭で考え始めるための第一歩は、常識を疑い、現状から抜け出すことです。そのための最も強力な方法が「ゴール設定」です。
「ノーマル(普通)」を憎み、「ノットノーマル(普通じゃない)」になれ
まず、あなたが「常識」「普通」「当たり前」だと思っていることを徹底的に疑うことから始めましょう。
著者は「ノーマルというのは最悪なワードだ」と言います。
「普通」の人生は、他人や社会によって植え付けられた、快適で居心地のいい空間(コンフォートゾーン)に過ぎません。その中にいる限り、あなたは他人の価値観で生きる「奴隷」のままです。
他人にどう思われるかを気にするのをやめ、自分が本当にやりたいこと、興味があることに本気で取り組みましょう。「普通じゃない」と言われることを、むしろ褒め言葉だと捉えるのです。歴史上の偉人や成功者は、誰もが「ノットノーマル」な存在だったはずです。
ゴールは「現状の外側」に設定する
思考を動かすゴールには、厳密なルールがあります。それは、「現状の自分のままでは絶対に達成できないゴール」であることです。
魚がより速く泳ぐことを目指すのは「最適化」であり、退化に繋がります。海から陸に上がるという、死ぬかもしれないほどの無謀な挑戦こそが「進化」です。
あなたのゴールも、この「進化」に値するものでなければなりません。
「どうすれば達成できるかわからない。けど、絶対に達成したい」
そう心から思える、強烈なゴールを設定してください。
そのゴールは、個人的な欲望(お金持ちになりたい、モテたい等)よりも、「社会貢献」や「多くの人を幸せにする」といった、より抽象度の高いものであることが望ましいとされています。
この強烈なゴールを設定した瞬間、あなたのコンフォートゾーンはゴールの世界へと移行します。すると、今の自分や環境が居心地悪く感じられ、脳は無意識的にゴールを達成するための方法を探し始めます。これが、スコトーマが外れ、思考が爆発的に動き出すメカニズムなのです。
思考の解像度を上げる「圧倒的知識」の習得法
強烈なゴールを設定したら、次に取り組むべきは、思考の原材料となる「知識」を圧倒的な量、手に入れることです。
ビジネスにおける意思決定の多くは、クリエイティビティというよりも「過去の最適化」です。答えが出なかったり、迷ったりするのは、単に判断材料となる知識が不足しているだけなのです。
その知識を最も効率的に、かつ体系的に得るためのツールが「読書」です。著者は、知識を血肉に変えるための独自の読書術をいくつか紹介しています。
苫米地式・知識が爆発的に増える4つの読書術
- 文面通り読む
まずは先入観や好き嫌いを捨て、著者が書いていることをフラットに理解することに努めます。自分の考えと違うからと拒絶するのではなく、まずは知らない知識を受け入れる姿勢が重要です。 - 著者になりきって読む
自分の自我を一時的に消し、その本の著者になったつもりで読み進める方法です。著者の経歴などを読み、人物像をイメージし、その人になりきって読むことで、「著者にとっての重要なこと」が素直に頭に入ってきます。自分では重要だと思わなかった知識の価値に気づくことができます。 - 意図、問い、関連性を持って読む
「なぜ著者は今これを書いたのか?」「その裏にある意図は何か?」「この知識は他の何と関連しているのか?」といった問いを持ちながら読むことで、単なる情報のインプットではなく、知識と知識が結びついた新しい全体像(ゲシュタルト)が生まれます。これこそが「自分の頭で考える」プロセスです。 - 並列読書
一つのテーマについて、関連する本を複数冊同時に、パラパラとめくりながら読んでいく方法です。脳は一つのことを順番に処理する(シリアル処理)よりも、複数のことを同時に処理する(パラレル処理)方が得意です。この読書法により、情報の関連性を見つけやすくなり、ゲシュタルト構築が一気に進みます。
また、読む本を選ぶ際には、自分の興味のある分野に偏らず、書店のランキング上位の本をジャンル問わず買ってみるなど、意図的に「ランダム性」を取り入れることで、スコトーマが外れ、知識の幅が格段に広がります。
「なんとなく」を卒業する!最強の論理力「トゥールミンロジック」
ゴールと知識が揃っても、それを正しく運用する「論理力」がなければ、思考はあらぬ方向へ進んでしまいます。
著者は、多くの人が無意識に使っている「AならばB、BならばC、よってAならばC」という三段論法は、絶対的な真理(アプリオリ)が存在しない現代では役に立たない古い論理だと指摘します。
それに代わる現代最強の論理ツールが「トゥールミンロジック」です。これは、以下の3つの要素で思考を構築する技術です。
- クレーム(Claim):あなたが主張したいこと、結論。
- データ(Data):クレームを裏付ける客観的な事実、証拠。
- ワラント(Warrant):データがなぜクレームの根拠になるのかを説明する「論拠」。
例えば、「今日は傘を持って行くべきだ(クレーム)」と主張する場合、「降水確率は90%だ(データ)」という事実だけでは不十分です。「降水確率が90%の時は、過去の経験上ほぼ確実に雨が降るから(ワラント)」という論拠があって初めて、論理として成立します。
多くの議論が噛み合わないのは、この「ワラント」が共有されていない、あるいは弱いからです。常にこの3点セットで物事を考えるクセをつけることで、あなたの思考や主張は飛躍的に強固で客観的なものになります。
ブログを書いたり、日々の出来事を説明したりする際に、このトゥールミンロジックを意識して文章化する訓練(トゥールミンライティング)は非常に有効です。
天才の思考法「ヒルクライミング脳」を手に入れる
自分の頭で考え続ける最終的な目標は、思考の抽象度を上げ、本質的な問題解決やイノベーションを生み出す「ヒルクライミングする脳」を手に入れることです。
抽象度を上げ、並列思考を使いこなす
抽象度が高い人とは、物事を俯瞰的・大局的に見られる人です。一方、抽象度が低い人は、目の前の自分のことしか見えません。
一流のサッカー選手が、ボールを扱いながらフィールド全体の選手の動きを把握し、数秒後の未来を予測してパスを出すように、私たちの脳は本来、複数のことを同時にこなす「並列思考(パラレル処理)」を得意としています。
この能力をビジネスで活かすには、まず自分が関わる仕事の全体像を一気に把握することが重要です。新人の頃から、部署の仕事だけでなく、会社のビジネスモデル、財務、業界を取り巻く法律まで、全体を俯瞰する視点を持つことで、思考の抽象度は一気に上がります。
脳のパフォーマンスを100%引き出す
ヒルクライミングする脳を維持するためには、脳のコンディションを最高に保つことも不可欠です。
- 最高の睡眠:記憶は睡眠中に整理され、長期記憶として定着します。特にゴール設定によって「重要だ」と認識された情報ほど定着しやすくなります。質と量の両面で十分な睡眠を確保しましょう。
- リラックス:脳が最高のパフォーマンスを発揮するのは、緊張状態ではなくリラックス状態にある時です。五郎丸選手のルーティンのように、自分なりの方法で意図的にリラックス状態(脳波でいうローアルファ波状態)をつくり出すことが重要です。
常に問題意識や仮説を持ちながら生活することで、脳は無意識の領域でも思考を続ける「バックグラウンドプロセッシング」を始めます。お風呂の中や散歩中にふとアイデアが閃くのは、この機能が働いている証拠です。
まとめ:最高の人生を手に入れる「考える力」
本書は、思考停止から脱却するための技術論に留まりません。最終章では、その先にある「最高の人生」について言及しています。
多くの人は、仕事での成功や出世に自己実現を求め、人生のすべてを捧げてしまいます。しかし著者は、ビジネスに自己実現を求めてはいけないと断じます。なぜなら、サラリーマン社会での出世は実力よりも「ごますり」の要素が大きく、人生の価値をそこに委ねるのはあまりにも危険だからです。
著者は、お金を稼ぐ活動(ファイナンス)と、自分が社会に機能を提供する活動(職業)は分けて考えるべきだと提案します。そして、仕事、健康、趣味、家庭、社会貢献など、バランスの取れた8つの分野でゴールを持つことを推奨しています。
「お金が欲しい」という欲求は、資本主義社会によって植え付けられた幻想かもしれません。お金はあくまでゴールを達成するためのツールであり、目的ではありません。
自分の人生の価値は、他人や社会の基準で決めるものではなく、あなた自身が決めるものです。
思考停止という病から抜け出し、自分の頭で考え、自分の価値基準で人生を選択していくこと。それこそが、情報に溢れ、変化の激しい現代を生き抜くための最強の力であり、最高の人生を手に入れる唯一の方法なのです。