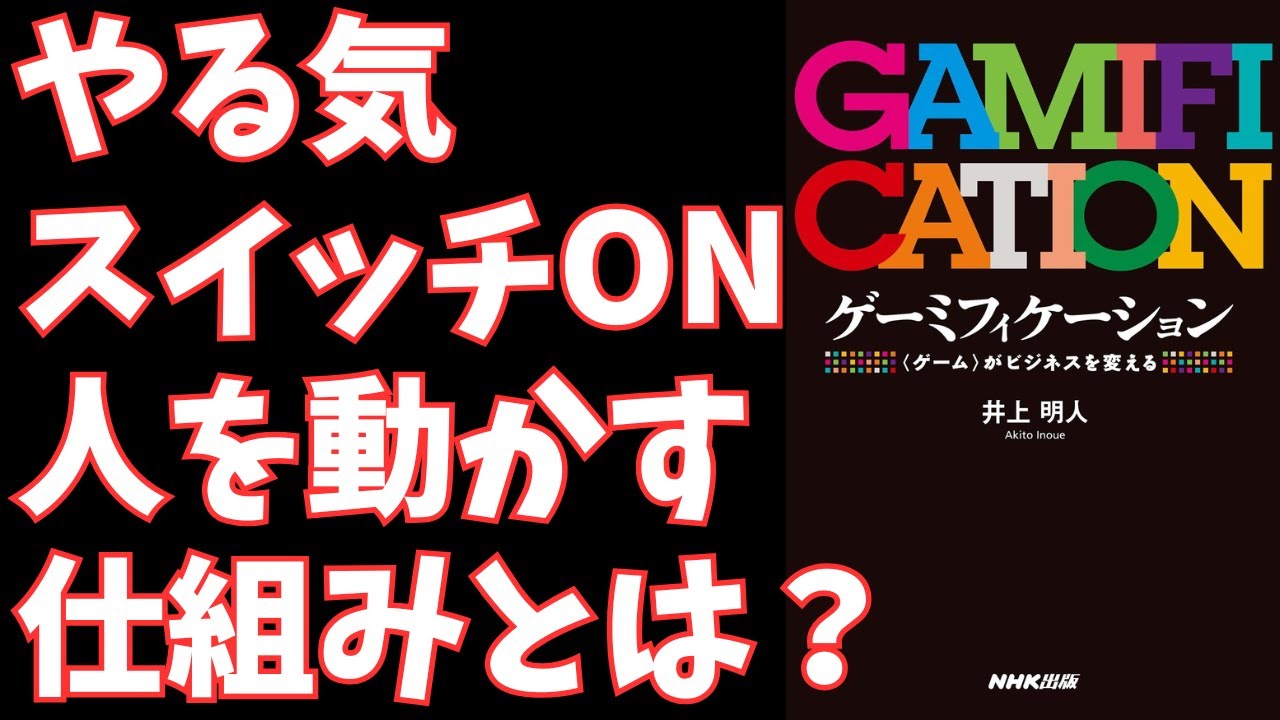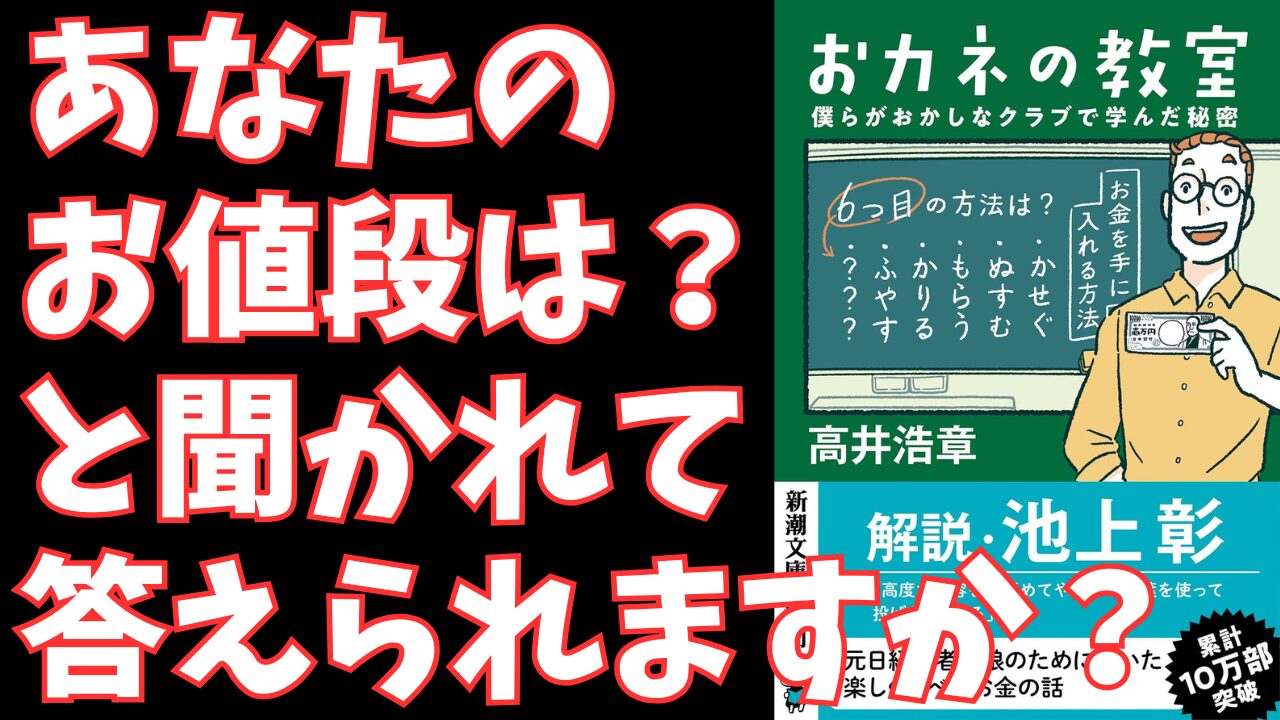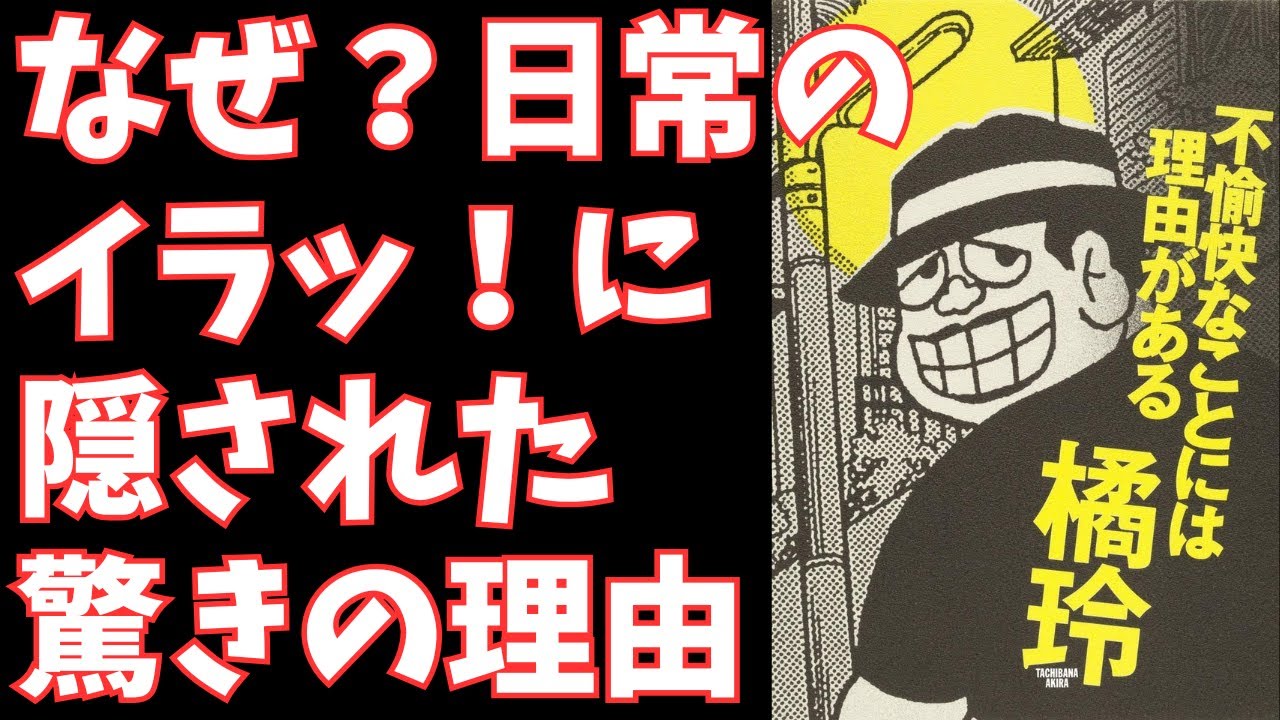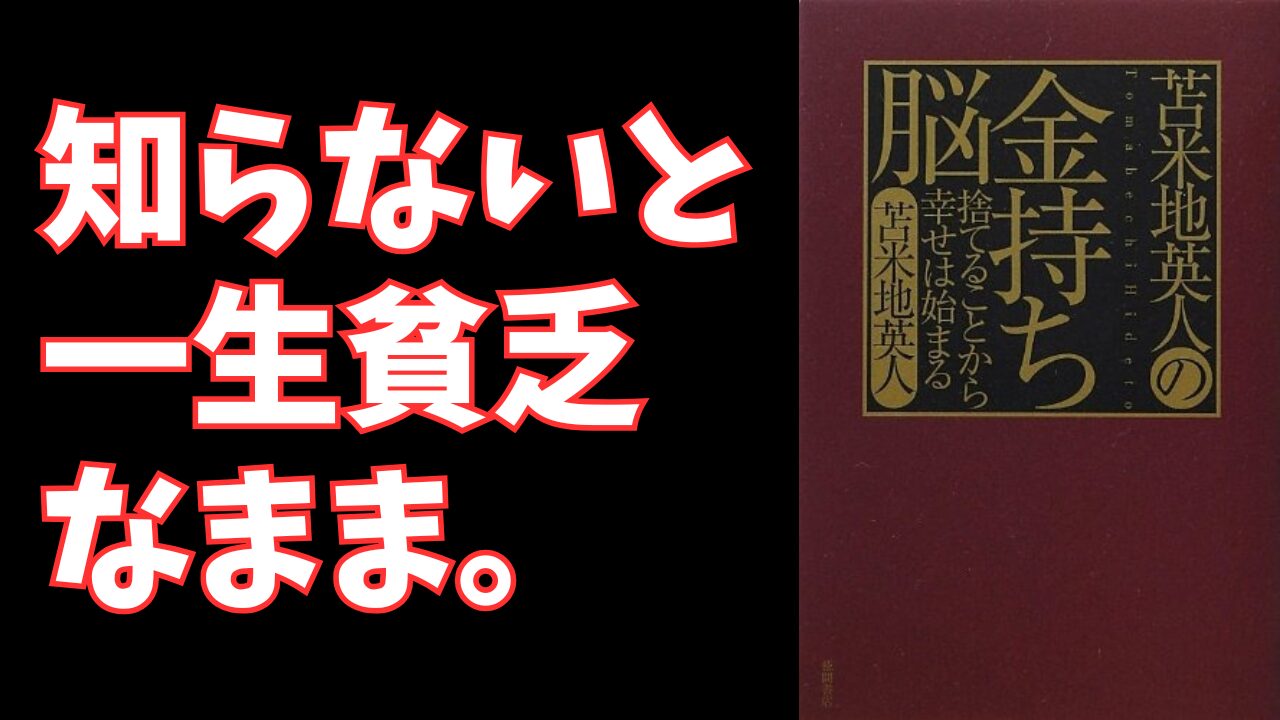「SNSマーケティングで掴む圧倒的成果!月商3.6億円への最短ルートとは」
本書では、元・手取り18万円の教員だった著者が、わずか1年で月商3.6億円を達成した理由と、その具体的なSNSマーケティング術を紹介しています。SNSを使った動画マーケティングの本質や、集客から販売までを一気通貫で行う「セールスファネル」の考え方、効率良くバズを生み出すためのテクニックなどがまとめられており、実践的な内容が特徴です。特にYouTubeを中心に展開する方法は、顔出しや毎日更新を必須としないにもかかわらず成果を出す仕組みが明確に示されています。SNS時代に必要な「質の高い情報発信」と「価値の提供」こそが成功への近道であることを教えてくれる一冊です。
はじめに:SNSマーケティングが生み出す新時代のビジネスチャンス
著者は「明確な理由なくして大きな成功はありえない」と強調します。これまでの広告市場やオンラインビジネスでは、有料広告や大がかりな宣伝を打てる企業だけが有利に見えました。しかし、本書で示されるのはSNS動画を活用すれば個人でも大規模ビジネスを展開できるという新時代の可能性です。実際に著者は、教員時代の月18万円という収入を逆手に取り、わずか1年で月商3.6億円を生み出しました。その背景にはSNSを駆使したハイブリッドマーケティングの巧みな設計があるのです。
この導入部分では、まず「SNSを制する者がビジネスを制する」時代背景を提示し、続く章で具体的な手法を段階的に解説していきます。
第1章:世界最先端のSNS動画マーケティングとは
「テクニック」よりも「本質」を捉える
著者が一貫して強調するのは、表面的なテクニックに走るのではなく、SNS動画マーケティングの本質を理解することの重要性です。アルゴリズム対策は日々変化し、特定の小手先の手法に依存していては長期的な成功は望めません。それよりも顧客のニーズを的確に捉え、継続的に価値を提供し続ける姿勢こそが、本質的な成功要因だと説きます。
YouTubeが最強プラットフォームである理由
なぜ数あるSNSの中でもYouTubeが注目されるのでしょうか。著者は以下の理由を挙げています。
- 検索エンジンとの連動
Google検索でも動画が上位表示される機会が増え、発見されやすい。 - 信用性の担保
テキストベースのSNSに比べ、動画は表情・声・視覚的な情報が多いため信頼関係を築きやすい。 - アーカイブ特性
投稿した動画の寿命が長く、後からでも何度も視聴されやすい。
さらに、顔出し必須ではない点も多くのビジネスパーソンにとって参入しやすい要素です。毎日の更新をプレッシャーに感じる必要もなく、「質を重視した戦略的な動画配信」ができれば、それだけで大きなリターンを得られます。
マーケティング=セールスを不要にする仕組み
マーケティングとはセールス行為を減らし、自然に顧客が集まる仕組みを作ることと著者は断言します。そのためには、YouTubeを「営業マン」として活用することが有効です。動画内で価値のある情報を提供しながら、自社の商品やサービスをさりげなく紹介する。視聴者からすると「営業を受けた」という印象は少なく、むしろ「お得な情報を得た」という感覚を得やすいため、高い確率でファンや見込み客に転じてくれます。
第2章:世界最先端の「セールスファネル」とは?
セールスファネルの仕組み
セールスファネルとは、見込み客を入り口とし、販売・購入へ至るまでの一連の流れを段階的に落とし込むマーケティング手法です。大きくは以下のステップに分けられます。
- 認知(Awareness)
SNSやYouTubeを通じて多くの人に存在を知ってもらう。 - 興味・関心(Interest)
見込み客が提供者の情報発信に興味を持ち、より詳しく知りたくなる。 - 比較・検討(Consideration)
他の商品やサービスと比べながら、詳細な情報を求め始める。 - 購入(Conversion)
最後の一押しが決め手となり、商品やサービスの購入に至る。
この仕組みを著者はSNS動画の中に巧みに組み込んでいます。動画やSNSで情報発信を続け、一定の教育・信頼関係を築いた後に、自然な形で商品やサービスに誘導するのです。
日本と海外のオンラインマーケットの違い
著者によると、日本のオンラインビジネスは海外に比べてまだ「安売り」が多い傾向があります。安価に大量に売る手法も時には有効ですが、それでは顧客が本当に価値を得ているのか疑問も残ります。著者は、値段設定が高めであっても、顧客が成果を実感できる質の高いサービスを提供することが重要だと説きます。特にSNSを活用すれば、実績や利用者の声を迅速に広めることができ、価格相応以上の効果を求める顧客を集めやすいのです。
第3章:「価値あるコンテンツ」を量産する方法
視聴維持率を高める重要性
YouTubeでは、視聴維持率(動画をどれだけ見てもらえるか)がアルゴリズム上とても重要です。視聴維持率が高いほど、YouTube側でおすすめ動画として露出されやすくなります。著者は視聴維持率を上げるために、最初の数秒で視聴者の興味を強く惹きつける工夫を凝らすべきだと述べています。例えば、動画冒頭で明確な結論やメリットを提示したり、BGMやテロップでテンポを作ったりするといった方法が挙げられます。
クオリティマーケティングが勝利の鍵
SNS時代は「量より質」が重視されると著者は繰り返します。特にYouTubeでの長期的なチャンネル成長を狙うなら、視聴者が「この人の動画は有益だ」と思う内容を積み上げる必要があります。そのためには、動画のネタ選びや構成、編集などを視聴者目線で入念に考え、わかりやすく提供することが大切です。
SNSの併用で最大効果を狙う
YouTube単体でも成果は期待できますが、さらにTwitterなど他のSNSと連動させると効果が倍増します。複数のSNSを通じて動画の存在を告知し、接触回数を増やすことで見込み客の印象に強く残るからです。著者はYouTubeの更新情報をTwitterで流す、あるいはTwitterのフォロワーに向けて限定情報を提供して見込み客リストを増やすなど、SNS同士を連携させる具体的な施策を提示しています。
第4章:実践編① ハイブリッドマーケティングの基本とYouTube動画の作り方
YouTube動画制作のフロー
著者が提唱するハイブリッドマーケティングでは、YouTube動画を軸として見込み客を教育し、最終的に高単価商品やサービスを購入してもらう流れを組み立てます。以下のステップで動画を作成することが推奨されます。
- サムネイル作成
第一印象を決定づける要素。視聴者がクリックしたくなるタイトルとデザインが重要。 - 動画の構成
興味を引く導入→具体的事例・解説→まとめとメリット→CTA(行動喚起)の順で構成すると効果的。 - テクニックの活用
BGM、テロップ、話し手のテンポなどを駆使して飽きさせない。 - 台本の作り方
話すポイントを大枠で整理し、視聴者が理解しやすい順番で情報を提供する。 - 撮影
スマホ撮影でも十分可能。照明や音声だけは最低限整える。 - 編集とチャンネル設計
視聴維持率を高める編集を行い、チャンネルのコンセプトや説明文なども整備しておく。
「18のYouTubeテクニック」
著者は、視聴者を引きつけ続けるための具体的な18のテクニックを示しています。たとえば冒頭で結論を述べる「結論ファースト」、動画内でQ&Aを入れ込む「疑問提示」、テンポ感を持たせる「話すスピード調整」など、どれも基本的なポイントではありますが、しっかり取り組むことで視聴維持率やチャンネル登録率が大幅にアップすることがわかっています。
第5章:ライバルに差をつけるYouTubeテクニック講座
サムネとタイトルの重要性
サムネイルとタイトルは集客の7割を決めるといわれるほど重要な要素です。著者は「悪用厳禁」と断りつつも、煽りすぎない程度のインパクトあるタイトルを推奨しています。キーワードを意識しつつ、「視聴することで得られるメリット」を具体的に示すとクリック率が上がるとのことです。
視聴維持率を高めるための演出
動画本編でも、「動画中盤でポイントの復習をする」「意外性のある事例を盛り込む」「時間経過とともに内容を深化させる」などのテクニックが効果的です。視聴者を飽きさせない演出を常に考え、次のパートも気になるような構成を意識します。
第6章:効率的にバズるためのTwitterテクニック講座
Twitterの原理原則
著者はYouTubeほどの詳細は解説していないものの、Twitterにもバズを引き起こすための基本原則があるとしています。その一例が以下です。
- 140文字(現行の仕様では上限拡大も)でいかに要点をまとめるか
- 共感や驚きを与える内容を入れる
- 継続投稿でアカウントの“信用度”を高める
ファン化とスクリーニング
Twitterは一瞬で拡散される特性がある一方、フォロワーに刺さらない投稿は埋もれやすいという短所もあります。しかし、それを逆手に取ることで、自分が提供するコンテンツに興味を示してくれるファンのみを集める(スクリーニングする)ことができるのです。これにより、見込み客の質を高めながら有益なフォロワーを増やす戦略が可能になります。
第7章:実践編② 集客の基本と高単価商品の販売戦略
教育とスクリーニング
本書の中でも繰り返し強調されるのが、「教育とスクリーニングの重要性」です。たとえ見込み客を大量に集めても、求めている価値と提供できる価値が合わなければ販売には至りません。そこでSNSやYouTube動画で先に内容を提供し、その価値を理解してもらった人だけが商品購入まで進むように仕組むのです。
高単価商品の販売戦略
単価の高い商品には購入ハードルがあるため、多くの見込み客にしっかりと商品価値を理解してもらう必要があります。本書では、その手順として
- 信頼関係の構築
YouTubeやTwitter等の無料コンテンツで、とにかく有益な情報を先に与える。 - 限定オファー
人数限定、特典付きといった形で希少性を高める。 - 継続教育
メールや追加動画などで詳細な内容を伝え、顧客が抱える疑問を解消する。 - クロージング
一般的なセールスのような押し売りではなく、「興味があればどうぞ」という自然な誘導を行う。
これらを繰り返すことで、高単価商品でも販売は十分に可能であると著者は証明しています。
第8章:イングリッシュおさる流マーケティング論
個人で稼ぐ時代の必須スキル
SNSにより、組織や大企業を介さずとも個人で大きく稼げる時代になっています。しかし成功するには、
- 自分ならではの強みやストーリーを活かす
- コンテンツの提供価値を冷静に分析し続ける
- 継続的な学習と改善を怠らない
ことが必要だと著者は説きます。
「相手に得をしてもらう」視点
マーケティングで何より大切なのは、常に相手にとってのメリットを提供する意識です。実際に著者はYouTubeやSNS上で、無料ながら非常に質の高い情報を公開し、多くのファンを獲得しました。結果としてブランド力が高まり、販売する商品への信用度も上がり、ビジネスを安定的に拡大できたのです。
第9章:イングリッシュおさる流ビジネス論
「努力できる才能」がすべてを変える
特別なスキルがなくても、地道に努力を重ねられる人は大きな成果をつかみやすいと著者は述べています。SNS運営や動画撮影・編集も一朝一夕に成果が出るわけではありません。しかし、毎回のフィードバックを生かして質を上げていけば、確実にファンや収益が積み上がっていきます。
ネガティブ思考を糧にする
著者の過去は、低収入の教員生活で苦労しながらも「もっと自由に生きたい」「収入を上げたい」という強い劣等感や悔しさを原動力にしていました。ネガティブな感情は行動力を妨げる一方で、正しく使えば成長の燃料となるのです。この「うまくいかない悔しさ」をエネルギーに変えて成功した実例は、ビジネスを始めるうえでも大きな勇気を与えてくれます。
最初の一歩を踏み出す意義
最後に、著者が何より強調しているのは「最初の一歩を踏み出す」ということです。YouTubeチャンネルを開設し、最初の動画を撮影して投稿する。Twitterにアカウントを作り、毎日少しずつでも投稿する。それらの小さな積み重ねこそが、やがて大きな成果として花開く――それを身をもって証明したのが、著者の「元・手取り18万円から月商3.6億円」という壮大な成功体験なのです。
おわりに
本書は「SNS動画マーケティングの真髄」を包括的に理解するためのガイドブックといえます。YouTubeをはじめとするSNSの活用方法やセールスファネルの組み立て方、高単価商品の販売戦略など、実践的かつ成果に直結しやすいノウハウが満載です。さらに著者の歩んできた具体的なストーリーも、多くのビジネスパーソンにとって共感の糸口や成功のヒントを与えてくれるでしょう。
SNSと動画を使ったビジネス拡大が不可避となった今、ビジネスパーソンが学ぶべきエッセンスがこの一冊には凝縮されています。「まずは行動し、質の高い情報発信を続ける」――このシンプルな原則を徹底することこそ、本書の最大のメッセージであり、誰もが再現可能な成功への鍵なのです。