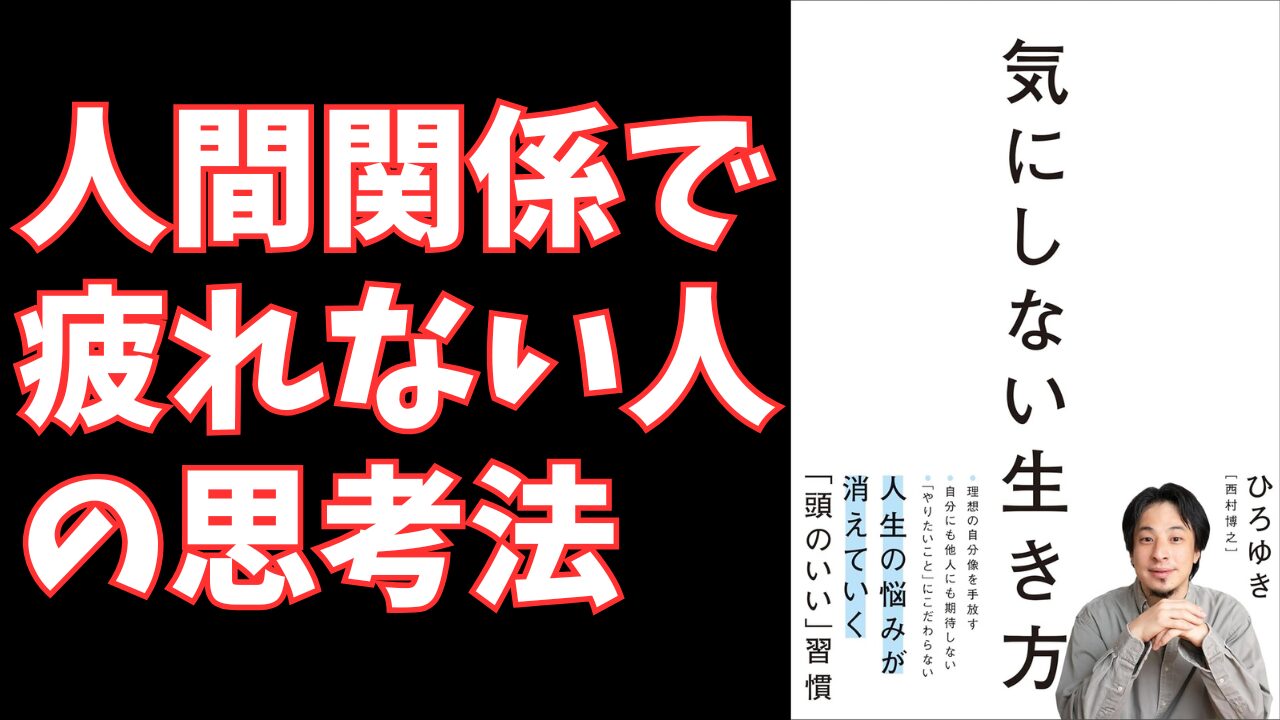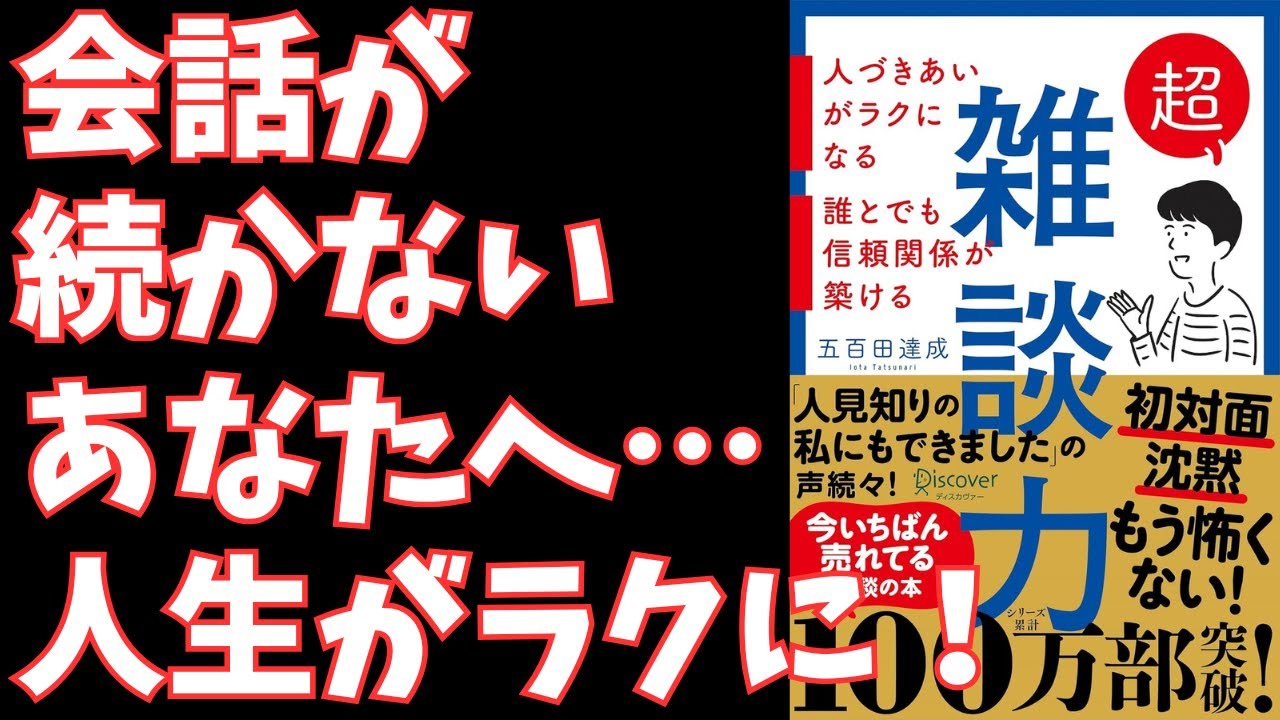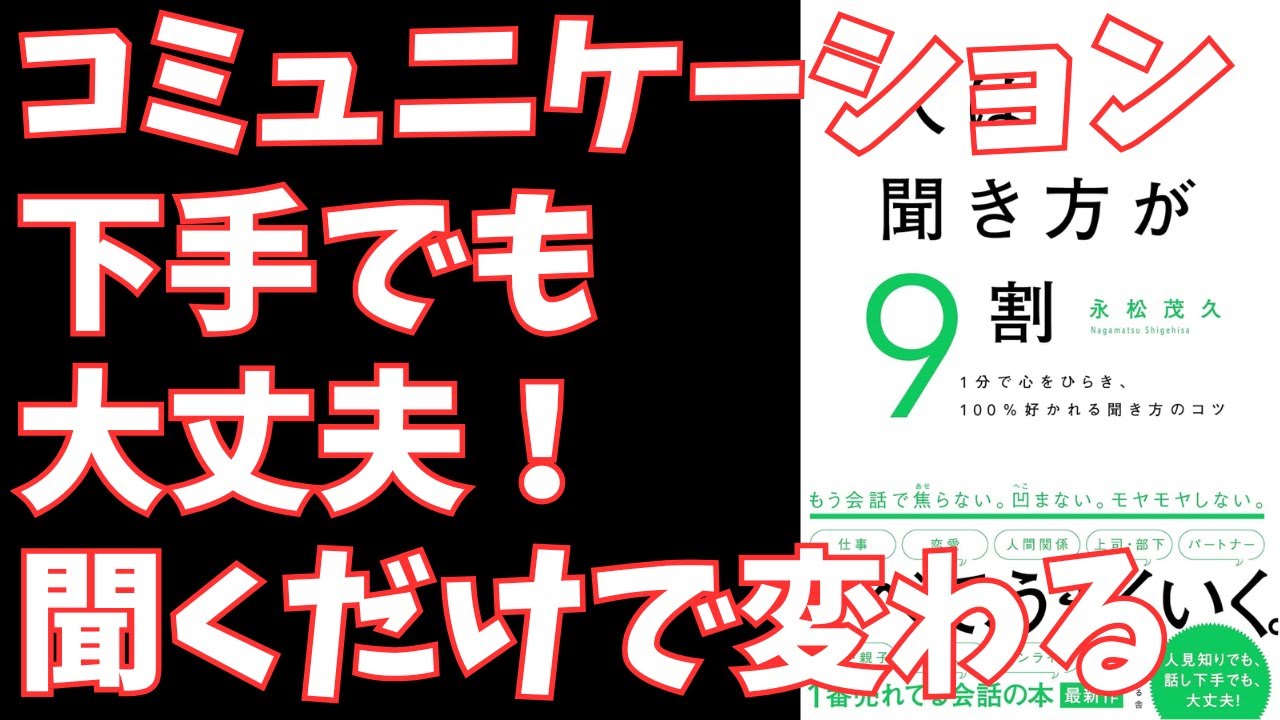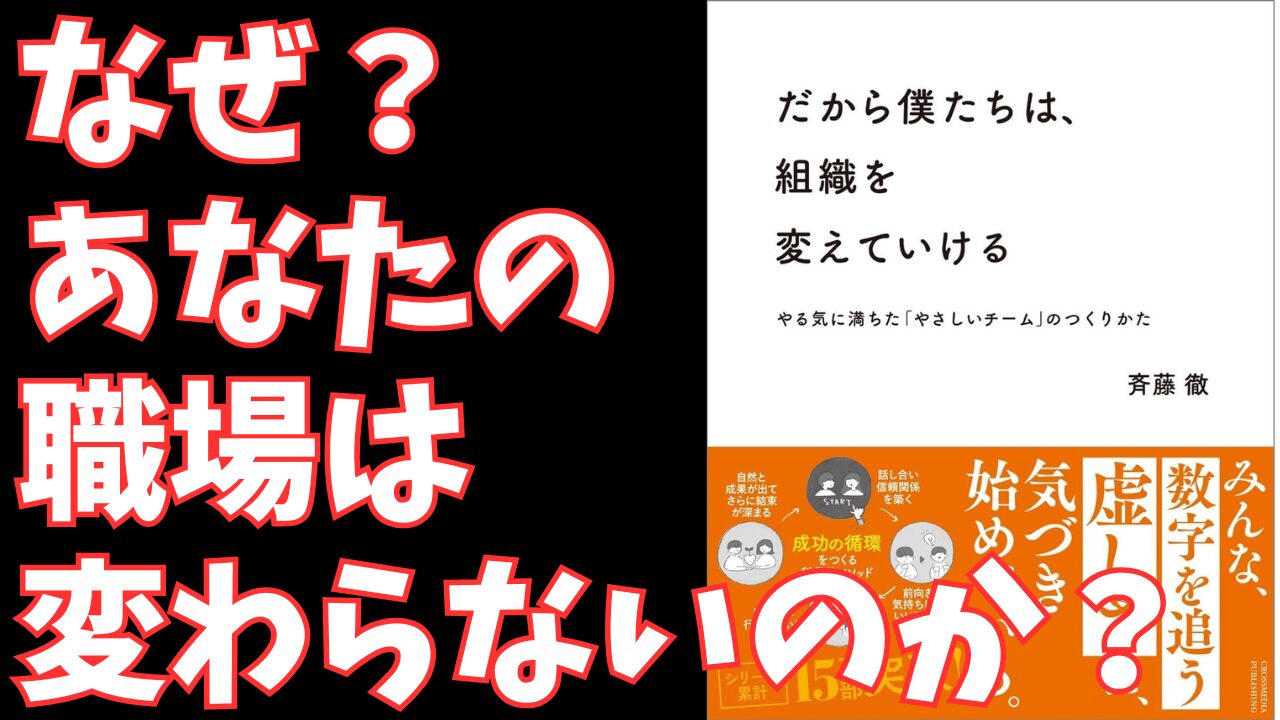世界の一流は「雑談」で何を話しているのか?明日から使える5つの戦略的会話術
多くの日本人が「雑談は世間話や無駄話」と捉えがちな中、世界の一流ビジネスパーソンは雑談を明確な意図を持った「武器」として活用し、成果に繋げています。本書『世界の一流は「雑談」で何を話しているのか』では、グーグルで人材育成を統括した著者が、日本と世界の雑談の違い、社内コミュニケーションにおける雑談の重要性、そしてビジネスで成果を出すための戦略的な雑談術を、具体的な事例を交えながら解説します。この記事を読めば、あなたの「雑談」に対する意識が変わり、明日からのコミュニケーションが劇的に変わるでしょう。
本書の要点
- 日本の雑談は「雰囲気作り」が目的である一方、世界の雑談は明確な意図と目的を持った戦略的なコミュニケーションである。
- 成果を出す雑談には、自己認識とそれに基づく自己開示が不可欠であり、相手への無条件の肯定的関心と共感が重要となる。
- グーグルでは、雑談を社内の風通しを良くし、生産性を高めるための重要なツールと位置づけ、意図的に機会を創出している。
- ビジネスの雑談は、相手の状況確認から始まり、信頼関係(ラポール)の構築、情報収集、意思決定プロセスの把握、そしてライフタイムバリューの向上を目指す。
- NGな雑談を避け、相手との関係性や状況に応じた適切な話題選びと質問力を磨くことで、雑談は強力な武器になる。
日本の雑談と世界の雑談、何が違うのか?
「今日は暑いですね」「本当に寒いですね」――こうした天候の話から会話を始める日本のビジネスパーソンは少なくありません。著者ピョートル・フェリクス・グジバチ氏は、これが日本のビジネスシーンにおける雑談の典型的なパターンであり、本題に入る前の「潤滑油」や「雰囲気作り」として捉えられていると指摘します。しかし、著者は「それだけでは、あまりにももったいない」と警鐘を鳴らします。
世界の一流は「意図」を持って雑談する
世界の一流ビジネスパーソンにとって、雑談は単なる世間話ではありません。彼らは明確な意図を持って雑談に臨み、それを武器として駆使することで仕事のパフォーマンスを上げ、成果を出すことを強く意識しています。具体的には、以下の5つの意図を持って相手と対面しているのです。
- 状況を「確認する」
- 情報を「伝える」
- 情報を「得る」
- 信用を「作る」
- 意思を「決める」
この5つの意図は、日本のビジネスマンが重視する「雰囲気作り」とは異なり、より戦略的で成果志向の強いアプローチと言えるでしょう。
「自己開示」の重要性――天気の話から一歩先へ
日本の雑談が定型的なフレーズに終始しやすいのに対し、ヨーロッパなどでは「その人」に特化した雑談が主流です。例えば、「今日は暑いですね」という話題から、「これだけ暑いと、週末は何をしているんですか?」といった形で、相手の個人的な領域に少し踏み込み、自己開示を促すような会話に発展します。
自己開示とは、プライベートな情報を含め、自分の「思い」や「考え方」を相手に素直に伝えることです。これにより、相手に自分がどんな人物なのかを知ってもらい、警戒心を解き、心理的な距離を縮めることができます。著者は、日本人が自己開示に慣れていない理由として、受け身の教育システムや、個人の意見を持つ必要性が薄い社会構造を挙げています。
しかし、多様な価値観を持つ人々と良好な関係を築くためには、まず「自己認識」(何を大切にし、何を正しいと思い、何を求めているのかを自問すること)を行い、その上で「自己開示」をしていくことが、これからの時代の雑談には不可欠です。
雑談は「準備」が9割――欧米の一流は周到に備える
欧米の一流ビジネスマンは、雑談に臨む際に徹底的な事前準備を行います。相手企業のIR情報を読み込むのはもちろん、SNSで近況をチェックしたり、共通の知人を通じて相手の人となりを調べ上げたりします。
例えば、自社製品をプレゼンする場合、相手企業の業界ニュースや担当者の仕事への向き合い方、家族構成、趣味・趣向までリサーチし、その担当者にピンポイントで響く「武器」としての雑談を用意するのです。「仕事を始める前に、それを終わらせるのが好き」という言葉が象徴するように、本題に入る前の雑談の段階で、すでに勝負は決まっているのかもしれません。
残念ながら、日本のビジネスマンの約半数は、何の準備もせずに雑談に臨んでいると著者は指摘します。事前に相手の情報を少しでも調べていれば、「お国はどちらですか?」といった初歩的な質問で相手をガッカリさせることもなくなるはずです。
グーグル流「社内雑談力」の極意――強いチームは雑談から生まれる
著者がかつて在籍したグーグルでは、社内コミュニケーション、特に雑談が非常に重視されています。それは単なる親睦のためではなく、生産性を上げ、成果を出すための重要なツールとして戦略的に活用されているのです。
意図的に「衝突」を生み出すオフィス設計
グーグルでは、社員同士が頻繁に雑談し、意見交換ができるように、意図的に「衝突(collisions)」が生まれるようなオフィス設計がなされています。広いスペースや会議室が狭い通路で繋がれていたり、社員食堂には一人席がなく、自然と会話が生まれるような工夫が凝らされているのです。
また、毎週金曜日の午後には「TGIF(Thanks Google It’s Friday)」という全社ミーティングが開かれ、経営陣と社員がフランクに意見交換できる場が設けられています。「社長の意見は間違っていると思います」といった厳しい意見も飛び交いますが、こうした風通しの良さがグーグルの強さの源泉の一つです。
「1on1」ミーティングは雑談が鍵
日本でも導入企業が増えている「1on1」ミーティングですが、著者はその多くが単なる「面談」で終わってしまっていると指摘します。その原因は、雑談の不足、そして雑談の本質を理解していないことにあると言います。
グーグルでは、マネジャーとメンバーは上司・部下という上下関係ではなく、コーチと選手のような関係です。1on1はメンバーのための時間であり、仕事の進捗確認だけでなく、プライベートな悩みも含めて腹を割って話せる環境づくりが重視されます。日常的な雑談を通じて心理的安全性を高めているからこそ、オープンな会話が可能になるのです。
雑談がもたらす7つの相乗効果
職場の雑談には、以下のような7つの相乗効果があると著者は述べています。
- 職場の人たちと仕事以外の「つながり」ができる
- お互いの「信頼感」が高まる
- 職場の「心理的安全性」が高まる
- 「働きやすい環境」が生まれる
- 仕事の「モチベーション」が高まる
- ミーティングで「発言」しやすくなる
- 会議の結論に「納得」して働けるようになる
実際に、「雑談をするチームは生産性が高い」というエビデンスも存在します。笑い声が聞こえない会社には何らかの問題がある、と著者は考えています。
「武器」としてのビジネス雑談――成果を最大化する4つの目的
社外のビジネス相手との雑談は、まさに「武器」としての側面が強まります。単なる挨拶や世間話ではなく、明確な目的を持って臨むことで、ビジネスの成果を大きく左右するのです。
雑談のミッションは「確認作業」から始まる
ビジネス雑談の最初のミッションは「確認作業」です。相手の状況(体調、心構え)、ビジネスの現状、そして新たに必要となる情報を雑談を通じて確認します。相手が明らかに忙しそうであれば、「何かありましたか?」と声をかけ、本題に入れる状況かを見極めます。この数分の確認作業が、その後の商談の成否を分けることもあります。
特に重要なのが、相手企業の「意思決定」の流れを確認することです。誰が最終的な意思決定者で、どのようなプロセスで決定が下されるのかを知らないままでは、効果的なアプローチはできません。
顧客の「ライフタイムバリュー」を高める雑談
営業目的の雑談であれば、単発の取引で終わらせず、長期的に良好な関係を築き、顧客の「ライフタイムバリュー(顧客生涯価値)」を高めることが重要です。そのためには、自社製品の魅力だけでなく、営業担当者自身の人間力、そして雑談を通じた信頼関係の構築が不可欠となります。「この人から買い続けたい」と思わせる「CtoC(個人対個人)」の関係性を築くことが鍵です。
ビジネス雑談の4つの戦略的目的
ビジネスにおける雑談には、大きく分けて以下の4つの目的があります。
- 「つながる」: 相手との距離を縮めて信用を作る(ラポール形成)
- 「調べる」: 最新の動向や現状に関する情報を収集する
- 「伝える」: 自社の意向や進捗状況などを報告する
- 「共有する」: 最新の情報を相互に認識する
これらの目的を意識し、アジェンダに入る前だけでなく、アジェンダに関する話が終わった後にも戦略的に雑談を交わすことで、より深い関係構築と成果の最大化が期待できます。
「対等な関係」を築くためのアプローチ
日本のビジネスシーンでは、発注元と受注元といった立場の違いから「上下関係」が生まれやすい傾向があります。しかし、これでは真の信頼関係は構築できず、仕事の質も向上しません。著者は、「CtoC」の視点に立ち、雑談を通じて対等な関係を築くための3つのアプローチを提案しています。
- お互いの共通の「趣味」を見つける
- お互いに共通する「体験」や「考え方」を共有する
- 相手にとって「必要不可欠」な存在になる
特に、相手の挫折体験などを共有できるようになれば、関係性は大きく変わるでしょう。
「興味深い人」になる秘訣は、相手に「興味を持つ」こと
「何を話せばいいのだろう?」と雑談のネタに困る人は多いかもしれません。しかし、著者は小手先のテクニックよりも、相手に「興味」や「好奇心」を持って接する姿勢が最も重要だと説きます。
デール・カーネギーの「If you want to be interesting be interested(興味深い人になりたければ、興味を持て)」という言葉を引用し、相手を深く理解しようとする姿勢が、本質的な会話を生み出すと述べています。
相手の価値観、信念、求めているものを知るために、著者は「7つの質問」(例:「あなたは仕事を通じて何を得たいですか?」、「なぜ今の仕事を選んだのですか?」など)を用意し、これらを自然な雑談の流れで投げかけることを推奨しています。
異業種の相手であれば、その業界の「サイクル→トレンド→パターン」を聞くことも有効です。相手は自身の専門分野について喜んで語ってくれるでしょうし、こちらも新たな学びを得られます。
エグゼクティブは雑談で「スクリーニング」している
企業の社長や幹部クラスといったエグゼクティブは、雑談を通じて相手を「スクリーニング(ふるい分け)」しています。彼らが求めているのは、お金では買えない「新たな刺激」となる情報や知恵、アイデアです。短い雑談の時間で、いかに価値のある話を提供できるかが、彼らとの信頼関係を築く第一歩となります。
もし、圧倒的な情報提供が難しいと感じるなら、著者のように相手を「質問攻め」にするのも一つの手です。人は自分に興味を持ってくれる相手には好意的に接するものです。相手のビジネスのきっかけ、挫折体験、ミッションなどを深く掘り下げることで、自然と心の距離は縮まります。
こんな雑談は危ない!避けるべき6つのNGポイント
雑談は関係構築の武器になる一方で、一歩間違えれば関係を悪化させる「凶器」にもなり得ます。著者は、絶対的なタブーは存在しないとしつつも、注意すべき「危ない雑談」のポイントを挙げています。
- 相手のプライベートに、いきなり踏み込まない: 結婚の有無など、デリケートな質問は避け、「休日は何をされていますか?」といったオープンな質問から入るのが賢明です。
- 「ファクト」ベースの質問は意外に危険: 学歴や職歴など、事実に基づいた質問は、相手によっては触れられたくない過去を想起させる可能性があります。「価値観」や「信念」ベースの質問を心がけましょう。
- ビジネスの場で「収入」の話はしない: これは国内外問わず、避けるべき話題です。
- 「シチュエーション」を考えた雑談を心がける: 周囲に人がいる状況でのプライベートな質問や、会社の悪口などは厳禁です。「壁に耳あり、障子に目あり」を忘れずに。
- 「宗教」の話は無理に避ける必要はない: 相手を尊重し、ビジネス上必要な範囲で(食事の禁忌など)、尋ねるべきことは尋ねる姿勢が大切です。是非を議論するのはNGです。
- 「下ネタ」で距離感が縮まることはない: ビジネスの場にふさわしくありません。人間らしい素直な会話ができない人は信用を失います。
最終的には、あえて「雑談をしない」という選択肢もあることを覚えておきましょう。すでにお互いの心理的安全性が確保され、ラポールが形成されているのであれば、無理に雑談をする必要はなく、業務に集中する方が生産性は高まります。
まとめ:雑談は「好奇心」「知識」「経験」で進化する
リモートワークの普及により、私たちは雑談の重要性を再認識させられました。本書で著者が一貫して主張するのは、雑談とは単なる世間話ではなく、相手を理解するための「本質的な会話」であるということです。
そして、相手を理解するための深い雑談には、以下の3つの要素が不可欠です。
- 「好奇心」: 相手の全人格に関心を持つこと
- 「知識」: 自分が持つ様々な知識
- 「経験」: これまでに得た経験
これらを総動員し、①相手を驚かせないレベルの「自己開示」、②好奇心を持って相手の「人間性」を知ろうとすること、③「信頼関係」の構築という目的意識、④相手と「ラポール」を作れているかの客観的な観察、という4つのポイントを意識して雑談に臨むことで、あなたのコミュニケーションは劇的に変わり、ビジネスでより大きな成果を生み出すための強力な「原動力」となるでしょう。