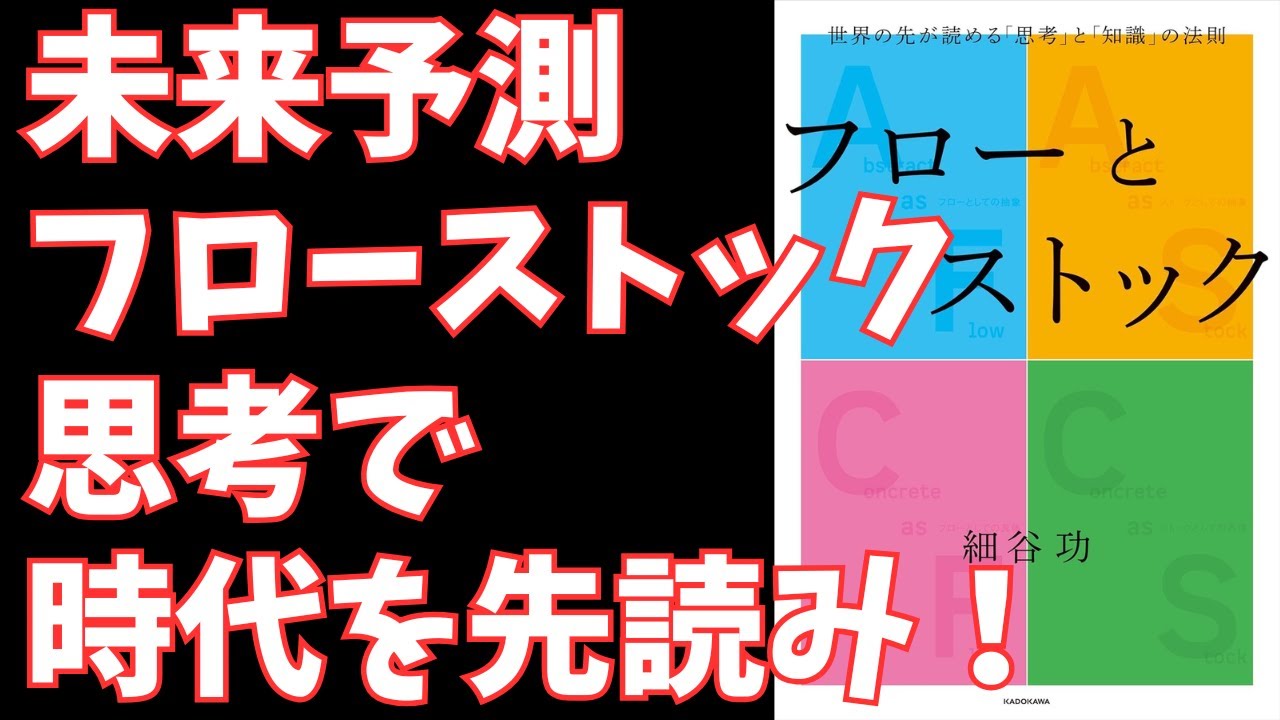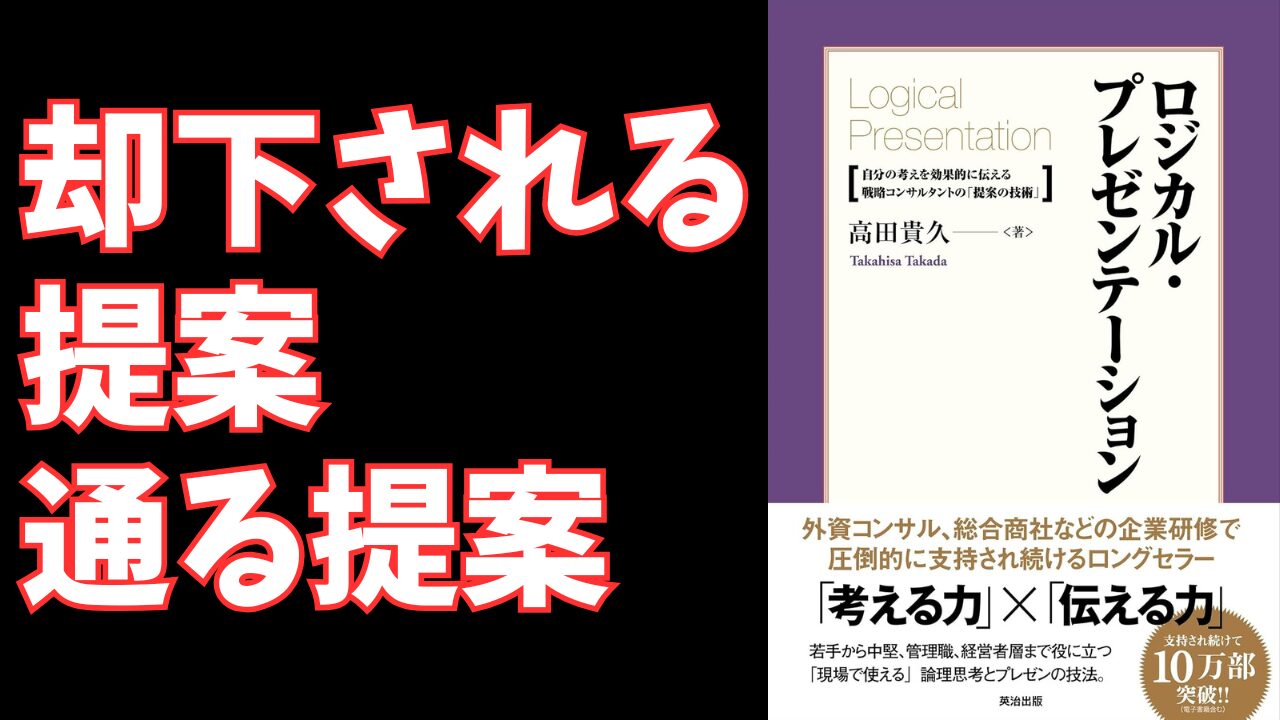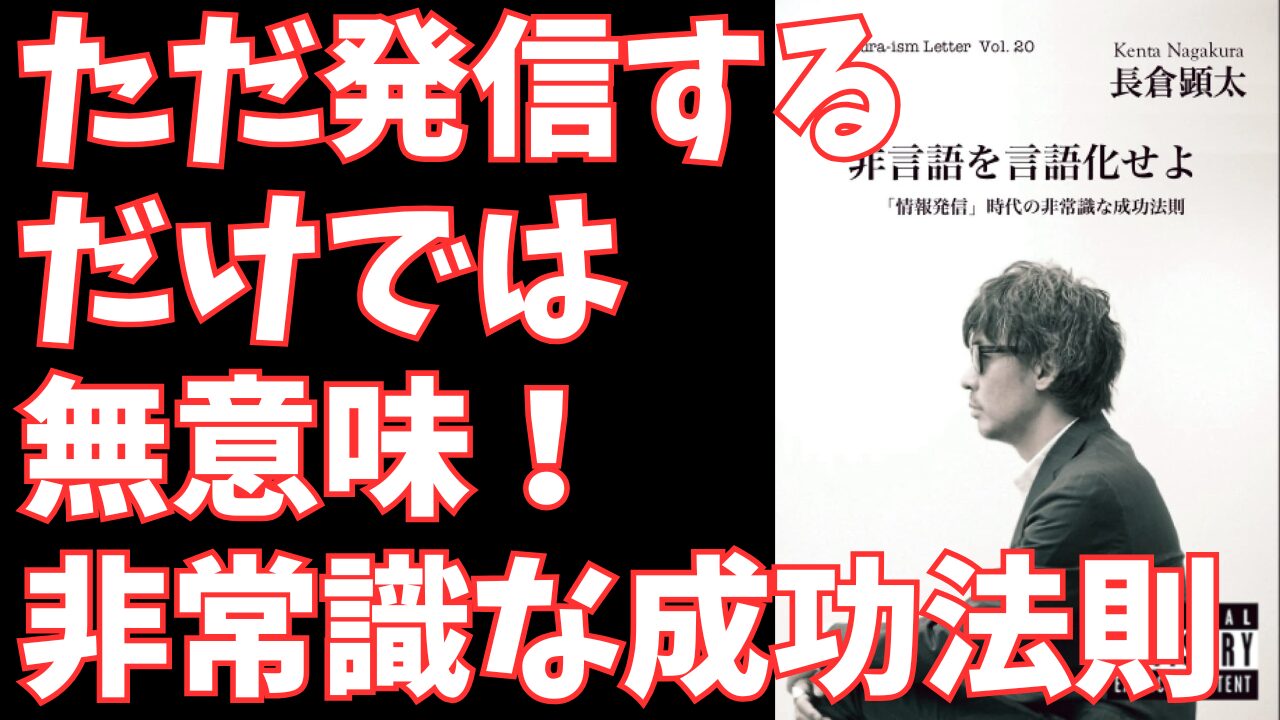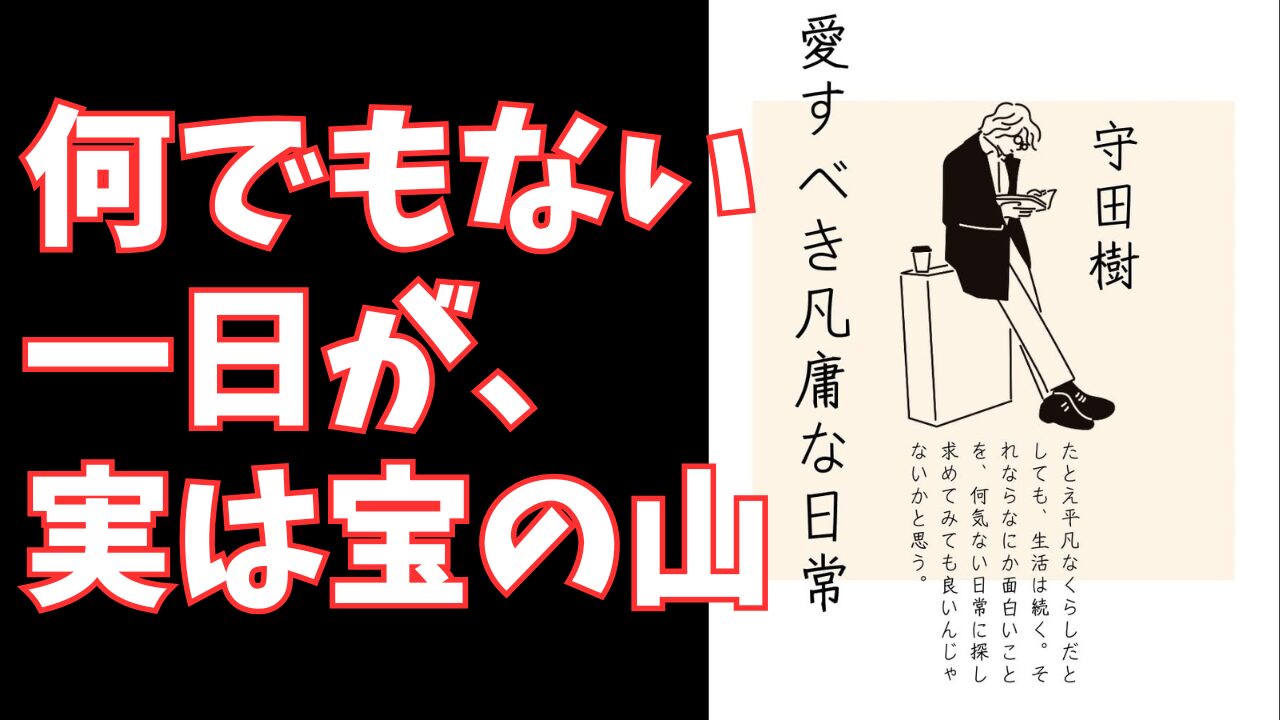「データと対話」で職場を変える技術|サーベイ・フィードバック入門【要約・実践法】
本書『「データと対話」で職場を変える技術 サーベイ・フィードバック入門』は、立教大学経営学部教授の中原淳氏が、多くの企業が直面する「データを活用しているはずなのに、なぜか職場が変わらない」という課題に、明確な答えを提示する一冊です。
近年、HRテックやエンゲージメントサーベイの流行により、多くの企業が従業員のデータを収集・分析しています。しかし、その多くが「データを取るだけ」で終わり、現場の負担を増やすだけで、実際の職場改善につながっていないのが実情です。 本書は、こうした「コケてしまっているサーベイ」の問題の根源を、データそのものが組織を変えるわけではなく、データに基づいた現場の「対話」こそが変革の原動力であると喝破します。
この記事では、本書の核心部分である「サーベイ・フィードバック」の理論と実践方法を、忙しいビジネスパーソン、特に日々チームを率いる管理職の方々が明日から使える形で、分かりやすく解説します。メルカリ、パナソニック、デンソーといった先進企業の具体的な事例も交えながら、勘や経験だけに頼るマネジメントから脱却し、データという武器を手に、チームを動かし、成果を出すための実践的な知恵をお届けします。
本書の要点
- データは「正解」を教えない。 データはあくまで職場の現状を映す「鏡」であり、変革の方向性を決めるのは、そこにいるメンバー自身の「対話」である。
- サーベイ・フィードバックは「①見える化」「②ガチ対話」「③未来づくり」の3ステップで進める。 このプロセス全体を丁寧に行うことが、組織変革の成否を分ける。
- 組織の問題を個人のせいにせず、データを用いて「外在化」させることが重要。 これにより、個人攻撃を避け、建設的で本音の対話(言える化)が可能になる。
- 効果的なフィードバックには「心理的安全性」の確保が不可欠。 メンバーが安心してリスクのある発言ができる場作りが、マネジャーの重要な役割である。
- サーベイは「やりっぱなし」が最も有害。 多くの企業が陥りがちな「サーベイの病」を理解し、それを避けることで、組織変革は成功に近づく。
なぜ、あなたの職場はサーベイを導入しても変わらないのか?
「AI(人工知知能)を使った職場改善をしよう!」
「最新のHRテックを導入して、離職を減らそう!」
「エンゲージメント・サーベイで、生産性を向上させよう!」
人事・人材マネジメント業界では、こうした威勢のいいかけ声が日々こだましています。 あなたの職場でも、全社的なサーベイが導入され、「またアンケートか…」とうんざりした経験があるかもしれません。
しかし、その結果、職場は本当に良くなったでしょうか?
著者のもとには、こうした「鳴り物入り」で導入されたサーベイが、現場に混乱と疲弊をもたらしているという声が数多く寄せられています。
- 「ただでさえ忙しいのに面倒な調査に協力したが、フィードバックもなく、あれはいったい何だったんだろう…」
- 「毎月アンケートに答えているが、職場が良くなる気配はいっこうにない。」
- 「膨大なデータが送られてくるが、何をどう改善すればいいか、さっぱりわからない…」
これらは、サーベイが「コケてしまっている」典型的な例です。本書は、こうした問題の根源を、データやサーベイに対する「浅薄な理解」に基づく「安易な導入」にあると鋭く指摘します。 多くの経営者や担当者が、「データをとれば問題が見えるはず」「サーベイさえ行えば組織は自然に変わるはず」といった「テクノロジー決定論」の罠に陥っているのです。
しかし、著者は断言します。
データだけでは、人は動きません。データは組織を変えません。
健康診断で「中性脂肪200mg/dL超え」というデータを示されても、多くの人が生活習慣を改めないのと同じです。 データが現場の人々に「解釈」され、「これは自分たちの問題だ」と意味づけられ、「対話」を通じて納得感が生まれたときに初めて、組織は変わるための一歩を踏み出すのです。
本書が提唱する「サーベイ・フィードバック」は、まさにこの「データと対話」をつなぐための技術なのです。
現代の管理職が「サーベイ・フィードバック」を学ぶべき2つの理由
では、なぜ今、私たちビジネスパーソン、特に管理職は「サーベイ・フィードバック」を学ぶ必要があるのでしょうか。本書は、その背景に現代の組織が抱える2つの大きな環境変化があると説明します。
理由1: 職場の多様化で「チームがまとまらない」問題
かつての日本企業は、「日本人・正社員・男性」が中心となり、長時間共に働くことで「村」のような濃密な関係性を築いていました。 しかし、終身雇用の崩壊、転職の一般化、グローバル化、人手不足などを背景に、職場のメンバーは性別、国籍、雇用形態、働き方など、あらゆる面で多様化しています。
この多様性は、イノベーションの源泉であると同時に、価値観のズレによる「遠心力」も生み出します。 放置すれば、チームはバラバラになりかねません。もはや、かつてのような「勘と経験とノミュニケーション」だけでは、チームをまとめることは困難です。
そこで必要になるのが、客観的なデータ(サーベイ)によって組織のコンディションを正確に把握し、多様なメンバーと対話しながらチームを運営していく技術、すなわちサーベイ・フィードバックなのです。
理由2: エンゲージメントを高め、離職を防ぎ、生産性を上げたい
「熱意あふれる社員」の割合が、米国32%に対し、日本はわずか6%(139カ国中132位)。これは米ギャラップ社による衝撃的な調査結果です。 日本企業の従業員エンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)が、世界的に見ても極めて低いことは、多くの調査で示されています。
そして、このエンゲージメントの低さは、企業の生産性や従業員の定着率と密接に関係しています。 働きがいを感じられない職場からは人は去り、残ったメンバーの生産性も上がりません。
深刻な人手不足の時代において、従業員の離職を防ぎ(リテンション)、一人ひとりの生産性を高めることは、企業の死活問題です。そのための有力な手段が、サーベイによって定期的にエンゲージメントを測定し、その結果を現場にフィードバックして改善につなげていくことなのです。
これらの「多様化」と「エンゲージメント」という現代的な課題に、現場の最前線で向き合わなければならないのが、管理職です。サーベイ・フィードバックは、こうした難問に「素手」で立ち向かうのではなく、データという強力な「武器」を手に戦うための必須スキルと言えるでしょう。
「データと対話」で職場を変えるサーベイ・フィードバックの3ステップ
本書の核心であるサーベイ・フィードバックは、具体的にどのようなプロセスで進めるのでしょうか。それは、以下の3つのステップに集約されます。
ステップ1: 見える化
これは、サーベイ(組織調査)を通じて、普段は見過ごされがちなチームや組織の課題を「可視化」する段階です。
本書では、組織の問題を「氷山モデル」で説明します。 私たちが普段目にしている問題(業績の悪化、ミスの頻発など)は、水面上に出ている「コンテント(内容的な側面)」に過ぎません。その水面下には、目には見えない「プロセス(メンバーの関係性的な課題)」が巨大な氷の塊として存在しています。
サーベイによる「見える化」とは、この水面下にある「たいせつなこと」に光を当て、組織メンバーの眼前に浮かび上がらせる行為なのです。
ステップ2: ガチ対話
「見える化」は、あくまで変革の「はじまり」に過ぎません。ここからがサーベイ・フィードバックの真骨頂です。見える化した組織課題に、チーム・関係者全員で向き合い、本音で話し合います。
重要なのは、データは「正解」を教えてくれるわけではない、ということです。データはあくまで「対話の素材」。そのデータを見て、「これは何を意味するのか」「なぜこうなっているのか」を当事者たちが話し合うプロセスこそが、組織に変化をもたらします。過去の研究でも、対話(フィードバック・ミーティング)のないサーベイは効果が薄いことが証明されています。
ステップ3: 未来づくり
「ガチ対話」を通して課題の根本原因を探ったら、最後は「これから自分たちの組織・チームをどうしていくか」という未来を、当事者たちが「自分ごと」として決め、具体的なアクションプランを作成します。
「誰かがやってくれるだろう」という他人ごとではなく、明日から自分たちが何をするのかを決める。このオーナーシップこそが、変革を本物にします。
多くのサーベイが「見える化」だけで終わってしまう中、この「ガチ対話」と「未来づくり」までを一気通貫で行うことこそが、サーベイ・フィードバックの要諦なのです。
なぜデータは人の行動を変えるのか?3つのメカニズム
そもそも、なぜサーベイでデータを集め、フィードバックすることが、人や組織の行動を変えるのでしょうか。本書では、そのメカニズムを3つの効果で説明しています。
1. コレクション効果
これは、「何を質問するか」ということ自体が、組織からの強力なメッセージになるという効果です。
例えば、サーベイで「あなたの職場では、オープンにコミュニケーションできていますか?」という質問を繰り返されれば、従業員は「この会社はオープンなコミュニケーションを重視しているんだな」と無意識に学習します。 つまり、質問項目を決める行為そのものが、組織変革の第一歩なのです。いい加減な質問項目では、組織は変わりません。
2. フィードバック効果
これは、システムのアウトプット(成果)をインプットに返すことで、システムの質を高めるというサイバネティクスの概念を応用したものです。
組織に置き換えれば、職場の成果や状態に関するデータ(サーベイ結果)を、職場のメンバーにフィードバックすることで、2つの機能が働きます。
一つは、理想と現実のギャップから「このままではマズい、変えよう」という「モチベーション機能」。もう一つは、「何を改善すれば良いか」の手がかりを得られる「ディレクション機能」です。
3. 外在化効果(本書の独自理論)
これは、著者が提唱する非常に重要な効果です。職場で問題が起きると、私たちは「Aさんのやる気がないからだ」「Bさんの能力が低いからだ」というように、問題を個人のせいにしてしまいがち(内在化)です。これでは個人攻撃の応酬になり、建設的な対話は生まれません。
しかし、ここに客観的な「データ」を介在させると、「データによると、私たちの職場はコミュニケーションが不足している」というように、問題と個人を切り離して議論できます。これを「外在化」と呼びます。 問題を外在化することで、メンバーは安心して本音を語れるようになり、これが「言える化」を促進するのです。
【実践編】明日から使える!効果的なフィードバック・ミーティングの6ステップ
サーベイ・フィードバックの成否は、フィードバック・ミーティングの質にかかっています。ここでは、現場マネジャーがファシリテーターを務めることを想定し、本書で紹介されている具体的な6つのステップを解説します。
Step1: 目的説明
ミーティングの冒頭で、「ねぎらいと感謝」を伝えることから始めます。 その上で、「なぜこの会を行うのか(目的)」「何をするのか(スケジュール)」「どんな良いことがあるのか(メリット)」を、マネジャー自身の言葉で明確に伝えます。関係者を全員集めることも重要です。
Step2: グラウンドルールの提示
「批判厳禁」「悪者探しをしない」「ここで話したことは外に持ち出さない」といったルールを全員で確認し、心理的安全性を確保します。 本書では、心理的安全とは「ぬるま湯」ではなく、「チームのためにリスクのある発言や言動をしても、対人関係上の亀裂が生じない状態」と定義されており、この場作りがマネジャーの重要な役割です。
Step3: データの提示
配布されたフィードバックシートをただ読み上げるのは最悪です。注目してほしいデータに焦点を当て、ストーリー仕立てで語りましょう。 その際の鉄則は「ポジからネガへ」。まず職場の良い点に関するデータを取り上げて感謝を伝え、信頼関係を築いてから、「この良い状態を持続させるために、気になるデータも見ていきましょう」と課題に移ります。
Step4: データに対する解釈
メンバーそれぞれが、データを見て何を感じたか、どう解釈したかを共有する時間です。正解探しや議論ではなく、認識の「ズレ」を顕在化させることが目的です。 ロジカルな意見だけでなく、「このデータを見て、どんな気持ちが湧きましたか?」と感情を聞いてみると、本音が引き出せることもあります。
Step5: 「未来」に向けた話し合い
メンバー間の認識のズレを受け止めた上で、「では、私たちはこれからどうありたいのか」という理想の未来を話し合います。 ここで求められるのは、お互いの違いを乗り越え、共に未来を探る本来の意味での「対話」です。マネジャーは、議論が逸れないように交通整理する役割を担います。
Step6: アクションプランづくり
最後に、話し合った未来を実現するための具体的なアクションプランに落とし込みます。重要なのは、「頑張る」といった精神論ではなく、「誰が」「いつまでに」「何をするか」という「明日からできること」を決めることです。 早く小さな成功体験(アーリーウィン)を得られる目標を設定し、全員で役割分担することが、行動を継続させるコツです。そして、やりっぱなしにせず、定期的に進捗をフォローアップすることまで計画に含めましょう。
【事例紹介】メルカリ、パナソニック、デンソーはこうして組織を変えた
本書では、サーベイ・フィードバックを実践する先進企業3社のリアルな事例が紹介されています。
メルカリ:サーベイの力で「未来永劫、サステナブルな組織」をつくる
急成長・急拡大を続けるメルカリでは、組織のコンディションを保つため、3ヶ月に1回というハイスピードでサーベイを実施しています。 特徴的なのは、理念(バリュー)を反映したサーベイを内製化し、経営会議からフィードバックを開始するカスケード型の展開。そして、課題の「見える化」から具体的なアクションプランへの落とし込みを徹底している点です。
パナソニック:「ガチ対話」を妨げる障害を取り除け!
巨大組織パナソニックでは、従業員意識調査のデータを鵜呑みにせず、インタビューによる定性情報と組み合わせて課題を深掘りします。 そして、いきなり「ガチ対話」を求めるのではなく、オフサイトミーティングでの「ジブンガタリ」や「自慢大会」といったポジティブアプローチによって、本音を言える関係性の構築を優先しています。 まずは「恐れ」を取り除くというアプローチは、多くの日本企業にとって参考になるでしょう。
デンソー:組織変革の鍵は「社員の関係性の質」にあり!
世界的な自動車部品メーカーであるデンソーも、サーベイ・フィードバックの土台として「関係性の質」の向上に注力しています。 伝統的な組織開発手法を現代風にアレンジした「NFT(ニューファミリートレーニング)」や、1時間で相互理解を深める「しゃべり場」といったユニークな取り組みが紹介されています。 問題解決思考が強い製造業の職場だからこそ、こうした関係構築のアプローチが有効であるという示唆に富んだ事例です。
あなたの職場は大丈夫?サーベイ・フィードバックが陥る8つの「病」
最後に、本書で警鐘が鳴らされている、サーベイ・フィードバックが陥りがちな8つの「病」を紹介します。 これらを反面教師として、自社の取り組みを振り返ってみましょう。
- サーベイすれば現実は変わる病: データだけでは組織は変わらない。フィードバック・ミーティングこそが本番。
- 項目が多すぎてわからない病: データを絞り、受け手が処理可能なレベルでフィードバックする。
- データがつながっていない病: 各部署でバラバラに行われる調査データを一元管理し、紐づける。
- サーベイに正解を求めてしまう病: 正解を導き出すのはデータではなく、メンバーの対話であると心得る。
- サーベイ結果を放置してしまう病: やりっぱなしは「学習性無気力」を生む最悪手。タイムリーに必ずフィードバックする。
- データをむやみにとりすぎ病: 特にパルスサーベイは、フィードバックの工数もセットで考えないと、現場の「サーベイ慣れ」を招く。
- サーベイは1回やればOK病: 組織は元に戻ろうとする力が働く。定期健診のように継続し、リバウンドを防ぐ。
- 数字ばかり気にしすぎ病: 数字の改善自体が目的ではない。数字はあくまで対話の「きっかけ」と捉える。
まとめ: 「素手」で戦うマネジャーから卒業しよう
変化が激しく、多様なメンバーが集う現代の職場において、管理職が「勘と経験」という「素手」だけでチームを率いていくのは、あまりにも無謀です。 メンバーの疲弊を招き、自らも消耗してしまうでしょう。
本書『「データと対話」で職場を変える技術』が示す「サーベイ・フィードバック」は、こうした時代の管理職にとって、データという強力な武器を手に、客観的な根拠に基づいてチームを動かすための、まさに「組織開発の教科書」です。
鏡(データ)にうつった自己像を見つめ、対話を通じて、自分たちの未来を、自分たちで決める。
このシンプルかつ強力なプロセスを、ぜひあなたの職場でも実践してみてください。本書を片手に、まずは小さな一歩を踏み出すことが、働きがいのある、強いチームをつくるための確かな道筋となるはずです。