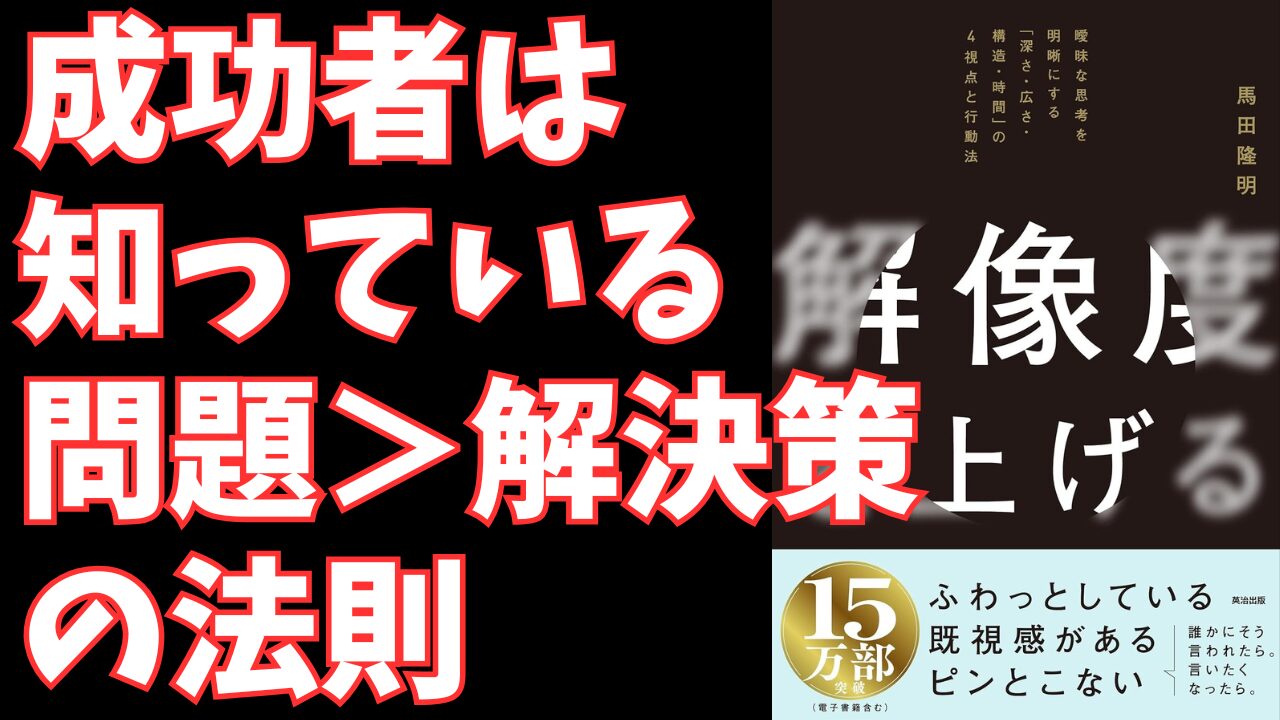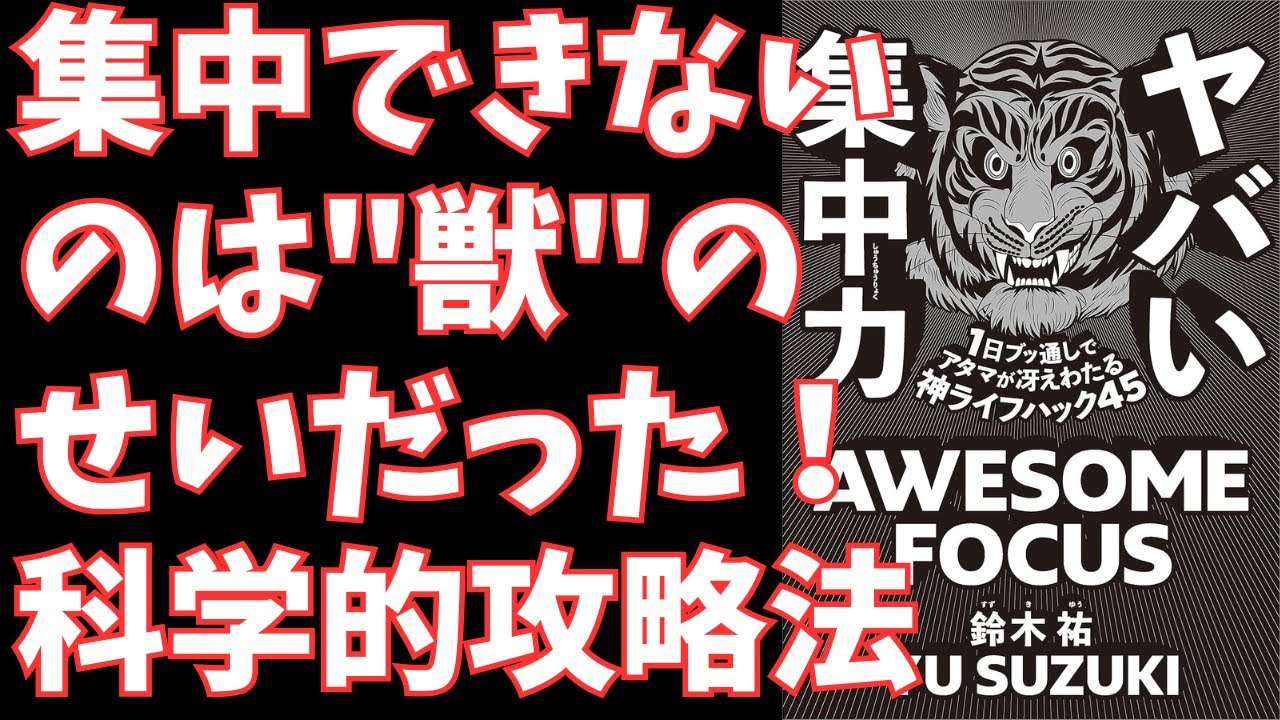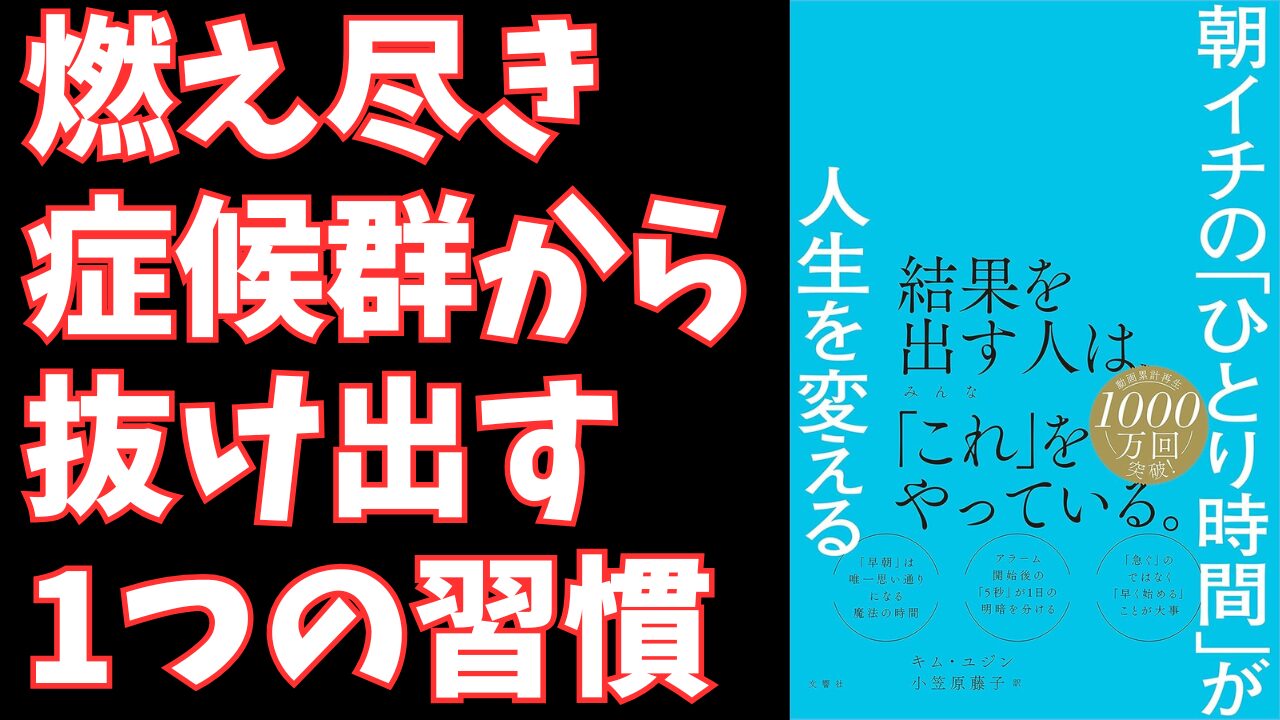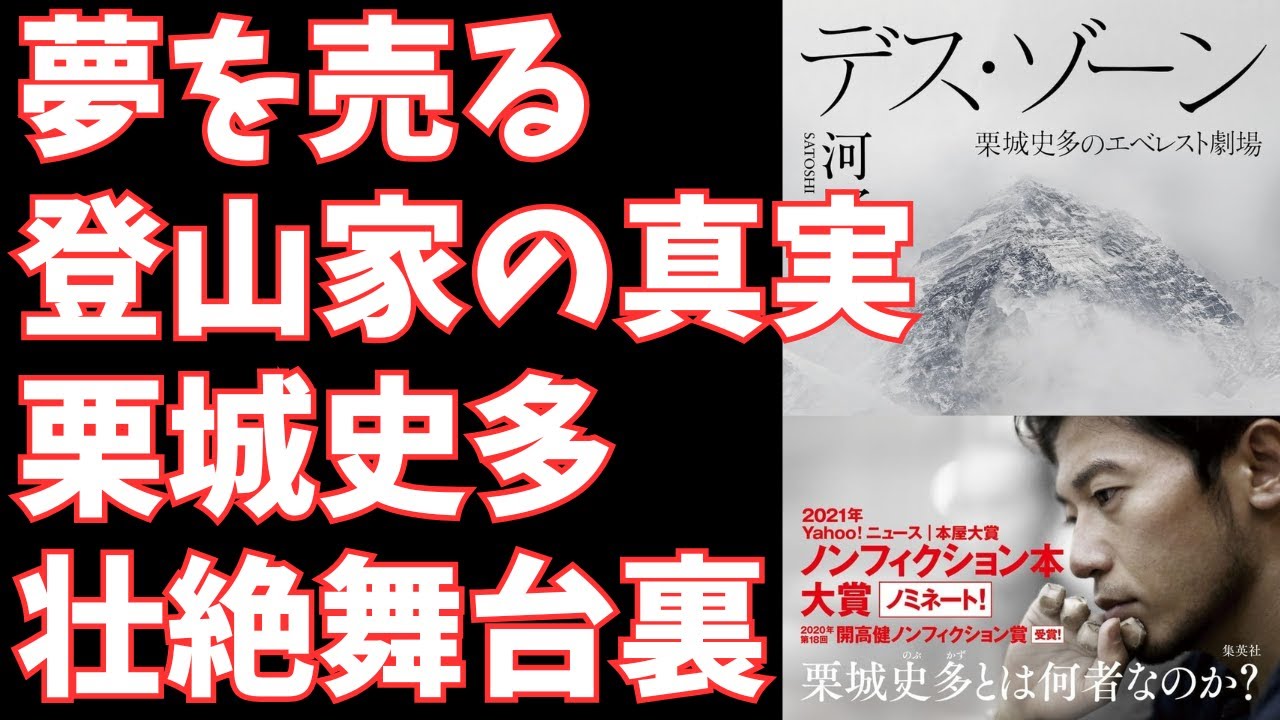多動力時代を自在に駆け抜けるための仕事術:垂直の壁を越えて価値を生み出す方法
現代は業界や肩書きの垣根が急速に薄れ、多方面にわたり行動できる「多動力」が重要視される時代です。本記事では、「一つのことをコツコツ続ける」常識を覆し、短期集中と複数領域の掛け算で爆発的な価値を生み出す具体的な方法を紹介します。仕事と遊びが一体化するような新しい働き方を手に入れるための視点や実践法をまとめました。自分だけの「原液」を持ち、ストレスフリーで効率の高い人生を送りたい方のために、多くの事例を交えつつ、その実践に役立つヒントを提供します。
はじめに:多動力とは何か
現代のビジネス環境では、「あれもこれもやりたい」という気持ちが湧き上がってくることが珍しくありません。テクノロジーの進化でありとあらゆる分野が横断され、「一つの分野だけに専念して手堅く生きていく」従来型の働き方が通用しにくくなっています。
一方、いくつもの事柄を同時にこなす「多動力」は、かつては落ち着きのない行動だとネガティブに捉えられてきました。しかし、業界がフラットにつながる今の時代には、逆にその落ち着きのなさこそが大きな武器となります。次々と興味を移しながら自分にしかできない掛け算を作り出すことで、これまでにない新しい価値が生み出されるからです。
「多動力」を身につければ、仕事と遊びの境界を超えて人生そのものが楽しくなります。本記事では、多動力を発揮していくために必要となる考え方や具体的な習慣づくりを解説していきます。
1章:一つの肩書きだけにとらわれない
1-1. 「一つのことをコツコツと」はもう終わり?
日本の社会では長らく「石の上にも三年」という価値観がありました。寿司屋の修業のように、長い時間をかけて技術を身につけることに意味があるとされてきたのです。しかし、情報のオープン化が進んだ今、修業年数よりも行動速度や「試す→修正する」のサイクルが重視されるようになっています。
たとえば、有名な寿司屋の卵焼きを再現したいときには、かつては親方に弟子入りして何年もかけて技術を盗むしかありませんでした。しかし、いまや専門学校やネット検索で基礎をさっと学び、短期間でノウハウを取得できる時代です。つまり、“車輪の再発明”をする必要がなくなったわけです。
寿司屋の例にとどまらず、あらゆる職業・業界でもノウハウ自体は比較的容易に共有されるようになりました。ここで必要なのは、自分が本当にワクワクできる分野を見つけ、素早く飛び込んでノウハウを取得し、そして飽きたら次に移るというリズムです。昔のように一つの肩書き・業界だけで一生を終えるのではなく、次々と興味のある領域に越境していく行動力が「多動力」の土台となります。
1-2. 三つの肩書きを掛け合わせれば価値は1万倍になる
世の中を見渡すと、「代わりのきく人」はなかなか高い評価にはつながりません。どれほどまじめに働いても、同じスキルを持つ人が大勢いる限り、あなたの給与はそれほど上がらないでしょう。一方、珍しい肩書きを複数併せ持てば、それらを掛け合わせた唯一無二の価値が生まれます。
たとえば「営業×デザイナー×翻訳」など、まったく違うジャンルの3つのスキルを持っていれば、「100人に1人」×「100人に1人」×「100人に1人」で「100万人に1人」の人材になれます。あまりにも希少性が高いため、その人ならではの仕事の依頼が殺到し、結果として高い評価や対価につながるわけです。
重要なのは、こうしたスキルをどう身につけるかよりも、“まず行動してみる”ことです。資格を先に取りそろえてから…というよりは、興味を感じた領域に飛び込み、必要に応じて知識や資格を得るくらいの軽やかさが「多動力」を高める近道になります。
2章:バカ真面目の洗脳を解け
2-1. 「全部自分でやらなくちゃ」からの解放
多くのプロジェクトを並行して進める上で一番のネックになるのは、「自分がすべてをこなさなくては」と思い込むことです。すべてをひとりで頑張っていては、時間も手が足りなくなります。そこで必要なのは、仕事を分担し、任せられる部分は他人に任せることです。
書籍の執筆なども、プロのライターや編集者との共同作業で効率化できる例といえます。小説や漫画でも、多くの場合は分業制が当たり前です。時間のかかる作業、ノウハウが特化した作業は専門家に任せ、自分しかできないクリエイティブな部分に集中するのが生産性向上のポイントです。
2-2. 「手作り」である必要はない
たとえば弁当の例がわかりやすいでしょう。忙しいのに無理して早起きし、時間をかけて手作り弁当を作る人は多いかもしれませんが、実は「冷凍食品をうまく使いこなす」ほうが総合的には質がいい場合もあります。
もちろん、毎回すべてを外注するわけにはいかなくても、少なくとも短縮できる部分は容赦なく短縮したほうが、心身に余裕が生まれます。緩急を付けながら、遊びや新しい学びの時間を確保するのです。
2-3. 見切り発車でOK
「準備が整ってから始める」「環境が万全になってから動く」という考え方は、変化の激しい現代ではかえってリスクがあります。準備に時間をかけすぎると、市場やテクノロジーの状況がどんどん変わってしまうからです。
むしろ見切り発車でスタートし、走りながら修正するくらいの気概が、「多動力」を発揮するうえでは欠かせない要素といえます。たとえば、突然大きなイベントを企画して数か月で走りきったとしても、終わった直後にもう次の企画に取りかかる。そうしてトライ&エラーを繰り返しながら完成度が上がるのです。
3章:サルのようにハマり、ハトのように飽きよ
3-1. まずは一つのことに異常なほど集中する
「多動力」は、あれもこれも浅く広くつまみ食いするという意味ではありません。一度でもいいから、何か一つのことにサルのように徹底的にハマる経験が重要です。そこまで深くハマる過程で、好奇心と集中力が格段に鍛えられます。
たとえば「パソコンゲームにはまりすぎて、徹夜で遊んだ」「料理にハマって毎日休まず試作を続けた」など、一見遠回りに見えるような熱中体験こそが、多動力の源になるのです。深く掘り下げることで得られた知識やノウハウは、まったく違う分野で思わぬ形で活きるものです。
3-2. 飽きっぽさを恐れない
特定のジャンルで80点までは短期集中であっという間に到達できますが、100点を極めるには莫大な時間がかかります。そこで80点くらいまで到達できた時点で見切りをつけて次へ移るのが、多動力を発揮する際のコツです。
「飽きっぽい=悪いこと」だと考えがちですが、実際には飽きっぽさこそが新しい学びを得る原動力になり得ます。飽きたから別の分野に飛び移り、そこでもまた短期集中で80点までいけば、掛け算による大きな成長が期待できます。
4章:「自分の時間」を取り戻そう
4-1. やらないことを決める
24時間という限られた1日の中で、「やりたいこと」に打ち込むためには、「やらないこと」を意識して切り捨てることが不可欠です。家事や経費精算、移動時間などに自分の多くの時間を奪われていないでしょうか?
企業に勤めている人なら、経費精算などは他者にアウトソースする工夫をするとよいでしょう。家事もプロのサービスを利用すれば数千円程度で済みます。自分が熱中できる活動にすべてのエネルギーを注ぎたいなら、割り切りも大切です。
4-2. 電話をかけてくる人とは仕事をしない
コミュニケーションが非同期化している今の時代、電話という同期的な手段は相手の時間を強制的に奪います。メールやチャット、SNSを使えばすむ内容をいちいち電話で説明するのは、仕事のリズムを乱す原因になるのです。
多動力を高めるためには、「自分のリズム」を崩されない環境づくりが欠かせません。常に電話に出ることを義務とせず、要件はメールやテキストで済ませる。周囲の人にも「電話は要らない」「まずはチャットで連絡を」と徹底し、不要な同期コミュニケーションを減らす工夫が重要です。
4-3. 会議中にスマホをいじる勇気
「会議中にスマホをいじるなんて失礼」と考える風潮も、実は過去の常識にすぎません。大切なのは、自分が行うべきアウトプットがブレずに行えているかどうかです。
無駄に長い会議や雑談から抜け出すには、自分を律するだけでなく周囲の「古い常識」にも対抗する必要があります。現代では、一つの会議中に他の仕事を進めたり、SNSでリアルタイムの意見を拾ったりするほうが生産性を高める場合もあるのです。
4-4. おかしな人から距離を置く
多動力を発揮するには、自分の時間を不当に奪う人とはできるだけ関わらないのがコツです。面倒な人、絡みづらい人、無理な要求を押し付けてくる人は、自分の集中力を削いでしまいます。
トラブルやしがらみを回避して時間を守るには、ときに冷酷に見えるほどの“距離の取り方”が必要です。とくにSNSやコミュニティで相手が苦手だと感じたら、早めにブロックやミュートを行いましょう。
4-5. 仕事は選んでいい
「今の仕事が嫌だが辞められない」「ブラックバイトでも我慢しなくちゃ」という考えは、現代では機会損失です。嫌なら辞めればいいし、「この仕事に専念する価値がない」と判断したら切り捨てるべきです。そうすることで、自分の時間を本当にワクワクする仕事に投資できます。
5章:自分の分身に働かせる裏技
5-1. 「原液」を作ろう
多動的なスケジュールをこなしながら成果を上げるには、「薄めるだけで広がる」原液となる仕事を仕込むのがポイントです。たとえば、自分が書いたアイデアやSNSでの発言が、あちこちに引用されて自動的に広まっていくようなイメージ。
こうした原液を作れば、自分の一挙手一投足が「分身」として動き続ける状態になります。テレビ番組やウェブメディアが、その発言を取り上げて拡散してくれる構図が典型例です。
5-2. 教養があると「原液」が増える
「原液」を作るうえで重要なのは、骨太の教養をもつことです。断片的な知識や数字、統計データを集めるだけではなく、歴史的な経緯や国際比較など深い背景を学ぶことで、自分の軸が鍛えられます。その土台があると、表面的な流行やテクノロジーの変化に振り回されず、自分なりの発信をしやすくなるのです。
5-3. 知らないことはその場で調べる
現代では、未知の情報はネット検索やSNSで瞬時に入手できます。恥ずかしがらずにわからないことは聞く、調べるを実行するだけで、多様な知識が手に入るものです。一方で、漠然と「質問したいことが多いんですが…」と長話するのではなく、焦点を絞って質問する習慣をつけると効率的に学べます。
5-4. 99%の会議はいらない
「無駄な会議」に時間を取られていては、多動力を発揮するどころではありません。目的・必要な情報・結論を明確にする三原則を守れば、会議は15分、あるいは数分で終わらせることも十分可能です。結局は、そこでどんな結論を出すかが肝心であって、ダラダラ集まって話すほど生産性のない行為はありません。
6章:世界最速仕事術
6-1. すべてをスマホで完結させる
パソコンの前にかじりつき、電話やFAXに時間を取られる時代は終わりです。スマホ一台あれば打ち合わせ、資料のやり取り、メッセージ送付、決済などの多くを済ませることができます。
極端に言えば、オフィスに行かなくても、外出先やジムの休憩中などを使って仕事は大方処理できるのです。「会社に行かなければ仕事ができない」という固定観念を捨てるだけで、大幅に行動範囲が広がります。
6-2. 仕事は「リズム」で決まる
「仕事が早い」とは、作業そのものの物理的速度よりもリズムを乱さないことが鍵です。ちょっとした電話で作業が中断するだけで、流れが切れてしまい、再開時に大きな時間ロスが発生します。
メールの添付ファイルや文書が重い場合なども同様です。「よけいなことでリズムが滞る」原因をとことん除去することで、高速かつ大量のタスク処理が可能になります。
6-3. レスポンスの即断即決
忙しい人ほど返信が早いと感じたことはないでしょうか? 仕事ができる人は、メールやSNS、メッセージアプリを即仕分けし、重要なものには即時返信を行います。
優先順位をつけて次々とタスクを処理する「トリアージ発想」により、膨大な量のメッセージも短時間でさばけるのです。逆に、返事を先送りにする人ほど、仕事が“渋滞”して非効率な状況に陥ってしまいます。
6-4. 寝る間も惜しまず…は悪手
「睡眠を削ってまで働く」という働き方は、かえって効率を下げます。しっかり休んだほうがミスが減り、新しいアイデアも浮かびやすくなるため、結果的に仕事の質が上がるのです。睡眠・栄養・運動といった基本的なコンディション管理が、多動力を支える重要な要素だと心得ましょう。
7章:最強メンタルの育て方
7-1. 人は他人に興味がない
「失敗したら恥ずかしい」「みっともないところを見せたくない」と考えると、多動力を発揮する前にブレーキを踏んでしまいます。ところが実際は、周りの人はあなたの失敗や恥など覚えていないのです。
恥をかいた分だけ自由になる、そう腹をくくれば、どれほど気が楽になるでしょう。小さな恥を気にして大きな挑戦を見送るほうが、結果としてはもったいないのです。
7-2. リーダーはバカでいい
チームやプロジェクトを動かすときに一番大事なのは、最初に手を挙げる“バカ”がいるかどうかです。小利口な人は失敗リスクを考えすぎて、いつまでも踏み出せません。一方でバカは、「とりあえずやってみる!」という勢いがあるため、行動を起こしやすいのです。
思い切って手を挙げる人がリーダーとなり、そのあとに小利口な人々がサポート役として集まってくるのが、越境型のプロジェクトを成功させる定石なのです。
8章:人生に目的なんていらない
8-1. 永遠の3歳児であれ
年齢が上がるとともに、仕事や人脈などこれまでの積み重ねが足かせになりがちです。しかし、「本当にやりたいこと」に飛び込んでしまう勇気があれば、いつまでも若々しくいられます。
新しいテクノロジーへの興味を失わず、未知の場所へ出かける心構えを持ち続けることで、3歳児のような好奇心が蘇り、自然と多動力も持続しやすくなります。
8-2. 資産を持つほど身動きが鈍る
もし土地や資格などの資産を持っていると、それをどうにか有効活用しようとして却って視野が狭くなる場合があります。大切なのは、本当にやりたいことをフラットに考え、必要なら資産を売って資金化するなど思い切った判断をすることです。中途半端に抱え込むより、一度リセットしたほうが軽やかに動けます。
8-3. ハワイに別荘なんてもたない
成功したらハワイや軽井沢に別荘を…という発想は、いわば“安定の象徴”です。けれども安定を求めすぎるあまり、新しい刺激が得られず成長速度が落ちてしまうことも多いものです。予定調和の幸福を追い求めるよりは、未知の国を回り、新しい文化や人との出会いを楽しむほうが、豊かな学びと刺激に満ちた人生が送れます。
8-4. 人生に目的はいらない
「人生の目的はなんですか?」と問われることも多いですが、実は今この瞬間にワクワクすることこそがすべてです。目的やゴールを設定してしまうと、それが足かせになって逆に行動が止まることすらあります。
子どもが遊ぶときに「何のために遊ぶの?」と考えないのと同じで、大人も「楽しいからやる」「興味があるからやる」でいいのです。そうしたフットワークの軽さが多動的な価値を生み、結果として面白い仕事やアイデア、収入までももたらしてくれるのです。
おわりに
「多動力」とは、単にやみくもに目移りすることではなく、強い好奇心を維持しながら複数の分野を横断し、新しい掛け算を生み出す力です。業界の垂直の壁が消えつつある今、専門分野を越境しながら学習し、思いついたアイデアを素早く実行する人こそがチャンスをつかみます。
- やらないことを決める
- 他人の時間に支配されない
- 自分だけの「原液」づくりを意識する
- ストレスを減らして一気に走り抜ける
これらのポイントを押さえながら、多動力を発揮していけば、仕事もプライベートも大きく変わっていくはずです。最初は勇気がいるかもしれませんが、「Just do it.」という言葉のとおり、小さな一歩を踏み出してみてください。
一つの分野に固執せず、複数の領域に次々と飛び込み、飽きたらまた他に移る。その先に、今までにない新しい世界や、自分でも想像もしなかった可能性が待っているはずです。
周りがどう言うかを気にせず、やりたいことにはどんどん挑戦していきましょう。あなた自身の多動力が花開けば、自然と新しい道が開け、これまでにないスピードとリズムで、人生を自由自在に駆け抜けることができます。