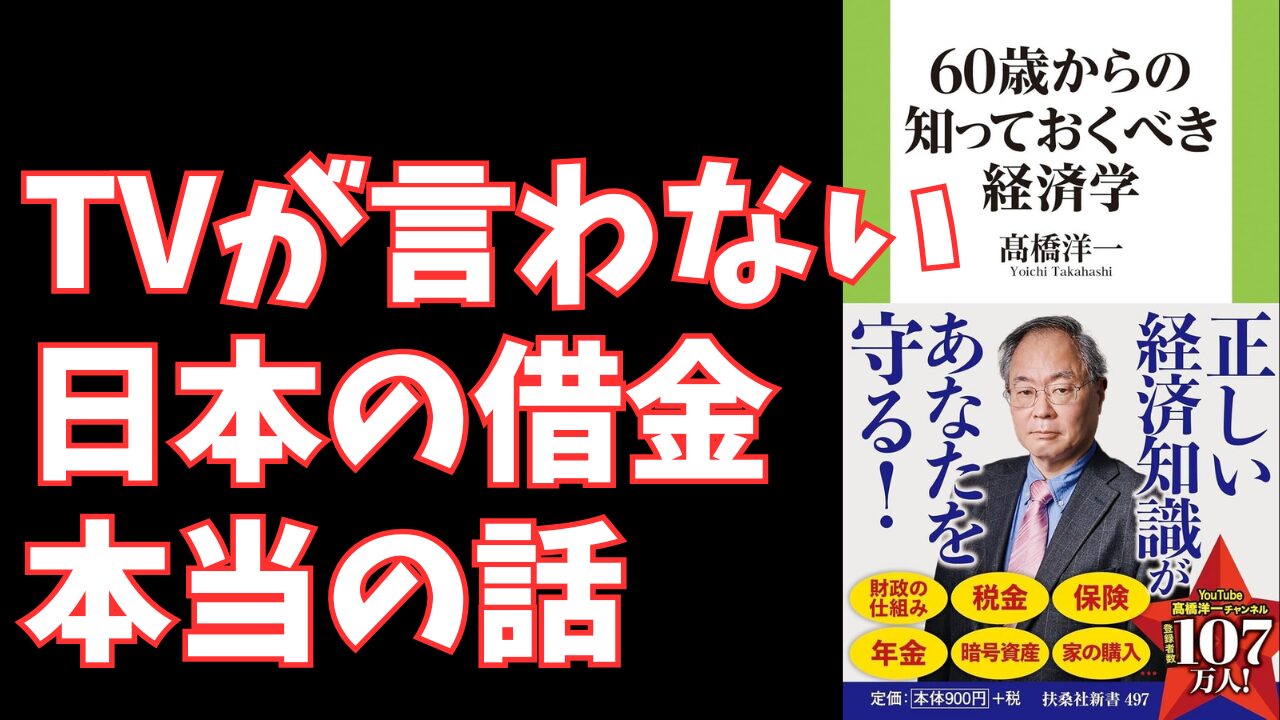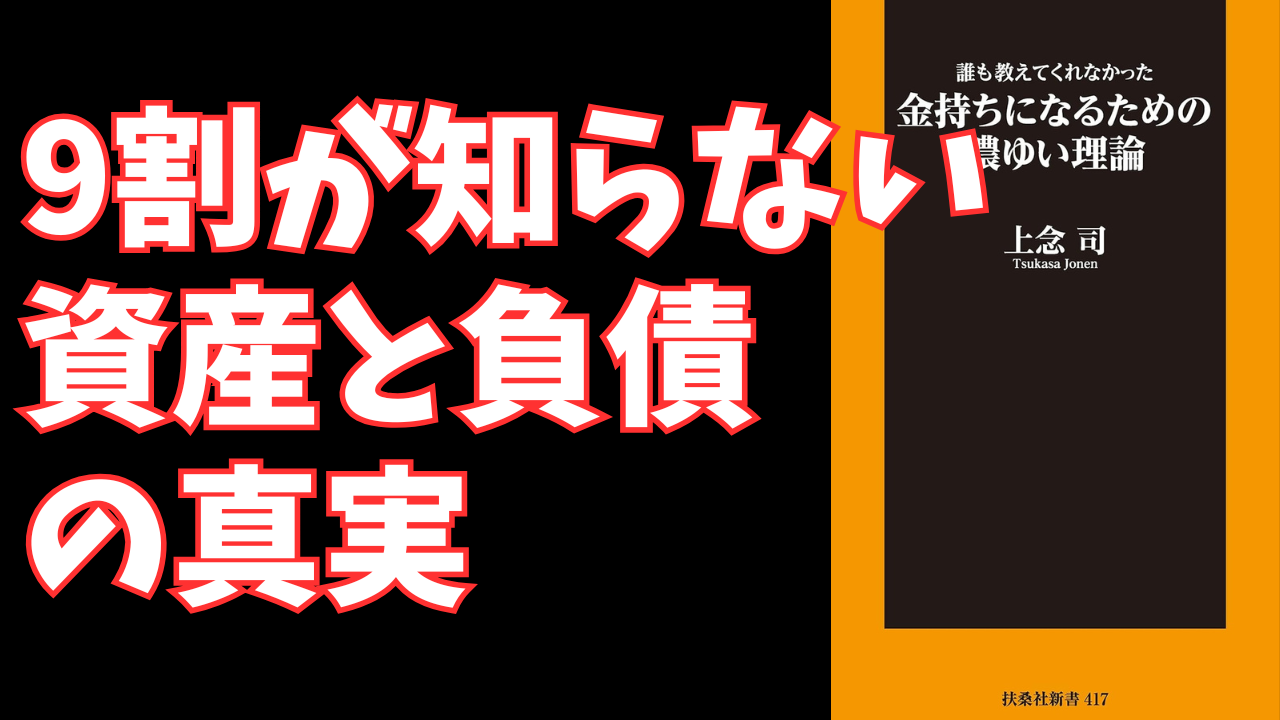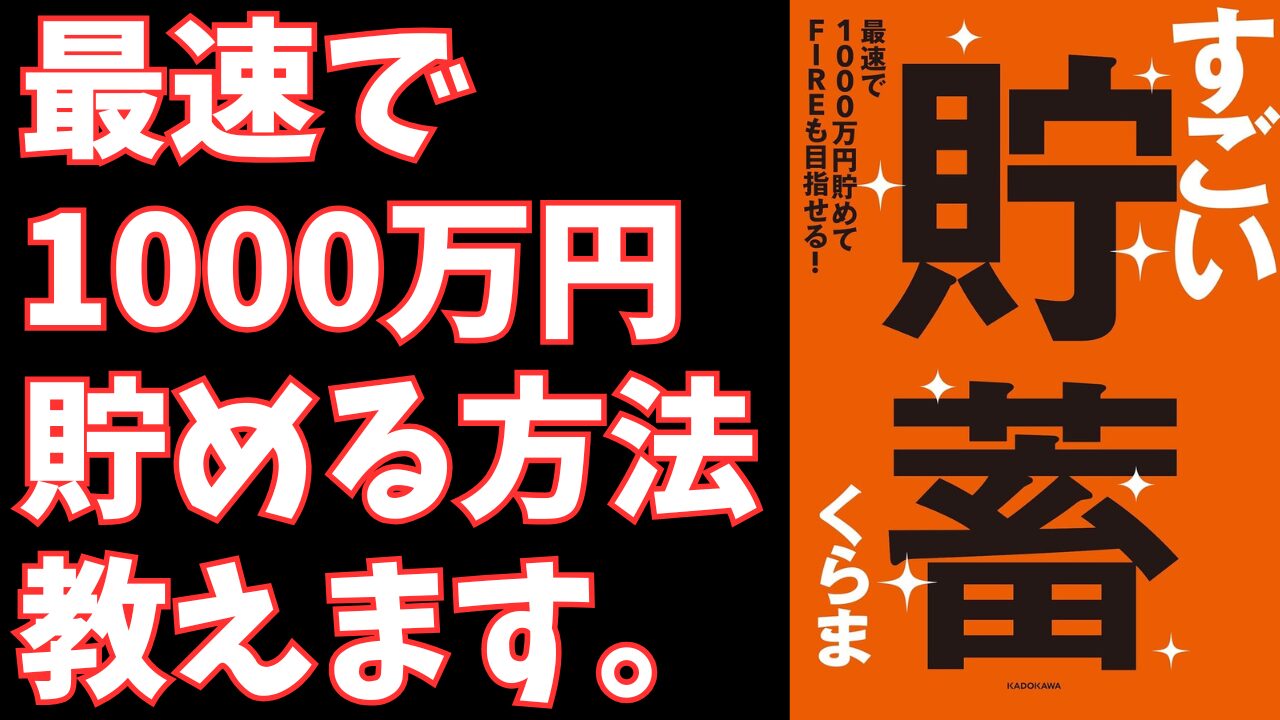高橋洋一『経済のしくみがわかる「数学の話」』|官僚とマスコミの「嘘」を数字で見抜く思考法
本書『経済のしくみがわかる「数学の話」』は、元財務官僚である著者・髙橋洋一氏が、数学的な視点から経済ニュースに潜む「嘘」や「カラクリ」を見抜く方法を、対話形式でわかりやすく解説した一冊です。
ターゲットは、経済の専門知識はないものの、世の中の動きに敏感でありたいと願うビジネスパーソン。著者は「世の中の人は、なぜ、これほどたやすく官僚・政治家・マスコミ・御用学者の嘘に騙されるのだろう」という疑問から出発し、その原因が「数学的思考の欠如」にあると断言します。
本書を読めば、「復興増税やむなし」「このままでは財政破綻する」といった、巷にあふれる言説がいかに偏ったものであるかが理解できます。そして、「歳入=歳出」という単純な数式や、確率、統計といった基本的な数学の知識がいかに強力な武器になるかを実感できるでしょう。情報に踊らされず、物事の本質を自分自身の頭で考えるための「思考のOS」をインストールしてくれる、すべてのビジネスパーソン必読の書です。
本書の要点
- 財源確保は増税だけではない。国の財源は「歳入=歳出」という恒等式で考えれば、「税収」以外に「税外収入」や「公債」という選択肢がある。日銀の国債引受などを活用すれば、増税なしで財源を捻出することは可能である。
- 「財政破綻」キャンペーンは意図的に作られている。日本の財政状況は、自国通貨建て国債であることや莫大な対外純資産を持つことなどから、対外債務に苦しむギリシャとは全く異なる。CDS値を見ても、市場は日本の破綻リスクを極めて低いと評価している。
- 人々が騙されるのは「定義」と「数字」に弱いから。議論の前提となる言葉の定義を曖昧にしたり、確率や統計を誤って解釈させたり、比較の基準を恣意的に設定したりするのが、官僚やマスコミの常套手段である。
- 日本の長期デフレは日銀の政策が原因である。データは、日本のデフレが日銀の「デフレターゲット」ともいえる金融政策に起因することを示唆している。インフレターゲットを掲げ金融緩和を行えば、経済は成長し財政も再建に向かう。
- マクロ経済の基本モデルで経済の全体像が見える。IS-LM分析などのマクロ経済学の基本を理解すれば、政府の財政政策や金融政策が経済全体にどのような影響を与えるのかを論理的に予測し、評価することができる。
はじめに:なぜ、私たちは経済ニュースに「騙されて」しまうのか?
「復興のためには、増税もやむを得ない」
「このままでは日本の財政は破綻し、ギリシャの二の舞になる」
「東電の値上げは、燃料費高騰のため仕方がない」
こうしたニュースを見聞きして、「そういうものか…」と納得してしまってはいないでしょうか。多忙な日々を送るビジネスパーソンにとって、一つひとつの経済ニュースを深く掘り下げて真偽を確かめる時間はなかなか取れないものです。
しかし、元財務官僚である髙橋洋一氏は、著書『経済のしくみがわかる「数学の話」』の中で、世の中に流布する経済言説の多くは、意図的に偏った「嘘」であると断言します。そして、その嘘をいとも簡単に見抜く方法、それこそが「数学的思考」なのだと説きます。
本書は、著者である髙橋教授と、数学がからっきし苦手な編集者S君との対話形式で進みます。S君の素朴な疑問や誤解を通して、私たちがいかに簡単に騙されてしまうのか、その思考のワナが浮き彫りにされていきます。
この記事では、本書のエッセンスを抽出し、忙しいビジネスパーソンが明日から使える「情報に騙されないための思考法」を、本書の具体的な事例を交えながらご紹介します。
【第1の嘘】「増税しかない」は本当か? – 予算制約式のワナ –
「東日本大震災の復興財源として13兆円が必要。そのためには増税が不可欠だ」
本書が執筆された当時、このような報道がなされ、多くの国民が「復興のためなら仕方がない」と感じていました。本書に登場するS君もその一人です。しかし、髙橋教授は、この記事を一目見ただけで「デタラメ洗脳記事」だと一蹴します。なぜでしょうか。
その鍵は、「歳入=歳出」という極めてシンプルな恒等式(予算制約式)にあります。
$$
歳出 = 税収 + 税外収入 + 公債
$$
国が何かにお金を使う(歳出)場合、その財源(歳入)は、必ずしも「税収」だけではありません。「税外収入」(政府保有株の売却、埋蔵金、日銀納付金など)や「公債」(国債の発行)といった選択肢も存在するのです。
「復興財源13兆円」という歳出に対して、「増税で13兆円」と結論づけるのは、「税外収入」と「公債」を意図的にゼロと仮定した、きわめて特殊なケースに過ぎません。これはまさに、増税へと世論を誘導したい財務官僚の「初めに答えありき」の議論なのです。
髙橋教授は、実際には増税に頼らずとも財源は確保できると指摘します。
- 公債の発行: 震災復興のような、便益が長期にわたる公共事業の財源は、世代間の公平性を保つためにも、長期の国債(建設国債)で賄うのが基本。これだけで3〜4兆円は確保できる。
- 税外収入の活用: 最も簡単で効果的なのが「日銀の国債引受」です。日銀が国債を直接引き受けることは、実質的に政府が通貨を発行するのと同じ効果(シニョレッジ)を持ち、将来的に「日銀納付金」という税外収入を政府にもたらします。髙橋氏によれば、これだけで当時18兆円もの財源が捻出可能だったといいます。
このように、「歳入=歳出」という数学的なフレームワークを持つだけで、「増税しかない」という言説が、いかに選択肢を狭めるためのプロパガンダであるかが見えてきます。これは、東京電力の値上げ問題にも応用できます。東電が「燃料費が増加したから」という理由だけで「電気料金の値上げ」を求めるのは、「収入=支出」の恒等式において、人件費の削減や資産売却といった他の選択肢を無視した、あまりに虫の良い話だということがわかるのです。
【第2の嘘】「このままでは財政破綻する」という脅しの正体
増税論とセットで語られるのが「財政破綻」の恐怖です。「日本の借金は1000兆円超え!」「ギリシャの二の舞になる!」といった煽り文句は、多くの人に「それなら増税もやむを得ない」と思わせる強力なパワーを持っています。
しかし、これもまた、数学的・事実的な視点から見れば、多くの嘘が含まれています。
嘘①:日本とギリシャは全く違う
まず、日本とギリシャを同列に語ること自体が間違いです。
- 国の信用の差: ギリシャは過去200年のうち半分以上の期間で債務不履行(デフォルト)を繰り返す常習国。
- 借金の中身の差: ギリシャ国債の多くは外国が保有する「対外債務」ですが、日本国債の9割以上は国内で消化されており、自国通貨(円)で発行されています。自国通貨建ての国債がデフォルトすることは、通常あり得ません。
- 資産の差: 日本は1000兆円の借金(債務)を抱える一方で、650兆円もの資産を持つ世界一の金持ち国でもあります。資産を差し引いた「純債務」で見れば、対GDP比は欧米諸国と大差ない水準です。
嘘②:市場は「日本は破綻しない」と見ている
本当に日本の財政が危ないのなら、日本国債の信用度は低いはずです。国債のデフォルトリスクに対する保険料を示す「CDS(クレジット・デフォルト・スワップ)値」を見ると、その国の信用度がわかります。
当時、ギリシャ国債のCDS値が「80%(1年以内にほぼ確実に破綻する)」という異常な高さだったのに対し、日本のCDS値はわずか「1.3%」程度でした。これは「80年間は破綻しない」と市場が判断しているレベルです。身銭を切って取引する市場参加者は、財務省の「もうすぐ破綻する」というキャンペーンを全く信用していないことの証左です。
嘘③:財政再建の数式は操作されている
財政の健全性を示す指標に「債務残高対名目GDP比」があります。この指標が将来どう変化するかは、以下の数式で表すことができます。
$$
\Delta (\frac{D}{GDP}) = -(\frac{PB}{GDP}) – (g-r) \times (\frac{D}{GDP})
$$
($\Delta$:変化分, $D$:債務残高, $GDP$:名目GDP, $PB$:プライマリーバランス, $g$:名目成長率, $r$:名目金利)
この式が示す重要な点は、もし名目成長率(g)と名目金利(r)が同じ(g=r)であれば、第二項はゼロになるということです。その場合、プライマリーバランス(PB)を黒字化するだけで、「債務残高対名目GDP比」は着実に減少、つまり財政は健全化に向かいます。
過去のデータを見ても、多くの国で経済が正常な状態では「g=r」となる傾向があります。しかし、財務省は財政危機を煽るために、意図的に「g < r」(成長率より金利が高い)」という、デフレ下でしか起こらない特殊な前提を置いて試算を行います。そして、「財政再建にはこれだけのプライマリーバランス黒字化が必要で、そのためには消費税を〇〇%に上げるしかない」という結論を導き出すのです。これもまた、「初めに答えありき」の数式の悪用と言えるでしょう。
【第3の嘘】なぜ私たちは騙されるのか? – 数学的思考でワナを見破る –
では、なぜ私たちはこれほど単純なカラクリに気づかず、騙されてしまうのでしょうか。髙橋教授は、その原因が私たちの「思考のクセ」にあると指摘します。
ワナ①:言葉の「定義」をしないまま議論する
「公共投資は効果があったのか?」という問いを考えてみましょう。一見、まともな問いに見えますが、ここには「効果」の定義がありません。「インフラが整備された」という効果なのか、「GDPが上がった」という経済効果なのか。定義が曖昧なままでは、議論はかみ合いません。
本書では、「公務員宿舎は必要か」「東電は潰すべきか」といった例を挙げ、議論の最初に使用する言葉の定義を明確にすることの重要性を説きます。定義がはっきりすれば、その後の議論は感情論ではなく、数字と論理に基づいた客観的なものになるのです。
ワナ②:「確率」を感覚で捉えてしまう
「今後30年以内に地震が起きる確率87%」
この数字を聞くと、多くの人が「すぐにでも起きそうだ」と直感的に恐怖を感じます。しかし、これを「1年以内に起きる確率」に計算し直すと、約6.6%にしかなりません。「15回に1回」程度の確率であり、過度に慌てる必要はないレベルだと冷静に判断できます。
本書で紹介される「モンティ・ホール問題」も、確率を感覚で捉えることの危うさを示しています。確率や統計の知識は、リスクを正しく評価し、いたずらに不安を煽る報道から身を守るための強力な盾となるのです。
ワナ③:「単位」と「桁数」に無頓着
「放射線量が2倍に!」といった報道に、私たちは一喜一憂しがちです。しかし、科学の世界では、重要なのは「桁」が変わるほどの変化があったかどうかです。2倍や3倍といった変化は、同じ桁の中の動きであれば「有意差なし」と見なされることも少なくありません。
また、発表される数値が「瞬間の値(フロー)」なのか「累積の値(ストック)」なのか、単位(マイクロシーベルトかミリシーベルトか)は何なのか、といった点に注意を払うだけで、情報の意味合いは大きく変わってきます。数字そのものの大きさだけでなく、その数字が持つ「単位」や「桁」を常に意識することが、騙されないための基本です。
結論:経済の本質を見抜く「数学」という最強の武器
本書『経済のしくみがわかる「数学の話」』は、単なる経済解説書ではありません。それは、情報過多の現代社会を生き抜くための「思考法」のトレーニングブックです。
これまで見てきたように、政府やマスコミが使うレトリックは、数学的な視点で見れば驚くほど単純なものです。しかし、数学的思考という「物差し」を持たない私たちは、いとも簡単にその術中にはまってしまいます。
髙橋教授は、日本の経済学が世界レベルに達しない理由の一つに、文系・理系と分けて数学教育を軽視してきた日本の学問体系の問題があると指摘します。数学は、本来、経済学を含むあらゆる科学の基礎となる「共通言語」なのです。
本書で求められる数学は、高校レベルの微分や等比級数、確率といった基本的なものばかりです。しかし、その威力は絶大です。
- 「歳入=歳出」 という単純な恒等式は、増税以外の選択肢を照らし出します。
- 「確率」 の計算は、リスクを冷静に評価する目を養います。
- 「データとグラフ」 は、日本のデフレが金融政策の失敗であることを雄弁に物語ります。
- 「マクロ経済モデル」 は、複雑に見える経済現象を、変数と数式の関係としてシンプルに捉えることを可能にします。
経済ニュースの裏側を読み解き、誰かの意見を鵜呑みにするのではなく、自分自身の頭で判断したい。そう願うすべてのビジネスパーソンにとって、本書は、一生使える知的武装を施してくれる、またとない一冊となるでしょう。